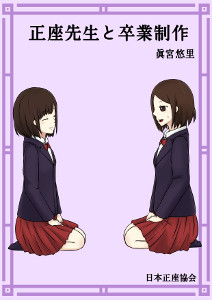[396]正座禁止をくつがえせ!
 タイトル:正座禁止をくつがえせ!
タイトル:正座禁止をくつがえせ!
掲載日:2029/1/13
著者:海道 遠
イラスト:鬼倉 みのり
あらすじ:
椿は木暮(こぐれ)茶道教室の師範。師匠の木暮先生の跡継ぎと噂されていた。茶道の時の正座の美しさは弟子たちの間でも評判で、椿自身は茶事の時、一輪の椿になりきろうとしていた。
そんな時、お弟子たちの欠席が多くなる。どうやらご近所にできた「ぐうたらしよう講座」に流れているらしい。しかも、その講座は「正座禁止」を謳っているそうなのだ。

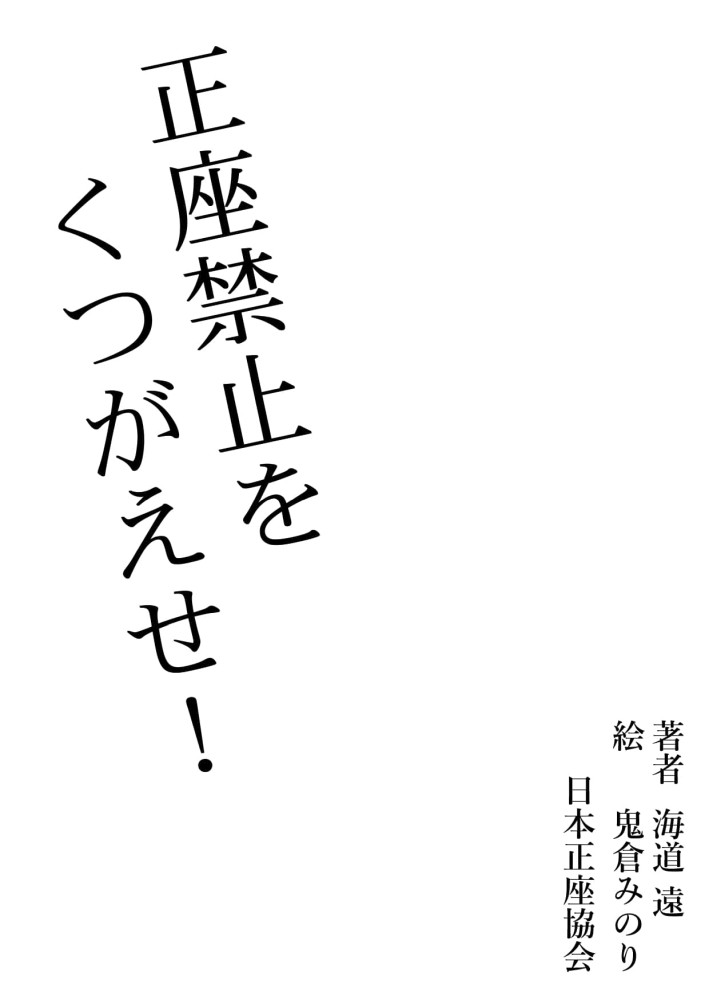
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 ぐうたらしよう講座
「けっこうなお点前でございました」
椀をおいた客が、18歳の椿に言う。
形式とはいえ、それが心からの言葉だと分かる。
椿の点てる茶は、格別美味しく、お点前も客のために心を込めていることが分かる。
茶室には、春の柔らかい光が満ちている。お辞儀を返した椿は、撫子色(なでしこいろ)の着物も艶やかに似合い、釜の前でゆったりとしていた。
茶道の師範免状をいただいた椿。
茶道歴50年以上の師匠の木暮(こぐれ)先生からも実の娘のように可愛がられ、一目置かれている。正座は特に美しく、釜の前に座ると真っ赤な椿が咲き誇っているようだと言われる。
黒髪も美しく季節ごとの着物もよく似合い、後輩弟子の憧れの的だ。
真っ赤な袱紗(ふくさ)さばきも優雅そのもの。後輩たちはため息と共に椿の所作を見つめていた。
ある日、お稽古が終わってから、釜の前に座り続けている木暮先生の姿があった。手元には象牙に珊瑚の花びら細工のかんざしがある。
「まあ、きれいですね」
「でしょう? 昔、大切な友人にいただいたの。私には華やかになってしまったけれど」
木暮先生は、椿の祖母と言っていい年代だ。
「大切な方からの贈り物なんですね」
かんざしを見つめる先生の眼差しは深く、穏やかだった。
ところが、ここしばらく後輩たちの何人かが休むようになった。
欠席者はだんだん増えていく。
「今日は山口さんと加藤さんがお休みです」
「分かりました。変ですね。最近、お休みの方が多くて」
椿は木暮先生と顔を見合わせ、首をひねっている。
ある日、椿が師匠からお使いを頼まれて急ぎ足で歩いていると、茶道教室で長年一緒の加藤さんに出会った。加藤さんは椿より少し若い。
「あら、加藤さん、お久しぶりね」
「あ、そ、そうですねえ」
加藤さんは、椿を見て歯切れの悪い返事だ。
「お元気でしたか? 最近、お休みが多いからいかがされているかと思ってましたよ」
「変わりないですよ。そのうち顔を出しますから、先生によろしくお伝え下さいね」
ご機嫌はよいようだが、いつもよりのんびりした口調だ。
(加藤さんはハキハキした女性なのに、どうしたんだろう)
椿は感じた。
お使いを済ませて教室に戻ると、友人のスミレが待っていた。
「椿ちゃん、大変よ」
「どうしたの?」
「最近、お休みのお弟子さんたちが多いでしょう。どうやら、三丁目にできた得体の知れない『ぐうたらしよう講座』に通ってるらしいのよ」
「『ぐうたらしよう講座』? なに、それ」
「現代人はせかせかしてるから、ぐうたらして精神を安定させようって考えらしいわ。それに正座は精神を緊張させるから、『正座禁止』を掲げてるんですって!」
「正座禁止ですって?」
これには椿も驚いた。茶道をしている身に、正座禁止など謳われては立つ瀬がない。それも茶道教室を休んで参加している生徒が多いとは。
第二章 茶道を愛する椿
高校時代から友人のスミレと誘いあい、始めた茶道だが、椿にとってなくてはならないものになっている。
お茶の作法はもちろんだが、お茶を点てたりいただいたりする時の正座の姿勢が気に入っている。正座すると、気分が落ち込んでいる時もしゃっきりするのだ。
正座の基本は背筋を真っ直ぐ、かかとの上に座り、洋装の時はスカートの裾をお尻の下に敷く。和装の時も同様。そして両手は静かに膝の上に置く。
こうすると椿はとても落ち着く。正座する時は、人間であることはもちろん、同時にお客の目と心を楽しませるような、存在感のある一輪の椿になろうと心に決めている。
正座を見て、師匠の木暮先生から、
「今日の椿さんは最高のお茶が点てられるわね」
などと言われると嬉しくなる。
茶道の歴史は、かなり古くにさかのぼる。
鎌倉時代に日本に禅宗を伝えた栄西は、中国から持ち帰った茶を九州に植えた。また、宇治の明恵上人にも茶の種を送り、それが宇治茶の起源とも言われる。茶の栽培が普及すると茶を飲む習慣が一般に普及していった。
それから何百年、武士の嗜み(たしなみ)だった茶道は現代では多くの流派に別れ、女性が主流となって庶民に広く愛されている。
三千家の祖、千利休の教えは、
「茶は服のよきように点て」
「炭は湯のわくように置き」
「夏は涼しく冬は暖かに」
「花は野にあるように」
「刻限は早めに」
「降らずとも雨の用意」
「相客に心せよ」、この七則だ。
椿にとって亭主(茶の会の主催者)になって茶事を行う時、茶室に飾る床の間の絵、飾る季節の野花を選んで摘んでくること、お客様の立場に立って寒い暑いを察して茶室内の温度を調節したり細かく気を配ってもてなしをすることも、楽しみのうちだ。
木暮先生はその素質を見抜いていた。
椿は決して場違いなもてなしや、心の籠っていない茶を点てたりしないことを。
そして、晴れがましい大人数の「大寄せ」よりも少人数で行う「茶事」の方を好む慎ましいところも。
木暮先生には子どもがない。
茶道教室の跡継ぎに、椿を抜擢しようという心も芽生えてきていた。椿も薄々、そのことに気づいていた。
そんな矢先、お弟子さんがお休みが多くなり、「ぐうたらしよう講座」なるものに通っているとの噂は、晴天の霹靂(へきれき)だった。
第三章 ぐうたらしよう講座
お茶のお稽古の欠席者は増える一方だった。
「先生、私、その『ぐうたらしよう講座』を訪ねてみようと思います」
木暮先生に椿は思い切って言った。
「放っておきなさい。自由にしておけばよろしい」
「でも、今のままじゃ、お弟子さん全員があちらに入り浸りになるかもしれませんよ」
「それでも放っておきなさい」
「放っておけませんわ。お弟子さんを取られるのが困るんじゃなく、ぐうたらすることを推奨するような変な教えを学んでほしくないのです」
こういう時、椿は頑固なのだ。
「仕方ないわね。じゃ、スミレさんとふたりで行ってらっしゃい」
やれやれと肩をすくめて、木暮先生は許しを出した。
「スミレちゃん、ごめんね。おつきあいさせてしまって」
「ぐうたらしよう講座」へ行く道で椿はスミレに謝った。もしかしたら怪しい雰囲気のところかもしれないからだ。
「いいのよ。私も気になっていたんだから」
スミレはにっこりして答えた。
ふたりとも動きやすいパンツスタイルだった。
和服を着こなす椿だが、手足が長くパンツスタイルも抜群だ。
一キロほど歩くと商店街が途切れ、住宅街の中に看板をかけた一軒がある。
「ぐうたらしよう講座」と墨でユーモラスなゆがみ文字で書いてある。アートっぽい歪み方だ。
真新しい木造住宅だ。玄関は民家の玄関ではなくガラス戸がたくさん並んでいる。そして土間があり、畳敷きのお座敷がある呉服問屋という感じだ。
「呉服問屋でも買い取って講座を開いたのかしら」
チャイムも無いのでガラス戸を少し開け、声をかけてみた。
「ごめんください」
応えがない。
「誰もいないのかしら。中は真っ暗だわ」
「でも戸は開けたままだったわよね」
「ごめんくださ~~い」
土間から奥へ叫んでもシーンとしている。何度か呼びかけたが十五分も経っただろうか。人が出てくる気配がして、暖簾(のれん)がめくられた。
茶道教室で一緒の加藤さんではないか。ティーシャツにジーンズ姿だ。
「加藤さん。やっぱりここにおいでだったのね」
「あら、椿さんとスミレさんじゃないですかあ」
加藤さんは酔っぱらってるように、へらへらしながら椿たちにもたれかかる。
「どうしたんですか、加藤さん! まるでお酒に酔ってるみたい」
「あら、そう?」
加藤さんは危なっかしい足取りで暖簾まで戻る。
「加藤さん、ここの先生はどこ?」
「奥にいらっしゃいますよ」
加藤さんの言葉に従って奥へ進んでみると、畳十畳くらいの部屋があった。そこには、思い思いの格好で過ごしている男女の姿がある。
柱にもたれてぼんやりしている者、手枕で雑誌を読んでいる者、立膝でスマホを触っている者、みんな、だらんとした表情だ。
学生かサラリーマンだか、アーティストか主婦か、よく判らない。様々な格好をしていて、年齢は二十代から四十代くらいだろうか。
椿とスミレが、思わず後じさりするような集団だ。
その時、ぬっと顔を出したのは、職人さんの頭領によくいそうなヒゲの濃い大男だ。ふてぶてしい顔で椿とスミレをじろじろ見まわした。スミレが思わず椿の背中に隠れた。
「何か用かな、お嬢ちゃんたち」
声もドスが効いている。
「あ、あの、ここの代表の方にお話が」
「代表? ああ、ボスか。ボ―――ス! お客さんですぜ!」
奥へ向かって熊の吼え声のように叫んだ。
「お客さんだって?」
声がして、三十歳くらいの普段着の青年が出てきた。椿たちは身構えた。
「何の用だい? ここへ入りたい?」
「まっまさか! こんな怠惰な集団の仲間に入りたくないわよ」
椿が勇気を出して言った。
「怠惰な、とはご挨拶だなあ。皆、好き好きにリラックスしてるだけだよ。現代社会のストレスやプレッシャーに負けないように」
「リラックスというより、集団で怠けてるみたいにしか見えないわ」
「集団で怠けてるだとう?」
熊のような大男が、いっそう怖い目つきで睨んだ。
「おい、羽田さん」
青年が呼ぶと大きなリュックに荷物を詰めていた男がぴしりと立ってきて、椿たちに頭を下げた。
「何でしょうか、ボス。こちらはお客様ですか」
軍隊ほど厳めしくもなく、だらけてもいない清潔で爽やかな態度だった。
「ね? お客さん。皆、名前を呼ぶと羽田さんみたいにしっかりした態度に戻る。この座敷でリラックスしてるのは、ピシリとした態度に戻るためなんだよ」
「ええ?」
本当かしら? という視線を投げると、男は聞こえたように、
「本当ですよ。僕は最木(さいき)と言います。最木若彦(さいきわかひこ)。『ぐうたらしよう講座』の代表です」
「あなたが代表!」
椿とスミレは手を握り合った。
「私は木暮茶道教室から来ました。深山椿(みやまつばき)です」
「谷川スミレです」
「で、用事は何ですか」
「最近、うちのお弟子さんたちがここに通ってきているでしょう。洗脳しようとしているのでしたら、返して下さい」
「洗脳?」
最木若彦は、その言葉に苦笑したが、やがて大笑いした。
「僕たちはただ、ぐうたらしたいだけで僕はその場所を貸してるだけ。募集もしていないし宗教法人でもなんでもないよ。好きに来て好きに帰ればいいんだ。費用も何もいらない。ましてや強制もしてない」
最木という男は開き直っている。
「ただ」
「ただ?」
「僕が推奨したいのは『正座禁止』だ」
第四章 ぐうたらの報告
木暮茶道教室のガラガラと開ける戸は、激しく開けられ、バシンと閉められた。
「何なの、あの最木って人!」
椿が珍しく頭をかっかさせて帰ってきた。
「椿ちゃん、落ち着いて」
スミレがおろおろしている。
「だって、『正座禁止』って言われたのよ、正座からほど遠い人から! いくら何でも怒るわよ」
「まあま、玄関で騒がしいわよ、あなたたち」
木暮先生が奥座敷へ入るよう勧めた。
奥座敷で座卓を囲んで三人は座り、「ぐうたらしよう講座」の報告を始めた。
「何なんです、『正座禁止』だなんて! 道理であの講座に寝転がったりしてる人たちのお行儀の悪さ、やる気のなさ!」
かなり頭に血が昇った椿は、怒りのあまり言葉が乱れ気味だ。
「椿さん、冷たいお茶でもお持ちしましょう」
木暮先生が驚いて言ったので、スミレが台所に立ち上がった。
冷茶をごくごく飲んでから、椿はやっとひと息ついた。
「ボスの最木って人、東都大出身なんですって。卒業証書が額に入れて飾ってあって身分証明書まで見せられましたよ。肩書は何も無かったですけど」
「何もなかった?」
「ええ。趣味で『ぐうたらしよう講座』をやっていて無職なんですって。それも高学歴ニート」
「高学歴ニート! そういえば、そんな言葉がいっとき流行ったわね。聞いたことはあるけど本当にそういう方、いらっしゃるのね」
木暮先生も眼をくりくりした。
「『ぐうたらしよう講座』の方のほとんどがそうなんですって。どこの一流企業の就職試験受けても合格できるか、医者や司法書士の免状も持っているのに就職も開業もしないとか、一般知能指数の人と同じ職業につけるもんか! と、プライドばかり高くて仕事に就こうとしない人たち。そういう方々が『ぐうたらしよう講座』の面々なんですって」
「まあ」
「何をしようと、その人のご勝手ですけどね」
スミレも口をはさんだ。
「でも、ここのお教室の生徒さんを引きずり込むのは良くないでしょう? スミレちゃん」
「それはそうですよ」
「正座が必須項目の私たちに、『正座禁止』してぐうたらポーズしてリラックスしなさいってのは」
「それは本当に困りますね」
木暮先生もため息で言った。
「うちの生徒さんたち、私の教えのプレッシャーで『ぐうたら』したいと思ってらっしゃるのかしら」
「木暮先生のご指導はピシリとしていて、茶道の腕前も確かで、そしてお弟子さんたちに思いやりもおありですわ」
椿は力を込めて言った。
「茶道の指導でネを上げてるのではなさそうですけど」
「椿さん、その最木さんて『ぐうたらしよう講座』の代表の方、どうしてそんな講座を開こうとなさったのかしら」
「それです! 不思議なのは。もう少し調べてみる必要がありそうですね」
「椿ちゃん、スミレちゃん。引き続いてお願いしていいかしら」
「もちろんです! 木暮茶道教室の危機ですもの。できるだけのことはしますわ」
椿は胸をドンと叩いた。
第五章 再び「ぐうたら講座へ」
椿とスミレが「ぐうたら講座」の見える角まで来ると、美しい和装の妙齢の女性と老婦人が最木を引っぱって出てきたところだった。
「坊ちゃん、お願いです。旦那様のいうことを聞いて『ぐうたらしよう講座』をやめて下さい」
「若彦さん、婆やさんのおっしゃることを聞いてあげて下さいな」
ふたりとも悲痛な面持ちで最木に頼んでいる。
スミレが椿に耳打ちした。
「若彦さんですって」
「綺麗な方ね。多分、花街の方ね、あのお美しさは」
「そんなこと分かるの? 椿さん」
「だいたいね。花街の方とのおつき合いがあるくらい裕福な方なのかしら、ぐうたら講座のボス」
最木は老婦人の手を振りほどいた。
「親父にはっきり言ってくれ! 俺はかんざし屋は継がないと」
ピシャリと戸を閉め、カーテンも閉めてしまった。
手をほどかれた拍子に老婦人が転んでしまい、美人が慌てて起こして泥をはらっている。
「大丈夫ですか? 浪江(なみえ)さん」
「ええ、ありがとう。大丈夫よ」
助け起こされた老婦人に、椿が声をかけた。
「失礼ですが、ここの『ぐうたらしよう講座』の方でしょうか。私は深山椿と申します」
老婦人と美人は驚いて椿を振り向いた。
「いえ、そうではないんですよ」
「最木さんのお知り合いですか? 実は『ぐうたらしよう講座』のことで困っている者です」
「まあ、坊ちゃんがおたく様にご迷惑を? 詳しく聞かせて下さい」
椿とスミレはふたりを近くの和風カフェに案内した。焦げ茶色の内装で、すべてお座敷席の落ち着いたカフェだ。
四人はお座敷の一角のテーブルに着いた。
老婦人と美人の正座をついつい注目する椿だ。ふたりとも優雅と言える素晴らしい正座だ。正座に慣れている。
「申し遅れました。私とこちらのスミレちゃんは、三丁目先の茶道教室に通う者です」
コーヒーが運ばれてきて、品のある色目の着物をまとった老婦人が口を開いた。
「私はさっきの場所にあった老舗かんざし屋に長く仕える浪江と申す者です。こちらは、お得意様の楽乃(らくの)さん。芸妓さんです」
楽乃という芸妓は、伏目がちに頭を下げた。艶やかな美しさ、襟元、うなじの線、さすがの色っぽさだ。
「実は最近、茶道教室の者がどんどん『ぐうたらしよう講座』に流れていってしまって。事情がよく分からず困っているのです」
「まあ、坊ちゃんの開かれた風変りな『ぐうたらしよう講座』に?」
「坊ちゃんというのは、最木さんのことですね?」
「そうです」
老婦人は大きなため息をついて肩を落とした。
「江戸時代から続くかんざし屋の老舗、『さいき』の長男なんですが、跡を継がないと言い張られて店が新しい場所に移転しても古い店に残られて、あの講座を開いてしまわれたんです」
「まあ」
「私は坊ちゃんの亡きお母さまのお付きの女中として『さいき』にお仕えしているのです」
老婦人の表情には、亡くなった母親に代わって若彦を見守るのだという決意が浮かんでいた。しかし困り果てているようだ。
「旦那様は坊ちゃんの態度に烈火のごとくお怒りです。小さい頃から老舗の跡取りとして育ててきたのに、大学を出られたら急に旦那様に反抗なすって」
「どうして急に」
「はっきり分かりませんが、かんざし屋は、呉服屋さんと同じようにお座敷からお客様を正座してお迎えします。それがどうしてもお嫌だとおっしゃって」
「正座するのが嫌ですって」
椿の心に、また怒りがこみ上げた。
それまで黙っていた芸妓の楽乃さんが、控えめに、
「奔放な若彦さんのこと、大学までたくさんのスポーツをされてきたので、かんざし屋さんの商いが合わないと感じたのでは」
椿はカンカンになって、
「自分が勝手にイヤになるのは構わないけど、どうして変な講座まで開くのよ、ただの反抗心? お父さんへの見せつけってこと?」
口走ってしまった。
「椿ちゃん、言い過ぎよ、まだ事情が分からないんだから」
スミレが慌てて止めたが、浪江は、
「誠に申し訳ないことをいたしまして。おそらく旦那様への反抗だと思われます。元からあまり仲の良くない親子でしたから。お母様を亡くしてから、よけいに」
平謝りする浪江に椿は謝り、後はかける言葉がなかった。
カフェの前で別れ、浪江は楽乃に支えられるようにして帰っていった。
つい声を荒げてしまい、椿は反省していた。年老いた背中の浪江が気の毒に思えた。
「スミレちゃん。私、もう一度、『ぐうたらしよう講座』に行くわ」
「椿ちゃん!」
第六章 強行作戦
椿は若彦の前で土下座して、
「浪江さんのためにもお店に帰ってあげて下さい」
とお願いしたが、
「それはできんと言ったらできん!」
若彦に取りつく島は無かった。
しょぼくれて茶道教室に帰り、木暮先生に報告する。
「かんざし屋さん『さいき』知っています。私も何度かかんざしを買わせていただいたわ。そう、あそこの息子さんが代表なの」
木暮先生もしみじみと言うのだった。
その翌日、茶道教室に来客があった。
昨日の芸妓、楽乃だった。ちゃんと菓子折りを持参して木暮先生と椿の前で挨拶した。
「おそらく、若彦さんは正座の姿にお母様の面影を見てしまい、辛いのだと思います。それでも本当は寂しがり屋なので、お仲間と共に『ぐうたらしよう講座』を開かれたんでしょう」
心から若彦を心配している様子だ。
「こうなったら強行作戦に出るわ」
楽乃が帰ってから、しばらく考えこんでいた椿は宣言した。
「スミレちゃん、また無理を言うけれど、きいてもらえる?」
「何? 椿ちゃん」
「『ぐうたらしよう講座』に身分を隠して参加してほしいの。そして、無理やり軟禁されてるって、皆の前で証言……」
「ええっ」
「いえ、証言までしなくていいわ。ボスに伝えてほしいの。この木暮茶道教室に来てほしいって。さもなくば、無理やり大勢の人を軟禁して『ぐうたらしよう講座』をやってるって、警察に訴えますからって」
「ボスを脅すの! 椿ちゃん、私、そんなこと言えるかしら。それに私、ボスに会ってるのよ。顔が……」
「なんとか変装すれば分からないでしょう。お願い、スミレちゃん、勇気を出してボスをここに連れてきてほしいの」
椿はスミレの肩をつかんで瞳の奥を見つめた。
「お気の毒な婆やさんと、楽乃さんのためよ」
「婆やの浪江さんと楽乃さんの――」
「そして、これは木暮先生のお願いでもあるの」
「木暮先生の?」
スミレは不思議そうな顔をした。
「わけはすべてがうまく行ってから話すわ。そして誰より、ボスの若彦さん親子のためでもあるの」
「椿ちゃん……」
スミレは椿の真剣さを受け止めた。
いつもきちんとした身なりのスミレだが、ストレートのロングヘアは櫛がちゃんと通ってないような乱れ方にして、紺のジャージの上下を着て、お化粧はいっさいなし。メガネはずらしてかける。
そんな恰好をして、『ぐうたらしよう講座』に向かった。
夜になって椿のスマホに、スミレから連絡が入った。
「潜入成功」と。
椿はしっかり頷いた。
毎日、スミレからの報告をじりじりして待っていた椿だったが、やっと電話がかかってきた。スミレかと思ったが、若彦本人からだった。
「俺を茶道教室に呼び出そうってのは、どういう魂胆(こんたん)だ」
椿が言い返そうとした時、木暮先生が素早くスマホを取り、電話に出た。
「もしもし、わたくし、三丁目で茶道教室を開いている者です。どうか、こちらへいらして下さい。お見せしたいものがありますから」
「なに?」
有無を言わせず、木暮先生は電話を切り、椿に返した。
第七章 若彦、茶道教室へ
大男の弟子、虎徹が気をもんでいるにも関わらず、若彦はスニーカーを履いた。
「ボス、お供しますぜ」
「勝手にしてくれ」
若彦は茶道教室に向かった。
玄関でチャイムを鳴らすと、椿が出てきた。
「庭にお回り下さい」
庭には風流な植木や鹿威し(ししおどし)、花手水(はなちょうず)がこしらえてある。その中に小さな茶室が建っている。
にじり口と呼ばれる小さな入り口から客は入ることになっている。
「こんな小さいところ、わしは無理ですぜ」
虎徹が嘆いた。
「確かにどう考えても無理だな。そこで待っててくれ」
「ボス! くれぐれもお気をつけて」
若彦がかがんでにじり口から入ると、釜で湯を沸かした木暮先生が美しい正座をしたままお辞儀をした。
「ようこそいらっしゃいました。若彦さん。お久しぶりですね。お母様とご一緒によく来て下さった頃は……」
「まだ小学校に上がる前でした」
「こんなに立派になられて。お母様のことはお聞きしていました。まだお若かったですのにね」
「はあ……で、今日は何ですか」
「あなた、お店を継がずに風変りなリラックスできる場所をお作りになったとか」
「それをやめろということですか」
「まあまあ、せっかく懐かしい人がおいでになったのですもの。お茶を一服、召し上がって下さいな」
襖を開けて入ってきたのは、楽乃だった。白い鶴が翼をたたむように華麗に正座し、
「私が点てさせていただきます」
「どうして楽乃さんが」
若彦は驚いて立ち上がりかけたが、座りなおした。
楽乃は袱紗(ふくさ)さばきも鮮やかに茶を点て、茶碗を置いた。
若彦が椀を手に取り、一服喉に流し込んだ。熱くほろ苦い。身体の芯を温め、胃の底に落ちてゆく。
それは、亡き母が茶を点てる姿と重なって、よけい身体の中心に沁みた。
「結構なお点前でございました」
一礼して顔を上げると、楽乃が髪に刺しているかんざしに気づいた。象牙の中に珊瑚の花びらが散りばめてあるバチ型のかんざしだ。確か、母親が気に入っていたものではなかったか。
「かんざしにお気づきになって?」
木暮先生が口を開いた。
「お母様から昔にいただいたお品です。今日は楽乃さんに刺していただきました」
「……」
楽乃は、頬を染めている。
「若彦さん。お母様はかんざしのお店を継がれることを望んでいたはずです。どうして違う道に行かれたのですか」
「木暮先生、僕は今、必死で耐えています。正座やお茶を見ると、病でやせ細った母を思い出してしまうんです」
「困ったことねえ。お父様もそれを望んでいらしたでしょうに」
「意気地なしとでもなんとでも言って下さい」
こうべを垂れる若彦だった。
「若彦さん、結局、あなたのお始めになった『ぐうたらしよう講座』の目的も、茶道と同じではないかしら? 煩瑣(はんさ)な毎日の騒音から逃れて、ひと時、静寂に浸る……同じ境地だと思うわよ。きっとお母様も喜んで下さいますよ」
「……!」
若彦の表情に光が点った。
「若彦さん、私もそう思います。どうかお父様と浪江さんの元へ帰ってあげて下さい」
楽乃も深々と頭を下げた。
庭の遠くから、水琴窟(すいぎんくつ)の一滴が反響する音が聞こえた。続いて野鳥のさえずりが。
木暮先生は遠い目をして、
「小さかった若彦さんは、お母様のお教えされる順序をちゃんと守って上手に正座していたわ」
ちゃんと身体を真っすぐにして、着物の裾はお尻の下に敷いてかかとの上に座り、両手は膝の上に乗せる。
「微かに覚えています」
急に、木暮先生が立ち上がり、
「正座禁止をくつがえせ!」
と、叫んだので若彦も楽乃も呆然とした。先生は座りなおし、ふたりに微笑み、
「正座を禁止しちゃいけません。お母様が嘆かれますよ。今のであなたの弱気は飛んで行ったはず。どうか、お父様の元へ帰ってあげて下さい」
木暮先生の長いお辞儀を、若彦は見つめていて、
「……分かりました。時間はかかるかもしれないけれど、努力してみます」
「ありがとうございます、若彦さん」
楽乃も涙をこらえて深々とお辞儀した。
すべてを襖の外で聞いていた椿とスミレも泣いていた。
「椿ちゃん、いいの? ほんとは若彦さんのことを」
椿はスミレの可愛らしい唇に指をあてた。
若彦と楽乃、そして虎徹が帰っていくのを、木暮先生と椿たちは見送った。
晩春の陽の長い夕暮れ、三人の影が長く伸びて遠ざかっていく。
「今度は、若彦さんのお父様と婆やさんもお呼びしてお懐石もいただいて、ちゃんとお茶事しましょうね」
「そうですね、先生」
「その時は椿さんが亭主よ」
「心得ました」
師匠と弟子は微笑みあうのだった。