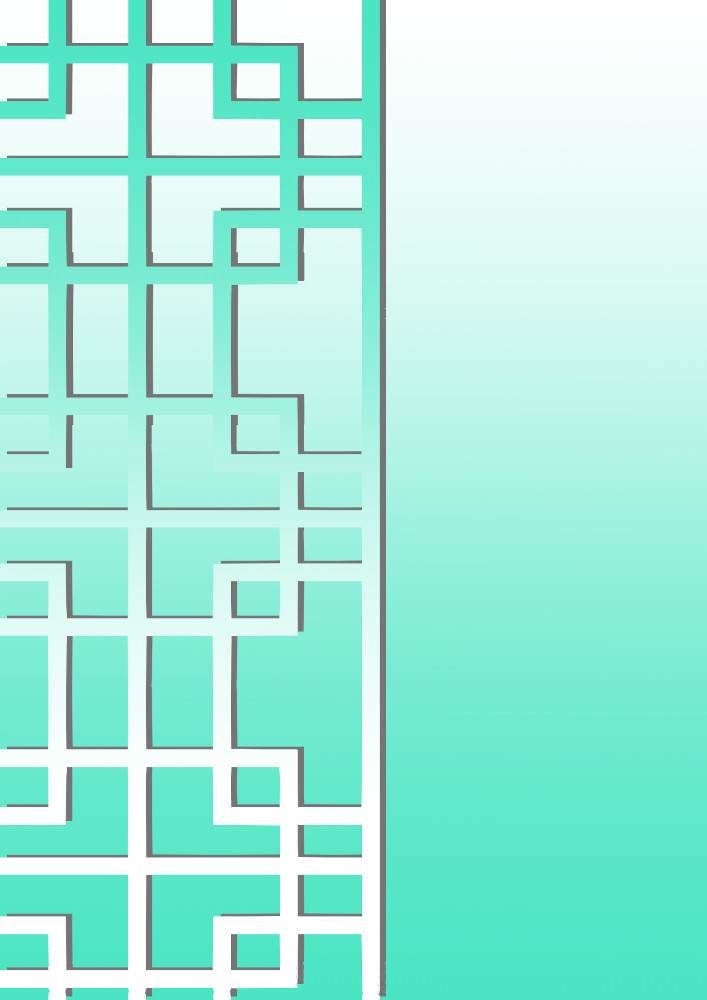[229]螺鈿(らでん)姫の正座

タイトル:螺鈿(らでん)姫の正座
発行日:2022/06/01
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:52
販売価格:200円
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
彩華(さいか)は高校生。正座を習っていた祖母が亡くなり、四十九日の法要で、又従兄(またいとこ)の漆山うるしと久しぶりに会う。上手く正座ができないことをからかわれて傷つく。
祖母の部屋には奥にもうひとつ部屋があり、螺鈿細工の施された大きな鏡台があった。彩華が覗くと鏡の向こうは果てしない草原で、向こうから一騎の馬がやってくる。兵士に引っぱられ鏡の向こう側へ入ってしまった。それを目撃していた漆山うるし。
彩華は若い将軍、太都馬(たづま)に馬に乗せられ、湿地帯の草原(星宿海)を駆けて行き、螺鈿城という小さな城へ連れて行かれる。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/3906815


本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序 章
星宿海(大陸の黄河の上流)の湿地、一面の緑、空の白い雲を映した美しい湖沼の群れ。
馬に乗って駆けてくる若い兵士。馬に着けられた鞍やあぶみ(乗り手が足を乗せる馬具)は瑠璃色と真珠色のきらびやかな螺鈿細工が施されている。
池の中のひとつに、青空とは違うものが映っている。
(あの娘だ!)
第 一 章 祖母の法要の日
山深い地方にある父の実家が、彩華は好きだ。
庭の木々が豊に茂り、半月に一度訪れる時と同じ空気だ。違うのは、彩華が喪服を着ていて、優しい祖母がいないことだけだ。
法事を終えたばかりの人々が、お膳をいただく間へ渡り廊下を黙々と移動していた。
「彩華?」
グレーの高校の制服姿の男の子が声をかけ、喪服姿の彩華が立ち止まる。
「えっと、うるしくん……よね?」
確か、又従兄(親同士がいとこ)の漆山うるしだ。
黒目がちの瞳とツヤツヤとした黒髪の少年で、子どもの頃から思ったことをずけずけと言うやんちゃだ。
「驚いた! 同じ学年よね? ずいぶん背が伸びたわね。うるしくんもお祖母ちゃんから正座の所作を習っていたのよね?」
「正座の下手な彩華。習いに来ていたって聞いていたが、曜日が違うから顔を合わさなかったな」
彩華は、ムッとした。
「久しぶりに会ったのに相変わらず口が悪いわねぇ」
「後ろから見ていたら、ご住職の読経の間も上半身グラグラだったぜ。お祖母ちゃん、安心して天国行けるかな〜?」
「お祖母ちゃんは言ってくれたわ! 少しくらいどこか曲がっていても、私の正座は私らしさだから、そのままで大丈夫ですよって」
「俺にも同じこと言ってくれたぜ」
お膳をいただく親戚たちは、お葬式の時よりも悲しみが和らいだと見えて、祖母の思い出話に興じていた。
「蒔絵さんは、八十歳を越えられても美人でしたね」
「正座姿が美しくて、いつも背すじをピンとされていたわね」
彩華は、長年可愛がってくれた祖母が呆気なく逝ってしまったので、お膳にもあまりお箸をつけられなかった。
(お祖母ちゃんが生きているうちに、もっと正座を上手になるんだった……)
向かい側を見ると、うるしがお膳の品をパクパク食べていたが、時々うつむいて箸を止めている。悲しみを隠せないようだ。
彩華は、席を立って通い慣れた祖母のいた離れへ向かった。
部屋には穏やかな日差しが入りこみ、祖母が亡くなる前と何も変わっていない。
祖母の愛用していた和だんす、文机、その上の硯、書棚、茶道の用具の並んだ棚、そして螺鈿細工の座椅子。
螺鈿細工の椅子は足のついた品がほとんどだが、正座ができるように祖母が特注したと聞いていた。花や蝶々など、繊細な細工がなされていて青白く輝いている。
座椅子に正座してみる。まず、背すじを伸ばして立ち、膝を座椅子の上に着けて、スカートの裾をお尻の下に敷き、かかとの上に静かに座る。両手は膝の上に置く。
(これでちゃんと正座できてるかな? お祖母ちゃん)
祖母の座椅子には、温もりが残っているように感じられた。しかし、正座には相変わらず自信がない。
今日の親戚たちは美しく正座できていた。しかし彩華は両親から「もっとちゃんとしなさい」と言われるほど、うまくできていないのだ。
「生まれつき、うまくできない女の子は、どこかへ消えてしまいました……」
童謡が、そっと唇からこぼれた。
ふと部屋の隅に目をやると、祖母の部屋の衣紋掛け(着物を広げてかけておく家具)の向こう側に見たことのない襖があることに気がついた。
(奥にも部屋があったなんて気づかなかったわ)
彩華はそっと入ってみる。四畳半くらいの小さな部屋だが、彩華の背丈ほどの鏡台が置かれていた。螺鈿細工が神秘的な青白い光を発している。独特の紋章のようなものが浮かび上がっていた。
かけられていた布をそっと外してみる。
そこには――。
果てしない緑の草原が広がっていた――! !
第 二 章 螺鈿一族の城
鏡の向こうに夢のように美しい緑の草原――!
草原には、いくつもの湖や沼が点在していて青空と白い雲を映して眩しい。
あまりに意外な光景に、彩華はへたりこむように鏡台の前に座った。
(どうして鏡からこんな景色が? ここは日本じゃない――?)
地平線から何かが近づいてきた。目を凝らしていると、見慣れない瑠璃色の鎧をまとった若い兵士が一頭の馬に乗って駆けてくるではないか。
彩華は目が離せない。
水飛沫を立てて鏡台の前まで駆けてきた体格の良い兵士は、馬を下り、彩華を見て目を輝かせる。
「その座り方は?」
「正座、あのう、いえ、腰が抜けただけですが……」
恥ずかしさのあまり彩華は小さい声で答えた。
「素晴らしい正座だ! 来てください!」
いきなり腕を引っぱられた。不思議なことにスルリと鏡の向こう側に入れた。
襖のかげから漆山うるしが一部始終を見ていた。驚きに目を見開いて動けない。
彩華は瑠璃色の鎧の青年の後ろに乗せられた。
「どこへ連れて行くんですか!」
馬の背に乗ってみて分かった。馬具にも青白い螺鈿がくまなく施されている。
「ハイッ」
青年が馬の腹を蹴って駆け出す。
湖の群れの果てには、白い雪を頂いた険しい山脈が見えるが、彩華は青年の背につかまるのに懸命で眺めている余裕もない。
「しっかりつかまっていなさい。あの山脈のふもとに向かう」
頬を切るように冷たい風が、耳の横をビュンビュンと過ぎてゆく。
やがて、馬は山麓にある漆黒の小きな城にたどり着いた。
城門が開けられ、兵士たちが青年を迎える。彩華も鞍から下ろされた。
「ここは……」
「螺鈿城だ。螺鈿一族の長の城だ」
「螺鈿一族――?」
初めて聞く民族の名だ。
城の壁は真っ黒で、あちこちに青白い飾りが嵌めこまれている。
本殿らしき建物から女人が十数名、迎えに出てきた。そろって細かい金糸を散りばめた純白の着物を着ている。
「彼女を頼むぞ」
「え……え?」
女官たちは彩華を本殿の奥へ導いていく。
長い長い漆黒の廊下を通り、ひとつの部屋にたどり着いた。瑠璃色の絨毯が敷かれ、椅子といい寝台といい、大陸の異国めいた贅沢な調度だ。
大きな座椅子が置いてある。
「この座椅子は!」
彩華は目をこすった。祖母が特注した螺鈿の品とそっくりなのだ。
「ささ、こちらでお着替えになって。お手伝いいたします」
女官たちが寄ってきて、ツルツルの肌触りの衣に着替えさせていく。仕上げのように、馬で連れてきた青年が金糸を散りばめたヴェールを頭からかぶせた。
「私は太都馬。太都馬将軍と申す」
青年はいかつい形の兜を脱ぎ、その場に正座して彩華を見上げた。
焦げ茶色の髪と瞳が誠実に満ちている。
「どうして私を連れてきたんですか? 私は祖母の部屋にいて……」
「この座椅子に正座してみてください」
太都馬は、指さした。
ついさっき、昼過ぎに、法事のお膳の席を抜け出して祖母の部屋で座ったのとそっくりな座椅子だ。
「どうぞ、お座りになってください」
女官たちにも促され、彩華は螺鈿の座椅子にいつもの所作で座る。
(背すじを真っ直ぐ……、座椅子の上に膝をついて、衣はお尻の下に敷いて、かかとの上に座る……。こ、これでいいかな?)
額に汗が浮かぶのが感じられた。
「素晴らしい正座です! 次は大広間の玉座に座っていただきます」
「玉座? 玉座って王様とか偉い人が座る席のことよね」
太都馬に案内されるまま大広間に行くと、大勢の人々が正座して待ち受けていた。東洋人と、水色に透けて見える人までいる。
(うわ、映画でしか見たことのない景色だわ!)
「高官や女官、庶民も集まっております。水色の存在は螺鈿細工の妖精です。さあ、玉座に正座してください」
またもや太都馬将軍が勧める。
彩華はカチコチになりながら、皆の前で正座してみた。
大広間の人々は、しばらく水をうったように静かにしていたが――、パラパラと拍手が始まり、やがて大拍手が起こり、庶民たちは誇らしげだ。
「さすが螺鈿姫さまだ! 特別な正座ですな」
「一族の長らしい威厳があふれている」
「文句なしの素晴らしい座り方だわ」
割れんばかりの拍手の中で、彩華は呆然とする。
(私の正座が褒められている? ――し、信じられない!)
(みんな螺鈿姫って言ってるけど、人違いよ)
彩華の耳元に、太都馬将軍が螺鈿細工の花かんざしをそっと挿そうとした。
「これは?」
かんざしにも祖母の鏡台と同じ紋章が螺鈿で嵌めこんであるではないか。
第 三 章 替え玉
人々に褒められても、彩華は素直に喜べなかった。
自分の正座がどんなに下手で堂々としていないか、よくわかっている。
『彩華は大丈夫。彩華らしい正座でいいのよ』
祖母の懐かしい励ましが聞こえたが、彩華はどうしても自信が持てない。
(お祖母ちゃん……、自分で納得できなければダメだわ)
部屋に戻って考えていると、太都馬将軍がやってきた。
「知らないところへ連れてこられて、さぞお心細いことでしょう」
「心細いです。言葉が通じるのだけが救いだわ。いったい、ここはどういう世界なの」
「少し外へお連れしましょう。緑と湖に囲まれた中でお話します」
連れて来られた時のように馬の背に乗せられ、星宿海という広大な湿地帯へやってきた。
「ここ星宿海には、螺鈿細工の職人がたくさん生活しています。他にも螺鈿占い、螺鈿守りなども多数暮らしています」
「何も見えない。人の気配も感じられないわ。湖と沼の上を緑の風が吹き渡っているだけ」
「彼らは妖精のような存在ですから」
太都馬将軍は、星宿海をぐるりと見渡した。
「人間の庶民や妖精たちを守るのが、螺鈿姫のお役目なのです」
「螺鈿姫って――?」
「螺鈿城の城主です。この国は高度な螺鈿技術を持つがゆえに、他の国から狙われています。螺鈿姫のお命もまた、狙われています。そこで――、彩華さん、あなたに来ていただいたのです」
「――?」
「あなたは螺鈿姫の面差しによく似ておられる。それで、姫の代わりに……」
「代わりですって? つまり、その螺鈿姫の替え玉をさせるために私を連れてきたということ?」
「それもありますが、姫は今、安全な場所に隠れておられます。不在の間、庶民に安心してもらうためでもあります」
(この太都馬将軍とかいう人の言うことを信じてもいいのかな)
焦げ茶色の瞳は誠実そうで、ウソを言っているようには見えないが、決して心の奥を覗かせない厳しさを感じる。
「ひとつきいていい?」
「はい」
「どうして私が、螺鈿姫と似ていると判ったの?」
「あなたのお祖母さまが、大鏡を通して常に螺鈿姫とお話してらしたからです」
「お祖母ちゃんと螺鈿姫が――!」
いっそう強い風が吹き抜け、丈の長い草を波打たせた。
「太都馬将軍。その、螺鈿姫にお会いすることはできますか」
彩華の口から自分でも驚くような言葉が出た。
太都馬も、やや驚いたのか、彩華の顔をまじまじと見つめた。
「会わせてください。私をここへ連れてきたのが螺鈿姫のご意志なら、お会いする権利があると思います」
「……言われるとおりです。螺鈿姫におうかがいしてみましょう」
太都馬は口の端に笑みを見せ、馬首を返した。
第 四 章 星空に飛びこむ
その夜、彩華の部屋に再び太都馬が姿を現した。
「螺鈿姫がお会いになるそうです。もう一度、星宿海に行きます。凍えるような寒さだ。身支度してください」
侍女たちが急いで彩華の着替えを持ってきた。厚手の衣に、羊の毛皮のコートだ。
昼間のように太都馬の馬に乗せてもらい、星宿海に向かう。なんという冷たい空気。馬の吐く息の湯気のなんというすさまじさだろう。
鞍に着けられた沢山の馬鈴がシャンシャンと鳴る。
丘から見下ろすと、星宿海の湖沼群は、それぞれ星を映して地面に星空があるかのようだ。
「将軍さま、螺鈿姫はどこに?」
「星の海におわされる」
「えっ? ――きゃあっ!」
次の瞬間、太都馬は丘を下って馬に乗ったまま、湖のひとつに飛びこんだ。水しぶきが派手に飛び散ったところまでは、彩華は見ていない。
苦しいはずなのに一瞬冷たかっただけで、青い世界が開ける。
水底の地面に馬は降り立った。意外にも水は無い。
「さ、鞍を下りられよ」
太都馬の手を借りて彩華も下りてみた。
青い壁に無数の洞窟があり、その中で半透明な妖精が大勢で、螺鈿細工に精を出していた。
奥まったひとつの洞窟に、青い炎のろうそくが一本、燃えている。中ではひとりの女性が正座して螺鈿かんざしを作っている。
「螺鈿姫である」
太都馬が紹介した。
「さ、彩華です」
姫は細工の手を止め、正座したまま笑顔で迎えた。普通の東洋人と変わりない。笑顔がなんと美しい女性だろう。
「彩華さん。突然のお呼びたてにも関わらず、よくおいでくださいました」
彩華は螺鈿姫の面差しがなんとなく自分と似ていることに驚く。緊張しながら彼女の正面にゆっくり正座した。――つもりだが……。
思いきって尋ねる。
「生前の祖母と大きな鏡越しにお話なさっていたと聞きました。祖母は何をお話していたのでしょうか」
螺鈿姫の眼が穏やかに見つめてきた。
「あなたのことです。蒔絵さんは、ずいぶん心配されていましたよ。正座の所作が上達しないと言って嘆いていると」
「は、はあ……」
「蒔絵さんは、正座は所作を大切にしなければならない。けれど、あなたらしさがどこかに入っていても構わないという考えでした。わらわもそう思います」
「でも、何度やってもきれいな正座ができなくて……なんてダメな人間なんだろうと」
足元に視線を落として、もぞもぞ言い訳してしまう。
「所作が完璧にできないからといって、あなた自身がダメな人間ではありません。大切なのは向上しようという意志です」
螺鈿姫は続けた。
「この国は昔から荒い気質の魂胆族に狙われています。螺鈿細工のできる職人を根こそぎ連れて行くつもりです。猛荒という男が将軍になってから、よけい攻撃が激しくなってきて、すでに何人かの螺鈿職人がさらわれました。城に総攻撃をしかけてくるのも、そろそろかと覚悟しています」
「まあ……」
「そこで、以前から鏡を通して蒔絵さんから聞いていたあなたに、来ていただいたのです」
螺鈿姫の視線が彩華を射抜いた。
「で、私は何をすれば?」
「わらわが魂胆族から身を隠す間、民を安心させるために代わりに玉座に正座していていただきたいのです」
「でも、私なんかに姫さまの代わりが務まるでしょうか? 民の皆さんは認めて下さるでしょうか?」
「民衆の前で正座する難しさは、よく分かるつもりでご無理なお願いをしています。どうか『私なんか』などと謙遜なさらないでください。あなたはお祖母さま――蒔絵さんのお孫さんなのですから」
彩華は泣きたくなった。
(いきなり知らない世界に連れてこられて、城主の代わりに苦手な正座をするなんて……)
「彩華さん、あなたならできます。蒔絵さんから正座を習ってらしたんですもの」
「いえ、私なんか……」
「『私なんか』などと二度とおっしゃらないこと! もっと堂々として。あなたの正座が自信を連れてきてくれます」
螺鈿姫の白い手が彩華の両肩に置かれた。細くてしなやかだが、力強い。
第 五 章 悩みと目覚め
螺鈿城に戻った彩華は、与えられた部屋を歩き回って考えた。
(どうして、あんなに正座にこだわるのだろう? 敵が攻めてきても、何の防御にもならないのに)
床の上で繰り返し祖母に習った正座をしてみる。
『座ったら、胸を張って! 彩華』
祖母の声が心によみがえった。
『姿勢、呼吸、心よ、彩華』
「はっ!」
彩華の心の奥で大きな灯りがともった。
「正座の姿勢が、呼吸を調え、自信ある心を作るのね!」
星宿海の底で会った螺鈿姫の落ち着いた笑顔を思い出した。
女官が訪ねてきた。
「姫さまからの書状でございます」
「螺鈿姫さまから?」
彩華は軸になっている書状を文机に広げた。日本語だ。
『 彩華さま
更に、お話したいことがありましたので書状をしたためました。正座は、礼儀であるばかりでなく相手の戦意をくじく力も持っています。「戦いません」という平和主義の意志表示です。しかも屈服せず、誇りを捨てず、自分の国を守り抜くという決意を表わします』
(――!)
彩華の心に青空が広がったように思えた。
(これを読んだおかげで、少し自信がついたような気がする)
次の文章を読んで更に衝撃を受けた。
『これは、あなたの祖母、蒔絵さんにも繰り返し教えたことです。私は蒔絵さんの乳母だったのです』
(! ! 螺鈿姫が蒔絵お祖母ちゃんの乳母? ?)
(ど、どういうことだろう)
書面に目を当てたまま呆然としていると、護衛兵の鎧を着た若い男がひとり、忍び足で入ってきた。
「あなたは?」
護衛兵は兜を脱いでにやりと笑った。ツヤツヤした黒髪があらわになった。又従兄の……。
「うるしくんじゃないの!」
「よう、正座の下手な彩華。こんな異国まで来て、正座のお勉強かい」
いたずらっぽい瞳だ。
「どうしてあなたがここに?」
「お祖母ちゃんから、鏡の向こうの世界の話を聞いていたんだ。彩華が行くかもしれないってさ」
「なんですって」
「その時に守ってやってくれって言われてたのさ」
うるしは照れくさそうに小さな声で言った。
「うるしくん! ここは螺鈿姫の国なの。敵国に狙われているんだって!」
「知ってるよ」
「ここにも軍隊があるから、きっと太都馬将軍という人が守ってくれると思うんだけど……」
「彩華!」
うるしは素早く近寄ってきて、垂れ幕の奥に引っぱった。
「太都馬将軍は敵の魂胆族と通じている。信用できない」
「な、なんですって?」
宮廷の天井がぐるぐる回った。
第 六 章 密書
「太都馬将軍が敵と通じているですって? うるしくん、どうやってそんなことが分かるのよ?」
彩華はうるしに食ってかかった。
「手紙からさ」
「手紙なら、螺鈿姫はお祖母ちゃんの乳母だっていう手紙をもらったわ。頭がこんぐらがりそうだけど」
「きっと螺鈿姫は、見かけは若くても相当トシなんだろうさ」
「うるしくんてば、相変わらず失礼ね」
「その手紙じゃなくて!」
うるしが床をドンドンと踏んでさえぎった。
「俺、太都馬将軍が魂胆族とやりとりした手紙を手に入れたんだ。運んでいた使いを待ち伏せして取り上げた」
「ええっ? そんなことまで!」
やんちゃな又従兄は、何を言い出すのだろう。
「早く螺鈿姫に太都馬将軍の裏切りを告げなければ!」
「そ、そうよね。姫さまは太都馬将軍を全面的に信用してらっしゃるようだし、早くお耳に入れなければ大変なことになってしまうわ!」
「すぐに星宿海の螺鈿姫のところへ行こう!」
うるしは彩華を急がせた。
日が落ちて闇が迫ろうとしていた。
城の外へ出ると、うるしが手に入れたという軍馬が一頭、待っていた。
「うるしくん、馬に乗れるの?」
うるしは鞍をまたぎながら、
「あったりまえさ! 高校の馬術部だぜ」
「湖の中に飛びこまなきゃいけないのよ。大丈夫なの?」
彩華が鞍に這い上がり、うるしの背につかまった。
「どうにかするさ!」
「どうにかって!」
闇にまぎれて、馬は駆けだした。ふたりの会話はびゅんびゅん後ろへ流れていく。
彩華は目をかたく閉じて、螺鈿姫に願った。
(姫さま、大切なお話があるのです。どうかお会いできますように!)
馬は、星宿海を駆け抜け、ひとつの湖の前で立ち止まった。湖面には空の星々が映ってきらめいている。
ほとりに人影が見えた。
「螺鈿姫さまですね!」
「彩華さん、あの書状を送った後、あなたがもう一度来るように感じて待っていました」
彩華とうるしは馬を下りた。
「その者は?」
「私の血縁で、同じく蒔絵お祖母ちゃんの血縁者です。鏡の向こう側から来ました」
うるしは変装のよろい姿のまま、水辺で所作正しく正座した。
「うるしと申します。祖母から正座を習っていました」
(こういう時だけカッコよく見せるんだから)
彩華は心の中で肩をすくめた。
「美しい所作ですね。さすがは蒔絵さんの孫です。で、彩華さんとそろって何用です?」
彩華も改まって、うるしの横に正座した。
「姫さま。落ち着いてお聞きになってください。――太都馬将軍は魂胆族と通じています。これが彼らのやり取りした密書です!」
ふところから書状を取り出し、うるしは螺鈿姫に差し出した。
姫は袖から白い手を出して書状を受け取り、星明りの下で広げた。
第 七 章 螺鈿姫の戦い方
「うすうす感づいていました」
螺鈿姫の第一声は、彩華とうるしを驚かせた。
「数か月前、我が国の軍力を縮小すると決定してから、太都馬将軍の態度はよそよそしくなりましたもの」
「軍力を縮小されるのですか? 魂胆族に狙われているというのに?」
「はい。守りのみに徹し攻撃も迎撃もしません。たとえ魂胆族に襲撃されようと、屈服しない意志は正座してじっと動かない姿勢のみで示します。細工職人がどれだけ連れ去られようと、絶対に抵抗しません」
「姫さま……」
彩華とうるしは呆然とした。
「いくら抵抗してもこちらに怪我人が増えるだけです。太都馬が私の意向に反対なのなら仕方のないことです」
姫の苦し気な表情が痛ましい。
(姫さまは、太都馬将軍を愛しておいでなのだわ。どんなにお辛いことかしら)
「彩華さん。一族をひとりでも多く守るためには、武器を持たず、正座の精神を見せつけることで敵に向かうと決めました。だから、あなたに来ていただいたのです。後悔はしません」
姫は胸を張り、魂胆族との密書をはらりと草原の風にまかせた。密書は風に乗って広い草原の上を飛んでいく。
日の出が近い。
暁の空を、五色の鳳凰が飛んでいるのを見た気がした。吉祥(良い兆し)のしるしと言われていることは彩華も知っていた。
『彩華、あなたならできます。顔を上げて、胸を張って!』
暁の空から、祖母の声が聞こえたような気がする。
彩華とうるしが帰ると、螺鈿城は騒然としていた。
大広間には老若男女の庶民が満ちていて、兵士もずらりと居並んでいる。武器は持たず丸腰だ。
「魂胆族が迫っているそうです」
女官が恐れおののきながら彩華に報告した。
続いて物見やぐらの兵士が叫ぶ。
「山脈の向こうから、魂胆族来襲~~!」
まもなく、たくさんの馬蹄音が響いてきた。まるで地震の地響きのようだ。
彩華は身体が震えだすのを感じた。
「武者ぶるいかい、彩華」
こんな時にも、うるしはからかう。
「そうよ、武者ぶるいよ。こうなったら魂胆でも何でも来なさい!」
「お、カラ元気出したね」
雨のように矢が降りそそいできた。
螺鈿の兵士たちは螺鈿で作られた瑠璃色の盾で防ぐので矢は役に立たない。
魂胆族の騎馬兵がなだれのごとく攻めてくる。
螺鈿族は、抵抗することなく城門を開放した。
猛荒将軍の軍隊は赤土色の鎧の軍装、傍らには瑠璃色の鎧の太都馬将軍がぴたりと馬を着けたまま入城してきた。
「太都馬将軍さまが、魂胆族と共に!」
「どういうことだ、これは!」
庶民たちは慌てふためいた。
彩華はうるしと共に大広間で敵を待ち受けていた。
「皆さん、落ち着いてください。皆さんは私が守ります」
祖母の言葉が再び、脳裏に響く。
『彩華、あなたならきっと出来る。顔を上げて、胸を張って正座するんです。そして―――』
(実行するのね、螺鈿姫のご意向を)
第 八 章 敵の来襲
城内に攻め入ってきた魂胆軍の兵士たちは、大広間にいた兵士や庶民を捕え始めた。
「皆さん、逆らってはなりません」
彩華は叫んで玉座で所作の順序を守り、しっかり正座した。
背すじをまっすぐに、膝を床につき衣は膝にはさみ、かかとの上に座る。
「これはすぐに敵に歯向かえないカタチの座り方です。魂胆族の猛荒将軍、私たちは抵抗しません。戦いません。ここで正座して動きません」
毅然とした正座姿から微動だにしない。
「どうやらカラ元気じゃなく本気だな」
彩華の横で、うるしも正座し、大広間の庶民たちも一斉に正座した。どの庶民も気品を持って座り、動揺はない。
猛荒将軍は虎のように牙をむいた顔を強張らせた。
「こ、これは……」
「その代わり、ひとりでも庶民を傷つけたら、私たちは永遠に螺鈿細工を作りません」
猛荒将軍が玉座まで迫ってきて、剣の切っ先を彩華の喉元に当てた。
「これでもか。螺鈿細工を作らせなければ命はないと申しても?」
彩華のこめかみからひとすじの汗が垂れた。
「……はい」
猛荒将軍の喉元には、うるしが素早く短剣の刃を押し当てていた。
「剣を動かす前に、俺の短剣がお前の喉に食いこむぞ」
「ううっ」
将軍は唸って飛びすさった。
第 九 章 彩華の務め
魂胆軍の伝令がやってきて将軍に伝える。
「我が軍の周りが瑠璃色の鎧の兵士に囲まれております!」
「な、なにいっ」
大広間の庶民たちが、扉を開けて外へ駆け出た。
「瑠璃色の幟と瑠璃色の鎧だ!」
「太都馬将軍の軍が魂胆軍を囲んでいる!」
城の外へ飛び出した猛荒を、太都馬が待ち構えていた。
「猛荒どの、戦いは無しだ。とっとと魂胆の山へ帰られよ」
下馬して優美に正座した。それにならって庶民たちも正座して魂胆の軍に向かってしっかり座る。
「城も螺鈿細工職人も誇りも渡さぬ。我らの揺るがぬ心だ。螺鈿の侵略は諦められよ」
「うぬは、我の味方につくと言っておきながら――」
「我が螺鈿姫を裏切るはずがない」
猛荒将軍は歯ぎしりしながら後退し、配下に助けられて馬に乗った。
「おのれ……。皆の者、退け、退け――!」
太都馬将軍が退却していく魂胆族に向かって叫んだ。
「何度、侵略してこようと我々は戦わぬ。正座して静かにその意を示すだけだ」
星宿海を、赤い幟の兵馬たちが遠のいていく。
大広間から出てきた彩華は、ヘナヘナと地面に座りこんだ。
「終わった……」
うるしもやってきて、太都馬に近づいた。
「変だな? 俺、あんたが魂胆族と手を組んだ密書を手に入れたんだけど」
「うるしくんだな。螺鈿姫から君のことを聞いた。君がワケの分からない庶民の懸想文(=恋文)を持ってきたと」
「庶民の懸想文? ?」
「君はこちらの国の文字が読めるのか?」
「よ、読めないけど……」
「うるしくん! あなた、庶民の恋文を敵との密書と間違えたのね?」
彩華は立ち上がった。
「どうやらそうみたいだ……。魂胆族への使い文だったんで、俺、てっきり。すみません、ごめんなさい、将軍!」
うるしは太都馬に土下座した。将軍は苦笑が止まらない。
「螺鈿姫は納得しかねたが鏡の向こうの人間ゆえ、話を合わせておいたということだ。ま、私が魂胆族と手を組もうとしたと見せかけたのは事実だがな」
「ふたりとも一枚上手だったか!」
うるしはトドメをさされてのけぞった。
「太都馬将軍」
栗毛の馬に乗った螺鈿姫が近づいてきた。周りの者が速やかに正座する。
「許しておやりなさい。その者が彩華さんのことを思って一生懸命やったことです」
姫が下馬し、彩華は駆け寄った。
「螺鈿姫さま! 魂胆軍が撤退しました!」
「ようやってくれました。あなたの正座は凜として立派でしたよ。わらわの代わりを務めてくれてご苦労様でした」
「お役に立てたのですね。良かった。祖母も喜んでくれるでしょうか」
「無論ですとも」
薫るような笑顔で応じてくれた。
「あなたは謙遜ばかりしていましたが、ちゃんと出来ましたね」
「姫さまが勇気を与えて下さったからです。祖母の声も聞こえたような気がしたのです」
「その昔、幼い蒔絵さんに正座の心構えを熱心に教えた成果かしら」
「姫さまが永いお命を活かし、祖母の乳母でいてくださって感激です」
「これで、鏡の向こうの世界に帰っても大丈夫ですね」
「はい。ありがとうございます」
太都馬将軍に送られて、星宿海の鏡まで帰ってきた彩華とうるしは、元の世界へ戻った。前の通りの祖母が使っていた離れだ。
大きな鏡台はもう、草原を映さない。部屋の中が見えるだけだ。螺鈿に祖母の温もりが感じられた。
(お祖母ちゃんは意気地なしの私を勇気づけるために、貴重な体験をさせてくれたのだわ。――ありがとう、お祖母ちゃん)