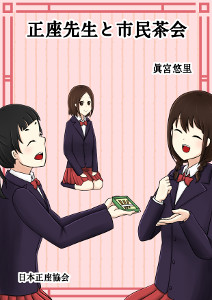[66]羽衣のバレリーナ
 タイトル:羽衣のバレリーナ
タイトル:羽衣のバレリーナ
分類:電子書籍
発売日:2019/09/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
パリでプリマ・バレリーナの座についた緋美子は、プレッシャーに悩み、大切な公演のクライマックスで倒れてしまう。
数日前の車の事故での加害者は能の家元の御曹司の白滝龍太郎で、自分の家で養生をと勧める。
ちょうどその頃、浜で眩しい羽衣の夢を見るようになっていた緋美子は、直感で能との縁を感じ、改めて正座の練習をし、正座もバレエも能も「体幹が基本」ということに気づく。
さて、緋美子は復帰できるか?
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1542534

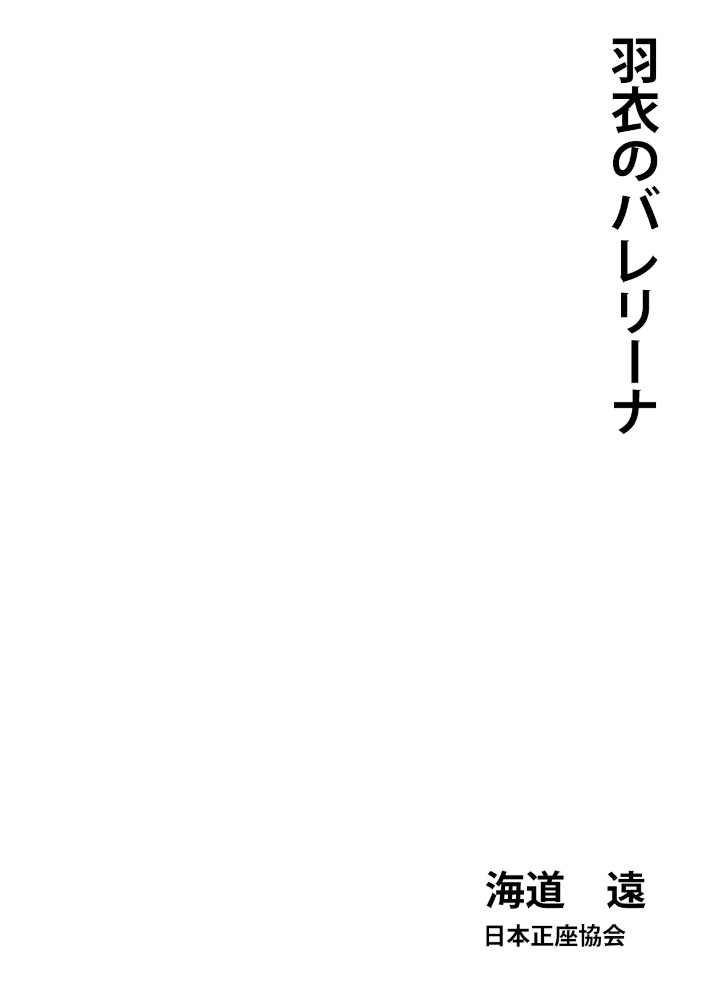
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 悪夢からの眼覚め
月白という和名の色がある。
月の青白さを表現した色だ。今宵の満月も青白く輝いているが、黒い雲が湧きあがり光を隠してゆく。
耳の横を、黒い翼がバサバサと羽ばたいていった。暗い広場に赤々と焚かれているのは、篝火。顔半分を仮面で覆った人間たちが周りで踊っている。
(何だろう、黒い鳥と仮面の人間は。ヨーロッパ中世の黒の魔術の祭りに巻き込まれてしまったみたい)
緋美子は、生暖かい夜風に吹かれて翻弄されていた。全身が軋むように痛い。脚全体も痺れて、背中といったら重い石を乗せているようだった。
誰かが、叫びを発した。
そこで目が覚めた時は胸が轟くように鳴って、上下に揺れていた。
「緋美子さん! 緋美子さん! しっかりして!」
遠くで誰かが呼んでいる。その声がバレエ団の団長、本村美絵だと気づいた。周りは白い壁だ。
「私は……」
ごつくて暖かい手が緋美子の手首をとって脈を診た。
「脳震盪だけですから、時間が経つと落ち着くと思われますよ」
男の声に、本村美絵が礼を言っている。
「先生、私……」
「ここは病院よ。緋美子さん、あなた、舞台の上でクライマックスの時に倒れてしまったのよ。覚えていない?」
思い出せなかった。先ほどの悪夢の余韻がズシリと残っているだけだ。
「緋美子さん、先日、稽古に来る時にぶつかった車があったでしょう。その後遺症としか思えないわ」
「そうでしょうか。あの事故の後、加害者の方は、信用できる病院で精密検査を受けさせて下さったんですよ。異常なしで踊れる体調でした」
「そうよねえ。あなた、今日もクライマックスまでは、好調だったものね」
緋美子の脳裏に、車を接触させた青年の顔が甦る。仕立てのよいスーツを着て、どこかの御曹司という感じだった。
確か名は、白滝龍太郎。
事故を起こしたことにとても驚いて、彼の方が真っ青になっていた。すぐにバレエ団の主催をしている本村美絵を呼んでくれて、自分も秘書の青年を呼んだ。
舞台の上でほんの数分間、意識を失くした間に紅蓮の炎や真っ黒い翼の夢まで見てしまい気分はどん底だった。
それに、今日の公演のために来る日も来る日も練習を重ねたのに、最後に倒れてしまい、団員の皆やお客様に迷惑をかけてしまったことが頭の中を渦巻いた。
ダークな世界がテーマの創作ものだったせいだろうか。
しばらくして、母親が血相を変えてやってきた。
「緋美子、いったいどうしたの。朝、あんなに張り切っていたというのに」
「大丈夫よ、どこにも怪我はないから。ただ身体が重いの」
先ほどの医者が入ってきた。
「身体に不調があるなら、もう一度ここで精密検査を受けた方がいいかもしれないね」
「バレエ団五十周年記念公演を台無しにした上にこれ以上、皆さんにご迷惑は……」
「これ以上、迷惑をかけないために、しっかり検査しておこうね」
「その方がいいわ、緋美子。先生のおっしゃる通り、検査をしていただきましょう」
母親の切望もあって精密検査を受けることになった。
第二章 松原の夢
風がびょうびょうと唸っていた。長い髪が顔面に巻きついたり天に昇ったりしてうっとおしい。
白い浜と松林が果てしなく続いている眩しい世界だ。彼方には、キラキラ光る水平線。澄んだ水色がどこまでも広がっている。吸い込まれてしまいそうな碧い空。
緋美子は気づいた。砂浜の上に背筋を伸ばしてきっちりと座っているのである。小さな砂粒が脚を汚すのも構わず、辺りを見回しながら正座しているのだった。
ひとつの松の枝に見つける。純白の衣が風にひらひら舞っているのを。
透けて光る布が虹色に煌めき、なんと美しいことか。
衣はまるで緋美子においでおいでと手招きしているようだ。
緋美子は立ち上がり松の木の根元まで行き、見上げた。その途端、強い風が吹き、衣は舞い上がり、真っ青な空に吸い込まれるように高く飛んでいく――。
(待って―――)
思わず、砂浜に踏み出して追いかけようとした時、母親の声がした。
「緋美子、お見舞いに来て下さったわよ。目が覚めている?」
数日前、緋美子と車で接触した若い紳士がやってきたのだった。
「申し訳ありません。この子、検査を受ける前後から意識を失くしたり戻ったりを繰り返してるんですの」
母親に背を支えられて起き上がると、視点が結ばれてきた。
先日、車で接触した青年だ。
「白滝龍太郎と申します」
青年は名乗った。
「白滝龍太郎さんというと、お能の有名な流派、神仙流の?」
バレエ団の本村美絵が驚いて聞き返した。緋美子は、この時、本村美絵も付き添っていることに気づいた。
「栗原緋美子さんが倒れられたとお聞きして……。私の起こした事故のせいなら、全面的にお詫び致します。何せ、パリに留学してプリマ・バレリーナになられたことは有名な方ですから、何事かあったら大変です」
「それは、もう一度こちらの病院の検査結果が出てからにいたしましょう」
母親が答える。
「緋美子さんのお身体も勿論のこと、バレエ団の損害もこちらで責任を持ちます」
白滝龍太郎は、顔色悪く眠る緋美子から目を離さずに見守るのだった。
結局、検査結果はどこといって異常が見つかったわけではない。ただ、緋美子の身体から気だるさは抜けないままだ。
「緋美子さん」
龍太郎が、母親に支えられてベッドの上に上半身起き上がった緋美子の顔を覗き込む。
「分かりますか、私のことを覚えていますか」
緋美子はうなずくでもなく否定するでもなく、師匠の名を呼んだ。
「本村先生」
「はい。ここにいるわよ。大丈夫?」
「私……お客様やバレエ団の皆さんに沢山のご迷惑をかけてしまって」
大粒の涙が、血色のよくない頬を伝った。
「私……決めました。本村バレエ団を辞めさせていただきます」
本村美絵と母親は飛び上がるほど驚いた。
どうにかふたりで緋美子をなだめて、辞めるというのを長期休業ということにさせたのだった。
第三章 同じ舞の手として
「緋美子さん、お大事にね」
「戻ってらっしゃらないとイヤよ」
「約束よ、緋美子先輩」
バレエ団の後輩たちが、プリマ・バレリーナである緋美子の休業を惜しむ。
中には競争の激しいバレエ界のこと、ライバルたちは内心、喜んでいたかもしれない。そんな中でも本村美絵は、いつも緋美子を見守ってくれた恩師である。
三歳の時から母親に送り迎えをされて通ったバレエ団の想い出が、緋美子の脳裏に鮮やかに蘇った。
自分から習いたいと言いながら、いざとなるとうまく踊れず最初は泣いてばかりいたこと。それでも持ち前の負けん気で続けてきた。発表会の度に母親に手作りの衣装を縫ってもらった。
ビーズやレースやリボンを縫い付けてくれる母親の縫う衣装は緋美子の自慢だった。
バレエ団を休んで自宅に籠もるようになった緋美子は、殆ど横になっていた。
白滝龍太郎は、毎日のように緋美子の元を訪れた。母親が彼の過失を責めても毎日訪れた。
「どなたのせいでこんなことになったとお思い?」
「お母さん、これは彼のせいじゃないわ」
龍太郎の方へ向き直り、
「白滝さん。本当にあなたのせいだとは思っていません。少々無理をしたようで、私の身体が悲鳴をあげたのです。ゆっくり養生します。ですからもう明日からお見えにならなくて大丈夫ですわ」
「緋美子さん、家の中で籠もっていちゃダメだ。勘を失わないように、お稽古場にだけでも行って見学することをお勧めするよ。同じ舞の手として」
緋美子はふと顔を上げた。
(同じ舞の手として……! そうだ、この人はお能の舞手なんだ)
「お言葉は有難いですけど、バレエのお稽古を見学するのは、辛いですわ」
「では、私のところへ気晴らしに来ませんか。異なる文化を見るのも面白いですよ」
龍太郎は意外なことを言い、にっこり笑った。
「ちょうど今、『羽衣』の練習をしていまして」
(羽衣!)
時々、意識を失う中で水平線に向かって松の枝から、虹色の透けた衣が飛んでいく情景が思い出された。
「『羽衣』という演目を?」
その時、緋美子の心は大きく動いた。『羽衣』という演目を見てみたいと思ったのだ。
第四章 能の宗家
車が正面玄関で止められた。
緋美子と母親は、大きな門がまえに圧倒され、奥に見える壮大な母屋に息を飲んだ。質実剛健な灰色の瓦屋根が広い。
「すごい威厳あるお屋敷……」
「さすが、お能の宗家ともなると違うわねえ」
母娘は肩を寄せ合って言葉を失った。
運転手に車を任せた龍太郎がふたりを案内しようとした。
「そんなに硬くならないで下さい。ただ古いだけの建物ですから」
その時、門の内側から三十年代半ばの和装の女性が現れて、三人の前に立った。梅紫の着物が品がよく、とても似合う。
「若様、お帰りなさいませ。緋美子様のことは心得ましたが、もうおひと方はどちらさまでございましょう?」
「こちらは緋美子さんの母上だよ」
「ま、お母様?」
西山と呼ばれた女史は、赤ぶちメガネの奥から冷たい視線を繰り出した。
「緋美子さんと一緒にここにしばらく滞在していただくのだ」
「まあ、先ほどのご連絡だと、緋美子様おひとりが滞在だったはずですが」
「あちらの家を出る時に急に決まったんだよ。体調の十分でない娘を他家に預けるのは心配だということで、急遽、お母様にもついて来ていただくことになったんだ」
「まああ、急なこと。万全の体制で緋美子様をお迎えしようと準備しましたのに、信用していただけないばかりか、お仕度が倍に増えてしまうなんて! ……婆や! 婆や! 寝室をもうひとつ用意して!」
両手をパンパンと叩きながら婆やを呼ぶ。そして、言い忘れていたと大げさに、
「神仙流本家の執事を務めております西山と申します。お部屋を案内させていただきますので、こちらへ」
くるりと背を向けると部屋へ案内した。
緋美子は母親の肩を借りながら、西山の後を進んでいった。
翌日、能の舞台に西山に案内されると、格式ばった建築に緋美子母娘は、またもや息を飲んだ。
屋根と廊下と階が着いた、白洲に囲まれた本舞台。木目のそろった光り輝く床。樹の匂い。鏡板という背後に描かれた立派な松の枝。荘厳としか言いようがない。
舞台の袖の壁に一枚のポスターを発見する。それは、大きく『羽衣』と書かれた公演のポスターだ。シテ(主役)の天女が牡丹の花を着けた冠で大きく艶やかに写っている。
数人のお弟子さんが立ち働いていた。浴衣姿の龍太郎がふたりを迎えた。皆が和装の中、自分たちだけがカジュアルな洋装なので、ふたりは内心うろたえた。
「よく眠れましたか」
「はい。最近は私、松原の夢を見るのです。この『羽衣』の舞台のような」
「ほう? それは偶然ですね」
お稽古場では、お弟子さんたちのお稽古に龍太郎がひとりずつ手をとって指導している。
「父の家元がただ今、留守にしております。もうじき帰宅すると思いますが、緋美子さん方のことは連絡してありますのでご心配なく。温厚な父ですから」
緋美子はとりあえず、本舞台の脇に座ることにした。そろりそろりと、母親と身体を支えあいながら板張りの床を進んだ。中心に立ってみる。なんという静謐な世界だろう。十数メートル四方の床なのに、果てしなく広く感じる。まるで俗世と別世界だ。バレエの舞台とはまた異なる――。
「では、お稽古の邪魔にならないよう、端に座らせていただきます」
見学者が座布団を敷くわけにはいかない。しかし、身体全体が重だるい状態では正座でいるのは無理かと思われた。
「椅子のようにかけてくれていいからね」
龍太郎が耳打ちに来たが、背筋を伸ばして足の上に体重をかけたとたん、だるさが消えて身体が安定した。正座によって軸が出来たというべきか。
今の緋美子からは、家で寝込んでいた面影はない。能の稽古場の空気が元気にしているのかもしれない。
母親の方が音を上げた。
「緋美子、大丈夫? 私はもう駄目だわ。足が痺れちゃって」
「大丈夫よ。家のベッドでだらだら寝ていた時の方が気分が良くなかったわ。体幹がしっかりしている感じ」
龍太郎が様子を見に来る。
「緋美子さんは、さすがに正座が上手にできていますね。でも、今日は冷えますから、また明日に」
「そのうち、ここで『羽衣』のお稽古風景を見せて下さいね」
「お約束でしたね」
緋美子に頷いた。
第五章 月白
部屋に帰った緋美子は持参していたパソコンを開いた。「能の羽衣」について調べる。
「緋美子、もう休んだら? 今日はお稽古場に座っていて疲れたでしょう」
「大丈夫よ。すぐに寝るから」
今夜中に調べたかった。今まで縁のなかった「能の羽衣」について。バレリーナの勘が何かを告げていた。
『羽衣を漁師が持ち帰った話は世界中に存在していること、その化身は天女だけでなく、白鳥や魚にも姿を変えるということ』
その記述を見つけて、バレエの「白鳥の湖」を思い出し、想いを馳せるのだった。初めて身近に触れる「能」と長年打ち込んできたバレエとの接点を見出せそうな気がした。
翌日、執事の西山女史が、朝食の後、緋美子と母親に知らせに来た。
「家元様が昨夜遅く、お戻りになられました。おふた方にお目にかかりたいとのことですが」
緋美子と母親は、緊張で言葉がうまく出なくなった。
「どうしよう、能の家元とお会いするなんて初めてだわ」
「お母さんだってそうよ。あなた、なんだって家元の息子さんの車に跳ねられたりするのよ」
「そんなこと言ったって……」
母娘で言い合ってるうちに西山がコホンと咳をした。
「お召し物は普段着で結構ですから早くなさって下さい、龍太郎様も、ご一緒にお座敷でお待ちでございます」
母娘は、よけい顔色を変えて西山の案内する長い縁側を歩いて奥座敷に辿り着いた。ふたりには若葉色の庭の景色も見えていなかった。
「お連れいたしました」
西山が障子の外側に正座して静かに開ける所作を、緋美子は見つめていて心から美しいと思った。裾に手を当て膝を折って座り、少し腰を浮かせて障子に手をかけるさま――。
(これこそ正座の神髄だわ)
初めて西山女史を尊敬した。
「おお、これはこれは」
広い床の間を背に座る家元と龍太郎はにこやかに迎えた。
ふたりは西山の後ろで十分頭を下げてから座敷ににじり入った。
家元は、神仙流六十三代目の白滝永龍である。さすがに能の家元だけあって、恰幅よく穏やかな表情の初老の紳士だ。桑茶色の和装姿、白髪まじりの整った髪、緋美子母娘はすっかり見とれてしまった。
隣に座る龍太郎も、父親と面差しが似ていて品の良さは血筋からくるものらしい。
「この度は息子がお宅のお嬢様にとんでもないことをしでかしまして、なんとお詫びを申し上げてよろしいやら」
「いえ、娘の怪我は大したことはございません。こちらの方こそお留守中に滞在させていただき失礼しております」
母親がカチコチになって挨拶した。家元が緋美子に向き直った。
「初めまして。マドモアゼル・緋美子。欧州で磨かれた所作と姿勢は、さすがですな」
「お父さん、初対面のお嬢さんに失礼ですよ」
「これは失礼申し上げました。とんだご縁から始まりましたが、この品はお近づきの印に……」
家元の合図に、西山が持ってきた品は、月白という白の種類の反物だった。
「是非、お仕立てしていただきたい。先にお写真を拝見して、失礼ながら見繕ってみました」
「まあ、月光が輝くような白い生地」
緋美子は思わず手に取った。流れ落ちる絹の感触が、あまりにもすべすべでうっとりしてしまう。
夢の中で松に引っかかっていた衣を思い出した。光沢が布からこぼれ落ちるような虹色だ。
第六章 羽衣の舞
緋美子の母親はひと足早く自宅へ戻ることになった。
「本当に大丈夫なの、身体の具合は?」
「大丈夫。私もそろそろ失礼しなきゃならないけど、もう少しお能のことを勉強したいの」
「分かったわ。では、家元様と若様に宜しくね。この月白の反物は預かっておきます」
「ありがとう、お母さん。じきに戻るから心配しないでね」
緋美子は母親の乗る車に歩みより、
「その月白なんだけど……」
何やら母親に耳打ちした。すると、母親は驚いて叫ぼうとしたが、娘は素早く母親の唇に人差し指をあてた。
「この子ったら何を考えているの。母さんはもう知りませんよ。身体だけは気をつけて、じゃあね」
母親は、ちょっぴり心配そうに車の窓から手を振りながら、車で遠ざかっていった。
ある日、龍太郎が「正座についての本」を持参した。
「ここを読んでくれたまえ。『正座の何よりの長所は、体幹を鍛えられることだ。能の第一歩は体幹を鍛えることから始まる』とある」
緋美子の顔が輝いた。
「バレエの基本と同じですわ」
「なるほど、能も舞の時に足元が寸分違ってもいけない。そのためには体幹が一番大切。バレエもそうだね」
「はい」
「今度、あなたのレッスン場へ見学に行ってみたいのだが」
緋美子は慌てた。
「それはもっと先にして下さい。長期休業を宣言してしまい、まだまだ踊れる自信がないのですもの」
「ははは、分かっているよ。だから、今日からお稽古場に能楽囃子の奏者も呼んで正座の練習をしてもらおうと思ってね」
「能楽囃子ですか?」
「ああ、皆、ベテラン揃いだが、先日から見えているお若いお嬢さんは? と、かまびすしくてねえ」
稽古場には、笛と小鼓、大鼓の奏者の男性たちが待ち受けていた。
「私どもも、楽器を習う基本にまず正座を練習しました」
初老の奏者たちが、緋美子に丁寧に接する。龍太郎が、
「きっと、三人のベテランに習えば正座も上手になり、身体の不調も良くなるよ」
「はい、お気遣いありがとうございます」
緋美子は三人の奏者に改めて「正座」を教わった。
そして、着衣稽古の日が来た。
笛、小鼓、大鼓。太鼓。ゆるりと奏でられる中、頭上の金の冠に牡丹の大輪を着け、白鶴の翼の描かれた衣装を纏ったシテ(主役)が床に進み出る。
シテ(主役)は『羽衣』の天女。今日の着衣稽古は、龍太郎がシテだ。なんとゆるりとした所作だろう。一旦、時間が止まってしまったかと思われるような舞の進行具合だ。天女は天から浜に舞い降りて、あまりに美しい景色に魅せられて海辺で羽衣を脱ぎ、水浴びを始める。
ツレ(脇役)の漁師が松の枝に引っかかっている羽衣を見つけて、美しさに目がくらみ、持ち帰ろうとする。
天女は慌てて、
「その羽衣が無ければ、わらわは天に帰れませぬ。どうぞお返しください。その代わりに舞をお見せしましょう」
「そのようなことを申して舞を舞っている間に天に帰ってしまうのであろう」
「いいえ、わらわは偽りは申しませぬ」
漁師は舞を見ることにする。天女の運命を決める舞だ。
真剣に龍太郎が天女の気持ちになって舞う姿が、緋美子の心に深く沁みてきた。
ゆるく奏でられていた笛や小鼓、大鼓、太鼓が激しくなる。
正座して見学していた緋美子も、すっかり世界に入ってしまい、純白に鶴の描かれた能衣装の天女の振る袖に目が釘付けになっていた。
龍太郎が舞い終えた時、緋美子の心にかかっていた黒い靄は、すっかり晴れていた。
第七章 創作に燃え
二か月後、本村バレエ団の稽古場で、熱心に踊る緋美子の姿があった。
稽古場に貼り巡らされた鏡に、緋美子の肢体と相手役の男性が伸びやかに映っている。クライマックスの部分だ。
「ハイッ、休憩」
手拍子で声かけしていた本村美絵は、緋美子が躍っていることが嬉しくてならない様子だ。彼女と相手役の男性、丹羽透にタオルを渡した。
「いい調子ね。先日まで家で籠もっていたなんて信じられない」
「神仙流におじゃましていた成果です」
「僕もびっくりしましたよ。青白い顔をしていた緋美子ちゃんが、こんなに元気になって、完璧な踊りを見せてくれて」
相手役の丹羽透もやる気十分だ。緋美子も満面の笑みで汗を拭いた。本村美絵が微笑んで、
「最初は驚いたわ。能からヒントを得て創作バレエを創るだなんて。前よりもきれいな体幹ができている」
「美しい正座を教えていただいたおかげです」
「それで、うちの生徒にも稽古前に正座を取り入れたのね」
「はい。正座もバレエもお能も、体幹が基本ですよ!」
今では緋美子の薦めで、若い弟子たちもバレエのお稽古場でしばらく正座をしてからバレエのお稽古に入る。
「しゃんと正座をしてから稽古に入ると、何か座禅に似た感じを得て、プレッシャーや競争心、怯えなどが消えて、すっきりした気分になるんです」
緋美子が以前、悪夢を見てステージで倒れた時には、そういう黒い感情に支配されていたのだ。
「身体の重い感じは無くなり、痛みも感じませんわ」
「よほどプレッシャーに苦しんでいたのね。雨降って地、固まるってことかしらね」
「その言葉は、発表会が無事に終わるまで取っておきましょう、先生」
「そうね」
その時、入り口から緋美子の母親が大きな箱を持ってレッスン場へ走りこんできた。
「どうしたの、お母さん、そんなに慌てて」
「だって、あなたに一秒でも早くこれを見せたかったんですもの」
箱を開けた。中には、月白の反物と緋色のオーガンジーで作られた衣装が入っていた。
「さあ、仕立て上がりのほやほやよ。着て見せてちょうだい。ここ一か月、デザインを考えて縫い上げるのにかかりきりだったのよ」
緋美子は震える手で、箱から白い布と緋色の布で縫い合わせられた長い裾の衣装を取り出した。
「これは、お母さん!」
「どう? あなたのイメージ通りに出来上がってる?」
月白を肩にあててみた。丈に添って長さをまちまちに、斬新なカットで縫い合わせられた緋色のオーガンジーが、何倍もの長さで床に垂れている。
「これを着て舞ったら、緋色と白の鳥が乱舞しているようだわ、きっと」
本村美絵も眼を輝かせた。
「映えることでしょう。群舞の子たちにも、月白と似たような色で純白と緋色のオーガンジ―で衣装を作りましょうね」
「ありがとうございます。先生」
「さあ、相手役の丹羽くんには、何色を着てもらうの」
「透き通るような水色の衣装を。青空と浜の水平線をイメージしたものを」
「お母様、宜しくお願いしますよ」
本村美絵の言葉に、母親は慌てた。
「え、相手役の方の衣装まで私が?」
「そりゃあ、そうですよ。緋美子さんの復帰の大切な公演ですから。振付は私にお任せ下さい」
「緋美子さん復活のお相手は、僕にお任せ下さい」
丹羽も、ややおどけて言った。
「そうですね。こうなったら頑張るしかないですわね」
四人の笑いあう声がレッスン場に響いた。
第八章 白い月と緋色と蒼穹と
その日の本村バレエ団の公演は会場のお客があふれんばかりだった。
観客が話題を集めていたのは、今度の舞台「白い月と緋色と蒼穹と」というタイトルで、能の「羽衣」をバレエの演目にしたという事だ。
『有名な能の「羽衣」を、どうやってバレエにアレンジさせるのだろう?』というところに注目が集まっていた。
第一幕で、天女役の主役、緋美子が月白と緋色のオーガンジーの衣装で踊り出てきた時は、客席からため息が湧いた。
真っ白なトウ・シューズで輪を描くようにステージを回り踊ると、彼方の水面を見つめ、衣装を縫いで樹の枝にかける。
踊りから布を手に持つ所作までなんと身体の線の美しいことか。
よほど体幹が出来上がっていなければ見られない姿勢である。
客席で、神仙流の家元と龍太郎父子も、はっきりそれを見てとり、頷きあった。
「緋美子さんの踊りは、まるで水鳥のようじゃないか」
「はい。お父さんの見立てられた、月白の反物がバレエの衣装として見られるとは思っていませんでしたよ。衣装が彼女を引き立てているせいもありますよ」
「お前が能舞台の上で正座をお教えした功績も大きいと思うがな」
天女が水に入り水浴びをしているところへ、爽やかな青の衣装をまとった男性の踊り手が登場して彼女に見惚れる。ふと見上げると、まばゆい純白の布が虹色に映えて、樹の枝にかかっているのを見つける。
民間伝承の「羽衣」では、羽衣を見つけた漁師が、天女に「嫁にならなければ、羽衣は返してやらない」と言い張り、天女は仕方なく漁師の妻になる話だが、能では「羽衣を返す代わりに舞いを見せろ」と言い、天女が渋々舞うのである。
このバレエでは能の通りにした。
漁師役の丹羽透が「羽衣を身につけ、舞いを見せろ」と言い、天女役の緋美子は羽衣をまとい、泣きながら踊りを見せる。天上の国が恋しい、帰りたい。思いが伝わってくる切ない踊りだ。
「いいわ、その調子よ、緋美子ちゃん……素晴らしいわ、天女の心情がよく出ている……」
本村美絵が舞台の袖で涙を浮かべた。
「あなたは、あなたの天上、今、立っている場所に帰りたかったのよね」
しかし、未練がある漁師は、踊る天女の腰にまとわりついたりして妨害しようとする。
天女と、漁師役の丹羽のこの辺りの絡みも見応えがある。丹羽が緋美子の腰を背が折れるほどに抱きしめ、緋美子は背をのけぞらせて苦悩を表現する。十分、観客の眼を惹きつけた。
しかし―――、やがて、漁師は天女の熱い思いに屈して、砂浜に崩れ落ち「天に帰ってよい」と告げる。
遂にクライマックスだ。
夕焼雲と共に、緋色と純白の衣装を着けた群舞の女の子たちが出てきて夕空を演出する。
いっそうの迫力で天女の緋美子が舞う。
恋しい天の国へ帰れる―――。喜悦の舞いだ。
くるくる回転する天女に美しい衣装が共に舞い、同時に夕焼雲役の群舞が舞い、壮大な空が表現される。緋美子のワンステップワンステップと、指先まで力と心を込めた踊りが観客を魅了した。
会場をわれんばかりの拍手が渦巻き、水鳥が羽根をたたむようにお辞儀をする緋美子の顔は感激の涙で泣きぬれている。
数か月前に転倒した悔しい思いから、やっと解き放たれたのだ。
「お母さん、先生、ありがとう!」
舞台を降りるや母親と本村美絵が涙で迎え、背後から神仙流父子が大きな花束を持って現れた。
「復帰、おめでとう」
龍太郎は花束ごと、天女の衣装を着けたままの緋美子を抱きしめた。
数日後、輝くように磨きこまれた能の舞台―――。
中央にバレエの衣装を着けた緋美子がトウ・シューズですっくと立った。
背後で正座して見守っている龍太郎の元へピルエット(回転)しながら彼の周りを一周してから、背中をぴったり合わせて緋美子も正座した。
「ありがとう。一度、能楽堂で踊ってみたかったの」
「君は、我が家にやってきた天女なのかもしれないね」
「帰りませんよ、私は。龍太郎さんが帰れったって」
緋美子はにっこり笑った。
「ほら、背中同士で正座すると、あなたの胸のドキドキが聞こえるわ」
「君の胸のもね」
ふたりは背中でお互いの命の脈動を感じ続けていた。