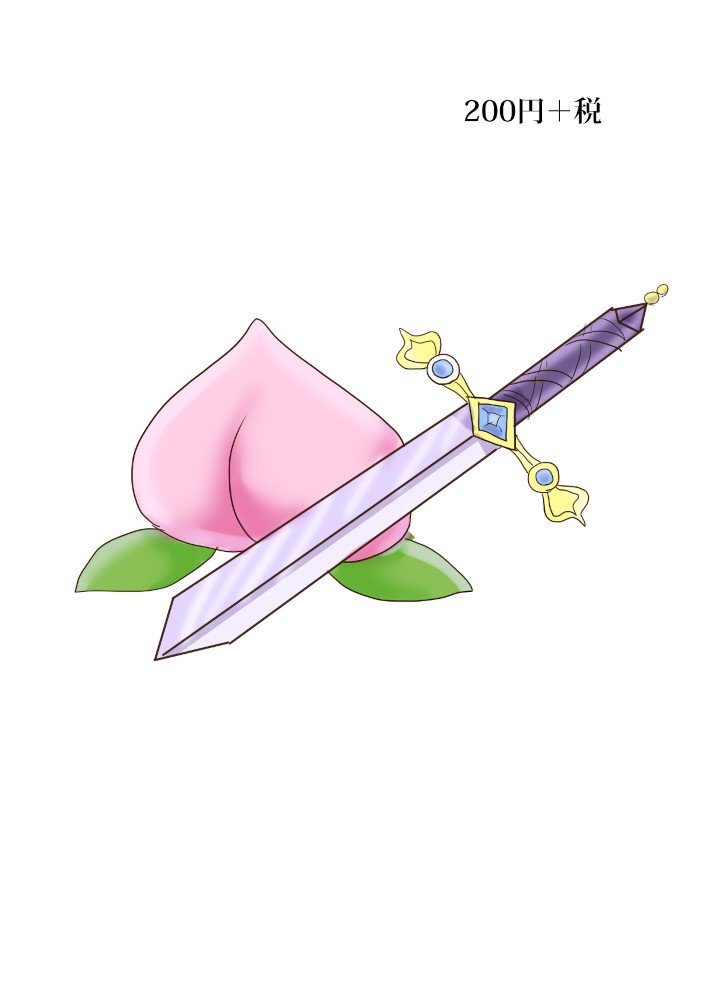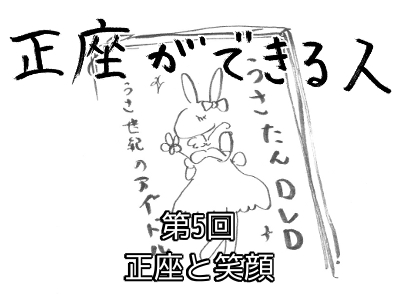[79]桃太郎・天下無敵の正座
 タイトル:桃太郎・天下無敵の正座
タイトル:桃太郎・天下無敵の正座
分類:電子書籍
発売日:2020/01/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
陰気な大学院民俗学の研究を何年も続けている、桃源 郷(もももと さとし)は、桃太郎は桃の中で正座していた説を、学会で発表。
輝夜(かぐや)女史が反論する。郷は証明するため、桃の産地へふたりで出かけ、村の長老から山奥の洞穴から西王母の君臨する桃源郷へ行けることを聞き出す。
三人は洞穴の奥へ。そこは思い描いた桃源郷とは程遠い、焼け野原になっていた。鬼どもと桃源郷の女神たちとの戦いに巻き込まれた郷と輝夜は、無事に人間界に戻れるのだろうか。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1757054

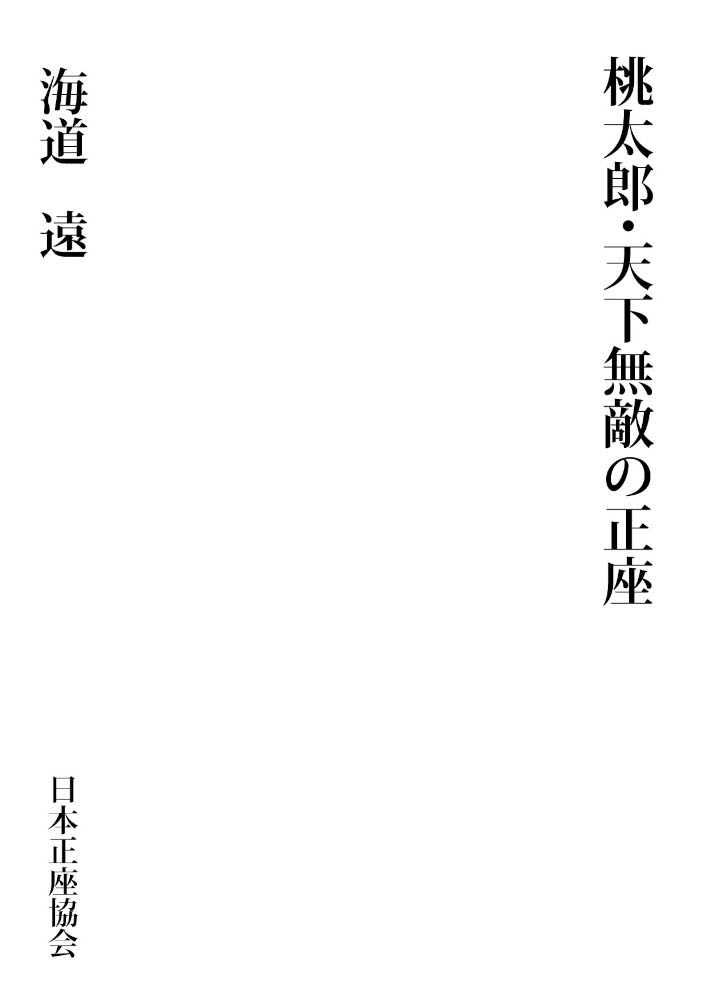
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 桃源郷
昔からの人々の怨念でも漂っているのではないか、というような沈殿した空気がそこにはある。べっこう色の廊下、かび臭い。
民俗学部、大学院研究室。看板も焦げ茶色に変色している。
「ここ、うす気味悪いな」
「まるで開かずの間だ」
「何年も前から、何かの研究を続けている院生が使っているんだとか」
新しい院生が、話しながら足早に通り過ぎる。
院生たちからは、とっくに見放され教授も無視状態だ。
というのも、男があまりにも研究に没頭しすぎて、まだ三十歳前だというのに年齢不明のような風体で浮世離れしているからだ。
彼が日常、豪語して研究を続けているのは、民話の桃太郎について。
「桃太郎は桃の中で正座していた」というもの。
しかも、彼自身、正座の達人で研究室では畳の上で二十四時間過ごす。もはや痺れることもない。精神統一だ。
そして「桃太郎は、人間の胎児と比較して逆さにならず正座していた」と信じている。人間の子は子宮の中で逆さに丸まっているが、桃太郎は包丁で割られた時にバンザイ! して生まれてくるので、待機中は正座していたというのだ。正座の効力で幼い時から頭脳明晰で鬼を退治に行くと言い出すほど勇ましいのだと、学会で発表した。
それを知って乗り込んできた女子がいる。
同じ民俗学専攻の三年生、満月同好会の輝夜だ。
「こちら、桃源さんの研究室でしょうか?」
かびた畳の上にずかずかと土足で上がるなり、声をかけた。
郷は、白衣で机に向かって文献を開いていた。
「なんだね、君は。畳の上に土足で」
「満月部同好会の竹中輝夜と申します。桃源郷さんですね」
「そうですが」
今時、牛乳瓶の底のような分厚いメガネをかけ、口の周りには無精ひげ。いつ髪の毛にくしを入れたか分からないような乱れた爆発アタマをしている。離れていても汗臭い薄汚れた白衣。
輝夜は鼻をつまんだ。
(想像した通りの、研究室妖怪だわ)
「今回、学会で発表なさった『桃太郎正座説』に、ひと言あってまいりました。貴論では、正座していた方が桃から生まれたとたんに、勇ましく動き回れるとのことですが、私はそうは思いません」
「はあ?」
(何、ほざいてるんだ、この女)
内心つぶやいて、郷はおもむろに振り返る。
「桃の中では、羊水の中に浮かぶように、彼も桃の果汁の中で種を抱っこして浮かんでいたのです。その方が、知能アップ、キジと猿と犬を従えて計画的に鬼退治ができます」
輝夜は、腰まである一本の三つ編みの黒髪を、背中へポンと投げて鼻息荒く言った。
「つまり僕の発表した説と正反対ですね」
郷の分厚いメガネがギラリと光った。
「そういうことです」
「では、どちらが正しいか勝負しましょう」
ふたりは顔を突き合わせてから、ふん! とそっぽ向き、お互い嫌な第一印象を再確認した。
「なんだ、この妖怪黒髪の毛女。ぎゃふんと言わせてやるぞ」
かくして「桃太郎が正座していたか否か」勝負は火ぶたを切って落とされた。
第 二 章 桃の村の訪問者ふたり
桃の実がたわわになる初夏――。
桃の名産地のある村。村人が、見慣れないふたり連れに注目した。ひとりは女と分かる。長い黒髪を一本の三つ編みにして、大きなリュックをしょっている。化粧っけ、まるでナシ。Tシャツとジーンズ姿だ。
もうひとりはインスタントラーメンみたいな縮れ髪の薄汚れた男。中年だか若いのか分からない。年季の入ったジーンズを穿いて、女の三倍くらいの大きさのリュックをしょっている。
実はこの村、昔から中国の伝説とつながりが深いという噂だ。ふたりは、これっぽっちも同士感などないが、桃と中国の伝説に繋がりが深い村ということで、黙々と下を向いて歩きながらも何が聞き出せるか、ワクワクしていた。
桃といえば、「桃源郷」。桃源郷の名前の元になった理想郷の名前だ。
桃の理想郷の女主は、西王母という絶世の美女。中国特有の道教(老子を神とした土俗的な宗教)から発生した最高位の女神。他の仙女すべてを支配し、西の聖地崑崙山を統治し、不老不死の桃園を管理する絶世の美女として篤い信仰を集める。
西王母といえば蟠桃会だが、西王母の生誕祭で、陰暦三月三日に西王母自身の主催で行われ、位の高い仙人や神を天の瑤池に招き、九千年に一度実をつけるという蟠桃をふるまう。蟠桃の中で三千年に一度の桃を食べると仙人になることができ、六千年に一度実をつける桃は長生きができて年をとらず。九千年に一度実をつける桃は天地と同じ寿命を得られる。七夕物語にも西王母は登場。織姫と彦星は許しを得ずに結婚し、西王母の逆鱗に触れて天の川の両岸に別れ別れにされてしまう。という言い伝えだ。
ふたりは村の長老に会いに行った。長老は赤銅色に日焼けして白いヒゲを生やした好々爺でニコニコして桃畑の中にいた。大きくなった桃の実がぶら下がり、それは美しい風景である。
「はあ? 桃太郎のことを聞きにきたじゃと?」
「なんでもいいです。桃と、桃太郎のことに関することなら」
長老は岩に腰かけ、腰のポケットから煙管を取り出し、煙を吐いた。
「この村の奥の岸壁に洞穴がある。そこを通り抜けていくと西王母の住まう桃源郷があるという言い伝えが、祖父さんのひい祖父さんの、ひいひい祖父さんくらいの代から伝わっておるが、誰も行き着いた者がおらぬ。帰ってきた者もおらぬ」
「理想郷に通じる洞穴が!」
郷と輝夜は、そろって叫んだ。
「案内してくれ、長老。そこに行けば桃太郎について何か判るかもしれん」
「日本にあるわけないと思うけど」
輝夜がぼそりと言った。長老は首をかしげ、
「洞穴は不思議な時空とつながってるから、行き着けるぞよ」
第 三 章 闖入した織姫
桃畑にひらひらした女が走りこんできた。村娘に見えない。
「どうなすった」
長老が声をかけると、娘は、
「お願いでございますっ。助けて下さいましっ」
輝夜は、腰につけていた水筒の蓋を開け、娘に与えた。ようやく生き返ったようだ。
「あんたは誰、落ち着いて」
「私は織姫と申します。機を織れと言われ、ずっと励んできましたが、見張りの眼をごまかし逃げてきました」
「どこから」
「桃源郷からです」
「ええっ」
「ほら、やっぱり桃源郷が洞穴の奥にあるんだよ」
「桃源郷の西王母様の捕らわれの身になっていました。彦星様との婚姻の許しを得なかったことが逆鱗にふれたのです」
「彦星?」
「牛飼いの夫でございます」
郷は、踵を返すと長老の家に上がり込んで、正座を始めた。
輝夜が、
「足腰痛くて休憩してるんでしょ」
「これが休憩に見えるのか? 背筋をピンとして膝と垂直に座る。これが正座だよ。精神共に鍛えられる。お転婆なあんたには無理だろうがな」
「だ、誰がお転婆なのよ。この器量だから、求婚者が両手の指に余るほどよ。生まれる前から竹の中に座ってたんだから正座くらいできるわよ!」
「ん? じゃあ、あんたがかぐや姫なのか」
「知ってんの? 桃太郎以外の話」
織姫という娘が、ふたりのおしゃべりに痺れを切らしたて叫ぶ。
「西王母から、彦星様を助け出してくださいっ」
「これこれ、西王母様から助け出すとは、バチが当たるぞ、おなご」
長老の言葉に、織姫は、
「しかし、あの方はあまりにひどい仕打ちを私どもに」
織姫は両手で口をふさぎ、真っ青になった。
「今、申したことは忘れて下さいませ」
もう何も言わない。
「こうなったら、洞穴の向こうへ行くしかないな」
正座からリュックを背負って立ちあがり、輝夜も続いた。
「西王母に会いましょう。桃太郎のことも全てご存知よ」
長老も旅支度を始めた。
「ワシも。西王母様から蟠桃をいただき、不老不死になるのじゃ」
輝夜も、
「そんな桃ならカタチも色も美しい桃なんでしょうね。満月のように」
「おや、あんたも不老不死になりたいのか? その顔のまんまで? きっと後悔するぜ」
「なんですってえ!」
郷がからかうとムキになる輝夜。そして長老。三人は夜明けに洞穴向けて出立した。織姫は合掌して三人を見送った。
第 四 章 桃源郷への洞穴
三人は洞穴の入り口にたどり着いた。
まるで悪魔の口腔のように、人がふたりほど通れる広さの穴が空いている。真っ暗で生ぬるい風が顔面に吹き付けてくる。
「行こう」
三人は歩き始めた。
「じ……実はのう」
長老がピンクの頬をさらに赤らめて、もぞもぞと口を開いた。
「半世紀以上前になるかのう、この穴を通って桃源郷へ行ったことがあるのじゃ」
「えっ!」
(もったいぶって、知らん顔してたんだな、爺)
郷は舌打ちして長老を睨んだ。
「どんな感じ? 桃源郷って」
輝夜が長老に食いつくように尋ねた。
「そりゃ~、この世の天国じゃよ。広い窪地になっておってのう、山に囲まれて美しい緑が溢れ、桃の実が実り、桃の香りの小川が流れ、美しい仙女たちが歌いながら酒を汲み交わしたり舞を舞ったり。朱塗りの橋を渡ると、西王母様の壮麗な御殿がそびえて」
「爺さん、夢、見てたんじゃないだろうな」
「当たり前じゃよ。そして――わしは西王母様と、むふ、むふ、むふふ……」
「なによ、いやらしい笑い方」
「西王母様の輝くような白い桃そのものの胸、膝……柔かったぞえ」
「ま――! 長老ったら」
輝夜の軽蔑しきった声が穴の中で反響した。
「彼女の膝で桃酒に酔って寝てしまい……目が覚めると洞穴の入り口に戻っておったのじゃが……」
「それじゃ、不老不死になれると蟠桃は、食べなかったの?」
「その前に酔って寝てしもうたからのう。しかし、西王母様は不老不死。今でもさぞ美しくてお若いことじゃろうの。ひっひっひ」
「長老ったら」
「ほっとけ、そのうちニヤニヤ笑いも止まるだろう」
郷はリュックを背負いなおした。
洞穴の彼方に小さな出口の光が見えてきた。
「お、出口だ」
郷が走り出した。そして出口のところで仁王立ちになったまま、動けない。
「こ、これが桃源郷なのか……」
ふたりも後からやってきて、目の前に広がる景色に呆然となった。
緑の「み」の字もない。赤茶けた地面と焼け野原になった悲惨な桃畑が続いている。小川の跡も無残に干上がっている。
「どうしたんじゃ、これが桃源郷? わしが西王母様といちゃいちゃした緑したたる森と大地と桃がいっぱいぶら下がっていた天国なのか?」
長老も顔色を失くして呻く。
「長老、本当に間違いなかったの、この洞穴で」
輝夜が長老の肩を揺さぶった。
いきなり郷の足元に太い矢が風を切って飛んできて、地面に突き刺さった。
「わ、なんだ、これ」
他のふたりも追いついた時、
「何者じゃ! 一歩も動くでない」
赤茶色に焼けただれた窪地の周りの岸壁に鎧兜に身をつけた女どもが立って弓矢を構えている。
兜の羽根飾りがひときわ大きい女人が叫んだ。
「何者だ、名を名乗れ」
「わ、わしは、麓の大桃村の長老、緑原権助じゃ」
「俺は学生の桃源郷」
「あたいは竹中輝夜」
「何用じゃ!」
郷が大きな声で張り合った。
「西王母に逢わせてほしい」
「西王母様を、呼び捨てとは何事であるか」
「そんなに偉いのかよ、西王母ってのは」
周りの弓の先が、サッと郷に向けられた。
「西王母様に聞きたいことがあるんだよ」
「言ってみろ」
「桃太郎は生まれる前に、桃の中でどんな格好をしていたのか、聞きたい」
「桃太郎じゃと」
大きな羽根飾りのついた女戦士の背後から、きらびやかな黄金の鎧をまとい、薄桃色の肩布を足元まで垂らした女が、ずいと現れた。周りの女戦士どもが、場所を空けてかしづく。
「桃太郎……、あの大たわけめが! わらわが人の世に生まれさせてやったというのに勝手なことを。おかげで桃源郷はこの有様じゃ」
「あの……何のことで?」
「学生とか申したな、男。わらわの前でもう一度、『桃太郎』という名を口にしてみい。命は無いぞ」
面の中の眼がぎらついて郷たちを睨みつけた。
「桃太郎がどうかしましたか?」
「まだ分からぬかっ」
女戦士の声は、獰猛だ。
「わ、分かりましたよ、もう言いません。で、もうひとつ聞きたいことが。織姫の夫の彦星とやらをご存知ないかと」
女戦士どもが、またざわついた。
「織姫が、そっちの国へ逃げ込んだらしいな。彦星は、わらわの大切な任務を果たさねばならぬ身ゆえ、織姫の元へは行けぬ。そう伝えよ」
「ええ? 任務ですか。いつまで?」
今度は輝夜が尋ねた。
「分からぬ。今は、戦のさなかじゃ。いつ襲撃されるか分からぬ。彦星は牛で戦隊を作り、持ち場を離れるわけにはゆかぬ」
「あのう、あなたはもしかして」
輝夜がおそるおそる尋ねる。
「おう、我こそは西王母。天界にある瑤池(崑崙山中にある池)と蟠桃園の女主人で、すべての仙女を支配する女神。東王父に対応する神だ」
第 五 章 西王母
三人は呆然と岸壁の上の西王母を見上げた。面頬が邪魔をして素顔を見えないが、威厳と堂々とした態度は、仙女の最高位の女神と納得できる姿だ。
「あのう」
郷が、ごくんとツバを飲み込んで言った。
「私は『桃太郎』について学問をしてきた者です。先ほど怒っておられたようですが、いったいどうして?」
「まだ桃太郎の名を口にするか」
女戦士が一喝したが、西王母は手を出して引き留めた。
「桃太郎についての学問とな?」
「は、はい。桃太郎が桃の中から生まれるまで、正座していたかどうかをずっと研究して」
「物好きな者よのう。あの太郎は、桃源郷の桃から生まれるはずじゃったが、わらわが川に流したのじゃ。人間界で修行させるつもりで」
「桃の中で、どんな風に」
「大きくなるにつれ膝を折って品よく座っていたはずじゃ。わらわがそう教えたからの。お行儀よく、いざという時に十分戦える体制になるための正座をして」
「えええ~~」
輝夜がこの世の終わりのような声で叫んだ。
「丸まっていたんじゃないの!」
「桃源郷の者じゃからの。人間界では赤ん坊は生まれる前に丸まっているのか?」
逆に西王母から聞かれて、輝夜は答える元気もなかった。自分の考えが間違っていたと判明したのだ。
「ほら見ろ。輝夜女史。俺の発表が正しかっただろう」
輝夜はその場にくずおれた。
「西王母様。さっき、桃太郎のことをお怒りじゃなかったですか?」
西王母の兜の中の顔が、ハッとしたようになり、
「あの愚か者が! お爺とお婆に過保護に育てられたゆえ、いい気になり、鬼退治なんぞを!」
「え、それって、村人が喜んだことでは……」
「村人は喜んだであろう。しかし鬼どもの怨みを買って桃太郎の生まれ故郷の桃源郷に総攻撃をかけたから、このざまじゃ」
緑あふれるはずの桃源郷が、見るも無残な焼け跡になっている理由がやっと判った。
「鬼が島の鬼が、復讐のため桃太郎の故郷、桃源郷を荒らしにやってきたのでしたか」
「わらわの城が灰塵に帰してしもうた。そして戦はまだ続いているのじゃ」
西王母の拳が握りしめられ、黄金の面頬から涙が流れた。
「これはこれはおいたわしい」
長老も共に涙を流した。
「無理やり剣や弓矢を取って戦わねばならんとはのう」
「いつ、また鬼どもが襲撃してくるか分からぬ。そこで防御に牛を操れる彦星の牛の大群を伏せてある。彦星は戦に参戦中じゃ。織姫には気の毒じゃが、今は桃源郷存亡の危機なのじゃ」
陽が傾きかけ、篝火が焚かれた。
女神たちの悲鳴が上がった。
「西王母様、鬼どもが東から崖を越えてやってまいります!」
「なに!」
西王母は勇ましく首を東に向けるや、急いで洞穴まで降りてきた。
長老はじめ、郷も驚いた。西王母の黄金の鎧の眩しいこと。戦の格好をしていてさえ甘やかな香りに酔いそうだ。
西王母は足元にうずくまっていた輝夜の腕をつかんで引きずり上げた。輝夜は間近から顔を見られて、寸分も動くことができない。
「そなた、来てもらおう」
そのまま、輝夜の腕を引っ張って、崖の上の砦まで登っていく。
「あ、その子をどこへ」
「ちと、借りる。そなたらは安全なところへ隠れていやれ」
郷と長老は、西王母と輝夜の後ろ姿を呆然と見送った。
紫の空に篝火の火の粉が舞う。
第 六 章 鬼どもの来襲
崖の向こうから、恐ろしい顔が覗き込んだ。鬼である。たちまち、崖をよじ登り、こちら側へ何十匹もの鬼がなだれこんできた。
郷は、身体がすくんだ。
桃太郎に出てくる赤鬼、青鬼とかいう生やさしいものではない。これは鬼神だ。人間の三倍ほどの身の丈。怒髪天を衝くとは、この形相をいうのであろう。首からは髑髏の連なった首飾りを着け、桃源郷の女人どもを喰ってやろうと言わんばかりだ。
「鬼が島から宝物を持ち帰ったことが、こんなことになってるなんて!」
どうやら、鬼神どものプライドは、西王母と同じくらい高いらしい。
桃源郷の女戦士から一斉に矢が射られる。しかし、硬そうな鬼の皮膚に当たってぽろぽろ落ちるばかりだ。そのうち、一匹の赤黒い鬼神が女戦士をつまみあげ、岸壁の向こう側へ放り投げた。
続いて他の鬼神たちも、群がって抵抗する女戦士たちをどんどん投げていく。
「いかん。彦星、出やれ」
西王母の檄が飛んだ。
反対側の岸壁に、火がたくさん灯り始め、先頭の巨大な真っ黒な牛に乗った戦士が怒号を上げながら突進を始めた。地響きが伝わってくる。彦星が牛の角に松明をくくりつけ、鬼神を迎え撃つのだ。
「ちょい待ち。彦星って七夕であんなに勇ましかったっけ? 織姫のヒモのような優男のイメージがあるんだけど……」
呆気にとられている郷である。西王母の城があった焼け跡は、高台になっていて戦況がよく見てとれる。鬼神たちが牛の大群にひるんでいるのが分かった。
「女ばかりの桃源郷に、あの戦力は欲しいはずだ。彦星は当分、帰れんな」
それでも、鬼の大群は、西王母の城の焼け跡近くまで迫ってきた。
好色そうな緑色の鬼が、獲物を見つけたようだ。
ひときわ美しい女人をつまもうとして手を止めた。
「きゃああああ! 助けて!」
叫んでいるのは、輝夜ではないか。緑色の鬼は、輝夜を投げるのをやめて地上に下ろした。
「それ、輝夜とやら。お前から鬼神に桃酒をたくさん与え、酔いつぶしてしまうのじゃ」
西王母が叫んだ。その通り、桃酒を持たされた輝夜は、濃い化粧を施され、ひらひらした織姫のような衣装を着せられ、飾られている。
「どうして、あの女史が」
「ふふん、あの女、まったく化粧っけがないが、よく見ると類稀なる美しい眼鼻立ちじゃ。鬼の接待係となってもらうことにしたのじゃ」
西王母が得意げに言う。
「学生よ、ここまで戦を目の当たりにして、戦の気が溢れて来ぬか? そなたも男じゃろう」
「む?」
長年、研究室に籠もった青びょうたんと言われてきた郷だが、西王母の言葉に奮い立った。西王母が腰に穿いていた大剣を、軽々と抜いた。
「だ、大丈夫かのう、学生さんや」
長老がおどおどしたが、郷の横顔には赤々とした篝火が映り、強い戦意が沸き上がってきた。
牛乳瓶底のメガネをうっちゃり、インスタントラーメンの縮んだ髪の毛をひとつにまとめ、厳めしい眉を露わにした。
「俺も男、桃源郷をここまでされて黙っていられるか! あんなに研究してきた桃太郎の故郷を! それに……」
郷の視界の端に、いやいや緑色の鬼に桃酒をお酌する輝夜の姿が飛び込んできた!
「あんな不慣れな真似がさせられるかっ!」
「え?」
長老がきょとんとしている間に、郷は緑色の鬼に突進し、輝夜に手を伸ばそうとしている腕に向かって剣を振りかぶった。
「うおおおおおおっ!」
緑色の鬼が肩を押さえてのたうち回っている間に、郷は、輝夜の腕をつかんで高台まで戻ってきた。
「ちょ、あんた、研究室の桃源さん? よくあんなことが」
「俺にも分からん、やっちまった」
「その剣の持ち手は、桃の木で作られておる。桃の花言葉は『天下無敵』。剣の魂が憑依したのであろう」
西王母が、ようやったとばかりにころころ笑った。
「『天下無敵……』桃源さん、あなたって」
輝夜が潤んだ瞳で見つめている。
(本当だ、この女、よく見ると織姫みたいに可愛いじゃないか)
目の前に迫る鬼神たちめがけて、郷はもう一度戦乱の渦へ巻きこまれていった。
第 七 章 夜明けまでの戦い
戦いは一晩続いた。
西王母の采配が振られ、檄が飛び、伝令の女戦士が行きかい、彦星率いる牛の軍隊や女戦士も力のかぎり鬼の群れから桃源郷を守った。篝火から飛んだ火が鬼に燃え移り、夜明け近くなってからようやく退散を始めた。
なだれをうったように崖を飛び越え、頭を抱えて逃げていく。
「やったぞ、鬼たちを退散させたぞ!」
女戦士たちは、勝鬨を上げた。
「二度と来るでない、桃源郷は我らのもの」
夜明けの黄金の雲の上から梯子が下り、煌びやかな衣装の男がひとり、音もなく降りてきた。西王母が気がつき、
「ま、東王父様ではありませぬか」
「東王父?」
郷が不思議そうにもらすと、長老が、
「西王母様の旦那様じゃよ。男仙人を統べるお方じゃ。ここはあの世の仙界じゃが、現世の仙界の王じゃ」
「ふうん」
「あなた、今頃ノコノコと。此度の戦いは今までになく大変でございましたのよ」
西王母がツンとして言った。
「こちらの仙界までキナ臭いのが漂ってきたから分かった。朕にもできることはないかと思うての」
「何もございません。配下の者が鬼を追い払ってくれました」
やっと兜を脱ぎ、長い髪を打ち払った西王母の素顔を見て、郷は腰が砕けてしまった。
(なんという、なんという見目麗しさ、気高さ……そして……)
驚いたのは、そればかりではなかった。
「用がないなら、朕は帰るぞ」
東王父は、照れ笑いをして雲に登って行こうとする。
「あなた。現世から、大和の国の『正座』という座り方を教えて下さったこと、改めてお礼申し上げますわ。ではまた、お元気で」
「また鬼神が来たら朕を呼べ。達者での」
東王父は黄金の雲に乗って帰っていった。
怪我人は少なくて済んだ。
西王母は、城跡の高台に皆を集めた。
「皆、ご苦労であった。これまでにない激しい戦いであったが、これで当分の間、鬼どもは襲って来ぬじゃろう」
皆は胸を撫でおろした。
「輝夜じゃったの。いきなり戦いに巻きこんでしもうて悪かった」
「こ、怖かったですよ、あんなでかい鬼……」
「ほんにご苦労じゃった。褒美をとらせよう。何がよい? 不老不死の桃の実かな? あいにくこの有様でひとつも無いのじゃ」
「じゃあ、私の研究費用!」
輝夜は叫んで、西王母がころころ笑った。
「地下の宝物庫に金銀などいくらでもある。持っていくがよい」
「やった!」
「次に、彦星。そなたと織姫には辛い思いをさせたな。織姫は洞穴の向こうで待っておる。迎えに行ってやるがよい」
彦星は、鎧がぼろぼろになっていたが、パッと顔を輝かせた。
「では、私どもが西王母様の許しを得ずに夫婦になったことをお許しいただけるのですか」
「おうとも。戦の褒賞じゃ」
「ありがとうございます。早速、迎えに!」
戦の疲れも見せず、彦星は走っていった。
「わ、わしには褒賞は? 昔の恋人に会い、戦の力が増したじゃろうが」
長老がにひらにひら笑いながら、西王母の答えを待った。
「昔の恋人? さて、星の数ほどおるが、おぬしから特に何も感じんなかったのう」
「そ、そんなあ」
西王母の大きな剣を持ったまま郷は岩の上に腰かけ、ぼんやりしていた。
「剣をお返しします。俺みたいな弱虫が鬼たちと戦えたのも、この剣のおかげです」
「ほほほ」
西王母は慈悲に満ちた笑いを浮かべて、剣を腰の鞘に戻した。
「あのう、西王母様……」
郷がもじもじしながら言う。
「俺―――、もしかして、あんたの子ども? 桃太郎?」
「今頃、気づいたか」
「さっき、あんたが兜や面頬を取り去った時に、そっくりだって気づいたんだ」
「鈍いやつ」
「感激の親子対面はしないのか?」
「ふん、桃源郷の桃は全てわらわの子どもじゃのに、珍しゅうもないわ」
かっかっかと豪快に西王母は笑い、
「そち、桃の中でどのような格好でいたか、知りたいのであろう」
「……」
「そちは桃の中で、東王父から教えてもろうた大和国の『正座』という座り方で桃から生まれるのを待っていたのじゃ。丸まっていたのでは、すぐにバンザイ! 出来ぬからの。種の時代に、わらわが気品のある正座を教え込み、気品と怪力を得たのじゃ」
「おお! やはり!」
「『正座』は、桃の花言葉にあるように『天下無敵』の座り方じゃ」
誇らしげに笑い、西王母は背後に並んでいる女戦士たちに合図した。彼女たちは一斉に膝を折り、美しい正座をしてゆっくり頭を下げた。
「桃太郎様、此度は誠に有難うございました」
数えきれないほどの女戦士が大地に伏せてお礼を言う景色は見事だ。
「さすがは、天下無敵の座り方じゃな。これが、母としてのそなたへの褒賞じゃ。達者で暮らせ」
西王母は踵を返し、城跡へ下っていった。
郷と輝夜と長老は洞穴を戻り、村に戻り着いた。彦星と織姫が涙を流して喜びあっていた。
長老にも別れを告げ、元来た緑あふれる道を、郷と輝夜は歩んでいた。来る時のような刺々しさ、やる気の無さはまったくない。
ただ、輝夜が足を止めては郷を振り返った。
「なんだよ、さっきから」
「郷くん、おでこあげた方がいいわよ。それと毎日、洗濯もして。研究室に籠もっていないで」
「大きなお世話だよ。あんたも、少しは化粧した方がいいぞ。でも、西王母からもらった褒賞で、高い化粧品買っちゃいかん」
「わかってるって。……ありがとうね。緑の鬼から助けてくれて」
両脇に桃の成るのどかな道を、ふたりは並んで歩いていった。