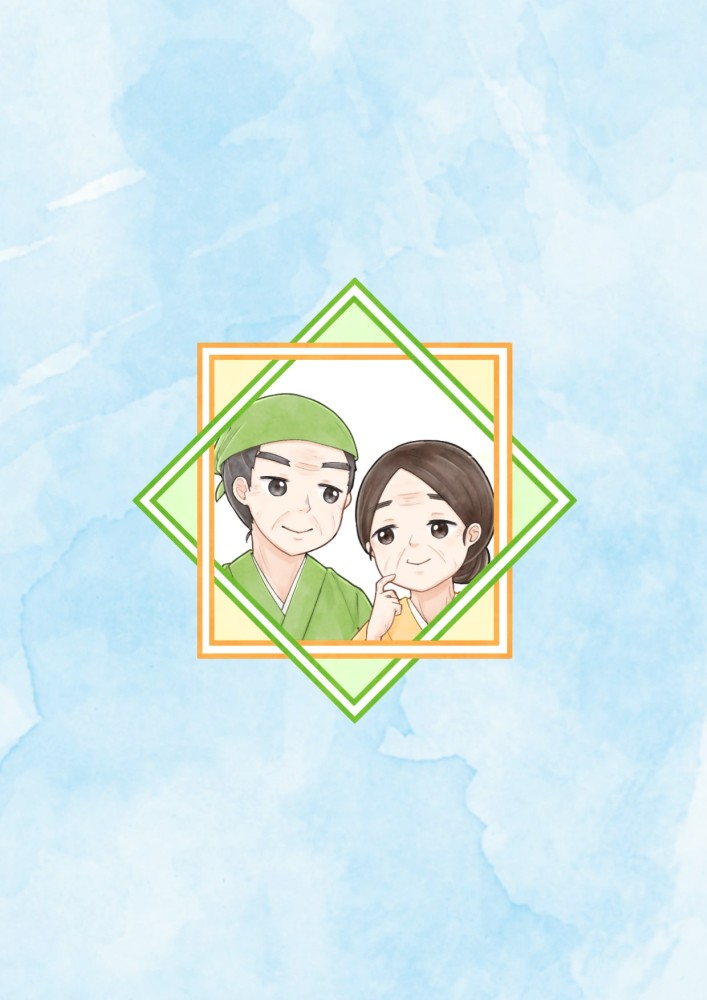[251]豪華客船かちかち山の正座
 タイトル:豪華客船かちかち山の正座
タイトル:豪華客船かちかち山の正座
掲載日:2023/03/11
著者:海道 遠
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
ある村に、毎朝、正座して静かに朝げをいただき、畑仕事に精を出す老夫婦がいた。
山で道に迷ったお爺さんは、落ち着いて正座し夜明けを迎える。白ひげの老人が現れ、正座の所作を教えてくれるように願う。以来ふたりは友となった。
村にホストくらぶというものができて、お婆さんも通いつめ、かなりなお金を使っていた。

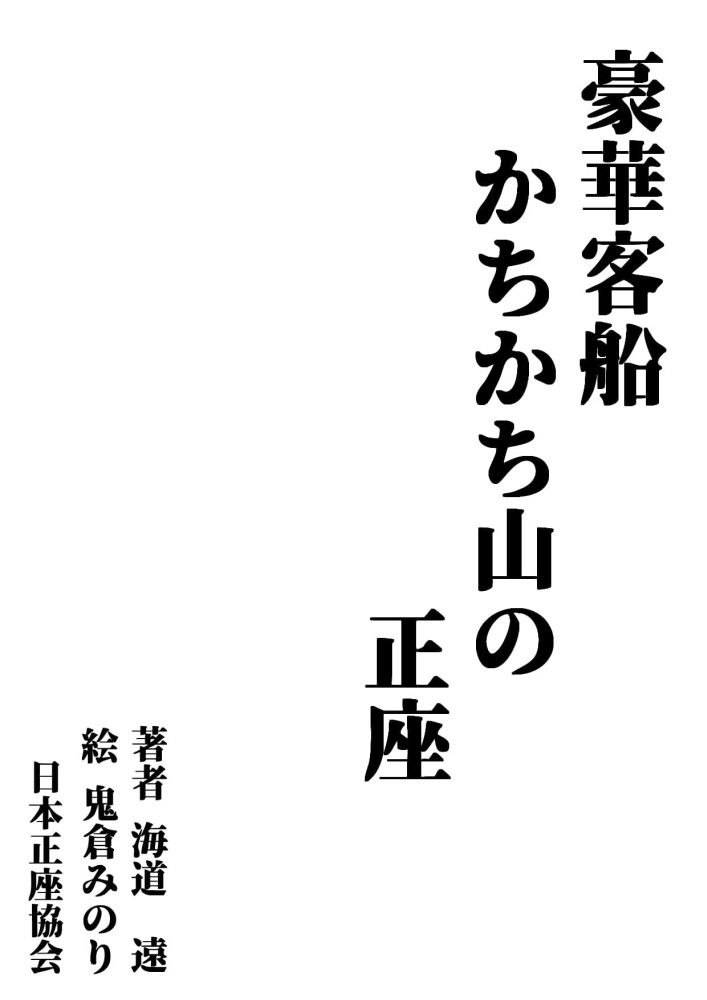
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序 章
ある村の老夫婦は、毎朝、向かいあって丁寧に正座し、
「今日も一日宜しくお願いします」
お辞儀しあって一汁一菜のあさげをいただき、畑仕事に精を出す毎日を送っていた。
お爺さんはある日、山へ焚き木用の芝刈りに行き、若い頃から慣れた山なのに、道に迷ってしまった。
夕暮れが迫る。
慌てず騒がず、山道で荷を下ろし、背筋をまっすぐにして膝をつき、かかとの上に座り、両手は膝の上に置く所作をして正座し、じっと座り込む。若い頃、剣の道場で習った通りの正式な所作だ。そうすると心が落ち着いた。迷っても、翌朝には元の道に戻れるだろうと思えてくる。
やがて長い夜が去り、夜明けを迎える。
朝もやの中から、白く長いアゴひげを生やした老人が姿を現した。
「おぬしの正座を見ていたが、一晩中乱れぬ。感心したぞ」
「そこもとは?」
「山に住むつまらぬ老人じゃ。それより、そこもとの正座を教えてもらえぬかな?」
「よろしいですとも」
白ひげの老人は、お爺さんから正座の手順を習い、
「これは良き所作をお教えいただいた。お礼に帰り道をお教えしましょう」
帰り道まで教えてくれた。
以来、お爺さんは山に登る度に白ひげ老人に会い、小さな庵(いおり)に正座してお茶しながら、世相について話したり、囲碁を楽しんでいた。
ある日、白ひげ老人は、とても言いにくそうにしていたが、やがて口を開いた。
「あのう、そのう、おぬしのおかみさんがだな、夜な夜なホストくらぶとやらで派手に遊んでいるとかの噂をスズメたちが運んできたのじゃが」
「ああ、それなら知っております。ご心配には及びませんで」
「知っているとな?」
「何十年も夫婦やってますからな。大抵のことは」
「ほほぅ〜〜」
「そのうちにどうにかしますから、ご心配には及びませぬ」
お爺さんは余裕で笑っている。妻を持ったことがない白ひげ老人は、返す言葉がなかった。
「おや、海の方が騒がしい」
白ひげ老人は耳をそばだてた。
「こんな山から海の音が聞こえるのですか」
「まあな。大方、海の神、ワタツミのお転婆娘ふたりが騒いでおるのじゃろうて」
ふたりは打ちかけていた碁盤に目を戻した。
第 一 章 ウサギとタヌキ
村のホストくらぶに銀髪縦ロールのシンガーあり。
歌がうまく、シャープなサングラスしたルックス良し、スタイル良し、マダムたちを熱狂させている。イケメンホストナンバーワンのウサギとふたり組でお客を魅了していた。
「おい、銀髪シンガー。次は何を歌うつもりだピョン。俺さまはどんな歌でもいいぜえピョン」
タキシードを着たウサギも、ますますやる気いっぱいだ。
お婆さんは甘いマスクと歌声で白いふわふわ毛の美しいホストウサギにかなり貢いでいる。
お爺さんと汗水垂らして耕し、生活の糧にしてきた畑まで手放さなければならないかもしれないほど、借金してしまっている。
(どうしよう、このままでは、お爺さんに離縁されるかもしれぬ)
危機感を感じたお婆さんは、タヌキの質屋にお爺さんの大切な先祖代々の鎧兜(よろいかぶと)を牛に引かせて持っていく。それを預けてお金を作る。
質屋のタヌキは大歓迎だ。
「お婆さん、毎度ポンポコ!」
タヌキはお婆さんからの質草を喜んで預かっていた。お婆さんが今までイケウサギへ貢いだものは、タヌキの店の質流れ品。イケウサギとタヌキが共謀していたのだ。
お爺さんには若い頃からひとつの夢があった。
歌の帝王となって自分だけの豪華客船でディナーショーすることだ。準備のためにホストくらぶで歌を歌い始め、自信をつけ、その気になり始めている。
ホストくらぶの銀髪シンガーの正体は、お爺さんだったのだ。
第 二 章 お爺さんの夢
お爺さんは自分の夢について、お婆さんに打ち明けた。
「婆さんや。若い頃から叶えたい夢があってのう」
「お爺さんの夢ですか?」
「歌手になって、豪華客船でディナーショーを催す。それが大きな夢じゃ」
「な、なんですって? お爺さんが歌手に?」
「ホストくらぶで銀髪ロールの歌手に変装してな、修行を積んだのじゃ」
「えええっ、あの銀髪がお爺さんですって?」
(このままでは、ふたりで耕した畑で穫れた野菜代金で貯めたお金は、お爺さんの夢のために無くなってしまう!)
お婆さんは自分の犯した罪は棚に上げ、お爺さんが貯め込んだ資金を使われないようにするために、ウサギを訪ねた。
「ウサギさん、いつも素敵な歌をありがとうね。実はお願いがあってのう」
「こりゃ毎度ごひいきに、お婆ちゃん。どうしたんでピョン?」
真っ白ウサギは、眼をくるくるして尋ねた。
「あんたとデュエットしている銀髪シンガーのう、実はワテの連れ合いなのじゃ」
「ええ、そうだったのピョン。ボクたち、私生活についてはノータッチなので全然知らなかったよ」
「豪華客船でディナーショーをやるのが夢だそうで、うちの家計から貯金を使われると困るのじゃ。そこで、少しでも夢を叶えるのを延ばすために、お爺さんにウサギさんからうまく言って地方ドサ回りの旅に連れ出してくれないかのう?」
「ドサ回りの旅?」
「世間さまの風に当たれば、ディナーショーなんて簡単に叶わない夢だとわかるだろう」
「分かったよピョン」
ウサギは白いふわふわ毛の胸を、ドンと叩いた。
「お爺さん、豪華客船ディナーショーを実現するために、村以外の方々にも歌を聴いてもらった方がいいと思うピョン」
「ふうむ、村の中の井の中のカワズでいてはいかんのう。ウサギ、おぬしの言うとおりじゃ」
ウサギはうまくドサ回り修行に連れ出す。タヌキもウサギも一台ずつバイクに乗り出発する。
途中のかちかち山では、バイクレースが行われていた。
ウサギが抜け目なく、司会者に「○○村で有名な銀髪シンガーがお忍びで来ている」と告げたので、レースを見物に来ている観客たちも大喜びだ。お爺さんはスペシャルゲストとして歌うことになった。
いざ、マイクを握るとカチカチ音がする。
「なんでカチカチ音がするんだ?」
「ドラマーがスティック叩いてるピョン」
と、ウサギが答える。
「では、ボウボウと音もするのは何じゃ」
「バイクのエンジン音ですピョン」
首をかしげながらも、お爺さんは歌い始める。
伸びやかな歌声に観客たちは聞き入り、ダンスも言うことなしなので、満場の拍手と歓声をもらう。
お婆さんの思惑とは正反対に、お爺さんはしっかりした自信をつけて豪華客船を借りる資金まで作って戻ってきた。
第 三 章 豪華客船で
お爺さんは客船の甲板の舳先に「帝王座」という席―――客船がもし水没しても、絶対に沈まない席を作っておいた。
お爺さんは、お婆さんを利用したタヌキのこともお見通しだ。
「わしとウサギがデュエットで歌うディナーショーに招待するぞ」
タヌキを懲らしめるつもりで豪華客船に招待した。
一行は港に着き、お爺さんはタヌキを船長に任命。ウサギを支配人に任命した。
さらに帝王座にタヌキを正座を教えて座らせ、タヌキに言い渡す。
「船長は船に何があっても最後まで残るのが使命だぞ。よいな」
「わ、分かりましたポンポコ!」
銀髪のシンガーが、豪華客船でディナーショーを行うと知ったファンたちが次々に乗りこむ。
いよいよディナーショーが始まる前に、銀髪シンガーからお客様に、正座の所作が教えられる。甲板にたくさんの座布団が用意された。
客船は沖に出てディナーショーが始まる。甲板には無数の灯りがともされ、チラチラと海面に映って美しい。
たくさんの座布団の間をめぐりながら、銀髪シンガーは何曲も歌った。イケウサギもはりきってデュエットもした。
客たちや、お婆さんは魅了された。
ひとりで舳先の席に座らされたタヌキは、首を伸ばしていたが、
「歌声しか聞こえないな~~。ディナーショーの様子が見えないよポンポコ!」
二時間はあっという間に経ち、フィナーレにさしかかる頃、船底から変な音が聞こえ、不気味な揺れが船を襲った。
「な、何の音?」
「大きく揺れたわよね?」
客たちは歌を聴くのを止め、棒立ちになった。
エンジン室長が正座するタヌキのところへ駆けつけてきた。
「大変です! エンジンアクシデント!」
「なんだってポンポコ?」
もうひとりが息を切らせて走ってきた。
「大変です! 船底が溶け始めました!」
タヌキは信じられずにポカンとした顔をした。
「船底が溶け始めただって?」
「は、はい! まるで泥が水を吸うように」
「そんなバカな。この船は木造だぞポンポコ?」
タヌキは真っ青だ。
お爺さんが大声で命令する。
「助けの船を呼び、お客様に救命ボートに乗っていただくように」
船員たちがバタバタ動き始め、客たちがざわめく。
お爺さんからアナウンスが流れた。
「お客様に申し上げます! この船は後三時間くらいで沈みますので、船員の指導に従い、落ち着いて救命胴衣を着け、救命ボートに乗ってください!」
第 四 章 異変
客たちはパニック寸前だ。
お爺さんはお婆さんのところへ駆けつけてきて、腕をガシッとつかむや、タヌキの座る舳先の席へ客が混乱を起こす中をかいくぐって連れていった。
「タヌキ。お前を船長の任から解く。今すぐに婆さんに席をあけ渡してくれ」
タヌキはびっくりする。
「ここは、どんなことがあっても沈まない席だろポンポコ?」
「そうだ。だからこそ婆さんに座らせたいんだ。生きていてほしいからな」
「お爺さん……」
お婆さんの眼を潤ませるが、タヌキが食いつく。
「じゃあ、俺はどうなるんだポンポコ?」
「お客様が認める素晴らしい正座ができたら、優先して救命ボートに乗せてやってもいいぞ」
「そんな悠長なポンポコ。俺は正座を習ったばかりだぞ」
沈まない席か、救命ボートに乗るか、お婆さんの熱い願いに迷ったタヌキは、救命ボートに乗るため、正座を認めてもらうことにする。
全身から滝のような汗を流し正座に挑んだタヌキは、お客たちからも必死な様子と真面目な正座の所作を認められ、優先的に救命ボートに乗れることになる。
「やれやれ、ポンポコポコ……」
「タヌキよ、かたじけない。これで婆さんを沈まない帝王座に座らせられる」
お爺さんは丁重にお礼を言う。
騒ぎを知らないお婆さんは、周りが沈んでいくのを見ながら、半畳ほどの広さの「帝王座」に正座したままガタガタ震えていた。
「婆さんや、大丈夫じゃ。船が沈んでもその席は絶対に沈まない。そこで正座しているのだぞ」
お爺さんが勇気づけた。
「お、お爺さんはどうなさるんですか」
「わしは救命ボートに乗る。大丈夫じゃ。お客さんたちと港まで帰ってみせる」
客船は更に傾いて沈んでいく。救命ボートへ誘導する船員の声、おびえる客の声で辺りは満ちた。
そこへ海上から、ゆらりと浮かび出た大きな人影。
「うわ~~~、これは何?」
「怪物?」
第 五 章 ワタツミ
大きな人影は、いかつい灰色のヒゲを生やし手に槍のようなものを持っている。
「我は……ワタツミである」
洞窟から響いてくるような声だ。
ランランとした大きな眼、筋肉隆々(りゅうりゅう)とした偉丈夫だ。
「ワタツミ? 海の神だな」
お爺さんの眉間が寄せられた。
「絶対に沈まない席だと? 船つくりの細工ではなさそうだな。我の海の底に強力な杭でも打ちこんだのであろう」
ワタツミの黄金の瞳がお爺さんを睨みつけた。
「ワタツミよ、海の底を荒らすようなことはいたしません」
「む? ではどうして絶対に沈まない席など作ることができたのだ」
そこへ、いきなり真上から朗々とした声が降ってきた。
「ワタツミよ。わしが手を貸したのよ」
ワタツミは、天を振り仰いだ。
「久しいのう、ワタツミ」
「おお、雷神ではないか。えらく落ち着いた風情ではないか。どこぞの深山の仙人かと思うたぞ、その白い穏やかなアゴひげ姿はどうしたのだ」
「怒る時は、鬼の形相にもなり角も生やす。今はその時ではないのでな」
雲間から覗きこんだ白ひげの老人は、とても雷神には見えない。
「友の老人は、沈まぬ席を作る際、おぬしの大切な海底まで荒らしてはおらぬ」
「ではどうやって?」
ワタツミは怪訝(けげん)な顔をした。
「我が雲から丈夫な糸を垂らし、席をぶら下げておるのだ」
「糸だと?」
なるほど、婆さんの座る席は天からの輝く細い糸四本で吊るされている。
雷神は雲間から下界を覗き、お爺さんと頷いた。
救命ボートに人々が全員乗り込み、客船を後にし始めた。船はズブズブと沈み続けている。
お爺さんがお婆さんに向かって、
「さて、そろそろわしも救命ボートに乗らねばならん。婆さんや、周りの甲板が全て沈んでしまって広い海の中にポツンとひとりになるが、大丈夫だな」
「ええっ」
お婆さんの顔が引きつった。
「広い海の真ん中で正座したままひとりでですか! いつまで待てばよろしいのですか?」
「雷神と申すわしの友が、陸地に運んでくれる時までかのう?」
「そ、その雷神さんは信用できるのですか?」
「気まぐれなところがあるが」
「くれぐれもお願いしておいてくださいな。すぐにも陸地へ運んでくださいますように」
お婆さんは両手を合わせて懇願した。
「では、救命ボートに乗る。陸地で会おう」
お爺さんは行こうとする。
「お爺さん〜〜、 きっときっとですよ!」
第 六 章 雷神、力を出す
客船は沈むスピードを早めて傾いてゆく。
「きゃああああ」
大きな波のうねりが、お婆さんの膝元に迫った。
「助けて、助けて! ワテは泳げないんだよ! 雷神さまとやら。早く陸地に届けておくれ」
「婆さま、あんたの正座がしっかりしてるから、波に飲まれたりせん」
雷神が雲間から見下ろして言う。
「さて、そろそろ陸地へ運んでやるか」
雷神が雲の中から糸を探し出して引っぱり始めた。
ところが! 海の真ん中で正座するお婆さんが重くて、ビクとも動かない。
「うぬっ、どうしてだ?」
雷神は満身の力を込めるが、動かせない。
ドロドロと雷が鳴り、稲光がひらめく。
雷神の白い顔面は力を込めたために真っ赤になり、額からは角も生えてきた。
もう一度、こめかみの血管が切れそうなほど力を込めて引っぱってみるが、雲の上にへたりこんだ。
「なんてことだ、ビクともせん」
下界のワタツミが、
「どうした、雷神。もう終わりか?」
不思議に思ったワタツミが、身をひるがえしてお婆さんの座る帝王座の底へ潜ってみる。クジラのしっぽのような大きなひれがチラリと海上に見えた。
第 七 章 正座の根
そこには!
帝王座の下から伸びる銀色の樹の根のようなものが、海底へ伸びており、たどって深く潜っていくと海底まで達して根を広げているではないか。
「何だ、これは! 婆さんの座る帝王座から伸びてしっかり根づいておる」
ワタツミは海上へ戻る。
お婆さんは眼を閉じて恐怖に耐えて、合掌したまま正座していた。
(八百万(やおよろず)の神様、どうかお爺さんと船のお客様たちをお守り下さい)
(どうかもう一度、お爺さんと清々しい朝げをいただき、畑仕事に出かけられますように。どうか、どうか)
ワタツミはピンと来た。
(婆さんは正座の下から伸びる銀色の根に気づいていないが、婆さん自身の念力が作り出したものではないだろうか? 爺さんともう一度、平和に暮らしたいという思いが生んだ産物だろう)
(小魚から噂に聞いた、婆さんが陸地のホストくらぶとやらに通い詰めたことを心から悔いているのだろう)
ワタツミは雲の上へ向けて、
「お〜い、雷神! 婆さんはしばらくしてから引っぱってやってくれ。わしも力を貸す」
「あん? 本当か、そりゃ」
雷神は拍子抜けしたとたんに、真っ赤な鬼から白ひげの温厚な老人に戻った。おまけに帝王座を吊り下げる糸を手放してしまった。
「おや? この糸は」
雲から落ちてきた糸をつかんだのは、ワタツミだ。
その瞬間、お婆さんを竜宮まで連れていけば、帝王座の下から根が生えるほどの素晴らしい正座を、ふたりの姫たちや竜宮の侍女たちに指導してもらえると思いついた!
ワタツミは、常々、竜宮の侍女たちの座り方の乱れが気になっていたのだ。
すぐさま、サメの大群を呼んだ。
「サメども、至急、出動せよ!」
大きなサメが群れをなしてやってきて、お婆さんを取り囲む。
「さあ、サメども、帝王座の下から伸びておる銀色の根を食いちぎるのじゃ!」
お婆さんは悲鳴をあげた。
「きゃあっ、サ、サ、サメ〜〜!」
(ああ、ワテはお爺さんに内緒で宝物を質に入れたりしたから、ついにバチがあたった! サメに食べられるのじゃ)
お婆さんの恐怖をよそに、サメたちは海底深く潜って帝王座から伸びている根を、尖った歯で咬み切りはじめた。
第 八 章 お婆さんさらわる
雲の上の雷神が、下界を覗き、海面にサメの群れが舞ってるのを発見した。
「ワタツミ〜〜! お婆さんをどうするつもりだ?」
「竜宮にて侍女たちの正座指導を行ってもらうのじゃ」
「それは困る。お婆さんはお爺さんの元へ返すと約束したのだ」
「我の知ったことではない」
「ワタツミ、困ったヤツめ」
お婆さんが、波しぶきを顔面に受けながらチラリと横を見ると、帝王座から銀色の根を握りしめているのは、海から現れたいかついひげを生やした老人ではないか。
「あんた! ワ、ワテをどこへ連れていくんだい」
「我はワタツミ。ちょいと我の居城まで来てもらう」
「?」
「お前の正座を我の大切な娘たちに教えてもらいたい」
「ワテが姫さま方に正座を教えるですとっ?」
「お転婆でなぁ、宜しく頼むぞ、婆さん」
「とんでもございませんから〜〜」
首をぶんぶん振ったが、ワタツミは聞く耳持たない。
水上スキーさながら、お婆さんは波の上を引っぱられていった。
「お爺さんにお婆さんを確(しか)と送り届けると約束したのに」
雷神が困っていた。下界を見下ろすと岬の先にタヌキとウサギが上に向かって両手を振っているではないか。
「おーい、雷神さま〜〜」
「俺たちもお婆さんが心配だ。連れて行ってくだされ、ポンポコ」
雷神は雲を地表に下ろしていった。
「ワタツミの城は海の底だぞ」
「でも、お婆さんが心配で居ても立ってもいられませんポンポコ」
「心配で心配で……ピョン……」
タヌキもウサギもベソをかいている。
「お前たち、それは誠の涙かな? ふたりでグルになって、お婆さんから大金を巻き上げたのではないのか?」
雷神は睨んだ。
「ひぇっ、全部、お見通しで! ポ、ポンポコ!」
タヌキもウサギも土下座した。
「だからこそ、償いにお婆さんを助ける手伝いがしたいのですピョン!」
ウサギが雷神にすがりつく。
「う〜ん、どうやらウソではない様子じゃな」
「どうか、俺たちもお連れ下さいませ、ポンポコ!」
「どうか、どうか、ピョン!」
二匹とも土下座したまま動かない。
「仕方ないのう、雲から落ちても拾いに行かんぞ。足手まといになったら、海の中でも放り出していくぞ」
第 九 章 龍宮にて
朱塗りの柱の長い廊下をしなやかに泳ぎぬけ、錦糸の袖を海水にたなびかせて、姉のトヨ姫が妹姫の部屋へやってきた。
ここには水はない。
「タマ姫、もうすぐお父様のお帰りよ。今、タツノオトシゴが知らせたわ」
「お父様ったら慌ててでかけられたと思ったら、お戻りになるのも急だこと」
姉のトヨ姫とよく似た、つぶらな瞳のタマ姫がため息をついた。
少年のように男用の着物を着て髪はみずらに結っている。
「わらわたちに正座という座り方を教える老婦人を連れてお戻りになるらしいの」
「お父様は人間の大きな船が沈みそうになっているのを偵察に行かれたのよね。どうして、座り方を教える老婦人を連れて帰ることになったのかしら?」
「お父様のご命令は絶対ですからね、怖い老婦人でないことを祈りましょ」
トヨ姫は覚悟が決まっているようだ。
やがて龍宮の門番たちがざわめく気配がして、姫たちの居室までワタツミの出迎え準備が伝わってきた。
ワタツミは龍宮の海上で泳ぎを止めた。
片手でお婆さんの正座する席を吊るした糸を束ねて握りしめている。
「海よ、割れろ。我が居城まで開け」
波が渦巻き、やがて両側に割れた。海底に朱塗りと金をほどこした壮麗な建物が見える。
「婆さん、あれが我が龍宮じゃ。しばらく滞在して姫ふたりに正座を教えてやってくれ」
「あ、あれが噂の龍宮城……」
「そ〜れ、投げるぞ」
「あ〜れ〜〜」
お婆さんの小さな身体は帝王座ごと弧を描いて海の上を海底の城へ投げられた。
海水は両側からぶつかるように渦をつくり、海面を閉じる。
龍宮城の正面へ落とされたお婆さんは、海水で濡れそぼったまま尻もちをついた。
「アイタタタ…… ここはいったい……」
腰をおさえて立ち上がろうとした時、ふたりの若い娘が駆け寄ってきた。
「これは大変! びしょびしょではありませんか」
「すぐにお着替えをお持ちいたしましょう」
「あんたがたは?」
お婆さんは、きらびやかな唐風の着物を着て金色のかんざしをつけた娘と美少年に驚いた。
「わらわたちは、ワタツミの娘でトヨとタマと申します。座り方を教えて下さる先生がお見えになるとうかがい、お待ちしておりました」
面長で大人っぽい顔立ちのトヨ姫がにっこり笑って、侍女に着替えを持ってくるように言った。
「さあ、こちらへおいでなさいませ。わらわは男装しておりますが女です。妹のタマ姫と申します」
丸顔の可愛らしい姫が、お婆さんのびしょぬれの着物を解いた。
ふかふかで温かい席と着替えを用意された。
上質の絹で作られた唐風の着物だ。淡い緑色で帯は細く紅色である。
「こ、こんな鮮やかな色は着たことがありません。お婆にはもったいないこと」
「まぁま、お袖を通してみてくださいな。鮮やかな色を身にまとうと心まで元気におなりになれますよ」
ふたりの姫は手早くお婆さんに着物を着せた。
「おお、これは」
変わったカタチの着物だが、侍女が持ってきた姿見に映すとお婆さんは、
「生まれてから地味な色の野良着しか着たことがなかったが、いやはや」
「わらわたちの正座の先生ですから、それなりの格好をしていただかなければ」
タマ姫が威厳を持って言った。
「とてもよくお似合いですよ」
妹のタマ姫はニコニコして、お婆さんと姿見を眺めている。
「正座とやらのお稽古をお待ちしております」
第 十 章 正座の稽古
その頃、雷神とウサギとタヌキは、雲の上からお婆さんが竜宮城に落とされたところを目撃していた。
「あ~~あ、お婆ちゃんが海底へ落とされちゃったピョン」
「大丈夫かのうポンポコ」
雷神は慌てず騒がず、
「お前たちを偵察係にすることにした!」
言うなり、雲に穴を開け、タヌキとウサギを海へ落とした。
「ちゃんと偵察するのじゃぞ! お前たちがつぶやく声は、我に届くようになっておるからな!」
雷神は、かかかと笑い、雲をもっと上空へ登らせた。
さて、竜宮の姫たちの部屋ではお婆さんが正座の見本を見せていた。
「背筋をまっすぐして立ちます。膝を静かに床につけ、着物の裾を膝の内側にはさみこみ、ゆっくりとかかとの上に座ります。そして両手は膝の上に静かに置きます」
タマ姫が顔を輝かせて、手をパチパチした。
「素晴らしい座り方ですわ! このような高貴な座り方を、どこでお知りになったのですか?」
「どこでと申されましても……、先祖代々の座り方でしたから、自然と親から教わったのでしょうね」
「先祖代々、そうですか」
「ああ、それと夫が正座をきれいにする人でしたから見習って正座するようになりました。毎朝、正座して挨拶して朝げをいただく。それが日課でした」
「先生の夫君さまが。で、そのお方は?」
タマ姫が目をまん丸くする。
「お爺さんは……、山の村の家でワテ、いえ私の帰りを待っているはずです」
お婆さんの瞳に涙が浮かぶ。
トヨ姫とタマ姫が、慌てて背中をさすったり、涙をふくための布を差し出す。
その様子を、柱のかげからウサギとタヌキが見ていた。
「お婆ちゃんは、お爺ちゃんに悪いことをしたと悔いているのだなピョン」
「そうさせたのは、どこのどいつだポンポコ」
「グルになったのは、どこのどいつだピョン」
二匹は口をとんがらかせた。
「お婆ちゃんは、一刻も早くお爺ちゃんの待つ家へ帰りたいのだポンポコ」
ウサギとタヌキの会話を、遥か雲の上で雷神が聞いていた。
「そんなこと、わかっとるわい」
第 十一章 お爺さんからのプロポーズ
豪華客船が沈没してから、早やひと月。
お爺さんは村の家に戻っていた。ひとりで黙々と朝げをいただき、畑を耕し、作物に水をやり雑草を抜き、小石を取りのぞいたり農作業にいそしんでいた。
(あれから婆さんはどうしたのか? 雷神は婆さんを送ってくると言っていたが遅いのう)
ひとりでいると自然と鼻歌も出てくる。ホストくらぶで歌っていた華やかな歌だ。
(今度は、婆さんひとりのために歌ってやりたいのう。ウサギに入れ込んで大金を使ってしまったことなど水に流す。鎧兜をタヌキの質屋に質草として入れたことも許す。もう一度、婆さんと美味い朝げが食べたいのう)
「聞いた、聞いた、聞いたぞ、ご老人」
納屋のかげから姿を現したのは、山の白ひげ老人、つまり雷神だ。
「ら、雷神!」
「ご老人、おかみさんは竜宮城で正座の師範をつとめている」
「竜宮城で正座を? どういうことじゃ」
「ワタツミがおかみさんの正座をたいそう気に入り、竜宮城へ連れていったのじゃ。侍女たちや姫君たちに正座を教えて立派にやっておいでじゃ」
「そ、そんなことになっていたとは……」
「おかみさんの船の帝王座には、海底に銀色の強力な根が生えていたそうじゃが、あれはおかみさんの念力ではなく、そこもとの愛情が生んだ根っこではないかな?」
「?」
「どうも自覚がないようじゃが。おかみさんに帰ってきてほしければ、自ら迎えに行き、再度、結婚を申し込んではいかがかな?」
お爺さんは真っ赤になった。
「婆さんとは家どうしが決めた相手で、プロポーズをしたわけではない」
「なら尚のこと。龍宮城まで送って進ぜるゆえ、ぜひ、そうなされ。おかみさんも待っているに違いない」
「送ってくれるとな?」
お爺さんはさっそく農耕馬のアオに農具をくくりつけた。
「アオや、婆さんを連れてすぐに帰るから、馬小屋に帰ってくれ」
「ブヒヒッ」
アオが歯をむき出していななき、承知した。
雷神はにやつきながら、雲を呼びつけた。
竜宮城の奥、侍女に囲まれて正座のお稽古をしていたトヨ姫は、勘づいた。
「正座の先生、ご夫君が海の上の空に来ておいでじゃ。海面をただようクラゲが知らせてくれた」
「まことですか、姫さま」
「お待ちください。父から預かった、潮引きの玉があります。今、道をお開けしましょう」
トヨ姫がたもとから玉を取り出して、呪文を唱えると頭上の海が引いて空がはっきり見えた。
お爺さんを乗せた雲が低くすべり下りてくる。
「婆さん、会いたかったぞ。すべてを許す。もう一度、わしの嫁になってくれ」
「ま、まあ、お爺さんたら」
トヨ姫やタマ姫も歓声を上げた。
「先生、どうぞお幸せに。おうちへ帰っておふたりで正座して美味しい朝げを召し上がってください。教えていただいた正座は忘れませんよ」
「姫さま方、ありがとうございます」
お婆さんは身をひるがえすと、お爺さんの腕の中へ飛びこんだ。
竜宮城で偵察係になったタヌキとウサギがどうなったか、誰も知らない。