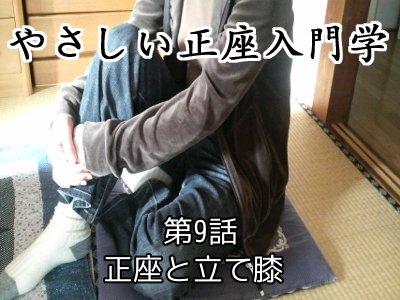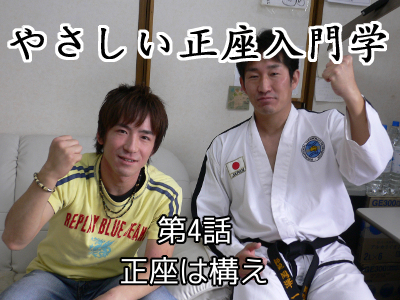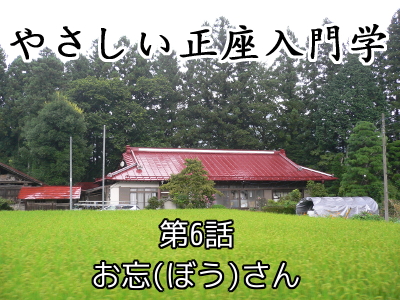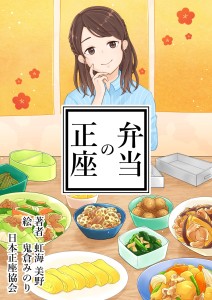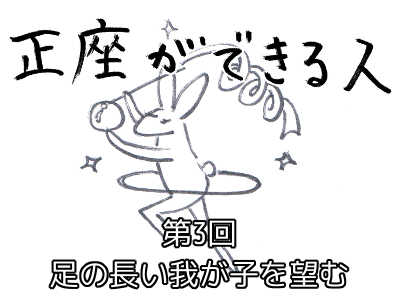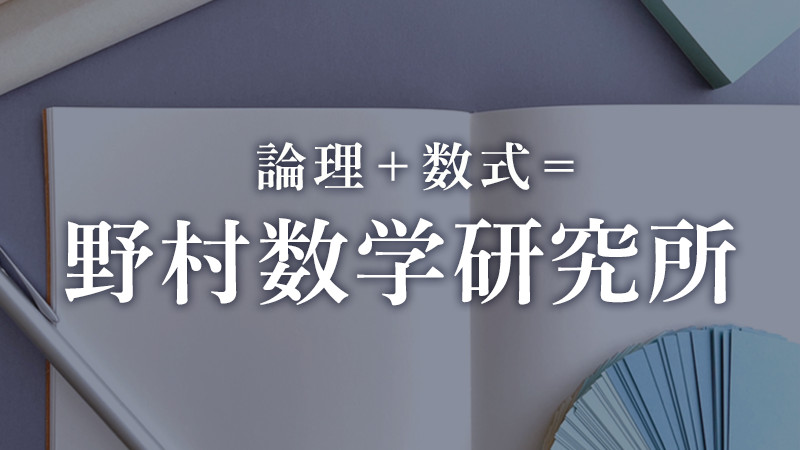[353]第30話 正座とお茶のまったりした関係
 発行日:2025/05/02
発行日:2025/05/02
タイトル:第30話 正座とお茶のまったりした関係
シリーズ名:やさしい正座入門学
シリーズ番号:30
著者 :そうな
イラスト:あんやす
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止します。
やさしい正座入門学
第30話 正座とお茶のまったりした関係
29回目の記事で、日本には四季があり、その節目で自律神経を崩しやすいという記事を書いた。また、正座が「正座療法」として改善に一役買うのではないかという趣旨を記した。
「とはいってもなー。飲むだけ、食べるだけで自律神経を整える方法はないの?」などと思うのが、人の欲である。(単純に筆者の欲かもしれない)
そう思い、ある健康雑誌の『自律神経を整えるには?』という記事に目を通していたときのことだ。記事には、次のように書いてあった。「ソワソワして落ち着かない状態や、寝つきが悪い・眠りが浅いといった睡眠の悩みは、交感神経が優位な状態が続くことで起こりやすい不調。温かいお茶でひと息つくなど、リラックスタイムを持つよう心がけましょう。」
つまり、お茶には自律神経を整えたり、リラックスできたりという効果があるということだろうか? これはまさに、飲むだけで自律神経を整える方法なのではないだろうか? 私は期待を胸にこの記事に飛びついた。
ここで気になるのが、お茶の効能についてだ。お茶といっても緑茶、紅茶やその他多種多様な種類がある上に、国によって見解やたしなみ方があり、飲んだ個人の感想についても、それはもうさまざまである。
例えば、海外のある人にとっては、「本物の紅茶とは、琥珀色になるまで濃く抽出したものであり、一口飲めばたちまち目が覚めるような感覚が体を駆け巡る。」のだそうだ。それが「本物の紅茶」かどうかは置いておくとして、これでは、リラックスとはほど遠い上に、あまり一般的ではない気もする。さらに文章は続いていた。「濃く抽出したお茶は、酒なんかよりうまい。一口で飛ぶぜ!」それはなんだかマズいんじゃないかという気がしてくる。比較するものが酒であるところも問題だが、最後の「飛ぶぜ!」も目的のない場所へ飛んで行ってしまいそうな恐ろしさがある。紅茶を飲んだだけなのに……なんてことにもなりかねない。
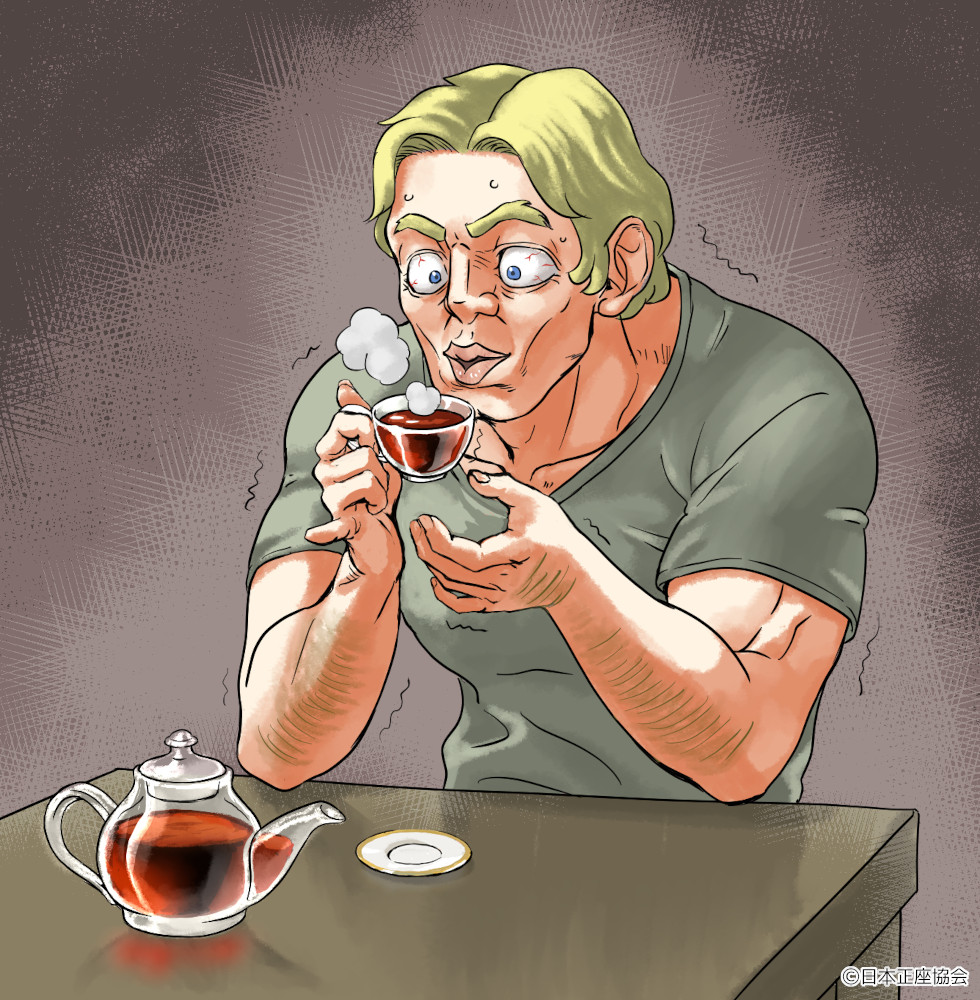 紅茶は酒に勝る? こんな感想もちらほら散見されたとはいえ、やはり海外でも日本でも、緑茶も紅茶も「ひと息つける」という感想が一番多かっただろうか。特に日本茶において「ホッとする」という感想が多くみられた。中でも「緑茶をのんだときの感想を例えるなら、温泉。」と書いている海外の人は、一見するといったい何なのかと思ってしまう文章だが、よくよく考えてみるとなかなか的を射ている気がしてくる。温かい緑茶をすすって心から一息つくときの気持ちは、温泉に入ったときにひと息つくときのソレにも似ている気がする。温泉の場合は、熱い湯による寒暖差や水圧によるものという解説も聞くが、気持ち的には、なんとなくこの現象に似ている気もする。
紅茶は酒に勝る? こんな感想もちらほら散見されたとはいえ、やはり海外でも日本でも、緑茶も紅茶も「ひと息つける」という感想が一番多かっただろうか。特に日本茶において「ホッとする」という感想が多くみられた。中でも「緑茶をのんだときの感想を例えるなら、温泉。」と書いている海外の人は、一見するといったい何なのかと思ってしまう文章だが、よくよく考えてみるとなかなか的を射ている気がしてくる。温かい緑茶をすすって心から一息つくときの気持ちは、温泉に入ったときにひと息つくときのソレにも似ている気がする。温泉の場合は、熱い湯による寒暖差や水圧によるものという解説も聞くが、気持ち的には、なんとなくこの現象に似ている気もする。
このホッとするという気持ちは、きっと紅茶ではだめなのだ。緑茶だ。きっとティーカップじゃだめなのだ。湯のみだ。そんな気持ちで資料をあさっていると、昨今、海外で日本茶がブームになっているという記事が見つかった。主にカナダのトロントで人気が出ており、緑茶も人気だが、特に抹茶やほうじ茶などいろんな種類の日本茶が人気だという。
その理由の一つに『カフェインクラッシュ』を避けるというものがあるらしい。アジア圏以外の海外では、お茶よりコーヒーを飲む文化が多い。そのため、『カフェインクラッシュ』という現象に悩まされる人も少なくないようだ。ちなみにその『カフェインクラッシュ』というのは、コーヒーなどのカフェインを含んでいる飲み物を飲むと、急激にカフェイン効果が表れ、そして急激にカフェインがなくなっていく感覚が生まれることだという。
それに対し、「日本茶はゆるやかにエネルギーが持続する。コーヒーとは違う。」と称賛されているのだという。
なるほど、カフェインは交感神経を優位にするため、自律神経を乱しやすいといわれている。少なからず緑茶にもカフェインは含まれているが、コーヒーのほうが圧倒的に多く含んでいるらしい。それでも、「ホッとする」、「リラックスするために緑茶を飲もう」と言われるのだから、緑茶とは一体どんな存在なのだろう? お茶を飲むだけで改善できるのだろうか? 飲むだけで改善できるなら、今日からでも気兼ねなくできるのではないだろうか? そんな希望を秘めつつ、緑茶にしぼって調べていくことにした。
お茶といえば、静岡が有名だ。ということで、早速静岡市のホームページ『お茶のまち静岡市』へアクセスしてみた。
 お茶のまち静岡市のHP 以下は、その中の「知る・学ぶ」というカテゴリーの「お茶の効能」を参考にしている。まず、お茶が体に良い理由を探してみた。
お茶のまち静岡市のHP 以下は、その中の「知る・学ぶ」というカテゴリーの「お茶の効能」を参考にしている。まず、お茶が体に良い理由を探してみた。
「緑茶には、健康によい影響を与えるとされる成分が多く含まれることは広く知られていますが、『緑茶を習慣的に摂取することで、男女の全死亡リスク及び心疾患、男性の脳血管疾患及び呼吸器疾患による死亡リスクの減少がみられた』という研究結果が、国立がん研究センターから発表され、その効能がますます注目されています。」
なんと、自律神経に効果的か調べていたはずが、死亡リスクや心疾患のリスクまでもが減少するのだということを知ってしまった。これだけでも毎日飲みたいものである。だが、ここからだ。私は、お茶のリラックス効果や自律神経にどう作用するのかを探るべく、静岡市のホームページの奥地へと進んでいった。
静岡市のホームページによると、お茶の成分には、お茶の苦み成分『カフェイン』、お茶の渋みと苦み成分『カテキン』、お茶の甘味とうま味成分『テアニン』、他に『ビタミンC』や『ミネラル』が入っているとのことだった。
中でも、『テアニン』には、お茶の葉だけに含まれているアミノ酸があり、心と体をリラックスさせる効果があるとのことだった。この成分こそが、緑茶をのんでホッとするという成分なのだろう。
また、『カフェイン』には、眠気を飛ばしたり、脳や心臓の働きを活性化させたりする効果があるため、体調不良の原因にもなることから過剰な摂取には注意が必要とのことだった。
コーヒーによる『カフェインクラッシュ』の症状で悩まされている人が気にするカフェインだが、これは緑茶にも含まれている。緑茶で『カフェインクラッシュ』はなかなか耳にしたことがないが、気になるので調べてみた。
いろいろな緑茶専門店のページを巡り、緑茶との含有率の差を調べてみたところ、だいたいコーヒーの3分の1程度のカフェインが含まれているようだった。一日に飲み物を3杯飲むとしよう。その場合、コーヒーを3杯飲むのと、緑茶を3杯飲むのでは、カフェイン摂取の割合がかなり大きく変わってくることが分かる。
このような結果を知れば、確かにコーヒーを日常的に摂取する国の人は、緑茶に目を向けるきっかけになるのであろう。(※これは一般的な作法で緑茶を煎れた場合の結果である。濃く煎れる、薄く煎れるなどの煎れ方によって、カフェインの濃度も変動することを覚えておきたい。)
しかし、カフェインが問題であるのなら、もっと減らせば健康にいいのではないだろうか? 例えば、ほうじ茶は焙煎の過程で茶葉に含まれるカフェインの一部が気化するから、緑茶と比べれば少しは含有量が少ないだろうか? それともいっそ、もっと含有量の少ない玄米茶やカフェインレスの麦茶を飲むべきだろうか? ……このようないろいろな考えが、頭の中をめぐり始めるのではないだろうか。
この考えを払拭してくれるのが、『お~い お茶』のフレーズで有名な伊藤園だった。
 伊藤園のHP カフェインや緑茶を調べていくうちに、私は伊藤園のホームページへと足を踏み入れていた。最初こそ、「あ、『お~いお茶』のCMのページだ。新しい商品出てるかな。」くらいの認識しかなかったのだが、読み進めてみると、私の安易な考えが一瞬で吹き飛んでしまうほど、とんでもなく有意義で本格的な研究をしている会社だと再認識した。以下は、『お~いお茶』のホームページにある『ニュースルーム』欄2024.07.09の記事より抜粋した。
伊藤園のHP カフェインや緑茶を調べていくうちに、私は伊藤園のホームページへと足を踏み入れていた。最初こそ、「あ、『お~いお茶』のCMのページだ。新しい商品出てるかな。」くらいの認識しかなかったのだが、読み進めてみると、私の安易な考えが一瞬で吹き飛んでしまうほど、とんでもなく有意義で本格的な研究をしている会社だと再認識した。以下は、『お~いお茶』のホームページにある『ニュースルーム』欄2024.07.09の記事より抜粋した。
〇研究の内容
「健常な成人男性の試験参加者20名を対象に、安静5分間の後に暗算作業を5分間×3回、最後に安静5分間を実施し、各作業前と最後の安静前に飲料(白湯、市販の緑茶またはほうじ茶;50ml×4回)を摂取させました。安静時および作業時に生理反応を計測し、作業前後に主観的疲労感を評価しました。白湯+緑茶、あるいは白湯+ほうじ茶の試験は別日に実施し、全参加者が2回試験に参加しました。」
なんて難しい資料だ。一度では理解しきれなかった。これは本当に伊藤園が書いたのだろうか、などと不躾に思った自分がいる。いや、伊藤園が書いたに決まっているからこそ、伊藤園のホームページに載っているのだ。私は、お花畑ならぬ緑茶畑な脳内を叩き起こし、読み直した。つまりは、白湯(さゆ)と緑茶、ほうじ茶を男性20人に飲んでもらい、疲労感の変化を実験したよ。疲労感を与える方法は暗算作業だよ。とのことだった。
そして、以下がその結果だ。
「本研究の結果より、作業前や合間に緑茶およびほうじ茶の飲用は、デスクワークなどの作業成績向上や疲労感の軽減につながることが示唆され、日常生活で摂取する程度の少量であっても短時間でストレス感を軽減させる機能が期待できます。」ちなみに、慣れの影響も懸念して、今もなお研究中とのことだった。
カフェインの入っていない白湯より、緑茶やほうじ茶を飲んでいた方が、疲労感が少なかった理由は、ほっこりする『テアニン』だろうか。いやいや、渋みが刺激をもたらしたのかもしれない。はたまた、ビタミンCの効能による疲労軽減だろうか? あるいは、少量のカフェインならば、脳や心臓の働きを活性化させるともいわれ、むしろ良い効果を生み出すことも知られているから、これかもしれない。いろいろな可能性を内包している。やはり、お茶は奥が深い。
この伊藤園の実験は、伊藤園『ニュースリリース』項目の2024.07.09の記事『緑茶およびほうじ茶の飲用は複数の生理反応へ影響を与え、作業成績の向上や疲労感の軽減にも寄与することを確認』という記事を参考にしている。より詳しい内容や研究の成果をグラフに表して説明してくれているので、ご興味のある方はぜひ伊藤園のホームページを訪れてみてほしい。
緑茶には『テアニン』によるほっこり作用があり、またこの量のカフェインならば、むしろ良い効果を発揮することも分かった。これなら、自律神経にも良い影響をもたらしてくれるであろう。最後に、自律神経に良いという太鼓判を押してもらうべく、『千紀園(せんきえん)』のホームページを訪れた。
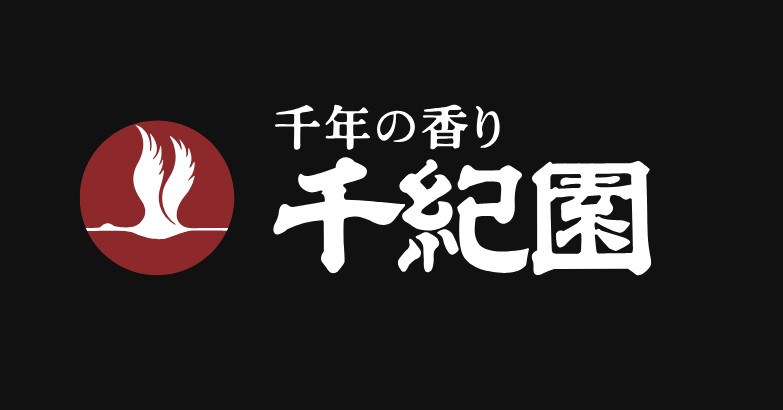 千紀園のHP 1661年に創業した日本茶の老舗だ。以下は、千紀園のホームページ内にある『読み物』カテゴリーの2020.10.15に掲載されている『緑茶によってもたらされるストレス軽減と不眠改善の効果とは』の文章からの引用である。
千紀園のHP 1661年に創業した日本茶の老舗だ。以下は、千紀園のホームページ内にある『読み物』カテゴリーの2020.10.15に掲載されている『緑茶によってもたらされるストレス軽減と不眠改善の効果とは』の文章からの引用である。
「日本茶にはカテキンなどのタンニンやポリフェノール、カフェインなどに加えてアミノ酸も含まれていて、健康に良い効果があることが解明されてきています。その中でもリラックス作用があることで注目を浴びているのがテアニンです。テアニンは緑茶に含まれているアミノ酸の約50%を占めていて、緑茶にしかあまり含まれていないことが知られている成分です。お茶のうま味、甘味を醸し出し、高級茶葉に多く含まれています。」
「テアニンはリラックス効果やストレス軽減、不眠改善、認知症の予防などといった効果があることが明らかにされています。ストレスになる刺激への応答として起こる自律神経系の活動を抑制したり、脳神経系の活動を正常化したりするといったメカニズムが示唆されていますが、リラックス作用を示す理由として脳波のα波が増加することも確認されているのが特徴です。脳波は脳の活動のあり方を解析するときに測定されるもので、自律神経系の活動が穏やかになったときにα波が増えることが知られています。テアニンを多く含む緑茶を飲む習慣を作ることで、脳の興奮を鎮めてリラックスさせ、神経系の影響による心身の不調の改善を目指せると期待できるでしょう。」
やはり『テアニン』だ。緑茶にしかあまり含まれていない『テアニン』が、自律神経をしずめリラックスさせてくれるようだ。
お茶はほっこりする、まったりするという日本人の口伝は、単純な昔話に近いものを感じていた筆者だったが、しっかりとした科学的根拠のある話でかつ的を射た発言だったのだ。
日本の伝統文化である茶道も、亭主が茶をたてている間は気を引き締めて待つが、お茶をいただいた後は、どこか心がまったりする感覚に包まれることも、こうした日本茶の効力が一役買っているのかもしれない。
ぜひ、正座(正座療法)を取り入れながら、日本茶をのんで、自律神経を整えてみてはいかがだろうか。これで、季節の変わり目も怖くない!?
 季節の変わり目も日本茶効果でおだやかに
季節の変わり目も日本茶効果でおだやかに
参考資料
「お茶のまち静岡」HP
https://www.ochanomachi-shizuokashi.jp/
「伊藤園」HP
https://www.itoen.co.jp/
「千紀園」HP
https://www.senkien.jp/f/shop