[36]墨の香りと痺れた足
 タイトル:墨の香りと痺れた足
タイトル:墨の香りと痺れた足
分類:電子書籍
発売日:2018/07/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:56
定価:200円+税
著者:こころ彩
イラスト:時雨エイプリル
内容
四月。青翔高校に入学した縦山明日香(たてやまあすか)は、部活勧誘の際に配られたビラを見て、書道部に興味を持つ。
横川蒼士(よこかわそうし)という三年生の先輩が書く字に見惚れ、自分も人を感動させる字を書いてみたいと彼に憧れの感情を抱いた。
しかし、正座をするとすぐに足が痺れてしまい、集中力を保つことができないことに気づき、自分は書道に向いていないと悩むのだった。
販売サイト
販売は終了しました。

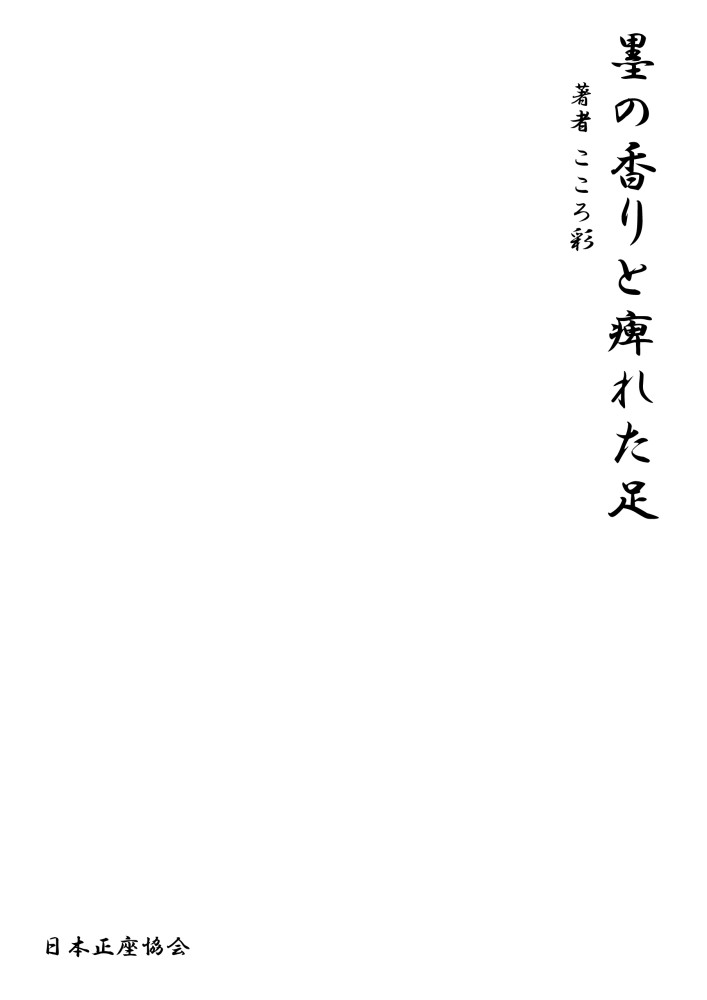
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
……春。
ひらひらと舞う桜で染まったピンク色の道を歩く。
私、縦山明日香は今日、この青翔高校で入学式を迎えた。
新しいクラスも明るい子が多くて、これから一緒に学校生活を共にしていくのが楽しみで仕方がない。
(天気もいいし、絶好の入学式日和って感じ!)
そんなことを思っていると、グラウンドや体育館前、あちらこちらでチラシのような紙を配っている人を見かけた。
「ご入学、おめでとうございます! 良かったら部活見学に来てくださいね」
「は、はい……!」
どうやら、部活勧誘のチラシを配っていたらしい。
先輩に手渡されたチラシを見た瞬間、私はある文字に一瞬で目を奪われた。
「す、すごい……」
受け取ったのは書道部のチラシだった。
チラシの一番上には、高校の名前である『青翔』が筆文字で書かれていた。
力強さの中にも、繊細さを感じられる筆文字。
今まで書道なんて習ったことがなかった私でも、一目ですごいと分かった。
「この文字って、どなたが書かれたんですか……!?」
「三年生の横川蒼士って人だよ。横川くんは部内でも一番上手くて、書道展で何回も受賞しているすごい人なんだ!」
チラシをくれた女の先輩は、少し頬を赤く染めながら興奮気味に話す。
もしかして、その横川先輩って人のことが好きなのだろうか。
「あの、横川先輩の書いたものを見せていただくことってできますか?」
「部室に来てくれれば、横川くんが書いた作品が飾ってあるから、ぜひ見学に来てね!」
「は、はい! 行きます、絶対行きます!」
「あはは、じゃあ待ってるね!」
先輩は手をひらひらと振ると、他の新入生の子にもチラシを配り始めた。
もう一度、書道部のチラシを見つめる。
「やっぱりすごい……」
さっきからすごいしか言っていないような気がするが、とにかく私は横川先輩の文字に心惹かれた。
「どんな人が書いているんだろ……。書いてるところ見てみたいな!」
チラシを胸の前でギュッと抱きしめ、私は部活見学の日を楽しみにしていた。
2
「ねぇねぇ。皆って、この後の部活見学どこに行くの?」
「私はテニス部!」
「私はバスケ部かなぁ。マネージャーに興味があって!」
今日は待ちに待った部活見学の日。私が向かうのはたった一つ。
そう心に決めて意気揚々としている私を、クラスの女の子は不思議そうに見つめていた。
「縦山さんはどこの部活を見学するの?」
「私は書道部だよ」
「へぇ~、なんか意外かも! もしかして書道とかやってたの?」
「ううん、全くの初心者……」
本当に、今までこれっぽっちも書道には関心が無かった。
無知な私が、果たして書道部に入部してもいいのか、ちょっと悩ましい部分もあるけど……。
「気になる人がいるんだ!」
横川先輩に会ってみたい。横川先輩が字を書くところを見てみたい。
そう自分に言い聞かせながら、私は書道部の部室へと向かった。
3
「え、これって書道部の見学者……!?」
書道部の部室に着いて、私は驚愕した。
部室の前には大勢の女の子。全員、書道部を見学しにきた子たちなのだろうか……。
「きゃー! あの人かっこいい!」
「横川先輩って言うらしいよ。超イケメンだよね!」
横川先輩という言葉に、私は思わず反応してしまった。
(ということは、部室に横川先輩が……!?)
何とか隙間を見つけ、そこから部室を覗く。女の子たちの視線は、一人の男子生徒に集中していた。
その男子生徒は、女子生徒の黄色い悲鳴を気にもせず、背筋を伸ばして目の前にある半紙を見つめている。
おそらく、彼が横川先輩なのだろう。
「はいはい、入部希望者以外は帰ってねー!」
未だに横川先輩を見て騒ぎ続ける女子生徒を、一人の女の先輩が追い返すように両腕を広げた。
何となくこの先輩に見覚えがあり、私は思わず凝視する。
(そうだ! あの時、ビラを配ってた先輩だ!)
「ん?」
私の視線に気づいたのか、先輩は首を傾げて不思議そうに見つめ返してきた。
そして、考えるように顎を手に当てた後、何かを思い出したように手をぽんっと打った。
「あぁ! 確かあなた、私が部活勧誘のビラ渡した子だよね?」
「え、私のことを覚えてるんですか?」
「もちろんだよー! 見学に来てくれたんでしょ? ささ、そんなとこに突っ立ってないで中に入って」
先輩は、私の腕を引っ張り、部室の中に入れてくれた。それに続いて、他の見学者の子たちも続々と部室に入ってくる。
さすがに、部室前にいた全員が見学希望者というわけではなかったが、それでも結構な人数だった。
「あ、自己紹介が遅れちゃったね。私、部長の斜森琴美です。よろしくね」
「縦山明日香です……!」
「自由に見学していいからね! あと、もし書道を体験してみたかったら遠慮なく言ってね」
そう言って、斜森先輩は他の見学希望者のもとへと走っていった。
(書道部って寡黙な人が多いイメージがあったけど、あんなに明るくて優しい先輩もいるんだな)
斜森先輩を微笑みながら見つめつつ、私はある人物に視線を移した。
それは、今も集中して半紙と向き合っている横川先輩だ。
正座をして、筆についた余分な墨を取っているだけなのに、かなり絵になる。
「何?」
ふと、横川先輩が横目で私のことをチラリと見つめた。
さすがに凝視しすぎてしまったみたいだ。
「あ、えっと、見学に来ました。縦山明日香といいます」
「ふーん、そう」
横川先輩はあまり興味が無さそうに返事をしたあと、再び半紙へと視線を戻した。
なんとなく、彼から静かな怒りを感じる……。
「すみません、お邪魔してしまって……」
私は、横川先輩に向かって深々と頭を下げた。
誰だって集中しているところを邪魔されるのは嫌なはず。
「別に。騒がれないだけマシ」
横川先輩は、今度は部室の入り口に視線を向けた。
「あれ、横川先輩こっち見てない?」
「きゃーっ! 横川先輩と目が合っちゃった!」
そんな横川ガールズたちは、愛しの人から鬱陶しがられているとはつゆ知らず。
彼女たちの様子を見て、横川先輩は深く溜め息をついた。
(多分、私のことも鬱陶しく思ってるよね)
そう思った私は、横川先輩と距離を取った。
なるべく彼を見ないように、他の先輩たちの作品に目を向ける。
しかし、やはり気になってしまう。見ないようにと思うほど、どんどん気になっていく。
私は作品を見つつも、横川先輩の様子をちらちらと見始めた。
(見ないようにって決めたのに……!)
意思が弱すぎる自分を情けなく思いつつ、彼の書く字を見る。
その瞬間、見ないようになんていう思いはどこかへと消え去ってしまった。
「わぁ……!」
ビラでも書かれていた字と同じく、力強く、それでいてしなやかな字。
上手いか下手かで表すなら、もちろん超がつくほど上手い。でも、それだけじゃ横川先輩の字を表現するのには物足りない。
いつの間にか、横川先輩が書く一文字一文字に目を奪われていた。
「……あのさ」
横川先輩の動きが突然止まった。誰かに話しかけているようだ。
彼が振り向いたことで、後ろにいる私と目がばっちり合う。
(もしかして、私に話しかけてる……?)
周りをきょろきょろと見渡しても、横川先輩の視線の先に立っているのは私しかいない。
「わ、私ですか?」
確認のために自分を指差す。横川先輩はゆっくりと頷いた。
「見たいなら見ればいい。覗くように見られると逆に気が散る」
こっそり見ていたはずなのに、完全にばれていたことに私は恥ずかしくなる。
「は、はい。じゃあ、お言葉に甘えて……」
恐る恐る、横川先輩の真横に座る。
本当に邪魔に思われていないか、少し心配だった。
横川先輩は、再び字を書き始めた。筆で半紙を撫でる音がとても心地よく聞こえてくる。
(お手本も何もないのに、どうしてこんなに綺麗に書けるんだろう)
横川先輩の動きの一つ一つを見逃さないように、私は目を凝らす。
しかし、なぜか彼の動きはぴたりと止まってしまった。
不思議に思って顔を上げると、横川先輩が私を見つめていることに気づく。
「お前……」
「あ……! じっと見すぎちゃいましたか!?」
『見ればいい』と言われたものの、見すぎたらやりにくいのは当然のこと。
そんなことにも気がつかなかった自分を殴ってやりたかった。
しかし、横川先輩は首を振る。
「いや、そんな興味津々に見られたのは初めてだったから少し驚いた。気にしないでくれ」
横川先輩の言葉にほっとした。
それでも、あまり凝視しすぎないようにしようと自分に言い聞かせる。
しかし、頭ではそう思っていても、目はずっと横川先輩の動きを追ってしまっていた。
もっと、書道のことを知りたい。その一心だった。
……後日。
ついに部活の仮入部の日がやってきた。
仮入部の申請届けを手に、私は目的の場所へと向かう。もちろん、書道部の部室へ。
「失礼しまーす……」
緊張でドキドキと高鳴る胸を押さえつつ、書道部の部室のドアを開ける。
「あ、明日香ちゃんだよね! 嬉しいな、また来てくれたんだ」
ドアを開けると、私の存在に気づいた斜森先輩が手を振って走り寄ってきてくれた。
「あの、これ仮入部の……」
「申請届けね! おっけー!」
私の手から用紙を受け取ると、斜森先輩はにこにこと微笑む。
「書道部へようこそ! さ、中に入って」
斜森先輩は、また前のように私の腕を引っ張って部室の中に入れてくれた。
中に入ると、部活見学のときに知り合った人が数名ほどいた。
見学者はけっこう多かったのに、仮入部希望者は思っていたよりも少ないことに驚く。
「もしかして、『仮入部の人数が思ってたよりも少ないな』なんて思ってる?」
「え……!?」
図星をつかれ、思わず動揺する。
そんな私を見て、斜森先輩はおかしそうに笑った。
「あはは! 明日香ちゃんって分かりやすいね」
「すみません……」
「謝らなくていいよ。少ないのは事実だし」
斜森先輩は一頻り笑ったあと、なぜか横川先輩のほうに目を向けた。
「実は、横川君がほとんどの仮入部者を追い払っちゃってさ。まぁ、去年もこうだったんだけど」
「え……、横川先輩が?」
正直、そんなことをする人には見えなかった。
昨日、じっと見つめていても鬱陶しがられなかったことを思い出し、少し意外に思う。
(だから、こんなに人数が少なかったんだ……)
「仮入部者のほとんどが書道じゃなくて横川くん目当てでさ。それで怒っちゃったみたいなんだよね」
私は、斜森先輩の言葉を聞いて、部活見学の日のことを思い出した。
確かに、近くには寄らずに遠まきから横川くんのことばかり見ていた女の子もいた気がする。
「でも、私も横川先輩のことばかり見てました……」
「明日香ちゃんは、横川くんの字に興味を持ってたでしょ? 多分、それが……」
斜森先輩の言葉が途切れる。彼女は、私の後ろを口をあけたまま見つめていた。
まるで、『まずい』とでもいいたげな表情だった。私も勇気を振り絞り、ゆっくりと振り向く。
「余計な話、しなくていいから」
そこには、私と斜森先輩を見据える横川先輩がいた。
無表情だが、何となく圧を感じるのは気のせいだろうか……。
「いつまでも話してないで、準備して」
「はいはい、分かりましたよーっと。行こう、明日香ちゃん」
口を尖らせ、斜森先輩は私に手招きをする。
「明日香ちゃんは、この場所で書いてね」
「はい!」
斜森先輩は、空いている場所の一つを指差す。
私は元気よく頷き、指定された場所に座った。座っただけなのに、また緊張してくる。
「本格的に入部することになったら、道具を買うことになってるんだ。それまで、部室にある道具を貸すね」
「はい、ありがとうございます!」
斜森先輩から書道で使う道具を受け取る。ほんの少し、墨の香りが鼻をかすめた。
(書道の道具、見るの久しぶりだな)
書道の授業のときしかみたことがない道具。それぞれの名称は、授業のときに教えてもらった気がするが完全に忘れてしまった。
あの時から……、もっと早くから書道に興味を持っていればよかったと後悔するが、時すでに遅し。
「じゃあ、仮入部の人はこのお手本を真似して書いてもらおうかな」
そう言って、斜森先輩は私を含めた仮入部者の全員に一枚ずつ紙を配る。
その紙には『万里一空』と書かれていた。
(四字熟語かな? あとで意味を調べてみよう)
「分からないことがあったら呼んでね。すぐに駆けつけるから!」
斜森先輩の言葉に頷き、周りの仮入部者たちは道具の準備をし始める。
私も急いで準備に取り掛かった。
「えっと、これに墨を入れて……、半紙の下にはこれを引いて……」
準備の仕方は、中学で書道の授業をやっていたこともあり、案外テキパキと準備することができた。
(よし、早速書くぞ……!)
正座をして、姿勢を正す。少しだけ、筆を持つ手が震えた。
墨はどれぐらい取ればいいんだろう。どれぐらいの力強さで書けばいいんだろう。
質問したいけれど、なかなか一つにまとまらない。ぐだぐだと悩んでいるせいで、未だに一枚も書けていなかった。
「……っ!」
次の瞬間、妙な足の痺れに気がつく。
始めはぴりぴりとしていた感覚が、強い電流が流れてきたかのような感覚になる。
「明日香ちゃん、どうしたの?」
私の異変に気がついた斜森先輩が、心配そうな表情で駆け寄ってくる。
「すみません、足が痺れちゃったみたいで……」
「そうなの? じゃあ、姿勢を崩して……」
そう言って、斜森先輩は私を支えてくれた。
正座をやめて足を伸ばすと、だんだんとその痺れはなくなっていった。
「痺れがなくなるまで休憩してていいからね」
「はい……」
斜森先輩は優しく言ってくれたが、私は情けない気持ちでいっぱいだった。
「……」
ちらりと、横川先輩のほうへ視線を向ける。
偶然にも、彼とばっちり目が合ってしまった。
(足の痺れのせいで集中できなくて字も書けないなんて、もしかしたら書道に向いてないのかもしれない)
悔しさで、私は横川先輩から目を逸らしてしまった。
4
部活は終わり、部員がぞろぞろと道具を片付け、帰りの支度を始めていた。
「あれ、明日香ちゃんは帰らないの?」
斜森先輩が、未だに道具を片付けようとしない私を見て不思議そうに首を傾げた。
「あの……」
足の痺れのせいで、他の人たちよりも字を書くことができなかった。
しかも、私は正座をするとすぐに足が痺れてしまうみたいだった。
私は、目の前にある真っ白なままの半紙を見つめる。
「もう少しだけ、部室に残っていても大丈夫ですか?」
斜森先輩は、私の言葉に目を丸くしたあと、優しい笑顔で頷いてくれた。
「まだ下校時間まで時間あるし、いいよ。その代わり、部室の鍵をお願いしてもいいかな? 帰りに職員室に返しに行くだけだから」
「はい、分かりました!」
「じゃあ、私は用事があるから先に帰るね! 戸締りよろしくね」
そう言って、斜森先輩は私に手を振りながら部室を出て行った。
彼女の後ろ姿を見送り、私は再び書道の道具に目を向ける。
「まずは、正座に慣れないと……」
集中力を保つには、足を痺れさせないようにしないといけない。
しかし、足を痺れさせない正座なんてできるのだろうか。正直、全く想像がつかなかった。
「はぁ……」
深く溜め息をつきながら、斜森先輩からもらったお手本の字を見つめる。
「万里一空……」
この文字の意味が分からなかった私は、その文字を調べてみることにした。
「目的、目標、やるべきことを見失わずに励む、頑張り続けること……」
私は、その部分に目が釘付けになる。
(何を落ち込んでたんだろう、私……)
足が痺れることぐらい、誰にだってある。
集中力が切れてしまうのは、きっと私の心が弱いせいだ。
(足の痺れに負けないように、頑張り続ければいい!)
私はグッと拳を握り締め、気合いを入れる。
「よーし、頑張るぞ!」
「まだ残ってたのか」
「わぁぁぁっ!?」
突然、背後から声が聞こえ、素っ頓狂な声をあげてしまう。
急いで振り向くと、そこには横川先輩が立っていた。
「よ、横川先輩! なぜここに!?」
「それはこっちの台詞だ。お前のほうこそ、なんでまだ部室にいるんだ」
「それは……」
正座に慣れるためと言ったら、横川先輩に呆れられるかもしれない。
(もしかしたら、正座すらろくにできない奴は書道部にいらない、とか言われちゃったり!?)
変な妄想が、頭の中をぐるぐると駆け巡った。
まだ何も言われてないのに、一人で勝手に落ち込む。
「正座」
「え……?」
「いいから、早く正座してみろ」
横川先輩の言うとおりに、崩していた姿勢を正して正座をする。
端から見たら、まるで横川先輩に説教されているような状態だ。
「縦山は、かかとに全体重をかけてるからダメなんだ。それだと、すぐに足が痺れるに決まってる」
「かかと……」
意識したことはなかったが、確かに指摘されるとかかとに体重がかかっているせいで、足の甲が痛く感じる。
「膝とかかとを少し開いてみろ。無理に開きすぎないようにな」
「はい!」
横川先輩の言われるがままに、姿勢を変えていくと足の甲の痛みが消える。
「たまに重心を移動させると痺れにくくなる。覚えておけ」
「は、はい! ありがとうございます!」
横川先輩にお礼を言いつつ、ブレザーのポケットに入っていたメモ帳を取り出し、先ほど教えてもらったことをすぐメモに取った。
しかし、私には一つだけ疑問に思うことがあった。
「あの、どうして正座のやり方を教えてくれたんですか?」
もしかして、正座で悩んでいることを気づかないうちに話題に出してしまったのか。
思い出す限り、そんな話を横川先輩にした覚えはなかった。
「別に、なんとなく教えただけだ」
「そうだったんですね」
横川先輩が正座のやり方を教えてくれたのは、ただの偶然だったようだ。
それでも、私にとってとてもありがたいことだった。
「実は、正座ができなかったら入部すらできないんじゃないかって思っちゃって……」
「入部ができない? ……ぷっ、あはは!」
私の言葉を聞いた瞬間、横川先輩はお腹を抱えて笑い始めた。
今まで無表情だった彼の、無邪気な笑顔に思わず見惚れてしまう。
「いや、すまない。入部ができないなんてことはないから安心してくれ」
横川先輩は、笑いすぎたのかうっすら涙を浮かべていた。
「縦山は、書道の世界に興味を持ってくれた。その気持ちはちゃんと伝わっている」
「ほ、本当ですか?」
「ああ」
完全に邪魔をしてしまったと思っていたが、そう思われていないようで安心する。
私はほっと胸を撫で下ろした。
「横川先輩の字に、一瞬で心を奪われてしまったんです」
「そうなのか……?」
「はい、こんなにも人を魅了できる字を書けるなんてすごいなって。そこから書道に興味を持ったんです」
初めて横川先輩の字を見たときの気持ちを、今でも覚えている。
まだ気が早いかもしれないけれど、私も誰かを魅了できる字を書いてみたい。そう思った。
「そういえば、横川先輩はいつから書道を始めたんですか?」
「中学二年生ぐらいからかな」
「けっこう最近なんですね! もっと幼い頃からやっているのかと……」
勝手なイメージだったが、私はそう思い込んでしまっていた。
「小学生の頃から習字はやっていたんだ。でも、このときは母親に無理やり習わされていたから、あまり好きではなかった」
横川先輩は、正座をしている私の隣に腰を下ろす。
昔を懐かしむような、そんな表情をしていた。
「誰かに指示されて字を書くのは楽しくなかった。絶対にすぐにやめてやるって思ったりもしたよ」
「え、そうなんですか!?」
私は、小さい頃の横川先輩を思い浮かべる。彼がそんなことを思うなんて意外だった。
「だけど中学二年生になって、書道を体験する機会があったんだ。そのときに、自分の思うままに字を書けるのってすごく楽しいことなんだって気がついた」
横川先輩は、部室に飾ってある作品や書道の道具を見て、嬉しそうな表情をしていた。
本当に、心の底から書道が好きなんだと感じられる。
そんな横川先輩を見て、私も思わず嬉しくなって微笑んだ。
「私は、そんな横川先輩が書く字に感動して、書道に興味を持ちました」
「俺の字に……?」
「はい、このビラに書かれている『青翔』って文字に感動して……!」
私は、ブレザーのポケットから書道部の部活勧誘のビラを取り出す。
「あぁ、これか」
「今までは、感動したことはあっても心の中で『すごい』と思うだけで終わってたんです。だけど、この字を見て、初めて自分もやってみたいって思いました」
「そうだったのか」
興奮気味に話しすぎてしまったような気がして恥ずかしくなる。
しかし、横川先輩は少し嬉しそうに微笑んでいた。
「縦山が書道に興味を持つきっかけになれてよかったよ」
横川先輩が優しく微笑んでくれるたびに、ちょっとだけ鼓動が早くなっている気がする。
顔もちょっとだけ熱い。横川先輩の笑顔の破壊力、恐るべし。
「……さてと、結構話し込んでしまったな」
その後も、横川先輩と他愛もない会話をして、気がつけば外は真っ暗になっていた。
部室の時計を確認すると、針は下校時間に近付いてきている。
「そろそろ帰ろう。練習の邪魔をして悪かったな」
「いえ! 横川先輩のお話を聞けて嬉しかったです」
そう言って、立ち上がろうとすると足に違和感を覚える。
この感じは、なんだか嫌な予感がした。
「いたた……」
その違和感が、だんだん痛みへと変わってくる。
私の足は完全に痺れていた。
助けを求めようと、私は横川先輩に視線を向ける。
「よ、横川先輩……。すみません、足が痺れちゃったんですけど……」
「俺は、足が痺れにくくなる方法を教えただけだ。痺れないとは言ってない」
今思い返せば、確かにそうだった。
横川先輩の教え通りに座っていれば、絶対に痺れないものだと勘違いしていた。
「そ、そりゃそうですよね……」
なんてバカなんだろうと、自分を笑いたくなる。
「ふっ、あはは……!」
そんな私よりも先に笑ったのは、横川先輩だった。
普段のクールな表情を崩して、また無邪気に笑う。
「本当にお前は、単純というか素直というか……。見てて面白いな」
横川先輩は、瞳に溜まった涙を拭った。
……その動作すらも絵になる。
「道具の片付けは俺がやるから、お前は治るまでゆっくり休んでおけ」
「は、はい……」
手馴れた動作で道具を片付け始める横川先輩。
動くたびに揺れるサラサラの黒髪に思わず目を奪われる。
「片付け終わったぞ。足はどうだ」
「え、いつの間に!」
私が見惚れている間に、道具は綺麗に片付けられていたようだ。
しかし、私の足は未だに痺れたままだった。
そんな私の表情を見て悟ってくれたのか、横川先輩は私に向けて手を差し出す。
「ほら、支えてやるから」
横川先輩は、私の手を掴んで優しく引いてくれた。
(えええええっ!?)
突然の距離の近さに、私の頭の中は完全にパニックを起こしていた。
「お前のカバン、持っても大丈夫か?」
「そんな! 悪いですよ!」
「気にしなくていい」
横川先輩は、私のカバンを持ち上げて、そのまま私のことも支えてくれる。
まるで、お姫様にでもなった気分だ。
「ごめんなさい、歩くの遅いですよね」
「痺れてるんだから当たり前だろ。俺だってそうなる」
「え、横川先輩も足が痺れるんですか!?」
私がそう言うと、横川先輩は一回きょとんと目を丸くしたあと、くすくすと笑い始める。
「お前は、俺を何だと思ってるんだ」
「なんというか、そんなイメージがなかったので……」
「まぁ、顔に出さないようにしてるから」
こんな痺れも耐え切る横川先輩は、やはりさすがだと思った。
「正座は慣れも必要だ。もし痺れたとしても、少しは我慢できるようにしないとな」
「そうですよね。正座、頑張ります!」
ぐっと拳を握り、私は気合いを入れる。
「縦山なら、大丈夫そうな気がするけどな」
「本当ですか?」
横川先輩と話していくうちに、だんだんと足の痺れも薄れていき、痛みもなくなる。
……だけど、まだ横川先輩の手を離したくない。そんな気持ちがあった。
「足の痺れはどうだ?」
「……まだ、痺れてます」
「そうか」
嘘をついてしまったことに、少しだけちくりと胸が痛む。
(横川先輩、ごめんなさい……!)
心の中で横川先輩に謝りつつ、私は足が痺れているフリを続けた。
ドキドキと高鳴る胸を押さえ、私は横川先輩の横顔をちらちらと見つめていた。
5
……次の日。
「明日香ちゃん!」
「斜森先輩!」
部室に入ると、斜森先輩が私のもとに走り寄ってくる。
斜森先輩の笑顔を見ていると、私もついつい頬が緩んでしまう。
「そこ、通行の邪魔になるぞ」
「あ、横川くん。ごめんごめん」
私と斜森先輩の横を、横川先輩が通っていく。
「よ、横川先輩。こんにちは」
横川先輩に話しかけようとすると、緊張してしまう。
頬も少し熱くなっていた。
「こんにちは」
横川先輩は、優しい口調で挨拶を返してくれる。
それだけなのに、飛び跳ねて喜びたいくらいの衝動に駆られた。
「ねぇねぇ、昨日は二人で何してたの~?」
斜森先輩は、私と横川先輩を交互に見つめてにやにやしている。
その言葉を聞いて、私は一つ疑問に思うことがあった。
「どうして横川先輩と一緒にいたことを知ってるんですか?」
私が質問すると、斜森先輩はなぜか横川先輩を見て再びにやにやしていた。
反対に、横川先輩は斜森先輩を睨んでいた。
「ふっふっふ。それはねぇ、横川くんが……痛いっ!」
話し出そうとする斜森先輩を止めるために、横川先輩は彼女の頭にチョップを入れる。
斜森先輩は、痛そうに頭を抱えていた。
「斜森、余計なことを言うな。さっさと部活を始めるぞ」
「はいはい、言わないってば~」
斜森先輩は、拗ねたように口を尖らせていた。
そんな斜森先輩を無視して、横川先輩は道具の準備をし始める。
彼の頬が少し赤く染まっていたように見えたのは、私の気のせいだろうか。
「なーんて、私が秘密にすると思ったら大間違いよ。明日香ちゃん、耳貸して」
斜森先輩に手招きをされ、私は素直に応じる。
「はい、なんですか?」
斜森先輩に耳を向けると、彼女は手を添えながら私の耳に近付いてきた。
「実は昨日、横川君は明日香ちゃんのことを探してたの。それで、私に明日香ちゃんの居場所を聞いてきたんだ」
「え、私を……?」
「そう。明日香ちゃんが元気ないように見えて心配してたみたい」
斜森先輩の話を聞いて、私は昨日のことを思い出した。
確かにあの時は、足の痺れに負けて一枚も作品を書くことができなかった自分を情けないと思っていた。
(横川先輩、気づいてくれてたんだ……)
「横川くん、明日香ちゃんのことかなり気に入ってるみたいだよ」
「えええっ!?」
予想外の言葉に、私の顔は湯気が出るんじゃないかと思うくらい熱くなっていた。
斜森先輩は、そんな私を見て再びにやにやしていた。
「明日香ちゃんのその反応、まさか横川くんのこと……」
最後まで言われなくても、斜森先輩が言いたいことは分かった。
恥ずかしさで俯きながらも、私はゆっくりと頷く。
「うんうん、青春って感じで甘酸っぱいね! 若いっていいなぁ~」
「斜森先輩、私と二つしか変わらないじゃないですか」
「二つは十分変わるよ!」
斜森先輩は、腰に手を当てて怒ったような表情をする。
だけど、可愛さのほうが勝っていて全く怖くはなかった。
「横川くんもね、明日香ちゃんの話をすると……」
「斜森」
「……」
いきなり名前を呼ばれ、斜森先輩の動きが凍りついたように固まる。
表情も引きつっていた。
「部活を始めるぞって言ったよな?」
「言いました……」
「部長のお前がいつまでも喋ってていいのか?」
「ダメでした……」
部長は部長でも、横川先輩のほうが斜森先輩より立場が上のように見える。
斜森先輩は、そそくさと道具の準備を始めた。
「縦山も早く準備しろよ」
「は、はい!」
そう言って戻ろうとする横川先輩だった。
しかし、なぜか動きを止めてこちらを振り返る。
「おしゃべりな斜森に言われる前に、自分の言葉で伝えておく」
横川先輩が私に近付いてくる。
思わず後ずさりをしてしまいそうになったが、その前に横川先輩が私の耳に顔を近づけた。
「俺は、字を見ているときのお前のきらきらした目が好きだ」
「え……」
「初めて見たときから、お前のその目に見惚れてた」
横川先輩は、顔を離し、私を見据える。
私は彼の真っ直ぐな瞳から目を逸らせないでいた。
「昨日、元気がなかったように見えたから、もしかしたら部活をやめてしまうんじゃないかって思って焦った」
横川先輩はそう言ったあと、安心したように穏やかな微笑みを浮かべる。
「正座に慣れるように、これからも練習頑張れよ」
「……はい!」
私の返事に、横川先輩は満足げに頷いてくれた。
私も準備に取り掛かろうと、道具に手をかける。
しかし、私の心臓は飛び出るんじゃないかと思うくらいに大きく音を立てていた。
(びっくりした……)
横川先輩の真っ直ぐな言葉を思い出し、さらに顔が熱くなっていく。
(でも、横川先輩は私じゃなくて、『私の目』が好きって言ってくれてたんだよね)
ほんのちょっとだけ残念だったけど、それでも『好き』って言ってくれたことは素直に嬉しかった。
道具の準備を終えた私は、文鎮で丁寧に半紙を伸ばして姿勢を正す。
横川先輩から教わった正座のやり方。前よりも、集中して半紙に向き合うことができた。
「よし……」
自分に気合いを入れるように。でも、みんなに声が聞こえないように小さな声を出す。
筆を取って、墨を付け始めた。ゆっくりと、筆が半紙をなぞって墨が滲んでいく。
初めて書けた『万里一空』は、我ながらなかなかの出来だと思った。
この文字の意味のように、やるべきことを見失わずに励み、頑張り続ける。
そして、あわよくば横川先輩に目だけじゃなくて、私自身のことも好きになってもらえるように。
そうなるには、まだまだ先は遠いと思う。でも、諦めないで頑張ると、私は心の中で誓った。
「お前の初めての作品は書けたか?」
「横川先輩……」
私が字を書けたことに気がついたのか、横川先輩が様子を見に来てくれていた。
ちょっとだけ恥ずかしいけれど、私は作品を横川先輩に見せる。
「まだまだバランス的に問題があるところが多いが、お前の気持ちがこの文字から感じられる。初めてにしてはいい作品だ」
「ありがとうございます!」
ふと横川先輩を見ると、彼は私の足元を見つめていた。
「足、痺れてないのか?」
「はい! 横川先輩のアドバイス通りにやったら、前よりも全然痺れなくなりました」
「そうか、それはよかった。その調子で続けるようにな」
横川先輩の言葉に頷き、再び半紙を見つめる。
深く息を吐いたあと、私は筆に墨を付ける。
私の気持ちを文字に表現できるように、私は再び筆を半紙に滑らせていった。








