[98]正座の神官、真城
 タイトル:正座の神官、真城
タイトル:正座の神官、真城
分類:電子書籍
発売日:2020/08/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
近江の小さな村に、最近、馬を襲う妖怪が出没して、村人や旅人を困らせていた。妖怪は瑠璃色の小馬に乗って緋色の着物を着た少女の姿で、馬の皮商いの娘が化身したものだという噂だ。
妖怪退治に呼ばれたのは、京の馬神神社の神官、真城(ましろ)。舞楽にも秀でた美しい青年である。近江の庄屋の娘チグサは村人に正式な正座を教えて迎える。
幼なじみのルリが妖怪馬魔(ギバ)の正体ではないかという。ルリは貧しい小屋で父親とふたり暮らしをしていて、真城を拒絶する。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/2262091

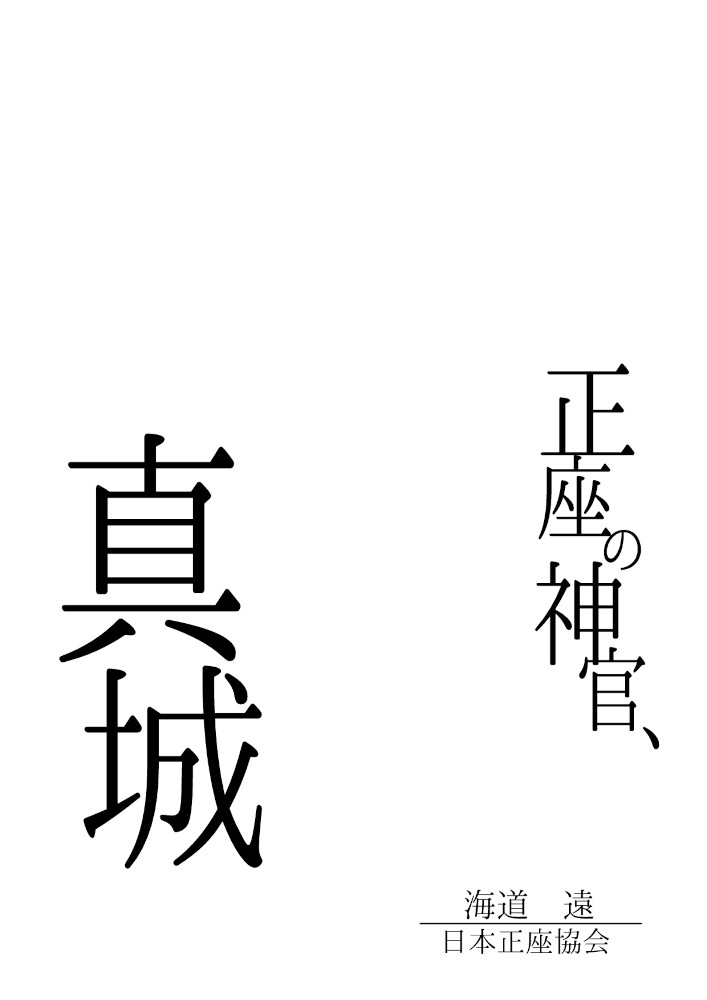
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 白き神官
京の都の東山に馬神神社という小さな社がある。
緑濃い五月、今日は神社の祭りだ。縁日の店が境内や参道に並び、風車や大根の煮物や、着物のはぎれや、いろんな物を売っていて、沢山の人出でにぎわっている。
「ルリちゃん、こっち来てごらんよ、ヒヨコを売ってるよ」
「待って、チグサちゃん。あたい、こんなつるつるの着物や高い下駄をはいたことがなくて走りにくいのよ」
「でも、牡丹の柄の着物よく似合ってるわよ」
「そう? 貸してくれてありがとうね、チグサちゃん」
日頃、親の手伝いでくたびれた絣の着物しか着たことのないルリも、今日は嬉しそうだ。チグサの家は庄屋で、おつきの女中までいる。ふたりとも女中に髪を結ってもらって今日はすっかりおしゃれだ。
「ルリちゃん、これ、私から花かんざしを贈り物にさせて」
「え、着物を貸してもらってるだけで十分よ」
「ルリちゃんは、庄屋の娘だからって、近寄ってこない他の子供と違う。私と仲良くしてくれるから、そのお礼よ」
チグサがルリの髪に桃色の花かんざしを挿すと、大きな瞳の顔によく映った。
「それに、今日の縁日には、真城さまがお出ましになるのよ。おめかししなくちゃ」
「真城さまって?」
「この馬神神社の宮司のお跡継ぎよ。それはそれは、とても美しい青年だそうよ」
「チグサちゃんたら」
ふたりとも、そんなことが気になる十四歳だ。庄屋の娘と貧しい家の娘だが、もっと幼い頃から仲が良かった。
宮司の跡継ぎの真城という青年は、村の者たちにも慕われているようで、今日は縁日だからということで純白の装束で舞を奉納するというのだ。
チグサとルリは、人混みにもみくちゃにされながら、ドキドキして待っていた。お付きの女中が見失ってどこかで叫んでいる。
馬神神社は、荷物を運ぶ馬や武士の乗る馬の守り神様として、人々からあがめられている。
宮司の祝詞を読む声が終わると、境内の小さな舞台で、舞楽器の雅な音色が響き始めた。笙の笛やしちりき、太鼓など。
「やってこられるよ。みんな、正座してお出迎えするんだよ」
誰かが叫ぶ。
チグサが父親の命令で村人に正式な正座を教えることになった。
真っ赤になりながらチグサは村人の前に出た。
「皆さん、真っ直ぐ立ってかかとの上に座って下さい。着物の裾は、膝の内側に折りこんで。そうです。そして両手は揃えて膝の上に静かに置いて下さい」
村人は、どうにか歪まず正座ができた。
「はい、そして頭を深くゆっくり下げてお迎えして下さい」
チグサがホッとした時、神官の真城が純白の狩衣で本殿へお出ましになった。
皆は一斉に玉砂利の上に正座して真城を迎えた。
「あの方が真城さま。なんて清々しい神官さまなんでしょう」
「チグサちゃんたら、顔が赤いわよ」
「ルリちゃんだって」
「あの透き通るような頬に濃い睫毛! 白鷺より美しい袂の白さ!」
真城は、ゆるりと優雅に金色の扇を広げ、舞台の上をひと巡りして舞いはじめた。
優雅で上品なこと。目も綾な顔立ちのせいもあろうが、民たちは誠に神様に浄められる気分を味わっていた。
その時、
「お嬢様、今、村から使いが参りまして」
チグサのお付きの女中が人混みをかき分けてやってきた。
「どうしたの?」
「ルリさんのお母さまのお具合がよくないそうです」
「おっかさんが!」
聞くなり、ルリは人混みから抜け出した。
第 二 章 妖しの出現
それから半年――、夏も過ぎ、秋も過ぎ、冬支度を始める頃となった。
琵琶湖の南、刈り取られた稲の並ぶ街道を白い馬に乗った若い神官が、ふたりの共を連れて道を急いでいた。その顔はきつく緊張しており、鼻梁の高い美貌がよけい際立っている。
漆黒の高烏帽子を被り純白の狩衣を身につけ、下は濃い紫に紫の花紋が入った袴。高貴の神官の身分を示す。
やがて、彼方に琵琶湖が陽に照らされてキラキラ輝く様を遠くに臨むことができる小さな村に到着した。
村は全体的に活気がない。大人たちはがっくり肩を落として歩き、子どもたちも痩せて眼だけぎらぎらさせている。きっと最近、馬が突然、何者かに襲われて急死する事件が起こっているせいだろう。
村の入り口で中年の男が待ち受けていた。
「これは、馬神神社のご神官様。京よりはるばる、ようこそお越しくださいました」
「庄屋どのか。我は馬神神社の神官の真城と申す。して、詳しく話を聞かせてほしい」
真城は、庄屋の家へ案内された。
大きな黒い梁がめぐらされた屋敷で、他の農民の家より何倍も大きい。しかし、下男も女中の顔も沈痛な面持ちである。
「他でもございません。この辺りを通る馬が突然、いななき暴れて倒れてしまうのです。ここ半年ばかりの間に何度もです。それで、商人もこの村に近づくのを嫌がるようになりました。このままでは、村は衰えるばかりです」
庄屋は肩を落として言った。
「それで私をお呼びになったのですな」
神官は、静かに庄屋の話を聞いていた。
「妖しを見た者が何人かおります。空が曇り生暖かい風がどこかから吹いてきて、空に瑠璃色の小馬が現れ、緋色の衣を着た少女が乗っていると。少女の合図で瑠璃色の小馬が馬に憑りつき、あっという間に馬は息が絶えてしまうと」
「庄屋、それは、話に聞く妖怪馬魔であるな。確か少女の正体は、馬の皮商いを稼業としている家の娘だとか」
「よほど世間に怨みがあるのでしょうな。なんとか神官様のお力でギバを追いはらっていただくことはできませんでしょうか?」
空を睨んで神官が考えを巡らせた。
その時、座敷に茶を運んできた十四、五歳の少女がお茶を置いてからも、なかなか立ち去ろうとしない。
「神官さま!」
いきなり駆け寄り、真城の膝元に椿柄の真っ赤な膝で正座して、愛らしく結った頭を下げた。
「庄屋の娘、チグサと申します! 実は、私、ギバという妖怪に心当たりがあるのです」
「むむ?」
「これ、チグサ、いい加減なことを申すでない」
庄屋の父親がたしなめたが、少女は構わず続けた。
「いいえ。間違いありません。ギバという妖しになってしまったのは、幼なじみのルリちゃんだと思います」
「お前の幼なじみだとな」
「はい。ルリちゃんは、谷に住む貧しいおうちの子ですが、とっても良い子です。私のたったひとりの大切なお友達です」
「これ、チグサ。あの子とは身分が違いすぎるから遊ぶでない、とあれほど申したではないか」
父親に怒られても、チグサは必死だ。
「ルリちゃんのお母さんが病で半年前、亡くなったのです。貧しくてお医者さまに診ていただくことも、薬を飲むこともできないまま……。その頃からです。ルリちゃんの様子がおかしくなって、村で馬が突然、倒れるようになったのは」
「ふうむ」
真城は眉間のしわを深くして考えこんだ。
第 三 章 ルリの家
宿になる別棟へ移る時である。共の者が真城の馬を厩に連れて行こうとしていた。
急に馬が高くいなないた。
初冬だというのに、なんとも生暖かい風が空から吹いてくる。
ふと、曇り空を見上げると瑠璃色の小馬に乗った緋色の衣の少女の姿がある。
「おのれ、妖しっ」
空を睨みつけている間に、瑠璃色の小馬が真城の馬の首にしがみつき、馬は暴れて三回、きりきり舞いした。そして悲しげにいなないてドウッと地面に倒れた。
「白山!」
真城が馬の名を呼んだ時には、少女の甲高い笑いが響き、空の彼方へ飛び去った。わずかな間のことである。
「白山!」
真城が馬に駆け寄ると、まだ息がある。急いで下男に厩へ運ばせた。
「誰か、馬の医者を!」
厩の入り口で、チグサが震えて一部始終を見ていた。
「神官さま、間違いありません。あれはルリちゃんです!」
真城は愛馬の命を救おうと必死だ。
「白山、待っておれ、私が下賀茂神社に行き、妖しの恐れる剣を拝受してくるからな。妖しを倒せばきっと元気になる」
代わりの馬で出立しようとすると、庄屋の少女が、袴に取りすがった。
「お願いです、幼なじみのルリちゃんに会って下さい!」
「むむ、仕方ない、そこまで言うのなら案内せよ」
馬から下りて、少女の後をついていった。
せせらぎの音が間近に聞こえる。
足元も泥にぬかるんでいる。谷川に沿って細い道を進んでいくと、小さな集落が見えてきた。
端の一軒の小屋へ、少女は歩いていく。
小屋のかたわらには、獣の皮がたくさん干してある。イノシシ、シカ、そして……馬の皮も。
少女が小屋の入り口の筵をめくると、中はひどく薄暗い。
「頼もう。我は神官の真城と申すが誰かおらぬか」
何度か声をかけると奥の人影が動く気配がして、重い声が響いた。
「何かね、今、手が離せんのだが」
その声とは別に、チグサと同じくらいの少女が顔を出した。
とても結い髪とはいえないざんばら髪、顔は泥だか垢だかで真っ黒に汚れている。着物はつくろいだらけで、素足で草履を穿いている。
「ルリちゃん、もう馬を襲うのはやめて!」
チグサの言葉に少女は鼻で笑い、
「チグサちゃんは、生まれた時からきれいなべべ着て、白いまんまをたくさん食べられて不自由ないだろ。でも、うちは獣の皮を商うう稼業をしなきゃ生きていけないんだ。毎日、毎日、こんな仕事を誰がやりたいと思うんだい」
「……」
「朝、暗いうちから夜遅くまで働いても、病気になったおっかあを助けてやれないで、おら、もうイヤになってしまったんだ」
汚れた顔のルリが青白い視線を暗闇から射すように投げてきた。
「だからって馬を襲うのはいけないよ」
ルリはチグサと神官を睨みつけた。その眼はいつものルリではない。父親が入り口に近づいてきた。
「これが、わしらの生業なんでね、止めろと言われて『はい』とやめるわけにはいかんのさ」
ふたりの目の前の筵をバサッと下ろした。
「この父娘はギバ妖怪に憑りつかれている。まずは、剣を拝受するため、下賀茂神社へ行ってくる」
真城はチグサに言い含めて身をひるがえし、出立した。
第 四 章 馬頭観音を求めて
下賀茂神社では、真城からの知らせを受けて、宮司が妖しを倒せる剣を宝物庫から取り出して待っていた。
「真城どの」
立派なあごひげを持つ宮司が、宝刀の入った箱を差し出しながら神妙な顔をしていた。真城は恭しく正座して白い袖で箱を受け取った。箱を開けると見事な美々しい宝刀が納められている。鞘から抜いてみると、刀身に真城の眼が映る。
「ギバという妖しは、おそらく残念ながらこの宝刀だけでは倒せませぬぞ、真城どの」
「かと申して、ギバを倒してしまうわけにもいかないのです。ギバの正体の娘も貧富の差のために辛い思いをしているのです」
「神官どののお気持ちも分かるが……」
「では、どうすればよろしいのでしょうか、宮司様」
「馬頭観音の力をお借りするのじゃ」
「馬頭観音……」
「馬頭観音は馬の命と人々の幸福を願ってくれる菩薩様じゃ。きっと馬の安全のためにギバを倒すのではなく、慈悲の力を貸して下さるじゃろう」
宮司の瞳はとても誠実だ。
「ギバを倒すのではなく、救うのですな」
真城の瞳の奥にも、やる気が燃えてきた。
「宮司様。いずこの馬頭観音様におすがりすればよろしいでしょうか」
「馬頭観音は西国にも沢山、お祀りしている寺はあるが、播磨の国の寺にある像がいちばん霊験あらたかじゃ。そこへ行くがよい」
「播磨の国の寺……」
京から播磨の国へは、ひと夜泊まればすぐに着ける。真城は宝刀を背にくくりつけ、馬を飛ばした。
第 五 章 煩悩を食べて救う観音
寺にたどり着いたのは、あくる朝の夜明けだった。
すでに下賀茂神社からの伝令を受け、真城を迎えるために準備がなされていた。
住職が御影堂で待ち受けていた。
「これは、ご住職。急なお願いをきいて下さりお礼を申します」
白髪の住職は真城を迎え、
「拙僧どもに手伝えることがあれば、なんでもお手伝いしよう。とりあえず、馬頭観音様とご対面していただこう」
寺の奥へ案内した。
そこには、銅で作られた、巨大な馬頭観音像が飛翔する馬に乗った姿で立っていた。大きさに真城は驚いた。身長は人の三~四倍はあろうか。顔は三面、左右の腕は四本ずつ、それぞれに刀や斧など武器を持っている。怒りに燃えた顔は真城も恐怖を覚えるほどだ。
「慈悲深いと聞きましたが、どうして観音様はこのように恐ろしい形相なのでしょう」
「人の幸せをお守り下さる観音菩薩じゃが、馬を害するものを威嚇するために怒りの形相をしておられる。怒りの激しさによって煩悩を取りのぞいて下さるのじゃ」
「煩悩を取りのぞいて……」
繰り返しながら、真城は馬頭観音を仰いだ。
「家畜の安全と健康を祈ったり、旅の道中を守る観音様としても、馬を供養する仏としても信仰されている。また、人差し指と薬指を伸ばして中指を折る馬口印を結んでいる」
「……」
「馬頭観音の真言は『オン・アミリトドバン・ウン・パッタ・ソワカ』という。今度、ギバが襲来する時は、馬口印を結びながらそのように唱えて戦うがよい。そのギバと申す妖しは人間の煩悩が産んだものじゃ」
住職は重々しく説明した。
(私は、あの少女の煩悩を取りのぞくことができるのだろうか。そして、少女を馬頭観音の御前でお詫びの正座をさせることができるのだろうか)
真城に絶対の自信があるわけではない。
馬頭観音のぎょろりとする眼のなんと大きいことか。
ルリを救うには、馬頭観音の御前でお詫びの正座をさせるしか方法はない。
第 六 章 ギバの襲来
低い風の音が響いてきて、獣の息のようなつむじ風が起こった。
空が曇り、天空から瑠璃色の小馬に乗った少女が駆け下ってくる。
「ギバが来た! 私の後を追って?」
真城が僧侶たちとうろたえてるうちにつむじ風が強くなってきた。目も開けていられない。恐ろしい強風だ。
風に耐えかねた馬頭観音像がぐらりと傾き、轟音を立てて倒れた。もうもうと土煙が立つ。
周りの人々は愕然とした。
「何をするっ! ルリ、眼を覚ますのだ。馬頭観音像を傷つけてはならん。お前を護って下さっているのだ」
真城が叫んだが、小馬に乗った少女は恐ろしい顔つきで身をひるがえした。真城の唇が小さく動いた。
「オン・アミリトドバン・ウン・パッタ・ソワカ」
人差し指と薬指を伸ばして中指を折り、馬口印を結んで真言を唱えながら、下賀茂神社から拝受した宝刀をスラリと抜いた。
庄屋の娘、チグサの顔が浮かんだ。ルリのことを心配する表情が。
(チグサ、安心せい。ルリは斬らん。妖怪のみを斬って自由にしてやる!)
真城の剣が、妖しの風を斬りつけた。
「ぎゃあっ!」
子馬の背から少女は地上へ落ちた。真城が走り寄った時には、恐ろしい形相で跳ね起きた。
「オン・アミリトドバン・ウン・パッタ・ソワカ……。少女ルリよ、目を覚ませ。お前は妖しに操られているのだ。罪のない馬を襲って地獄へやることはお前の本意ではないはずだ」
「ぐ……」
「妖しを追いはらうため、この剣を拝受してきた。殺めはせぬ」
「ぐぐ……」
「貧しさの辛さは分かる。しかし、馬主や馬方にとって馬は大切だ。その馬を突然、失ったらなんとしよう。どうか多くの罪なき馬を襲うことは止め、馬頭観音像に頭を下げてほしい。正座して誠心誠意謝るのだ。心からの正座には煩悩をなくし罪を許す寛大さが存在するのだ。きっと馬頭観音は心からの正座を感じて許して下さるだろう」
「あたいが……あたいがどんな思いで娘らしく着飾るチグサを毎日見ているか、お前なんかに分かるものか」
叫ぶなり、ルリは地上に降りてきた小馬に飛び乗って空へ駆けていく。
「よくも邪魔をしたな、神官。馬頭観音を木っ端みじんにするまで諦めぬ!」
僧侶たちの顔から血の気が引いた。
第 七 章 僧兵と神官は集まれ
真城が住職に頼んだ。
「ギバは馬頭観音をすべて砕くまで襲うと言っています。できるかぎりの僧兵を集めて下さい、ご住職」
住職はあたふたと周辺の寺や本山に書状をしたため、伝令の馬が十数頭放たれた。
僧侶たちは観音様に縄を縛りつけ、立ち上がらせる作業に入る。真城自身は自らの馬神神社から人手を呼ぶ使者を送った。
翌朝、馬神神社から若い禰宜(神職のひとつ)たちがやってきて、僧侶たちと力を合わせて、倒れた馬頭観音像や足元の馬像に縄を縛りつけた。
引き上げるために農耕馬も駆り出され、十頭ほどの馬が境内に集まった。
観音像の体に合わせて三十か所以上の縄がくくりつけられ、せーの、で馬たちを引く。馬頭観音像は少しずつ、少しずつ持ち上がり、日暮れにようやく台座に立てかけられた。
僧侶も禰宜たちも汗だくである。
「よいか、皆の者。観音像をぐるりと囲んで正座し、真言を唱え、ギバをおびき寄せるのだ」
真城が声を張り上げた。
第 八 章 ギバとの心の戦い
雲の色が血の色のように赤く染まった。夕焼でもないのに。人々はその色に不吉さを覚えた。
逞しい僧兵どもが一斉に弓矢を構えた。妖しよ、どこからでも来るがよい、とばかりに。
禍々しい赤い雲からつむじ風が起こり、寺の瓦がめくれて大量に吹き飛んでいく。頭を抱えて寺に仕える者たちが逃げていく。
「来たな、ギバ」
真城と僧侶たちは、観音像の周りにまるく囲んで正座し、人差し指と薬指を伸ばして中指を折り馬口印を結びながら真言『オン・アミリトドバン・ウン・パッタ・ソワカ……』と唱え始めた。
「ルリよ、お前がどれだけ暴れても観音像を砕いても、母親は甦って来ぬ! 亡き母親が知ればどのように悲しむであろう」
ギバの表情が苦悩に歪む。
「むぐぐ……」
「母親だけではない、チグサも悲しんでいるぞ」
「ぐぐ……」
「あの娘は心からお前のことを案じている。どうかチグサのためにも……」
「チグサはあたいに無いものをいっぱい持っている」
ギバ――のしぼるような声はルリの声だ。
「裕福な暮らし、優しい両親……後、数えきれないほどな」
「お前には、チグサがうらやむものがあるではないか」
「えっ」
「それは……優しい母親のいた記憶だ。チグサの母親は産んですぐに亡くなったと聞く」
ルリは、あっという顔になった。
「人と自分を比べて卑屈になってはならん。お前にはお前だけの幸せがある」
ルリはその言葉を振りはらうように観音像の方へ駆けていき、それっとばかりに両手を突き出し、つむじ風を送りこむ。観音像が細かく震える。
「観音様に害をなすでない!」
真城が声を高めて正座を座りなおした。
第 九 章 真城の秘密
「お前の苦しみ、貧しさへの怒り、ひもじさ、屈辱……すべて分かる」
「何が分かるというのじゃ、高貴な神官の者に」
「私もまた幼き頃、貧しい馬方の子として生まれ育ったのだ。可愛い妹は餓死させてしまった。両親も病で亡くなり、私は神社の宮司に引き取られ育てられたのだ」
「……!」
真城の意外な言葉にルリは目を見開いて硬直した。
「神官が、あたいと同じ貧しい生まれだった?」
「貧しい身分のみなしごの私を、宮司様が引き取って下さり、神職の勉学をさせて下さったのだ。このご恩を忘れず、貧しい子供に恩返ししてやりたいのだ」
「神官……」
「悪いことは申さぬ、馬頭観音像に正座して頭を下げるのだ」
その時、背後から雅な音楽が流れてきた。
笙の笛や太鼓、~~~いつぞやの馬神神社で奉納された楽の音だ。
真城は馬頭観音に向かい静かに正座して額を地面につけてから、立ち上がって金色の扇で舞い始める。純白の袖がちょうど昇ってきた朝陽に輝いてひらひらした。続いて宝刀を鞘から抜き、朝陽にかざす。光はルリの額めがけて一筋に貫いた。
「うっ……」
ルリは眩しさによろめき、倒れた。顔をしかめたまま玉砂利の上にうつ伏せになっている。
真城は扇をパンとたたみ、懐に戻して少女のところへ歩み寄った。
「ルリ、私の声が聞こえるか」
「う……」
意識はあるようだ。
「……なんて眩しい舞いだ……あたいの心の中の膿を出してくれるような……」
舞の清らかさにルリは目が覚めたようだ。
「あたい……貧しさに負けてひどいことをしてしまった……罪もない馬を襲い、観音様にまで害を与えてしまい、恥ずかしい。恥ずかしいよ」
瞳に涙があふれていた。
瑠璃色の小馬は朝日に溶けるように消え失せた。
「分かってくれたのだな、ルリ」
真城の顔が晴れた。ルリの身体をゆっくり支え起こした。
その時、籠が到着し、近江の国の庄屋とチグサが下りてきた。
「ルリちゃん、大丈夫?」
「チ……チグサちゃん、あたいは……あたいは……」
ふたりは抱き合って泣いた。
第 十 章 正座して詫びよう
真城の手によって、ルリの頭上でお祓いが行われた。
馬頭観音の馬口印を口の前で結び、真言が長々と唱えられた。
「さあ、これでギバの魔は追いはらった。後は観音様にちゃんと正座して心から謝るのだ」
「ルリちゃん。私も一緒に謝る」
チグサが力強く言う。
「チグサだけではないぞ。私も、神社の禰宜たちも僧侶様方も皆して正座して詫びようぞ」
一同は倒れて台座に寄りかかっている観音像を囲んで静かに正座する。
真城がルリの傍らにひざまずいた。
「踵の上に座り、膝の上に静かに手を置く。それから観音像を見上げて心で詫びながら合掌する。……それでよい。よくできたぞ、ルリ」
大きな手のひらで頭を撫でてもらったルリは、泣き笑いした。
皆、それぞれ思い思いのお詫びの言葉を唱えた。
「観音様を倒してしまいすみませんでした」
「ルリちゃんの心を思いやってあげられず、すみませんでした」
「これだけの者がいながら、観音様を倒してしまって力が足りず、申し訳ございませんでした」
やがて、観音像は皆の力を合わせて、元あった台座に再び戻すことができた。
「これで、ギバを追いはらうことができた。近江の村には現れんだろう。馬頭観音様に醜い煩悩を取りのぞいてもらったから、妖しは消え去った」
真城は宣言するように皆に言った。
帰りの籠には、チグサとルリのふたりが乗ることになった。
「ルリちゃん、いい知らせがあるよ。神官様が私たちの村に半月に一度、正座を教えに来て下さるそうだよ」
「本当?」
ルリが目を向けると、真城は穏やかに頷いた。
「ルリも、ちゃんとお稽古して大きくなったら行儀の師匠になればよい。そうすれば、村の者にも正座を教えられる。おとっつぁんにも楽させてあげられるぞ」
「神官様……、そこまであたいたちのことを?」
真城は自分の純白の上衣を脱ぎ、少女ふたりの肩にかけてやった。
少女たちは恥ずかしさと嬉しさにクスクス笑って肩を寄せ合った。純白の衣から早春の花のような香りがした。
「さあ、帰ろう、近江の村へ。私の馬、白山が待っている。ギバは封じたゆえ、きっと元気で迎えてくれるだろう」
真城は純白の衣をひるがえし、鮮やかに騎乗するや、馬の尻に鞭を当てた。




![[2]正座ができる人](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)



