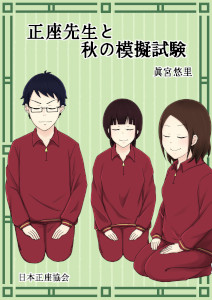[249]ばぁばの願い、折り紙と正座
 タイトル:ばぁばの願い、折り紙と正座
タイトル:ばぁばの願い、折り紙と正座
掲載日:2023/03/02
著者:海道 遠
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
カスミのばぁば(祖母)のスズカは観光地の路地奥の自宅前で、子どもたちや観光客に日本の折り紙、おはじき、いろいろな遊びや正座を教えている。
ばぁばはとても若々しい。車に乗って、パンプスを履くファッション。同時にぼた餅も作れる優しいお祖母ちゃんだ。ある日、盲腸で手術することに。カスミたち兄弟や両親も駆けつけ心配するが、手術は無事に終わり、すぐに退院する。カスミは入院中から路地奥の折り紙教室を任されていた。そこへ、折り紙師範の高田宗助が現れ、路地奥で折り紙をしている人の態度を見て怒り出す。さて?

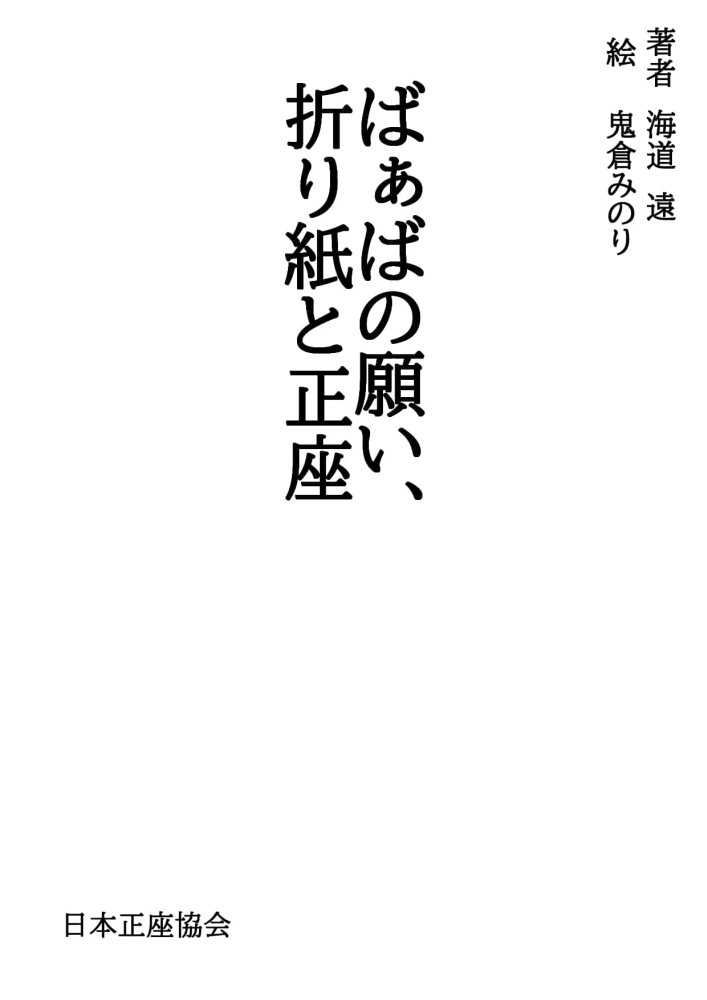
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 スズカばぁば
「ただいま、ばぁば」
家の玄関前の庭にレジャーシートを敷き、子供たちが座りこんで遊んでいる。中には外国観光客と思われる人たちも何人か混じっている。
「おかえり、カスミ」
「今日も楽しくやってるわね、ばぁば」
見守っているのは、カスミの祖母だ。「ばぁば」と呼んでいるが、おしゃれなショートのグレーヘアで、母親に見える若々しさだ。
「何度言ったらわかるの、カスミ。ばぁばじゃなくて『グランマ』って呼んでって言ってるでしょ」
「だって小さい時から私たち兄弟全部、ばぁばで慣れてしまったもん」
ばぁばは背が高くて颯爽と歩く。ワインカラーのトレンチコートがよく似合う。子どもたちを見守っている時も、ちゃんとタイトスカートを穿いて、若草色のタイトルネックのセーター、パンプスを履いている。ちょっとご近所にはいないお洒落なばぁばは、カスミの自慢の祖母だ。
子供たちや観光客たちは、日本の折り紙やあやとり、紙風船やおはじき、竹とんぼなどで遊んでいる。大人も夢中になり、きゃっきゃ歓声が上がる。
「お腹が空いたでしょ。おやつにぼた餅を作ったからお茶の間に置いてあるわよ」
「わあ、嬉しい! ばぁばのぼた餅は天下一品だもんね」
カスミはすぐに家に上がり、カバンを放り出して手を洗うや、お茶の間のぼた餅にありついた。
「もう少し、お上品に食べられないの。カスミももう十六歳でしょ」
「十八よ。高三になったって言ってるでしょ」
「十八! じゃ、なお更だね。女らしくしていただきなさい」
「古いわね、ばぁば。今は女だから、男だからってことは言わない時代なのよ」
「だからってお行儀よくなくていいってことはないでしょう」
「それはそうだけどね……、正座はちゃんとしなさい、ばぁばの教えた通りに。スカートがぐしゃぐしゃじゃないの」
「はいはい」
カスミは言われる通りにきちんと正座して。お尻の下にスカートを敷いた。
「あ~~! ねぇねだけずるいぞ!」
入ってきたのは妹のミチルと末の弟のタスク。中学二年と、まだ六歳の幼稚園児だ。
「ぼた餅はたくさんありますよ」
ばぁばが微笑んで戸棚から追加のぼた餅を出してきた。
「あんたたちもちゃんと正座していただくのよっ」
「カスミ姉ちゃんたら、偉そうに。さっき、怒られてたの聞こえたわよ」
ミチルが口を尖がらかした。
カスミがふと気づき、
「ばぁば、なんだかいつもより元気ないわね。どうしたの?」
「そうかな。気のせいよ」
ばぁばは、いつも元気だ。ぼた餅やお赤飯を炊くのも得意だ。山菜めしなんかお店のより美味しい。お裁縫や刺繍もできる。何より、日本の昔からの子供の遊びに詳しい。それをご近所の子供たちや観光客の外国の方に教えるのを楽しみにしている。
正座の先生でもある。若い頃から行儀作法を習ったとかで、お作法の中でも正座の所作は完璧だ。
「あら、ご仏壇にお供えするのを忘れていたわ、私ったら」
「じぃじが怒るわよ~~。甘いもの大好きだったから」
じぃじは三年前に病気で亡くなったが、ばぁばとは大恋愛だったそうで、今でもばぁばは仏壇の前で話しかけて、いちゃいちゃしてる時がある。
慌ててご仏壇にお供えしてから、居間に戻ろうとしたばぁばは、急によろけて柱につかまった。
「どしたの、ばぁば!」
カスミが立ち上がって駆け寄ると、ばぁばの額に汗が噴き出ている。
「今朝からなんだか、脇腹が痛くて……」
口元にあんこをつけているミチルに、カスミが叫んだ。
「救急車呼んで!」
第 二 章 ばぁばの夢
ばぁばは救急車で運ばれ、お父さんとお母さんが慌ててやってきた。緊急手術したのだ。
「しっ! まだ麻酔で寝てるから静かに」
カスミが両親を廊下に連れ出した。
「大丈夫、ただの虫垂炎だって」
「虫垂炎……、盲腸……」
病名が分かり、ふたりは力が抜けたようだ。
「良かった、盲腸ならすぐに退院できるわね」
意識を取り戻したばぁばは、翌日、カスミを呼んだ。
「カスミ。ばぁばが入院している間、路上の日本の遊び教室はあなたが責任者になって、やってちょうだい」
「ええ? だって四、五日で退院できるんでしょう」
「でも、その間に活動しなかったら、子どもたちの気が緩むわ。正座だってばぁばが教えて上手にしているのに、お行儀が乱れるかもしれないし。だからカスミちゃん、あなたが学校終わったらちゃんと見ておいて。子どもさんたちを預かってる責任もあるから、ね」
カスミは胸をドンと叩いた。
「分かったわ。ばぁばが退院して、元通りの生活になるまで、ここの遊びは私に任せて」
「ありがとう、カスミちゃん」
カスミの家は少し路地を入った静かな場所だが、表通りは観光地で、日本の遊び教室は正座を愛しているばぁばが考案したものだ。
この場所を利用して、外国人や子供たちに正座して日本の遊びを伝えたいと思いつき、続けることがばぁばの夢なのだ。
カスミが責任者になった当日、子供の数も、足を止める観光客の数も多かった。
広いレジャーシートを三枚敷いても座り切れない有り様だ。
「皆さん、押さないでえ。ちゃんと譲り合って座ってね!」
カスミは一生懸命に皆に指導した。狭い中ではあるが、初めての人や外国からの観光客に「正座」を教える。
「背筋を真っ直ぐにしてそのまま、かかとの上に座り、女の子のスカートはお尻の下に敷くこと。手は膝の上に。そこから遊びにとりかかって下さい」
カスミ自身がやってみせると、小さい子や外国人観光客にもなんとか通じたようで、ゆっくり正座している。
「これが日本の正座という座り方か……」
「この前、お寺で座ったじゃないの」
外国人夫婦がしゃべっている。
折り紙やあやとりを始めかけたところへ、
「なんだ、これは! 正座して折り紙しているのか!」
いきなり頭ごなしに叱る男の声がした。
まだ二十代半ばくらいのカジュアルな服装の男だ。
「正座して折り紙しちゃいけないんですか?」
カスミがちょっと不機嫌な顔で言い返した。
「いけないとは言わないが、ほら、皆、正座をくずすまいとして、折り紙に意識が行ってないじゃないか。挙句の果てに膝で踏んだり、折れ曲がった折り紙も大切にしないで。もっと指先に意識を集中させないと細かいものは折れないぞ」
確かに、正座を崩すとカスミが注意するので、初めての子供や観光客は正座に意識が行ってしまい、折り紙に没頭できない。
「じゃあ、どうしたらいいのよ」
「ポーズを自由にするんだよ。お茶やお華じゃないんだから、折り紙は寝転がって折ろうが、動き回って折ろうが自由に!」
「そういうわけにはいかないわ。私は祖母に頼まれているんです。正座を最も重視する祖母から任されてるんです!」
男は、ややたじろいだ。
「だいたい、いきなり、あなた何者なのよ?」
「僕? 僕は日本折り紙師範の資格を持つ者だ」
「折り紙師範?」
「あっ」
カスミの一番末の弟、タスクが高い声で叫んだ。
「このおにいちゃん、知ってる! 折り紙の偉い先生だ」
「君は、織部タスクくん!」
青年も叫んだ。
「どうしてタスクのこと知ってるの?」
「織部タスクくんは、たった六歳で子ども折り紙博士の特別認定を受けた天才少年です。そうか、ここが君の家だったのか」
青年は顔を輝かせた。
「カスミねぇね、この折り紙の先生とケンカしないで」
末っ子のタスクからうるうるした瞳で見つめられると、カスミもどうしていいか分からない。
「でも、折り紙の前に、まず正座。それがばぁばの教えよ。折り紙の師範だか何だか知らないけど、寝転がって折り紙するなんてとんでもない話だわ」
「極端な例を言ったまでだ。いい作品のためなら、どんな姿勢でやっても構わない。それが僕たちの考え方だ!」
「正座より折り紙の方が大事なの?」
「折り紙より正座するのが大事なのか?」
ふたりは睨みあった。
第 三 章 春の路地の対決
桜の花びらがひらひら舞い落ちてきた。
路地の表は観光客の喧騒が絶え間なく続くが、織部家が突き当りにある細い路地はしいんとしていた。
青いレジャーシートの上に、カスミと先ほどの青年が改めて向かい合って正座している。
「織部カスミです」
「高田宗助です」
カスミの妹のミチルが抹茶をそっと、ふたつ持ってきて置いていった。
「君は折り紙ができるのか?」
「いえ、ばぁば、いえ、祖母から教えてもらった簡単なものができるだけです。ごく一般的な」
「何度も言うが、私は折り紙師範だ。日本の各地で教えている。こんな道端で教えているのとわけが違うんだ。神聖な日本の伝統の折り紙を、子どもが膝で踏みつけながらしているのを見て、黙っちゃいられない」
宗助という青年は険しい顔になっている。負けるもんか、とカスミも睨み返す。
「子どもが楽しく遊ぶ。それが折り紙の始まりでしょう。お行儀よくできれば、それに越したことはないでしょうけど」
「楽しく遊ぶのと膝で踏みつけるのと、同じにしてるじゃないか」
「してませんよ! 年端のいかない子どもが踏んでしまうのはしかたないことです」
「許せんな。神聖な折り紙を、小さな子であれ踏みつけるとは」
「頑固な方ね! よくそれで師範なんかやってられるわね」
「なんだとぉ!」
思わず、宗助青年が立ち上がりかけたが、足ががたがた震えて、そのままドシンとレジャーシートの上に派手に倒れた。
「いてて……」
「痺れたんですね。折り紙の師範が正座ができないのね」
「ちょっとカスミねぇね、あんまり失礼よ」
ミチルがレジャーシートの上に駆けつけてきて、菓子皿を盆から落としかけた。
カスミと宗助は、火花散る視線を交わしていた。
「じゃあ、君は折り紙ができるのか。折り紙の神聖な世界が分かるのか」
「で……できないわよ。鶴も難しくて」
「弟くんがあんなに小さくて折り紙博士になれたのに、姉の君が折れない! はっは、僕が正座できないよりひどい話じゃないか」
「なんですってえ」
カスミが悔しまぎれに、ミチルの持ってきたお饅頭をむんずとつかんで口に押しこんだ。
「不愉快だ!」
宗助は、今度はちゃんと立ち上がり、レジャーシートから靴を履いた。
「また来る! このままじゃすまさないからな」
「また下手な正座して転べばいいわ!」
頬ばったお饅頭をもごもごして、カスミは背中へ毒づいた。
第 四 章 ばぁばへの来客
ばぁばが退院した。彼女らしくひとりで車を運転して帰ってきた。
バイカラーのパンプスをコツコツ鳴らして車から降りると、孫たちが群がった。
「お帰り、ばぁば!」
「良かったね、早く帰れて」
「ただいま、みんな」
その夜、退院祝いが開かれた。
「心配かけたねえ。ありがとうね」
ばぁばは、お祝いのケーキをパクパク食べた。
「盲腸くらい吹き飛ばすお袋だと思ってたよ」
おとうさんがもう酔っぱらっている。
カスミ始め四人の孫たちもご機嫌だ。
「カスミ、路地の遊びはちゃんと留守番できた?」
「ばぁば、カスミねぇねったらね~~! 折り紙師範の高田宗助さんと……」
ミチルが折り紙師範との一件を持ち出しかけたので、カスミが急いで口をふさぐ。
「何? 折り紙師範の高田さんがどうしたって?」
ばぁばが目を輝かせて尋ねる。
「あ、なんでもないの。気にしないで」
「ばぁばは今度、折り紙師範の試験を受けるつもりなんだけど。高田さんは、ばぁばの先生よ」
「えっ」
カスミが目を見開いた。
カスミの弟のタスクが、
「ぼく、知ってたぜ。ばぁばの部屋、折り紙だらけだもん」
「いつのまに習いにいってたの」
「公民館で高田先生の講座に参加したの。家の前のお客様にも、もっときれいな折り紙をお教えしたいからね」
顔を輝かせて言うばぁばを見て、カスミは何も言えなかったが、あの宗助という折り紙師範の鼻もちならない態度がよみがえる。
(折り紙が折れないことをバカにしたわね! 自分は正座できないで転んだくせに! おまけに、ばぁばまで巧妙にトリコにして)
退院お祝いの後片付けをしている時に、ばぁばが、ミチルに手招きした。
「なんだかカスミのご機嫌が悪いけど、高田先生が来た時、どんな感じだった?」
「いや~~、もう長年の仇が巡り会ったって感じだったわよ」
「よほど相性が悪いのかな。ばぁばは、高田先生をとても気に入ったから、カスミに会わせてやろうと思ったんだけどね」
「カスミお姉ちゃんと?」
ミチルは目をくりくりした。
「お似合いだと思わないかい」
「なんだ、ばぁばもお見合い大好きな平凡なおばあちゃんだったのね。なんだかがっかりだわ」
「あら、そう?」
「今どき、親や身内の勧める相手となんて」
「出会いはどこに転がってるかわかんないじゃないの」
「それがおせっかいっていうのよ」
ミチルの言葉に、ばぁばはシュンとした。
「外側だけ若くしていてもジェネレーションギャップは仕方ないのかしらね~~」
チャイムが鳴った。
ばぁばが出てみると、相手の顔より先にでっかい花束が顔の前をふさいだ。ピンクの百合にグラジオラスにフリージア。紅いカーネーションがいっぱい。
「病院にお見舞いに伺ったら、退院されたとお聞きして」
高田宗助だ。
「ご退院、おめでとうございます」
「まあ、高田先生、ありがとうございます。どうぞお上がりになって」
意外な客に、ばぁばは大喜びして案内しようとしたが、
「いや、お顔を見ればそれだけで。先日、お孫さんのお嬢さんと面白い対決させてもらったことだし」
宗助は急いで帰ろうとする。
「面白い対決は、まだ決着がついてないわよっ」
奥から声がして、カスミが玄関に出てきた。
「やあ、いたんだ」
「ばぁばは元気そうでも、まだ無理できないから学校休んでいたんです」
「じゃあ、これ」
宗助は巨大な花束と、カラフルなでかい折り紙らしきものを、ドサッとカスミに渡した。
「こ、これは」
巨大な、紅色の鮮やかなフラミンゴの折り紙作品だ。
「何を折ればいいか悩んだんだけど、前にスズカさんがフラミンゴが好きって言ってたのを思い出して。今度、折り方をお教えしようと思ってたとこなんだ」
「まあ、宗助先生、ダイナミックなフラミンゴ! いっぺんに元気になりますわ」
フラミンゴの羽根の色と同じくらい、頬を紅潮させたばぁばがお礼を言う。
(「スズカさん」だって……)
カスミとミチルは目で合図しあった。
第 五 章 ばぁばと高田先生
カスミとミチルは、客間から聞こえてくる声をドア越しに聞き耳立てていた。ばぁばと高田宗助の朗らかな談笑が洩れ聞こえてくる。
「ちょっと、カスミねぇね」
ミチルが神妙に言った。
「高田先生って、じぃじに少し面影が似てると思わない?」
「じぃじ? ご仏壇のじぃじの遺影に?」
カスミは目を丸くした。こういうことは、妹だがおませなミチルの方が鋭い。仏壇へ走っていってよくお祖父ちゃんの写真を見てみると、似ているような気もする。
「じゃあ、ミチル。あんた、ばぁばが、高田先生に気があるとでも言いたいの?」
「いくつになっても女って女よね」
「……」
疎いカスミは、どうもピンと来ない。なんとなく面白くないだけだ。
台所へ走っていって、冷蔵庫に入っていたシュークリームをかたっぱしから食べた。
「ねぇね、やけ食い? あのふたりにヤキモチ妬いてるの?」
「ばか言いなさいよ。凜としてるばぁばが、デレデレしてるのがイヤなだけよ」
「それをヤキモチと言わずして何と言いましょうか?」
ミチルが舌をペロリと出したので、カスミは手を振り上げるマネをした。
台所にまで客間のふたりの笑い声が聞こえてくる。
カスミはむしゃくしゃするのがたまらなくて、玄関に出た。
そろそろ近所の子どもたちが遊びにやってくる頃だ。案の定、いつもの子どもたちが集まり始めていた。
「スズカばぁば、病院から帰ったの?」
健気な瞳で女の子が見上げて尋ねる。
「はい、帰ってきましたよ、元気になって。ご心配ありがとうね。アッちゃん」
子どもたちも安心して遊び始めた。
玄関の扉が開いて、ばあばが高田先生を見送りに出てきた。
「お見舞いありがとうございました」
「教室へ復帰するのをお待ちしていますよ。まだしばらく安静にしてください」
高田宗助は帰っていった。
スズカばぁばは、それから順調に回復し、折り紙教室に出かけていった。
「ばぁば、嬉しそうだったわね」
「そりゃ、高田先生、素敵ですもの」
カスミの誘いに乗ってしまったミチルが口元を押さえた。
「ミチルったら、あんたまで。私にハジをかかせた男を褒めるなんて」
カスミはふくれて家の掃除にとりかかった。
両親や兄弟たちは出かけ、ひとりになった。
ご仏壇に行って、じぃじの遺影を眺めてみる。
「う~~ん、似てるような気もするけど。じぃじ、しっかりしてよね! ばぁばがよそ見しようとしてるのよ」
その時、スマホが鳴った。電話だ。電話をとったカスミは、たちまち真っ青になり家を飛び出した。
第 六 章 大グランマ
カスミが病院に走りこんだ時は、手術室のランプが点いていた。
ばぁばの緊急手術が行われている。手術室の前に高田宗助が真っ青な顔で立っていた。カスミを見ると、深々と頭を下げた。
「申し訳ありません。僕がついていながら」
「いったい、どうしたというの」
看護師の説明によると、虫垂炎の手術後、癒着から腹膜炎を起こしたので、緊急手術になったそうだ。
最初の時のように、両親が駆けつけ、兄弟たちも慌ててやってきた。
やがて手術室からストレッチャーで出てきたばぁばは、意識の戻らないうちに病室へ移された。
「今度は十日間の入院になりますが、大丈夫ですよ。術後は家でも安静にしていて下さい」
主治医の言葉である。
意識が戻らないばぁばの顔は眉をゆがめて苦しそうだ。
「ごめんね、ばぁばがいつも元気だから安心してたわ。もっと注意してればよかった」
泣くカスミを、そっとお母さんが抱きしめた。
その夜は、お母さんが泊まり込みをして、他の家族は家に帰った。
布団の中に入ったものの、カスミはなかなか寝つけない。
「こうなったら連絡しよう!」
起き上がって、枕元のスマホを手に取った。
二日後、ばぁばは意識を取り戻し、食事も摂れるようになっていた。
カスミひとりが付き添いしていた。
そこへ、ドアが静かに開いた。
真っ赤なトレンチコート、銀髪にピンクのメッシュを入れた熟女がサングラスを外した。
ベッドのばぁばが、驚いて食事の手を止めた。
「スズカ、久しぶりね」
「大グランマ! いえ、ママ」
ばぁばのお母さんのトワコだ。ふたり並ぶと姉妹のようだ。
「虫垂炎の術後が良くないらしいじゃないの。だらしないわね。二度も入院するなんて」
堂々とした態度に、ばぁばは気圧されている。
「どうしてこの事を……」
「カスミが連絡してくれたのよ。あの子のためにも放っておけなくて」
「カスミといつ、連絡先を」
「昨年、修学旅行でカスミがパリに来たでしょう。その時に会ったの」
「まあ」
カスミが照れるとも申し訳ないともつかない顔で、
「ごめんね、黙っていて。私、どうしても大グランマに会ってみたかったの。ばぁばのママってどんな人かなってずっと思っていて。そしたら、ばぁばよりももっともっと素敵な人だったわ」
「カスミは優しい子ね。あの人の孫にしちゃ上出来だわ」
あの人とは、亡くなったばぁばの夫のことだ。
ふたりは大グランマの反対を押し切って結婚したというのも、カスミはパリの修学旅行に行った時、初めて聞いたのだった。
大グランマに反対され、駆け落ち同然だったという。
「よけいなことまで孫に聞かせて……」
「よけいなことまで孫が連絡してくるような心配をかけないで!」
大グランマは矢庭に両手の手袋をはめたまま顔を覆って泣き出した。
「遠い祖国に勝手に帰ってしまって、どんなにずっと心配していたか」
「ママ……」
ばあばは、ベッドに泣き伏した大グランマの肩に手を置いた。
「ごめんなさい、心配かけたわね。一度もママのところへ帰らないでごめんね。私は孫に囲まれて幸せに暮らしています」
「スズカ……よかったわ」
ばぁばはカスミに目を向け、
「カスミ、あなた、ママにどうやって連絡つけたのよ」
「ソーシャルメディアのワールドブックで見つけたの。大グランマは正座の第一人者で世界の折り紙協会理事。すぐに見つけたわ」
その時、病室に飛びこんできたのは、高田宗助だ。
「本当ですか! スズカさんのお母さまが世界の折り紙協会の理事とは!」
カスミとばあば母娘は、唖然と宗助に目を向けた。
「そうです。高田先生」
「いやあ、知らなかった! 僕ということが! お顔は存じ上げてましたが、まさか」
「大グランマ。ばぁばの折り紙の先生よ」
カスミが紹介し、高田先生は大慌てに慌ててお辞儀した。
「スズカも日本で折り紙をしていたのねえ」
「大グランマ。正座もよ」
「正座は、スズカの物心つく前から私が教えたのよ、カスミ」
大グランマは涙を拭いて微笑んだ。
ホテルのロビーに大グランマ、高田先生、カスミの姿があった。
「正座と折り紙がどうのこうので、カスミとやり合ったって聞きましたが」
「はあ……」
「カスミもよく聞きなさい。正座と芸事はひとつのもの。茶道しかり、華道しかり。折り紙もそうかもしれない。正座して、心を落ち着けてから取りかかると出来が違います。離そうと思っても離れないもの」
「はい」
「そのふたつは仲良く成立しなくちゃね」
「はい、あの時はナマイキ言って、すみませんでした。高田先生」
「いや、カスミさん、僕が大人げなかったよ」
ふたりは謝りあい、大グランマは微笑んだ。
「高田先生、あなた正座がお苦手だそうだから、お教えさせていただきます」
「え、ここでですか」
「はい、ソファから下りて。カスミ、あなたもよ」
ホテルの静かなロビーで正座講座が始まった。周りの人や、ロビーの従業員がじっと見ている。
「真っ直ぐに立って、かかとの上に静かに座って。カスミはスカートをお尻の下に手を添えて敷いて。両手は静かに膝の上に置く。そう、それでよろしい」
「ありがとうございました」
「高田先生、今、膝の上に置いていらっしゃる大切な両手は、折り紙を折る大切な手。そのことをよく覚えてらして下さい」
「は……はいっ!」
「そして、私の脚は美しく正座するための大切な脚です」
大グランマはロビーで真っ赤なパンプスを脱ぎ、正座してみせた。
一同、鶴が降り立ったような凛とした美しさに心打たれた。
「カスミ、折り紙をもっと子どもたちに教えるのなら、スズカと一緒に高田先生のお教室へお行きなさいね。もうケンカしちゃだめよ」
見物していたホテルの従業員たちが、ぱらぱら拍手した。
「さ、私はそろそろ空港へ行かないと」
大グランマはソファから立ち上がる。
「うちへ泊っていかないの、大グランマ!」
「そうもしていられないのよ。仕事が立てこんでいてね」
真っ赤なベルトの腕時計を見た。
「スズカのこと、お願いね、カスミ」
「はい!」
トレンチコートをひるがえしてタクシーに乗りこんだ。
タクシーが都会の車の流れに小さく混じっていく。
ふと横を見ると、高田先生が自分の両手を見つめていた。
「折り紙を折る大切な手……確かにそうだ」
「大切にして下さいね」
「カスミさん、僕の折り紙を習いに来て下さい。その代わり、正座を教えて下さい」
「まあ、この前みたいにすってんころりしたら困りますもんね」
カスミはにっこりして答えた。
危うく、またケンカになりそうだったが、高田先生が言葉を飲みこんで微笑み返した。
(鶴も折れないくせに……)
(フラミンゴでもダチョウでも折れるようになってみせるわよ)
大グランマの言いつけをやぶって、一戦交えそうなふたりだった。
ばぁばがまた、高笑いするだろう。