[264]座玉(すえたま)ドロボウ
 タイトル:座玉(すえたま)ドロボウ
タイトル:座玉(すえたま)ドロボウ
掲載日:2023/09/24
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
奈良時代――。倭国(昔の日本)の丹後地方の国の年若い役人の紫紺郎(しこんろう)は、唐の国からの遣いの接待を命じられ、頭を悩ませていた。唐の国から伝わった所作で、正座をしなければならないからだ。紫紺郎は正座するとすぐに痺れてしまう。そんな時、丹後の国の由緒ある籠(この)神社の欄干に座え(すえ)られている紅い玉を膝に乗せると痺れないという噂を聞く。
「盗んできてやる」という少女、もえぎに依頼する。

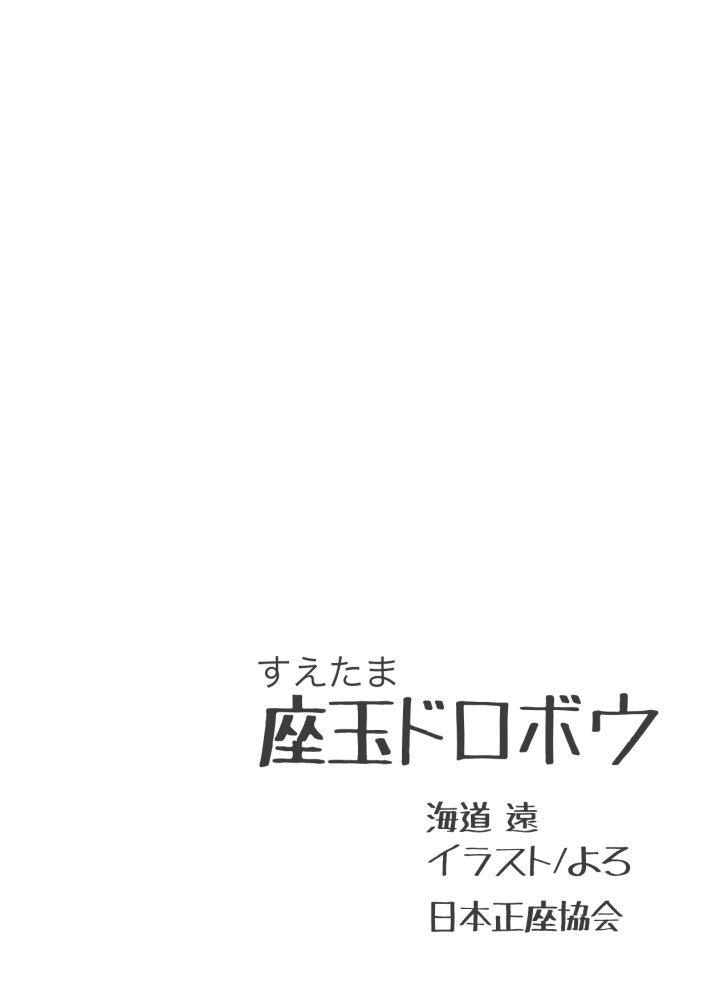
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 唐からの使者
今から遠い昔――。千数百年も昔の奈良時代。
日本海に面した丹後地方。小さな港町と人家が点在している。
「はあ……」
まだ若い役人の紫紺郎(しこんろう)は、ため息が止まらなかった。
当時、倭国(わのくに=日本)は大陸の唐の国と交易が盛んに行われていた。
紫紺郎は、この度、唐の朝廷からやってきた遣いの役人を接待しなければならないお役目だ。
宴席では、唐の国から渡ってきた文化である「正座」で座らなければ失礼にあたるのだが、紫紺郎は「正座」が大の苦手だった。お尻を乗せて膝を折って座ると、すぐにしびれてしまうのだ。普段は立て膝か胡坐(あぐら)座りばかりなので無理はない。
唐からの遣いの前で、しびれて立てなくなったり、転んだり、失態は許されない。
何せ、唐の国が新羅の国と結託して百済の国に攻め込んだ「白村江(はくすきのえ)の戦い」が起こってからまだ数年しか経っていない。百済の国の救援に出兵した倭国は大敗した。大国、唐王朝は以前にまして倭国にとって脅威になっている。
――というわけで、紫紺郎は会食の接待命令が出てから悩みに悩んでいる。
(なんとか正座しても、しびれずに済む方法はないものかな)
「紫紺郎どの、浮かぬ顔をしているな」
声をかけたのは同僚のひとりだ。
「浮かぬ顔にもなるさ。今度の唐の遣いとの宴席で正座しなければならないのだ」
「そりゃあ、困ったことだな。あれは、しびれが悩みのタネだ」
「何かいい方法はないだろうか」
「そういえば、天橋立の北側にある籠(この)神社の奥殿の欄干に並んでいる五色の中の紅い座玉(すえたま)を膝に乗せて正座すると、しびれないとかいう噂があるぞ」
「ほ、本当か、それは! ありがたい!」
紫紺郎は踊り上がった。
しかし、座玉のある籠神社というと、丹後一之宮と言われる伊勢神宮と同じ格式の神社だ。そんな神社が玉を貸してくれるわけがない。
(本当に座玉にそんな力があるなら、喉から手が出るほど欲しいけどなあ)
役所を後にして、辺りが暗くなるまでため息を繰り返して、海岸に立っていると、背後から女の声がした。
「お役人さん、あたいが盗んできてやろうか?」
振り向くと、まだ若い娘が目をキラキラさせていた。漁民の娘だろうか。地味な着物を膝までめくり上げていて、活発そうな少女だ。
「お前は? まさか、今のひとり言を聞いてしまったのか」
「あたいはちょいとオツムとワザを使って生業(なりわい)にしてる者さ。あたいの手にかかりゃあ、籠神社の座玉を盗み出すなんて、朝飯前さ」
「しっ!」
紫紺郎は慌てて、娘の口をふさいだ。
「でたらめ言うと承知せんぞ!」
「しょっぴくつもり? あんたが座玉を盗もうと命令したって、役所に言っちゃおうかな」
「ま、待て!」
紫紺郎は真っ青になった。
「本当に盗み出してこれるのだな。証拠を見せよ」
「証拠たって。手っ取り早く現物を持ってくりゃいいんだろ?」
「あの玉は重そうで、欄干にきっちり固定されているに違いない。本当にできるのか?」
「疑り深い役人だな~~。さては、あたいのこと知らないんだな。つむじ風のもえぎって言うと、ここらではちょいと名の知れた姐さんだぜ」
紫紺郎は目を白黒させた。役人がドロボウに盗みの依頼したなどとバレれば、打ち首は間違いない。しかし……、唐の遣いの前でしびれて転べば、これもまた打ち首は間違いない。
「ううむ、では、手間賃は後払いだぞ!」
ワラをもつかむ思いで、紫紺郎はもえぎに座玉を盗んでくるように依頼した。
「座玉は五色あるが、しびれに効能があるのは紅い玉らしい。間違えるなよ」
「紅玉だな、ガッテンだ!」
もえぎは野狐のような素早さで、夕暮れの港町に消えていった。
第二章 宴の日
宴の当日。
紫紺郎は玄関から母親に送り出される。いつもと違い、少し格式ばった礼服すがただ。
「お前が、唐の皇帝さまのお遣いのおもてなしを命じられるなんて、なんて誉れ(ほまれ)なことだろうね。亡くなった父親にも、その姿を見せてやりたかったねぇ」
「こんな格好するのは数年に一回、あるかないかじゃないか。普段は田んぼや畑もしなきゃ暮らしていけないんだから」
「だから、よけい感激してるんじゃないか」
涙ぐむ母親を残して出かける紫紺郎は、罪悪感に押しつぶされそうになっていた。
唐からの遣いの黄(こう)どの一行数十人は、奈良の平城京へ上って天皇陛下に挨拶した後、丹後の国へ帰ってきて丹後の国の郡司と会うのだった。
紫紺郎が役所から離れた一本杉の根元で待っていると、部下が見知らぬ男から預かりものだと言って、地味な布で包まれたずっしり重い物を持ってきた。
チラリと布をめくってみると、鮮やかな紅色が見えた。
(あやつ、本当に座玉を手に入れたか)
役所で一連の儀式が終わると、郡司の館で宴が開かれる。いよいよ正座する時だ。
いつもならしびれの心配をしなければならないが、紫紺郎は少し安心して正座しようとすると、黄どのが、
「お待ちあれ、お役人さま方。今日はせっかくのことですから、皇帝陛下直々(じきじき)にお習いした『正座の所作』を伝授いたしましょう」
通訳を通して言った。
(正座の所作? 皇帝陛下直々の?)
倭国の役人たちは一斉にドキドキしたに違いない。皇帝陛下直々の所作を間違えでもしたら、無事に家に帰宅できるだろうか、と。
黄どのが静かに立ち上がった。
「背すじを真っ直ぐに立ち――、膝を着きます。次に、お尻の下に衣を敷きながら、かかとの上に座ります。両手は膝の上にゆったりと置く。これが我が大唐での正座の所作です」
黄どのの一同、倭国の丹後の国の郡司や部下一同も、同時に無事に正座した。ひとりだけ、紫紺郎が丸い布包みを膝に乗せて座った。
「紫紺郎どの、その包みは?」
隣席の同僚が尋ねた。
「これは、ちと自宅に置いておけぬ貴重な品ゆえ、仕方なく持参したまでです。これを膝に乗せると、正座しても足がしびれないのです」
引きつる笑顔で答えた。
唐の黄どのが気づいて、通訳を通して紫紺郎に尋ねる。
「いったい、その玉は、どこから手に入れられたのかな?」
「有名な巫女から、お祓いをしてもらった品でございます」
「それは、なんとありがたい品だ……。実を申せば、我が大唐の皇帝陛下も正座する時の足のしびれに困っておられるのだ」
黄どのは、超、機密事項を打ち明けた。
「その紅い玉、ぜひとも皇帝陛下への土産に唐の国へ持って帰りたい。帰りの船に紫紺郎どのも乗って同行し、皇帝陛下に直接、献上されよ」
「私が唐の都の皇帝陛下へですかっ」
「うむ。そうしてくれれば、唐王朝と倭国の物資のやり取りがもっと増えるよう、口添えさせていただこう」
倭国の民が貧しいことをよく知る紫紺郎は、唐へ行くことを決意した。
第三章 出航
いよいよ、黄どのが祖国に帰る日が来た。
紫紺郎も支度をして船に乗りこむ。多くの船子が荷物を積みこんでいた。その中に、見覚えのある小柄な少年がいるではないか。男装したもえぎだ。
「おい、そこの者!」
集団の中から、もえぎを引っぱり出した。目立たない場所に連れて来て、声をひそめながら、
「やっぱりお前だったか、もえぎ。なぜ、こんなところにいる?」
「えへへ。実は、欄干から紅い座玉が無くなっていることが露見しちまって、神社からの追手に追われて船に逃げこんだんだよ」
もえぎは照れ隠しのように笑いながら白状した。
「よりによって、この船に……」
紫紺郎は空いた口がふさがらない。
「まずい! 籠神社は丹後一之宮。伝説の海都(かいづ)王朝と繋がりがあったとか、なかったとかの言い伝えもある。捕まったら一巻の終わりだ! 俺はともかく、残してきた母親と弟や妹はどうなるか……」
一気に不安の波が押し寄せた。
「そう、心配しなさんなって。お役人さんとあたいの繋がりまでは、嗅ぎつかれないはずだから」
案外、楽観しているもえぎだ。
「船は出航しちまった、仕方ない。船子に混じって、このまま行くしかない。女だってことバレないようにしろ」
「はいはい。大丈夫。船子仲間とはすっかり仲良くなってるから」
やがて、船はひと月ほど海を走り、大きな港、寧波(ニンポー)に入った。外国からの大きな船が幾艘(いくそう)も停泊していて、乗組員は管署(かんしょ)を経て上陸する。
商人の出入国や貿易品、ご禁制の品の検査が行われている。
(なんだか厳しそうな検閲だ。あの座玉が盗品だとバレやしないだろうか)
紫紺郎は船から大量の品が下ろされていくのを見て、生きた心地がしなかった。しかし、それは思い過ごしに終わった。
港には、黄どの遣いの一行を迎える荷馬車や、出迎えの役人が乗った馬車がたくさんひしめいていた。
港の混雑で、もえぎを見失ってしまった。
紅の玉は、倭国からの献上品として厳かに扱われ、ひと際華やかな馬車に乗せられて都をめざして出立した。護衛の兵や付き人などが周りを取り囲み、たいそうな行列になっている。
紫紺郎も追いかけるように別の馬車で都に向かった。
丹後の国から十人ほどの部下を連れてきたものの、初めて踏む大陸の風景は、郊外に出ると地平線まで見えそうな田畑が広がり、圧倒されるばかりだ。
珍しい唐風の壮麗な建物の町をいくつか通りすぎる。馬車の車窓から見える風景は珍しいものばかりだ。
馬車の中でも正座していると、しびれてガマンならなくなってしまい、先を行く馬車を停めて座玉を取り出して膝に置いた。不思議にも乗せるとしびれない。こうして、紫紺郎は少しでも緊張をやわらげていた。
第四章 都へ
都の長安までは、馬車で何日かかかる。途中で宿屋や農家に泊まり、進んでいく。
紫紺郎は馬車の中で、ふと疑問に駆られる。
(本当に、座玉のおかげでしびれないんだろうか)
布の隙間から覗いて座玉を確認してみる。つやつやとした赤い玉だ。素材は何で作られているのだろう? 珊瑚(さんご)だろうか?
(籠神社は海の近くにあり、勢力を持っているのでおそらく珊瑚だろう。近くには浦嶋子(うらしまこ=浦島太郎)の言い伝えのある神社もあるので、浦嶋子が竜宮城から持ち帰ったとか? では、紅以外の、青や黒や白の玉は?)
(そもそも、どうして紅の玉にしびれを防ぐ力があるのだろう?)
(それを、唐王朝の皇帝陛下から下問(質問)されたら、どう答えよう? 素直に膝の上に乗せてくれるかな?)
――などと取り留めのない思いが頭をめぐった。
その時の皇帝は、まだ二十歳になったばかりの青年で、滋宗(じそう)と言った。父親が数年前に崩御した時に即位したのだが、母親の皇太后が実権を握って力を持ちすぎるために、お飾りの皇帝と言われているらしい。
――ということを、黄どのの部下から、紫紺郎はそれとなく聞き出した。
(強い母親の言いなりになっている若造の皇帝なら、紅い玉のことを信じるかもしれん)
ついに長安の都に到着した。
皇帝の宮殿、大明宮に入る。途轍もなくだだっ広い石畳の広場を持つ居城が待ち構えていた。
石畳の上をガラガラと馬車と共の者たちの列が進んでいき、壮麗な門前の階段にたどり着く。階段の脇には金色(こんじき)に光り輝く龍の立像が左右に配されている。
共の者が素早く馬車の足元に踏み台を置き、もうひとりが簾(すだれ)をめくり上げる。
紫紺郎は、紅の玉を小脇に抱えて降りようとしたので踏み台から足を滑らせてよろけてしまい、座玉の包みを落としてしまった。座玉が布から飛び出して石畳の上を転がる。
「し、しまった!」
その場にいた者たちは、鮮やかな紅の、ツヤツヤと光り輝く大きな玉に視線を吸い寄せられた。紫紺郎が慌てて追いかけようとすると、先に拾った美しい袖の細い手がある。ふと顔を見ると、宮女(きゅうじょ)の着物を着たもえぎではないか。髪もちゃんと唐風に結い上げてかんざしを沢山さしている。
「もえぎ? その姿は? いつの間に?」
「あんたに何かあったら、座玉を返せなくなってしまうからね。ずっと監視していなきゃ」
なんと変わり身の早い娘だろう。
「この座玉は皇帝陛下に献上するのだぞ。ここまで来てしまったら、神社に返すのは無理だ」
「いつの間にか、そんな大きな話になっちまって。あたいは、あんたの足のしびれのためにちょいと拝借しただけなのにさ」
もえぎは大きくため息をついた。
「まあ、成り行きでそうなってしまったのだ」
「乗りかかった船だ、あたいも玉を追いかけて船に乗って唐の国まで来てしまった。仕方ない」
もえぎはにやりとしながら、手早く座玉を包み、駆け寄った役人に丁寧に渡した。しとやかな所作といい、艶やかな宮女姿といい、最初に女盗人(ぬすっと)として会ったお転婆な少女と同じ人物とは思えない。
鮮やかな薄紅色の裾をひるがえし、もえぎは居並ぶ宮女たちの中にまぎれてしまった。
第五章 謁見
黄どのが皇帝陛下に、倭国から帰ったことを報告する日がやってきた。長安に到着してから十日ほど経ってからのことだ。
皇帝陛下の居城は大明宮と呼ばれ、堅固な城壁に囲まれている。
南正門として丹鳳門(にほうもん)が巨大な姿で建っている。丹鳳とは赤い鳳凰、赤い朱雀のことである。
上層の楼では宴会なども行われる。と、昨晩の宿で、黄どのが教えてくれた。
四角い敷地の中に第一正殿として含元殿(がんげんでん)、宣政殿(せんせいでん)、紫宸殿(ししんでん)が立ち並び、含元殿では外国使節との謁見や様々な国家儀式が行われるとのことだ。
大明宮の敷地内には園林区(庭)があり、ひょうたんの形をした池もあり、その付近に建つ麟徳殿(りんとくでん)では、本格的な外国使節との謁見や宴が行われるそうだ。
まず、含元殿の入口までの広大な石畳が白く光り輝き、目を射る眩しさだ。
石畳の両側に兵が一糸乱れず居並ぶ。
殿の入口には、厳かな細かい細工を施した鎧兜(よろいかぶと)を身に着けた番兵が両側に立っている。
いよいよ中へ足を踏み入れると、真紅の敷物の上にペルシャ絨毯という凝った模様の敷物が重ねられ、正面に続いている。壇上の豪華な席が皇帝の座る玉座だと思われる。
その玉座といったら、五人くらいはゆったりと座れそうに大きく、背もたれにも肘を置く両翼にも霊獣の飾りがふんだんに施され、まばゆいばかりだ。
玉座に向かう通路の両側には、足元に黄金をあしらわれた巨木のような柱が何本も立っている。柱と柱の間には、太い蝋燭が何本も据えられる燭台が置かれ、昼間でも薄暗い宮殿の中を照らしている。
そんな空間に、おびただしい宮廷の役人たちが居並んでいる。彼らは官位ごとに異なる色の衣を身に着け、冠のカタチもそれぞれ異なる。両手で笏(しゃく)を持ち、玉座に向かって微妙な角度で腰を曲げて顔を伏せている。
外側に居並ぶのは、話に聞く皇族の側仕えを務める宦官(かんがん)だろうか。ちらほら見られる宮女もまた、前かがみの姿勢で一様に顔を伏せて少しも動かない。
(立礼では、皆、疲れることだろうな)
紫紺郎は思った。
(俺は地方の役人だから、祖国の平城京へも行ったことがないが、町の造りは長安を参考に造られたと聞く。天皇陛下の宮殿も、こんな感じなのだろうか?)
あまりに大がかりな臣下と宮廷の様子に、紫紺郎は委縮するというよりは呆気に取られていた。
第六章 滋宗皇帝
「皇帝陛下のおな~り~!」
文官だかなんだか分からないが、役人が壇上で叫んだ。
間もなく大勢の共に従われた、黒地に金糸銀糸の刺繍の衣装の青年が現れ、玉座に着いた。
「皇帝陛下にご挨拶申し上げます」
殿の中の役人たちは、ひざまずいて一斉に頭を下げる。紫紺郎も慌てて同じようにした。黄どのもきびきびとひざまずく。
青年皇帝の手のひらがわずかに動いた。それを合図に一同は立ち上がった。
役人たちが順番にひとりずつ皇帝の前に出て報告していく。
「次、倭国から帰還した黄文官!」
ようやく黄どのが前に出て、笏を持ったまま座礼をする。
「倭国への使者、ご苦労であった」
皇帝の声が聞こえた。多分、そう言ったのだろう、と紫紺郎は推測した。黄どのが、
「倭国の天皇陛下より献上の品々を持ち帰りました。それと、今回は誠に珍しき品を持ち帰りました」
宮殿のあまりの壮麗さに、紫紺郎は忘れそうになっていたが、今回の旅は、正座してもしびれないための紅い座玉を献上するためなのだ。そして、引き換えに倭国が潤うように豊富な産物をいただけるよう契約を取り付けるのだ。
紫紺郎は自分に喝! を入れるために心の中で頬を打った。
「珍しき品とは?」
「正座される時に、膝の上に置いておけば長い間座っていても足がしびれないという便利な紅い玉でございます。これを所有していた倭国の役人が持参しております」
「なに? 長く正座してもしびれぬとな? それは重宝するのう」
皇帝の瞳が輝いた。
「倭国、丹後の国の役人で成山紫紺郎と申します」
「紫紺郎と申すか。はるばるご苦労であった。宴の席でさっそく試してみようぞ」
第七章 宴の席で
翌日、麟徳殿で宴席が設けられ、紫紺郎は珍味が並んだ豪華な膳を前にした。
意外といえば意外だったのが、宴席の行われる広間が広大な畳敷きであることだ。祖国でも、畳敷きの家は身分の高い者の家に限られているが、こんなに広大な畳敷きの間を目にするのは初めてだ。
滋宗や、朝廷の役人たちも膳の前で美しい所作の正座をしている。
滋宗は謁見の際に言った通り、正座してから紫紺郎に声をかけた。
「紫紺郎。正座しても足がしびれぬ紅い玉とは?」
「はは、今すぐ」
代わりに黄どのが答え、宮女に指図した。
ひとりの年若い宮女が、盆の上に布をかぶせた品を捧げ持ち、滋宗の前に運んできた。髪をふたつにわけて、輪のカタチに結い上げた華麗な髪型、薄絹の衣を着こなした宮女は、またもや――もえぎではないか。視線は伏せ気味に、唐の言葉の受け答えもしっかりこなして、すっかり宮女になりきっている。
(いつの間に宴の席の出入りまで許される立場になったのだ? いったい、もえぎという少女は?)
もえぎは滋宗の側仕えの宮女に玉を渡し、正座した膝に玉を乗せた。
「まずは皆と杯を」
ひとりひとりの杯に酒が注がれ、滋宗が重そうな袖に手を添えて、杯を高く捧げた。一同もならって杯を捧げ持ち傾ける。
「では、心ゆくまで膳と酒を楽しむがよい」
高官たちは膳に箸をつけ始めた。
しばらくして、滋宗が、
「おお、足がしびれぬという玉は具合がよい」
と言って立ち上がった。
「この通り、すんなり立ち上がれる。足の痛みもない」
「陛下、よろしゅうございました」
「黄文官と、紫紺郎どのに褒美をとらせよう。何でも好きなものを申すがよい」
黄どのは、
「恐れながら……、紫紺郎どのの望みを叶えて差し上げてくださいませ。それが私の望みでございます」
「これはまた殊勝なことじゃのう。では、そういたそう。紫紺郎どの、望みを申してみよ」
「有りがたき幸せにございます」
紫紺郎は、しびれを我慢して正座の向きを変えて、陛下に向き直り、床に額をつけて礼をした。
この時ぞとばかり祖国の庶民の窮状を訴えた。望みは思ったより叶えられ、紫紺郎は唐の国に来てから初めてほっとした。
第八章 泣き言
滋宗皇帝は、宴の後日、紫紺郎を召した。
皇帝の私室に呼ばれた紫紺郎は、またしても緊張この上ない。
私室にも美しい畳が敷かれている。
皇帝はくつろいだ衣で正座して書机に向かっていた。膝には紅い玉が置かれている。側仕えの報告を聞いて向き直り、人払いしてから通訳だけを残した。
通訳の官には、「内容を口外すれば、厳罰に処す」と念を押した。
通訳以外、ようやくふたりきりになったところで、
「こんな日々は、もうイヤじゃ~~」
突然、泣き崩れた。
弱気な皇帝とは聞いていたが、紫紺郎はおろおろしてしまった。
「陛下、いかがなされました?」
「そなたも、風聞により知っているやもしれぬが、朕(ちん=私)は名ばかりの皇帝じゃ。実権を握っているのは母親の白(はく)皇太后なのじゃ」
滋宗皇帝の実母、白皇太后は、夫の皇帝亡き後、息子に位を就かせたが、形ばかりの皇帝位にすぎなかった。近い将来、皇太后自ら皇帝の座に就くべく、実家の血筋の者ばかりを政(まつりごと)の役人に登用し、反対派は躊躇なく排除している。
紫紺郎は思った。
(皇帝母子の確執は思った以上だ。しかし、見知らぬ倭国人にこんなことを打ち明けるとは、よほど弱気になっておいでのようだ)
滋宗は、袖で涙をぬぐった。
「情けない皇帝と思ってくれてよいぞ。この紅い玉は母親の機嫌を取るためにちょうどよい。母親も正座する時のしびれに悩んでいるのだ。献上するつもりだが、よいな?」
(ええ? 猛々しい皇太后に献上する? よけいに取り戻すのが難しくなるではないか!)
紫紺郎は全身から焦りの汗がにじみ出た。
しかし、大唐の皇帝陛下に「否」と言えるわけがない。
第九章 皇太后
滋宗は、母親の皇太后に日取りの伺いを立てて、紅の玉を献上することにした。
これ以上、今まで尽くしてくれた旧臣に厳しい命を下したりしないでほしいという願いを込めて――。
皇太后は初老なので派手な色の衣は着けなくなっているが、衣地には刺繍は一流職人が針を運んだ手の込んだ柄が施され、髪飾りも一流の品を着けている。
いつもの不愛想な表情で、畳の部屋に正座して息子を待ち受けていた。
滋宗がやってきて、ひざまずいて手を組んだ。
「皇太后陛下に拝謁いたします」
「楽にいたせ」
滋宗は、正式な所作でゆっくりめに正座した。
「この度、倭国に遣わせていた文官が帰りました」
「ふむ」
「その文官と共に、おおいにご満足いただける品を、持ち主だった倭国人自ら赴き献上いたしましたので、皇太后陛下に是非ともお使いいただきたく……」
「満足する品とな?」
皇太后の表情が少し興味を示した。
女官が、盆の上に乗せた品を忍び足で持ってきた。滋宗が被せてあった布を取ってみる。紅色の大きな玉だ。
「これなる玉を膝に乗せれば、正座が長引いてもしびれませぬ」
「しびれぬとな?」
皇太后の目が見開かれる。
「いぶかしい品ではあるまいな?」
「実際に朕(ちん=私)が使わせていただき、効果を確かめました。倭国の由緒ある神社の玉だということで、長く正座してもしびれを感じませぬ」
「それが誠なら良いことだが、何ゆえ、そのような効力がこの玉に?」
「それは謎だそうでございます」
「なんと摩訶不思議(まかふしぎ)な……。それではためしに使ってみるとするか」
皇太后の正座の膝に、ふたりの女官が両側から手を添えて、そっと玉を置いた。
「ずっしりと重い。これは珊瑚でできているのか?」
「それも不明です」
「……しばらく写経する。下がってよい」
皇太后は書机に向き直った。滋宗は廊下まで下がって待った。
第十章 しびれ
「……」
微かにうめき声がするので、下がっていた側仕えの宦官が声をかけた。
「皇太后陛下、お呼びでございますか? 陛下?」
応えがない。側仕えが扉を開けると、皇太后は書机にもたれかかるようにして目元をしかめて額に汗していた。
滋宗も驚いて部屋へ入り、皇太后の元にひざまずいた。
「母上!」
「膝の上の玉をどけよ。重くてかなわぬ……」
宮女もふたりやってきて、膝の玉を持ち上げたり汗を拭いたり、ひと騒ぎ起こった。
座玉は、書机の脇の置台に戻された。
「ふうう、しびれないどころか、足が押しつぶされるかと思うたぞ。これはいかなるわけだ、陛下」
「そ、そのようなはずは……。玉は朕が使った時に、確かにしびれから救ってくれました」
皇太后は、厳しい剣幕で振り向いて、眉のつり上がった顔を見せた。
「おとぼけなされても無駄でございます。陛下はわらわのかねてよりの政策や人事に不満を持たれて、このような嫌がらせをなさったのでしょう!」
滋宗は青ざめて畳の上に顔を伏せた。
「お鎮まりください。決してそのようなことは……」
「いや、そうに違いない。わらわが大半の政を行い、そなたはそれに従っているだけ。臣下や民は垂簾(すいれん)政治と申している。それは腹立たしいことであろう」
「朕はただ、しびれに悩んでおられる母上のお御足(みあし)を楽にしてさしあげたかったまでのこと」
「誠にそれだけか?」
目力の強い眼が滋宗をとらえた。
「ただ、今まで尽くしてくれた旧臣に厳しい命を下したりなさらぬよう……」
「それ見よ、交換条件があるではないか。このような役に立たぬイカサマな品を持参した自分の罪を棚に上げ――」
勢いで立ち上がった皇太后は、足を押さえてくずおれた。
「くくう、いつもよりひどいしびれじゃ。侍医を呼べ!」
医者が呼ばれることになり、滋宗は一旦、退散した。
第十一章 もえぎの玉
玉を献上された皇太后が、ひどいしびれを起こしたと聞いて、紫紺郎と倭国に遣いに来ていた黄どのは驚きふためき、ふたりで皇太后の元へ参上した。
侍医の話では、皇太后は御年も御年ゆえ、二、三日は安静が必要だということだ。
皇太后の部屋の外でふたりは正座し、床に額をつけた。
「陛下、お見舞い申し上げます。この度の不始末、なにとぞ、なにとぞ……」
背後から滋宗もやってきた。
「母上、朕からもお見舞い申し上げます。この者たちに何とぞ、お情けあるご措置をお願い申し上げます」
滋宗は先日の弱気はどこへやら、皇太后が答える間もなく部屋へ入った。皇太后は寝台に伏していたが、驚いて顔を上げた。
「まずは痛められたお御足に、良きものを持参いたしました」
若い宮女がまたもや、布を被せたものを運んできた。滋宗にそっと渡す。
重そうな丸いものが、皇太后の寝具の上に置かれた。
「これは、先日の紅い玉ではないか! そなた、そこまでわらわを苦しめたいのか」
「とんでもございません。母上なしでは、皇帝の務めは果たせませぬ。ご健勝でいていただきたい気持ちに偽りはありませぬ」
「そのようなことを申して……。うむ?」
皇太后の表情が和らいだ。
「何やら、寝具の上に乗せた玉から温かさが、じわじわと……。うむ、これは心地よい……」
皇太后の寝具の上に紅い玉を乗せた若い宮女が紫紺郎をふりむいて、いたずらっぽく笑ってみせた。
(もえぎではないか! ついに皇太后の私室出入りの宮女にまでまぎれこんだか)
しばらくして、皇太后の下半身はすっかり温められ、しびれが取れるばかりでなく持病の足の痛みまで取り去られた。
紫紺郎はその報告を聞いて、心の底からほっとした。
(やれやれ、これで首がつながった~~~)
紫紺郎は倭国に帰ることを許され、寧波の港に戻ってきた。倭国への船を待っていると、またもや少年の船子に戻ったもえぎを見かけた。
「もえぎ! お前のせいで首が飛ぶところだったではないか。紅い玉はどうした?」
「皇太后さまが気に入って手放さないものだから、代わりの玉を置いてきたよ」
「代わりの玉とは、偽物か?」
「大丈夫、ちゃんと温かくなる玉だから」
「いったい、お前は……」
「あたいかい? あたいは籠神社を護る役目の、海都一族の者さ。五色の玉が正座の時のしびれを起こさないなんて噂が立っていたから、仲間と警戒していたら、お役人さんと出くわしたのさ」
悪びれず答える。
「もしかして、あの玉は最初から偽物……?」
もえぎは頭をそびやかし、
「しびれないと思えばしびれない。偽物だと思えば偽物。本物だと思えば本物。人間なんてそんなものさ。思いこみひとつで結果は変わる。あの玉だって人によって何色かに変わるかもしれないよ」
「そんないい加減な……」
「でも、正座の発祥の地、大陸の正座が見られて良かったじゃないか」
港の混雑へ戻ろうとする。
「おい、倭国へ帰らないのかい?」
「今度は波斯(ペルシャ)の国へ行かなきゃならないんだ。お役人さん、ご縁があったら、丹後の国でまた会おうね!」
ひとつに結わえた髪をぴょんとさせて、軽い足どりで走り去った。




![[210]正座先生ギャラクシーと星が丘高校茶道部](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)



