[265]甕覗(かめのぞき)色に魅せられて
 タイトル:甕覗(かめのぞき)色に魅せられて
タイトル:甕覗(かめのぞき)色に魅せられて
掲載日:2023/10/31
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
中二のちぐさは、亡き母の実家に遊びに行き、大きな水甕があることに気づく。中には明るい水色が見え、藍の絣に袴すがたの書生が正座する姿が見える。
ちぐさは一年前に新しい母となった藍華を、まだ「お母さん」と呼べずにいることを悩んでいた。
水甕の中で正座していた書生が、夜中に枕元に座っていて、正座の所作を教えてくれる。それは日舞の師匠である継母から教わる所作と同じだった。

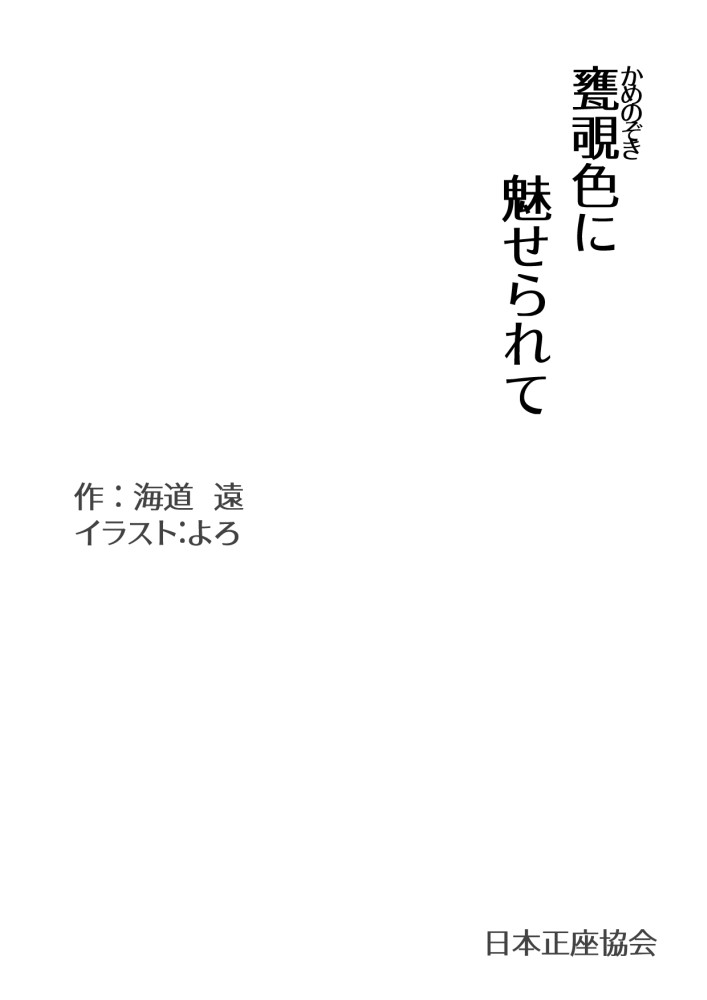
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 母方の実家
思春期真っただ中の中学二年生のちぐさは、白い帽子の大きいツバを持ち上げて上を向いた。夏空に白い雲が輝いている。
愛猫の角エモン(かくえもん)の入っているキャリーバッグと荷物を持ち直す。
母方の実家の周りには、青々とした畑と水田が広がっている。幼い頃から夏休みや冬休みには母親に連れられてきた。
(今はもう、お母さんの姿はどこにもないけれど……)
ちぐさは到着した時、藤の木の側に置かれている小豆色と灰ねず色の大きな水甕に気がついた。蔦(ツタ)に巻きつかれていて年代を感じる水甕だ。
藤の花の時期は終わり夏の青葉が繁っているが、花の盛りの時期も、ちぐさはよく知っている。かんざしの飾りがたくさん垂れているみたいでとても優美だ。
(藍華さんも日舞の舞台では、藤の花のかんざしを髪に飾って踊るのかな)
美人で日舞の踊り手の継母、藍華のことを思い出した。
水甕に目を戻す。
(こんなのあったかしら? 古い水甕だわ)
足を止めたが、見覚えがない。
キャリーバッグから顔を出したトラ猫の角エモンが、ちぐさの胸を伝って飛び降りる。しなやかに水甕の竹製の蓋の上に飛び乗った。
「あ、角エモン、だめだめ」
玄関が開いて、伯父と伯母が飛び出してきた。
「ちぐさちゃん、いらっしゃい! さっき、藍華さんから電話があってびっくりしていたところよ」
「うちに来るのなら言ってくれれば、トラックで迎えに行ったのに」
伯父と伯母は、久しぶりに会う姪を喜んで迎えてくれた。
「暑かったでしょう。バス停から、ずいぶん距離があるから」
「さ、涼しいお座敷でゆっくりしなさい」
「ありがとう、伯父さん、伯母さん。藍華さんから電話があったの?」
ひんやりする土間からサンダルを脱いで上がった。
「そうよ。送って行きたかったけど、仕事で行けずに申し訳ありませんって」
「私が急に言い出したから、送ってもらわなくて大丈夫。もう中二ですもん」
ちぐさは、伯母が運んできたコーラをストローで吸った。
「ああ、美味しい! 生き返ったわ」
見慣れた、懐かしく広い座敷だ。
壁の上方には代々のご先祖さまと祖父、祖母の写真が飾られている。優しかった祖母の隣には、曽祖父の写真。厳格そうなヒゲを生やしている。
「ちぐさちゃん、一年前のご両親の結婚式で会った時より、グンと背が伸びたわね」
「どうだ、新しいお母さんの藍華さんとはうまくいってるか?」
尋ねる伯父の膝を、伯母がポンと叩いた。
「うん。藍華さんは優しいし、ちゃんとした女性よ。亡くなったお母さんの命日やお盆には必ず一緒にお墓参りへ行ってくれるわ。お仕事も頑張ってるし、お料理は美味しいし、時々教えてくれるわ。お父さんがお休みの日は、三人でピクニックへ出かけたりするの」
ちぐさは元気よく言ってから、言葉を切った。
「でも……。まだ『お母さん』って呼べないの」
「そ、それは無理ないわよ。大きくなってから急に新しいお母さんができたんだもの、ねえ」
伯母が助け舟を出した。
「ちぐさの父さんが、日本舞踊のお師匠さんと再婚するとはな」
伯父が目をくりくりさせて言った。ちぐさの実の母親の兄に当たる。
「職場の上司さんに誘われて、日本舞踊の発表会に行って知り合ったんですって」
ようやく陽が傾き、シャワーを浴びたちぐさは、水色の浴衣に着替えた。薄く美しい空色にピンクの朝顔模様だ。帯は赤紫色のを伯母が結んでくれた。
「この浴衣、藍華さんが縫ってくれたの」
「きれいな水色ねえ」
「甕覗色(かめのぞきいろ)っていうんですって。藍染めの最初の段階の藍色なんだそうよ」
「へええ。藍華さんは詳しいのね」
「藍華さんの実家は藍染めのお仕事をしてらっしゃるからでしょう。そういえば、伯母さん、藤の棚の下にある水甕は? あんなのがあったのね」
「伯父さんが納屋で見かけて引っぱり出してきたのよ。水色とあずき色の組み合わせが気に入ったらしいわ。曽祖父さんが、昔に行商人から買ったとか」
「ふうん。ひいお祖父ちゃんが」
ちぐさは正座しようとして、ふと、
「伯母さん、最近は、藍華さんから美しい正座の所作を習ってるのよ」
「美しい正座の所作?」
ちぐさは立ち上がり、正座の所作をして見せた。
「まず、背すじを真っ直ぐにして立ち上がるでしょう。それから床に膝をついてお尻の下に着物を敷いて、かかとの上に静かに座る。両手は膝の上に静かに置くの。これが美しい正座の所作の順序」
「ほう~~、さすが日舞の先生が教える正座は違うなあ」
伯父と伯母は感心した。
「でも、藍華さんから見たら、まだまだなんだって」
ちぐさは小さくため息をついた。
「ただいま~~。ああ、暑かった! おや、ちぐさちゃんじゃないか」
「おじゃましてます。進くん」
従兄の進が高校から帰宅して、その夜は賑やかな夕食になった。
第二章 ちぐさのひとり言
『新しいお母さん――藍華さんは優しい。美人だし、お料理も美味しい。好きなものをたくさん作ってくれるし、たまには一緒に台所に立つことも。
日舞の師匠をしていて沢山のお弟子さんを抱えているのに、ちっとも偉ぶらない。
お父さんとふたりして私に優しくしてくれる。
正座のお稽古もしてくれる。
でも……。
何故だか最近、空を見上げても狭く感じる。子供の頃、校庭を駆け回ったり、鉄棒やブランコをこぎながら見ていた、どこまでも続く広い青い空がどこかへ行ってしまったような?
空がきゅうくつなものに変わってしまったような?
自分の背が伸びたからかな?
もしかして……藍華さんが日舞を強く勧めるせいだろうか。日舞の師匠の跡を継いでほしいと毎日のように強く言う。
「背筋が伸びてませんよ」
指導される時、ちょっと小さくなってる私……』
第三章 水甕の中
次の日の昼下がり、縁側でお昼寝していたちぐさは、セミの合唱の中で目が覚めた。
庭に目をやると、猫の角エモンが水甕を覗いている。竹製の蓋を取り去って前足を突っこんでいる。
「こらこら、角エモン。ダメだって言ったでしょう?」
急いで駆け寄り、抱き上げてから水甕の中を覗いた。
ちぐさの視界に爽やかな水色が広がった。瞬間、顔面に涼しい風が吹いてきたように思った。
「あれ? 水甕の中が明るい?」
空の色が映っているのだと気がついた。今日もきれいな夏空だ。
「なんて明るい水色なのかしら!」
水甕の中にはメダカがたくさん泳いでいる。角エモンには、これが魅力的なのだ。
「角エモン、ダメよ。後でニャンコフードあげるから、メダカさんには悪さしないこと。分かったわね!」
顔を突き合わせると、角エモンは「にゃ~ご」と、ふてぶてしく鳴いた。
角エモンを地面に放して、もう一度、水甕を覗いてみる。
「あれ? メダカと水草以外に何かが見える……」
明治か大正時代の書生姿の青年が、藍色の絣(かすり)に袴姿で正座している後ろ姿だ。青年の涼やかな首すじに、ちぐさは思わず魅入った。
ふと彼が振り向いた。なんとなく親しみを覚える書生だ。
(どうして水甕の中に人影が……)
「ちぐさちゃん、かき氷食べましょう。いらっしゃい!」
縁側から伯母が呼んだ。
「は、は~い」
ちぐさは急いで母家に戻り、水甕の中に見えたもののことを忘れてしまった。
第四章 謎の書生
その夜、ふと目を覚ますと、いつの間にか知らない青年が布団の傍らに正座していた。
「きゃっ! あ、あなた、誰っ?」
慌ててパジャマの前をかき寄せようとすると、青年は涼やかな目元で微笑みかけた。
「やあ、ごめんごめん、驚かせてしまった。昼間、僕のことを見つめていたでしょう。そのお返し」
「昼間? あなたは水甕の中に座っていた書生さん?」
書生はうなずいた。
(え? 私、夢でも見ているのかしら? でも、書生さんは現実に目の前にいるわ)
「僕の名前は天藍(てんらん)というんだ」
「天藍? 珍しいお名前ですね」
「濃い青の色の名前なんだ」
「……」
「僕に会ったことは誰にも言わないと約束して。これから、正座のお稽古してあげるから」
「正座のお稽古ですって?」
(どうして正座の所作に悩んでいるって分かったのかしら?)
ちぐさは首をひねった。天藍と名乗った青年は穏やかに笑った。
「じゃあ、正座の稽古をしよう。パジャマのままでいいから。まず、背すじを真っ直ぐにして立って……」
青年の教える所作は、藍華から習う順番と同じだ。何回か繰り返して、多少は所作がきれいにできるようになった。
いつのまにか眠ってしまったらしい。
目を覚ました時には朝になっていて、青年の姿はどこにもない。庭に飛び出して水甕を覗いてみても、水色の空が映っているだけだ。
「あれ? やっぱり夢だったの?」
しかし、その夜も次の夜も、三夜続けて天藍という青年は現れ、正座の稽古をちぐさに繰り返した。
「迷ったり悩んだりした時には、正座して心を静かにすればいいよ。きっといい答えが見つけられる」
ちぐさが町の家に帰る日が来た。
(思いがけなく広く美しい空を水甕の中に発見できたなんて! 狭く暗い水甕の中にあったなんて! 角エモンに感謝しなきゃ!)
出立する前に、もう一度水甕の中を覗いた。
(なんてきれいな薄い空色なんだろう)
(あの空だ。ブランコをこぎながら近づこうと力いっぱい足を振り上げた水色の空は! 心に沁みる。癒やされる)
天藍という謎の書生が正座の稽古をしてくれた。
(夜中にレディの寝室に現れるなんて、失礼な人だけどね)
ちょっとしぼんでいた心が弾むのが分かった。
(角エモン、いい子ねえ)
ちぐさは、猫のおでこにチューした。
第五章 水甕、割れる
六年の歳月が流れた。
二十歳になったちぐさは、藍華の希望に添って日舞の名取(なとり)(日舞の段階)の免状を取った。
しかし、ここまで来て、日舞を続けるかどうかに悩んでいる。
目下の藍華の希望は、ちぐさの名取のお披露目会に藍染めの着物を着せて発表会を成功させることだ。藍染めは高級品ではあるが、日舞の衣装には使われない。藍華は、それを覆そうという目標を持っていた。
更に、今の流派から独立して「藍染流(あいぞめりゅう)」という流派を打ち立てることだ。
迷うちぐさに藍華は、さとす。
「美しい正座さえできれば、物事を冷静に考えることができます。
迷ったり悩んだりした時は、正座して深呼吸して目を閉じるのよ。私は、いつもそうしています」
(どこかで聞いた言葉だわ)
ちぐさは藍華の勧めるとおり、しばらく古刹(こさつ)(歴史ある寺)めぐりをして、ゆっくり縁側で正座して庭を眺めながら考えた。
結果、「藍染ちぐさ」という芸名で名取のお披露目の発表会をすることを決意した。下の名前は普通、師匠からつけてもらうのだが、藍華が提案してくれた。
「『ちぐさちゃん』という名前は、実のお母様が名づけられたと聞いています。そのまま日舞でも使いたいのなら、そうしてちょうだい。私は大賛成よ」
家元にも、その旨をふたりで報告しに行き「藍染流」という新しい流派も、「藍染ちぐさ」という名前も認められた。
そんなある日のこと――。
藍華の実家の水甕が、何の衝撃も無いのに、真っ二つに割れた、と連絡が入った。
藍染めに使う作業場の甕ではなく、藍染めの品を売る店先に装飾用に置いてあった大きなものだ。
若い藍師たちは震えあがった。かねてから、師匠からは絶対に割ってはならんと言われていたからだ。
割れれば何か良くないことが起こる予兆だそうだからである。
藍華が血相変えて電話に出た。
「うちの店先の水甕が割れたですって?」
目撃していた若い店員が震える声で証言する。
「前ぶれもなく、いきなり……。ヒビは入っていなかったのですが」
藍華とちぐさが急いで駆けつけたが、連絡のとおり、水甕は見事にふたつに割れていた。店先は甕の中に入っていた水でびしょびしょになっていた。
父親と弟子や店員たちは、ようやく拭き掃除を始めたところだ。
しばらくして、藍染めの師匠――藍華の父親が病で突然、倒れた。
ちぐさと両親も病院へ駆けつけるが、師匠は意識が戻ることなく、還らぬ人となった。
「師匠、こんなに突然……」
弟子たちも呆然として泣き崩れるばかりだ。
「あの水甕が割れたのは、この予兆だったのだわ」
藍華が下唇を噛みしめながら洩らした。
お葬式が終わり初七日を済ませると、気丈な藍華は泣くのを止めた。
「ちぐさちゃん、お母様のご実家に行くわよ」
「え? 母の実家に?」
手早く身の回りの品を荷造りし、ちぐさと共に里へ向かう。
第六章 天藍と再会
電車とバスを乗り継いでたどり着いた。
ちぐさの田舎の水甕は、中学生の頃のままの姿で、どっしりと置かれてあった。
藍華は着物が汚れるのもかまわず、水甕の前に正座した。
「藍染の着物での日舞発表会、必ず成功させてみせます。それまでご無事でお見守り下さい」
水甕に向かい、地面に額をつける。
(同じ水甕が母の実家にもあることを、藍華さんは知っていたんだわ)
ちぐさと伯父と伯母は、藍華のただならぬ気迫に見守っているだけだった。
その夜、藍華とちぐさは実家に泊まった。
真夜中、ふたりの枕元に藍の絣に白い袴姿の天藍が現れた。
神妙に正座し、お辞儀する。
「藍華さんのお父様のご不幸、お悔やみ申し上げます。藍染め匠(しょう)のご実家の水甕は、ここの庭の水甕と対(つい)になった品です。これまで割れてしまうと、私の実態が無くなるかもしれません。もう、こうしてお会いすることができなくなるでしょう」
「私が割らせません」
藍華がきっぱり言った。
「藍染めの衣装を着て発表会を成功させれば、天藍さん、貴方の生命力も増すはずです。決して消えさせたりしません」
「藍華さん?」
天藍と母親が、以前からの知り合いのような話し方であることに、ちぐさは気づいた。
「ちぐさちゃん。私は子供の頃に、割れてしまった藍染め匠の水甕の中を覗いて、天藍さんと初めて出会いました。正座の所作を教えていただき、日舞をやるきっかけとなったのよ」
驚くべき過去を打ち明ける。
「わ、私と同じだわ」
ちぐさは中二の夏に、水甕を覗いて美しい水色に出会い、天藍から正座の所作を教わったことを話した。
「ちぐさちゃん、大きくなったね。いや、綺麗に成長したね」
ちぐさは、だしぬけに自分のことを言われて赤くなった。
「あれから六年……。もう二十歳ですもん」
天藍が、更に意外なことを打ち明ける。
「藍華さんのご実家とこの家には、何か『えにし』を感じて、対になった水甕を僕がお売りしたのです。行商人として……。ちょうど曽祖父さんが、ひい孫さんのご誕生記念に水甕を欲しがっておられたのでね」
藍華がうなずき、
「ちぐさちゃんのお母様のご実家にも同じ水甕があると、天藍さんからお聞きして知っていました」
「天藍さん、あなたはいったい……」
ちぐさの疑問は増すばかりだ。
第七章 藍の華
藍華は父を失った悲しみに負けずに始動する。
ちぐさも、何か力になれることはないかと考えた。
「藍華さん。ご実家の藍染めを着させていただくのですから、その工程を見学させてほしいのですが」
「藍染めの工程を? いいわよ。父のお弟子の藍師さんたちに頼んでみるわね」
数日後、ちぐさは藍華の実家で藍染めの工房を見学させてもらった。
(昔、水甕を覗いて甕覗色っていう水色を知った時から、気になっていたのよね)
ベテラン藍師さんは、Tシャツにジーンズ姿のちぐさを迎え、丁寧に藍染めの順序を説明した。ちぐさは一生懸命、メモを取る。
***************
藍染めはタデ藍の葉を乾燥させ、さらに発酵させた蒅(すくも)が染料の元となる。藍は水に溶けない性質なので、発酵させて溶かせる性質にすることで染料になる。
藍汁をためておく藍甕(あいがめ)に蒅を入れて、微生物による自然発酵や化学薬品を用いて水溶性の染料へと還元させる。この一連の工程を「藍を建てる」という。
作業場には、十以上もの藍甕が並んでいる。
染めたいものに藍染の柄を出すための準備をする。「絞り染め」や「板締め絞り」など多くの技法がある。
染料液の表面には、次第に「藍の華」と呼ばれる泡が浮かんでくる。「藍の華」が立ったら染められる合図である。
染めたい物を染料に入れて乾かし、染めたい濃さの色になるまで繰り返す。しっかり洗い流して乾かせる。最後に色落ちしないよう「色留め」の作業をする。
***************
藍師さんから藍染めの技法を説明してもらったちぐさは、鼻をタオルで押さえながら「藍の華」というものをしげしげと見つめた。
目を開けていられないような、藍の迫力ある発酵のにおいだ。それに、沸々(ふつふつ)と沸き上がってくる藍色の泡……。まるで藍色の溶岩口のマグマのようだ。
(藍華さんの名前は、これから付けられたのね)
彼女の沸々と沸き上がる情熱を藍の華に見た気がした。
第八章 家元の説得
藍染め衣装で、ちぐさの名取お披露目の舞台を舞う許しを得るために、家元のお宅にちぐさと藍華は挨拶に行く。
家元の流派から別れたと言っても、本家から分家したようなもので、重要なことは許しを得るのが筋(すじ)になっている。
家元は、頭髪に白髪が目立つが、女ながら長年にわたり家元をつとめてきた舞の流派の筆頭である。
藍華の斬新な願いを黙って聞いていたが、
「藍染めを日舞衣装に使うとは――。本番には藍色だけでは映えません、足りません。お客様に満足していただけるわけがないわ。伝統を破るわけにはいきません」
厳しく突っぱねた。
「破格的なお願いであることは重々、承知しています。どうか、藍染めの衣装に統一して踊らせてください」
藍華は慎ましい正座の所作で三つ指をつき、家元に深く頭を下げる。
家元は眉間を寄せ、
「私が許したとして、何の演目を踊るつもりですか?」
「『藤娘』を踊りたいと思います」
「なんですって? 『藤娘』? 彩り鮮やかでない藍染めだけで、よりによって若い娘が主役の『藤娘』を演目にしたいなどと!」
『藤娘』とは、美しい藤の花の精の舞である。深い物語はない。衣装と衣装の早変わりと舞で観客の眼を楽しませる。
「家元、藍染めの衣装を身に着けた娘を見てやってください」
藍華がちぐさを呼ぶ。
「ちぐささん、お支度できたのなら、こちらへいらっしゃい」
藍染めの藤娘の衣装を着たちぐさが家元の前に出て、しっかり美しい正座で頭を下げる。
「家元、どうか、藍染めの衣装だけでの発表会をお許し下さい」
「なんと……、これは」
家元の眼が見開かれた。
「藍染めでこれだけの華やかさを表現できるとは……。普通の日舞の衣装に勝るとも劣らぬ艶やかさだわ……」
「藍染めならではの濃淡の差を最大限に活かした着物を、藍師の方に何枚も染めて作っていただき、絞りの技法で藤の花を表現していただきました。一番濃い藍色と一番薄い生成り色で、早変わりの見栄えも表現できます。着物だけでなく藤や笠など小道具もそろっています」
藤の花房まで藍の布で細かく作られている。
家元は、ちぐさの頭のてっぺんから足袋の先まで、目力(めぢから)を強くして眺めまわした。
「ほほう……。分かりました。藍染めの素晴らしさとあなた方の熱意、承りました。――小さな規模のお披露目会なら開いてみられたらよろしい」
家元は、遂に藍染めの衣装を許した。
「ありがとうございます。精一杯舞わせていただきますので、宜しくお願いいたします」
藍華とちぐさは家元に深く頭を下げてお礼を言ってから、笑顔で向き合った。
「ちぐさちゃん!」
「藍華さん! お許しが出ましたね」
「『藤娘』、力を入れて指導するわよ。宜しくお願いね!」
「はい!」
ちぐさの心に、甕覗色のような空が広がった。
藍華と共に「藤娘」の稽古に励み始めた。毎日、それを見守る猫の角エモン。
第九章 曽祖父の日記
稽古に明け暮れていたある日、ちぐさの伯父から、曽祖父の日記が見つかったと連絡が入った。
それには、天藍という水甕の精と名乗る青年のことが記されているらしい。天藍は先日、田舎の家で会って以来、忽然と消えていた。ちぐさと藍華は急いで向かう。
「おお、ふたりとも、よくいらした。ご苦労様!」
ふたりが実家に到着した時、伯父は座敷に古い日記帳を数冊、広げて待っていた。
「これがひいお祖父ちゃんの日記なのね」
日記は和紙を紐綴じされたもので、年数を経ているために、少し黄ばんでいた。曽祖父が若い頃から使っていた物らしい。
日付は、ちぐさの生まれた日になっている。
伯父が開いて読み上げる。
『若い行商人がやってきて、水甕を売っているという。ぜひ、この家に置いて帰りたいと言う』
「天藍さんのことだわ。彼が言った通りだわ」
ちぐさがつぶやいた。再び日記に視線を戻す。
『何故だと尋ねても、青年は【この家に縁があるものだからですよ、お守りになりますから、置いていかせてください】と笑って答えるだけだ。ちょうど、ひい孫の女の子が生まれたと孫娘の家から連絡があったばかりだから、水甕を置いていってもらうことにした』
「お守り? 先日、藍華さんのお父様が亡くなる前に、あちらの水瓶が割れてしまったのだけど……」
「水甕が藍華さんのお父さんの急病を告げたのかもしれんな」
ちぐさと藍華は、黄ばんだ日記帳を見つめるばかりだ。
「曽祖父さんと天藍さんは、とても気が合ったらしいぞ。ほら、その先を読んでみておくれ」
『若い行商人はとても人あたりがいい。お互いに気が合って、その夜は楽しく酒を酌み交わした。こんな朗らかな青年がひい孫娘の婿になってくれればなぁ』
「まあ、ひいお祖父ちゃんたら」
ちぐさは頬を赤くした。それから、壁に掛けてある曽祖父の写真に目をやり、話しかけた。
「ありがとう、ひいお祖父ちゃん。ちぐさは天藍さんとお会いできましたよ」
後年、天藍は、ちぐさと予想通りの出逢いを果たしたのだった。
第十章 藤娘発表会
日舞発表会の日がやってきた。
ちぐさは、舞台の中央で正式な所作でゆっくり正座をして、
「藍染めの衣装で踊らせていただきます」
観客に向かって深々と挨拶する。
衣装が全身すべて藍染めの着物なので、観客たちはどよめいた。「藤娘」の演目名だけを発表して、写真まではメディアのどこにも載せていなかったのだ。
「これは、いったいどういうわけなのでしょう? 藍染めの衣装で『藤娘』を踊るなんて、前代未聞ですわ」
「色とりどりの艶やかな衣装を拝見するのを楽しみにまいりましたのに、藍色ばかりだなんて、なんだかがっかりですわ」
観客の奥様方は、踊りを観る前から浮かない表情をしている。
ちぐさが気づいた。
「藍華さん、皆さんのご様子が……」
「大丈夫よ、ちぐさちゃん。あなたが完璧に踊れば、藍染めの衣装も映えますから、皆さんから見直されること間違いないわ」
藍華は胸を張った。
その頃、田舎では――。
ちぐさの曽祖父が天藍から購入したという水甕が、音もなく割れるのを伯母が目撃した!
「水甕が! 真っ二つに! 何もしていないのに?」
舞台上でも大変な事態が起こっていた。
藤の木の太い幹の舞台道具が、舞っている最中のちぐさの背後から倒れてきたのだ。
「きゃあ~~~っ」
上部から無数にぶら下げられた藤の房も一斉に落ちてきて、舞台裏では大騒ぎだ。
「幕だ、幕だ! 幕を下ろせ!」
ちぐさは、足元に引きずる衣装のため、早く動けずに大木の下敷きになってしまった。
天藍が舞台の袖から飛び出してきた。
「ちぐさちゃん!」
「天藍さん。天藍さんね? 観に来てくれていたのね?」
「ああ。君のお披露目を観に来ていたさ! さっき、お母さんのご実家の水甕が割れたのを感じた。そろそろ老朽がひどかったんだ。ちぐさちゃん、しっかり。今、この大木をのけてやるからな」
「大丈夫よ、天藍さん。踊りの続きをしなくては」
天藍は力を振り絞って藤の幹を持ち上げ、その間に、ちぐさは這い(はい)出した。
ハリボテの舞台道具だったので、幸いケガはなかった。藍華が駆けつけてきた。
「良かった、ちぐさちゃん」
伯母から藍華に電話がかかってくる。
「たった今、水甕が割れてしまったんだけど、そちらではなんともない?」
「い、今さっき、ちぐさちゃんが大道具の下敷きになるアクシデントがありました! でも、ちぐさちゃんにケガはありません。踊りを続けます」
舞台裏も観客も大騒ぎになったが、藤の大木は立たされ、ちぐさが衣装の乱れを整えてもう一度、幕が上げられた。
第十一章 甕覗色に魅せられて
ちぐさは、舞の後半、薄い藍と濃い藍の使い分けで早変わりを見事にこなし、藤の大木が倒れてくるというアクシデントに見舞われながら、観客から拍手喝采を受けた。
上演後、ちぐさは藍華と並んで毅然と正座して観客に挨拶する。
「途中で、お恥ずかしいアクシデントがありましたが、無事に『藤娘』を踊らせていただきました。ご鑑賞の皆様には多大なご心配とご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます」
ふたりして神妙に頭を下げた。
「裏方の報告によると、お客様にはひとりもお怪我などなかったとのこと。胸をなで下ろしております。今後は、このようなアクシデントが二度とありませんよう、裏方、踊り手一同、力を尽くす所存でございます」
ちぐさは言葉を選んで挨拶した。藍華が感心するほど完璧な内容である。
「ちぐさっ娘(こ)さん、『藤娘』立派だったよ!」
「藍染めの衣装での『藤娘』、画期的で見応えありましたよ」
観客席から、ちぐさに愛称で呼びかける応援の声が飛ぶ。
「あ……ありがとうございます」
ちぐさは涙声になりそうになるのを堪えてお礼を述べ、改めて顔を上げた。
「ある日、甕覗色に魅せられて藍染めに興味を持ち、勉強させていただき『藍染ちぐさ』と名乗り、日舞の精進を続けて本日、名取のお披露目を舞わせていただきました」
「ちぐさっ娘ちゃん、がんばって!」
観客の声が飛ぶ。
「実の母は物心がつく前に亡くなり、日舞の道へいざなってくれましたのは、隣に座しております継母の藍華でございます。彼女が、日舞の基本である正座の所作と藍染めの美しさを教えてくれました」
「ちぐさちゃん……」
藍華が涙を目にいっぱいためて、娘を見つめ、ちぐさは見つめ返した。
「今日こそ、今まで呼べなかった呼び方で、皆様の前で呼びかけたいと思います」
会場内に、パラパラと拍手が聞こえる。
「ありがとう、お母さん。ちぐさに正座と日舞を教えてくださって本当にありがとう」
藍華の頬を嬉し涙が伝った。
「ちぐさちゃん、こちらこそありがとう。『お母さん』と呼んでくれて」
ふたりは両手を握りしめ、会場内は割れんばかりの拍手の渦に包まれた。
「いよっ、藍華師匠、ちぐさっ娘さん!」
「ちぐさ、藍華、よくやったな」
幕の下りた舞台に、スーツ姿の紳士がやってきた。ちぐさの父親である。
「お父さん! 観てくれたのね」
「ああ。ふたりともよく頑張った。藍華、指導をご苦労だった。ちぐさ、天国のお母さんも喜んでいるぞ」
三人は肩を寄せ合って嬉し涙にくれた。
舞台そででは猫の角エモンを抱いた天藍が、泣き笑いの顔で、ひとり言をもらした。
「『ちぐささんは、藤の精。僕は水甕の精。一緒にさせてください』……って、かなり練習したんだけどなあ。やっと親子三人抱き合ったばかりのタイミングでは無理そうだから、また今度にするよ、角エモン」
そっと足元に角エモンを放した。








