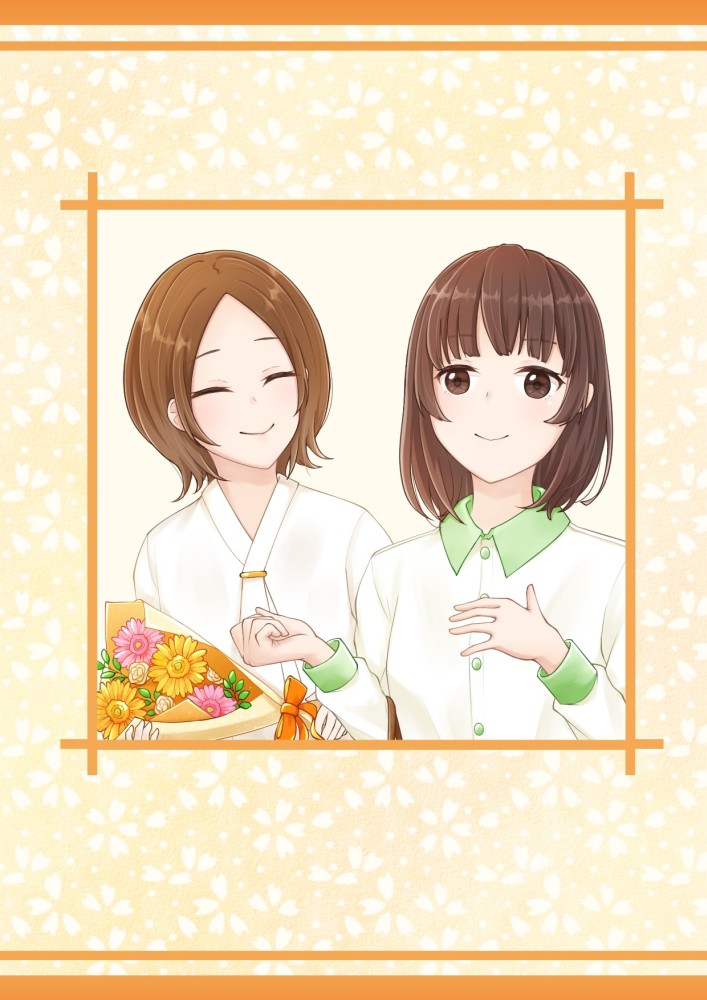[263]お披露目会の正座
 タイトル:お披露目会の正座
タイトル:お披露目会の正座
掲載日:2023/09/23
著者:虹海 美野
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
毎実は夫、高校生の二人の子どもと四人暮らしで、同じ敷地内に両親が住んでおり、平日の弁当作りを親に頼み、パート勤務をしている。
ある日、パート先に高校の同級生だった走子がやって来る。優等生で苦手意識のあった走子だが、毎実のことをよく覚えており、お琴のお披露目会に誘う。
気軽に応じた毎実だったが、お披露目会があるのは地主さんのお宅で、正座だと気づく。
尻込みする毎実に母は正座を事前に練習すればと提案し……。
地元正座シリーズ第二段です。

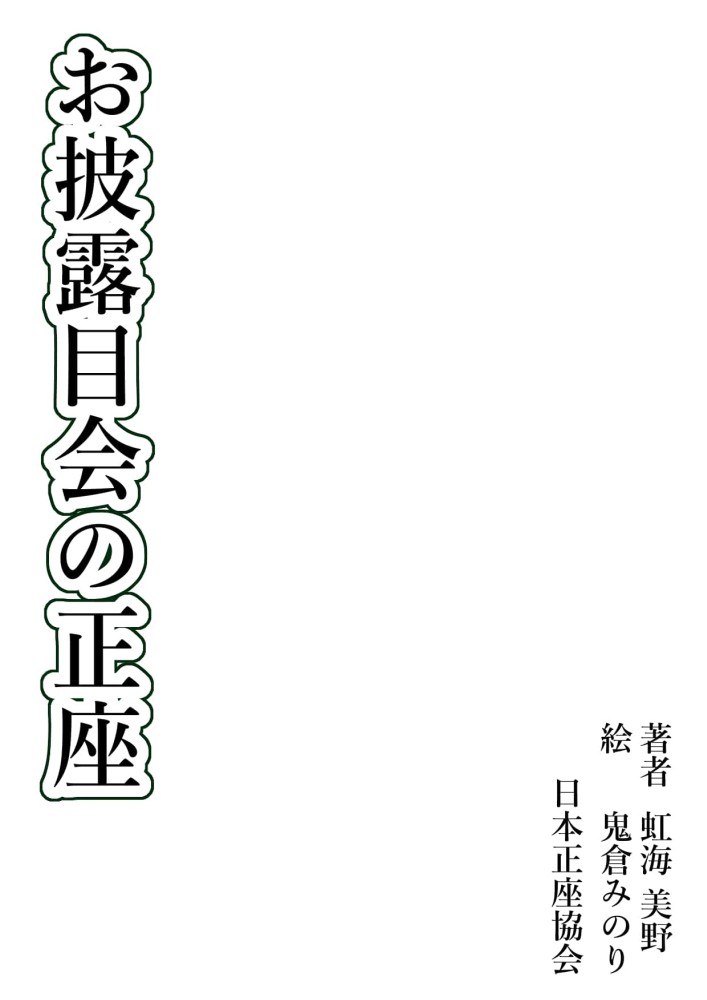
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
毎実(まいみ)は夫、高校生の息子と娘との四人暮らしである。
同じ敷地には両親が暮らしている。
毎実の家族は平日の朝、食事を済ませた後、家を出るとまず毎実の両親の家へ行く。そして玄関に用意された弁当を鞄に入れつつ、出かけてゆく。
つまり、毎実の一家は、毎実の母、毎子に平日の弁当の面倒を見てもらっている。
毎実は実家から離れて暮らしたことがなく、給食の期間を終え、大学での学食、一時期の社食を除き、毎子に弁当を用意してもらい、未だにそれが続いている。言い訳がましいようではあるが、その代わりに、週に何度か、スーパーの目玉商品の豚肉ロースを大量買いして生姜焼きにした日や、日曜の夜に大鍋でカレーを作った日、はたまた持ち帰りでピザを割引購入した日など、両親の夕飯も用意している。幸いというか、普段毎子の一から味付けをする、あっさりとした食事をしている父も、毎子自身も、週に何度かの十代の子二人と同じ食事を喜んでいる様子である。食べる時間は毎実の両親が夜七時前、毎実の家族は八時過ぎ、或いは帰って来た家族で食べ始め、遅くに帰った家族が後で別に食べる。食器は食洗器で洗い、最後に食べ終わった家族が自分の食器を入れて、スイッチを押す決まりだ。翌日の弁当の支度がないので、炊飯器のごはんは残れば冷蔵庫に、食べきれば水につけておけばそれでよい。
毎実としては、このバランスがお互いの心身の健康にいいと考えている。
今日、うっかり寝過ごしたが、前日にパン屋さんで閉店間際、二割引きで買えたロールパンとクロワッサンがあり、前日の残りのシチューをレンジで温め、バナナを一本づつ出して、朝食を整えた。夫も娘もそれほど朝は食べないので、パンに果物程度でもよいのだが、息子が異常なほどの食べ盛りである。ロールパンとクロワッサンは全部で十二個あったが、そのうちの八個を息子が平らげて行った。
家族が続けて家を出た後、お皿を軽く流して食洗器に入れてスイッチを押し、皆が使った洗面所に落ちている髪を掃除機で吸い、ウェットシートで拭く。本来なら今日はトレイとキッチンの流しを掃除してから出勤する予定だったが、帰宅後か、明日に延期を決め、髪にヘア美容液を馴染ませた後にアイロンで整え、簡単に化粧を済ませ、出勤用の服を着ると、大きめのバッグを手に、その内ポケットに入っている鍵で玄関を施錠する。
すぐ隣の両親の家の玄関には、毎実の分の弁当だけが残っていた。
それをバッグに仕舞い、庭に止めてある自転車に乗って、ようやく出勤である。
自転車に乗って、起きてから初めて座ったのが自転車であったと気づく。
実家では昔、座敷で食事をしていた。
寝過ごしたとて、食事の時は座っていたはずだ。
今はダイニングに慌ただしく食事を出し、毎実が見ていようがいまいが、それぞれ遅れぬように食事をし、一応「行ってきます」と言い、出かける。
それに「行ってらっしゃい」と毎実は常に手を動かし、どこかしらを片づけたり、簡単に化粧をしたりしながら応じる。
今日もシチューは家族に出したが、毎実にその時間はなく、パンとバナナ一本を立ったまま食べるのが精いっぱいだった。
そんな慌ただしい朝を過ごす毎実が、まさか立派な日本家屋で正座をすることになるとは想像だにしなかった。
今日は朝礼のある日で、三十人弱の社員が集合する。
そこで、新たなパートさんの紹介があった。
主な業務はパソコンへのデータ入力だという。
パート業務であるが、これまでもずっと仕事をしてきた人に感じるしっかりとした芯のようなものと、自信が感じられた。
慣れるまでご迷惑をおかけするかと思いますが、頑張りますのでよろしくお願いしますと、控えめなあいさつをしたが、恐らく迷惑をかけることはないだろうと毎実は思った。毎実自身はこの会社にパート採用された当初は、経理の仕事とパソコンの操作はわかっているものの、会社自体の流れを掴むまでにずいぶん苦労した。職場の人間関係というものに順応するのが遅かったのだと思う。その点、この新たなパートさんは年齢は毎実と同じくらいといった感じだが、自分の席につくと、早速パソコンの入力業務を開始し、その間に事務員のコピーや電話取りもさりげなく手を貸している。かなりの戦力になる人材であることは、業務開始から一時間足らずでそのフロアにいた全員が確信したと思われる。
毎実は納品された品と請求書とを確認する作業をし、パソコンに入力していく。
きりのいいところで昼休みを取り、社内の食堂へ行った。
朝毎子が用意してくれた弁当を開けると、「もしかして毎実ちゃん?」と声をかけられた。
顔を上げると、会社の入っているビルの向かいにあるパン屋で昼食を買って来たらしい新人パートさんがこちらを見ている。
確かに毎実の名ではあるが、結婚し、子を授かってからは、ほとんど名前で呼ばれたことがなかった。
顔を上げ、暫し首をかしげていると、「覚えてるかな。高校で一緒だった」と相手は破顔する。その笑顔を見て、あ、と毎実は思い出した。
高校で弁当を開けていた時、「すごくきれいなお弁当。お弁当箱も高級そう。育ちがいい人って、こういうところでわかるものなのかもね」と言った同級生の女の子がいた。活発でしっかり者で、十代にやりがちな悪ふざけ、揶揄といった、思い出すと消したくなるような失敗を見たことのない、いわゆる人格者だった。付き合うグループが違っていて、体育の球技のペアや学校行事の時に話したことがあるくらいだった。
「……もしかして、走子(そうこ)ちゃん?」と毎実は訊いた。
「よかった。覚えていてくれて」と、走子はとても喜んでくれた。
「今朝、もしかしたらそうかな、と思ったんだけど、気づいてないみたいだったし、人違いかもしれないと思ったんだけど、お弁当見て、あ、絶対毎実ちゃんだって」
「……よくそんな前のこと覚えていたね」と、毎実は首をかしげた。
そして、高校からどれほど年月が流れたのか、自分たちがもうとっくに大人になっているかを思い出し、恥ずかしくなった。高校当時から、少数ではあるがお弁当を自分で用意している子はいた。まだ、それでも高校生であれば親に用意してもらっても、一般的な範疇であった。しかし、自分の弁当を用意するのを通りこし、家族の分を用意する年代になっているという自覚が毎実にはあった。まさかここで、夕飯はたまに親の分も用意しているからと説明するのは、どうにも言い訳がましいというか、そもそも三食用意している人は世の中にたくさんいる。
いろいろと考えていたが、走子は全く意に介さない様子で、「隣座って平気?」と訊いた。
社員、パートを含め、外食や、昼休みに一度自宅に戻り、素早く食事を済ませ、家の片づけや、軽く夕飯の準備をして戻って来るという人も幾人かいる。
だから走子は昼休みにその時間を自分と一緒に過ごして大丈夫かと気遣ってくれたようだ。そういう人だった、と毎実は思い出した。
2
走子はあっという間に、もう何年もこの会社にいる人のように、欠かせない人材になった。
正社員にならないかって言われるんじゃないの、と周囲は冗談半分に言っているが、そうなる日も遠くないだろうなと毎実も思う。
走子は仕事ができるのはもちろん、物事を明確に伝えるのが上手で、気配りも身についている。
そして何より、理屈でない安心感がある。
毎実より二十近くも年下の社員の女の子は、走子をいつの間にかお母さんと呼ぶようになっている。毎実のことは、毎実ちゃんと呼んでいる。どちらも了承を得てのことだが、ふとこの差はなんだろうと思う。
皆に慕われ、頼りにされる走子だが、昼はいつも毎実と一緒である。
ある時、「いやだったらいいんだけど」と、走子が若干歯切れ悪くというか、やや迷いながら切り出した。
「何?」
「うちのご近所の人がね、お琴のお披露目会をやるから、よかったらお友達も呼んで来てねって誘ってくれたの」
「へえ、お琴、素敵ね」と毎実は言った。
以前子どもつながりの友達に、ダンスの発表会に呼ばれたことがあって行ったが、なかなかに楽しめた。
「そういうの、毎実ちゃん好き?」
「うん、自分は出ないで見たり聞いたりするだけでしょう? それだったら好きだよ」と正直に答えた。
「それじゃあ、お琴のお披露目会、一緒にどう? 私が車で送り迎えするから」
「行っていいなら、そうさせてもらうけど、車出してもらうなら、駐車場代くらいは出させて」と頷きながら毎実は言った。
「ううん、何台でも止められるような広いところで駐車場代は必要ないから。そんなこと、気にしないでよ」と走子は言うと、お披露目会は金曜の午後六時から七時過ぎくらいまでだと教えてくれた。
「ちょうど夕飯の時間くらいになるけど、大丈夫?」
「うん、前日にカレー作るか、ピザでも家族に買ってきてもらうから」と言うと、「いいね。私もそうしようかな」と走子が笑った。
この日は帰りにスーパーの魚屋で取り扱っている握りずしの詰め合わせが三割引きになっているのに出くわした。次々と売れていく寿司の詰め合わせを素早く吟味し、家族、両親の分を買い物かごに確保した。それから今日のお買い得、と出ている旬の野菜をいくつか見繕い、それで天ぷらを作った。
なんとなく、昼間の弁当を未だ親に任せていることを走子に知られていることにうしろめたさのようなものを感じていたからかもしれなかった。
3
家族が帰って来る前に母の毎子を呼んで、天ぷらを皿に分け、寿司の詰め合わせをふたつ渡した。母はエプロンのポケットから紙幣を出したが、「いいから。そういう約束でしょう」と留めた。
そして、走子の話をした。
高校で一緒だった子で、お弁当で毎実だと確信したらしいと言うと、母は嬉しそうだった。まさか、お弁当を覚えていてくれるなんてね、と言いながら、当時何を作っていたかを思い出そうとしていた。
その走子が、ご近所の人のお琴のお披露目会に誘ってくれた、と毎実は思い出して話した。
走子が今も毎実と同じ市内在住であることと、お琴、お披露目会、という言葉に、母は「もしかして……」と、この辺りでは地主さんである家ではないか、と言った。
「知っているの?」と訊くと、「昔、地区のボランティアをしていた時に、とても広い畑があって、そこで子どもたちにさつまいも掘りをさせてくれるっていうおうちがあってね、お母さんはその子どもたちの付き添いのうちの一人で行ったことがあるんだよ」と言う。
「ずいぶん親切なのね」
「そうねえ。自分の畑を解放して子どもたちにおいも掘りさせてくれるんだから……。それで行ってみたら、本当に広い畑なのよ。おいもだけじゃなくて、なんかいろいろ栽培しているみたいでね」
「へえ」と毎実は相槌を打ちながら、家族の分の天ぷらの大皿にラップをかける。
「それでおいも掘りさせてもらって、そのままお礼を言って解散かと思ったら、一休みしていってくださいって、みんなを家に上げてくれたのよ。おいも掘りした後の子どもたちと、付き添い全員をね。お茶まで出してくれて」
「全員入り切れるものなの?」と訊くと、「地主さんのお宅っていうのが、みんながみんなそうかはわからないけれど、柱とか梁とか、本当に立派で、玄関に土間があるのよ。もう、そこだけで、うちなんかのリビングくらいはあったんじゃないかしら。その先の板の間がお部屋かと思ったら、まだ入り口なのよ。その先に延々と座敷があって、大げさな言い方だけど、体育館くらいあるんじゃなかって思うお屋敷」と説明する。
「え、そうなの?」
「うん。だから、お披露目会っていうのも、そのおうちの人がやるのなら、多分ご自宅なんじゃないかしら」
「そういえば、駐車場のこと訊いたら、車いくらでも止められるって言ってた……」
「じゃあ、多分そうね」と母が頷く。
「え、どうしよう……。ただ、お琴のお披露目会って聞いたから、公民館かどっかで聞いてくるものだと思ったのに。そんな由緒あるお屋敷って」
「まあ、向こうから呼んでくれるんだし、しっかりした走子ちゃんが一緒なんでしょう?」
母の中でも、やはり四十代になっても娘の同級生といえば、高校生の姿になるのか、『走子ちゃん』とごく自然に呼ぶ。それに安堵し、毎実は頷く。
「ああ、でもお座敷なんだから、簡単にお作法とか、正座はできた方がいいかもね」と、母が思い出したように言う。
「え、そうなの?」と毎実が目を見開いて聞く。
「この前、お母さん、お弁当屋さんの試食会に行ったじゃない?」
毎実は頷く。
毎日の弁当作りのほかは、これといった習慣もなく、出かけるといえばスーパーくらいの母が、毎実がずいぶん前にプレゼントした服を着て出かけ、大層豪華なお惣菜をいただいたと、いくつものプラスチック容器に詰められたおかずをわけてくれたことがあった。それを機に、母の弁当のおかずも味付けや素材に変化があったので、毎実はよく覚えていた。
「そこでね、お弁当屋さんの試食っていうから、ベンチかどこかで気軽に食べると思ったら、きれいなお座敷でね、ちょっと正座については指導してもらってから行ったのよ。まあ、正座は子どもの頃からしていたというのはあるんだけど、やっぱり事前に指導してもらったおかげで、あちらに行って慌てて座りなおすこともなかったし、おいしく色々いただけたしね」
「……そう」と毎実はやや青ざめた。
今から理由をつけて断ろうか、という思いが過る。
同じ職場で、ほぼ予定は向こうもわかっているだろうし、そもそも事前に興味があるか確認してくれており、その日の夕飯の準備についてまで話している。
今から断わり、その理由が嘘であったとしても、走子は「そうか」と納得し、感じよくしてくれるだろう。それがわかる分、良心が痛む。
「何よ、そんなに心配なら、練習していけばいいじゃない」と毎子が言う。
「うん、まあ」と毎実は頷く。確かに、毎実の子どもたちの逆上がりとか縄跳びとか、そういう新しい挑戦がある時には、「練習すればいいじゃない」と、公園に連れだって行ったものだ。昨今では、下の娘が高校受験を終え、すっかりそうした機会からも遠ざかっていた。塾の送り迎えは行っていたが、勉強に関しては模試や検定のお金を出すようなことばかりになっていた。
「ほら、こっちで」と、毎子が絨毯の敷いてあるところへ毎実を促す。
先に毎子が正座し、見本を見せるようだ。
「背筋を伸ばして。スカートはお尻の下に敷くんですって。それで膝はつけるか、握りこぶし一つ分開くくらい。脇は締めるか、軽く開く程度で。手は膝と太もものつけ根の間にハの字でね。親指同士が離れないように気をつけて」
毎子の言葉に従いながら、毎実も正座をする。
「こんな感じ?」
「そうそう。姿勢なんかに気をつけるようにするといいわよ」
「思ったより、いいわね」と毎実が言う。
「そうなのよ」と、毎子は頷いた。
「年のせいかわからないけど、正座ってなれると、とても腰なんかに楽な気がするのよ。まあ、足がしびれたりしたら、無理しない方がいいでしょうけど」
「そうね。どうもありがとう」と言い、「いいえ」と毎子は言うと、「じゃあ、またね」と立ち上り、「ごちそうさま」と、寿司と天ぷらを両手に去って行った。
4
木曜の夜、夕飯の後に毎実は大鍋にカレーを作った。
ごはんを多めに炊き、これで朝ご飯、兼夕飯にするつもりだが、多分、ごはんはもう一度炊くようだな、と予測する。
案の定、息子が朝からカレーとともにごはんを二合平らげ、残りは一合ちょっとで、帰ってからごはんをもう一度炊くことになった。冷ました鍋と残りのごはんを冷蔵庫にしまう。
まあ、昼食も毎実が用意するのであれば、ゴムパッキンの弁当箱なり、保温容器なりに入れてカレーを各自持参していたかもしれない。娘が嫌がっても問答無用で、嫌ならお小遣いで好きなものを買ってと言っていたところだろう。実際にパート先でも、子どもが反抗期真っ盛りで、おにぎりを作っておいても持っていかなかった、という話も聞く。そういったところでも、毎子の存在と弁当は、毎実にとって大きな救世主である。
いつも通り、身支度を済ませ、各々が燐家に毎子の弁当を取りに行き、そのまま出かける。
慌ただしく、実家の玄関を開ける日も多々あるが、いつもきちんと用意された弁当がそこにある。寒い時期は保温できる容器を使い、暑くなれば保冷剤をつける。小さな別の容器には季節ごとの果物も入っているので、夜、毎実はあまり果物を出さない。季節ごとの野菜や果物は、朝、夜の食卓というより、弁当で子どもたちは気づいているかもしれない。
いろいろと考えをめぐらせながら、毎実は仕事に向かった。
5
走子はいつも通り自身の仕事をしつつ、周囲にも気を配っている。
毎実は残業にならぬよう、経理の仕事に精を出した。
ものすごく忙しい時期ではないが、それでも毎実は万が一にも走子との予定が中止になるのを心配して過ごした。
考えてみれば高校の頃から、テスト前にアンケートだの、ノート集めだの頼まれるのが苦手だった。特にアンケートやノート集めが勉強の妨げになるほど必死に勉強した記憶はないが、予定が複数できるのが苦手だった。だが、走子は委員会や部活でよく代表になっていたが、それを理由にほかの係を断ったり、愚痴をこぼしたりするのを見たことがない。自分のような一般の生徒とは違うのだ、と尊敬と妬みと半々の思いで走子を捉えていたのを思い出す。
その走子に今誘われてでかけるとは、当時の毎実は思いもしなかった。
走子は仕事を終えると、「今から一度帰って、六時過ぎに迎えに行くね」と言い、「毎実ちゃんのおうちって、確かホームセンターのある交差点を右折して、交番を過ぎた先だったよね」と毎実の家を確認する。「駅とか、どっかわかりやすいところまで出るよ」と毎実は言ったが、「そんなに変わらないから。近くまで行ったら連絡するね」と返し、「ありがとう」と毎実が言うと、会社の駐車場に向かって行った。
夕方五時半に自宅に着くと、手洗いし、朝脱いだままになっている部屋着に着替え、米研ぎをして炊飯器のスイッチを入れ、弁当箱を水につけておく。ここまでで第一段階クリアといったところだ。次にバスタブを簡単に流し洗いして、風呂を沸かすスイッチを入れる。部屋の床に落ちている畳まず山になっている洗濯物やティッシュの箱、クッションを一度にかき集め、ソファに放る。明日出すゴミを各部屋から回収し、まとめておく。
ここまでできれば、家の方は上出来である。
走子が来てくれるまで十分弱。
ちょっとした外出用のカラーつきのシャツに、毎実の年でも違和感ないロングスカートに着替える。靴はお屋敷に上げていただくので、脱ぎやすいパンプスにして、ストッキングは新しいものを選んだ。ストッキングを履く前にトイレを済ませる。
座敷に上がり、正座をすることを事前に知っているからこそできた準備だと毎実は思う。
うっかり脱いだり履いたりするのに時間のかかる靴や、座ると裾が膝より上になる丈のスカートを選択しなかったのは、知っているが所以である。
小ぶりのバッグに貴重品とハンカチを入れると、携帯に走子から連絡が入り、数分後に車の停止する音がした。
6
走子はシルクの白いシャツに黒のパンツスーツを合わせていた。
それが体型をしっかり維持している走子に大層似合っている。
気おくれする毎実に、「わあ、素敵。毎実ちゃんはおしゃれして来たのね。とても似合っている」と満面の笑みで言ってくれる。
こういうところも、優等生所以であると毎実は思う。
「今日はありがとう」と言って運転席から走子が開けてくれた助手席に乗り込み、後部座席に花束があるのに気づいた。
「走子ちゃん、途中でお花屋さんかお菓子屋さん、寄る時間ある?」と、蒼白になって尋ねた。
うっかりしていた。
そうだ。
発表会とかお披露目といえば、お花だった。
「ああ、ごめん。先に言えばよかったね。これ、二人からってことにしない? 毎実ちゃんがよければだけど」
「……いいの?」
「うん。多分、お花やらお菓子やら、たくさん持ってくる人がいると思うの。ありがとうって、受け取ってくれる人だけど、細かいところまでそんなに見ることないから。二人でひとつで十分でしょう」
こういうところも、本当に気遣いの人であると毎実は思う。
「ごめん、いくらかな? 半分出させてもらっていい?」
「……ああ、三千円くらいだったから、出してもらいうなら千五百円くらいだけど」
「助かる。ありがとう」と、毎実は車が出る前に手早くお釣りのないようお金を渡す。
「じゃあ、確かに」と走子はそれを財布に収める。
お呼ばれしての贈り物だとかお土産だとかの費用は、だいたい千円、二千円が毎実の相場である。
考えてみれば、走子が連名にしてくれたおかげで、豪華な花束を訪問先にお渡しできる。
なんとか体面が保てたので、毎実は安堵した。
そして、「ああ、携帯、マナーモードにした方がいいよね」と毎実がついでに携帯を出し、「そうだった」と走子も携帯を操作する。
「毎実ちゃん、普段コンサートなんかに行きなれているから、こういうところ本当にきちんとしているね」とさりげなく褒めてくれるところは、先ほどの花束で焦った毎実へのフォローだろう。
「じゃあ、行こうか」
走子は毎実がシートベルトを締めるのを確認すると、車を出した。
7
車の中のBGMは、最近の曲に混ざって、大層懐かしい毎実たちが高校生の頃によく聴いた曲もあった。
「ねえ、高校の頃、校外学習で地元の人に昔の町の様子を聞くってあったよね」と走子が切り出す。
「ああ、あったかも」と毎実はうろ覚えに答えた。
行ったことのない場所だったので、友達と朝駅で待ち合わせをするところまでは記憶にあるが、その後のことは覚えていなかった。
「由緒あるお宅で、結構厳しそうなおじいさんで」
「ああ、そうだったかも」と頷きながら、いつでも堂々として、リーダーとしてあいさつをするのが役目の走子が『厳しそうなおじいさん』と、今になって言うことが少し意外だった。
「おじいさんが部屋に通してくれたんだけど、数人分の座布団なんかないし、言うまでもなくお茶も出ないから、おじいさんが資料を取りに行くって部屋を出たとたん、一人が持っていたお茶を回し飲みしたんだよね。確か、毎実ちゃんが持ってきたの」
「ああ、そうだったかも」
「多分この子、お母さんが出かけに持たせてくれたんだろうなって、思った。いつもアイロンのかかったハンカチを持っていて、クラスで誰かティッシュない?って言う時、大抵『あるよ』って持って来てくれるの毎実ちゃんだったよね。私、そういうのにすごく憧れていたんだ。自分の親も尊敬しているし、ちゃんとやってくれたけど、そういう細かなところで、毎実ちゃんは育ちがでるような、この子、ちょっと特別だなって思うようなところがあってね。だから、いつか子どもに毎実ちゃんちみたいなお弁当を作るお母さんになろうって思ったんだ。実際は、あんなきれいなお弁当は詰められなくて、とにかく満足できる量のおかずを入れて、後は緑と赤の野菜のおかずが入るように気をつけるのが精いっぱいなんだけど」
「え、全然覚えてないよ……」と毎実は曖昧に答える。
「そうそう。それでね、そのおじいさんのお宅に行った時、みんなで慌てて回し飲みをしていた時に、それを持って来てくれた毎実ちゃんがね、『ちゃんと座った方がいいんじゃない』って言ったの。私、全然気づかなくて。ああ、そうだねって。それでみんな水分補給して、正座したんだよね。そうしたら、戻ってきたおじいさんが、『今の学生さんは洋間ばかりで育っていると思ったけれど、お行儀がよいんですね』って、急に優しくなって、その後、資料なんかもすごく丁寧に説明してくれて、やりやすかったの」
本当に毎実は全く覚えていなかった。
ただ、新年のあいさつなど、家族内であっても正座をして「本年もよろしくお願いします」と言う習慣は、かつてあった。そういう時代というか、家庭教育が珍しくはなかった頃だ。
「だから、毎実ちゃんからは、本当にたくさんのことを学ばせてもらったっていうか、こういうふうになりたいって思っていたんだけど、そんなに話す機会もなくて。それがこの年で再会できて、すごく嬉しかった。」
そんなことを言いながら、走子は住宅街の曲がりくねった道を難なく進み、両側に田畑が延々と広がり、大きな山の前に建つ、大層立派な古民家の前のそれはそれは広い庭というか、庭の手前といった何もない場所に車を止めたのだった。
8
母の毎子に聞いていた通り、大層なお屋敷であった。
昔から大事に手入れされた家というのは、こんなにも来る者を心地よくさせてくれるものなのか、と驚く。
歴史あるお屋敷でも、格式ばったところがなく、大きな調度品なども見当たらないが、広い玄関は隅々まで清められ、靴箱にはさりげなく季節の花の一輪挿し。
出迎えてくださった高齢の女性に走子はあいさつして、毎実を紹介し、お花を渡す。
「あらまあ、来てくださるだけでありがたいのに。走子さん、今日はお仕事もあるのに、本当にありがとうね」
高齢のこの家の女性は気さくで、優しい。
この高齢女性の義理のお姉さんが、お琴の先生なのだそうだ。
「もうそろそろ始まる予定なんだけど、姉の到着が少し遅れるんですって。姉を家族が車で連れて来てくれることになっているんですけど……。お茶をお出しするので、座って待っていてくださいな」
そう言うと、奥の座布団の並んだ座敷の方を手で示し、奥へと向かって行った。
走子と前から三列目の誰も座っていない場所に座った。
「そうだ、こういうところではちゃんと座らないとね」と走子が言う。
「毎実ちゃん、そういうところも、本当に昔から変わらない」
「ああ、そうじゃなくて。走子ちゃんに誘われたって言ったら、多分、このお屋敷だろうって聞いて、一応正座はできるようにはしておいたの。最近そういう機会もなかったから」
「ちょっと指導してくれる?」
「あ、ええと、背筋を伸ばして。脇はしめるか、軽く開くくらいで。スカートの場合はお尻の下に敷いて。膝はつけるか、握りこぶし一つ分開く程度で。手はハの字にして太もものつけ根と膝の間に。足の親指同士が離れないようにね」
「こんな感じ?」
もともと姿勢がよく、品のある走子は、今日のシルクのシャツに黒のパンツスーツで正座をすると、マナー教室の講師のように見えた。
「十分」と毎実は頷く。
そこへ人が大勢入って来る気配がした。
毎実と走子は、お茶の用意で大変だろうこの家の女性を思い、そっと台所へ向かった。
「あの、ご迷惑でなければお手伝いさせてください」
「まあ、お客様にそんな……」と、恐縮する女性に、「お琴の演奏を聞かせていただくのですから、これくらいさせてください」と走子が言い、さりげなくお茶の並んだ盆を運んで行く。
「こちらもお茶をお入れしていいでしょうか」と毎実は訊き、並んでいる湯呑に茶を注いでいく。
「あの、もしかして、お母さま、毎子さんとおっしゃいますか?」とふいに訊かれ、毎実は顔を上げた。
「はい……」
「ああ、やっぱり。走子ちゃんのお友達だって聞いていたし、毎子さんに似てらっしゃるからもしかしたら、と思っていたんですけど」と、女性は切り出す。
「もうずいぶん昔になるんですけど、毎子さんが自治会でやっている図書館の係をやってくださっている時、うちの子どもが本を返しに行ったことがあったんです。その日、雨が降っていて、本を返す時に見たら濡れていたんですって。その時、毎子さんが『おばちゃんが拭いておくね』って、ご自分のきれいなハンカチを出して、本をきれいに拭いてくれたそうなんです。その一年後だかに、うちで子どもたちをおいも掘りに呼んだ時、毎子さんがいたって、後になってうちの子が言ったんですけど、お礼を言いそびれてしまって。本当にその節はありがとうございました」
女性は丁寧に頭を下げる。
「いえ、そんな大したことでは。母の方は、大きなお宅でおいも掘りをさせてくださって、おうちにまで上げてくださったと、とても感謝しておりました」
「まあ、そんなふうに言ってくださって。毎子さんも本当にいい方で、こんなにいい娘さんに恵まれて……」
……現実には、未だに弁当を作ってもらい、そのお返しの食事は大概が買ってきたもので、今日ここへ来る前も床にあるもの全てソファに置いて片づけたことにしてきたとは、この女性は想像だにしないのだろう。
なんだかやるせなくなり、毎実は「このお茶、お出ししてきますね」と、台所を辞した。
それから毎実と走子もお茶をごちそうになり、空いた茶碗を台所に下げに行った頃に、先生が到着され、準備が整い、お琴のお披露目会が開始された。
9
お披露目会が開始される直前、座った走子と毎実は、そっと正座を確認し合った。
背筋を伸ばし、脇をしめるか、軽く開く程度。膝はつけるか握りこぶし一つ分開くくらいに。スカートはお尻の下に敷く。手は太もものつけ根と膝の間でハの字に、親指同士が離れないように。広いお座敷で、座布団の間も十分にあったが、正座をして鑑賞していると、やはり周囲との幅に余裕があり、また聴く側としての誠意が伝わる気がする。
幽玄的な調べに、毎実はうっとりとする。
そういえば、こういう時間が最近なかったなと思う。
それにこのお屋敷は天井が高く、しかも昔ながらの日本家屋なので、梁や柱も大層立派意である。こうしたお屋敷というのは緊張するものだが、できる範囲であっても礼を尽くし、こうして座っていれば、とても居心地がよい。
お弟子さんたちのお披露目の後に、大層高齢のお師匠様が今回のお披露目会開催のお礼を述べ、大きな拍手でお披露目会は終了した。
10
「今日はありがとう」と言う走子に、「こちらこそ、本当にありがとう」と毎実はお礼を言う。
「ちょっと遅くなっちゃったけど、夕飯大丈夫?」と走子が心配してくれる。
「ああ、全然大丈夫。今日カレーなの。ごはんもセットしてきたから、帰って来ておなかが空いていれば、先に食べていると思う。走子ちゃんのところは?」
「うちは夫もまだだし、子どももバイトの日だから、全然平気」
「そうなんだ。それなら安心だね。お子さんはお弁当を持っていくの?」と毎実は訊いた。夕飯が遅くても平気であっても、その後弁当の支度があれば、その分寝るのが遅くなる。
「うちね、お弁当は家族で当番制にしたの。前は私も午前までの仕事をしていたんだけど、子どもも高校生になったから、みんなで当番制にしてね、代わりにどんなお弁当でも文句は言わない約束なの。作るのが間に合わない日は、自腹でパンを買うお金を提供するって約束もしているの。ちなみに今の会社に初出勤の日は、私の当番の日で、お金を置いて、各自で買ってもらったから、私もパンだったんだ。私が忙しくなったっていうのもあるけど、もう子どももバイトしているし、お弁当を作るのは時間も労力も必要なんだってわかってほしくて」
「すごくいいやり方ね」と毎実は感心する。
「私なんて、今でも親に頼っているし、走子ちゃんもさすがに驚いたでしょう?」
走子の顔を見られず、毎実は俯いて、これまでずっと気にかかっていたことを訊いた。
「なんで? 誰が作っても、買ったものでも、おいしいと思えて、その人の体に合ったものだったら、それでいいと思う。それに、それを家族が担うっていいことよね。うちは当番制だけど、毎実ちゃんのうちはそうじゃないだけで、ほかの面で毎実ちゃんがフォローしているんでしょう?」
「まあ、大鍋に作ったカレーとか、テイクアウトのピザとか、スーパーのお寿司なんかだけど……」
「すっごくいいと思う!」と走子は言った。
「いろんなおいしいものがあるもんね。それを幅広く食べられるって最高だよ」
ああ、この人の人望とか、優等生的な品性は、基本的に否定しない、肯定的にいい面をすくい取るところにあったんだ、と毎実は気づいた。
気づくまで、ずいぶんと時間がかかった、と思う。
けれど、遅くはない、と思う。
「ねえ、今度会社の帰りに三十分くらい、よかったらお茶しない? ケーキのおいしいお店があるの」と毎実は言ってみた。
「いいね! 嬉しい。それで家族にお土産のケーキも買って帰れば、二度おいしい」
「そうだね、私もお土産に買って帰ろう」
高校生の時より、行動もお金も自由にはなった。
大人としては、ごくごくささやかな楽しみであり、贅沢ではあるが、走子とのこれからの時間を考え、毎実は心が躍った。