[269]課題の正座
 タイトル:課題の正座
タイトル:課題の正座
掲載日:2023/12/28
著者:虹海 美野
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
毎哉は高校二年生。
同じクラスの走太は優等生で皆に好かれている。
完璧な走太が好きになれない毎哉だが、学校の課題で走太と二人、お寺へ取材に行くことになった。
取材の手配もしてくれた走太だが、毎哉にお寺での正座やお作法はどうしようかと相談する。
毎哉はお寺に行く前に、自宅隣に住む祖母毎子に正座を指導してもらおうと提案する。
素直に感謝する走太に戸惑いつつ、毎哉は走太を祖母宅に連れて行き、正座を指導してもらう。
地元正座シリーズ第三段です。

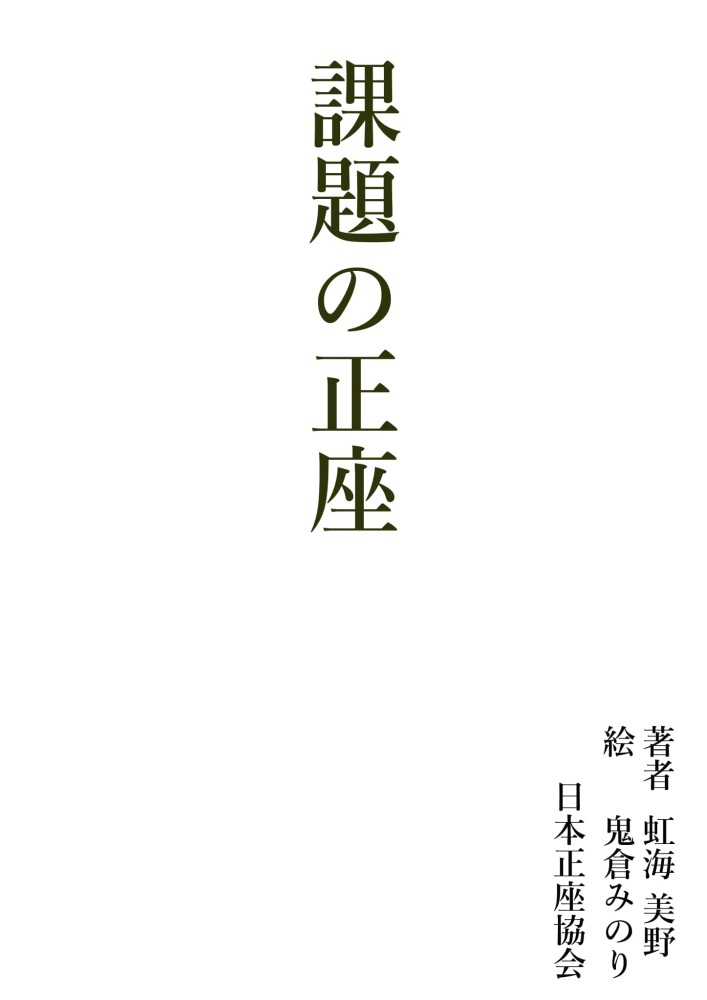
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
足がしびれる、というのがどういうことかを毎哉(まいや)は、初めて知ったように思う。
なんだ、この感覚は、という戸惑いから一分だろうか、二分だろうか、どうにか歩を進めていると、「うっ」と顔をしかめるほどの痛みがやって来る。
正座をしている時、知らず知らず前のめりになり、姿勢が悪かったのがいけなかったのかもしれない。
隣では、どうせ走太(そうた)が涼しい顔をして普通に歩いているのだろうと毎哉は忌々しく思った。
段差に気を付け、どうにか足を靴に入れた。
揃えておいたから、そのまま足を入れられたので、ささやかなマナーが役に立ったと思った。
靴を履き、外へ出たところで、とん、と肩に走太の手が当てられ、ほら、『大丈夫、気にすることないよ』とでも言うのだろうと、毎哉は足がしびれる中でも警戒する。
が、置かれた手は妙にずしり、と体重がかかっている。
横を見ると、いつも清々しい優等生の顔をしている走太が、耳まで赤くなって、足元がおぼつかない。ローファーのかかとを踏んずけて、スリッパみたいにして履いて、引きずっている。
「正座で足がしびれた?」と訊くと、走太は大きく頷いた。
毎哉が優等生の走太の意外な一面を見た時だった。
毎哉は高校二年生である。
毎哉は普通科の高校に入学し、二年生でクラス替えがあり、ここで文系と理系に分かれ、三年ではクラス替えが行われない。
つまり、現在のクラスのメンバーで二度の文化祭だの合唱祭だの体育祭だのという行事に加え、修学旅行から卒業式までを共に過ごす。これは、義務教育を終え、この先の進路をそれぞれに選択できる一見一番よい時期のようで、なかなかに処世術を要する時期である。
それに加え、志望校は国立にするのか、私立にするのかによる三年での授業選択における具体的な説明、及び指定校推薦での内申がどの程度必要かといった話も進路説明のガイダンスで受け、五月から始まる学校見学会の参考にするようにとしめくくられた。
体育館で行われたこのガイダンスに向かう時、すでに出来上がりつつあるグループのひとつに入っていた毎哉は、ここですでにクラス内での居場所確保という観点の第一関門はまあなんとかできたと、安心を得て、すぐに次の大きな進路という関門を前にすることになった。
ただ毎哉の場合は、親にどこそこの大学に入るようにと言われることもないし、逆に親に応援してもらえない進路ゆえにバイトを今からして貯蓄する必要もない。だから、自身の希望と学力とを照らし合わせてこれから考えていこうといったところである。
進路について誰に尋ねられるでもなく、ガイダンスを終えてグループ内の会話に合わせていた毎哉は、その前で、「ねえ、走太くんはやっぱり国立?」と、女子のグループに駆け寄られた存在を見た。
「でも走太くんなら、指定校、どこでも取れそうだよね」
走太のブレザーの袖をさりげなく掴む他の女子。
それに対して、「何人かいいなと思う教授のいる学校があるから、今度見学に行って、できれば個別相談の方も参加しながら考えようと思ってるけど」と、動じる様子もなく、答える。
そして、「すごい、さすが!」という女子の黄色い声に如才なく応じ、何気なく、どこのグループにも入っていないらしい、一人でいる男子に話しかけている。
もともと話し方が上手いのか、そういった経験を積んできたからなのかわからないが、無口そうな一人でいた男子は、走太の問いかけにはさほど肩に力を入れず答える。それに走太が相槌を打ち、短くまた何かを尋ね、そういうやり取りをしているうちに無口なはずの男子は笑って頷き、走太が会話を進める。
自然に走太の周囲は人の輪が広がる。
無口な男子には、何やらとてつもない独学の深い知識があることがわかり、それを走太を取り囲む女子を含めて、認め、称賛し始める。
走太は清潔感があって、背が高い。顔立ちも整っているけれど、それだけではなく誠実さというか、優しさを感じさせる。新学期すぐに行われた実力テストの結果の各教科全て上位三位以内の秀才で、昨日の体力テストも全て最高評価だったはずだ。
おまけに学級委員選出で、どうせくじ引きかじゃんけん、或いはお人よしや、推薦入学を狙っている誰かがやるだろうと思っていたところ、すぐに走太が推薦され、走太は全く抵抗せず、その役を承諾した。一年生の頃より同じクラスだった数人とともに、委員会だか部活だか知らないが、とにかく顔見知りらしいクラスの三分の二ほどが、盛大な拍手を送っていた。
走太に人徳があるのは新学期早々によくわかった。多分、世間の七割以上の娘のいる親世代が、うちの娘の彼氏、お婿さんがこんな人だったら、と言いそうな、いわゆる好青年だ。
そのいい人、という雰囲気が、毎哉にとってはいけすかない。
二年間同じクラスで過ごすのなら、なるべく接点を持たず、せいぜい委員長とか、これから選出する卒業に関する係なんかを引き受けてもらおうと、毎哉は考えていた。
しかし、である。
家庭科の最初の課題は、昭和の歴史を学ぶというもので、先生は何をどう考えたのか、男女別に順不同に二人組を決めた。毎哉は家庭科で調理や家計簿のつけかたについてすぐに学びたいわけではなかった。だが、初っ端から、この課題はどういうことだろう。否、課題自体はそれほど苦ではない。それよりも、順不同で決まった相手が走太である、ということが重大だった。一年生から同じクラスだった友達は、走太と組む毎哉をうらやましがった。いいなあ、走太と組めば絶対評価最高じゃんと言う。まあ、確かにそうだろうが、評価が最高でなくとも、提出のところに可がつくくらいの評価でいいから、別の人と組みたいというのが、毎哉にしてみれば本音であった。
だが、そんな毎哉の想中を知ってか知らずか、走太は優等生的な、実に感じの良い笑顔と口調で、よろしくと言い、具体的にはどうしようかと毎哉の都合や希望を最大限尊重する方向で話を進めたのだった。
ありがたいが、この優等生然としているところが、どうにも毎哉には受け付けない。
だが毎哉ももう高校二年生だ。反抗期のような態度を取ったら、それこそ優等生を困らせる面倒な人だと周囲から思われてしまう。自身でもそう自覚するのは嫌だ。余計に心の負担になる。だから、表面上はありがとうとか、助かるよとか返事をしておいたのだった。
2
とりあえず表面上愛想をよくして、適当に走太との課題を行えばいいという毎哉の目論見は大きく外れた。
最初の段階で走太が課題について相談した際、走太は毎哉にどうしたいかといった希望はあるかという点についても尋ねた。ここで、毎哉は適当に、楽に、という考えが大前提というか、もうそれが言うまでもない決定事項の状態で、何か走太にいい案があれば、その方向で一緒に調べものや資料作りをすると答えた。これは確かだ。確かに、走太は毎哉に確認を取った。
家庭科の課題について、クラスメイトは校内にいる五十代とか、六十代の先生へのインタビューとか、図書室で資料を集めるといった方法をとるようだった。
だから、毎哉もそのつもりであった。多少インタビューした先生や参考資料がほかの生徒と被ろうと、構わない。
だが、走太は「誰か心当たりがあったらでいいけど」と前置きし、この辺りの地域でできるだけ長くある建物、特に歴史博物館など市が管理している場所で館長などを務めている人に当てはないか、と訊いた。そして、できればそういう人物や場所を探してほしいと言う。
何をどうすると、そんなに面倒なことを思いつくのだろう、と毎哉は呆然とした。
図書館でいいじゃないか。
先生で十分じゃないか。
なんでこの校内以外の場所と人を探そうと言うのか。
「できれば、昔の写真なんかも資料に加えて、その場で暮らした人にその場で今話を聞くことに意義があると思う」と走太は言う。
すぐに断りたかったが、すでに話は決定し、進み始めている。ここで、新たな案を出す気力はない。
毎哉は「わかった。おばあちゃんの家がすぐ隣だから、そういう人がいるか聞いてみる」と返事をしておいた。
毎哉は帰ると、自宅より先にすぐに隣の祖父母宅へ向かう。
走太との家庭科の課題のためではない。
毎日の弁当を祖母の毎子が作ってくれているので、弁当箱を返しに行くのだ。一応弁当箱は一人につき二つづつ用意してあって、一日置きで二つの弁当箱を使用する。ついでにいうと母からは、使った弁当箱は自宅で洗ってから祖母に返すようにと言われているが、祖母は「こっちでついでに洗っておくから」と、言ってくれるので、毎哉はいつも母がいないのをいいことに、洗わずに祖母にそのまま弁当箱を返している。
毎子は玄関の郵便受けを開けているところだった。
「おばあちゃん、ごちそうさま。おいしかった」と弁当袋を出しながら言った時、どういう偶然か、地域の歴史めぐりについて特集された市の広報を祖母が夕刊とともに郵便受けから出した。
それを見た毎哉は本当に迂闊にも走太の家庭科の話を思い出し、「ねえ、このあたりで昭和の頃から、っていうか、古くからある建物で、地域に詳しい人がいる場所ってある?」と尋ねてしまった。
祖母は「あらお帰り」と言いながら、弁当袋を受け取り、「そうねえ。ああ、あなたのママが小学生の頃書道を習いに通っていたお寺は? 住職さんもお元気だし、お寺の敷地には公園もあって、今も子どもたちが出入りしているから、聞きやすいんじゃない?」と、これまた簡潔、且つ実に具体的な答えをくれたのだった。
「ああ、そうなんだ……。ありがとう」と毎哉はお礼を言い、祖父母宅と同じ敷地内にある自宅の鍵を出し、玄関を開けた。
これまで毎哉や妹が帰宅する前には家に帰っていた母だが、最近仕事先で高校の元同級生に再会し、時々仕事帰りにお茶をしてくるようになった。夕飯は日によって、スーパーで買ったお寿司や、ピザ屋さんで持ち帰りで買ってきたピザ、前日に大鍋に作ったカレーなど、さまざまである。
今日はなんだろう、と思いながら、洗面所で手を洗った後、食洗器の食器を棚に仕舞い、洗濯物を居間のソファに放った。特に言われたことでもないが、なんとなく、仕事から帰って来た母が座る余裕もなく、それらをしているのを横目にスマホをいじっているのは居心地が悪いので、毎哉と妹は暗黙の了解で、先に帰宅した方がこの二つのささやかな家事だけはやるようにし、後に帰って来た方が最近では風呂掃除をするようになった。
洗濯物を端に寄せ、ソファに座る際、カウンターに置いてあるクロワッサンの袋詰めと、箱買いしてあるペットボトルの清涼飲料水を取りに行き、やおらソファに座った。
スマホをいじり、そうだ、と思い出し、走太に先ほど祖母に聞いたお寺の件を伝える。
返事はすぐに来て、丁寧なお礼とともに、ぜひそこで話を聞かせてもらおうと書かれていた。それに返事をし、やり取りは終わると思ったが、走太はこのお寺に電話をして話を聞けるか、また日時はいつがいいかの確認をしたいので、毎哉の予定を教えてほしいと言う。クロワッサンを咀嚼しながら思案し、できれば休日は外したいが、そこしかなければそれでいいと返事をする。そこで走太からの連絡は一度終わり、毎哉はスマホでゲームを始めた。帰って来た母は、スーパーで特売だったという豚ロースを何パックも買ってきていて、今日は生姜焼き丼にすると言う。多分それに祖母の作った数種類の根菜類の入った味噌汁と、何かしらの果物でもつくのだろう。
毎哉がやっておいた洗濯物と食器の片づけにありがとう、と言いながら、母は明日の朝食予定のクロワッサンがなくなっていることと、絨毯やソファにパンくずがたくさん落ちていることを嘆き、洗面所で手を洗うと、そのまま風呂掃除をして風呂を沸かし、すぐに台所で米とぎをする。妹が帰って来たのが風呂が沸いた直後で、父が帰って来たのが夕飯の準備が済んだ頃だった。
3
お寺へ行くのは、授業が五限までの水曜日、職員会議のある日に決まった。
毎哉は自分の都合を考えて走太に返事をしたが、考えてみれば走太は学級委員をやっていて、毎哉よりもかなり忙しいはずだった。ほかにも学校で何かあるかもしれないし、予備校に通っているかもしれなかった。走太はそういう自分が忙しい、ということを一切こぼさずに、日程を調整してくれていた。
今さらありがとう、とも言えず、わかったとだけ毎哉は返事をする。
「それで、それまでにどういう方向で話をうかがうかとか、そういうのを決めたいんだけど、それとさ、お寺だから、きちんと正座してお話をうかがうことになると思うんだよ。そういう作法みたいなの、どこで教わったらいいかな。……なんか、聞くばっかりで申し訳ないんだけど」
本当に走太は申し訳ない、という顔をしている。
走太は自分の手際の良さや、これまでの段取りをしてきた経緯について、全く毎哉と自身の労力を比較していない。なんというお人よし。
毎哉はそんな走太に内心驚き、「正座だけなら、うちのおばあちゃんが前に料亭の試食会に行く時にお友達に指導してもらったって言ってたけど」と話した。
いつも毎哉の家族四人分の弁当作りを引き受けてくれている祖母の、弁当のおかずや味付けが変化したのに気づき、以前毎哉がそれを訊くと、昔のお友達に誘われて、毎哉でも知っている大きな料亭の弁当の試食会に行ったのだと言っていた。ずいぶんいいところに行ったんだね、と毎哉が言うと、だから事前にお友達に正座を指導してもらったの。おかげであまり緊張せずにいろいろご馳走になって、お土産までいただいて、本当に楽しかったわ、と笑った。普段食材の買い出し以外、あまり出かけない祖母が、そういえば毎哉が見たことのなかった服を着るようになり、お友達と出かけたと言っては、プリンやケーキをお土産に買ってきてくれるようになった。正座だの試食会だのが、祖母の年齢になるときっかけになって、日常に変化をもたらすものなのか……。
「あの、すごく厚かましいお願いで申し訳ないんだけど、その正座やなんか、おばあさんに教えてもらうわけにいかないかな」
走太のお願いに、毎哉はああ、と思った。
ここまで方々に思い至る走太の考えの先を少しは読んで、毎哉からうちでよければ練習して行こうかというべきだった。
けれど、走太は本心から毎哉に頼んでいる様子である。
「ああ、大丈夫だよ。学校から戻る頃には大抵いるけど、一応話しておくから」と伝えた。
「ありがとう。本当に助かるよ」と、走太は心からのさわやかな笑顔で言うのだった。
4
走太を連れて来た毎哉に、祖母は「あらあら毎哉がお世話になっています」とかなんとか、ちょっと緊張して舞い上がり、毎哉の自宅ではなく、祖母の家の方に案内してくれた。
これからお寺に行くからそんなに時間はないと言っているのに、祖母は走太が来るからと、お取り寄せの瓶入りのジュースを開け、ご丁寧にもショートケーキまで出してくれた。
「え、いいよ」と焦る毎哉をよそに、走太は勧められるままにダイニングセットの席に着き、「ありがとうございます。嬉しいです。いただきます」と実に感じよく、そして行儀よくグラスやフォークを手に取った。
祖母は自身には緑茶を入れ、並んで座る走太と毎哉の向かいに落ち着いた。
毎哉の家はダイニングテーブルに誰かしらが使って放置したカップだとか、袋の口が開いているお菓子だとか、そういうものに混じって学校から保護者に宛てた月の行事予定や保護者会や面談の案内などが雑多に置いてあって、食事の前に書類一式は親が簡単に目を通して、保存しておくものは妹用ファイルと毎哉用ファイルに分け、電話台の横の引き出しにしまい、近日再度内容を確認するものは電話台のメモ用紙の下へと振り分けられる。
それ以外は食器はとりあえず流しに、お菓子なんかはもうテーブルの端に押しやっての食事である。
その点、祖母の家は大層きれいに片付いていて、テーブルには小さな白い陶器の花瓶に、庭で咲いていた花を一輪、二輪挿している。
食器も統一され、いつ来客があっても慌てることはない。
そういう点で、まだそれほど仲の深まっていない毎哉を呼ぶにはこちらの家の方が好都合ではあった。
走太は実にきれいにケーキを食べた後、手を膝に置き、「この度は、課題の取材先から、正座のご指導まで、本当にありがとうございます」と頭を下げた。
祖母の毎子は驚いて、「あらあら、そんな。全然大したことをしてないのよ」と顔の前で手を振ったが、「本当に大したことができませんが、ご丁寧にどうも」と改め、頭を下げる。
それから「これからもよかったら、毎哉と仲良くしてね。毎哉のお友達に会うのは、小学校以来かしら」と言う。
「こちらこそ」と丁寧に応じた走太を、毎哉はなんとなく居心地の悪い思いで見ていた。
「高校にもなると、みんな家が離れていることが多いので、そんなに家に行くこともないですよね」
上手に話をつなげる走太に、「おうちはここから遠いのかしら」と祖母の毎子が訊く。
「おばあちゃん、そういうの今、個人情報っていうんだよ」と、毎哉が口を挟むが、「いや、同じ学校だし、こっちは家にまでお邪魔させてもらっているから」と走太は毎哉に言うと、「同じ市内です」と答えた。
「まあ、毎哉の母もね、昔同じ高校で市内に住んでいる人と会社で再会してね、お世話になっているのよ。大人になってからのお友達とはまた違うみたいで楽しそう」
「そうですか。うちの母も、少し前に高校で一緒だった人と会ったって話していました。そういう偶然あるんですね」
そんな会話を毎哉は「そろそろ正座の練習して行かないと」と、切り上げさせた。
祖母の毎子は、「じゃあ、こっちの方に」と、ダイニングから隣の部屋に毎哉たちを案内する。
「それでは、まず背筋を伸ばして」
祖母の毎子は、走太と毎哉を見る。
言うまでもなく、走太は授業中同様真っすぐに背筋を伸ばし、顎も引いている。
毎哉がブレザーの裾をくるぶしで踏んでいるのに祖母が気づき、それを直しながら、「スカートの場合は、広げずにお尻の下に敷くのよ」と付け足す。
「脇はしめるか、軽く開く程度にね。肘は垂直に。手は膝と太もものつけ根の間でハの字に。膝はつけるか、握りこぶし一つ分開くくらい」
そこまでを祖母は確認し、「できているけど、足の親指同時が離れないようにね」と注意を加える。
「ありがとうございます」と、走太は正座したまま、丁寧に祖母の毎子に礼を述べる。
「いえいえ、こちらこそ、毎哉のお友達と会えてとっても嬉しかったわ。これからも、時間があったら、ぜひきてね」
「ねえ、おばあちゃん、そのお寺のお坊さんて、怖い? 木刀持ってて、叩かれたりしない?」
毎哉の問いかけに祖母は、「ええ?」と首を傾げ、「少なくとも、あなたのママが通っていた時にそういう話は聞かなかったけど」と答え、「ちゃんとお話を聞かせてもらおうって気持ちが伝われば大丈夫」と言って、毎哉を安心させた。
そうだった、と毎哉は思い出す。
祖母の毎子はあまり外交的な印象はないが、何か絶対的な安心感が昔からある。毎子に言わせれば、毎哉の両親は、親だからこそ、心配になったり、不安になったりすると言う。もちろん、祖母の毎子もそれは同じだが、孫というのは少し離れたところから見られるのだという。だからか、ごはんの前にお菓子が食べたいとか、ほかのものを買ってもらったばかりなのに、あのおもちゃがほしいなどと言って駄々をこねても、毎子は顔を真っ赤にして怒ることはなかった。いつも穏やかな表情と口調で、毎哉を諭した。諭す時、両の手を握り、その目を見つめ、毎哉が大人しく頷くと、そっと背を撫でた。
この安心が走太にも伝わったのか、「この前考えた質問で大丈夫だよね。ちょっと見てから行こうか」と、毎哉に相談した。
いつもなら、こういう話し方はしない。
自分であらかじめ決めて、毎哉に何かを訊く時も方向性までを見通していた。
なんだか初めて同学年の友達と話した、という気がした。
毎哉は素直に頷いて、そうしようと言った。
二人で事前に用意した質問を確認している間、毎子はまだ広げていなかった夕刊を読んでいた。そうして、走太と毎哉がお寺に行く時には、「昔から小さな子の書道を指導しているお坊さんだから、子ども好きで優しい方よ。安心して行ってらっしゃい」と、送り出してくれた。
5
お寺は山に隣接した昔ながらの大きな家の建ち並ぶ地区にあった。
祖母の毎子が言っていたように、お寺の境内の手前には、大木が枝を広げた黒土の敷地があり、そこにブランコや滑り台、砂場があって、子どもたちが遊んでいた。
公園の入り口近くには自転車が並んでいて、公園の向こうから「ありがとうございました」という明るい声と、「気をつけて帰りなさい。また来週」と子どもたちを送り出す声がする。
習字道具と思しき、ノートパソコンくらいの大きさに厚みのある箱型のケースに持ち手のついた鞄を手にした子どもたちが、次々ととめていた自転車に乗り、住宅街の方へと走ってゆく。
そうした光景を毎哉は懐かしいと思いながら見ていた。
「ここの公園、来たことあるの?」と走太に訊かれ、「多分、ないかな。ちょうどうちの近くの公民館跡の敷地に新しい公園ができた頃だったから、公園ていえばそこだった」と答える。
「そうか」と頷いた後、走太は「ここ、いいところだね」と言った。
お寺のご住職の一家が暮らしている場所である安心感とでもいうのだろうか、新緑の放つ匂いが濃く、風は涼やかで優しく、心が凪ぐ。
「うん」と毎哉が頷いた。
公園を横切り、お寺の方へ行くと、子どもたちを見送っていたご住職が「こんにちは」と二人を見た。年齢は七十代半ばくらい。泰然とした、というのはこういう方のためにあるのだろうと思うような、何事にも動じない故の穏やかさを讃えた人だった。
走太はすぐにお辞儀をし、高校名と毎哉と自身の名前、今日の取材を快諾してくだすったお礼を歯切れよく述べた。隣で毎哉はお辞儀をし、時折走太とともに頷いたりするのが精いっぱいだった。
「まあ、そう緊張なさらず。さ、どうぞどうぞ」とご住職はついさっきまで子どもたちに書道を指導していたと思われる広い部屋に二人を通してくれた。
よく磨かれた廊下や柱、高い天井は毎哉にとって見慣れない室内であった。そもそも築二十年ほどの毎哉の自宅も、築三十年ほどの祖父母の家にも柱というものがなかった。
住職は長机のいくつかを部屋の端に寄せる。
走太がごく自然にそれを手伝い、毎哉も慌ててそれに加わる。
ご住職と走太、毎哉を挟んだ長机を残したところで、ご住職が、「昔の写真があるので持ってきますね」と席を外した。
「今のうちに正座をしておこう」と走太がそっと言った。
「そうだね」と毎哉は頷く。
「まず、背筋を伸ばす」と走太。
「うん、伸びてる」
「脇は軽く開くか、しめる」
「しめてる。しめてる」
「肘は垂直に」
「垂直。はい」
「膝はつけるか握りこぶしひとつ分開くくらい」
「少し開いてるけど、握りこぶし一つ分くらい」
「手は太もものつけ根と膝の間にハの字で」
「ハの字。置いた」
「スカートは広げずにお尻の下に敷く」
「ここは、僕らは大丈夫」
「足の親指同士離れないように」
「大丈夫。ついてる」
走太が覚えた正座の仕方を毎哉が確認していく。
ちょうど正座が大丈夫、というところでご住職がやって来た。
6
ご住職がごく自然に走太と毎哉の向かいに正座をし、アルバムを長机に置いた。
「父の代からのこのお寺の普段の様子を撮った写真です」
ご住職は走太と毎哉の方にアルバムを向け、ゆっくりと開いていった。
最初の頃は白黒の小さな写真が多かった。
「ここの裏山が竹林で、たけのこを毎年掘っています。うちでは掘り切れなくて、今でも声をかけているご近所さんが来て掘っていきますよ」
「この辺りは竹林が多いですね」と走太が訊く。
「ええ、昔はそれこそ、そこらじゅう竹林でした。竹は根が丈夫で地盤がしっかりしていますから」
「このおもちゃはこの頃からあったんですか」と走太は訊く。
たまに量販店で見かけるフラフープやホッピングを、このお寺の前の公園でしている子どもたちの写真だ。
「これは、私の時ではなく、私の子どもの代、お二人のお父さんやお母さんくらいの時ですかね。その前からありましたけど。その後、ローラースケートだのスケートボードだのも出て、それは舗装されたところじゃないとうまくいかなくてね」
アルバムのページとともに、話が進む。
「このおはぎやお赤飯は、ご近所に振る舞っているのですか?」
「そうそう。この頃はね、おはぎやお赤飯、ほかにも畑、今でいう家庭菜園ていうのかな、そういう自宅で採れた野菜だとかね、食べ物のおすそ分けは日常茶飯事だったんですよ。大抵の家には蒸し器や大きな窯があってね。今みたいな電気で炊ける炊飯器ではなくて、ガス窯でね」
「最近は炊飯器を家に置かず、直火で炊いたりする方がいいって人もいるみたいですし、小さな容器を使って電子レンジでも炊けるみたいですね」
「へえ、そうなんですか」
ご住職と走太が主に話し、それを毎哉が漏らさずノートに書き留める。
必要な資料になるか、無駄になるかは走太が取捨選択するだろう。ただ、後で「ねえ、あの話、どうして書かなかったの」と言われるのだけは避けたかった。
毎哉は話しながら、「これ、撮影させてもらっていいですか」と了解を得て、スマホで写真を撮影していく。
ほかにもお風呂は昔は自ら温度を見ながら沸かすもので、今のように電気のスイッチで適温にはできなかったことや、エアコンのない家も多かったこと、パソコンのない時代で何か調べるには、本を買ったり、図書館に行ったりするのが一般的だったことなどをご住職は話してくれた。
それからアルバムの写真で、ご住職がどこかのお宅で寿司やビールなど並んだテーブルで袈裟を纏い、喪服の人たちと写るものが出てくると、昔は一周忌の後も、三回忌、七回忌、十三回忌と法事を行い、そこで一族が集うことが多かったが、今は一周忌の後は、身内だけの墓参りで済ませるご家庭が多いように思うと語った。
一方で、神社で行う神前式の結婚は平成の頃より増えているようですねとも語る。
還暦、古稀、といったお祝い事はどうでしょうかね、と二人を見る。
「祖父母の還暦祝いは、親戚で集まった時の写真があります。僕はまだ小さくて覚えてないです」と走太が答え、「うちは隣に住んでいる祖父母は誕生日に一緒にケーキを食べて、別に暮らしている祖父母の誕生日の近い日に家族で行って外食するか、都合がつかない時にはプレゼントを送ったりしています。だけど、還暦のお祝いとかは、どうだかわかりません」と毎哉も答えた。
「そうですか」とご住職は目を細めた。
「私はね、実はあまり人付き合いは上手な方ではないのですよ」
ご住職の言葉に走太と毎哉はやや戸惑った。
つい今しがた見たどこかのお宅での法事の様子は、とても和やかそうで、ご住職は十分にその場の人と打ち解けているように見えた。
ご住職は「あちこちの檀家さんのお宅でお経を唱えて、仏教についてのお話をしていますし、お習字に来た子どもたちと、お習字以外の話をすることもありますけどね」と付け足す。
「はあ」と走太と毎哉は頷く。
「ですがね、それでもこの辺りだけでなく、少し遠くまで出た先で、檀家さんや、習字を習いに来ていた元生徒さんなんかが見つけて声をかけてくれることがあるんです。そうすると、人とのご縁というのは、やはり大切だと思うのですよ。まあ、少し話は逸れますが、お二人も今の学校を卒業して、何年かして同窓会なんかの案内が来ることもあるでしょう。先ほども言いましたが、私はあまり人付き合いは上手な方でない。こういう時、正直、あまり気が進みません。それでもね、行ってみると、いいものなのですよ。いや、決してお二人や、誰かに強制したくて言っているのではないですが、同窓会で顔を合わせていれば、どこかですれ違うだけだったかもしれない同級生に気づいて、あいさつくらいはするわけです。そういう些細なことが、年を重ねると意外と嬉しいものなんですよ」
ご住職の優しい目を見つめ、毎哉は隣にいる走太のことを考えた。
今でも走太のことはあまり好きではない。
今回の段取りをつけてくれたことに感謝しているし、祖母と対面してもとても感じよく接してくれた。今だって、走太のおかげで八割以上の物事が進んでいる。毎哉だけでは、とてもこうはいかない。
だが、だからといって、何年も顔を合わせず、偶然再会したら嬉しいかと問われれば、今時点で考える未来では嬉しくない。もしかしたら、気づいても、知らぬ振りをするかもしれない。
「この写真も、今回のお話がなければ今日見ることもありませんでしたしね」
そう言いながら、ご住職はアルバムをくる。
「これは、何の集まりですか」と、走太が訊く。
「ああ、これは昔、うちで作っていたさつまいもがたくさん収穫できたので、書道教室の生徒さんや、そのお友達も呼びたかったらどうぞと言って、焼き芋会をしたんですよ。生徒さんのお友達には、事前にここへ来ることをおうちの人に言っておくことだけ約束してもらってね。まあ、子どもがたくさんで危ないんで、焚火でなくて、切ったさつまいもを、火鉢をいくつか持ち寄って焼いてね」
二十人弱の小学生の中に、毎哉は見覚えのあるカーディガンに気づいた。桃色と水色のこのカーディガンは、確か祖母が昔編んだと言っていた。桃色と水色の動物のかたちをしたボタンを使っていて、それも特徴的だった。物持ちのいい祖母の家でそれを見つけた妹が気に入って、昔大切に着ていた。そして、この飴玉のような二つの飾りの髪ゴムで、長い髪をひとつに結んでいて、カメラの方を見ているのは……。
「これ、多分、お母さんです」
呟くように言った毎哉の見る先を、走太とご住職が追う。
「お母さん、ですか?」
「はい」
「この子は、確か、ええと、毎実ちゃん。そう、毎実ちゃん。雪の降った日も、学校の振り替え休日の日も、通って来てくれた生徒さんでしたね。そうですか。そう言われてみると、目元が似ていますね。こんな立派な息子さんがいるんですか」
ご住職は記憶を呼び起こしながら、次第に昔をかみしめるように笑い、それから毎哉を通して母の毎実に話しかけるような口調になった。
7
「また、いつでも来てください」と言うありがたいご住職の言葉に頭を下げ、走太と毎哉は取材に用いた筆記具をしまい、正座のまま、「ありがとうございました」とお礼を言った。
二十分弱の取材の予定が一時間近く経っていた。
そうして立ち上がった時、毎哉は足が大層しびれていたことに気づいた。
なんとか平静を装って公園内まで来たところで、隣にいた走太が毎哉の肩に手を置き、大層難解な表情をしている。
互いに足がしびれていることがわかり、「あのベンチに座る?」と毎哉は訊いたが、「いや、いい。今の姿勢が限界」と言う。
「まあ、確かにそうかも」と言う毎哉も足のしびれがまだ抜けない。
よたよたと、腰の引けた状態で歩いていると、「ああ、よかった」と後ろからご住職の声がした。
不意打ちで、走太と毎哉はさっとなんでもない顔をして振り返った。
ご住職は大きな籠に山積みのたけのこを持っていた。
「たった今、家族が掘ってきたのですが、少しいかがですか?」
ずっしりと重量感のある籠を走太と毎哉は覗きこんだ。
「……いいんですか?」
「ええ、よろしければ」
ご丁寧に籠の下にビニール袋まで用意してくださっている。
ひとつづつ、皮のついた堀りたてのたけのこをありがたくいただき、お礼を言うと、「正座でずいぶん頑張ってお勉強されていましたね」とご住職は言い、回覧板を持って来た近所の人に気づき、「では」と言い、その人にもたけのこをおすそ分けしていた。
恥ずかしさからくる決まり悪さに、走太と毎哉はしばし俯いた。
足のしびれはだいぶ和らいでいた。
8
翌日の弁当は、たけのこご飯に、魚の切り身、肉団子、卵焼き、レタス、キャベツ、セロリ、アスパラのサラダ、別の容器にメロンといちごが入っていた。お寺のご住職にお世話になり、たけのこまでいただいたと知った母は、昔お世話にもなったし、近いうちにご挨拶に行ってくると話していた。
弁当を全て平らげ、購買で買ってきたパンを開けていると、何かの用で昼が遅れたらしい走太が教室に入り、すぐに弁当を開けた。
近くの席にいた女子数人が、「走太くんもこっちに机つけようよ」と、ここぞとばかりに走太を誘っている。初めから教室にいてもそんな誘いを受けたことのない毎哉は、冷めた目でその光景をちらり、と見た。
「走太くん、今日は青椒肉絲? エビチリまである! すごく豪華!」
華やいだ声も毎哉はやり過ごした。
「エビチリは湯せんのパックのだけど……」
へえ、と、ここも毎哉はやり過ごした。
「え、走太くん、これ自分で作ったの?」
「学級委員とか、いろいろ忙しいのに?」
「毎日じゃないよ。週に一回か二回くらいかな。うち、弁当は当番制になっているから。作れない日は、家族分のパンとかを買う食費を用意するって約束。一応、バイトとかだけど、家族みんな収入っていうか、少しはあるから、全員で相談して、そういうふうに決めた感じ。作るなら家にあるものを使って、できるものを作って詰めればいいからさ」
そこで毎哉は走太の方を見た。
どこまでできたやつなんだ! と、嫌味なのを通り越して呆然とする。
周りでは、部活の朝練から放課後まで休まず参加しているとか、連日バイトが入っているとか、家事全般を担っているとか、年の離れた兄弟の保育園のお迎えをしているとか、きっと頑張っている生徒はたくさんいると思う。
だが、学級委員などの忙しい学校活動に加え、バイトという賃金を得られる働き、それに加え弁当、料理という分野を日常的に行っているということ、そして、それが勉強ができて、性格もいい、人気者の走太というところがもう、決定打としか言いようがなかった。
もう、この家庭科の課題の発表が終わったら、金輪際近づかない、と毎哉は決意した。
だが、この日自宅に帰ると、「お邪魔しています」と、自宅のダイニングで母とお茶をしていた、きりっとして、大層きちんとした、母の高校の同級生で今は会社の同僚だという人が、走太の母であることが判明するのだった。








