[270]正座を育てる渾天儀(こんてんぎ)
 タイトル:正座を育てる渾天儀(こんてんぎ)
タイトル:正座を育てる渾天儀(こんてんぎ)
掲載日:2024/01/01
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
正座師匠の万古老が、洞窟の裏山に建てられた白亜の宮殿で、玉帝陛下(宇宙で一番偉い仙人)の命で、渾天儀(こんてんぎ)という太陽系の巨大模型について若者に正座で講義することになった。
弟子の百世(ももせ・女の子)と流転(るてん・男の子)もついていく。万古老は、若い時の青い髪の青年の姿に変身する。
孔雀明王まゆらちゃんと孔雀のピーちゃんまで後を追いかけてきた。生徒の中には朱い髪の少年がいて、麒麟の一種、炎駒(えんく)だと名乗る。
玉帝陛下はやや元気がないようだ。

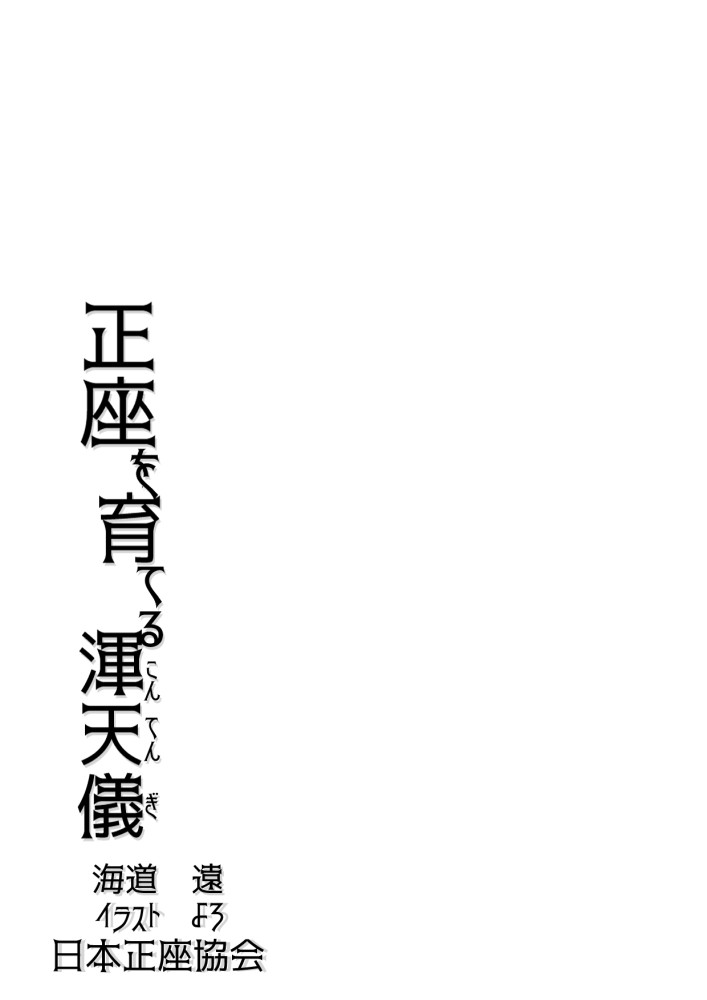
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
長雨の季節に入った。
洞窟の入口で霧のような雨を見つめながら、正座師匠の万古老(ばんころう)は、長いアゴヒゲを触っていた。
木の節がこぶこぶした杖で、岩をコツンと叩いてから、弟子の名前を呼んだ。
「おい、百世(ももせ)、流転(るてん)」
百世は岩の上に座って熱中していたスマホゲームの手を止め、流転は草で編むコオロギ作りの手を止めた。
「わしは、しばらく裏山のてっぺんで生活するぞ」
「え? 裏山の崖っぷちに突然できた白亜(はくあ)の御殿で?」
万古老はうなずき、
「そうじゃ。あれは、玉帝(ぎょくてい)陛下が若者の勉強する学校として用意された建物じゃ。玉帝陛下はわしの正座師匠でもある」
「え、そうだったの。初めて聞いたよ!」
百世も流転も声をそろえて言った。
「お前たちはどうする?」
「お師匠の行くところへついていくよ」
百世がいきいきとして答えた。
「流転は?」
「ボクがお師匠と離れるわけないでしょ。……ってことは、ボクたちも『あれ』について勉強できるんですね」
「そうとも。毎日、正座してな」
振り向いたお師匠の姿は、老爺ではなく藍色の髪を肩まで垂らした体格の良い青年だった。
百世と流転は、目を飛び出させて口をパクパクした。
「今日からしばらく、わし……私のことは、藍万古(あいばんこ)と呼ぶがいい」
第一章 渾天儀
渾天儀は古代中国から伝わる、星の動きを読み解く装置だ。
地球と他の星の動きを読み解き、暦(こよみ)が作られて国の行動が決定される。
操る者は渾天儀師と呼ばれ、宇宙の頂点に立つ玉帝や、人間界の皇帝と深くつながっているが、今となってはほんの少数しかいない。
玉帝の渾天儀は巨大な黄金造りで、大きな輪がいくつも重ねられ、歯車やゼンマイがひっきりなしに動いている。
今回は玉帝の強い望みで、藍万古という青年が若者や子どもの希望者に造りや読み解き方や操り方を教えることになった。しかも、正座による講義が望ましいということで、人間界でも正座師匠を永く永く務めてきた万古老に白羽の矢が立った。
万古老は、かなりな老人の姿をしていたので、『古木竜吟』(こぼくりゅうぎん)とでも言おうか、若く美しい姿に蘇り、大命を担うこととなった。
藍万古と百世と流転は、玉帝陛下の元に挨拶に参上した。
カチンコチンに緊張した百世は、
「こんな思いするくらいなら、洞窟の中で世界一キライな料理の勉強でもしとくんだったよ!」
「もう遅いよ、百世。姿は見えないけど、玉帝陛下は玉座に着かれた気配がするよ」
藍万古が、唇に人差し指をあてて「しっ」とした。
背すじを真っ直ぐに立ち上がり、床に膝を着く。そして衣はお尻の下に敷き、かかとの上に静かに座る。
毎日、お稽古している正座の所作だが、手本を示す万古老の姿が若返ったのと、金ぴかの玉帝陛下の御殿なので、百世と流転は緊張して正座した。
「お久しゅうございます、陛下。この度は大命を拝し、藍万古は背を正す思いでございます」
大きくうなずく気配がした。
「こちらは仙界で拾ったふたつの魂。共に勉強させたく連れてまいりました。よろしくお願いいたします」
藍万古と百世と流転は深々と床に額をつけた。
(玉帝陛下のお気持ちが乱れている気がしたが……)
藍万古は玉座をちらりと振り向いた。
第二章 孔雀明王たちの参加
神仙の者や、人間界からも半永久の命を持つとされる生徒が、五十名ばかり各地から集まってきた。幼く見えても、百世や流転のように何百歳の者もいる。
共通するのは、玉帝の渾天儀を間近で見るのが初めての者ばかりであることだ。白亜の御殿の中で、渾天儀を見渡せる大きな窓のついた教室に移動した。
生徒たちは、渾天儀の巨大さときらびやかな様に驚く。
全体がゼンマイ時計という外観で、あらゆる場所で回転盤が思い思いの方向に回っている。
「これは【渾天儀】という。先人が星の動きを読み解くために作りだしたものだ。中央の巨大な金色の天体が太陽の模型だ」
藍万古の説明に、生徒たちは口をあんぐりするばかりだ。
ゴォン、ゴォンと地響きのような音が、絶え間なく渾天儀の心臓の鼓動のように鳴っている。眺めていると、渾天儀が生き物のようにも感じられてくる。
「大きな仕掛け、まるで生きているみたいだね」
流転が声を震わせて言ったが、百世はまったく別のことを考えていた。
「うちの師匠って、こんなに優秀でイケメンだったんだね」
流転はガクッとした。
「洞窟に住んで正座師匠やってる時は、垢だらけの布を巻きつけてるだけの痩せた爺さんなのにね! 玉帝陛下の信頼を得ているだなんて! 玉帝陛下だよ、仙界も天界も含めて一番偉い方だよ!」
「孔雀明王まゆらちゃんの元カレって信じられなかったけど、今なら信じられるよ」
「ウワサをすれば何とやら。孔雀の羽ばたきが聞こえてきたよ」
タマムシ色の美しい羽根の鳥が、四本の腕を持つ仏像を背中に乗せて飛んできた。
「百世! 流転! どうしてボクたちを誘ってくれないのさ! ズルいぞ!」
孔雀のピーちゃんがふくれっ面をして降りてきた。生徒たちの視線が一斉に集まり、まゆらちゃんがそっと地上に降りて、教室に入ってきた。
「私たちにも教えてくださいな。万古老……。ば、万古老? あなた藍色の髪の藍万古じゃないの!」
「仕方ないなぁ。空いてるところに正座して。そこの孔雀とお嬢さん」
しぶしぶ講義に入れてやった。
「お嬢さんですって。万古老ったら照れてるわ」
まゆらちゃんは、にやにやして緋色の毛氈の上に正座した。
「おお!」
生徒たちが、まゆらちゃんの正座の所作の完璧さに驚いた。
第三章 地球は丸い
生徒たちは、孔雀明王がこなした正座の所作を藍万古から習い、渾天儀の見える大きな窓の周りに正座した。
「これは【渾天儀】という。先人が星の動きを読み解くために作り出したってとこまでは言ったな」
藍万古が説明を続ける。
「先人って、藍万古より先に生きていた人?」
流転が質問した。
「誰が作ったのか、私にもはっきりしないのだ」
藍万古は、長い木の枝を取り出し、渾天儀の中に浮かぶ小さな青い球体を指し示した。
「今までの研究によると、この青い球体が我らの故郷、地球だ」
百世が、
「じゃあ、あたいたちは丸い表面で生きてるってこと? あたい、砂漠の地平線を見たことあるけど、ずっとずっと平たい土地が続いていたよ。丸くはなってないよ」
「そりゃ、我らの住んでいる球体が大きすぎて丸いカタチが感じられないからだ」
ピーちゃんがけたたましく、
「地球って、模型の中じゃこんなに小さいよ。他にデカい球体がいくつもある!」
「そうとも。地球より大きな球体――天体は他にいくつもあるんだ」
「あのう……」
流転がそっと手を挙げた。
「渾天儀は『太陽系』を示しているのですね?」
「おお、さすが流転だな。『太陽系』というものを知っていたか」
「はい。以前、百年に一度くらいやってくる貸本屋の馬車で借りた本で読んだことがあります」
「ほほう」
生徒たちも耳を大にして流転の言葉に注目した。
「地球から離れて宇宙空間というところに浮かぶと、身体の重さを感じなくなるんですよね? 今、正座している足が痺れてきているのですが、そこに行けば治るでしょうか?」
「ああ、治るだろうな」
藍万古は白い歯を見せて笑い、流転の青い頭をガシガシ撫でた。そのせいで綺麗に結ってあった髪がゆがんでしまった。
「へええ~~、流転くんて物知りだな~」
朱い髪の毛がツン立った、流転と同年代の男の子がもらした。
「それなら正座の痺れ、どうにかしてほしいな~~」
百世がすかさず、
「あんた、誰? 名前を言いなさいよ。あたいは藍万古の弟子の百世よ」
少年は燃えるような炎色の短いツンツン毛から、白い角が二本生えている。
「いいのかなぁ、名前言っても……怖気づかない?」
「あんたみたいなちっこい坊やに怖気づいたりする百世ちゃんじゃないわよ」
「ケンカはやめなさい」
藍万古が注意した。
生徒たちは、とたんに足の痺れを感じたらしく、呻き声を上げながら足をマッサージしたり、無理に立ち上がって倒れたりしている。
「みんな痺れがひどいようね。なんとかならない? 藍万古」
孔雀明王まゆらちゃんが、おねだりするような甘い視線を送りながら、まつ毛をパチパチした。
(な、何だ? こんな目つきは長いこと見なかったが)
藍万古が、まゆらちゃんにだけ聞こえる心の声で言った。
(藍ちゃんたら、長い間、垢だらけのモモヒキ姿の爺さんでいたから、こんな甘え方も出来なかったのよ)
「仕方ないな。特別室を使わせてもらえるよう、玉帝陛下にお願いしてみるか」
藍万古は生徒たちを引き連れて教室を出て、廊下の分厚い扉の前に立ち止まった。
「陛下からお許しの許可が下りた。模型とは言っても本物の天体と呼応するから、勝手な行動はしないように」
藍万古の最後の注意の言葉に、生徒たちは緊張した。
第四章 無重力の部屋
藍万古は分厚い金属の扉に手を当てた。
「今から渾天儀の内部に入る。一歩出たら、無重力空間だから浮き上がる。君たちは慣れないから、五人ずつ組んで手をつなぎなさい」
「五人ずつ……」
生徒たちは自分の隣りにいる者と視線を合わせた。
百世は、さっきの朱い髪の少年と目を合わせて「ふん!」とそっぽを向こうとしたが、彼の方から手をつないできた。
「何よ、馴れ馴れしいわね」
「一緒に授業を受けようよ」
「あんた、やっぱり生意気ね!」
百世はツンとした。
流転は、まゆらちゃんとピーちゃんとがっしり手をつないだ。
扉が開かれた。
扉の向こうは一面の星空だ。漆黒の空間に、先ほどまで覗いていた教室の窓が小さく見える。間近に迫るのは、渾天儀の複雑なゼンマイと歯車と、大きな輪っかや色とりどりの惑星たちだ。
「うわっ」
皆は思わず叫んだ。
(身体が宙(ちゅう)に浮いてる!)
まゆらちゃんは四本の手で必死に藍万古につかまり、ピーちゃんは浮くのに抵抗して翼をバサバサしたが、思うように羽ばたけない。
他の生徒たちもじたばたしている。
「みんな落ち着け。身体を動かすな。そのうち静止する」
藍万古の言う通り、自然に漆黒の空間に止まりはじめた。
「さっきは痺れて立てなかったけど、これなら楽だ!」
ひとりの生徒が言った。
「ここでなら、いくら正座したって痺れないぞ」
「はははは。そういうわけにはいかんがなぁ」
藍万古が、浮きながら笑った。
「正座の所作をキメる床が無いからな」
「こうして皆で手をつなげば、床が無くても正座のカタチはできるんじゃない?」
まゆらちゃんも楽しそうに浮きながら言う。
「やってみる価値はありそうだな」
藍万古が答えた時、急に渾天儀の歯車が止まり音も止まった。
「あれ、渾天儀の歯車が止まったぞ」
ピーちゃんが叫んだ。
と思ったらすぐに動き始めた。だが、軋み(きしみ)はじめて変な音を出している。動きが遅くなったり早くなったりして、滝の水も無重力空間で水滴になって固まったりしている。
「どうしたんだろう、故障?」
朱い髪の少年が声色を変えて叫ぶ。
「早くこの空間を出た方がいい。渾天儀が悲鳴をあげてる!」
「ちょっと待て! みんな、静かに!」
藍万古が玉帝陛下の取り乱した声を聞きとる。
『真響(まなり)を! 真響を助けてやってくれ!』
「皆、手をつないだまま扉を目指して降下しろ。玉帝陛下のおなりだ!」
「ええっ」
生徒たちは驚きながら、藍万古の誘導で無事に扉にたどり着いた。
教室に戻ると、薄い衣を着た壮年の男が床に手をついて座りこんでいた。かなり取り乱して肩で息をしている。
「玉帝陛下!」
藍万古が駆け寄り、生徒たちはその場に正座した。
「こ、このおじさんが宇宙で一番偉い玉帝陛下?」
「想像してたのと全然違う……。なんだか、めちゃんこしょぼくれてるぞ」
玉帝の近習の者たちが続いて教室に駆けこんできた。
「陛下、お部屋にお戻りくださいませ。こんなに憔悴されているではありませんか」
しかし玉帝は近習たちの手をはらいのけ、藍万古にすがりつく。
「藍万古! 真響を!」
「陛下、落ち着いてください。何が起こったのです」
「しばらく以前に側室の真響が、渾天儀に憑りついた『輪の魔物』にさらわれたのだ。そして、身柄を渾天儀の中の青い球体に閉じこめられたのだ」
生徒たちはゾッとした。流転も真っ青になって、
「万古老師匠、渾天儀は人のように感情を持っているのですか?」
「どうやら、そうらしいというところまでは来ているのだが」
藍万古のひたいに、汗がひと筋たらりと落ちた。
「真響を助け出してやってくれ! 余の子を身籠っておる大事な身体なのだ」
玉帝は震える手で袖から端末を取り出し、写真を見せる。
「これが余の大切な側室の真響だ!」
「このお方は……!」
藍万古は黙りこんだ。
第五章 藍万古、モテる
(真響さまとかいう玉帝の側室って聞こえたけど……。どこかで聞いた名前だわ。陛下の側室なら、さぞお美しい方でしょうね)
ふたりの会話が、孔雀明王まゆらちゃんは気になった。
(そうだ! 女生徒に聞けば知ってるかもしれない)
休憩時間に白亜の校舎の通路を歩いていった。曲線を描いた白い廊下が続く。
「誰もいないな。女生徒はどこに……」
すると後ろから、
「ま~ゆらちゃん、どこ行くの?」
聞きなれた声が聞こえた。
「あら、ピーちゃん。中庭でも散歩しようと思って」
「ホント? イケメンに蘇った万古老とデートでもしようと思ったら、承知しないよ」
まゆらちゃんは吹き出した。
「どうして? 万古老とは1万年前……10万年前だったかな? 恋人同士だったんだから、いいじゃない」
「とんでもな―――い!」
ピーちゃんのけたたましい叫びと羽ばたきが響き渡った。
「ボクとまゆらちゃんの清い友情が汚れちゃうよ!」
「友情なんだから恋愛とは別でしょう」
まゆらちゃんはさっさと職員室を探し当てた。
透明な羽根が生えたり、頭に一本角が生えていたり、色んな体形をした女生徒が連れだって、華やかな衣をひるがえしながら出てきたところだった。
「あのう、どなたか玉帝陛下の、真響さまとおっしゃるご側室をご存知かしら?」
まゆらちゃんが尋ねると、女生徒たちは怖い眼で睨んだ。
「なぁに? あなたも真響さまのことを口実に、藍万古先生にプレゼントを持ってきたの?」
「プレゼント?」
「献上品のことよ」
まゆらちゃんが急いで職員室の中を覗くと、真ん中にたったひとつの文机は山盛りの花で飾られている。
藍万古が好みそうなネクタイや筆、文鎮、髪飾り、煙草の葉、茶葉、刺繍を施した匂い袋や靴まで、てんこ盛りになっているではないか。
「な、な、何よ、これは! 許さないわよ、万古老~~!」
女生徒たちがはしゃいで、
「カッコいいわよね、藍万古先生って」
「藍色の髪に整った横顔。渾天儀を操る鮮やかな手際といい、ダンディな声も。なんといっても正座の所作と姿が!」
まゆらちゃんのオツムが噴火した。
「あの人のモモヒキを洗濯したことあるのは、私だけよ~~!」
第六章 胎児が正座
真響は、1万年前、万古老の正座の先輩弟子だった。万古老はリスペクトするだけでやましい思いはひとつもない。日々、大師匠の玉帝陛下から共に正座を学ぶ日々だった。
「真響さまとは、本当に兄弟弟子というだけの間柄なんでしょうねっ?」
まゆらが眉を吊り上げて詰め寄ったが、
「ああ。玉帝陛下にかけて誓う!」
藍万古は言い切った。
玉帝陛下は、真響が渾天儀の内部に監禁されていることを嘆いて食事も喉を通らない。ため息ばかりついている。その上、酒を運ばせて際限なく飲み続けている。
藍万古が知る玉帝陛下は、こんなに情けない有り様ではなかった。
全人類が、宇宙で唯一無二の大帝と敬うに値する、堂々とした帝として君臨していた。
(側室の身を案ずるあまり、ヘタレになってしまったのか?)
(玉帝の跡継ぎが生まれるなど、前代未聞のことだ。真響は、仙界、天界の常識を書き替える力を持っているのか?)
(玉帝はこのままにしておけない)
藍万古は、古くから知る帝の近侍のゴンズイという爺やを呼んだ。
ゴンズイも帝を心配するあまり、身体が弱っていた。床まで届く白いアゴヒゲを垂らし、咳きこみながら、
「真響さまが後宮に入内された頃から……。陛下は次第にかつての威厳を失くされ、真響さまを一瞬たりと離さず側に置かれるようになりました。どうすればよろしいのでしょう」
藍万古に泣きつく始末だ。
「真響のことは昔からよく知っているが、帝を骨抜きにするような下品な女性ではない。どうも腑に落ちぬな」
ゴンズイ爺やが陛下の元を下がる時に、視界に入ってきた朱い髪の少年がある。
「これ、そこの少年、待ちなさい!」
老いたりといえど、ゴンズイ爺やの思念は強い。朱い髪の少年は身体を動かすことができなくなり、立ち止まった。
「お前は……確か、確か、真響さまの小間使いじゃな」
藍万古は生徒全員を集めて、自分たちの部屋に帰るよう言いつけた。
ひとりになり、シンとなった廊下から無重力の空間への扉を開けて足元の床を蹴り、浮遊して泳いでいった。
目の前に青い球体がある。目を閉じて球体に意識を集中させる。
透視しているのだ。確かに真響の存在を感じた。しかも――。
(胎児が真響の胎内で正座している――?)
胎児は将来、玉帝にとってかなり重要な、懐刀(ふところがたな)になる可能性があることを感じた。
(これは真実なんだろうか)
第七章 炎駒(えんく)
廊下に戻ると、朱い髪がツンツンした少年が待っていた。
「お前は生徒のひとりだったな。え~~、名前は……」
「俺は炎駒」
「炎駒だと? 心優しい神獣の、あの炎駒か?」
少年はうなずいた。炎駒とは朱い麒麟(きりん)のことだ。
「藍万古先生、今、渾天儀には『輪の魔物』が巣くっている。奴らが側室さまを閉じ込めたんだ」
意外なことを言い出した。
「俺は危険を察知して真響さまの側に控えていたんだが、少し目を離した隙に、奴らに拉致(らち)されてしまった」
(そう言えばゴンズイ爺やが真響の小間使いと呼んでいた……)
藍万古は思い出した。
「信じていいのか? 『輪の魔物』とは一体、何だ」
「『輪の魔物』とは渾天儀に集中した輪の圧力とでも言うかな。輪が重なりすぎて――天上赤道帯、黄道帯、二分雙環(にぶんそうかん) 雙環(そうかん)、 二至環(にしかん)、子午雙環(しごそうかん)、子午線――。何重もの輪に巻かれて赤ん坊は苦しくなり、悲鳴をあげている」
「『輪の魔物』は、渾天儀と赤ん坊の両方を苦しめているのか?」
「とりわけ渾天儀の中心にある青い球体を締めつけて、真響さまのお腹のお子を無事に産ませないように企んでいる」
「な、なんだと?」
「お腹のお子は未だかつてない存在だ。産まれて育ったら、玉帝陛下の最強の部下になる。何せ、十年間もお腹の中で正座修行していたのだから」
「十年も胎内で正座していただと?」
藍万古も長い時間生きてきたが、そんな話は初めて聞く。
「だから『輪の魔物』は、真響さまの子に産まれてほしくないんだ」
「『輪の魔物』は正座する者を敵視しているのだな」
「俺はなんとしても無事に産ませたい。神獣の使命でもある」
炎駒の朱い瞳がらんらんと燃え盛り、頭の白い角がにょっきり伸びた。
「炎駒は闘いを好まないのでは? 草木を踏むのも好まんとか聞いたが」
「嫌いだよ。だから――、藍万古、あんたに協力してもらいたいんだ」
「俺に、戦えと?」
「そう!」
炎駒が初めて、にっこり笑った。
第八章 正座陣
藍万古は、教室の窓から渾天儀を見つめ続けていた。
巨大な黄金の球体を三番目に周る(まわる)青い球体の中に、真響姐(ねえ)がいる。あそこから脱出させるには……)
背後から、まゆらちゃん、ピーちゃん、百世と流転がそっと様子を見ている。
「何か悩んでいるようだね」
ピーちゃんが真面目に言った。
「よほどのことだよ。学生食堂のダチョウ卵の目玉焼き定食、食べなかったんだもん。大好物なのに」
「だよね? じっと目玉焼きを見つめていたら、急に立ち上がってここへ走ってきたんだよ」
百世が言った。とたんに藍万古は窓辺から離れ、膝をポンッとたたき、
「よし、正座陣だ!」
「正座陣……?」
叫ぶなり、床に赤いチョークで大きく線を描き、魔法陣のようなヘンテコな模様を描いた。――ただし、四角の。
「これでどうだ? 朱い頭の坊主!」
窓の外へ大声で尋ねると、空間に待っていた朱い炎駒が答えた。
「いいだろう! よく見えるよ。四角の正座陣が」
「この正座陣に真響を正座させれば『輪の魔物』も手出しできまい」
藍万古はダッシュして教室を出て行き、残された皆は顔を見合わせた。
「朱い髪のアイツと師匠、いつの間に接近?」
次の瞬間、窓の外の空間に藍万古が浮いていた。炎駒が彼を追いかけて丸い金属のものを渡した。
「何だろう、あれ?」
「円盤投げの円盤みたいだね」
スポーツ大好きな百世が言った。
藍万古は、円盤もどきを受け取り、少年は藍万古の両足首をしっかり持って顔を伏せた。
「ひゃあ、やっぱり投げるつもりだ!」
流転が叫んだ通り、藍万古は何度も腰の後ろで構えなおし、ようやく円盤を投げた。
「あの筋肉! 惚れ惚れしちゃうわ!」
胸の前で二組の手を組んで、まゆらちゃんが叫んだ。
円盤は青い球体向けて飛んでいった。球体の模型の大きさは直径10メートルもあるだろうか。
カ―――ン!
円盤は表面のガラスにはじき返された。球体の表面にはキズひとつついていない。
「くくっ、円盤じゃダメか……」
藍万古は歯を食いしばり、足元の少年に目をやった。
「炎駒、次は槍投げの槍だ!」
「えええ~~~? 槍はダメだよ! もし、ガラスを突き抜けたら、本物の天体と呼応する。誰かに当たったら怪我させてしまうよ」
「じゃあ、他に何が?」
「ハンマー投げの砲丸はどう?」
ハンマー投げ競技の砲丸にはクサリがついている。
「槍みたいに人間に刺さったりすることはないだろうから」
「やってみよう」
炎駒が、ハンマー投げの用具をそろえた。
渾天儀を見渡せる大きな窓が全部で三か所、生徒たちや学校職員で人だかりができている。
押すな押すなの大盛況とはこのことだ。ついに、ゴンズイ爺やを引き連れて玉帝陛下までが現れた。
「藍万古! そなた、何をするつもりだ? 青い球体をキズつけたりすれば、内部の真響とお腹の子もキズつけてしまうではないか!」
宇宙一の威厳はどこへやら、爬虫類のようにガラスにへばりつき、叫んでいる。
「陛下、少々荒療治かもしれませんが、外からガラスを破壊して、真響を救い出します」
窓に群がっていた人々がざわついた。とりわけ、ゴンズイ爺やが玉帝陛下に負けないほどの取り乱しようだ。
「藍万古! ここまでやれとは、わしは言うておらぬぞ。どうしよう? と相談しただけじゃ」
「ゴンズイどの、一刻を争うのです」
第九章 正座陣へ
炎駒が、長い長いロープを無重力空間への入口の柱と藍万古の胴体に結びつけた。
いよいよ、藍万古はハンマーの鎖の持ち手を持った。青い球体を睨んで狙いを定めてからぶんぶん廻しはじめ、勢いをつけて持ち手を離した。砲丸は無重力空間を弱々しく飛んでいき――、遠心力を発揮して表面ガラスを見事に破壊した!
「やった~~~!」
思わず炎駒が叫んだ。
青い球体は半分以上粉々になり、ドッと水が流れ出た。水の帯は竜のようにのたうちながら渾天儀の輪のすき間を通り、教室の窓にぶつかってガラスを砕いた。
流転と百世は見た。藍万古が、躊躇なく流れの中に飛びこむのを。
「万古老師匠~~~~!」
万古老――藍万古は激流の中を、抜き手を切って泳ぎながら必死で真響の気配を探した。
(真響姐、どこだ、無事でいてくれ――!)
祈る思いで泳いでいると、紅色の衣が視界のハシになびいていった。
(あの衣の色は宮仕えの女官の――)
懸命に泳いで近づき、腕をつかむ。女が目を開いた。
「真響! あの『正座陣』目指して泳げ――!」
水流の泡の果てに、赤色で描きなぐられた四角い正座陣が見えてきた。
「正座陣を目指せ―――!」
泳ぎながら真響の腕をひっぱり、藍万古は浜に打ち上げられた海藻みたいにぐにゃぐにゃになって正座陣にたどりついた。
「真響姐……?」
驚いたことに、真響はいち早く四角い正座陣の中央に美しく正座していた。水びたしになった教室に藍万古と真響だけが残った。
「あなた、藍さん……?」
全身びしょびしょの真響が眼をまん丸にした。
「どうして、私はここに?」
「どうしたもこうしたも、真響姐が渾天儀の青い球体に閉じこめられたって聞いたから助け出したんだよ。お腹の子は大丈夫か? 玉帝陛下のお子だから、無事でいてもらわないと」
真響はお腹に手を当て、
「大丈夫、元気そうよ。でも……、この子は玉帝陛下のお子ではないわ」
あっさりと否定した真響に、藍万古は呆然とした。
「玉帝陛下のお子ではない――? では、父親は一体……」
「私にも分からないの」
「分からない? 真響姐って、そんなにだらしない女だったのか?」
水に滑ってジタバタと藍万古は後じさりした。
「違うわ、覚えがないだけよ」
「お、覚えがないだと?」
「いつの間にか、赤子がお腹に宿っていたの」
「そんな! 陛下は自分の子だと思いこんでいるぞ」
「勝手に側室という位に拝命されたのよ。しばらくして、朱い髪の少年がやってきてお告げを聞いたの。藍さんの正座の大師匠、玉帝の御子かも? と。正座の神の子ともいうべき子なのよ。お腹にいる間からきちんと正座していたでしょう」
「……!」
藍万古は尻もちをついて意識を失った。
今度は真響がびっくりする番だった。目の前にいた逞しい青年はどこへやら、床に倒れているのは、あばら骨が浮かび白いアゴヒゲが長いやせ細った老人だったのだ。
第十章 正座の申し子
水びたしの教室に、孔雀明王まゆらちゃんと百世と流転が走りこんできた。
「万古老師匠!」
「お師匠!」
まゆらちゃんが師匠の身体を抱き起こし、頬をピタピタ叩いた。
「ちょっと目を覚ましてよ、万古!」
「う、う~む」
万古老の目元はしかめたままだ。
「ちょっと皆さん」
万古老の足首に繋がれたロープの先っぽから声をかけたのは、朱い髪の少年だ。
「あの流れ出す水の中を全力で泳いだんだ、少し休ませてあげましょう」
「あっ、お前は!」
思わず百世が叫ぶのを流転がとがめる。
「百世、炎駒さまを『お前』呼ばわりしちゃいけないよ。心優しい神獣なんだから」
「ああ。炎駒が告げたから、真響さまは赤子を身籠ったと思いこみ――」
「それは本当のことだろうよ」
まゆらちゃんが真響を支えて立ち上がらせ、別室に連れて行った。
真響は静かな部屋で清潔な衣に着替えさせられ、ふかふかの寝台に横になった。まゆらちゃんが女官に指図したのだ。
「ありがとう、孔雀明王さま。あなたと藍万古のことは、玉帝陛下に正座を習っていた昔から知ってるわ」
「はい。私も思い出しました。年月が経って、思いがけない再会をしましたね」
「本当に」
「お腹に手をあててよろしいですか?」
まゆらちゃんはそっと手をあてた。
「――確かに感じます。聖なる命の存在を。この子も『正座の申し子』なんですね。炎駒が告げに来た……」
真響は、じきに母親になる女性の柔らかい表情でうなずいた。まゆらちゃんも微笑んで、
「陛下がご自分の子でないと知られるとショックでしょうから、私からうまく申しておきます。今はご安産だけをお考えください」
「ありがとう」
まゆらちゃんは窓の外の遠くに見える海に視線を投げて、
「『輪の魔物』とは何のことだったのかしら」
扉が開いて、炎駒が入ってきた。
「渾天儀の苦しみのことだろう。太陽系の仕組みが解明するにつれ、沢山の輪をまとわされてしまい、息苦しくなったんだ。設計ミスだな」
ズズズズ……。
異様な地鳴りのような音がしてきた。
寝台の上の真響とまゆらちゃんも腰を浮かせた。
渾天儀がガラガラと崩れていく。何千年もかかって知識を蓄積させ、カタチになった渾天儀が短時間にして喪われて(うしなわれて)しまった。
目の当たりにした玉帝は、絶叫してその場にくずおれた。
「真響さま、渾天儀が!」
炎駒も、顔色を変えて寝室に飛びこんできた。
「そう――」
真響は落ち着いている。
「お腹の子がゆったりしているわ。やはり『輪の魔物』は、この子には重圧だったのね」
白亜の御殿も崩れて、岬から海へ落下していく――。
孔雀が鮮やかに翼を広げ、女人たちを背中に乗せて滑空した。
結びの章
数か月後のある朝――。
洞窟の入口では、百世と流転が毛氈を敷き、正座の所作のお稽古をしていた。
「ほほう、どういう風の吹き回しかな? お前たちから率先して」
万古老がラジオ体操をするために出てきた。
「おはようございます、お師匠。今朝の分はお祝いの正座です」
「お祝いとな?」
「生まれたんですよ。真響さまの赤さんが!」
百世がはずむ声で告げた。
「おお、正座の申し子が生まれたか! どっちかの?」
「それが……炎駒は教えてくれなくて」
「ふうむ」
万古老の横顔に寂しさがよぎった。
「炎駒のやつ、心優しい神獣のくせに意地悪だよな」
百世が唇を尖らせた。
「ケンカ友達がほしいのじゃな、百世」
「大丈夫。渾天儀を造りなおすそうだから、炎駒が玉帝の元に時々、呼んでくれるそうだ」
「何っ? 厄介な渾天儀を再び造るとな? 玉帝も懲りられぬことよのう」
「今度は真響さまがお造りになるとか」
「な、なに――? あのじゃじゃ馬!」
生き生きとして渾天儀を造る指図をする真響の姿が、万古老の脳裏に浮かんだ。








