[281]若君、おやつの時間です!
 タイトル:若君、おやつの時間です!
タイトル:若君、おやつの時間です!
掲載日:2024/04/01
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
平安時代、九条家の若君、薫丸(くゆりまる)は14歳。正座の稽古も武術のお稽古も詩歌のたしなみもせず、朝から晩まで、傀儡子たちと一緒に過ごす毎日。乳母は悩んでいた。どうにか若君を屋敷で勉学させられないものか。
世間では、朝餉と夕餉の間におやつの時間というものが出来たと知った乳母は、侍女のひじきに菓子職人捜しを命じる。
やってきたのは唐の菓子職人、李橙実(リ・チャンシー)という青年だ。

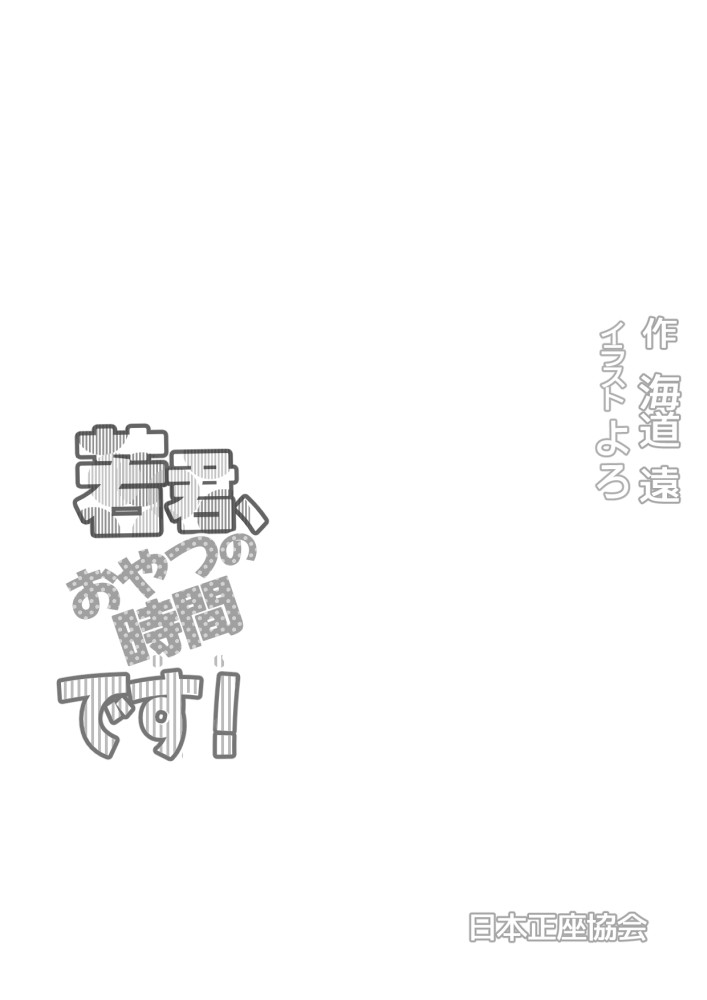
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 やんちゃ若君
薫丸(くゆりまる)の乳母は、いつもいつも薫丸の外出に頭を悩ませていた。
京の九条家の若君、薫丸は14歳にもなるというのに、勉強も和歌や楽器のたしなみも武芸も馬術もまったくせず、朝餉を済ませると、町の場末で大道芸を見せている傀儡子の仲間のところへ行ったきり。宵に帰ると夕餉だけは忘れずにかきこみ、すぐに「バタンキュ~」の生活なのだ。
使いの者に伝言もせず、2~3日帰らないこともある。
父君の殿も薄々は感づいているだろうが、母君の心配も増していた。乳母にはキツく言われないたおやかなお方なので、よけい応える。
成人の儀も迫っていることだし、乳母としては、いい加減に真面目に勉学に打ち込んでほしい。
(なんとか、薫丸様を家に縛りつける手立てはないものか――)
「若君がお好きなことは何かのう?」
ひとり言をもらすと、
「弓矢でしょう」
女房のひじきが答えた。
「弓矢よりお好きなものは――」
「お食べになることでしょう」
何せ育ち盛りだ。
「朝餉と夕餉だけじゃからのう」
「あっ」
ひじきが手を打った。
「最近、暮らしの中で、朝餉と夕餉の間に食事することが流行と申しましょうか、始まってきたようですわよ、乳母さま」
「何? では、1日に3度食事をするのか?」
「食事と申しましても『唐果物』(からくだもの)とかお八つ(おやつ)とか申して、ご飯や総菜ではなく軽く甘いものなどいただくのですが。果物とは別に手を加えた『唐菓子』ですわね」
「甘いもの?」
甘いものに目がない乳母も乗り出した。
「蜂蜜やアマズラ(ツタの樹液を煮詰めたもの)を米粉ダンゴにかけたり、蘇(そ)など……八つ時にいただいて、夕餉を遅らせるとか」
「蘇? 蘇とは何じゃ?」
「牛の乳を煮詰めたものだとか」
「牛の乳からとな? ほ~う?」
※蘇=牛乳を10%に煮詰めたもの。練乳。
「それは、私もまだ口にしたことがない。そなた、今、申したものを作れる職人を捜してくれるかな?」
「かしこまりました!」
ひじきは顔を輝かせた。
「唐果子を召し上がる時に、若君の正座のお稽古に持ってこいじゃ。1日も早う職人捜しを頼むぞ。お給金ははずむゆえ」
「はい!」
ひじきは袴を両脇で持ち上げ、簀の子を走っていった。
第二章 唐の菓子
乳母の命令を受けた女房――ひじきは、はりきっておやつ職人を探した。
ひとり、知り合いの紹介で唐の国から来ている若い職人を紹介してもらった。
李橙実(リ・チャンシー)という。
ひじきが紹介人のところで会ってみた。
「おやつ時の唐菓子を作るのでしたら、お任せください」
まだ若いが腕は確かだということだ。唐風の着物を着ているが、倭国語は流暢(りゅうちょう)に話せる。目が垂れていて穏やかそうな青年だ。
「やんちゃで評判の若君の胃袋をつかんでみせますよ!」
手際よく粉をこねて油で揚げたものに、蜂蜜という黄金色の粘っこいものをとろりと振りかけた。
「黄金色のたらりとしたものは『蜂蜜』です。ミツバチが花の蜜を集めたもので、貴族方にしかお口にできない大変、貴重なお品です、と若君にお伝えください」
壷から、ひとさじの先っちょにすくって、ひじきに味見させてくれた。
「う―――ん、これはッ!」
ひじきは和紙で包んだ唐果物を二、三個抱えて、屋敷に帰るなり台所から渡り廊下をいくつも滑り台のように渡り、乳母のところへ駆けつけた。
「乳母さま! サイコーの唐果物ができましたよっ。これで若君はおやつ時には確実に戻ってこられます!」
「どれどれ」
乳母もワクワクして味見してみた。
「うう―――むっ! 美味い! ようやった、ひじき! これで若君はどこにも行くまい! 唐果物職人にたんと(沢山)褒美をとらせい!」
「はい! 喜ぶことでございましょう」
ところが! ところがである。
その日の午後、乳母が薫丸に試食させたところ、
「ふうん、まあまあだな」
薫丸は感激した様子もなく、ひと口だけ食べた。
「まあまあ……でございますか?」
「蜂蜜をかけた菓子なら何回も食べたことある。傀儡子たちは、あちこち国を巡ってくるだろう? お土産からいっぱい味見するんだよ。飽きるくらい」
「……は?」
「もう、一座に戻っていいかい? 傀儡子の夕方の客が来る頃だ」
「戻られる? 若君!」
薫丸は台所の上がり口に少し腰かけて、ひと口味見しただけで屋敷から全速力で飛び出した。
第三章 橙実の通力
「若君は珍しい味に飽きられているのですって?」
李橙実は薫丸の反応を聞いて、よけいやる気が湧いたらしい。
「では、もう一段階、進んだ唐菓子をお作りするとしようか」
「もう一段階、進んだ唐菓子?」
「乳母さまに、ちょっと若君のお心を覗いていいかどうか伺ってくださいな、ひじきさん」
ひじきが急いで行って戻ってきた。
「何のことか意味が理解できませんが、若君を屋敷に縛りつけておくためならご自由にって!」
「よしっ」
李橙実は、全身からやる気をみなぎらせて飛び出していった。
戻ってきた時には、飯を炊く台所の釜の中から顔を出した。
「きゃ―――!」
台所の女房たちが腰を抜かし、来合わせたひじきもびっくりした。
「チャンシーさん、いったいどこから戻られるやら」
李橙実が自信たっぷりに、いろんな食材を釜の中から取り出す。まず、かんきつ類を出して、
「これならどうだっ! 公家幼稚園舎、ぴちぴち組時代の美甘(みかん)ちゃんの額の汗入りの夏みかんふれっしゅ!」
みかんを二つに切ったものを青く透きとおった杯に絞ってみせる。
「一滴、美甘姫が間違えて若君のおみ足を踏んだ時に、にじんだ甘めの血を加える」
「李……橙実どのとやら」
いつの間にか、乳母が台所に来ていた。
「私が若君の乳母じゃ」
「こっ……これはこれは! 乳母どの、お初にお目にかかります。唐からまいりました李橙実と申します。この度は大任いただきまして」
李橙実はすんなりと正座の所作をして、乳母に挨拶した。
「ひとつ、お伺いしてよいかの?」
「は、何なりと」
「そなた、何ゆえ、美甘姫のことをご存知なのじゃ」
「は……」
台所に散らばって作業していた侍女たちも、動きを止めた。
「美甘姫は若君の又従妹にあたられるが、ひ弱なお身体ゆえ、お小さい時に母方の紀伊の国のお屋敷で暮らされることになり、それからずっと京にはお戻りになっておられぬ。それを、何ゆえそなたがご存知なので?」
「はは」
李橙実は深く頭を下げ、
「乳母どのの疑問、ご無理ありませぬ。私、ちと人様の心の中を覗ける力がありまして」
「何? 人の心の中を覗けるとな?」
「はい。私は唐の果物の郷と言われるところで生まれ育ちましたが、不思議な通力があるらしく、お顔を拝見するだけでその方の過去に起こったことや思い出を感じ取ることができるのです」
「そ、そんなことが!」
「若君の祖父君が膝の上で幼い若君を座らせて、吸っておられた煙草の香りとか」
「そう言えば、祖父上の左大臣さまは、若君を膝に乗せられて煙草をたしなんでおられましたわ」
「美甘姫が紀伊の国に移られる牛車を見送られる時、『再びまみえて、青い杯に入れようと誓った、たわわに実ったみかんのひと絞りのこと』とか」
「まあ」
「なにより、初めて正座の所作を教えてくれたのは、美甘姫だったこととか!」
「そういえば私どもも、幼かった美甘姫からお教えいただいたのでしたわ」
乳母とひじきは呆然とした。
第四章 思い出入りの唐菓子
薫丸は、さっそく李橙実が作った唐の揚げ菓子を、傀儡子たちのところへいくつか持って行った。
「こりゃあ美味いじゃないか、薫丸」
黒いあごひげを生やした親方が、パクつきながら言った。
「本当だ、今まで出会った『唐菓子』とは大違いだ!」
弓矢の達人青年、半夏(はんげ)も、珍しく酒のアテにならないおやつを褒めた。
「その、チャンシーっていう唐菓子職人、やるなあ。オダマキ、お前も無くならないうちにもらえ」
「は……はい……」
オダマキも近づいてきて、ひとつつまんでパクついた。
「美味しいわ。とても甘いし、ふわふわね」
薫丸がもぐつきながら、
「李橙実……チャンシーさんっていう菓子職人が不思議な力を持っているんだ。人の心にどんな思い出があるか分かるんだって。おいらが幼なじみの美甘姫のことを考えていたら、言い当てたんだぜ」
「まあ」
「美甘ちゃんは身体が弱くて、小さい頃、紀伊の国の祖父君のところへ引き取られたんだ。あっちは温かいからな。元気に育ったかな? オダマキと同じくらいの年だよ」
「へえ……」
オダマキは下を向き、
「きっとあたいみたいな砂ボコリだらけの子じゃなく、きれいなお姫さまでしょうね」
「オダマキ、お前は人形遣いの働き者だから、汚れてしまうだけさ。十分、可愛いぞ」
「薫丸ったら」
「昔は紀伊の国からみかんが沢山、送られてきていた。あのみかんを蜂蜜に混ぜたら、もっと美味しくなるんじゃないかな」
【蜂蜜の中にみかんを……】
一同は想像してみて、よけいにヨダレが溢れた。
第五章 説得の方法
「じゃあ、次の興行先は紀伊の国にするか」
黒ヒゲの親方が言い出した。
「え? いいのか?」
「ああ。紀伊の国には長いこと行ってなかったからな」
「おいらもついて行きたいな」
「若君、いいんですかい? ご両親さまがお許し下さらんでしょうが」
「父上、母上より、まず乳母が真っ赤になって怒るだろうな」
しかし、美甘姫を思い出して会いたくなってしまった。
翌朝、薫丸が朝餉を食べていると、李橙実がやってきた。
「若君、おはようございます」
ニコニコしている。
「ああ、おはよう。チャンシーさん。昨日はありがとう。傀儡子たちにも唐菓子をいくつか持って行ったら、すっごく評判良かったぞ」
「それは、ありがとうございます」
薫丸は円筒状に高く盛られた雑穀米のご飯をを食べ終わり、箸を置いた。
「ご馳走様でした~~!」
昨日の親方の言葉が思い出されて、いてもたってもいられない。
「傀儡子仲間が、次は紀伊の国で興行するって言うんだが」
「存じております」
ニコニコ顔のままだ。
「そっか、あんたには筒抜けだったな」
薫丸は女房たちが膳を下げるのを見届けてから、小さな声で、
「どうしたら、父上、母上、乳母からお許しが出るかな?」
「簡単にございます」
すんなりと橙実の答えが返ってきた。
「か、簡単?」
「紀伊の国へ行かせてもらえたら、1日中、屋敷にいて勉学に励みますって、お約束すればよろしいのですよ」
「そっ、それが一番、難しいんだよ!」
第六章 紀伊の国
ドドッドドッ、と馬の蹄の音が背後から聞こえてきた。
紀伊の国に入って海岸沿いの道を下り、しばらくするとタチバナ神社の朱い鳥居が見えてきたところだ。
「な、何だ?」
傀儡子たちは驚いて一番先頭の荷車を止めた。数頭の馬に乗った武者が駆けてくる。しかも、皆、弓矢を備えて鷹狩りの時のような装束を身に着けている。
彼らを乗せた馬は、荷車を取り巻いた。
「どちらのご武家さまでしょうか?」
半夏も乗っていた馬の首をゆっくり回し、失礼のない口調で尋ねた。
「はははは……」
可愛らしい笑い声が上がった。
武者たちの馬の一頭から下り立ったのは、まだ年端のゆかない女の子ではないか。
「武家じゃなくて公家よ」
荷車の垂れ布から顔を出した薫丸が叫んだ。
「公家? 美甘ちゃん! もしかしたら美甘ちゃんか?」
女の子も目を輝かせて、
「薫丸くん! 薫丸くんじゃないの、久しぶり~~!」
「やっぱり美甘姫か! どうしたんだ、その勇ましい格好は!」
「今はわらわが祖父上の屋敷やみかん畑、それと神社の警護に当たってるのよ。祖父上が腰を痛くされたから。常に弓矢のお稽古もしているわ」
配下のひとりが、ぽ―――ん、と青空に目の沁みるような橙色のみかんを放り上げた。
美甘姫が背中の矢筒(やづつ)から矢を一本抜き取るや、つがえて青の天井に放った。みかんは姫の矢にスパッと打ちぬかれ、手元に落ちてきた。姫はそれを薫丸に投げた。
「今年の早生(わせ)みかんよ。召し上がれ」
薫丸は急いで皮をむいて食べてみた。
「美味い! 甘酸っぱい!」
「ふふっ、美味しいでしょう。うちの農園のみかんは特別の味よ! それにしても、薫丸くん、変わらないわねえ。下げみづらの髪を垂らして水干を着て。おチビさんだし。乳母さまに叱られてるんでしょう」
「お前さんより背は高いよ! おいらのことより、美甘ちゃんは身体が弱かったから心配していたのに、馬に乗って警護してるなんてオドロキだよ!」
「矢の腕も見てくれたでしょ?」
「ああ」
「この方たちは?」
「傀儡子の友達だよ。屋敷に泊まるのは、おいらと唐の菓子職人の李橙実さんだけ」
「唐の菓子職人ですって? ちょうど良かった、わらわもみかんを使ったお菓子も作ってみているの。教えていただけるわ!」
(美甘姫って、こんなにハキハキしていたっけ?)
戸惑っているうちに、美甘姫が馬で屋敷まで先導した。
第七章 過保護な乳母
薫丸は美甘姫の屋敷でわらじを解くや、すぐに祖父上に挨拶に上がった。もちろん正座で。
昔、姫に教えてもらった所作の通り、真っ直ぐに立ち膝を床に着け、衣をお尻の下に敷きながら、ゆっくりとかかとの上に座った。
「姫さまの祖父上さま。京でお隣に住まっていた九条家の薫丸でございます」
祖父上はすっかり白髪だが、顔の色つやもよく上機嫌で迎えてくれた。
「おお、九条家の若君。下げみづら髪、よう覚えておりますぞ。大きゅうなられましたのう。乳母どのからお文をいただいております」
(ちぇっ、やっぱり。あの過保護婆ぁってば)
「若君、なりませぬぞ! そんなはしたない言葉遣いは!」
後ろから厳しい声が飛んできた。李橙実が叱ったのだ。
薫丸は咳ばらいして、
「祖父上、お顔の色もツヤツヤと。ご健勝で何よりでございます。此度はしばらくお世話になります」
「この地はとても美味なみかんが採れる。たんと召し上がっていかれたがよろしい。孫姫もみかんの食べ方に取り組むようになりました」
「騎乗のお姿を拝見いたしました。この度、唐の菓子職人の李橙実も、同行しております。多少なりとお役に立てれば嬉しゅうございます」
薫丸の背後で、橙実が正座して頭を下げた。
「やんちゃ姫をよろしゅう頼みますぞ」
(まったく、李橙実とは「たいむりい」に知り合いになれたものだ。祖父上には気に入られるし、乳母を説得する時も彼がこちらの様子をちょいちょい『思念』で送ると約束してくれたから、すんなりいったのだ。
第八章 打ち掛け選び
「この子は人形遣いの芸を見せてるんだ。仲間には同じ年頃の女の子がいないから仲よくしてやってほしい」
薫丸が美甘姫の元へオダマキを連れてきた。
「いいわよ。お名前は?」
「オダマキといいます」
「オダマキちゃんね。わらわは美甘よ。いくつ?」
「じゅ……12です」
「わらわと同い年ね。着物の裾が汚れているわ。着物を貸してあげましょう」
「え、そんな……」
美甘姫は侍女に言って、ありったけの秋柄の着物を出させた。
衣文掛けにたくさん打ち掛けが掛けられ、床にも広げられるだけ広げて、花畑みたいになった。
「さあ、好きなのを選んで」
薫丸はあくびしながら庭へ出ていった。
「どうぞ。何枚でも好きなだけ」
「でも、もし汚してしまったら」
「大丈夫よ、そんなこと気にしないで」
身つくろった打ち掛けを侍女に言って、オダマキの肩に着せかけていく。
「う~~ん、どれも似合うけど、菊の花車のとかえでの柄が……」
鏡の前で取っ替え引っ替えしていると、侍女が簀の子に手をついて声をかけた。
「姫さま、お馬係の者から、お支度ができたそうにございます」
「あ、今日はアマズラ刈りに行く日だったわ。オダマキちゃん、あなたも行く? 袴はいて馬に乗せてあげるわ」
「は、はあ」
「わらわが馬の手綱を引いていくから大丈夫よ。ツタの枯れた幹を集めて甘い汁を採るの」
簀の子を歩いていくふたりの話が、隣の部屋にいた李橙実の耳に入った。
(アマズラ……、倭国にしかない甘味料だ)
すぐに後を追って、姫の背後に正座して伏した。
「私もお供させていただいてよろしいでしょうか? 唐にはアマズラが無いのでございます」
「まあ、そうなのね。橙実さん。いいですよ! ご一緒いたしましょう」
玄関には、馬が数頭とお付きの舎人たちが待っていて、オダマキは馬に乗せられて山道を進んでいった。
第九章 オダマキが!
「この辺の洞窟には、氷室(ひむろ)という夏も冷たい部屋が作ってあって、氷を保存してあるのよ」
美甘姫が言った。
「氷室?」
オダマキは初めて聞く言葉だ。
「そう。冬に池に張った氷をたくさん入れておくの。真夏の暑~~い時に細かく削って、アマズラという甘い樹液をかけて食べると身体が冷(ひや)こくなって美味しいわよ。まずはツタを刈りに行くの。これで切るのよ」
美甘姫の手には薪木を切るようなナタが握られている。
「まあ、美甘ちゃんて逞しいのね」
「祖父上にきたえられましたから。何でもできなきゃ厳しいのよ」
樹々がうっそうと茂る山に入っていく。昼間でも薄暗い。
一行をそっと待伏せしている怪しい影がうごめいている。山賊だ。
「きっと、あの赤い着物を着ているのが美甘姫に違いない」
「お前、樹の枝から飛び下りてふん捕まえろ!」
「よし!」
頭上から飛び下りてきて、口元をふさがれたオダマキは悲鳴を上げることもできない。馬も別の男に奪われた。
「~~~~~!」
「みんな、大変、来て! オダマキちゃんがさらわれた!」
美甘姫が大声で叫んだ。
舎人たちが大急ぎで姫のところに集まったが、オダマキをさらった賊は素早く駆けていった。
「姫さま、お怪我は?」
「わらわはなんともないわ! オダマキちゃんを追いかけて~~!」
舎人たちは、八方に伸びる尾根へ馬を走らせた。美甘姫も、松明(たいまつ)をかざして山の中へ分け入った。
一行の最後尾にいた橙実も、突然のことに歯噛みした。
「賊の気配を感じ取れなかった! 私としたことが!」
(薫丸さまにお知らせしなくては!)
橙実からの知らせを心で感じ取った薫丸は、ふもとの屋敷で蹴鞠(けまり)をしていて心臓が破裂しそうになった。
(オダマキが山賊にさらわれた?)
「半夏!」
「行きましょう、山へ!」
ふたりは山へと急いだ。
第十章 オダマキの腕力
今まで襲ってくる時は、農園のみかんの木や実を奪っていった山賊だったが、今回は違った。
舎人たちに氷室のありかを聞き出し、さっそく氷室を見つけ、ムシロをかぶせて隠されていた氷が荷車に積まれて運んでいく。貴重な氷を売って一儲けしようとしようという魂胆(こんたん)だ。
そこへ美甘姫という人質が手に入った。これで公家衆は手も足も出まい。山賊たちはほくそ笑みながら、氷を運び出している。
「そうはさせるか!」
追ってきた橙実が怒鳴った。
彼が倭国へ来た目的は、アマズラの作り方を覚えることだ。それには削った氷が必要だ。
(大切な氷を奪われてなるものか!)
荷車に体当たりする。山の斜面に落ちた氷は次々に割れてしまう。
「ああっ、大切な氷が……!」
山賊が騒ぎを聞きつけた薫丸と半夏が馬で駆けつけた。
「邪魔すると美甘姫の命はないぞ!」
山賊のひとりがオダマキの喉元に刃物を当てて立ちふさがった。
薫丸は震え出し、
「やめろ、や……め……」
うめいて、半夏の身体にふにゃ~~と、もたれかかってしまった。
「薫丸! ひどい熱じゃないか、しっかりしろ!」
オダマキが山賊の手を払いのけた。
「誰が美甘姫さまだって? あたいはオダマキよ!」
細い腕は次の瞬間、荷車を押して谷底へ落とした。
「えいやっ!」
次々と氷を乗せた荷車が谷底へ落ちていく。
「クソッ! なんて力の娘っ子だ!」
「小さいからって見くびらないでよね! あたいは図体がデカいのをいいことに悪事を働くヤツが一番キライなんだ!」
半夏がボーゼンと見ていてニヤリと笑った。
「オダマキめ、力こぶる部の底力を解放したな~~~」
第十一章 ツタ刈り
美甘姫がふもとの屋敷へ知らせ、舎人たちが山を登ってきた。
氷を落とされて慌てていた山賊たちは、次々に舎人たちに捕えられて、役人に引き渡された。
「オダマキちゃん! オダマキちゃん! 大丈夫?」
美甘姫が血相変えてやってきた。
「あたいは大丈夫だよ、美甘姫。でも薫丸が……」
薫丸は、半夏の腕の中で熱を出してぐったりしたままだ。
「あ~~あ、だらしないわね。公家幼稚園舎ぴちぴち組の時からよく熱出して倒れてたもん。わらわより寝込む回数多かったのよ」
美甘姫が呆れて言った。
「あれ、そうだったの? 薫丸は、美甘ちゃんのことを心配してたのよ」
「わらわは祖父上に鍛えられてすっかり丈夫になったの。オダマキちゃんほど腕力ないけどね」
「えへへ、つい」
美甘姫は半夏に向き直り、
「薫丸くんを馬で屋敷まで送ってやってくださる? わらわたちは、せっかく山に来たからアマズラを刈って、残った氷を持ち帰るわ」
橙実がかたわらに膝をついて、
「姫さま、オダマキちゃん、私もご一緒します」
三人はアマズラが絡みついて生えている大木のところへ行った。美甘姫が下男にハシゴを持って来させて大木に登りついた。アマズラをナタで刈り取っていく。オダマキに負けない力の持ち主だ。アマズラの切り口から樹液がポトポトあふれ出してきている。薪くらいの寸法に切って地上のムシロに並べていく。
姫がオダマキと橙実に一本ずつ渡して、
「口をつけて吸ってはダメよ。唇が腫れちゃうから。口を離して吹いて手のひらに受けて、それを舐めてみて」
ふたりは言われた通りにした。
「甘い! でも、蜂蜜の甘さとは違う!」
「これをたくさん集めて持って帰って、お鍋で煮るのよ」
「美甘姫はよくご存知ですね!」
橙実が感心して言った。
「祖父上に教わって、今まで三度やったことがあるの」
「これは、確かな方法が祖父上からお習いできそうだ!」
「まずは帰って、熱を出した若君に食べさせなければなりませんね!」
「はい!」
オダマキが元気よく返事した。
美甘姫のお屋敷――。
舎人のひとりが氷を削ろうとすると、橙実が、
「私にやらせてください」
ノコギリを持ち、氷を削った。その間に台所でアマズラの樹液を鍋で火にかけていた美甘姫とオダマキは、じっと鍋を見つめていた。
ずいぶん煮込んで透明だった樹液がキツネ色になった。
「これでいいわ」
美甘姫がうなずき、冷ませてから削られた氷にとろりと垂らした。
座敷に床をのべてもらって寝ている薫丸は、まだ熱が下がらず赤い顔をしていた。枕元に美甘姫の祖父上が来ていた。
「大切な九条家の若君じゃからのう。何かあったら大変じゃ」
美甘姫たちが、アマズラをかけた氷を持って行く。
「薫丸、まだ気がつかない?」
オダマキが声をかけた。橙実が、
「大丈夫のご様子です。意識は戻っておいでですが目が開けられないだけです」
「まったく、世話が焼けるわねぇ」
オダマキが、アマズラの器からひとさじ氷をすくい、口元へ運んだ。氷は唇を伝い、薫丸はごっくんと飲みこんだ。
「う……甘い……、冷たい……」
器のアマズラを平らげ、布団の上に起き上がった。
「美味い! もっと所望だ!」
「何言ってるのよ、起き上がれるほど元気なら、自分で作ってきなさい!」
オダマキのお叱りが飛んだ。
第十二章 ダンゴ完成
薫丸一行は、京の都に帰ってきた。
傀儡子一座に一番お客が集まる七つ(午後四時)すぎ。
京の河原には、様々な店の客や傀儡子が、芸を披露するのを観に来る客でごった返す。
そんな中で、薫丸は干物を焼く火をうちわでバタバタしながら、猿まわしの猿たちの番をしていた。
お屋敷の女房、ひじきの声がする。
「若君、おやつの時間ですぅ~~!」
「あ、ひじき! こっちこっち!」
薫丸が手を上げる。
「おやつの時間でございますよ!」
「分かった! お前はこれを持っててくれ」
猿5匹に繋がれたヒモを渡す。
「あ、それから干物を焦がさないように見てるんだぞ」
「えっえっ、このお猿たちを? わたくし、お猿は苦手……、きゃあ~~」
猿たちは早くもひじきの身体に昇りつく。
薫丸は河原から、公家屋敷の並ぶ北へ向けてだっしゅした。下げみづら髪をぴょんぴょんさせて屋敷内へ走りこむ。門を過ぎて玄関からワラジを脱いで上がろうとすると、乳母が待ち受けていた。
「ダメですよ! そんな砂だらけのおみ足で玄関から! 裏側の井戸端でお洗いになってからお上がりください」
急いで足を洗ってから台所へ回り、座敷へ走っていく。
座敷は整然としてチリひとつ落ちていない。薫丸は長畳の上に、所作に気をつけながら正座した。
乳母が菓子台を捧げ持って、しずしずと入ってきた。台の上には、キツネ色のタレのかかったダンゴが盛られている。
「おお、うまそっ! いっただきま~~す!」
合掌するなりパクつき、うっとりとした。
「美味~~い、いや、美味し~~い! アマズラの中に美甘ちゃんから送ってきたみかんの果肉入り! サイコーだ!」
夢中で食べていると、簀の子に人の気配がした。
「橙実……チャンシーさん!」
「アマズラかけのダンゴ、ご機嫌ようお召し上がりで」
「うん! オダマキたちとチャンシーさんのおかげだよ。ありがとう! あれ? どうしたの、そんな旅支度して」
「おかげさまでアマズラを作れるようになりましたので、一度、祖国の唐に帰ってこようと思いまして」
「そうか。帰っちゃうのか」
薫丸は器を置いて、しょんぼりした。
「少し帰るだけで行き来しますよ」
乳母が部屋の端に正座した。
「誠にありがとう存じました。ご恩は忘れません。すぐにお帰りあそばしませ」
「ご馳走さまでした!」
アマズラかけダンゴを食べ終えると、薫丸はすぐに出て行こうとした。
「若君! また河原へ行くおつもりですね! これでは何のために唐菓子の作り方を教えていただいたのか分らぬではありませんか!」
「……」
薫丸の足が一瞬、止まった。
「乳母さま、大丈夫ですよ」
オダマキが半夏と一緒に顔を覗かせた。
「これからは、傀儡子・力こぶる部で身体を鍛えていただきますし、勉学や和歌は半夏さんに教えていただきます」
「え? 傀儡子、力こぶる? 何ですか?」
「乳母どの、ご安心ください。紀伊の国で荷車を投げ飛ばしたオダマキをお見せしたかった! 力こぶる部の成果です」
半夏が胸を張って言ってから、庭先に正座して一本の結び紙を乳母に差し出した。
「何ですか? この結び文は」
言いつつ、乳母は結び文を受け取った。
「いつの間に力こぶる部なんか作ったんだ」
薫丸はふくれっ面だ。
「文句言ったら、おやつなしに戻るわよ」
「うわ~~! それだけはご勘弁を!」
オダマキにまで完全に弱点を押さえられた薫丸だった。
おまけの章
乳母は、半夏から差し出された紙をそっと開いた。
『若、叱る
熟れたる声のいとばちかわ
正座しうっとり
切なき胸よ』
「こっ、これは恋文……? まさか……」
乳母は思わず顔がほてるのを感じ、扇で隠した。
「『ばちかわ』って何かしら?」
陽が暮れるまで簀の子に立って、夢見心地で考えこんでいた。








