[280]正座の下のラブレター
 タイトル:正座の下のラブレター
タイトル:正座の下のラブレター
掲載日:2024/03/24
著者:海道 遠
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
英国のハイスクール生、アレックスはまったくモテないことに悩んでいたが、突然、出したラブレターが女の子たちからOKもらうことになって、自分でもびっくりするやら、浮かれるやら。理由を考えてみると、日本人留学生の麗馬とそのマエストロから「正座」という日本の座り方を教えてもらったことと関係あるようだ。

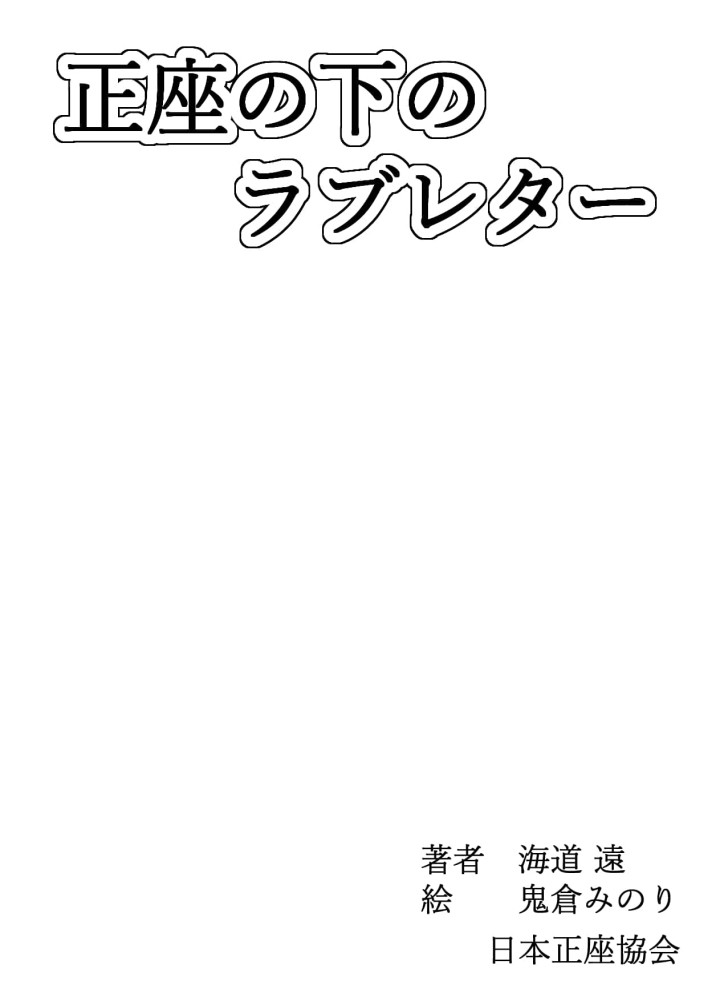
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 ラブ・シック
ビッグベンを間近に見て、若者が行きかう英国のハイスクールのキャンパス。
モテないのが悩みで、勉強もあまり優秀とは言えず、将来の道もあやふやでイライラしていた一年生のアレックスは、ある日、とんでもない幸せに見舞われた。
自分の正座の下に敷いたラブレターが、成功率百発百中という幸せに。
三か月前に渡したリナも、一か月前に渡したマリエットも、先週渡したミランダも、全部オーケーしてくれた!
最初は三人とも「今どきラブレター?」って顔で、イヤイヤ受け取ってくれたのに。
ところがどうだ! 翌日になると、三人とも目をキラキラさせて「ラブレターありがとう、私も好きだったの」と言って、まとわりついてくる子、返事を書いてくる子。
おかげで今は三つ又かけてるモテ男だ。どうして今までふられてばかりいた俺が、急にモテ男になれたのか?
すべては学年一モテる、日本人の麗真(れいま)から「正座」を教えてもらったからだ。いや、麗真の正座の先生、マエストロから正座を教わったからだ。
麗真の名前の英語の意味は、「スーパー・ビューティフル」なんだそうだが、残念ながら実物はそうとは言えない。ひどいニキビ面で口下手だし、ジュゴンのように太っている。それに足がとても臭いので、女子ばかりか男子からも避けられていた。
ところが、その麗真がなぜかモテ始めた。
立ち話していても感じた強烈な足の臭いは無くなり、少しスマートになった。麗真に尋ねてみると、少し前から『日本の正座』を習いだしたという。
「何だい、その、『せいざ』っていうの」
「座り方の種類だよ。日本人がかしこまった時に、その座り方をするんだ」
「どんなの? やって見せてよ」
「え? ここで?」
カフェのテラスだ。地面は石畳みで歩道を挟んで車が行きかっている。
「ここじゃ無理だな。じゃ、椅子の上にするか」
「いいか。背筋をまっすぐにして、かかとの上に座るんだ」
麗真は椅子の上に上がって座った。
「そして両手は膝の上に置く。これが正座だ」
「椅子から落ちそうじゃないか」
「日本では床にタタミというものを敷いてあって、その上に座るから大丈夫さ。とにかくこの座り方は、古代中国で生まれ、近年に日本に定着した伝統的な座り方なんだ」
麗真はドヤ顔で説明した。
「あ~~あ、正座の作法も知らないなんて情けないな。君のお祖父さんは日本にいたとかで、かなり親日家だったんだろう? 正座を教えてもらってないのかい?」
「そんな昔のこと、俺は聞いてないもん」
アレックスは面倒そうに答えると、
「で、麗真。正座と君のモテ方とは、どういうつながりが?」
「俺は正座の先生、マエストロのところで教わった。正座の効能もな。そこで学んだことを手紙に書いて女の子に渡したのさ」
「それだけ? それだけですごくモテるようになったのか?」
「そうだよ」
麗真はケロリとしている。
「先生が教えてくれた『正座の効能』って何だよ」
「えっと、―――『僕のスイートになれば永遠に若いよ』って言いながら、ずっと正座を続けている祖母の、若い時と現在の写真を見せたのさ。これ」
麗真は三枚の写真を見せた。着物を着た女性が写っている。撮影したのは、お祖母さんが二十歳、四十歳、六十歳の頃だ。しかし、お祖母さんの外見はまったく変わっていない。
「そんなバカな! 吸血鬼じゃあるまいし」
「よく見ろよ。ちゃんと年齢相応な顔をしているよ。違いは瞳や肌の輝きだよ。年齢を重ねた方が返って若々しい」
「ええ? 本当か?」
アレックスは三枚の写真を何回も念入りに見て、
「ほ、本当だ……。細かいシワは増えてきてるし、ほうれい線だってうっすらとある。でも四十年前より今の方が瞳も肌も、表情がいきいきしてる! こりゃ、女の子が飛びつくはずだな。誰しも若く美しくいたいもんな」
「だろう?」
「つまり『正座の効能』って、年とらなくなること?」
「うん。正座っていうのは心に作用するからな。ごらん、僕だって少しはブサ男から脱却しそうだろう」
スーパー・ビューティフルとまではいかないが、先日までの足の臭いが強烈な、じゅごんみたいなぽっちゃり男ではなくなってきている。
「ガールフレンドがいっぱいできたから、相乗効果もあるんだよ」
「麗真! 俺にも正座を教えてくれる人を紹介してくれよ」
「マエストロを?」
第二章 正座のマエストロ
麗真は、アレックスに一枚の封筒を渡した。
「何だい? これ」
「正座の先生、マエストロから。前から君に渡したかったそうだ。でも、いいと言うまで開けないでくれって」
「なんだ、そりゃ。俺のことをマエストロは知っていたんだな?」
「前にマエストロの家の前で待ち合わせしたことがあったろ。その時、窓から見てたらしい」
「あっ、覚えてるぞ。窓から黒い服の長身の人がじっと俺たちを見ていた!」
(あの時の、黒一色の洋服の背の高い人が正座の先生? どうして俺に手紙を?)
アレックスは白い封筒を裏返したり、透かしてみたりした。不思議で仕方ない。
放課後、ふたりは構内の大きなケヤキのところで落ち合って、麗真の運転する車に乗り、正座の先生マエストロのところへ向かった。
住宅街にたどり着く。美しく閑静な場所だ。
ひとつの家の玄関の階段を昇って行く。チャイムを鳴らすと、インタフォンから機械音声で「カム・イン」と答えた。ドアを開けて奥へ行くと、アレックスの見たこともない床材が広く敷かれていた。
「これが畳だよ。日本の家にはこれが敷いてあるんだ」
なんだか香ばしい香りがする。
「畳はイグサという植物からできていて、その香りなんだよ」
「ふうん」
ひとつのドアの前に来た。
「マエストロ! 新入弟子希望者、連れてきたよ」
麗真が英語で呼びかけると、傍らのドアが開いて長い服を着た人が入ってきた。足元まである直線のグレーの洋服の上にブラウンのエスニックなジャケットを着ている。
筒のような帽子の下の髪の毛は肩まである黒髪。顔は帽子から顔面にかけて黒いヴェールが垂れているので見ることができない。
男なのか女なのか、若いのか年配者なのか、身体つきが背の高い細身くらいしかさっぱり分からない。少なくともほんわかした女性らしさは皆無だ。あの時、窓から見ていた人物だ。
「初めまして。アレックスと言います」
「先生、ほら、例の手紙の」
麗真が言っても、マエストロは少し頷いて正座しただけだ。
「マエストロ。正座を教えて下さい」
精一杯かしこまって、アレックスは言った。
マエストロは正座のままゆっくり向きを変え、手で自分の前の畳を指し示した。
「おい、アレックス。ここへ正座してみなさいって」
アレックスは麗真が通訳をしてくれたとおり、見よう見真似でその場所に正座してみた。
背筋を伸ばして膝をつき、かかとの上に座ろうとして、バランスを崩して、ばったんと倒れてしまった!
マエストロはヴェールの奥からじっと見ていて、麗真に側に来るよう仕草をして耳元でしゃべった。
麗真がそれをアレックスに伝える。
「全然なってない。背筋は歪んでいるし所作はがさつだし、膝が割れてかかとは遠くに離れているし、話にならん。だって」
「なんだと? だから習いに来てるんじゃないか。丁寧に教えるのがあんたの役目だろう」
「アレックス、まあまあ堪えて。マエストロはとても厳しい方だが根気よく教えてくれるよ」
(先輩の麗真がそう言うのだから間違いないだろう)
思い直して、アレックスは黙った。
「一週間で正座の達人になれます。今はむちゃくちゃだが、スジがよろしい。形だけじゃなく正座の精神まで教えて進ぜようって」
麗真が通訳した。
(どうして自分でしゃべらないんだ?)
麗真にそっと尋ねると、
(英語がまるでダメなんだ)
(な~~るほど!)
アレックスはやっと納得して、正座を真面目に習う気になった。
それから十日後。
アレックスは「正座」をしっかり習得した気になって麗真のように女の子にラブレターを書き始め、現在の連戦連勝に至っている。
女の子三人が順番に誘うので、毎日が楽しくて仕方ない。
(これもマエストロの教えと麗真のおかげだ)
ある日の昼休み、麗真がアレックスの寝そべっている構内の芝生にやってきた。
「アレックス。君、本当に正座の心が分かったのか」
「ああ。麗真と同じ方法で正座の下に手紙を敷き、女性の三枚の写真を同封しておいたのさ」
「それはいいとして、本当に正座の真の心が分かったのかな?」
「正座を続けてると美容にいいってことだろ?」
「ま、シンプルに言えばそうだよ」
第三章 ロックシンガー源氏司
それからひと月ほど経っただろうか。
「私、やっぱりあなたとおつきあいするの、やめるわ」
アレックスが、ラブレターを最初に渡した女の子が言い出した。
「え、どうして?」
「だって、変な座り方をして永遠に若いままでいられるなんて信じられないから」
「あの写真、見ただろう?」
「そんなの、簡単に作れちゃうじゃない」
返す言葉がなかった。
二人目の子も、三人目の子も、もうあなたには飽きたとか言って、他の男の子と付き合い始めた。
最初はショックだったが、しばらくすると立ち直ることができた。元々そんな程度の女の子たちだったんだろう。それより、彼女らに新しい恋人ができて良かったと思う。
(え? なんて寛大なんだろう、俺って。今まで負けず嫌いでわがまま放題で、こんな気分になったのは初めてだ)
「それは、アレックス。君が正座によって人の幸せを願える人間に成長した証拠だよ」
心をすべて見透かしたように、すぐ隣りで麗真が言った。
アレックスは飛び上がった。
「びっくりした! 麗真、いつの間にここに! ――人の幸せを願えるように成長した? そんな効能もあるのか」
「そうとも」
「『心が寛大になる』っていう効能もあるんだな」
しばらくして、とんでもないことが判った。
アレックスの元から去った女の子たちが、マエストロに弟子入りし、正座の下にラブレターを敷いて相手に渡していたことだ。
アレックスはマエストロから習ったことを、気をつけて秘密にしていたのだが、どこからか洩れたらしい。
急いで麗真に伝えに行くと、
「ああ、あれ。宣伝したの、俺だよ。マエストロも生徒が増えた方が嬉しいだろ?」
と、ケロリとしている。
「つまり、俺は客寄せに使われたのか~~!」
「そういう意味じゃないって」
「顔もはっきり分からない胡散臭い(うさんくさい)人間の何を分かれっていうんだよ」
「アレックス、君、何か誤解してるなぁ。よし、ついて来な」
麗真は言うが早いか、アレックスを先日の住宅街までバイクの後ろに乗せていった。
正座のマエストロの家に行くと、今度は地下室へ降りていく。
重々しい扉をノックすると、黒い巻き毛を伸び放題にした男が出てきた。どこかで見たことがある。
「ロックシンガーの源氏司(げんじつかさ)だよ」
「源氏司だって? あの有名な」
アレックスは呆気にとられた。
(俺たちの親の世代から有名な日本のロックシンガーだ。先日、和服で正座していた顔に覆面していたのは源氏司だったのか? しかし、行儀作法の看板を出しているわけではない)
地下の防音壁の部屋で色んな楽器に囲まれて操っていた彼は、ぶっきらぼうに若者たちに言った。
「今、手が離せんのだが、腹が減ってな。とりあえず昼のメシでも作ってくれ」
「ええ?」
真っ黒な真円のサングラスをかけ、原色のマーブル柄のティーシャツを着ている。
「この人がこの前のマエストロ? 顔にヴェールをつけて正座を教えてた人かな?」
(英語だってしゃべれるじゃないか)
アレックスは小首をかしげながら、麗真とスーパーマーケットで食料を仕入れ、一緒にカレーを作った。
「先生、ご飯ですよ~~~!」
何度も呼ぶと、ヘッドホンを外してテーブルにやってきた。
「おお、美味そうにできたな。いただきます!」
源氏司は、勢いよくひと口食べるなり、目をむき出してドタドタと洗面所へ走っていった。ガラガラと豪快なうがいの音が聞こえる。
「なんだ、この辛さはっ。ゴジラになったかと思ったぜ」
「ちょうどいいくらいの辛さのつもりですが……」
アレックスが勇気を出して言い返した。
「あっ」
麗真が叫んだ。
「忘れてたよ! 司先生は超ド級の甘党なんだ。カレーに砂糖やハチミツを入れるくらいに」
「ええ?」
アレックスはまたもや呆然とした。
「君らに教えることがある」
源氏司はテーブルに戻ると、口元をナプキンで拭き、おもむろに口を開いた。
「自分の常識を人の常識と思うな」
「……」
「自分が好きで良いと思うものと、人の思うものは必ずしも合致せん」
「……?」
「味覚ひとつとってもこれだから、恋となると好みは星の数ほどある。男女が結ばれるというのは、奇跡に近い困難なことなんだ。俺なんか星の数よりたくさん失恋してきたわ」
「――!」
「しかし、正座の威力はそれを上回る。難しい男女の仲さえ取り持つ力がある」
やっと源氏司の口から「正座」という言葉が出てきた。
アレックスは椅子を蹴って立ち上がった。
「まわりくどい! もうあんたの手は借りない。麗真、行こう!」
イライラがつのって麗真を急かして地下室を出て行った。
「この封筒、開けてやるっ」
マエストロからの封筒をバッグから取り出して、破ろうとした。
「あ、まだダメだよ。マエストロがいいと言うまで待ってくれよ」
「だから、マエストロに会いに行ったら、あの源氏司だったじゃないか!」
「まあ、もう少し待ってくれよ。な?」
麗真が必死になだめて止めた。
第四章 封筒の中身
正座の効能は、その1、美容に良い。その2、心が寛大になる。つまり外面も内面も美しくなれる。
妙なマエストロから教えられたことが、強くアレックスの頭の奥に残っていた。それに、源氏司が黒いヴェールの人と同一人物とは思われない。
そっちの方が気になって気になって、ガールフレンドを作ることなんかどうでもよくなった。
周りの女の子たちがラブレターのことを忘れた頃、アレックスはもう一度、源氏司の住居を訪ねてみた。
午後のお茶の時間近くになると、数十人の老若男女がぞろぞろと住居に吸い込まれていく。
「ここで何かの集まりがあるんですか?」
アレックスはひとりの中年女性に尋ねてみた。
「ええ。正座の教室があるのよ。日本ファンなので、ひととき日本の雰囲気を味わいに来ているの」
(やはり……)
正座教室は幻じゃなかった。
「先生は日本のロックシンガーですよね」
「え? いいえ。そんなことは聞いたことがないわ。先生は大和なでしこを絵に描いたような美人の先生よ。源氏美洸(みこ)っておっしゃるの」
「源氏美洸?」
アレックスは、皆と一緒に奥座敷に上がり、苦手な畳の上で正座して、先生の来るのを待っていた。
そこへ、派手なTシャツ姿で走りこんできたのは源氏司だ。
「源氏司?」
アレックスはぎょっとした。
「皆さん、たった今、マエストロ美洸が気を失ってしまいました! しばらくお待ちを」
弟子たちはざわざわとした。アレックスも驚いて源氏司にすがった。
「いったいマエストロは、どうされたんですか?」
「しばらくしたら意識は回復する。待っていてくれ。マエストロは完璧であるがゆえに繊細なんだ」
「大丈夫なんですか?」
尋ねようとするアレックスに、さっきの中年女性が、落ち着いて答えた。
「大丈夫よ。よくあることなの。私はもう十年もマエストロ美洸に正座を習っているから承知しています」
源氏美洸は、ふかふかのベッドの中で苦しい夢を見ていた。足が真っ直ぐになったまま座れない夢を。
(座れない……! 正座できない! こんなことって! 助けて、マイルド先生!)
座ろうとしてよろめき、冷たい地面に倒れてしまった。紳士の後ろ姿が遠のいていく。
(あの桜の刺繍の座布団に正座しなくては。あの下には……)
瞬間に目が覚めた。
たくさんの顔が見下ろしていた。源氏司も、お弟子さんたちも、そして、英国青年も。
横たえられたマエストロのヴェールが外されて、アレックスは、やっと素顔を見ることができた。なんと麗しい……。
東洋人特有の真珠の光沢の肌、黒々とした濃い睫毛。頬がだんだん赤みを帯びてきた。
「大丈夫か、美洸」
源氏司が頬をピタピタすると、マエストロ美洸はしっかり目を開いた。
「……また失神してしまったのね。ヤワな身体だわ」
夜空のような瞳を下に向けてため息をついた。
日本語なので、アレックスは彼女が何を言ってるのか分からない。そこへ麗真も駆けつけた。
「マエストロ美洸、大丈夫ですか。あまり思いつめないで」
「ありがとう、麗真くん」
「アレックスも心配してここにいます」
眼が合ったとたん、マエストロ美洸は言葉を失くして胸を手で押さえた。
「マエストロ、胸が痛むのですか。今日のお稽古は中止しましょう」
源氏司がお弟子さんたちに言い渡し、マエストロの教室から、お弟子さんたちがぞろぞろ退出した。
「マエストロ美洸……」
やっと初めて彼女に呼びかけて、アレックスは手を握った。
「開けますよ。麗真経由でもらった手紙を」
アレックスはジャケットのポケットから白い封筒を出し、今度こそ封を開けた。そこには英語で、
「アレックス様
突然ではございますが、この正座教室を
貴方にゆだねたく、お願い申し上げます。
源氏美洸(正座師範)」
「これは……」
アレックスは天地がひっくり返るほどびっくりした。
「これはいったい、どういうことですか? どうして僕が正座教室を任されるなんてことに?」
すると美洸は、流暢(りゅうちょう)な英語で答えた。
「アレックス……あなた、お祖父様のアレックス・マイルド先生にそっくりだわ。穏やかな黄金の髪といい、透き通った碧い瞳といい」
「祖父のことをご存知なんですか?」
「日本でね、私の高校の恩師だったの。正座や行儀作法は彼から習ったのよ。とても日本を愛し、日本人より日本文化を愛していた。高校を卒業してからも彼の正座のお稽古を受けるために通い、お世話になったのよ」
「そうだったんですか。祖父は僕が中学生の頃に亡くなったので、そんなに記憶にないんです。殆ど日本にいましたから」
「本当に、心から日本文化を愛して下さっていたわ」
美洸の瞳は、過ぎ去った日々を思い出して蕩けそうになった。
「マエストロ美洸さんは、祖父の弟子だったんですね。でも、いきなり正座教室を継げと言われても困ります……」
「さっきの封筒はお祖父様の遺言なのよ。先生が亡くなる時にお預かりしたの。だから受け取って実現してもらわないと、困るのです」
「遺言~~? そうは言われてもなあ……」
アレックスにとって、晴天の霹靂(せいてんのへきれき)だった。
祖父が日本にばかりいて、たまに帰ってくることは両親から聞かされていたが、日本で何をしているのかまでは、教えてもらえなかった。
第五章 立ち場所を深く掘れ
美洸は深い眠りについた。眠ってすり減った心の疲れを取り去ろうとでもするように。
枕元で源氏司が口を開いた。
「俺はこのとおり、しがねえロック野郎だが、美洸は俺の年の離れた妹でな、日本に来ていたアレックス・マイルド先生にそれは心酔していたよ。妹から話を聞いていても素晴らしい人だった」
アレックスと麗真は、おとなしく聞いていた。
「ほら、この前、自分の常識と他人の常識は違うって話しただろう? あれもマイルド先生の受け売りさ。先生は、正座している間に昔に読んだ本とか、心に響いた名言とか、いろんな言葉を思い出されたんだそうだ」
源氏司はアレックスの顔を覗きこんだ。
「お前さん、何か悩んでいたんじゃないのか? それで、憂さ晴らしにラブレター作戦なんかやったんだろう」
「はあ。お見通しなんですね」
アレックスは降参とばかりに肩をすくめた。
「この先、自分がどの道を進んでいったらいいか分からなくて、モヤモヤしてたんだ」
「じゃ、『自分が立っている所を深く掘れ。そこからきっと泉が湧き出る』これは、マイルド先生が覚えていたニーチェの言葉だ。妹が言われたんだそうだ」
「『自分が立っている所を深く掘れ』?」
「お前さん、今、正座教室をゆだねられているんだろう?」
「あっ」
「進路に悩んでいるなら、用意された位置を深く掘ってみるっていうのもひとつの手だぜ。かくいう俺も、ロックしか興味なかったんで、先生のおかげで深く掘る決心がついたんだけどな」
丸い黒メガネをずらして苦笑いした。見返したアレックスも、バツの悪そうな顔をしていたが、微笑み返した。
次に美洸が目を覚ました時は、翌日になっていて、日本間の障子越しに柔らかい陽が射しこんできていた。
「私……?」
額に乗せてあった冷たいタオルがずり落ちた。
「あ、まだ寝ていてください。熱があったみたいだから」
「看病してくれていたの?」
アレックスは頷いた。
「ありがとう。少し根を詰めすぎたようね。頑丈にできていないのに」
美洸は毛布の中から片手を出し、指さした。
「……そこの刺繍の座布団の下に……」
「え?」
美洸が指さした先には、床の間の前の、桜色の刺繍が艶やかな座布団があった。
「いつも私が正座しているところ。桜色の座布団の下に手紙が入っているの。それを出してくれる?」
桜色の封筒が入っていた。
「どうぞ、開けて。今度は遺言じゃなくてあなたへの手紙よ。つまり……」
「――?」
ペーパーナイフを使ってそっと開封してみた。そして便箋を開けるとそこには、ひと言だけ。
『いっかい わたしに あやまれ』
「謝れ?」
「そうよ!」
目にいっぱい涙を溜めて、美洸は勢いよく起き上がった。
「アレク、謝ってよ。いつだったか麗真くんと一緒にこの家の外で見かけた時から、私は何も落ち着いてすることができないのよ。何をしていても頭の中をよぎるのは、あなたの深い瞳、柔らかそうな髪の毛、それから……とにかくあなたのことが頭を離れないのよ。正座が乱れてしまうくらいに!」
いきなりの剣幕に、アレックスはたじたじした。
「ま、待ってよ。美洸さん。それはもしかして」
「これは、ラブレターよ! 何か月も前から書いては消し、書いては破り、やめようと何回も諦め、また筆記用具を出してきて書かずにいられなかった……渡す勇気も出なかった……長い間、その座布団の下に敷いていたものよ」
「ええっ、待って! 美洸さんは俺よりずいぶん年上の正座のマエストロじゃないか。どうして俺なんかを」
「そんなこと、私に分かるわけないじゃないの。誰を好きになるかなんて。歳の離れた弟ほど年下の人でも。分からなくて苦しんだわ。1回どころか10回でも100回でも謝ってほしいわ」
「もしかして、美洸さんは俺の祖父にあこがれすぎていて、孫の俺に勘違いした気持ちを持ってしまったとか?」
「………」
美洸がムカッとした顔を向けた。
(ああ、俺、よけいマズいこと言っちゃったかな?)
「もう許さないわ! 100万回謝っても許さないわ! こうなったら、絶対に正座教室を継いでもらいます! 一生かかってね!」
派手に言い散らすマエストロの言葉に、アレックスは真っ赤になった。
今までモテたいとか思ってたことが本当にバカバカしく思えた。周りの女の子は軽い気持ちで恋人をとっかえひっかえするような子たちで、自分もそうするのが当たり前だと思っていた。
『自分の当たり前と人の当たり前は違うんだぞ』
源氏司の言葉まで思い出した。
美洸は違う。年下であろうが、名もないハイスクール生であろうが、対等な相手として真剣に愛してくれている。きっと窓の外に見た時に、直感で分かったんだ。
美洸とアレックスは同時に立ち上がった。
「正座しに行きましょう! 心穏やかになるために……」
「心穏やかに幸せをかみ締めるためにだね」
アレックスが答え、美洸はこっくりと頷いた。
ふたりは座敷に行った。そこには美洸の座布団が一枚。彼女は向かい側にもう一枚、座布団を敷いた。
そして、硯箱(すずりばこ)を出して来て墨をすった。
「これは?」
「日本の筆記用具よ。今度こそ、本当のラブレターを交換しましょう」
「また書くの?」
「書いて証拠として置いておきたいの」
「わ、分かったよ。疑り深いんだなぁ。正座の効能って寛大になることだって教わったのに」
ふたりは向かい合って、神妙に所作を確かめながら正座する。
背筋を真っ直ぐし、美洸はお尻の下に着物を敷き、かかとの上に座る。両手は膝の上に置く。
次は、しぶしぶ筆というものを持って白い紙に向かう。
筆と墨で格闘したアレックスは、書き損じた半紙の山に埋もれそうになり、顔には墨があちこちについていた。
どうにか書き上げたふたりは、半時間ばかりラブレターをそれぞれの座布団の下に敷いてから、「せえの」でお互いに渡した。
ふたり同時に開いてしばらく難しい顔をしていたが、やがて「ぶっ」と吹き出した。
半紙のラブレターには、それぞれ、
「愛しています」
「アイ・ラブ・ユー」
と、ひとことだけ書かれていた。
ふたりは吹き出した。
障子窓の側の桜が、笑い声につられたかのように、はらはらと舞い踊った。








