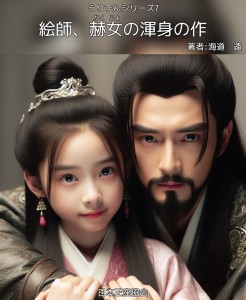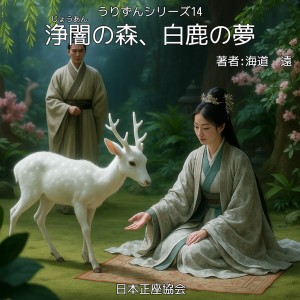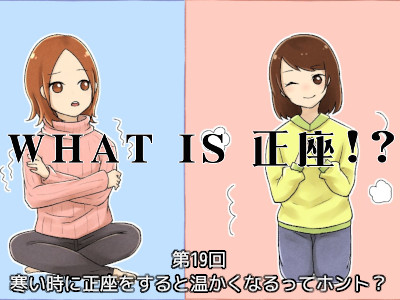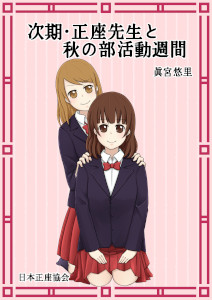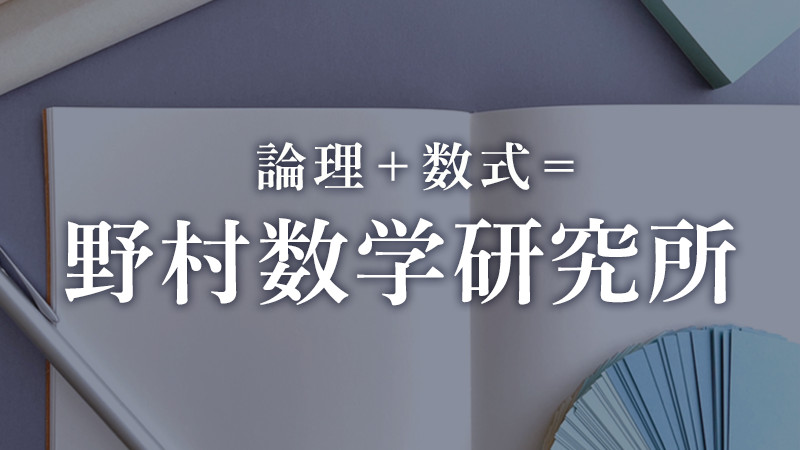[324]うりずんと天燈鬼
 タイトル:うりずんと天燈鬼
タイトル:うりずんと天燈鬼
掲載日:2024/12/08
シリーズ名:うりずんシリーズ
シリーズ番号:1
著者:海道 遠
あらすじ:
日本三景のひとつ天橋立には、月に一度、夜に邪鬼が灯りを点すことになっているが、最近とぎれているので、漁夫たちは不自由していた。
正座師匠の万古老の命令で天橋立を訪れた百世(ももせ、女の子・300歳)は、南国の早春の青年神うりずんと合流して、鬼からわけをきくことになった。
ふたりが無事に会ってから、うりずんは文殊堂の一室で、天燈鬼に正座の所作を教えて話を聞く。
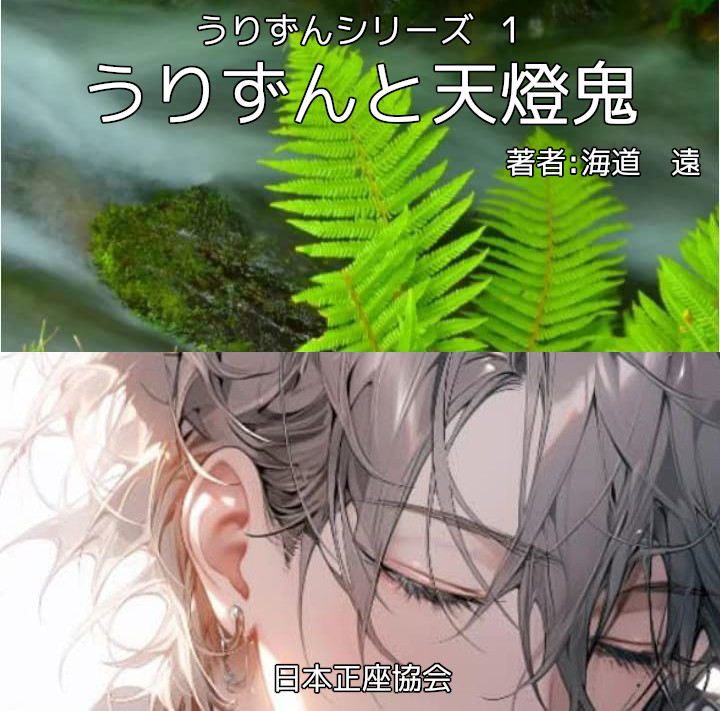
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
日本三景のひとつ、丹後の国の天橋立は、海岸線に沿って長い長い波の打ち寄せによって作られた砂州(さす)という地形である。
砂州に生えている立派な一本松に、毎月16日の夜に燈火が灯る(ともる)。罪を犯した邪鬼が罪を償うために毎月、課せられた仕事だという。その燈火が、ある時から灯らなくなった。
海から燈火を毎月見ていた漁夫(ぎょふ)たちは、
「この頃、天燈鬼(てんとうき)の灯りが点ら(ともら)ないな。どうしたんだろう?」
「天燈鬼め、サボってやがるのか?」
「邪鬼にされて燈火を点す罰を受けているのに、この上、罰を増やしてもらいたいのかね?」
「ありゃあ、不思議な燈火だ。舟から見れば遠くにあるのに両手で囲むと、目の前の蝋燭(ろうそく)の明かりに見えるんだ」
漁夫の男たちは笑ってウワサしていたが、天橋立の根元にある智恩寺・文殊堂(ちおんじ・もんじゅどう)の住職は、暗い面持ちでいた。
第一章 天橋立のたもとで
ツツジが満開になった晩春のある日、山の上から天橋立を見つめる11歳くらいの少女がいた。
まともな着物も着ず手足を出したまま、荒縄を腰に巻いた男の子のような身なりで、長い銀髪も無造作に縄で結んでいる。
文殊堂に参詣する旅人はひきも切らない。少女はその中に、目ざとくひとりの人物を見つけて走り寄った。
「あんた、ひょっとして『うりずん』て、兄さんじゃないかい?」
甘い茶色の髪をした青年が振り返り、前髪が鼻筋にかかった。
「いかにも、『うりずん』だが……。お前は?」
「あたいは正座師匠の万古老の弟子で、百世(ももせ)ってんだ。師匠の言いつけで天燈鬼の件で、あんたと合流しにきたのさ」
「お前が万古老師匠の弟子――? よく私を見つけたな」
「そう。ここの文殊堂のご住職から師匠に手紙が来たのさ。南国から、うりずんていう、やんちゃを呼んだってね」
「やんちゃはひどいなぁ〜、私は南国では尊敬されているんだぞ、名前の通り早春の季節みたいに爽やかな男だと」
「ひぇ~、こっちの早春はまだまだ寒いぜ」
「南国と丹後じゃ、季節が三月ほどズレてるんだよ」
笑った『うりずん』は真っ白な歯を見せて、誠実そうな若者だ。尊敬されているという言葉がよく分かる。
(いや、「モテる」と言った方が当てはまるだろう)
「じゃ、これからは『うりずん兄ちゃん』て、呼ぶね」
百世は思った。
(でも、あたいの馬宝刀(まほと)の方が素敵♡だな)
うりずんと百世は、智恩寺・文殊堂の大きな門をくぐり、修行僧に奥へ通された。
座敷にご住職が待っていた。
「うりずんさん、遠路はるばるご苦労さんです。百世ちゃんも、お迎えご苦労さまじゃったな」
伊勢の名物、赤福のような「智恵の餅」を出してくれた。
「いただきまっす!」
百世はすぐにパクついて、平らげてしまった。
「天燈鬼の気配は、すでに感じております。夕方には寺に来るはずです」
うりずんは正座を改めて、ご住職に告げた。
「おお! すでに気配を? では宜しくお願いいたします」
ご住職は丁寧に頭を下げて座敷を出ていった。
空は黄昏(たそがれ)て、夕星(ゆふづつ)の星が煌めきはじめた。
寺の裏口の木戸がトントンと鳴った。
「天燈鬼だ」
うりずんが短く叫び、裏口へ向かった。
「こちらは文殊堂のご住職さまのお部屋でしょうか? ワシは四天王さまにお仕えしていた小鬼でございます」
「天燈鬼だな」
うりずんが確かめると、声は、
「さ、左様でございます。あなたさまは?」
うりずんは裏口を開けながら、
「私は正座師匠の万古老さまからの命を受けて、お前を迎えに来たのだ」
「ほほっ、美しい若い神さんですな」
天燈鬼は短い角を2本生やして、うりずんの肩までしか背丈がない。下半身だけボロボロの衣を着け、ギョロギョロした眼に牙を生やした歪んだ口元はいかにも邪鬼だが、どこか憎めない。
「座敷に上がれ」
「よ、よろしいので?」
ガマガエルのように這いつくばって、遠慮がちに座敷に上がった。
「万古老師匠から習った正座の所作を教えてやる。まっすぐ背筋を伸ばして立て。できるところまででよい。床に膝を着き、着物の裾に手を添えて尻の下に敷き、かかとの上に座れ」
「こ、これでよろしいので?」
転がりそうになりながら、燈火鬼は、どうにか正座した。
「おじさん、まあまあ上手に正座できたんじゃない?」
百世が言った。
「ありがとよ、お嬢ちゃん」
第二章 サボっていたわけ
「さて……と、正座もできたことだし、そろそろ真面目に話そうか」
うりずんは燈火鬼の真正面に正座した。夕星が地上に降りてきたような透明な神々しさだ。
「天燈鬼。お前は、かつて四天王さまにお仕えしていたそうだな」
「へ、へい。お仕えというか、踏まれて……」
「酒が過ぎて、罰に寺の手水鉢(ちょうずばち)を支えるよう命じられたとか」
「へい」
「しかし、手水鉢が重くて逃げ出した。今度は罰に四天王さまから、月に一度、天橋立の一本松に燈火を灯すよう命じられたんだろ。漁夫らは、その灯りを頼りに漁に出たり帰ったりする。責任ある役目だ。それをも最近、なおざりにしているそうではないか。いったい、どうした」
うりずんの水色めいた瞳が天燈鬼を睨んだ。
「あの燈火の重いことと言ったら、肩の骨が砕けそうなんですぜ。あれを長い間、持ち上げているのはどんなに重労働なことか。それに……」
「それに、何だ?」
天燈鬼は歪んだ口をモゴモゴさせていたが、やや赤くなって、
「……かかぁがよ、かかぁが身ごもったんだ」
「ほう、それはめでたい。それなら、よけい使役に精を出さねばな」
「それが……、後しばらく、かかぁの腹にいなきゃならない赤ん坊が、もう出てきたいようで……、まだ手のひらに乗る大きさ、柿ひとつ分くらいなのによ」
天燈鬼の垂れ下がった眼に涙があふれた。
「それは……困ったことだな。が、何ゆえ、そんなことが判るのだ?」
「ワシが罰を受けて天橋立の務めに就いている間、かかぁは湖国の三井寺っていう寺の衆宝観音さまのところに身を寄せているから、観音さまが思念を送ってくださっただよ」
「衆宝観音さまが―――、その観音さまなら聞いたことがある。羅刹を救い、群衆を護り、群衆の持つ財も護ってくださると」
うりずんの瞳が宙を睨んだ。
「衆宝観音さまなら、よく知っているよ! あたいの正座仲間の孔雀明王さまとも正座勝負したことあるもん! 片膝立て座りがはんなりして、すっごく色っぽいおばさんさ!」
百世が鼻高々にクチバシを突っ込んだ。
「……コホン」
うりずんが咳ばらいした。
「で、天燈鬼。衆宝観音さまの元にいるおカミさんも、赤ん坊を産みたいと?」
「そうなんでさぁ〜。それで困っちまって、ワシは仕事が手につかなくて、また酒に手を出し、一本松に燈火をかかげる仕事をサボっちまっただよお」
天燈鬼は、下半身のぼろぼろの裾かふんどしの端っこか境目が判らない場所で涙を拭いた。
「お前はどうすれば安堵する?」
「そうだなぁ、かかぁの元気な顔を見て、赤ん坊が無事に生まれた姿を見れば安心して、一本松に明かりを灯す罰に専念できると思う」
「酒は断つか?」
「は、はい。今度こそ!」
天燈鬼は土下座した。
「では、湖国の衆宝観音さまの元へ送っていってやろう」
「ありがとうござえやす! うっ、いててて! 足がシビレちまって」
「シビレくらい、直し方を教えてやるから、ついてこい!」
うりずんは、すんなり立ち上がって草鞋(わらじ)を履いた。
第三章 湖国に来て
三人づれは湖国に到着した。
百世は湖国の三井寺までふたりについていった。衆宝観音さまの元に着くまで見届けなければ、万古老師匠にどやされるからだ。
それに、衆宝観音の元で修行を続けている元、羅刹(らせつ)の馬宝刀少年にも会いたかった。
丘の上から、大きな湖が見える。
「へええ。これが、琵琶の湖ですかい! なんてでっかいんでしょうね!」
天燈鬼は、ぴょんぴょん跳ねて嬉しそうだ。
「これ、物見遊山に来たわけではないぞ。天燈鬼。衆宝観音さまの元にいるカミさんに会って、お腹の赤ん坊のことについてちゃんと話し合わねばならん」
「へ、へい」
三井寺の立派な山門に到着した。
ツツジや春の花が咲く庭を歩いていくと、傍らに衆宝観音さまの片膝立ての輝かしい座像があった。
うりずんは胸が熱くなるほど、どっきりして立ち止まった。あまりにも崇高なお姿だったからだ。
「衆宝観音さま、ご機嫌よう!」
百世が声をかけると、観音さまは伏せていた眼を上げた。
「ま、まあ、百世ちゃん! いきなり驚いたわ。そちらの方々はどなた?」
「南国の春の精、うりずんさんと、天燈鬼さんだよ」
「まあ……」
衆宝観音さまの眼は、うりずんをとらえるや動かなくなった。
「なんて……春の微風のように美しいお方……」
天燈鬼が土下座してからガラガラ声で、
「これはこれは衆宝観音さまでございますか。お初にお目にかかります、天燈鬼と申します。カミさんがお世話になりまして、なんとお礼を申し上げてよいやら」
天燈鬼が照れて深く頭を下げたはずみに、下半身の衣がめくり上がったので、ふんどしが丸見えになり、衆宝観音が思わず悲鳴を上げた。
寺の奥座敷にうりずんたち三人が通されて、衆宝観音さまも正座した。しばらくすると、肩のところで丸く巻き上げた髷(まげ)の、薄衣をまとった天女のような若い女がやってきて茶を出した。
「お前さん!」
「あ、かかぁじゃねえか! お腹の子は?」
「お前さん!」
どうやら、天燈鬼の妻らしい。
ずんぐりして歪んだ顔の鬼の妻にしては、唐の国の女官のように美しい妻ではないか。まったく釣り合わない。うりずんと百世は唖然(あぜん)とした。
「かかぁよ、大丈夫なのかい、立ち働いて。もう臨月なんじゃないのかい?」
「そうなのよ。小さいけれど出てきたいらしいの。それで、観音さまに取り上げていただこうかと思っているの」
お腹をさすりながら、天女のようなカミさんはため息をついた。
第四章 夫婦げんか
天燈鬼は、赤ん坊がいたいだけ母体にいた方がよいという考えで、カミさんは、心配だから衆宝観音さまに陣痛薬を飲ませていただき、早く産んでやりたいという考えだ。
夫婦ふたりの意見が正反対なので、ぶつかり合った。
衆宝観音さまも、うりずんも、百世も、夫婦のことに口出しできずに困り続けていた。
「お前の精進が足りないから、こんなことになるんだよ、かかぁ!」
「何、言ってるのさ、元はといえばお前さんが、大酒飲んでサボってるから邪鬼にされて、燈火なんか持たなきゃならない罰が当たったんだろ!」
ふたりして、つかみ合いのケンカをはじめそうな勢いだ。
「なんだと、かかぁ、ワシがもらってやらなきゃ、貰い手がなかった貧しい下女だったくせに!」
「モラハラだわっ! あんたの今の姿を鏡に映して見てごらんな! どこから見ても、おぞましい地獄の邪鬼じゃないか! これも皆、お前さんがサボっているからだろ!」
「なにい! お前の言い分こそ、モラハラじゃねえか」
天燈鬼が飛び上がって妻の顔面に張り付いた。きれいに結ってあったおカミさんの髪がめちゃくちゃになってしまった。
「ちょっと、ふたりとも落ち着きなさい!」
「天燈鬼さん、おカミさん!」
うりずんと衆宝観音がふたりを引き離そうとした時、障子が開いて、手足に脚絆を巻いた少年が入ってきた。
「あのう、観音さま、知恩寺・文殊堂のご住職というお方がお見えなんですが、お通ししてもよろしいでしょうか」
「あ、馬宝刀! ちょうどいいところへ。このふたりを引き離して! おカミさんのお腹には赤ちゃんがいるのよ!」
百世が頼み、馬宝刀も手を貸して、ようやくふたりを正座させた。天燈鬼とおカミさん、他の者も肩で息をしている。
「やっとふたりとも座ったわね。馬宝刀くん、いいわ。ご住職さまをお通ししてちょうだい」
衆宝観音さまが言った。
しばらくして、知恩寺のご住職が座敷に姿を現した。
「これはこれは、衆宝観音さま、すっかりお世話になりまして……天燈鬼の嫁を預かっていただき、ありがとうございます」
慇懃(いんぎん)に頭を下げた。
観音さまは、
「うちの名物、蓮の饅頭をお持ちしてくれる? 馬宝刀くん」
「はい!」
馬宝刀が薄い桃色の蓮饅頭とお茶を持ってきて、ようやく皆は静かになった。
「実は、天燈鬼の相方、竜燈鬼(りゅうとうき)が、情けない顔で訪ねてきてのう、天燈鬼の灯が点らんから天橋立の龍神までが、おかんむりのようなのじゃ。丹後の国の海運がうまくいっておらんと言うてのう」
「な、なんですと?」
「なんですって!」
天燈鬼とおカミさんが同時に叫んだ。
竜燈鬼は天燈鬼の相方で、小さな竜を身体に巻き付けて燈火をかざしている。小さな竜の巳巳子(みみこ)が天橋立の海の龍神さまの意を、文殊堂のご住職に告げたという。
「龍神さまがお怒りに!」
天燈鬼が真っ青になった。
「いつまでも産まれぬ赤子のせいで、龍神さまが!」
「何を赤ん坊のせいにしてるんだよ! あんたが、サボってるからだろう!」
再び揉めはじめたふたりの間に、衆宝観音が入った。
「天燈鬼さんは反対のようだったけど、安心していただくために、赤さんに生まれてきてもらうしかなさそうね。ご加護をいただくよう、龍神さまにお文を書きます」
第五章 天橋立の龍
「しかし、観音さま、柿ひとつ分くらいの大きさで産まれてきて、生きられるんですかね?」
天燈鬼が恐る恐る尋ねた。
「大丈夫です! このわたくしが過去、何人取り上げてきたと思っているの? それに百世ちゃんは魂売りに売られてきた時は、オタマジャクシみたいな大きさだったのよ!」
「オタマジャクシ? あたいが?」
「ええ。万古老師匠からお聞きしたのよ。さあ、男性は皆、外に出てください! 百世ちゃんは残って、わたくしのお手伝いをしてね!」
「は、はい……」
~~というわけで、うりずんも天燈鬼も、ご住職も馬宝刀も、部屋から追い出された。
その頃、孔雀明王まゆらは、天帝に命じられた用事から帰る途中、ピーちゃんの背中に正座したまま乗って、北海(日本海)の上空を渡る途中だった。
「あ、東の空が明るくなってきたよ。夜明けになってしまうわ」
眼下には藍色の波が果てしなく続く海だ。
「もうすぐ丹後の海に着くよ」
ピーちゃんが言って、
「待てよ、夜明けの光じゃないよ」
まゆらちゃんがよく見ると、暗い海から無数の鬼火が飛び上がり、海の上を照らしているではないか。
「鬼火なの? こんなにたくさんの鬼火を見るのは初めてだわ。何かあったのかしら」
「この下は、そろそろ天橋立があるところだよ」
「あっ、あれは何かしら? ピーちゃん!」
光が眩しくてよく見えないが、海が激しく波うって渦ができた。
そのうち渦の中心から、巨大な長いものが無数の鬼火に照らされて飛び出してきた!
「うわ〜〜〜!」
ぶつかりそうになったピーちゃんは、すんでのところで羽根をバタバタさせて、長いものを避けた。
大きなアゴ、ウロコだらけの顔にギョロリとした巨大な目玉。ギザギザの口元と巨大な牙が見えて、ぞっとした。
「龍神だ〜〜〜〜!」
もう少しで大きな口に、パクリとされるところだ!
龍は天を目がけて登っていく。
たくさんの水しぶきで、まゆらとピーちゃんは、ずくずくびしょびしょになってしまった。
【どこだ〜〜! 鬼火のひとつが足りん!】
恐ろしい響きの叫びが登っていき―――、
空高く朝日に照らされた龍は、今度は落下してきた。
「うわ〜〜! 落ちてくるぅ〜〜〜!」
まゆらはとっさに、ピーちゃんの見事なしっぽの羽根を頭に被ったが、ピーちゃんはあばれるわ、羽根のすき間から水はダダ洩れするわ、何の役にも立たなかった。
大きな龍の頭が落ちていったと思うと、海へ突っ込んでいく水しぶきが湾の全域に飛び散った!
海面へ吸い込まれるように、龍は飛びこんでいった。
まゆらとピーちゃんは渦を見下ろして、はぁはぁ、息をするのがやっとだ。
「さっきの叫び、何がどうしたって?」
「お……鬼火のひとつがどうとか……」
気がつくと、少し先に天橋立が見えた。
「ここの鬼火って、確か天燈鬼と竜燈鬼が点す係の……」
「天燈鬼が一本松に灯す明かりのはずだよ」
ふたりの眼下に文殊堂が見えた。
第六章 お産
「かかぁ、もうひとふんばりだ、頑張りな!」
障子の外から天燈鬼のわめきが聞こえて、やかましいったらない。
「静かになさってくださいな! 母体に障りますから!」
衆宝観音は叫び返した。天燈鬼のおカミさんは、寝床の上で顔面に汗をたくさんかき、いきんでいる。
「衆宝観音さま、あたいには、ぜんぜん赤ん坊の姿が見えないんだけど、本当に産まれるの?」
百世が観音さまのかたわらから尋ねる。
「どうやら、柿の実より小さいようですから、見えないのですよ」
「柿の実より小さい?」
「小さいというより、抱くことができない赤ん坊よ」
「抱くことができない?」
庭に面した障子がメリメリっと音がして、全身びしょ濡れのまゆらとピーちゃんが、お寺の縁側に着地した。
「観音さま、まゆらです! お邪魔いたします! お産ですって?」
「あっ、まゆらちゃん!」
百世が飛び上がった。
「ピーちゃん、あんたは向こうへ行ってなさい!」
まゆらがピーちゃんを追いはらってから、やっと入ってきた。
「観音さま、この女人は……」
「天燈鬼のおカミさんなのだけど、普通の赤さんではなさそうなの」
「天燈鬼の子どもなら、人間ではないでしょうね」
外から大勢の人々の悲鳴が聞こえた。修行僧も小坊主も、参拝客も右往左往している。
「きゃああ~~~!」
「わあっ! 何だ、龍神さまか!」
まゆらと百世が縁側に出ると、彼方に見える琵琶湖から巨大な龍が飛び出してきて、こちらへまっしぐらに向かってくるではないか!
大木ほどもある胴まわりの巨大な龍が、寺の山門の上を飛び越えてきた。さながらヤマタノオロチだ。
「龍神さま!」
衆宝観音さまも縁側に出た。
「これは、龍神さま。なんとしたことで?」
響もす(どよもす)声がして、障子一枚よりもでかい目玉で観音さまをにらんだ。
「天燈鬼の嫁のお産を感じて、天橋立の地下海を通って琵琶湖にやってきたのじゃ!」
「産まれてくる赤ん坊に、龍神さまが何か?」
「赤ん坊は余に必要な鬼火たちじゃ。ひとつ足りなくても困るのじゃ。産まれたら、すぐにもらっていく!」
百世が目をくりくりさせて、
「赤ん坊が鬼火? それで抱くこともできないんだね!」
「人間に抱かせるひまなぞない!」
百世は、龍の前で落ち着いた所作で正座した。
「お願いです。龍神さま。鬼火の赤ん坊に、おふくろさんのお乳を飲ませて――、おとっつぁんにも抱かせてやってくださいませ!」
「お前は?」
「正座師匠の万古老の弟子で百世と申します」
神妙に頭を下げた百世を見て、龍はモヤのように姿を消し、直衣姿の貴公子になった。
「万古老師匠の弟子とな、娘」
「はい。あたいも神仙の者ゆえ、母の乳も父の温かさも知りません。どうか、どうか……」
貴公子はうなずき、
「分かった。鬼火の赤ん坊を両親に抱かせよう」
「あ、ありがとうございますっ」
その時、障子の内側から、元気のよい産声が上がった。
「ふぎゃあっ、ふぎゃあっ」
衆宝観音さまが産まれたばかりの鬼火の赤ん坊を白い布にくるみ、おカミさんに抱かせた。
(抱っこできるの? 鬼火の赤ん坊が……)
百世は呆気にとられていたが、天燈鬼もがまんできずに部屋に飛び込んできた。
「おお、おお、これがワシの子か……」
(親たちには、赤ん坊が見えているんだろうか?)
そっと覗いてみると、真っ赤な顔をした普通の赤ん坊ではないか。百世は首をかしげるばかりだ。
(観音さまが細工でもしたのかな?)
(お前の味わえなかった幸せを、鬼火の赤ん坊に味合わせてやっただけじゃ)
龍神の声が百世の耳元で聞こえた。
「龍神さまの仕業だったのね! 味な真似してくれるじゃないか!」
貴公子の直衣の肩を、バシンとたたいた。
「これ、百世ちゃん!」
まゆらちゃんと観音さまがそろって叱った。
第七章 赤ん坊を送り
その光景を、うりずんは穏やかに眺めていた。
(母の乳――。私も知らないな)
うりずんの胸中は、苦しいくらい甘酸っぱい香りに満ちた。観音さまが赤ん坊に手際よく産着を着せて、くるくると白いおくるみで包んで母親に近寄せてやる仕草を見て、彼の胸は熱くなった。
(私に母親がいれば、こんな風だったのかな……)
龍神の貴公子は赤ん坊を抱いて、三井寺を後にした。
天燈鬼とおカミさんは、目に涙をいっぱい浮かべて、
「良くしておもらいよ。龍神さまのためにご奉仕するだよ〜〜」
おカミさんが、天燈鬼の涙を拭いてやりながら、
「お前さん、寂しいのかい? アテがいくらでも産んでやるさ」
「ほ、本当け? いくらでも産んでくれるのけ?」
天燈鬼は、むせび泣いた。
まゆらちゃんとピーちゃんは山寺へ帰り、三井寺は静寂に包まれた。
座敷にはホッとした衆宝観音さまと、うりずんだけになった。
「衆宝さま……」
うりずんが照れくささと尊敬がないまぜになった顔で、観音さまから目を離せずにいた。
「ご苦労さまでした。衆宝さま」
「お産なら慣れているわ」
「赤さんが、あんなに小さいなんて……。産まれてすぐにあんなに力強くお乳を吸う姿を初めて見ました。神秘的だったなぁ。私が人間に生まれていたら、あんな時もあったのだな」
「わたくしも人間だったら、あんな子を産むかもしれなかったのですね」
ふたりは息のかかるほど近づき――、見つめあった。
障子越しに入ってくる柔らかい黄金の陽射しの中で、衆宝さまの唇に、うりずんは思わず知らず唇を重ねた。
「あ……あなた……」
「衆さんって呼んでいい?」
うりずんの手が衆宝さまの耳の後ろにすべりこんだ。ふたりの鼻腔にクチナシの花の香りが満ちて、むせるようだ。
晩春の寺の一室は静まりかえっていた。
第八章 毘沙門天さまの元へ
うりずんは万古老師匠の待つ洞窟へ行く前に、四天王に謝りに行く天燈鬼を送っていくことになり、百世は洞窟へ先に帰る。
「やはり、任務をサボったのだから、四天王の筆頭格、毘沙門天さまに謝らなければならないだろう」
「へ、へえ」
天燈鬼は地べたに伏せるように神妙にしている。
「大きな器の毘沙門天さまは、きっとお許しくださるぞ」
「へえ。うりずんさま、ありがとうごぜえます」
しかし、どこか不安げだ。
万古老師匠から、出産祝いの電話が衆宝観音さまにかかってきた。リモートで、おカミさんの美しい姿を知り、
「天燈鬼のおカミさん、どう見ても正座の稽古のモデルくらいはしないと、もったいない美貌じゃよ。パートでやってみないかね?」
「万古老師匠さん、勿体ないお話だけど、アテは行儀作法がなってないってよく叱られた。アテ向きじゃなさそうだ」
「ううん、そう~~お?」
万古老は、惜しそうに指をくわえていた。
天燈鬼のおカミさんも、毘沙門天さまの元へついてくることになったが「毘沙門天さま」と聞いてから、奔放な彼女の方が不安そうだ。
「いかがした、おカミさん。元気がないようだが」
うりずんが尋ねた。
「いえ、なんでもござんせん。四天王さまというと、奈良の東大寺まで行くのですか」
「いや、都の東寺だ」
「ということは……、西域タイプの兜跋(とばつ)毘沙門天!」
東寺にたどり着き、毘沙門天に面会を乞うた。黒ひげの武将姿で、金鎖甲(きんさこう)という鎖かたびらを肌に着けて、孔雀の紋つきの兜を被っているが、予想外に気さくなおじさんだ。
「眷属(けんぞく)だった天燈鬼がサボって、天橋立の灯りを点さずに?」
「はい。そのせいで自分の子の鬼火を龍神さまに託すことになりまして」
うりずんは、毘沙門天の前に正座して説明した。
かたわらに天燈鬼も、申し訳なさそうに土下座している。
「毘沙門天さま、ご無沙汰しております。以前、足元におりました邪鬼でございます」
「おお、あの邪鬼か。ワシの身体が重くて根をあげて、寺の手水鉢(ちょうずばち)を支える罰を受け、更に天橋立の灯り点けの役目になったのじゃったな」
「その罰もサボり……、今度こそ反省しておりますだ。毘沙門天さまにもお詫びしてから天橋立に戻った方がよいと、うりずんさんが勧めてくださいまして」
「それは、天燈鬼が世話になったの、うりずんどの」
毘沙門天が鷹揚に笑った。
「して、此度(こたび)の天橋立の務めは、なぜ放り出したのだ?」
「かかぁが身ごもりまして、お腹の赤ん坊が柿の実の大きさだというので心配になりまして……」
「天燈鬼、お前の妻が?」
奥の太い柱のかげから、おカミさんが姿を現した。
「お、お前はっ――!」
毘沙門天のでかい目玉がいっそう見開かれた。
「ちょっと小鬼をからかってやろうと思ってね」
おカミさんは、領巾(ヒレ)をひらめかせて照れ笑いした。
「お前――、吉祥天! 最近、見ないなと思っていたら、そのようなお転婆をしておったのか、このじゃじゃ馬めが!」
天燈鬼も、うりずんも呆気にとられた。
「天燈鬼のおカミさんが吉祥天さま? で、では」
「そう! みんな、わらわの口から出まかせ。戯言(ざれごと)さ」
「まったく……」
毘沙門天も、顔を覆ってうつむいた。
「そしたら、北海の龍神さままで大騒ぎして、湖国まで追っかけてくるハメになっちまって」
「北海の龍神さまにまで、ご迷惑をかけたのか?」
毘沙門天は卒倒しそうになりながら叫んだ。
「ヤバいっ! 北海の龍神さまに手土産を持ってお詫びに行かねば! 龍神さまの好物は何だったかな?」
「確か、龍神さまの好物は、人間のお祭りの出店の食べ物がお好きとか……」
うりずんが、ぼそりともらした。
「そこな若造、それは本当か、蓮の饅頭とか【龍の根性】とかいう日本酒じゃないのか?」
「は、はい。リンゴ飴やたこ焼き、ベビーカステラ、チョコバナナが好きとか聞いたことがあります」
天燈鬼が騒ぎ出した。
「かかぁが、吉祥天女だって? それじゃ、龍神さまが抱いていった鬼火の赤子は?」
「龍神さまの子の鬼火さ。本能的に分かったんだろ、それで追いかけてきたのさ」
「じゃ、じゃ、かかぁ、龍神さまとウワキ……」
「してないよ! 鬼火が勝手にわらわのお腹に飛び込んできたんだよ! ついでにあんたともウワキしてない! 全部、口から出まかせさ! わらわの夫は毘沙門天さまだけさ!」
うりずんがポカンと口を開けて、
「吉祥天さまだったとは……道理で人間離れした美貌だったわけだ……」
毘沙門天が台座から乱暴に下りてきたので、うりずんと天燈鬼は柱の陰に隠れた。毘沙門天の声がひびきわたる。
「今度という今度はお転婆がすぎる! キチジョウ! お前はしばらく、正座師匠の万古老のところへ修行に行ってこい!」
「ええっ?」
毘沙門天が手を結んで呪文を唱えると、キチジョウの姿は掻き消えた。万古老師匠の元へ送られたらしい。
「みっちり正座を稽古させてもらい、貞淑な女にしてもらうがいい!」
毘沙門天の怒声(どせい)は、東寺の敷地じゅうに響き渡った。
「それで、あの……ワシへの罰は……」
天燈鬼がべそをかきながら、柱の陰から出てきた。
「そこな若造と一緒に祭りの出店で、どっさりおやつを買って龍神さまに届けるのじゃ~~っ! ちゃんと紅白の熨斗(のし)をつけるのじゃぞ!」
「わ、わかりましたぁっ!」
ふたりは、あたふたと大門を出るや、天燈鬼はスマホで催し中の祭りを検索するのだった。
「あ~~あ、ワシもリンゴ飴、好きなんだよな」
「ついでに、衆宝観音さまにも怖い亭主がいないか、し……調べてくれないか?」
うりずんが震える声で、そっとつぶやいた。