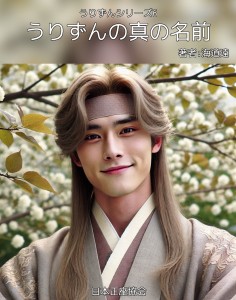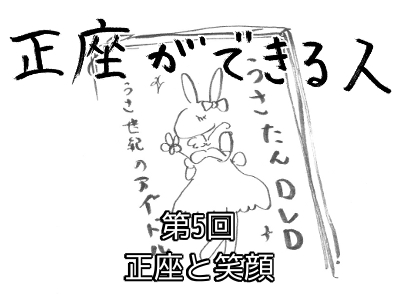[338]絵師、赫女(かくじょ)の渾身の作
 タイトル:絵師、赫女(かくじょ)の渾身の作
タイトル:絵師、赫女(かくじょ)の渾身の作
掲載日:2025/02/13
シリーズ名:うりずんシリーズ
シリーズ番号:7
著者:海道 遠
あらすじ:
正座の所作になじんでいる絵師の赫女(かくじょ)が、初の個展に都で画廊を借りた。しかし、画廊のオーナーは、赫女が画廊を畳敷きにして、正座して鑑賞してもらうことに反対で、困っている。
その後、八坂神社の拝殿でご祭神のひとり、マグシ姫と出会った赫女はその可愛らしさ神々しさに夢中になり、絵に描きたくなってしまう。

本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
万古老師匠の妹弟子の赫女が、都に来て八坂神社に向かって歩いていた。
(やっと決まった!)
浮き足立ってスキップでもしそうになっていた。
個人の展示会を開く画廊が、やっと決まったのだ。小路に面してはいるが、一応、三条通りから近い。
(展示会など生まれて初めてだ。お客さんが来てくれるだろうか?)
しかし、挨拶に寄ってみると、五十歳すぎの画廊のオーナーは、不機嫌そうに、
「困るよ。聞いてなかったな、畳敷きにしてわざわざお客さんに靴を脱いでもらうなんて。そんなことをしてお客が呼べるわけがないでしょう! フラッと立ち寄るのが街の画廊の良さじゃないか」
「は、はあ」
赫女は契約の話の途中から万古老正座師匠のことを思い出し、畳敷きを思いついたのだった。
「駄目ですか、やっぱり」
「お客を呼べて4日間の借り賃が払えるんだったら、わしゃ構わないよ。しかし、どう考えても無理な気がするけどねぇ」
「もう少しだけ猶予をください。どなたにも貸さないように。お願いしますっ。それまでに作品も仕上げますから!」
「えっ、飾る作品、まだ仕上げてないのがあるの?」
オーナーは、呆れた顔をして赫女を見送った。
なんだか、背中がジガジガしてきた。
さっきまでウキウキしていたのに、オーナーのおじさんの不機嫌な顔を見たからだ。
第一章 出会い
(なんだか暑いな〜〜。身体がほてるっちゅーか)
チベット地方の真っ赤な羊の皮で作った民族衣装は着ているが、そんなに暑くない日なのに、全身から汗が止まらない。
手ぬぐいで何度も顔面や首すじをゴシゴシ拭いた。相変わらず絵がすべてで、頭や首にはじゃらじゃらと飾りを何重にもかけているが、それ以外は身なりにはあまりかまっていない。
神社の拝殿にたどり着き、鈴をガランガランと鳴らした。
「絵の展示会が実現しますように」
一度、姿勢を正して、深いお辞儀を二回行う。次に胸の高さで、右手を少し引いて手を合わせる。肩幅ていどに両手を開き、二回打つ。手をきちんと合わせ心をこめて祈る。最後に深いお辞儀をする。お賽銭を入れてから、後じさりし……。
その拍子に、後ろにいた女の子の足を踏んづけてしまった。
「あ、これは失礼しました」
「すみません!」
赫女がぶつかった女の子は、
(まあ、なんて耀くばかりに可愛いくて神々しい娘さん!)
二度見、三度見するほど、女から見ても赤面するほど可愛くて、また汗が噴き出した。
(ホウキを持っているから、巫女さんかしら?)
社務所から、ワラワラと赤い袴の巫女さんたちが出てきた。
「奥方さま、掃除なら私どもがいたします」
「あなたたち、忙しそうやから少しお手伝いを……」
「奥方さまにお手伝いだなんて。私どもが宮司さまやスサノオさまに叱られてしまいます。さあ、お部屋でごゆっくりなさってください」
赫女は、その会話を小耳に挟んだ。
「お、奥方さま? じゃあ、この可愛い方は……」
当のマグシ姫が巫女さんたちにせっつかれて、戻ってきた。
「あのう、もしや、ご祭神のマグシ姫さまでいらっしゃいますか」
「は、はい」
「やっぱり!」
胸のドキドキを抑えようと形勢を立て直しながら、
「あ、あ、私は赫女というしがない絵師ですが、是非ともマグシ姫さまを描かせていただけませんでしょうか。いえ、こうなったら、スサノオさまとおふたりおそろいのところを―――」
「え? わらわと君さまの絵を?」
赫女はその場に正座した。背筋を伸ばし、衣に手を添えながらお尻の下に敷き、かかとの上に座るという正式な所作だ。
「いきなりお願いいたしまして、大変ご無礼なことは重々承知しております。しかし、私の『描きたい!』という気持ちはご託宣のように降ってくるのです。姫さまの穢れの無い面やお姿から、お優しい心映えが伝わってまいります。そのお姿を自身の筆で描きたいのです! 絵師が一目惚れしたのです」
「は、はあ。君さまにうかがってみます」
熱意の籠もりすぎた言葉と必死の表情、そして情熱的な正座に、マグシ姫はタジタジとなった。
第二章 櫛形の和菓子
本殿の奥へ案内された赫女は、マグシ姫の可愛さにドギマギしながらも、巫女さんから出されたお茶を味わおうとしていたが……。 早く姫を描きたくて仕方がない。
頭の中では、どういう構図やポーズにしようとかばかり渦巻いている。それと、スサノオさまと並んで正座などと口走ってしまったため、ご祭神の彼は何とおっしゃられるか――、もし、怖い方だったらどうしよう? と、不安になってきた。
「お菓子をどうぞ。老舗の和菓子店さんが、わらわをイメージして櫛の半月形のお菓子を作ってくれはったんです」
なるほど櫛の形になっている生菓子だ。ひと口食べてみると、柑橘系の果汁が餡(あん)にも表側にも入っていることが分かる。
「この味を思いついて配合してくれはったのは、琉球の季節神のうりずんさんなんですよ。なんでも、お公家さんのお知り合いの姫さまが和歌山育ちで、蜜柑をたくさん送ってもらわれるそうで……。赫女さん、ようご存知でしょう?」
「うりずんさん? はい、それはもう。何度も絵のモデルをしていただいております。海岸や樹の上の家でも」
「それは、さぞ素晴らしい絵になっていることでしょうね」
にっこり笑うと、真っ白のマシュマロの上にエクボができて、女の赫女でもチューしたい衝動に駆られるくらい可愛い。花に例えると、野原に咲く小さくて可憐な花――ピンクのユウゲショウか、勿忘草(わすれなぐさ)かってところか。
「わらわは君さまの妻ですが、赫女さんは? ご結婚してはるのですか?」
赫女は、思わず櫛形の生菓子をのどに詰めそうになった。
「ううっ」
「これ、これを早う飲んで!」
マグシ姫がお茶を勧めて、ごくんと生菓子を飲みこみ、生き返った。
「ふ〜〜っ! ま、まさか。私は人の妻になるなど考えたことがありません。絵を描くことばかりで……」
「うりずんさんのような魅力的な方に会われても、絵ばかりなんですか?」
「うりずんさんを結婚相手に? よけい考えられませんよ。あの方は涼やかに見えて、内側の焔(ほのお)が私なんかより輝かしい『赤』です。激し過ぎて近づけません」
「へぇ~、うりずんさんが……輝かしい『赤』? 翡翠色のイメージなのに」
マグシ姫がおちょぼ口をポカンと開けてから、
「わらわと君さまの場合はね……」
「あ、それなら日本の八割方の人が知っていると思いますので……」
赫女は遠慮した。ヤマタノオロチ退治の馴れ初めなど、今まで何回も聞いて、耳にタコだからだ。
第三章 赫女の正座
巫女が襖の外から声をかけた。
「スサノオの尊さまがお帰りになりました」
外出していたスサノオが帰ってきたらしい。
赫女が緊張していると、ドスドスと足音がして、今度は勢いよく襖が開けられた。
「ただいま―――! 今、帰ったぞ! 姫さん!」
駆けこむなり、マグシ姫を抱き上げて天井に頭を打つくらいに高い高いをした。
「お帰りなさい、君さま! 淋しかったわ!」
姫が首ったまに抱きつく。スサノオは姫のオデコといわずまぶたといわず、ユウゲショウのつぼみのような小さな唇といわず、何度も接吻する。
赫女は呆然としていたが、
(スサノオさまが、これほど奥方さまにぞっこん、首ったけだとは! 昔は高天原(たかまがはら)の暴君なんて言われていたけど……)
突如、立ち上がり、赤い風呂敷包みから紙と矢立(やたて=墨壺)と絵筆を取り出した。マグシ姫とスサノオをあらゆる角度から見て、左手に持った紙に絵筆を動かしはじめた。
「俺の姫さんは、じゃじゃ馬せずにおりこうでいたかな?」
「はい。……今朝から数時間ですけどネ」
スサノオはやっと赫女に気づいて、マグシ姫を下ろした。
「お客人だったか」
「こちらは絵師の赫女さん。わらわと君さまの肖像画を描いてくださるのですって」
「おお、それは有り難いことだ! 宜しくお願いしますぞ、赫女どの」
赫女は慌てて正座し直し、頭を下げた。
「赫女と申します。絵師の卵ですが、急な願いを聞いていただき、ありがとうございます」
「おや? そなたの正座は非常にしっかりして整っておるな。どなたかにご師事されたかな?」
「は、はい。仙界では万古老師匠の妹弟子でした。宇宙の根源神である天之御中主(アメノミナカヌシ)さまにお習いしました」
「ほう、ウワサによく聞く万古老師匠と共に、天地開闢(かいびゃく)時代の天之御中主さまにご師事されたと申すか。万古老師匠にはまだお会いしたことはないのだが、さすがに長く、長~~~く神仙で修行されただけあって美しいお姿だ」
「お褒めにあずかり、恐縮です」
とは言ったものの、胸の内でごちていた。
(そんなに「長~~~くを強調したら、しわくちゃのお婆ちゃんに思われてしまうわっ」
マグシ姫は、夫が帰ってきたのがよほど嬉しいらしく、饒舌(じょうぜつ)になった。
「琉球のうりずんさんも、赫女さんによく描いていただくそうよ」
「ほう、彼なら描き甲斐があるだろうね。作品を拝見したいものだ」
第四章 天燈鬼
夕暮れになり八坂神社に、参詣客に混じって大きな四角柱の燈火をかついだ小鬼が「えっほ、えっほ」と歩いてきた。
頭に角が2本生えていて、開いたハバの広い獅子鼻、鋭い牙が生え、ギョロリとした眼は三つ目だ。ひたいに三つめの緑の眼がついている。
あまりにもギョロリとした三つの眼が恐ろしいので、参詣客は避けている。
「なんや、なんや、ワイの顔に何か描いてあるのか!」
参詣客はよけいに怖がって離れていく。
小鬼はプンプン怒りながら、社務所に歩いていった。
「よお、皆はん、真面目に労働、ご苦労さんやな!」
「また、あんたね!」
巫女さんのひとりが顔をゆがめる。
「なんや、愛想あらへんな。べっぴんさんが台無しやでえ」
「べえ〜だ! あんたに心配してもらわんでも間に合ってます!」
「やれやれ」
小鬼は燈火の箱を地面に置いた。
「マグシ姫はんに取り次いでくれるか? 天燈鬼がまいりましたって」
「また、姫さまの櫛形のお生菓子を目当てに来たんでしょう」
「もちのろんやないか! 3日にいっぺんはあの菓子を食わんと、ワイは力が入らへん」
「あれ? 小鬼さん、いつもの赤っぽい肌の色と違うて、全身緑色やない?」
天燈鬼は夕闇が濃くなる中で、自分の身体を見下ろした。
「おや、どうしたことや、これは! ワイの身体が緑色や! カメレオンみたいになっとる!」
社務所の巫女さんたちがぞろぞろ出てきて、取り巻いた。帰りがけに見かけた通勤着の巫女さんも混じっている。
「緑鬼(みどりおに)になってるわ! どうしたの、邪鬼さん!」
「ワイにも、何が何やら」
巫女が本殿に駆けていった。天燈鬼の3つめの眼が光線を放つようにギラギラと緑色に輝いている。
本殿の入り口から、マグシ姫が飛び出してきた。
「天燈鬼はん、肌が緑色になったって、ほんま? いやっ、ほんまやわ!」
「ワイのひたいの眼が何か感じてうずいてるわ。誰かお客か?」
「ええ。赫女さんていう絵師さんが、緑色絵の具で下絵を描いたはるのやけど、関係あるのやろか?」
「え、赫女?」
天燈鬼は本殿のつやつやに磨かれた廊下に上がりこみ、ズカズカ進んでいった。
「赫女はん! ワイや! 前に万古老師匠の洞窟にしばし竜燈鬼と一緒に滞在した天燈鬼や!」
「天燈鬼さん?」
赫女も絵筆を持ったまま、廊下に飛び出してきた。
「いや〜、お久しぶり。天燈鬼さん。今、絵の下絵を緑色で着けるのに一心不乱で、その気持ちにあんたの3つめの眼が反応したようだね」
「……ようだねって、どうしてくれるんだよ! 緑色の鬼になっちまった!」
すごい剣幕の声をスサノオも聞きつけた。
「姫さん、私たちの肖像画に、天燈鬼さんも入ってもらったらどうかね? 赫女さんの絵に影響されたんなら……」
スサノオの申し出に、マグシ姫は仰天した。
「そんなん、わらわはいやですぅ~~、君さまとふたりだけの肖像画やないと〜〜」
第五章 ひたいの眼
「あのう、勝手なお願いですが……小部屋をひとつ貸していただけませんでしょうか。集中して絵を描きたいのと、天燈鬼さんとお話したいのです」
赫女の言葉に、スサノオ夫妻と天燈鬼は振り向いた。彼女の眼が爛々と赤く燃えている。
天燈鬼が「あちぃ〜〜っ!」と叫んで転がった。
「ちょっと、どうしたの、天燈鬼さん」
マグシ姫が、ひたいを覆っている手をどかせると、眼から湯気が噴出している。
「きゃあ、どうなさったの、これは!」
「あちぃよ、あちぃよ、あの女の眼が!」
赫女の視線のことを言ってるらしい。
「赫女どの、すぐに小部屋を用意しよう!」
スサノオが自ら天燈鬼を背負い、廊下を裏手へ大股で歩いて行った。
しばらくして―――。
用意された小部屋に赫女が正座し、天燈鬼もひたいの眼を押さえながら、どうにか正座した。
「天燈鬼どの、ひたいの眼はどうかな?」
「す……少しは熱さが退いたようです」
「赫女どのの『やる気』が、天燈鬼どののひたいの眼に反応したのだな」
「ど、どうして……」
「その3つめの眼から、画(え)の神の気配が感じられる」
スサノオが落ち着いた声で言った。
「画の神でっか? ワテ、絵なんか地面に棒っ切れで落書きするくらいしか描いたことありまへんで」
息切れしながら天燈鬼が応える。
「画の神は気まぐれだからな。全く絵心の無い者にも不意に憑依する。赫女どののやる気魂(だましい)を感じたのだろう」
その間にも赫女は絵筆を走らせ、正座しているスサノオを描いている。
「赫女どの、最近、画の神に近寄られたか?」
「は、はい。芸術の神といわれる神社には数カ所、お詣りしました。天宇受売神(アメノウズメのカミ)ひとりを主祭神とする丹波の神社や江の島の神社などへ」
「きっと、その気配を感じた天燈鬼どのの3つめの瞳が熱くなったのだろう」
「おいらのひたいの眼とどういう関係が?」
第六章 眼から生えた鬼
「あたいは旅の踊り娘でもあるんだ。アメノウズメの神さまにあこがれてねえ。小さい頃から旅から旅をして生活する……。踊りが高揚して止まらなくなると、照明を落とした舞台で正座するんだ。興奮しきった心臓が静かになる。しばらくそうしていると、穏やかな心になれる」
赫女は自分のことを語った。
「さっきは天燈鬼さんのひたいの眼から、緑色の息か何が吹き出したおかげで落ち着くことができたんだ、きっと」
そこで言葉を切り、
「おや、天燈鬼さんのひたいの眼から……」
天燈鬼はひたいに手をやると、眼からニョキニョキと得体のしれないものが出てくるではないか。円柱形の緑色のものが生えてきて、やがて人のカタチになり、長細い鬼が出てきた。
「わ〜〜〜っ!」
「きゃああ~~~!」
天燈鬼自身も赫女も、スサノオも愕然と見守った。
緑色で長細い鬼は、天燈鬼に支えられて畳の上に立たされた。
背の高さは天燈鬼の腰まである。頭から爪先まで緑色で、下半身は布を巻いたままだ。
びしょびしょに濡れたままで口を開いた。
「お、お前は誰だ? どこから来たんや?」
「おいらは翠鬼(すいき)だ。お前たち、天燈鬼、竜燈鬼の3番めの邪鬼だ。いや、画の神だ」
「翠鬼(すいき)だと〜? 3番めの邪鬼だと〜? 画の神だと~? いったい何者なんだ?」
天燈鬼は立ち上がった。
「だ、誰が、お前に出現しろと言うた? 誰がお前の存在なんか許したんや? おいらと竜燈鬼のリュウちゃんはふたりだけの邪鬼やぞ!」
赫女が、
「天燈鬼、正座して、落ち着いて!」
「ワイの3つめの目玉から、勝手に出てきやがって!」
「勝手やない! 毘沙門天さまの命令で出てきたんや」
「な、なにっ? 毘沙門天さまの?」
「天燈鬼、正座しなさいってば!」
しぶしぶ、天燈鬼は正座した。
第七章 芸術家の執念
「毘沙門天さまが命令されたのなら、仕方ないわね。この緑色の邪鬼も仲間に入れてやりなさい、天燈鬼さん」
「えええ、仕方あらへんな~」
「毘沙門天さまが、いっちょかみ(首を突っこんでくる)しているってことは、あの方も……?」
赫女はぶつぶつ言って天井を眺めた。
天燈鬼のひたいの眼から出てきた翠鬼は、いったん絵筆を握ると、鳥や花など有名な画家が描いたのか? と思われるような作品を生み出していく。
「お前はいったい?」
天燈鬼も赫女も舌をまいた。
来る日も来る日も、赫女は八坂神社に通い、スサノオの尊とマグシ姫にモデルになってもらい、正座すがたはもちろん、いろんな場面を描いていった。
熱意はますます熱く激しくなっていく。
マグシ姫の可愛さに強く惹かれているので、自然に彼女の肖像画が多くなっていく。
芝生の上で正座して、一緒にお昼をいただくこともあった。給餌のふりをして、天燈鬼がいきなり現れたりもする。
「はい、これ。巫女さんから預かった果物やで」
桃の入った籠を持ってくる。
「ありがとう。天燈鬼さんも一緒に食べましょう」
マグシ姫が誘うが、赫女は手を止めるどころではない。彼女のマグシ姫を描きたい気持ちは、火砕流のようにとどまることを知らない。
チラリと振り向き、
「後でいただきますから。今、ノリにノッていて……あっ! マグシ姫さまと桃の組み合わせ、最高ですね~! 別の肖像画で描かせていただきます」
無理に優しい表情を作って、また絵に向かう。
その「熱心」を通り越えた態度と表情に、マグシ姫はひいてしまうほどだった。
第八章 目撃
ある朝、マグシ姫がスサノオの尊の身支度を手伝っている時に、こぼした。
「ねえ、君さま。赫女さんがわらわを描かれている時、怖く感じる時があるのよ。背後に燃える光臨さえ見えそうなくらい」
「ほう、まるで不動明王だな。一流の芸術家とはそういうものだ。熱心に絵に取り組んでいる証拠だよ」
スサノオは穏やかにさとす。
地獄耳の天燈鬼が窓から顔を出す。
「姫さん、そういう時はワイを呼んでや!」
ひたいの3番めの眼から、翡翠色の小鬼をひっぱり出して、
「何やら、『画の神』だとも名乗ってますから、こいつを見張りと助手に着けますさかい、お役に立てることもあるかもしれまへん」
天燈鬼は、出現した時はびっくりしたクセに、翠鬼を良いように使っている。
「姫さん、あれだけ熱心に姫さんを愛でて描いてくれる人も、そうはいないんじゃないか。大丈夫だ、心配しなくても」
言いながら、スサノオの尊はマグシ姫の小さすぎる唇に、チュッと「小鳥キス」をした。襖を静かに開けて赫女が入ろうとした時と同時だった。
ふたりの熱い瞬間をまともに見てしまった赫女は、熱を出した時のように真っ赤になって失神してしまった。
第九章 朝のうりずん
毎朝、小鳥たちがうりずんの亜麻(あま)色の長い髪先をもてあそんで、くしけずって整えるのが進まない。どんどんもつれてしまう。
「こら、お前たち、いたずらがすぎるとエサはやらないぞ!」
板場にいて海を眺めながらくしけずっていた、うりずんは家の中へ入った。
百年ほど前、琉球の季節神のうりずんが住まいに選んだのは、海岸の樹の上だ。翡翠色の海は一望できるし、緑に囲まれている。ただし、うりずんが許した者にしか家は見えない。
昔、大陸の火砕流が村一帯をのみこんだ光景まで覚えていて見ることができる彼は、潜在的に焔(ほのお)の赤を避けて緑の世界を選んだ。
それを知った毘沙門天は、天燈鬼のひたいの眼を利用して、第三の邪鬼(翠鬼)を作り、うりずんの手先にして赫女の熱を抑える存在を作った。
赫女の作品に持つ熱意は、時として火山が噴き出す火砕流のように激烈なものと化し、周りのものを焼いてしまう恐れがあると気づいたからだ。
うりずんも、赫女の絵の腕は素晴らしいとよく知っているが、熱心さが怖いくらいなのもよく知っている。
都へ亜麻色の長い髪、いつの時代なのか不明な、すその長い着物を着た男がやってきた。
祇園八坂神社へまっすぐに向かい、奥殿を訪ねた。
布団に、寝かされていた赫女はまだ頬が赤い。慌てて起き上がると、布団に焦げ跡がついているではないか。
「これはまた、ひどい熱だなあ、赫女さん」
「うりずんさん!」
「そりゃあ、マグシ姫が可愛いのはよくわかるが、布団を焦がすまでとは……」
「ワイのひたいの眼から生えてきた緑の鬼も、熱さにぐんにゃり溶けてしもうて役に立たんのや!」
天燈鬼がひっぱり出して正座させようとしたが、くたくたになってしまって正座できない。
「ごめんなさい、すみません。全部、私がいけないんです!」
赫女が正座して深々と頭を下げたが、座った場所の畳が焦げてしまう。
しばらくして、三条通りを少し曲がった小路にある画廊で、赫女の作品展示会が行われた。
異例の畳敷きの画廊だ。赫女がオーナーに頼みこみ、畳敷きにする費用はこちらで受け持つからということで、ようやく実現した。
作品は、座った目線にちょうど良い高さに展示してある。畳の上に座布団も数枚ずつ用意した。
お客さんたちは、しばらく座布団の上に正座して、作品を心ゆくまで眺めて、隣へ移動していく。
長く鑑賞しているお客さんには、お茶が出された。運んでくるのは、八坂神社のご祭神マグシ姫だったから、顔を知っている人は驚き恐縮して後ずさりして正座し、頭をすりつけるように礼をしてお茶をいただいた。
赫女が展示会間際まで描いていたのは、マグシ姫とスサノオの尊が斜め差し向かいに正座している図のかなり大きい作品である。
しっかりと「非売品」という札が付けられていた。
「これだけは、絶対に売ることはできません」
と、赫女は頑としていた。
庭で、赤い毛氈の上ににこやかに正座している夫婦のすがたは、微笑ましい以外の何ものでもない。
鑑賞客たちは、ため息をついて長く眺めてからやっとあきらめて席を立つのだった。
「なんて愛らしいマグシ姫さまと逞しいスサノオさまのご肖像画でしょう」
「スサノオの尊さまと並ばれると、お父上とご令嬢のようですわね」
「スサノオさまは、若い奥方さまが可愛くて仕方ないご様子だそうよ」
「年齢差が奥ゆかしいというか、微笑ましいというか……ですね」
ご婦人たちは、扇を口元に寄せながらウワサ話にかまびすしい。
他には翡翠で作られた、珍しい邪鬼の肖像画や、マグマが噴き出す場面の風景画まである。
そして、中でも人だかりがしているのは、翡翠色の海を背景にしている淡い髪の色をしている青年の絵だ。
「このモデルさんは、なんてお美しいのでしょう」
「まるで人間じゃないみたい……蜻蛉(かげろう)のように、黄緑の羽根を持って飛翔してしまいそうな……」
それらの作品は、うりずんがモデルになって、樹上の家で描いてもらった絵だ。
終章
終盤の時刻には、スサノオの尊ご本人も画廊にやってきた。
「これが、私たちかね。まるで『鏡』だね」
肖像画をじっと見つめた。
「なるほど、素晴らしい出来だね。私たちの信頼の強さまで描けている」
「でも、売ってくださらないそうなの」
マグシ姫がしょんぼりして言うと、赫女がやってきた。
「お売りするだなんて、とてもとても。もっともっと修行してからですわ」
赫女の瞳はいきいきとしている。
「私の出番は無さそうだね」
いつの間にか覗きに来ていた、うりずんが洩らした。
「赫女さんの元気の源は、南の海辺で良い空気を吸うことよりも、画筆を持つことですね。それと、正座してお菓子とお茶をいただくこと。図星でしょう」
「うりずんさんたら!」
うりずんは真剣な目で赫女に向き、
「絵を愛しすぎて、思いつめないこと。身体も心も保たなくなるからね」
「はい」
いきなり背後から、
「もし、そうなりそうになったら、おいらが来てやりまっさ! 翠鬼をひたいの眼から出して熱を冷ませてさしあげますさかい、どうぞ、遠慮なく!」
天燈鬼の出現に、オーナーのおじさんや、お客さんたちが逃げ出しそうになった。
「なんや、なんや! おいらたちは、毘沙門天さまの使いやでえ!」
天燈鬼がいばるのを見て、マグシ姫とスサノオの尊夫妻は大笑いし、赫女とうりずんも顔を見合わせた。