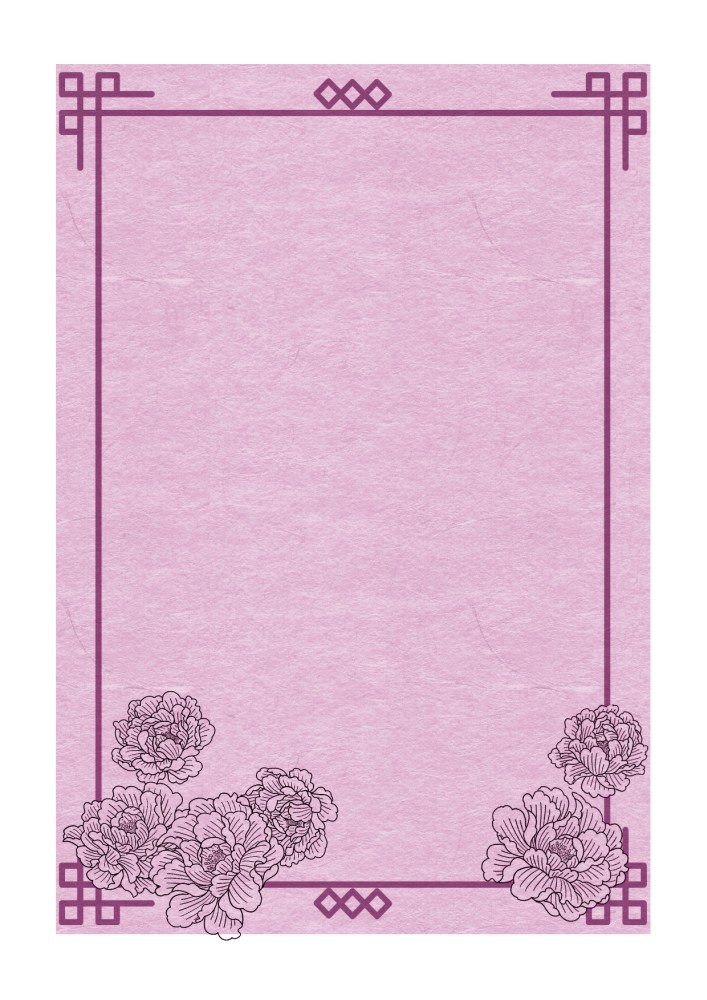[285]恋文は龍の珠
 タイトル:恋文は龍の珠
タイトル:恋文は龍の珠
掲載日:2024/05/05
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
平安時代。九条家の子息、薫丸(くゆりまる)は14歳。そろそろ成人の儀を執り行わなければならない年齢だ。
唐渡りの座り方、正座は幼少の頃から躾けられているが、かなりのやんちゃだ。
ある日、乳母が誰かから恋文をもらった。薫丸は可能性のある人物を『りすとあっぷ』したが見当がつかない。唐のお菓子職人か、結び文が簀の子にあった時に側にいた半夏? まさかの正座師匠、万古老? すべて違うような、そうであるような?
数か月前、乳母は都が大雨の時に空を飛ぶ龍から、輝く珠を手のひらに落とされた。その中には恋文が浮かび出ていた。

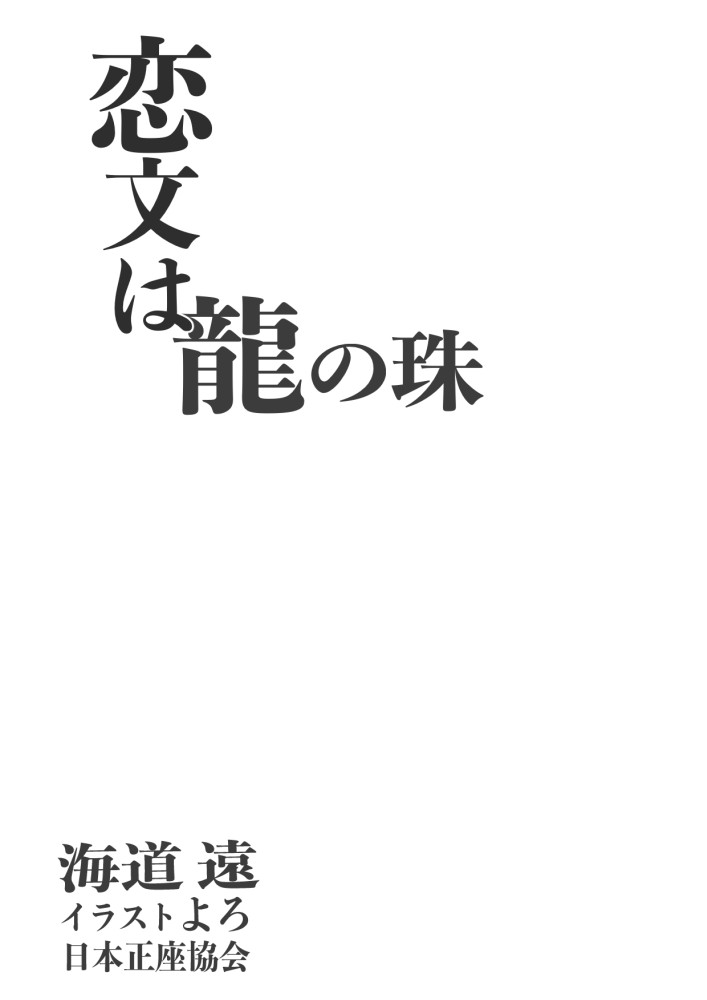
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
薫丸(くゆりまる)の乳母(めのと)は、半夏から差し出された紙をそっと開いた。
『若、叱る
熟れたる声のいとばちかわ
正座しうっとり
切なき胸よ』
「こっ、これは恋文……? まさか……」
乳母は思わず顔がほてるのを感じ、扇で隠した。
「『ばちかわ』って何かしら?」
陽が暮れるまで簀の子に立って、夢見心地で考えこんでいた。
【彩鳳】(あやほ)
乳母の名前だ。吉祥の賜物のような名前。
【彩鳳。五色の翼を持つ鳳(ほう)と凰(おう)一対が、人々の天下泰平、万民和楽の聖代を祝って雲ひとつない青空に出現し舞う、平和を高らかに歌い上げた歌】
『彩鳳よ、そなたの力を借りて、そのような吉祥の空を万民に見せたい』
都を襲った大雨の日に、空を飛ぶ龍から手の中に落ちてきた珠――、なんと龍王からの恋文の珠だ。珠――如意宝珠(にょいほうじゅ)の中に浮かび出た。
第一章 釣り合わない
驚かないで聞いてくれ。
おいら、九条家の御曹司、薫丸の乳母が恋文をもらった。
文面の内容を、不思議な力を持つお菓子職人の李・橙実(リ・チャンシー)が、おいらの頭に思念で送ってきた。びっくりだ!
熱い想いが綴られている。
誰からかは分からない。傀儡子のマッチョイケメンの半夏(はんげ)が、屋敷に来た時にわたしたので、
「ええっ?」
と、胸がドッキンコしたらしいのだが――、少し前に侍女のひじきが、結び文が簀の子(濡れ縁)に落ちているのを目撃していた。
両手がふさがっていたので、
(後で拾わなくちゃ)
と思っていたら、いつの間にか無くなっていた!
乳母は無言で半夏からわたされたので、書いたのは彼じゃなくて、落ちていた結び文を拾ってわたしただけかもしれない。
でないとあまりに変じゃないか。
乳母は、35~40歳くらい。半夏は傀儡子のお客さんたちにモテモテの弓矢の名手で、いつも片方の肩を出して革の上衣を身に着けている細マッチョ。20歳すぎかな? ……釣り合わない。
でも、傀儡子の舞いの姐さんたちに恐々(こわごわ)尋ねてみたら、大笑いして、
「ま~~、若君、まだまだお子ちゃまですね。恋に年齢なんて関係ないない!」
「若君の乳母さまは、豊満で美人さまなんでしょう。40は女盛り! 半夏にいさんが惹かれたって不思議じゃないわ」
って、あしらわれた。
胸は大きいかもしれないけど、乳母って美人かな? 普通だと思うけど。
あの時、簀の子の近くにいたのは、おいらと半夏と唐の菓子職人の李・橙実(リ・チャンシー)と侍女のひじきくらいだ。でも、恋文を書いたのは近くにいた人間とは限らない。
侍女たちの言うには、顔を知らない御簾(みす)越しに和歌のやり取りや、お香や気配でしか知らない人に恋したりするそうじゃないか。
おいらには、まだ分からない世界だ。
第二章 乳兄弟
【まさかの候補】
乳母を知る人物……半夏、橙実、マンダラゲお婆、十輝和丸(ときわまる=半夏の元カノ)、美甘姫(おいらの幼なじみ)のお祖父ちゃん……、なまず髭長(ひげなが)、大沢の池の黄金龍。
この中から女の子は抜いて。
……まさかな。ダメだ! みんな、まさかすぎる! 意外すぎる!
おいらは首をぶんぶん振った。
おいらって案外、乳母のこと知らないな。乳母の家にも訪ねたことがない。乳母の夫はこの家に仕える舎人(とねり)だから顔は知っているけど話したことはないな。
乳兄弟(ちきょうだい=乳母の子ども)にも会ったことがない。確かふたりいると聞いた。
考えてみたら、乳母がその子たちを産んでくれたから、おいらはお乳を十分もらって育つことができたんだな。
一度、ちゃんと会いに行こうかな。おいらが彼らの母上をひとり占めしたまんまだもんな。
(乳母の家に行って、夫と子どもに会いたい)って、誰に言えばいいのかな? おもうさま(父上)? おたあさま(母上)?
おもうさまたちには、いつからまともに会ってないのかな?
きっとおいらの傀儡子(くぐつし)一座通いしている日常は耳に入っているだろうから顔を合わせにくい。おたあさまは、「『おいら』とはどういう意味です?」と問われそうだ。
今は止めておこう。うん? 乳母の名前って何だっけ?
えーと、えーと?
思い出せないから諦めて、この家の書庫係をやってる乳母の夫のところへ行ってみた。
おもうさまの使用人が仕事している本殿の書庫(ふみくら)。
沢山の棚に書物が積んであり、舎人たちが立ち働いたり、文机に向かったりしている。おいらに気づき、次々に正座して床にひたいをつけた。
「あ、いいです、そのままでお仕事してください!」
慌てて言ってから、
「ここに嵯峨の兵太はいる? おいらの乳母の夫なんだけど」
「これは、若君。急なお越しでございますな。それがしは美濃田吾郎と申します」
進み出てきたのは、真面目そうな中肉中背の男だ。
「大変、残念ながら平太は一年前、病で亡くなってしまいました」
「え? 乳母の夫が? 聞いてないぞ!」
「はい……。なんとも急なことでして」
乳母からひと言も聞いていない。水臭いじゃないか!
「そんな重大なことを乳母は黙っていたのか。じゃあ、今の乳母は「ふりー」ってことか。乳兄弟のふたりはどうしてるのかな? 確か、おのこ(男子)とおなご(女子)がいたはずだ」
「父親が亡くなってから、息子は別のお家にご奉公に、娘はこちらのお屋敷で侍女に上がっています」
「侍女に? 誰かな」
「ひじきですよ。働き者の」
「ひじきだって! おいらの部屋付きの!」
こりゃまたオドロキ! ひじきが乳兄弟?
第三章 加冠役りすとあっぷ
おっと、話がヨコになりかけたが、問題は簀の子の上にあった結び文を書いたのは誰かってことだ。
やっぱりひじきに話を聞かなくちゃ。……乳兄弟のことは言いにくいなあ。
「あら、若君。珍しいですわね。こんな陽の高い時間までうちにおいでとは。傀儡子さんたちのところへ行かれないのですか?」
弓矢の手入れをしながら考え事をしていると、ひじきが朱い袴を引きずって御簾(みす)を上げにやってきた。
「ああ、ひじき、ちょうど良いところへ。昨日の結び文のことなんだけど」
「結び文? ああ、簀の子に置かれていた?」
「お菓子職人の橙実(チャンシー)さんから思念が送られてきて、内容が……その……どうも、恋文なんだよ」
「アラッ! どなたからどなたへの?」
ひじきは俄然と瞳を輝かせた。
「それが……乳母に宛てた文には違いなさそうなんだけど、誰が書いたのか判らないんだ」
「まあ、乳母さまに?」
「乳母って、ひじきの母君なんだってね。知らなかったよ」
照れ臭いけど言ってみた。
「そうなのです。若君と私は乳兄弟です」
ふたりで、なんだかもじもじしてしまった。
「私も心当たりがありませんわ。母に恋文をわたす方って」
ひじきも途方に暮れた。
「乳母に最近、変わったことはなかったか?」
「母はいつも若君のことで頭がいっぱい。……そうだわ。そう言えば……」
「何か?」
「若君は『成人の儀』がお近いでしょう」
「まだまだだよ、そんなの」
「早め早めに支度を始めなければって、加冠役(成人する者に初めて冠を着せる役)をどなたかにお願いしなければと言って、年長者の方の『りすとあっぷ』していましたっけ」
「加冠役? 年長の方?」
「普通は左大臣様とか、父上さまのご上司様にお願いするようですが」
「乳母はもう決めたのだろうか? 誰を『りすとあっぷ』したんだろう」
「乳母さまの手元の書が、チラッと見えたのですが、万……万古さんとか……」
「もしや、正座師匠の万古老さんのことだろうか」
ひじきは手のひらをポン! と打ち、
「正座のお師匠、万古老仙人さまなら、半夏さまからお聞きして存じています。若君の加冠役をお願いされるのかも?」
「仙人さまなら確かに年長者だ」
第四章 百世と流転の悩み
「お腹へった~~!」
正座修行中の百世(ももせ)が、大木の枝の上で足を丸出しにして寝そべっている。午前中の労働と修行は終わったから、そろそろお昼の準備だ。
夜明けから始まる正座修行のおかげで、お腹がグ~~ッと鳴っている。眼下の小川には、ちょうどよい川魚が銀色のウロコを光らせて跳ねている。
百世は腰の「べると」に手をやり小刀を取り出すと、狙いを定めて目にも止まらぬ速さで投げた。見事に仕留める。その調子で五匹を続けて仕留めると、地上に飛び降りて魚を集めた。
ついでにその辺の樹に成っている朱い実を採る。
「お~~い、流転! メシにしようぜ! きりのいいところで本を読むのを止めて、魚焼こうぜ!」
しばらくすると、森の奥から青く長い髪の少年が現れた。
「魚の用意、ありがとう。百世。火はボクが点けるよ」
「ああ、頼む」
ふたりは外見は11歳くらいの子どもだが、仙人なので実際の年齢は300歳くらいだ。
百世は女の子、流転は男の子。正座師匠万古老の弟子で修行中の身だ。
「百世、お師匠を呼んでくれるか? 最近、洞窟にいないで森の中をぶらぶらしてるから」
「万古老師匠~~! 昼メシ! 魚、焼きますよ!」
しばらく待ったが、何の反応もない。
流転が火打石をカチカチ鳴らす音が響く。
「どこまでぶらぶらしてるんだろう」
百世が魚に樹の枝を差しながら言った。
「なあ、流転。この頃、お師匠の様子が変だと思わないか?」
「お前も気づいてたか? 百世」
「どんなにぐうたらしていても、前なら修行サボってると厳しかったのに、最近、上の空って感じだろ。かと思うとソワソワしたり」
「うん、うん。何かあったんだろうか」
「この前、傀儡子たちに正座のお稽古つけに、都へ出かけてからだろ」
「そう言えば、稽古を頼んだ半夏っていうイケメンが留守だったとかで、出かけた先の九条家まで行ったらしい。それから何度か行ってるような?」
「九条家の侍女に一目惚れでもしたんだろうか?」
「ごふっ!」
流転が食べ物を喉に詰まらせて、百世から水をもらった。
「そう言えば、あたい見たんだ。夜中に机の前で白い紙に何か書いているのを」
「なんて?」
『若、叱る声 いとばちかわ
正座うっとり 切なき胸よ』
――とかなんとか」
「そりゃ、恋文じゃないか! お師匠が恋?」
「孔雀明王まゆらちゃんには絶対、言えないな」
「お師匠の元カノだもんな。言えない言えない! じゃ、誰に相談したらいいんだ?」
ふたりは首をかしげながら、焼き上がった川魚にかぶりついた。
「衆宝観音さまはどうだろう?」
「いいじゃないか! 百世、良い方を思いついてくれたよ」
ふたりが湖畔の寺においでの衆宝観音を訪れると、相変わらずのはんなりとした片膝立て座りで、たおやかな笑みを浮かべて百世と流転を寺の座敷へ通してくれた。
「いらっしゃい、可愛いお客様たち。なあに? 前触れの天女から聞くと、恋の悩みですって?」
「ち、違います、違います。恋をしたのは万古老師匠ですよ!」
「まあ」
「だから、今日のことは、絶対にまゆらちゃんには言わないでくださいね!」
「言いませんけど……。さ、あなたたちも召し上がれ」
衆宝観音さまは落ち着いて、蓮の揚げまんじゅうをひと口食べた。
「万古老師匠が恋文を書いたんですよ」
「まあ、そう……」
「あの、正座を極める道ひとすじの万古老師匠がですよ!」
「で、あなたたちは、わたくしにどうしてほしいの?」
「どうって……、別にどうも。師匠のことが心配なだけです」
「恋なんて、誰かがクチバシ突っこむものじゃなくてよ。温かく見守って差し上げたら?」
「は、はあ」
観音さまに穏やかに言われると、どうしてほしいのか分からなくなったふたりだった。
第五章 ふたりのみずら少年
流転は、翌日、薫丸さまの正座の出稽古に、万古老の代わりに出かけた。万古老師匠がまた行方不明だからだ。
日頃の木の葉っぱがまとわりついた、じゃんぐる少年みたいな格好じゃなくて、ちゃんと菜の花色の水干を召していった。
薫丸は珍しく時刻通り待っていて、流転の水干すがたを見て、
(仲間だ~~!)
とでも思ったのか、ご機嫌だ。
「流転どの、よくお似合いです! お稽古、宜しくお願いいたします」
かしこまって座礼した。
「万古老師匠は急用にて、代理の私で申し訳ございません」
「流転どのの正座の所作は確かです」
薫丸は立ち上がると、正座の所作をこなした。
「若君こそ、素晴らしい正座でございます。ところで、ひとつ、今の流行り言葉を教えていただきたいのですが」
「よろしいですよ。何でしょう」
「『ばちかわ』とはどういう意味でしょう。何せトシが300歳で山に籠もっておりますゆえ、若者の使う言葉がさっぱり……」
「今の流転どのが正にそうですよ!『ばっちり可愛い』のことです」
「ご冗談を。『ばちかわ』は、年古りたご婦人に使っても失礼のない言葉ですか?」
薫丸はキョトンとした。
「例えば、若君の乳母さまくらいの方にも」
「乳母なら『ばちかわ』と『年古りた』のちょうど中間でしょうか。あれで結構あどけない面もあり、『年古りた』いぶし銀の優しさを感じることもあり……」
「素敵な御方ですね。いつも若君のことを思われて」
「口やかましいのがタマにキズですが」
薫丸は苦笑した。
お茶と唐菓子で休憩してから、薫丸が、
「せっかく今日の流転どのは水干をお召しなのですから、おいらと同じ下げみずらに髪を結ってみては?」
「私の髪を下げみずらに?」
「きっとお似合いですよ」
ひじきが鏡を用意して、薫丸ははりきって流転の長い髪を櫛(くし)で梳き(すき)はじめた。
「藍色の豊かな髪だね。ふたつに分けて――と。ひじき、元結(もとゆい)をしばる糸をくれる?」
元結をしばると、藍色の髪に糸の白さが反射するように見えて、神々しいような髪だ。
「えっと、耳の上か下で輪っかを作るのはどうすればいいの?」
ひじきが「ばとんたっち」して、カタチの良い下げみずらが出来上がった。
「お似合いだよ、流転どの!」
ふたりとも似た背格好なので、髪と衣の色が異なるだけで、まるで双子だ。
「百世も来れば、三つ子になるね」
薫丸が言ったので、ひじきと3人で大笑いした。
「ふたりとも『いと、ばちかわ』だ!」
その後、ふたりの少年は庭を散策した。
流転は青空を見上げると不思議なことに、見上げているというのに、空から庭を見降ろしている視覚が開けた。誰かを懸命に探していた。
身体が熱い。不調かな? とは思ったが、どうも違う感じがする。
第六章 不機嫌な半夏
矢を弦につがえて、ギリリと振りしぼる。
発達した肩と胸の筋肉が盛り上がって緊張する。狙いは空き地に立てられた的だ。
矢が放たれた! しかし、とんでもない方へ飛んでしまう。
「ううっ、くそっ」
半夏の顔が悔しそうに歪む。
「ど、どうなさったの? 半夏にいさん、滅多に的を外したりしないのに」
「とても怖いお顔ねえ」
見守る傀儡子の姐さんたちも、近寄りがたい。
「お前たち、しいっ!」
親方が半夏に気取られないように注意する。
「どうやら恋わずらいだ。これ以上ご機嫌損ねると、もっと怖くなるぞ」
半夏は不機嫌極まりない顔のまま、矢を拾い、元の位置に戻る。
「半夏にいさんが恋わずらいですってえ?」
「いったい誰に!」
「許せないわ、あたいたちのたったひとりの貴公子さまを!」
姐さんたちが殺気立つ。
「お前たち、雀じゃあるまいし、かまびすしい!」
突然、半夏が吼えるように怒鳴りつけ、姐さんたちはピタリと黙り込んだ。
「知りたいなら教えてやろう。俺をこんなにしているのは、九条家の薫丸さまの乳母どのの彩鳳(あやほ)さまだ! 苦しい思いをやっと文にしたためたというのに、文が行方不明になってしまったんだ!」
親方と姐さんたちは、ポカンと口を開いてしまった。
(恋とは秘めやかなものなのに、大声で明かすだなんて!)
(それも、お相手は九条家の薫丸さまの乳母どの?)
流転が出稽古から山の洞窟へ帰ると、万古老師匠が浮かれて迎えた。
「師匠が、薫丸さまの成人の儀の加冠役を仰せつかったの?」
「そうじゃ。なんと勿体ないことじゃろう。『いと、ばちかわ』が効いたのじゃろうか?」
(師匠ったら、やっぱり恋文を書いたんだわ。イイトシして!)
百世がふくれっ面していた。
「さて、九条家まで出向いて『慶んでお受けさせていただきます』とお返事申し上げてこようかの」
洞窟の奥で、師匠はいそいそと着替えようとしたが、普段からボロ布を巻きつけている程度なので、ちっともマシな着物がない。
「だから、正座を教える月謝を貯金するように、口が酸っぱくなるほど言ってたのに……。仕方ないな~~!」
百世と流転が、日頃から貯めていた小銭が功を奏し、古着の直衣(のうし)をそろえることができたのだった。
「何かの時にと思って、生活を切り詰めて用意しておいたんだ」
ふたりが着物を差し出すと、
「ワシはなんと良い弟子を持ったことじゃろうのう。こんな山奥の仙人が、彩鳳の名を持つ女性から大切なことを頼まれるとは……」
嬉し涙さえ浮かべて、万古老は九条家からの迎えの牛車に乗り込んだ。
「彩鳳の名を持つ女性……?」
百世と流転が首をかしげた。それから慌てて、牛車の後を追った。
第七章 恋文は珠
九条家。
薫丸の乳母は、ついに若君の成人の儀の準備をする時が来たかと思うと、胸がいっぱいになっていた。
ふと格子戸の隙間から曇ってきた空を見上げ、「あの時」のことを思い出していた。 数ヶ月前、都が大雨に襲われた時、黄金龍が空から乳母の手に珠を落とした。
珠とは、龍王――黄金龍がアゴの下に持つという、願いを思うままにするという希少な如意宝珠(にょいほうじゅ)のことだ。
やがて。珠の中に文章が浮かび出た。
【彩鳳とは五色の翼を持つ鳳と凰一双が人々の天下泰平、万民和楽の聖代を祝って雲ひとつ無い青空に出現し、舞うという意味がある】
『彩鳳よ、そなたの力を借りて、そんな空を万民に見せたい』
なんと、信じられぬが龍王からの恋文だ!
(人間の私が、龍王さまからの珠のカタチの恋文をいただくとは――)
(これは、きっと若君の薫丸さまが素晴らしき大人になられる証に違いない。そんじょそこらのつまらない朝廷の大臣クラスの方を加冠役になぞ頼めやしないわ)
決心した乳母は、話に聞く正座師匠の万古老に加冠役をお願いすることに決めた。
半夏から渡された結び文は、少し中を見ただけで恋文とも気づかぬまま、たもとに入れて忘れてしまったのだった。
第八章 妙見菩薩(みょうけんぼさつ)
イノシシでも仕留めてやろうという剣幕で、九条家に向かって馬を駆っていた半夏は、乳母が若君を呼びつける声を思い出す。
『若君、若君〜〜!』
九条家を訪れる度に聞こえる、あの声が耳について離れなくなってしまった。
若君を見守る優しい視線も……。
「この狂おしい胸の炎をこそ、『恋』と呼ぶのだ――!」
色恋のことには奥手な半夏は一途に思いこんでしまい、折れくぎのような文字で、ようやく生まれて初めての恋文を書き上げた。
いざ渡そうとしたものの、乳母が目の前にいるというのに膝がガクガクして、声もまともに出ない。
仕方なく無言で乳母どのに差し出した。無作法だろうと思われたが、乳母どのの立つ簀の子に恋文を置いてくるのがやっとだった。
なんと、――その恋文が無くなったそうではないか。半夏は、真っ暗な谷底へ落とされた心地がした。
途中で川面に顔を写してみた。唐突にいつも垂れ髪に放ったらかしにしている髪がみっともなくなった。手を川の水で濡らして手櫛で髪を梳き、ふたつに分けて両耳のところで上げみずら髪に結った。俵型のおむすびが二つくっついているカタチだ。
気持ちが引き締まったような気がした。
「弓矢の神、妙見大菩薩さまだ〜〜!」
九条家の門番がふたりとも屋敷内へ逃げ込んできたので、侍女たちも驚いた。
堂々と馬で入ってきたのは、時々、正座の出稽古にやって来る傀儡子の半夏ではないか。
しかし、いつもの涼しげな表情ではなく憤怒の形相だ。荒々しい歩き方のせいで肩幅まで大きく見える。しかも妙見大菩薩さながらの上げみずら髪を結っている。
ひじきも仰天して濡れ縁まで出て膝をついた。
「半夏さん! いかがなさいました?」
「どうもこうもない! 簀の子の上に置いた恋文をどこかへやったのは誰だ!」
腰の刀を抜かんばかりの剣幕だ。
「半夏さん、落ち着いてください!」
ひじきは懸命に引き留めようとする。
玄関に1台の牛車が着いた。御簾が上げられ足台から下りてきたのは、長いアゴヒゲを胸まで垂らせた正座師匠万古老だ。
目を飛び出させて近づいてくると、半夏の襟首をつかんだ。
「簀の子の上に置いた結び文が、どこかに行ったじゃとぉ〜〜?」
半夏は、師匠の細い拳をふりほどいて、
「あれは俺が書いたんだ!」
「若造、何を言う! あれを書いたのは、わしじゃ! どこへやった?」
「聞きたいのはこっちだ! あれは苦労して俺が書いたんだ!」
燃えるような腹立ちに満ちた視線が絡みあった。
「お師匠!」
「半夏さん!」
百世と流転が駆けてきて、ふたりの間に入った。
「ふたりとも止めて! 落ち着いてよ!」
第九章 衆宝観音の提案
もう一台、牛車がやってきて、降り立ったのは薄衣をまとった、熟した美貌の衆宝観音だ。
九条家の人々はまばゆいばかりの美しさに無言で立ちすくんだ。
彼女の一声が情けない争いを中断した。
「どちらの恋文が乳母どのに届いたか、自分の願いしか考えぬとは、恥ずかしいと思われませぬのですか、万古老師匠、半夏! ふたりとも心を落ち着けて、よく考えるために正座しなさい」
「正座師匠のワシに向かって『正座しなさい』じゃと?」
師匠はツバキを飛ばした。
「そうです。あなたは恋文が行方不明になったことと、若君の加冠役の件で動転していらっしゃるわ。正座して今一度、冷静にお考えください、万古老師匠」
師匠はぐっと詰まった。
「乳母どの――彩鳳さまの大らかな慈悲は、黄金龍の協力を受けてこそ万人に降り注ぐ力が発揮されるのです。自分の欲しかない万古老師匠には不可能です」
観音は目線を上げ、
「私は……薫丸さまの加冠役は、正座の所作を落ち着いて教えることができた流転に任命します。乳母どのからも、ご両親さまからもご承諾いただきました」
「観音さま! る、流転ですと?」
正座していた万古老と半夏は飛び上がった。
「流転は、正座の修行に真面目に励んで300年にもなるということ。十分、薫丸さまの加冠役に相応しいと思います」
進み出た流転の身体から黄金に光る龍の影がフワリと抜け出る。流転の身体に宿っていたのは珠の持ち主、黄金龍王(人型)だった。
(空から見下ろす感じが何か変だと思っていたら、龍王さまが憑依していたのか……)
「薫丸さまの加冠役、頼みましたよ、流転」
流転にとっては、いきなり言われた話だったが、みずら髪を結うと双子のような薫丸さまのために、頑張ってみようという気になった。
「はい! 衆宝観音さま」
【龍王の魂が宿っていた少年に加冠役をしていただくお方など、滅多におられますまい】
衆宝観音はたおやかな笑みで微笑むと、ご自身の寺へ帰っていかれた。
屋敷の欄干の下の目立たないところで、万古老と半夏が正座をする元気もなく、ため息をついていた。
「結局、ワシの書いた恋文はどこへ行ってしまったのじゃろう」
「俺の苦労して書いた恋文はいったいどこへ……」
何度もため息をついて、ふたりが出した結論は、今度、恋文を書いたら、相手の真正面に正座してわたすということだった。
第十章 みずら髪で自由に
「龍王を宿していた少年に、加冠役になっていただくなんて光栄なことはないわ。若君にこれ以上、相応しいお方はおられないわ」
乳母は衆宝観音の決定に、異論などあるはずもない。それどころか感銘を受けた。
「私に授けていただいた如意宝珠は、この慶事の前ぶれだったのかもしれない……」
「成人の儀」向けて沢山の支度がはじまった。まず、大人の名前を加冠役に決めてもらわなければならない。
乳母は毎日のように屋敷に流転を呼び、ご両親の九条の殿夫妻も含めて良い名前を相談した。
流転は頭を掻きむしって奮闘した。
乳母は間を縫って佳き日柄を選び、屋敷での祝いの宴の献立を決めて、調理人と相談し、もちろん唐の「唐果物」(おやつ)を作ってくれた李・橙実を唐から呼び寄せた。
桜色や若緑色の粉熟(ふずく)という蒸し菓子や、木の実入りの揚げ菓子が作られた。
祝いの品が貴族や皇族や荘園の責任者から、山ほど屋敷に届けられた。
薫丸はまるで予定など無いかのように今まで通り、毎日、傀儡子たちと過ごしていた。オダマキが寂しそうな顔をして見つめていたが、気づいていない。
そして、遂に当日を迎えた。
当日の正午くらいからは、次々に招待客の牛車が到着しはじめた。屋敷の車寄せに牛車が列をなした。
時刻となり、薫丸は大人の衣を着せられ座敷に現れた。
縫腋(ほうえき)の袍(ほう)という大人の着物を身に着け、平緒を腰から下げ、後ろには下襲(しもかさね)の裾を引いた若い貴公子は輝くばかりだ。乳母の目には思わず熱い涙がにじんでいた。後は髪を結うばかりだ。
髪を結う役目の流転が入室して、薫丸の後ろに立った。
長年見慣れた下げみずらが、つやつやとして目の前にある。流転は用意された髪切りハサミを手にしたが震えが止まらない。
(いよいよ、薫丸の美しい下げみずらともお別れか……)
ハサミに力を入れようとしたその時、みずらの黒髪はするりと手の中を抜けた。
「へへん、加冠の儀なんか真っ平ごめんだ! おいらはいつまでも、みずら髪をやめないさ!」
大人の衣も脱ぎちらかし、祝いの菓子をいくつか手づかみすると、簀の子から庭に飛び降りてしまった。
「流転も、みずらにお結いよ!」
叫んで屋敷の外に駆けていく。
「若君! 戻っておいでなさい! 若君!」
血相を変えた乳母が叫んだが、屋敷の男衆の囲みを軽く身をかわし、流転とふたりで駆けていく。
「おお……、なんてこと」
乳母はへたりこんだ。来賓の貴族たちは、呆気に取られて見送るだけだ。
数日して、九条家の若君が傀儡子たちみんなに声をかけて、男も女もみずら髪にして正座の稽古をしているという噂が届いた。
流転も百世もオダマキも、半夏までみずら髪に結っているという。
「この度は、弟子の流転がとんでもないことをしでかしまして、この万古老、なんとお詫び申し上げればよいか……」
万古老が小さくなって正座していると、乳母は不意に扇も放り出して、豪快に笑いだした。
「ふっふっふ、あはははは……。さすがは黄金龍の魂を宿していた流転に加冠役を決めようとしたおのこ! お気のすむだけ、みずら髪を楽しみなさいませ! 龍王どの。如意宝珠の恋文、この彩鳳がしかと受け取りました」
乳母はしっかりと正座しなおした。
「天下泰平、万民和楽の聖代を祝って雲ひとつ無い青空を実現させるみずらおのこは必ずや燦然(さんぜん)と輝く大家(たいか)にお育ていたします」
龍王の鎮座していそうな七色の雲を見上げて、頭を下げた。
……万古老が指をくわえてつぶやいた。
「ワシもみずらに結いたいのう……」