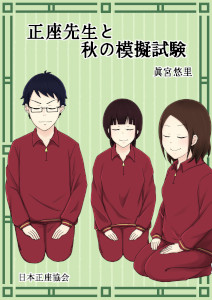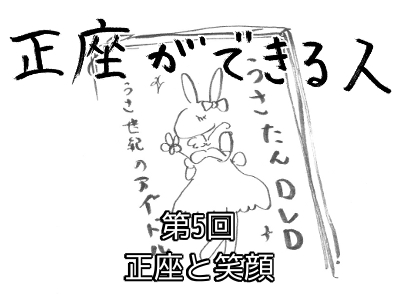[354]白いワンピースの正座少女
 タイトル:白いワンピースの正座少女
タイトル:白いワンピースの正座少女
掲載日:2025/05/05
著者:海道 遠
イラスト:よろ
あらすじ:
仙界に住む正座師匠の万古老は、三百年前、魂売り屋から男の子と女の子の魂を買った。
三百年が過ぎ、町の公民館で正座の講座を頼まれた万古老は、女の子の百世(ももせ)をお供に連れて出かけた。百世はある夫婦から気に入られて引き取られることに。残った男の子の流転(るてん)は、大ショック。
急に修行をサボるようになった万古老を見かねて、流転は公民館を訪ねる。


本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 魂売り屋
黄水仙とは別名、不凋花(ふちょうか)と呼ばれ、永遠に咲く花、しぼまない花とされる。
(今年も見事に咲いたのう)
洞窟の外の平原に黄水仙が一面に咲き乱れる季節――。
質素な着物の老人が長いあごヒゲを撫でながら、花々を眺めていた。
花畑の果てから、
「子の魂、いらんかえ~~、いらんかえ~~」
三角の編み笠を被り、深い籠を天秤棒に両側に振り分けて呼び声を発しながら痩せた男がやってきた。年に一回やってくる魂売り屋だ。
「おお、正座師匠の旦那。活きのいい魂はいらんかえ? 今年のは全部、桃源郷生まれの魂だよ」
「桃源郷生まれだと? よく仕入れられたことだな」
正座師匠と呼ばれた老人は、籠の中を覗きこんだ。
深い籠の底には、蛍のような小さな光がたくさん、うごめきながらチカチカしている。
「今年の桃源郷は特に活気づいていてのう、西王母(せいおうぼ=桃源郷の女神)はじめ妖精たちも、たくさん子を産んだのさ」
「ほほう?」
師匠の万古老は、籠からひとつの黄緑色の光をそっと手のひらにすくった。
「これは元気で聡明そうな子じゃな」
「さすが正座の師匠、お目が高いねえ。その子は西王母が一番に産んだ子だ」
「じゃあ、この子をもらおう。ちょうど身の回りのことをしてくれる弟子が欲しかったところじゃ。あ、そっちの籠も見せておくれ。ひとりでは寂しかろう」
「あ、その子は残念ながら、夜まで命が持つかどうか。今にも消えそうな蒼い光だろう。間引き(取り除く)しようと思っていたところだ」
「いやいやどうして。かなりな生命力を感じるぞ」
師匠は白い眉で覆われた目を輝かせた。
「他の子とは違う光を感じる。どんな子に育つか楽しみだ」
こうして、間引きされようとしていた百世(ももせ)と最初から輝いていた流転(るてん)は、魂売り屋からたまたま洞窟前で黄水仙を眺めていた万古老という正座師匠に買われて育てられ、弟子にされた。
百世は黄水仙のようにいつまでも瑞々しく、活き活きとした女の子になるだろうと万古老が見込んだ通り、行動力いっぱいの活発な、同時に思いやり深い子に育った。
買われたばかりの頃は、線香花火の先っちょの火玉のように小さく弱々しい存在だったが、今では万古老の言いつけを聞かないほどお転婆になり正座もうまくできる。流転の姉貴分を気取っているようで、実はおとなしい彼を見守っている。
百世(百回のように多くの命)を生きてきたのを万古老が見抜き、「百世」と名づけた。
一方の流転は買われた頃は、やけどしそうなほど熱い火球だったが朱色の炎はだんだん優しい黄色になり、少年に成長してからは書物をよく読み自然や動物を愛する優しい子だ。
その名のごとく生まれ変わりを流転した記憶を全て持ち、戦乱や陰謀の世を見てきたので、思いやりがありながら根は逞しい。苦悩を心の内に隠しながらも温和な少年だ。
第二章 正座の講座にて
人類暦二十一世紀のある日、万古老は日本のある地域で正座のお稽古つけを頼まれ、百世をお供に出かけた。流転はマイペースに「読みたい書物があるから」と言って、お留守番。
今年も春の訪れを告げる黄水仙が咲く季節がめぐってきた。
気の早い春の鳥がさえずっている深い青空の下、黄色の花の海をかき分けて歩いていく。
師匠の後に続いていた百世の足取りは自然と軽くなり、師匠を抜いて走り出すかと思えば、また戻ってきて地面に寝転んだりした。
「これこれ、花を踏みつけちゃならんぞ」
「分かってるわよ!」
銀色の長い髪をなびかせて、また走り出す。万古老に買われてから三百年は経つというのに見かけは十歳くらいの少女だ。
「やれやれ、お転婆め……」
万古老は、正座講座の講師に招かれた小さな町の公民館で正座の所作をしてみせた。
「背すじを真っ直ぐにして立ちます。背骨が真っ直ぐになっていることを意識して。そして床に両膝をつき、かかとの上に座ります。その際、衣の裾をお尻の下に敷きながら座ることをお忘れなきよう。裾が乱れたまま正座しては、だらしなく見えますし周囲の方のご迷惑にもなります。そして両手は、静かに膝の上に置きます。ささ、皆様もやってみてください」
集まっていた二十人ほどの住人は、自分でやってみた。
「あら、簡単に整った正座ができたわ」
「本当、いつもよりきれいに座れた気がする」
女性たちが口々に言っている。
「しびれを防ぐためには、身体の重心を前方に持ってくるようにして足に負担をかけぬこと。後は慣れですな。毎日やってみてください」
稽古に参加した人たちは、満足気にお礼を言った。
招いた町長が、
「万古老師匠どの。今夜は料亭を予約してあります。どうぞ、ごゆるりとこの土地の名産品など堪能していってください。何せ、水がきれいな土地ですからの」
「そ、そうですか? では、お言葉に甘えまして」
その夜、宴会を開いてもらった万古老は、勧められるままに杯を重ねてすっかりご機嫌になった。
昼間、稽古をつけられた中に中年の夫婦がいた。百世を見て、
「三歳で行方知れずになった我が子に面影が似ているわ」
「うむうむ、そっくりだ」
アグラ埼と名乗る夫婦は、万古老に「百世」を引き取らせてほしいと言い出した。
「行方知れずになった幼子に似ているとな?」
万古老が問うと、妻は涙をあふれさせて百世の頭を撫でている。
「応じてやりたいところじゃが、百世は普通の人間ではないのじゃ。仙界の生まれでのう」
「どこの世界の生まれでもいいのです。手元に置きたい! この子はきっと我が子の生まれ変わりですわ!」
「う~~む、仕方ないのう、では、あみだくじかジャンケンで決めるか」
「お師匠! そんなので決めるの?」
百世が驚いたが、万古老が耳うちした。
「どうせ、お前のお転婆ぶりにネを上げて、すぐに戻されるじゃろうて」
「お師匠ったら……。だいぶん酔ってるね」
アグラ埼夫妻がジャンケンに勝った。
第三章 新しい家
夫婦が百世を引き取った。
「うわあ、四角い家がたくさん並んでる!」
夫婦の住む住宅街に案内された。日本の二十一世紀前半の、そこそこの一戸建てである。
百世が使う部屋には、優しい花柄のタマゴ色の壁紙や真っ白な家具がそろえてあり、クローゼットとやらには奥さんの趣味なのか、リボンとレースとフリルの洋服がずらりと並んでいる。
「これは?」
「三歳で行方不明になった娘の部屋なんだけど、もし戻ってきたらと思って、毎年大きくなった時の洋服を揃えてたの。夢が叶ったわ」
薄暗い岩肌の洞窟の住処(すみか)とのあまりの違いに、最初は戸惑った百世だったが、すぐに慣れた。
「何か欲しいものはないかい? もっと綺麗な洋服とか、甘いお菓子とか……。何でも買ってあげるよ」
しかし、百世は、
「べつにほしい物なんてないよ」
「じゃあ、お前がイヤなことは何だ? 絶対しないように気をつけるから」
臨時の両親が目尻を下げて尋ねる。
その時、百世の心にちょっとワガママなことが思い浮かんだ。
「う~ん、それなら正座はもういいかな? 何百年も毎日毎日、何十回もお稽古してきたから、もう飽きた!」
この家に、そんなに長くいるつもりはないから、しばらくぐらいならサボってもいいかな? と思ったのだった。
「分かった! 今日から百世ちゃんはソファで寝そべったり、床ではあぐらかいたり、好きなポーズでいてくれていいよ」
臨時の両親は、ひとつ返事で請け合った。
「待って」
母親が言った。
「百世ちゃんが長い間、毎日お稽古してきた『正座の所作』ってどんななの? 止める前に見せてほしいわ」
「お安いご用だよ」
こざっぱりした白いワンピースを着せられた百世は、すっくと立ち上がった。
「こうして背すじを真っ直ぐに立ちます。そして床に膝を着きスカートに手を添えて、お尻の下に敷きながら、かかとの上に座ります。ここ、重要ね! スカートが乱れてるとだらしない座り方に見えるから。後は両手を膝の上に乗せます。これで正座の出来上がり!」
両親はパチパチパチ! と笑顔で拍手した。
「立派よ、百世ちゃん! 十分、お師匠さんを務められるんでしょう?」
「ま、まあね。何百年も稽古してれば」
「お休みするの、勿体ないわね」
「いいの、いいの。さっきの通り、あたい『正座の極意』は体得してるから」
「『正座の極意』を? 偉いね。まだ小学五年生くらいなのに」
母親が感心している。
「こう見えて、あたいは三百歳くらいらしいんだ」
「三百歳? 仙界の万古老さんの弟子ですもんね。不思議はないわ」
母親は唇のハシにそっと薄く笑いを浮かべ、臨時の父親と顔を見合わせた。
第四章 ぐうたら万古老
その頃、仙界の洞窟では、流転が万古老の帰りを迎えた。
「お帰りなさい、師匠。あれ? 百世は?」
「ああ、百世は講座を受けに来ていた若い夫婦のところへ養女にやった」
「養女? 百世を養女にやっただって? ウソだろ―――?」
流転はみるみるうちに真っ青になり、さっきまで鍋をかき混ぜていた木べらを落とした。
「いんや、本当だ。行方不明になった娘さんに似ているとかで、気に入って離さないご夫婦がおっての」
「百世は喜んで行ったのか?」
「まんざらでもなかったぞ。こんなひと気のない寂しい岩山ばかりの中の生活に飽きたんじゃろう」
「そんな……、だって、百世は」
「そんなに心配せずとも百世は逞しい。環境が変わっても生き抜いていくじゃろう。突然の別れに思えるかもしれぬが、若い魂はいつかは巣立っていくものじゃ」
「師匠、本気で言ってるの?」
流転は呆然と突っ立ったままだ。
「それより流転、土産に舶来の菓子をもらったぞ。ワシには高価な酒とアテをな。奥で夕餉(ゆうげ)にしよう」
「おいら、とても食欲なんかないよ」
流転は洞窟から見える紫の残照に目をやった。
「小さな魂の時から、ずっと一緒だった百世と別れて暮らすなんて……」
空を見つめる黒い瞳から、涙がじんわり沁み出てきた。
夜半、流転は眠れずに寝返りばかりうっていた。一昨夜まで百世が隣の寝床に寝ていたのに、今は敷いた藁はそのままで冷え切っている。
正座のお稽古がうまくできない時は、百世はよく慰めてくれた。本当の姉さんみたいに。
一睡もできなかったが、いつも通り夜明けに起きて身支度を整えた。朝の正座の稽古をしなければならない。
洞窟から出て、小さな滝壺のある稽古場に行った。しかし、万古老の姿はいつまで経っても見えない。
「どうしたんだろう、師匠。遅れたことないのに」
万古老師匠の様子を見に洞窟へ戻った。師匠はまだ夢の中ではないか。
「師匠、朝ですよ! 早く起きて!」
「むにゃむにゃ……、流転か……。たまには良いではないか。稽古は休みにして一日中寝ていても」
「はあ?」
とても万古老の言葉とは思えない。
流転は、魂売り屋から万古老の元へ来て、一日も欠かさず正座の稽古をしてきた。一日サボっただけで勘が狂うと教えられたからだ。その万古老が――。
その日から、万古老はどう動かそうとしても一日中ごろごろしてばかりで正座の稽古どころか、まともに起きることもしなくなった。お腹が減れば流転の作るメシを、寝床に座ってのんびり食べるだけで、食べ終わるとまた横になってしまう。着替えもしないしお風呂にも入らない。
「そんなに寝てばかりいると身体にカビが生えちゃうよ! どんどんお腹がぶよぶよになってきたよ」
万古老に、ぐうたらの神が憑りついたかのようだ。
『雲の峰大師匠、及第点をいただきまして、万古は光栄にございます』
急に起き上がってしゃべったかと思ったら、またバタンキューだ。寝言だったらしい。
(このままじゃいけない! もしかして、百世がいなくなってダレちゃった?)
流転は勇気を出して、百世を連れ戻そうと思い立った。
蒼く長い髪をお団子に結い上げ、この前、万古老が正座の講座を開いた町を目指して出かけた。
第五章 黄水仙の丘で
流転は町の小さな公民館に行った。
「あのう、先日の正座講座の参加者名簿を確かめていただけませんか?」
受付のメガネのおねいさんに頼んだ。
「あなたは?」
「おいらは講師に来ていた万古老の弟子で、流転といいます」
万古老の正座師匠の証明証と、弟子である証拠にテキパキと正座して見せると、おねいさんは納得して名簿を繰ってくれた。
「おいらと同じような皮の衣を着た女の子を、連れて帰った人がいるそうなんだけど……」
「ええと、アグラ埼さんだったかな。初めて参加したご夫婦よ」
「その人たちは、どこに住んでいるんですか?」
「地図ではご近所ね。丘の上の住宅街よ」
聞くが早いか、流転は公民館を飛び出した。しかし――。
(丘の上の住宅街?)
丘の上は黄水仙が咲き乱れる丘だった。
「家なんか一軒も見当たらないぞ」
流転が手をかざして眺めていると、水仙畑の果てから天秤棒をかついだ痩せた老人が歩いてきた。側まで来ると天秤棒を下ろし、歯の抜けた口でにんまりと笑った。あまりにも不気味な表情だったので、流転の背中にゾッとするものが走った。
「坊ちゃん、もしかして、これを探してるんじゃないですかい?」
皺深い手には小さな籠が握られており、流転が近づいて目をよ~~く凝らしてみると、
「百世! 百世じゃないか!」
籠の中には、マッチ棒くらいの寸法の百世とふたりの人間が閉じ込められている。男女の前で、百世はいつもの正座の所作をして見せている。
「百世!」
流転が大声で叫んでも聞こえないようだ。
「どうして、こんなに小さく……」
「クックック、坊ちゃん、無駄だよ。籠の中の者たちはワシの術によって聞こえないのじゃ」
老人が愉快そうに言う。
「お前は誰だ!」
流転は身構えて、老人から後じさりした。
「ワシか? ワシはしがない魂売り屋だ」
「何故、百世をさらって閉じこめた!」
「さらったりしてませんよ。女の子が夫婦の元へ行くと言ったんです」
「百世が万古師匠とおいらを見捨てるはずない! お前は誰だ、何か企んでいるだろう!」
「おやおや坊ちゃん、ひどい物言いですな。ワシは万古老さんと旧知の間柄ですぞ」
「……」
流転はおし黙った。
万古老が腑抜けになっている今、魂売り屋のことを確かめようがないが、その言葉は信用できない。現に百世を小さな籠に閉じこめている。助け出さなければ――。
(下手をすれば、おいらもマッチ棒くらいにされて閉じこめられるかもしれない。どうすれば――?)
懸命に頭をめぐらせて衣の下にハミ出ている鎖帷子(くさりかたびら)に触れた。
『雲の峰大師匠、及第点をいただきまして、万古は光栄にございます』
不意に万古老の寝言を思い出した。
第六章 黒麒麟(きりん)
(雲の峰大師匠……? そういえば、この三百年の間に何回か聞いたことのある名前だ。確か、万古老の大尊敬する正座の偉大な師匠のことだ。その方にお会いすれば、百世を助け出す方法を教えてくれるかもしれない)
(雲の峰大師匠は、おそらく雲の峰という聖なる座の秘境におわすはず……)
「ふぁふぁふぁ」
魂売り屋の老人が笑い出した。
「坊主、ムダムダ。雲の峰大師匠にお会いしたいと考えただろう。せっかくじゃが不可能じゃ」
「なっ……、やってみないと分からないじゃないか」
とたんに、流転は強引な力で足元をすくわれて転んだ。
魂売り屋の持つ、どす黒いビイドロからの引力に捕らわれたのだ。
「こ、これは」
「所詮、お前なんぞワシが昔に仕入れたオタマジャクシのような魂。逃げ出すのを食い止める方法くらい心得とるわ」
百世の囚われている籠に飛びつく度に、足を引っぱられて派手に転び、黄色い花びらや葉がぺちゃんこになった。心の中で黄水仙に謝りながらも、流転は何度も突進した。
「ふぉふぉふぉ、小僧ごとき、ビイドロの力に逆らえるものか」
ひょろひょろした魂売り屋だが、巧みに身をかわし逃げるのが素早い。
「くぅっ」
涙とドロとで汚れた顔を、流転はゴシッと腕でぬぐった。
その時――。
頭の上を巨大な影が覆い、一陣の風が巻き起こった。とんでもない強風だ。地響きがして、視界の端に黒い巨大なカギ爪が見えた。続いて大太鼓ほどある金色の眼玉がぎょろりと間近に迫り、流転は地面に身体ごと伏せた。
「ぎゃあああ!」
魂売り屋の悲鳴が上がる。
天から現れた龍のような鹿のような巨大な生き物は、樹齢数十年かという松の高さくらいはある。
黒いウロコに覆われた顔に見下ろされて、流転は動けない。
「下界が騒がしいゆえ、見てくるようにとの大師匠の仰せであったが、陰(かげ)しるべ、騒ぎの元はお前か」
深遠な声が黄水仙の畑に響いた。
「な、なんだ、黒麒麟の角端(かくたん)、お前か」
魂売り屋はペッとツバを吐いた。
「ワシも軽く見られたもんだ。戦いが苦手なお前を差し向けられるとは」
「無礼な口の聞き方は許さぬ。我は雲の峰大師匠の遣いであるぞ」
黒麒麟の眼光が鋭さを増した。
「へん、草も踏めない臆病者のくせに」
「口を慎めと申すに。――で、この度は何をしでかした?」
「万古老の弟子に両親を世話しただけだ」
流転が息まいて、
「三人とも、小さな寸法にして籠に閉じこめてるじゃないか! 黒い麒麟さま。おいらは万古老の弟子で流転と申します」
流転は正式な所作で正座し、挨拶した。
「む? この少年の申すことは誠か? 陰しるべ」
「流転! 助けてくれよ~~!」
陰しるべの手元の籠から女の子の声がした。
「あたい、ここから出られないんだ!」
「百世! 百世だな。やっぱり騙されていたんだな」
流転の返事を聞いて、黒い麒麟の眼に確信が宿った。
「陰しるべ、お前という奴は。雲の峰大師匠様の正座弟子でありながら姑息な行為をしおって」
麒麟のたてがみが赤黒く燃え上がった。
第七章 雲の峰大師匠って
「今すぐ籠の中の者を解放してやるがよい」
「分かったよ、すぐに出してやるよぉ」
魂売り屋の陰しるべは唇をひん曲げて、呪文のようなものを唱えた。とたんに籠から飛び出してきた夫婦の魂は蛍のような光になり、飛び去っていった。
百世は、白いワンピースを着たまま元の大きさに戻り、流転と抱きあった。
「流転! 会いたかったよ~~! やっぱり洞窟の生活がいい!」
「心配したぞ、百世。万古老師匠は腑抜けになっちまったよ」
「あたいも腑抜けになりそうだったよ。見慣れない変な道具に囲まれた生活はヤダ! 師匠と流転と一緒に毎日、正座の稽古をするのがいい!」
ふたりはしっかり抱き合って泣いた。
黒い麒麟が向き直った。
「陰しるべよ。お前は千年前、雲の峰大師匠から万古と共に正座の修行を受けた身にも関わらず、何故、万古の弟子をさらったのだ。申し開きをせよ」
「ええ? 万古老師匠と魂売り屋が共に正座修行を? ということは、ふたりは兄弟弟子だった?」
百世が叫んで、流転の目が丸くなった。
魂売り屋の陰しるべは、がっくりと地面に膝と両手をついた。
「ワ、ワシは『正座の極意』を会得しても貧しいまま。それに引き換え、万古は正座の師匠として名を馳せ、あちこちからひっぱりダコの人気。この差は何じゃ! と思うと悔しゅうて悔しゅうて……、三百年前、魂売り屋になって、ふたつの魂を売りつけたんじゃ。魂にあやつの得た『正座の極意』を盗ませようと潜在意識を埋めこんで――」
「なんてことを! あたいを利用したんだな」
百世は、今にも噛みつかんばかりに陰しるべに迫った。
「じゃあ、百世が操られて『正座の極意』を盗んだから、万古師匠は腑抜けになっちゃったのか? でも、『正座の極意』って?」
流転は首をかしげた。
百世は、強張った表情のまま、
「魂売り屋。あんた、三百年前、あたいが桃源郷で生まれた魂だと言って、万古師匠に売りこんだらしいな。師匠から耳にタコなくらい聞かされたぞ。それは本当のことか?」
「そ、それは……。今にも消えそうな弱々しい魂だったが、万古が気に入って買ったんじゃ」
黒い麒麟が念を押して尋ねる。
「誠にこの少女は、桃源郷の西王母さまが産まれた魂なのか?」
陰しるべは額から脂汗をしたたらせながら、
「い、いや……、実は、その子らは……雲の峰の大師匠がお産みになった子たちなの……じゃ」
「……!」
「……!」
黄水仙の群生を行き交うミツバチの羽音が聞こえた。
「えええええ―――!」
百世と流転が同時に叫んだ。
「雲の峰の正座大師匠って女性だったの――?」
「男の師匠だとばかり思いこんでた。道理で万古老が修行時代を話す時は、鼻の下が伸びていたはずだ」
ふたりは全身から力が抜けた。
「え――と、じゃあ、父親は?」
流転がそっと質問した。
「雲の峰大師匠さまにダーリンはおられませぬ。森羅万象の全てが愛される対象ですゆえ。お子も毎年、何万個も産まれます」
黒い麒麟が誇らしげに答えた。
「じゃあ、おいらたちは森羅万象の妖精みたいなもんなんだな」
百世と流転は、うなずきあった。
「森羅万象の平穏を乱した陰しるべよ。お前は今後、五百年間、仙界へも人間界へも立入りを禁ずる」
黒い麒麟が言い終わると同時に、陰しるべの細い身体は風に乗って飛ばされていった。
「さあ、万古老の弟子ふたりよ。住処(すみか)まで送って進ぜよう」
黒い麒麟が頭を差し出して角から背へ登るよう、うながした。
第八章 洞窟へ
百世が先に、麒麟の首によじ登り始めた。
その時――、流転の視界の隅っこに黒く鋭いものが飛びこんできた。
「百世!」
流転は麒麟の角に手を伸ばして百世の背中を覆い、盾になった。
「チャリ―ン!」
金属音がして、黒く鋭いものが弾かれて落ちていった。
「大事ないか?」
黒い麒麟も察した。
流転が皮衣の下に鎖かたびらを着ているのを見た百世は、流転を抱きしめた。
「ありがとう、ありがとう、流転。守ってくれたんだね」
「陰しるべって男は執念深いようだ。気をつけよう」
百世と流転を首に乗せた黒い麒麟は、空高く舞い上がり洞窟向けて飛び始める。
「本来、我ら麒麟は人間の太平の世におもむく。この度は雲の峰大師匠の特別の命でやってきたのだ」
「へえ」
「万古老どののおかげで洞窟の周辺は平和に満ちているが、将来、平和を保つ麒麟児が危ないかもしれぬとな」
「え? それって、もしかして百世が将来の麒麟児かもしれないってこと?」
流転が尋ねると、
「お前のことかもしれぬぞ、流転」
少々、笑いを含んだ麒麟の声だ。
「まさか、おいらたちのどっちかが麒麟児だなんて。結局、『正座の極意』なんておいらたちは教わってないもんな? 百世」
「そうよ。毎日、正座のお稽古の他は、万古老師匠のご飯作りと洗濯と掃除ばっか。後は師匠の一目惚れした女性への恋文の代筆とか……」
おしゃべりしているうちに、懐かしい洞窟が眼下に見えてきた。入口から人影が出てきて、両手を大きく振っている。
「ももせ~~~! るて~~~ん!」
「お師匠だ!」
「お腹がへこんで、いつもの筋肉質に戻ってる」
「遠路はるばる、ようおいでくだされた!」
万古老は、黒い麒麟、角端の思いがけない来訪に大喜びし、洞窟の一番奥に案内した。奥は広い空間が開けた場所で、巨体でもゆったり足を曲げてもらえる。
焚き火の上の煮物の鍋からは、甘辛い匂いが漂っている。
「この度は弟子ふたりが大変お世話になりました。酒なら村人からのお歳暮が樽にいくつもあります。どうぞどうぞ」
万古老はかなりご機嫌だ。百世が帰ってきたことが嬉しいのだろう。
黒い麒麟は品良く、人間の小さな盃に酒をついでもらった。
「雲の峰大師匠はお元気かな?」
「はい。ますます輝くようなお美しさで」
「そ、そうか。そうであろうのぅ~~」
万古老は目尻、口元が下がるのを止められない。
「お師匠、ヨダレ垂らしてないで、お酒もほどほどにしておいて!」
百世が万古老の手から盃を取り上げた。
「なんだ、百世。今宵くらいは良いではないか」
「酔わないうちに教わっておきたいことがあるんだ。あたいが陰しるべに狙われたのは、師匠が雲の峰大師匠から伝授されたっていう『正座の極意』を盗むためだ。この際、はっきり教えてもらいたい」
「師匠、おいらも同じことを思っている」
流転が鍋の落とし蓋を取る手を止めて、万古老の前に正座した。百世も並んで正座した。
「さあ、教えてください。『正座とは?』」
第九章 『正座の極意』
万古老は、目を閉じて長いあごヒゲを何度も撫でた。
「お前たちは何だと思う?」
百世が、
「ええと、神様にかしずく時の座り方とか、誠実を示す時の座り方とか」
流転が、
「心の奥からの祈りの座り方、非を詫びるのを精一杯あらわす座り方。後は――ただ心静かに待つ時の座り方」
「うむうむ」
万古老は目を閉じたまま幾度もうなずき、
「どれも間違ってはおらぬが、答えはもっとシンプル。正座とは――、『命と向き合う座り方』つまり『森羅万象を愛するための座り方』じゃ。これは黒い麒麟どのの、思いやりを持って『虫も殺さず草木も踏まず』という信念と通じておるな」
「万古師匠は、どうやって気がつかれたのですか?」
流転が尋ねた。
「雲の峰に住まう大師匠に師事し、やがて自分で気づいた。自ら気づかなければ『極意を会得した』とは言えぬ。いくら陰しるべが横取りしようとしても、自ら会得しなければ自分のものにならぬ」
「しかし……」
黒い麒麟が真摯な声で言い添える。
「運の良くない陰しるべにも、思いやりを持ってやってほしい」
「はあ~~、さすがは黒い麒麟さま」
百世は感心しきりにため息をついた。
第十章 黄水仙の中で
「陰しるべは寂しいんじゃないかな?」
百世がポツリともらした。
「『正座の極意』が目当てというより、稽古で賑やかにしているお師匠が羨ましいんじゃないかな?」
万古老と流転の瞳が輝いた。
数か月後――、
黒い麒麟が万古老の洞窟を訪ねてみると、奥から料理のよい香りと共に、歌が聞こえてきた。
「♪ はっぴぃばあすでい、とぅゆう、はっぴばあすでい、でぃあ、かげしるべ~~、はっぴばあすでい、とぅゆう~~♪」
(これは、もしや陰しるべが誕生祝いをしてもらっているのか?)
黒い麒麟が洞窟の入口で立ちすくんでいると、
「いいお天気だから、水仙畑に行こう!」
元気のいい声と共に足音が聞こえてきた。
万古老と百世、流転ともうひとりの青年が洞窟から飛び出してきて、水仙の海へ走り出した。
「あのう、そなたたち」
一同は振り向いて頭上を見上げた。
「黒い麒麟どの!」
美青年も足を止めた。
「陰しるべに、雲の峰の大師匠から祝い文を預かってきたのだが。そなた、陰しるべか?」
青年は即座に黒い麒麟の足元に正座して、紙片を受け取った。
「その所作……見事だ。やはり陰しるべ。雲の峰大師匠も驚かれるだろう」
「はい。初心に返って万古老から修行を受けました」
膝のつき方や頭の垂れ方、祝い文の受け取り方、言葉遣いまで、ひとつひとつの所作が凛々しく堂々としている。
百世が黒い麒麟を見上げて、
「麒麟さま、久しぶり! 陰しるべさんの正座、スゴいでしょう。あたいたちもお稽古に協力したんですよ」
「ほう……」
黒い麒麟は感心しきりだ。自信が容貌まで変えたのか、陰しるべは立派な体躯で生き生きした貌をしている。
「とても千二百六十三歳とは思えぬな」
「でしょう? 誕生日パーティーだから、あたいもこのワンピース着たの」
百世がアグラ埼夫妻にもらった白いワンピース姿で、クルリと回って見せた。
「踊りましょう、陰しるべ」
「うむ」
果てしない黄色の世界で舞い踊る師弟たち。黄水仙の花たちも祝福している。
「やはり、我は太平の世が好きだな」
黒い麒麟、角端の漆黒のたてがみが、そよ風に揺れた。