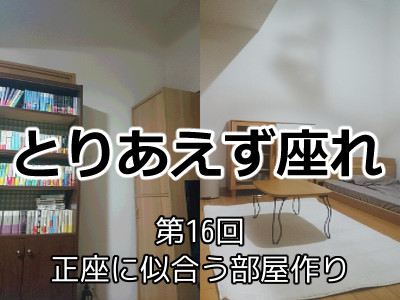[58]正座の春
 タイトル:正座の春
タイトル:正座の春
発売日:2019/07/01
シリーズ名:須和理田家シリーズ
シリーズ番号:10
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:44
定価:200円+税
著者:虹海 美野
イラスト:時雨エイプリル
内容
昭和五十年代、須和理田ハルは桜と縁側のある至上の自宅で暮らし、息子が結婚後孫の楽也、スグルが誕生する。
二人の孫は大人しい性格で、ハルが教えた正座も幼い頃からできていた。
しかし、楽也はおっとりした性格が徒競争で出てしまい、スグルはほかの子に正座をしていることをからかわれる。
二人が心配でもどかしいハルだったが、二人の七五三のお参り、春の入園、入学から、二人のよさ、そしてよその子のよさが見えてくる……。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1436396


本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
これは昭和五十年代半ば頃、東京郊外に暮らす須和理田ハルの温かな幸福と正座にまつわる物語である。
ハルは東京郊外の裕福な農家に生まれ育ち、女学校へ通った。お裁縫の授業が行われる時代で、自宅では正座をはじめとしたお作法についてもしつけを受けた。夫とは戦時中に出会い、夫が戦争から帰還後に結婚。四人の子どもに恵まれ、手狭な借家暮らしから、土地を購入して購入先の地元である工務店に依頼し家を建てた。
新居はそれまで住んでいた地域から更に郊外となり、都心からのアクセスはやや不便になったが、それを差し引いても、自然に恵まれた静かな新興住宅地はハルにとって至上の場であった。
ハルが家を建てる際にこだわったのが日当たりのよさと、縁側があること。いずれ余生を過ごす場所となる我が家の縁側で、ゆっくりと果物などを食べて暮らすことがハルの夢だった。そして、購入した土地には桜の木があった。言うまでもなく、この桜の木を残し、また負担をかけない条件で新居の建設は進められた。
やがて完成した家をハルは日々磨き、春から秋の始めまでの期間は縁側を開け放ち、そこに正座して庭を眺め、季節の果物を味わった。冬には貴重な日の出ている時間に和室の押し入れに仕舞ってある座布団を縁側に干しておき、ふとすればご近所の猫がそこで昼寝をしていたこともある。正座というと堅苦しいイメージもある昨今だが、ハルにとっての正座はごくごく日常の、そして愛着ある住まいにおいての温かな時間にあるものだ。
月日は流れ、三人の子どもが進学、就職、結婚で巣立ち、家からの通学通勤で実家暮らしの息子は結婚後に妻をこの家に迎えた。比較的大きな住宅の多いこの近辺では、当時それが一般的でもあった。夫と二人暮らしになることなく、新たな家族を迎え、そこから更に孫息子の楽也、孫娘のスグルが誕生した。
2
ハル自身も四人の子を授かったが、楽也を抱っこした時には、こんなに生まれたばかりの子は小さかったかと目を見張った。温かくて、小さくて、けれど男の子特有のずっしりとした重みがある。温かく湿ったような独特の匂い。それらはハルに生まれたばかりの子を抱いた時の記憶を甦らせた。
そして、孫というのは我が子の時とはまた違う楽しさがある。楽也が眠っていても、むずがっても、泣いても、嫁の両親、ハル夫婦ともに喜ばしい。産婦人科は過ごしやすい温度と湿度が保たれ、ミルクと石鹸の匂いが充満している。こんなにも優しい場所があるのだろうかと思うほどに、そこは生まれてから最初に過ごす場所として整えられていたとハルは思う。
ガラスで仕切られた新生児室に並んで眠っていたり、泣いていたり、手足を動かしていたりする子たちを見ていると、ハルは訳もなく涙ぐんでしまう。なんて無垢な目をしているのだろうと思う。
ハル夫婦は嫁の負担にならぬよう、新生児室で眠っている楽也をいつも見ては、差し入れの果物を渡し、長居せずに自宅へ戻っていた。
嫁は退院後、実家で一ヶ月を過ごし、それから須和理田家へ戻って来る。
それからは、ずっと楽也と一緒だ。
その日がとても待ち遠しく、嫁が実家で療養している間は息子の食事や洗濯をして過ごした。縁側に正座し外を眺めていると、時折通りかかる友人知人が楽也が来るのを待っているのか、と楽しげに尋ね、そのたびにハルは幸せな気持ちになるのだった。
3
それからの月日は本当にあっと言う間だった。
楽也が離乳食を食べられるようになり、寝がえりをうてるようになり、やがてつかまり立ちをするようになり、少しずつ喋れるようになり、その全てに須和理田家の大人四人は喜んだ。それまで寡黙だったハルの夫は楽也のことになるとずいぶんと饒舌になった。
そして暫くすると、息子夫婦は二人目を授かった。
嫁が出産で入院している間、楽也の面倒はハルが見ていた。
朝きっかり八時に起きる楽也にごはんやしらす、お豆腐、柔らかく煮た野菜の朝ごはんを食べさせ、散歩や公園に連れ出す。近所は古くからの知り合いばかりで、犬の散歩途中の友人や、庭の手入れをしている友人にたびたび会う。道に生えている草や、小さな虫を指差し、楽也が「あ、あ」とハルに教える。真剣に草や虫を眺める楽也は、そのうちにおでこから転ぶのではないかと思うほど前のめりになり、それを隣でハルは見守る。小さな楽也の小さな小さな世界は、楽也にとって果てしなく広いのが、ハルにもわかる。もう大人になり、結婚後の子育てではただひたすらに忙しく、マイホームを持つためにハルも必死に働いてきた。気付くと高齢に近付き、もう子どもの頃からは遠く遠く離れている。そのハルが思いがけず今、広がり始めたばかりの世界へと前進していく孫の楽也とともに、その世界の広がりを体験している。楽也の低い視点から広がる世界は明るく、そして彼を迎える温かい人の眼差しで満たされている。なんて美しい世界があるのだろう、とハルは思う。そして遠い昔、広い庭と裏には竹林の広がる生家で、蟻地獄を手で掘って遊んでいたような幼い記憶までもが甦り、一層ハルの心を温かくし、切なくもさせたのだった。
家に戻って来て、玄関で楽也の小さな靴を脱がせ、すぐに家の中を走り回ろうとする楽也を横脇に抱えて洗面所へ直行し、手を洗わせる。後ろから楽也の手を一緒に洗い、タオルでその手を包む時の幸福感……。自身の子育ての時に比べると、五十代後半のハルはくたくたになる。それでも気持ちは全く疲れなかった。
ハルより五つ年上の夫は六十歳で会社を定年退職し、今はビルの屋上の遊園地でアルバイトをしている。夕方には帰って来る予定だ。
それまでハルは楽也から目が離せない。
まだビデオデッキも普及していない時代である。
現代と比較すると、育児をフォローする商品は少なかったが、玄関の戸を閉め、縁側に面した和室を網戸にしておけば、楽也はそこでおもちゃを出して遊んでいる。これまで二階の子ども部屋にあったおもちゃを下の和室に持って来たので、夫とハルが主に使う落ち着いた雰囲気の和室は今、すっかり保育室と化している。
ハルは台所から顔を出して楽也の様子を見つつ、うどんを茹でたりして、簡単な昼ごはんを作り、ハルヤと食べる。
その後自宅から徒歩数分のところにある小さな一角を借りている家庭菜園に向かう。楽也に長靴を履かせ、帽子を被せ、おもちゃのバケツとシャベルを収穫用の籠に入れ、楽也の手を引いて行く。
季節により、イチゴ、トウモロコシ、ナス、キュウリ、ジャガイモといった野菜を収穫する。楽也にも取りやすいものを取らせてやると、それを自分のバケツに入れる。近所の公園で膝に乗せてブランコに乗り、楽也があちこちを走ったり、途中でまた草や虫を前に座り込むのに付き合い、帰って来る。
この後、日当たりのいい和室に楽也の布団を敷き、ハルは添い寝し、ひと時の休憩時間となる。寝る直前に水分をたくさん摂るとおねしょをするのを学んでからは、楽也が眠そうにしだすと愚図りだす前にトイレへ連れて行くのが習慣になった。干したばかりの布団の温かさに包まれて日の高いうちから眠るのは、どれくらいぶりのことだろうとハルは思う。並べて干した布団を入れ、楽也の分だけを敷き、ハルと夫の布団はそれまで押し入れに仕舞っていたが、三日と経たないうちにハルは楽也の昼寝の際に隣に自分の敷布団も敷くようになったのだった。
静かで温かい和室で楽也と二人、ひと時の眠りにつく。
網戸にしてある和室には心地よい風と庭木や土の匂いが流れ込む。
一時間弱の眠りで目覚めるハルは、その後洗濯物を取り込み、夕飯の準備に取り掛かる。
その頃には夫が帰って来て、目が覚めた楽也を夕方の散歩に連れて行ったり、庭先で遊んでやったりし、風呂に入れて面倒を見てくれる。
男の子だからよく動く。嫁と息子の子どもなので、自身の子どもよりも気を使うし、注意もする。それでもハルは楽也を大きな声で叱ることはなかった。恐らく、人間としての器が大きくなったのだ。体力は落ちたが。
和室のみの須和理田家ではそれほど家具はなかったが、子どもが触っては困るものは上に置く、という暗黙のルールで、それまで本棚に並んでいた大切な本も、飾ってあった花瓶も置時計も全て棚の上や収納に追いやってしまった。
夜、楽也が寝た頃には楽也のおもちゃやお絵描き帳が散乱していて、ハルはそれらを楽也専用の箱に放り込む。その繰り返しが一週間続き、嫁が退院とともに一ヶ月間実家へ行く時に楽也も一緒に連れられて行った。
久しぶりに散らからない静かな自宅でハルは、一ヶ月後の賑やかな生活に備えるかのように、思う存分昼寝をし、友達と出かけ、趣味を楽しみ、三人の帰宅に備えたのだった。
4
楽也の面倒であまり産院へは行けなかったが、息子夫婦が授かった二人目のスグルは女の子で、楽也と同じくらいの体重だったが軽く、柔らかい気がした。楽也が生まれた時、兜をハル夫婦がお祝いに買い、女の子のスグルのお雛様は嫁の両親が贈ると申し出てくれた。
新生児のスグルにはどうしても嫁の手が必要な時間が多かったが、母親と一緒にいたい楽也のことも慮り、スグルを外に連れ出せる時期になると、夕刻にはハルがスグルをベビーカーに乗せ、散歩に連れ出した。
楽也のお古で水色のベビー服のことも多かったが、それでも優しい顔立ちからスグルは女の子だと皆すぐにわかった。
三月の雛祭りには、豪勢な七段飾りが息子夫婦の部屋に飾られた。
まだ幼い楽也が雛人形で遊んでしまうかも知れないと思われたが、夫が雛人形の前で根気よく楽也にこれは遊ぶ人形ではないということを教え、楽也はこくりと頷いて、雛人形には触らなかった。
当時はまだコンパクトな家庭用ビデオカメラは普及していなかったが、息子夫婦は楽也誕生後すぐに八ミリカメラを購入し、その成長を記録してきた。今回もビデオの出番である。
雛人形の前にスグルを抱いたハル、その隣に楽也が座る。ハルはふと、楽也に正座の仕方を教えようと思い立った。もともと楽也も和室のみの家で育っているので正座はなんとなくできてはいたが、一度きちんと教えられたことは割と大人になっても身につくことが多い。
「いい? きちんと正座しておすわりする時には背筋を真っ直ぐにしてね。そう、上手。お膝はつけるかおてての握りこぶしひとつ分くらい開けて。足のお父さん指同士が離れないようにね。ほら、とてもきちんとした感じがするでしょう? こうして晴れの場や大切なところでは、きちんと正座をするのよ」
そう言葉で説明しながらスグルを抱っこする片方の手を伸ばし、楽也の座り方を直してやると、楽也はすっときれいな正座ができた。
小さいなりに品のようなものも漂っている。
「そう、上手」
ハルが手を叩くと、膝の上のスグルも笑って手足を動かす。
その二ヶ月後の端午の節句には兜の前で同じように正座をし、その記録をビデオに収めた。
5
スグルは楽也に輪をかけて大人しい子どもだった。当時はまだ布おむつが主流で、おむつが取れるのも早かった。楽也も早くに取れたし、スグルも二歳になる頃には完全におむつが取れていた。それもあり、ハルやハルの夫は比較的早い時期から楽也やスグルを連れてよく出かけた。もちろん出かける前、目的地に着いてから、そして帰る直前には「出ない」と本人が言い張っても必ずトイレへは行かせたが。
楽也が幼稚園に通い始めると、家で一人になったスグルをハルはよく連れて歩いた。スグルは大人しくはあったが、人見知りをしない子どもだったので、絶対にお母さんでなければ駄目、ということもなく、その点でも楽な子どもと言えたかも知れない。夫が行くのは近所の家庭菜園やホームセンターだが、スグルがついて来る時には、ついでにスーパーなり、デパートの屋上なりに寄って好きなものを一つ買ったり、遊ばせたりしてから帰って来た。
ハルは家にいる時は庭いじりか手芸、そして近所の同年代の女性との手芸やお茶会、公民館での老人会の集まりが主な行動範囲で、そのどれにもスグルはついて来た。
そして年寄りばかりの和室でお茶菓子をあさったり、お茶をひっくり返すなどという周囲の大人を煩わせることは一切しなかった。大人しくハルの隣でいつも正座をして、もらったお菓子を食べたり、ハルに分けてもらった手芸道具でスグルなりの何かを作っていたり、ご近所の猫と遊んでいたりする。ハルの友達は口ぐちにスグルのしつけの良さをほめた。特にしつけという印象は、嫁もハルも、そして夫にも息子にもない。もともとがこの性格だ。
そう説明しながらも、ハルは小さいながらに隣に正座し、ハルに寄り添う小さなスグルが自慢であり、それ以上にかわいくて仕方がなかった。
「しゅぐる~」と呼ぶと、「おばあちゃん」とにこっと笑う。ぺたっとくっついてくる。
6
小さな温かな世界で暮らすハルには、何一つ不満はなかった。しかし、これから広い世界へと歩み出していく子ども二人を育てる息子夫婦、主に嫁にとっては、ハルのように呑気に平和を満喫するばかりの日々ではなかったようだ。
楽也の初めての幼稚園の運動会には、もちろん家族で応援に出かけた。嫁の両親もやって来た。嫁は周囲との付き合いも怠らず、何人かの子どもを介した母親同士の輪にも加わっていて、楽也、そしてその妹のスグルもそうした人の輪の中に参加している様子だった。ハルの知らない若い母親の口から「楽也くん」とか「スグルちゃん」と呼び慣れている孫の名前を聞くと、ハルは何ともくすぐったいような、嬉しい気持ちになる。
運動会が開始され、暫くすると同じ場所で運動会を見ていた家族の下の子どもたちが飽き始めたのか、シートをつけて座っている仲間内の間を走り始めた。ハルは注意したものかどうか、少し迷う。自分の孫が行儀の悪いことをしていれば叱れるし、自分が母親であっても多少の口出しはしていた。しかし、祖母であるハルは完全にそうした幼稚園の小さく狭いコミュニティの蚊帳の外だ。下手な口出しはできない。しかも、孫のスグルはほかの子どもが騒いでいてもそれに加わらず、きちんと正座をして運動会を見ているではないか。須和理田家は祖父母四人も運動会を見ることから、通常のシートの上に布製の柔らかいマットを二重に敷いているので、ほかの家族に比べ、座りやすい環境ではあった。しかしそれを差し引いても、ハルはスグルを褒めてやりたい心境だったが、この場で褒めると波風が立つ。その思いは夫をはじめ、嫁の両親も同じであることが顔つきから覗えた。嫁の両親は、騒いで遊ぶほかの子どもの中、きちんとしているスグルがほかの子どもと一緒に行動しないのかが気がかりなものの、態度に出さぬよう気をつけているようで、スグルに「ほら、お兄ちゃん、あそこにいるね、わかる?」とか、「喉乾いてない? 麦茶があるよ」と話しかけ、この場をやり過ごそうとしている。
楽也は、徒競争の途中で宝拾いをする競技に出ていた。
ほかの家族も楽也と同学年なので、身を乗り出して競技を見守る。
スタートで楽也は圧倒的に速かった。
楽也を知らない人も、「あの子、速いわね」と言っているのが聞こえる。
しかし楽也は、置いてある袋に入った子ども用のシールブックをどれにしようかうろうろと迷い、しかもようやく手にしたものを袋の下から持ったことで中身を落とし、丁寧に袋に戻しているうちに後から来た子がゴールしたのに気付いて慌てて走り出し、一位を逃した。
楽也がうろうろしている時には息子が「もう、どれでもいいから」と楽也まで届かない音量で言い、袋を下から持った時には嫁が「あっ」と声を上げ、そのまま須和理田家は楽也がゴールするまで一言も発しなかった。
そしてなんとも言えない落胆が須和理田家一同に漂った。
「楽也らしいな」と目を細めて言ったのは、夫だった。
「運動神経は申し分なし、その上気持ちがおっとりしていて、言うことないじゃないか」
周囲に聞こえるほどの大声で、少し恥ずかしく、それをたしなめるのはハルの役割ではあったが、「そうよねえ」と一緒に頷いていた。
まだ納得していない顔の息子と、せつなそうな顔をしている嫁の気持ちが少しでも晴れればいいとハルは思う。これに似たような思いは、ハル自身、もちろん何度も経験している。我が子となると、悲しいとか悔しいとか、そういう気持ちは本人よりも親の方が強いことが多いものだ。自分が代わりにやった方がよほどいいと思うほどに、もどかしいものだ。しかしそれが年を重ねるごとに、まあまあ、と思うようになる。それをわかっている今、息子夫婦にも伝えたい気持ちはあったが、それは諭されることでなく、時間の中で思い出を消化する過程で学んでいくものでもある。
そんな思いでいると、さっきから遊んでいた子どもたちがスグルの後方で、「なんで大人みたいに座ってるの?」とからかうように言っているのが聞こえた。言った子は、入園前のここにいる子どもの中では年上のようで、言葉も思考もほかの子どもより長けているようだった。そうは言ってもまだ二つ三つの子どもの他愛のない会話である。けれど、孫をかわいがるハルとしては、ピクリ、と神経に触り、意地の悪い子どもだと感じ取られた。「大人みたいに座ってる~」とほかの二人の子どもが舌の回りきらない口調で真似をし騒ぎ始めたが、騒いでいる子どもの親は全く気にしている気配がない。見るに見兼ねた嫁の両親が「スグル、ちょっとジュースでも買いに行こうか」と、この場を離れる提案をした。なるほど、三人をいつ叱ってやろうかと思っていたハルは、その平和的解決に内心大きく賛成した。しかし、スグルは「ううん、いい」と首を振る。「ここでお兄ちゃん、見てる?」と嫁の両親が訊くと、「うん」と頷く。なんともいじらしい気がしたが、逆に言えば芯が強い子どもなのかも知れない、とハルは思った。
その後十分と経たないうちに騒いでいた子どもたちは、観覧席側にある砂場へ遊びに行ってしまい、静かになった。スグルは一緒にあの子たちと遊ばなくていいのか、遅れを取らないかとハルは心配だったが、夫は至極上機嫌でスグルと一緒に運動会を見ていた。うるさいのが遊びに出てよかったくらいに思っているのだろう。
お昼の休憩時間には昼食を摂るのに、ほかの家の親は砂場に行った下の子を迎えに行ったが、須和理田家はその間に昼食を始めた。
夫は家族席にやって来た楽也をやたらと褒めた。一位を逃した楽也は少し申し訳なさそうな顔をしていたが、夫の「楽也は優秀だ。運動も性格もよくできている」という言葉に何か思ったらしく、食の細い楽也のために嫁が用意した小さなお稲荷さんを食べ始めた。
スグルは普段家庭菜園へ行っているからか、野菜が好きで、畑で取れたとうもろこしを茹でて小さくカットしたものを食べている。楽也はまだ多少しょんぼりしていたものの、スグルが食べたとうもろこしの芯を片付け、「飲む?」と麦茶の入ったコップを渡してやっていた。
そうした須和理田家のまわりで、砂場で遊んでいた子どもたちが手を洗い、戻って来て食事を始めた。
また意地の悪いことをあの子どもたちが言い出しはしないかと、ハルは心を構えていた。
暫くして昼食が終わりに近付き、園児が自分たちの席に戻って行くと、さっき砂場で遊んでいた子どもの一人がスグルにチョコレートのパッケージを渡した。
スグルは驚いた顔をして、それからすぐに「ありがとう」と言った。
「あらあら、ありがとう」と嫁の両親が、感激してお礼を言う。
スグルはお弁当の箱からとうもろこしを出し、「食べる?」と訊いた。
ハルは慌てて、今日のために買っておいたビスケットを出す。さっき楽也に食べるか訊いたが、『今はいい』という返事だったので、仕舞っておいたのだ。せっかくのお菓子交換という交流のチャンスに、とうもろこしはいかがか、と思った。
しかし、その子はさっきからスグルのとうもろこしが食べたかったのだということを、その子の親が遠慮がちに説明し、スグルに「ありがとう」と言ってくれた。
その子はそのままスグルの隣に座り、特に話したりしないものの、子ども同士でわかり合えるような穏やかな空気を醸し出していた。その間もスグルはきちんと正座をしていて、それがハルには妙におかしかった。その子がとうもろこしを食べ終わるタイミングで、スグルは手を出しそれを受け取って、ハルが横に置いていたごみ入れに片付ける。こういうさり気ない心配りが須和理田家の孫二人は身についている。
運動会の終盤にある選抜リレーでは、楽也が二人を抜き、クラスの子やその親、先生からの大声援を受け、バトンをつないだ。
思わず乗り出して応援したハルは、涙が溢れているのに後で気付いたのだった。
7
その年の十一月は、須和理田家にとって一大イベントが待ちかまえていた。五歳の楽也、三歳のスグル二人の七五三である。嫁の両親、ハル夫婦、そして息子一家で連れ立って、衣装を買いに行った。楽也は水色を基調にした羽織袴、スグルは赤を基調にした着物に白の被布である。大人しい雰囲気のスグルに赤の着物は派手ではないかと思われたが、華奢な体型や大人しい雰囲気に華を添えるように着物はしっくりとスグルに馴染んでいた。
衣装購入後には、子ども用の写真館での前撮りも行った。
これは早朝からでスタジオも混雑するため、出来上がった写真を後で見せてもらった。
「あらあら、かわいらしい」とハルは顔をほころばせる。以前ご近所のお孫さんの七五三の写真を見せてもらい、なんてかわいらしい、と思ったが、須和理田家の孫の晴れ姿もなかなかのものだった。
お宮参りには、嫁の両親、ハル夫婦も付き添い息子家族四人と合わせ、八人での参拝になった。中でのご祈祷の時には息子家族だけで入るので、両家の祖父母は暖を取るのも兼ねて、境内の向かいにある喫茶店に入った。お祓いの開始時間まであと二十分ほどかかると息子が言っていたので、ちょうど良い休憩時間になった。
窓際の席からは、続々と七五三の参詣に訪れた親子連れが境内へ入って行く様子が見える。
「あらあら、みんなかわいいこと」と両家の夫婦は目を細めるが、内心『うちの孫ほどではないけれど』と思っていることは言わずともその顔が語っていた。
普段二人の孫ばかりを見ているハルだが、なるほど年の割に体格のしっかりとした子や、いかにも気の強そうな子、利発そうな子というのは少し見ただけでも覗える。同じ神社にお参りするだけの子どもではあるが、地元の神社ということもあり、この先小学校で一緒になる可能性は十分にあった。また、今見た子どもたちが別の学区だったとしても、体格や性格、能力など、あらゆる子どもの世界で比較される面において有利な要素を持っていそうな子はどこでも一定数いる。その中で、肩の薄い、自己主張のほとんどない孫たちがいざ競争となった時、どれだけ対抗できるかと自身で問えば、それはなんとも微妙な気持ちにハルをさせるのであった。楽也の運動会の日に垣間見た、子ども同士の世界での孫二人の立ち位置は、少し客観的に見れば「いいじゃないの」とおっとりと捉えられるが、本音ではやはりきれいごとばかりは言っていられないし、穏やかではいられない。
「そろそろ始まるみたいだけど、ちょっと行ってみないか」とハルの夫が時計を見ながら言った。
ご祈祷に同席はできないが、それでも境内のベンチからその様子は見られる。孫にすっかり甘く、ハルのように『うちの孫は大丈夫かしら』などという考えが、今よその子どもを見ても微塵も浮かぶ様子のないほど二人の孫を溺愛している夫は、暖を取って休むよりも寒空の下外からでも孫たちの様子を見たいらしい。
嫁の夫婦も「行きましょう」と腰を上げ、四人はいそいそと境内へと戻って行った。
季節柄、ご祈祷に訪れた親子連れは多かった。
その中に須和理田家四人の姿もあった。
四人並んで正座をしている。
「まあ」と声を上げたのは、嫁の母だった。
息子夫婦はもちろんだが、五歳の楽也、三歳のスグルがとてもきれいに正座をして、大人しく前を向いていた。
周囲の子とは一線を画した所作だと言って、過言ではなかった。
和服の映える薄い肩にほっそりとした首筋、そして真っ直ぐに伸びた背筋ときちんと膝をつけての正座の様子が後ろからでもよくわかる。
同じように外から孫の様子を見ているらしい祖父母と思われる年代の夫婦が、「まあ、小さいのにずいぶんきちんと座っている子がいるのね」と囁き合っている。
ハルは楽也に正座を教えた後に、お正月、お雛祭り、端午の節句といった折に、スグルにも丁寧に、そして繰り返し正座を教えてきていた。運動会の日にスグルがシートの上に二重に敷いた柔らかなマットの上で正座をしていたのも、今思えば、そうした日々の積み重ねの成果であったと思う。
ああ、あの子たちは大丈夫、とハルは一人心の中で思った。
ちゃんと大切なことは聞いて覚えている。それを実行できる。二人の気質がそのままあの姿として現れているではないか。
嫁と息子はきちんと二人を育てている、大丈夫だ、そう思ったのだった。
8
幼稚園の二年保育が主流だった当時、二歳違いのスグルと楽也は、春にそれぞれ入園、入学を果たした。楽也は放課後になれば近所の友達とあちこちへ自由に遊びに行くようになった。もうハルが手を引いて散歩や公園に連れ出す必要もない。「須和理田」と名字で呼び捨てにされ、それに普通に答え、嬉々として出かけていく楽也をハルは目を細めて見送る。
スグルは幼稚園から帰って、ハルたちのいる和室で絵を描いて遊んでいた。
そこへ「スグルちゃん」と呼ぶ小さな子の声がする。
ハルが縁側に出てみると、母親に手を引かれた子どもがいた。
あ、とハルが思ったのは、いつぞやの幼稚園の運動会でスグルに意地の悪いことを言った子どもだったからだ。少し構えはしたものの、「こんにちは」とハルは優しい口調で挨拶した。
「あの、この子がスグルちゃんと遊びたいと言ったので、声をかけさせてもらいました」
母親は、嫁との会話よりかなり丁寧な口調で説明し、子どもの前に立っている。
ハルは縁側から「スグル」と声をかけた。
ととと、とスグルがクレヨンを持って出て来る。
「あー」とスグルは嬉しそうに笑う。
「毎日、スグルちゃんとこの子、遊んでいるんですけど、今日は自由に遊べる時間が少なかったから、遊びたいって言い出して……」
「そうですか」とハルはスグルとその子どもの様子を見て頷いた。
「スグル、どうする? おうちに上がってもらって、遊ぶ?」
スグルはこくん、と頷く。
嫁が外での声を聞いて出て来て、子どもの母親と砕けた会話をし、母親には夕方迎えに来てもらう約束をし、子どもを家へ招き入れた。
子どもは嬉しそうにキルティングの手提げからスーパーボールや折り紙を取り出して、「どれで遊ぶ?」とスグルに訊く。スグルは嬉しそうに「全部やりたい」と飛びはねた。
二人は嫁に言われて、二階の子ども部屋へ行き、すぐに二階からは楽しそうな遊ぶ声が聞こえてきた。
ハルはお茶を入れ、縁側に座布団を二枚並べ、夫にも勧めた。
二人で葉桜になりはじめた庭の桜を眺め、温かな木漏れ日の中で穏やかな時を過ごす。
運動会の時、うるさくて嫌な子だと思ったことをハルは今更ながらに少し後悔する。
どの子もみな、いとおしいと思う。
須和理田家の孫は大人しく、外でもきちんと正座ができるのが美点だ。
そして、よその子にも、今のように「遊びたい」と思ったら、それを親に伝えて来る行動力や、たくましさ、明るさがある。それを先入観なしに、ただ心で受け止め、動きだせる子どものしなやかさ。それはなんと温かく、そして力強いのだろうと思う。
縁側に敷いた座布団に正座をし、見上げた春の空に、ハルは遠い日の懐かしい子ども時代を思い浮かべた。ハルは冬生まれである。近付く春を心待ちにするハルの両親は、春を前に誕生する予定の最初の子の名前を女の子ならハルと決めたという。
ああ、そうだ、とハルは空を見る目を細める。
もう建て替えてしまったあの農家の広い家。竹林を風が通る涼やかな音。土埃の立つ庭で遊んでいたハルを呼ぶ声。顔を上げると、いとしげにハルを見ている、かつてハルを守り、慈しんでくれた人。家を出た後、困ることのないようにという願いから、正座やお作法を仕込まれた。
無償で注がれたものを、ハルは今、確かに引き継ぎ、そして与えていた。
先日、立て続けに他県で暮らす子どもから連絡があった。仕事先での昇進の報告、結婚が決まったという報告、子どもを授かったという報告……。
電車で一時間ちょっとの場所に暮らす子どもたちを訪ねる機会も増えそうだ。
暖かな日差しは、希望に満ちている。