[266]満月の正座ガマ
 タイトル:満月の正座ガマ
タイトル:満月の正座ガマ
掲載日:2023/11/08
著者:海道 遠
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
いつの時代なのか。人通りの賑やかな街中で、小鬼姫とギボシ姫が、毛むくじゃらな白りんどうという男から「オーディション参加者募集」のビラをもらう。正座すると佳い匂いがするという「雅馬」(がーま)のマント持ちを募集するビラだった。
オーディションにはたくさんの女性が集まりすぎて、白りんどうはくじ引きにし、小鬼姫とギボシ姫が当たる。

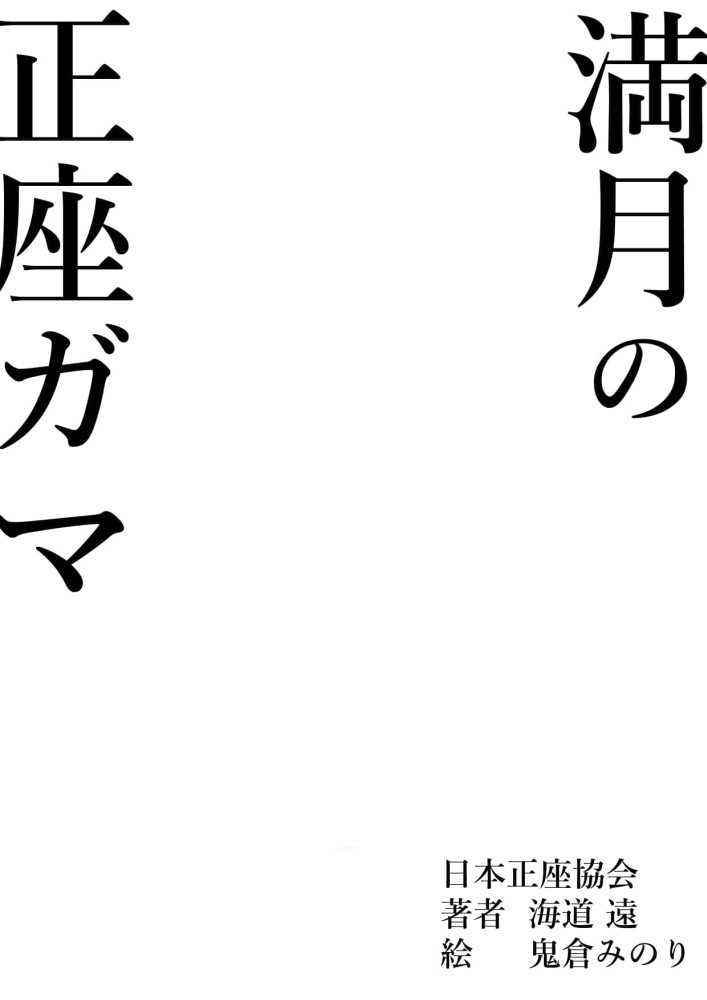
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 ビラ
いつの時代のことやら―――。
都の大路は人であふれている。旅人や金持ちらしきお供を連れた者、はしゃいでいる若者たち、大道芸人が道の隅っこで芸を繰り広げていたり。様々な物売りが屋根を連ね、客の呼びこみを大声でやっている。
「そこの旦那、この壺はお値打ちもんだよ」
「姐さん、反物、きれいなのがいっぱいあるよ!」
「今朝、畑で穫れた野菜がいっぱい並んでるよ」
小鬼姫という娘が歩いていた。丈の短い、白いフリルのいっぱいついたピンクの着物を着て頭はツインテール、ウサギの耳を着けている。
七色のソフトクリームをなめながら、人混みの中を歩いていると、急に腕がにょっきり伸びてきて一枚のビラを渡された。
振り向くとビラ配りの男がニヤリと笑った。熊みたいな男だ。
「なになに、オーディション出場者募集? 美青年のマント持ち、やりませんか?」
小鬼姫の後ろを歩いていた娘もビラを受け取ったようで、小鬼姫と目が合った。小鬼姫より頭ひとつ背の高く、年齢も上のような娘で、大人びた紫の小袖姿だが色っぽく着くずしている。
「え、このマント持ちって、今、噂の『正座するといい香りが漂ってくるとかいう雅馬(がーま)』という美しいと評判の?」
小鬼姫も慌てて読み直した。
「『雅馬のアシスタント、マント持ち募集!』 ほんとだ! ね、ビラをくれたおじさん! これなら、あたいが立候補するわよ!」
「何、言ってるのよ、小娘。このギボシ姐さんが先に立候補するのさ!」
紫の着物の女がはばんだが、小鬼姫も負けていない。
「若いピチピチしたあたいがやるんだよ、年増はお呼びでないのさ」
「誰が年増だって? このがきんちょ!」
ふたりはつかみあいのケンカを始めかねないばかりの剣幕で睨みあった。
「ちょっとちょっと、娘さんたち。ケンカしたら失格にするよ」
ビラを配っていた熊のように毛むくじゃらの男が止めに入った。
「マント持ちの役目をやりたかったら、そのビラに書いてある通り、今度の日曜に中央公園においで。オーディションやるから」
「このオーディションに合格したら、雅馬っていう甘い香りの青年のマント持ちをやれるの? マント持ちって何よ?」
小鬼姫が飛びついてきいた。
「雅馬の美しさは格別なんでな、簡単に見せるわけにはいかない。感化されて心が洗われて自分までご利益受ける。頭からマントを被せて見えないようにするのさ。雅馬のご利益が減ってしまっちゃ困るからな」
「それでマント持ちの係を募集してるのね」
「ああ、そうさ」
熊の毛むくじゃら男は頷いた。
「あたいがその係、やるわ!」
「いいえ、わちきよ!」
鮮やかな紫色の着物の女も叫び、一触即発だ。
パンパン!
熊の毛むくじゃら男が手を叩いた。
「オーディションに応募したかったら公園に来ること!」
「わ、わかったわ。ウサギの小娘、あんただけには負けないからね!」
「あたいだって、むらさき年増のあんただけには負けないよ!」
ふたりの甲高い声に、周りに人だかりができていた。
「じゃあ、待ってるよ。俺の名前は白りんどうだ」
ビラの束を持った男は名乗った。
「白りんどうですって~~?」
「そんな熊みたいな毛むくじゃらの身体で清楚すぎる名前!」
「誰が熊だって? これでも雅馬のマネージメント担当してるんだが?」
白りんどうが睨みつけた。
第二章 クジ引き
オーディション当日、中央公園には、入りきらないほどの女性が押し寄せた。真ん中から長い長い行列ができて何重にも伸び、噴水の周りを五重くらい回って、やっと列の最後が見つけられるという有様だ。
なにせ、かぐわしい香りが漂い、嗅いだだけで心が安らぐという正座をする美青年、雅馬のアシスタントのオーディションなのだ。
参加者のあまりの多さにパニックになった白りんどうは、顔全体に脂汗をかき、女たちの集団の真ん中でお手上げのバンザイをした。
「皆さん、ひとりずつのオーディションは不可能と判断しましたので、クジ引きします!」
「えええ~~?」
ブーイングのどよめきが湧いた。
(クジ引きだって?)
(せっかくとびきりのおしゃれをしてきたっていうのに)
白りんどうが一本ずつ選ぶクジ引きで、なんと偶然にも小鬼姫とギボシ姫だけが残った。
「また、このウサ耳の小娘! どこまでわちきの邪魔をする気?」
「ムラサキの年増局(としまつぼね)、あんたこそ! 目ざわりったらないわ!」
「ケンカはやめなさいっ」
白りんどうが叫びながら走ってきた。
「募集していたのは二名だから、ちょうどいいんですよ! ふたりに雅馬のマント持ちをやってもらいます」
「このムラサキの年増と?」
「ウサ耳のガキんちょと?」
ふたりは改めてイヤな顔をし、「ふん!」と顔を背けた。
中央公園に集まった女性たちは、がっかりしてぞろぞろと帰っていった。
「さ、ウサ耳さんと紫の年増さん、こっちへ来て」
ふたりは白りんどうに呼ばれて、公園の隅にあるケヤキの大木のところへやってきた。なんともかぐわしい甘い匂いが漂ってきた。
「この香りは……」
「もしかして……」
噴水の向こうから漆黒のマントを頭から被った長身の男がやってきた。歩き方がなんとも言えず優雅だ。
「おお、雅馬さま」
「この者たちか? 私のマント持ちをしてくれるというのは」
なめし皮のような? 滑らかな声だ。
「ものすごい数のおなごたちが集まりましてな、とてもひとりずつオーディションは無理と判断してクジ引きにしたのです」
「ふ……む」
男は優雅な所作で草地の上に正座した。
マントで半分隠れた顔がよく見えないが、小鬼姫とギボシ姫は強い視線を感じた。
「分かった。では今後はよろしく頼むぞ、ふたりのおなご」
雅馬はそれだけ言うと立ち上がり、白りんどうを従えて去っていった。
小鬼姫とギボシ姫はしばらく呆然としていた。
「この甘~~い香り……」
「あの静かな深い声……」
「きゃ~~~~っ! これからこんなにかぐわしい甘い香りの方のマント持ちができるなんて!」
ふたりは初めて手を取りあって喜んだ。
第三章 初興行で
町はずれに、今は石垣だけが残る城跡がある。
その住民の憩いの場で、突如よく通る声が叫ばれた。
「皆さ~~ん、かぐわしい甘い匂いが漂ってくるというウワサの男、雅馬の正座が始まりますよ~~~!」
風が強くてビュービュー耳に響く日だが、その声ははっきり聞こえた。
城跡に遊びに来ていた家族連れやカップルたちは、
「え? 正座するとかぐわしい甘い匂いが漂うって評判の青年が、ここで正座してくれるって?」
「甘い匂いだけでなく、癒されるんですってね」
ざわざわしながら城の二の丸部分に集まってきた。
やがて、城の石の階段を、黒いマントを頭から被った男が昇ってきた。かなり風が強いというのに、しっかりとしたかぐわしい甘い香りが強く漂う。くちなしのような、沈丁花のような蠱惑的(こわくてき)な甘い香りだ。
「なんて甘ったるい匂いだろう」
「毎日のくだらない悩みが溶けてなくなってしまうよ」
老若男女問わず、集まった人々は早くもうっとりしている。
ようやく雅馬は、城跡の草地に敷かれた毛氈の上に立った。両側からふたりの女の子がマントを押さえている。
黒いマントを頭からかぶったままの雅馬が、背筋を伸ばして立ち、ゆっくり毛氈の上に膝をつき、マントの中でかかとの上に座った。
そのとたん、風がいっそう強く渦巻き、なんともいえない甘い香りが辺りに強烈に香った。
「ふ~~ん、いい匂いだねえ。とろけるような」
「なんかさ、心が優しくなれるね」
見物客だけでなく、香りに魅了されたのは、小鬼姫もギボシ姫も同じである。
「こんなに香りが強いと思わなかった……」
「正座したとたんに香り始めたんだよね」
いつものように、もめることさえ忘れて香りに酔った。
自然に雅馬の傍らに正座したくなった。まず、ギボシ姫が、
「正座するからマントを頼むわ。後で交代するから」
そう言ってまっすぐに立ち、雅馬の横に膝をついて、着物をお尻の下に敷いて、かかとの上に座った。
じわっと涙が出てきた。だんだんあふれて止まらなくなった。
「やだわ、この人の香りに包まれると、故郷のおとっつぁん、おっかさんのことを思い出しちまったわ。家出してから何年も経つってのに……」
「鬼の目にも涙ってやつだね」
「おだまりっ! 小鬼はそっちじゃないか、ウサ耳娘!」
怒鳴ってもギボシ姫の声には迫力がない。涙が止まらないのだ。
「ありゃあ、びっくり。ギボシ姐さんを泣き顔にしちゃうなんて、この香り……」
「ウサ耳娘、今度はあんたがお座り。さっきの順序の所作で」
小鬼姫はぎこちなく正座した。とたんに声をあげて、おんおん泣き出した。
「この香りはどうしてこんなに涙腺を刺激するのよ! 元カレのことを思い出しちゃったじゃないよお!」
強い風が吹きつけてきて、マントがめくれそうになったので、ふたりは慌てて押さえつけた。
気がつくと見物客も全員、泣いていた。
第四章 雅馬の決心
癒しの甘い香りを放つ青年の噂は、遠く山々を越えて国々に行き渡り、毎日の正座には、ますますたくさんの人が押し寄せた。
そして連日、青年の正座を見物しては、かぐわしい甘い香りに癒され、涙したり感銘を受けたり、すっきりして帰っていくのだった。人々は感銘を受けたお礼に少しずつお礼の小銭を置いていった。
一か月も続けると、雅馬は大金持ちになった。彼らの寝泊りしているあばら家には、入りきらないほどの金銀の山ができた。小鬼姫もギボシ姫も驚いて、喜ぶやら恐ろしがるやら。
ほくほく顔なのは、白りんどうだ。
「よくやった! 雅馬! こんなに大成功するとは思わなかったぜ! お前の面倒を見てやった甲斐があったよ」
(そういえば、白りんどうとはどうやって知り合ったんだっけ?)
雅馬は、ハタと考えた。
(ある日、あの方の正座の稽古をサボって破門になってしまい、ガマの姿に変えられて、ひとりぼっちで途方に暮れていると、香りにつられてやってきたんだったな)
(そして、ひと儲けしようと持ちかけられて)
「なあ、白りんどう」
金銀の山に埋もれて浮かれている白りんどうに、雅馬は改めて言い出した。
「元の人間の姿に戻っても、外見と香りに寄ってくる人々ばかりなのではないだろうか? もっと人間性のにじみ出る正座ができる人間にならなければ恥ずかしいんじゃないだろうか?」
「何を言い出すんだ、雅馬。外見と香り! 上等じゃねえか。何を辛気くせえことを言い出すんだ。外見と香りがあれば最強の武器だ。このまま続けてればいいんだよ」
「お客さんたちの感激の涙を見ただろう。山分けする約束だったが、俺は金は要らない。全部あんたに渡す。このガマの姿のまま正座の修行をする」
「本気か、雅馬? 俺がこの儲け、全部もらっていいのか?」
「いいとも。山分けした金を持参して、師匠にお稽古をサボったことを詫びるつもりだったが、考えが変わった。人々の涙に応えられるように正座修行を頑張ることにした」
「その姿のままでか? 元の人間の姿に戻してもらわなくていいのか?」
雅馬はぐっと詰まった。
「う……うむ。頑張ってみる」
そんな矢先、いつものように大衆の前で正座をしようとしていると、長雨の季節が去る前にやってくる直前、突風が襲った。
黒いマントは、ふたりの娘が押さえる間もなく空へ飛ばされてしまった。
「きゃああ~~!」
小鬼姫が叫んでしまい、ギボシ姫も真っ青になって立ちすくんでしまった。
黒マントが飛んでいき、醜いガマの顔があらわになったのだ。横に広いカスタネットみたいなデカい頭、シワ深い茶色や灰色のまじったヌメヌメとした皮膚、ヨコにスジの入った黒い瞳孔の半眼のまなこ。口は大きくまなこの辺りまで割けている。
ふたりとも逃げ出した。
香りのご利益をいただこうと思っていた人々も、雅馬の姿を見て凍りついた。
「ガマだ!」
「美青年だと思ってたのに巨大ガマだったのか」
「大きな口をして、私たちを飲みこむつもりだったのだろうか」
「おお、怖っ!」
こぞって逃げ出し、やがて誰もいなくなった広場に風に舞い上げられていた黒いマントが落ちてきた。
「雅馬!」
白りんどうが呆然と立っていた。
「お前、香りが無くなってるぞ!」
いつの間にか、人々を魅了した芳しい香りはすっかり感じられなくなっていた。
第五章 絶望
「あの甘い香りの青年の正体は、ガマだったんだって」
話はすぐに広まった。
「それに正体がバレたとたん、感激して泣いてしまう、かぐわしく甘い香りは消えてしまったそうだよ」
「じゃあ、あいつももうダメだね。ガマだったわ、香りはしないわ、では客が集まるはずがない」
「それよりサギだと言って訴えられても仕方ない」
「みんな、あれだけ感動して泣いておきながら?」
「世間てのは、そんなもんだよ」
雅馬の耳にも世間の冷たい風評が流れてきた。
ガマの姿がバレてしまい、香りが消えたからには、誰も相手しないとか。
寝小屋の中に閉じこもっていると、白りんどうがやって来た。
「おい、本当にこのままでいいのか。お師匠さまに儲けの半分を献上して、人間に戻してもらったらどうだ」
「いや――いいのだ。私はやはりガマのまま正座の修行をする」
「頑固だねえ、あんたも」
「甘い匂いがするからって、正座するだけで人様からお金をもらうなんんてことが間違ってたんだ」
ねぐらに山積みになっていた金銀の山は、白りんどうがどこかへ持ち去ってしまい、もう顔を出さなくなった。
小鬼姫もギボシ姫も誰も近寄らなくなった。
「廃業すると言ったんだから、当たり前か……。あのふたりの女の子にお給金も払ってやれなかったな……」
雅馬は、大きくため息をついた。
季節も秋が深まり、板一枚の壁から隙間風が入る。冷えた風が笛のようにヒューヒュー吹き抜け、ひとりきりで小屋にいると寂しさが増してきた。
少し前まで「いい香り」と「美青年のウワサ」でちやほやされていたのだから、心まで冷え冷えとしてきた。
ガーン!
突然、板張りの壁に石が投げつけられた。怒鳴り声が聞こえてくる。
「この詐欺ガマ! 俺たちをだまして巻き上げた金を返せ!」
「そうだそうだ、金を返せ!」
雅馬の香りに惹きつけられていた人々の怒りが爆発したのだ。
雅馬はせんべい布団の中に頭をもぐりこませて震えていた。投石と暴言は何日も続いたが、じっと耐えるしかなかった。
小屋を一歩出ると石を投げつけられるので、食料の補給にも困った。
「ぐるるるる~~」
お腹が鳴ったが必死で耐えた。
くじけそうな気持ちをふり払おうと、正座の稽古に力を入れてみる。しかし、皆の前では気持ちが浮かれていたせいか、軽々とできた正座もガマの下半身では思い通りにできない。
雅馬の膝の上に悔し涙がポトンと落ちた。
長く正座を教えてもらった女性の師匠の言葉が思い出された。
『確かにお前は美しい。しかし、本当の美しさは魂が美しいかどうかです。外側の美しさなんて年老いてしまうか、悪い根性を持つと崩れてしまいますからね』
『それと、大切なのは姿勢の美しさです。本当の美しさはナヨナヨしたものじゃなく、しっかりどっしり確かな姿勢を保つことです。一度、習得するとめったに忘れません。だからちゃんとした正座をできるようになっておくことは大切なのです』
物心つかないうちから雅馬を拾って面倒みてくれた師匠だが、ずっと若く美しいままで、何者なのかは分からないままだ。
第六章 差し入れ
(よし、気を取り直してもう一度、正座の稽古だ)
背筋を伸ばして立ち上がった時、木戸が叩かれた。
「誰だ! 代金を弁償しろと言われてもしないぞ。香りは本物だったんだから。それに、代金はあんたたちが勝手に置いてったものだからな」
雅馬は開き直って言った。
「……あたいだよ。小鬼姫」
扉の向こうから少女の声がした。
雅馬がつっかえ棒を取ると、小柄な少女が包みを持って入ってきた。竹の皮に包んだ大きなおむすびが海苔を着せられてみっつ並んでいる。
「食べておくれ。この前は逃げてしまって悪かったよ」
「これは……」
雅馬は礼を言うのもそこそこに、おむすびにパクつき、無我夢中で頬ばった。
またもや扉を叩く音がして、今度はギボシ姫がポットに味噌汁を入れて持ってきた。
「寒いだろ。温まるよ」
雅馬は、おむすびを喉に詰まらせるたびにガブ飲みした。
全部、ペロリと平らげると気分が落ち着いた。
「ありがとう、小鬼姫、ギボシ姫。これで生きのびることができた。正座の修行を続ける勇気も湧いてきたよ」
「大げさだねえ。……あれ? 声は美しいままなんだね。ガマの『ぐえっ』じゃなくて」
「声が美しい?」
「ああ。聞き惚れちまう青年の声だよ」
第七章 師匠の姿
しばらく正座の稽古は続けられた。
ある満月の夜、寒さが厳しく、月がいつもより綺麗に白く輝いていた。おなじみの模様が見える。ウサギが餅つきをしているという伝説の模様だ。またはガマガエルだという伝説がある。
相変わらず正座の稽古は思うようにいかない。
(あんなに人々を騙してしまって天罰が下ったのだろう。私はきっと醜いガマガエルのまま一生を終えるのだ……)
枯れたススキの隅で頭を抱えていると、琴の音のように涼やかな声が聞こえた。美しいが厳しく響く声だ。
「何を情けない考えをおこしているのです。私がガマの姿にする前のお前の正座は、とても見事でしたよ。香りはお前の持って生まれた不思議なもの。得なもの」
雅馬が顔を上げると師匠が佇んで(たたずんで)いた。髪は高く結い上げ、古代中国の装束のような優雅で透けた薄い青色の着物を着ている。師匠からも甘い香りが漂っている。
師匠は夜空を仰いだ。
「あの月も満ち欠けを繰り返して、つまり再生して元の姿に戻る。ガマもまた冬眠しては醒め、再生をくりかえしている。そなたもきっと再生して人間の姿に帰り、元の素晴らしい正座ができるようになります」
雅馬の胸に、ふと感じることがあった。
「お師匠さま。今、気がつきました。私はこの姿のまま、正座と香りだけで人々の心を癒せればよいのです。そうです! 人間の姿に返れなくてかまわない! 再生するのは正座と香りだけでいいです!」
「雅馬、本当に?」
「はい。以前は、授けてくださった容貌と香りに頼ってしまい、正座の清々しさを人々に伝えられていないのではないか? と悩んでいました。金も要りません」
「雅馬、よくぞ言った。その言葉を私は待っていたのだ。それに、お前には人々が聞きほれる美しい声があるではないか」
師匠の声は感激に震えている。
「正座の稽古に励むがよい。その時こそ……」
微笑む顔が月光に溶けたと思った瞬間、師匠の姿は消えていた。
第八章 稽古の再開
また再び、正座の稽古が始まった。
「はいっ、もっと膝を伸ばしてストレッチ!」
「そんなんじゃ、ずっと『がに股』がなおらないわよ」
雅馬の身体をあちこちから押したり引いたりしているのは、小鬼姫とギボシ姫だ。
「痛い~~~~!」
「何を言ってるの、これしきのことでっ」
「だって、私の足は曲がって固定してるんだよ。無理に伸ばそうとしても痛いだけだ」
「まず、まっすぐにしないと正座できないでしょう? がまん、がまん」
ふたりの娘の特訓を、雅馬は歯を食いしばって耐えた。がんばった甲斐があって少しずつ膝が伸びてきた。
そして、ついに――正座らしき座り方ができるようになった。
「やった―――! 雅馬さま、やったね。どうにか正座できてるよ!」
「ありがとう、ふたりのおかげだ」
雅馬は心をこめて娘たちの手を握った。
「ガマが膝をきれいに曲げて正座してるところを見たら、みんなどう思うかな?」
「後は香りをどうやって取り戻すかだね」
「香りは思いがけないオマケだからな。正座を見てもらうことにするよ」
雅馬は晴れ晴れとした顔で言った。
第九章 感激の涙
「満月の夜に再生」という言葉をお守りに唱えながら、雅馬は復帰第一回めにその日を選び、皆の前で正座を見てもらうことにした。
『お代金はご遠慮いたします』
『ガマの姿ですが、怖がらないでください』
という立札を立てて、町の広場で待った。
「まあっ、この前のガマだよ。香りでごまかして代金をぼったくった(法外な料金を取ること)あのガマだよ。また正座して大もうけしようって企んでいるにちがいないよ」
「厚かましいねえ。今度こそ、警察に突き出してやろう」
広場を覗きに来た人々からは、冷たい言葉と視線が集まってくる。
警察官を呼んできた者までいる。
「ここで勝手に商売してはいかんよ、そこのガマ」
「前に稼いだ金を返せと言いたいくらいだよ、このガマガエル」
雅馬は、辛抱して背すじを伸ばして正座の準備をしていた。
小鬼姫とギボシ姫は、
「皆、あの香りに癒されるって、うっとりしてたクセにねえ」
「ま、ガマの姿を見た時には、わちきらも逃げちまったんだから仕方ないさ」
やがて日が暮れ、山の端から黄色い満月が昇り始めた。
「満月の夜に再生……、満月の夜に再生……」
凜とした声でお守りの言葉をぶつぶつ、つぶやきながら雅馬は着流し姿で娘たちが敷いた毛氈の上に乗った。
背筋をまっすぐ伸ばし、足も伸ばす。
「お、ガマガエルがまっすぐ立ってるじゃないか」
「足までまっすぐだ」
人々は、先日とは違う興味津々さをもって近づいてきた。
雅馬は膝を着き、着流しをお尻の下に敷いて、かかとの上に座った。そしてゆるりと茶色と灰色の混ざった手を膝の上に置いた。
人々は物音ひとつ立てずに見守っていた。
ひときわ明るい月光が雅馬を照らした。
とたんになんとも言えないかぐわしい甘い香りが満ちて、辺りに漂った。
「なんていい香りだ」
「前の時の香りと同じだ。心が癒されるな~~」
皆の瞳には、いつの間にか涙があふれていた。
「いや、香りじゃない……」
ひとりのおかみさんがポツンと言った。
「この感激の涙は、ガマさんが座っている姿に流してるんだよ」
「え?」
「ガマの足ってのは、正座ができるようなつくりじゃないのに、がんばって正座している。それも美しい正座をね」
第十章 暴徒
「そういえば、そうだ!」
「前の時よりも、私は胸が熱くなってるよ。香りのせいでもない。ここまでガマの姿で正座ができるように頑張ったガマさんのやる気にだよ」
おかみさんが手を叩き始めた。周りの皆も、うなずいて涙をふきふき拍手した。
「なんだか、あの正座を見て泣くと、今までの辛かったことや自分の悪かったことまで洗い流されていくようだねえ」
皆が感激の涙を流しているところへ、乱暴そうな男たちが乱入してきた。
「騙されるなっ」
「あのガマ、またしても法外な金もうけを企んでいるに違いない!」
「ねぐらの小屋をこじ開けてみろ、この前もうけた金が山のように貯めてあるはずだ」
「小屋は広場の奥だ。皆、続け――!」
クワや丸太を持った男たちが、小屋めがけて走り出した。
「小鬼姫っ」
「ギボシ姐さんっ」
ふたりの娘は震えて抱き寄せあった。
「ふたりとも、心配することはない。知っての通り、小屋には何もない」
雅馬が正座して眼を閉じたまま、落ち着いた口調で言った。
第十一章 満月の夜に
林の向こうで、メリメリメリ……という板壁をはがされる音、木槌で打ち壊される音が響いた。
「ちっ、小屋には一銭の小銭も残っちゃいない。どこに隠しやがった?」
男たちが戻ってきて、雅馬の胸ぐらをつかんだが、雅馬は毅然とした声で答えた。
「どこにも隠してませんよ。今はありません」
「ありませんだとっ? ふざけやがって、このガマ!」
男のひとりが殴ろうとした時、雅馬の大きな瞳が開かれた。香りがいっそう強くあふれた。
「う……」
男の手が雅馬から離れた。
「俺は何をやってるんだ? 罪もないガマをいじめて……」
急に男の覇気が落ちた。血走っていた眼がおどおどしたものになり、雅馬に加えていた威圧が無くなった。
他の男たちも同じだった。
「そんなに金を返してほしけりゃ、ここにあるよ」
一同が驚いて振り向くと、熊のような白りんどうがリヤカー(荷車)を引いてやってくるところだった。荷台には、ひとかかえもある白い布袋がふたつ乗っている。
「これがこの前のもうけ、全部だ。町のために役立ててもらう」
「白りんどう!」
雅馬が走り寄った。
「お前、自分のものにしたんじゃなかったのか」
「雅馬、俺様を誰だと思ってるんだい」
白りんどうは、毛むくじゃらの手で鼻の下をぐいとすくい上げてどや顔をした。
「誰って……」
「俺は月におわす高貴で小さなヒメアマガエル、カジカ姫さまの家来だ。詐欺まがいで市井(しせい)の人から集めた金を黙っておのれのものになぞしたりせん」
白りんどうはふんぞり返って言った。
リヤカーから二つの大袋を下ろし、中身をちらりと見せた。まちがいなく金銀がザクザク入っている。
「これからこれを役場に持っていく。文句はないな、皆の衆!」
「白りんどう……」
雅馬も呆然としてなりゆきを見守っていた。
「雅馬、黙っていて悪かったな。正座のお師匠さまは、月の姫アマガエルの化身、カジカ姫さまだ」
「ええっ、白りんどう、お前は正座のお師匠さまを知っていたのか」
「俺はカジカ姫さまに頼まれて、破門してしまったお前を見守るように命じられてたのさ」
「ええっ」
「いいなあ、お前。あんな美人に正座を習えたばかりか、気にかけてもらえて……」
雅馬は、はじらうように両手で顔を隠した。
「ちょっと、白りんどうさん、聞き捨てならないじゃないの!」
「そのカジカ姫って私たちより美人なの?」
小鬼姫とギボシ姫が詰め寄った。
「もちろんさ。気品が違わぁ~~な」
「まあああああ~~~!」
ふたりの娘の頭から湯気が立った。
「おや、お嬢さんたち。雅馬がガマガエルでもジェラシーかい?」
「変かい? ガマだろうがヘビだろうが、中身は誠実な雅馬さんだから大好きなんだよ。ね? ギボシ姐さん」
「あ、ああ。もちろんさ。わちきらは、雅馬さんに命を捧げてるのさ。見な。今回も雅馬さんの香りを嗅いだ者は心を癒されて泣いているよ」
さっきまで小屋を壊していた男たちも、心を癒されておいおい泣いていた。
空の月は金色から銀色に変わった。
「雅馬よ、どうします? 今夜はちょうど満月。再生して人間に戻れますよ」
第十二章 カジカ姫
雅馬の背後に煌びやかな衣装を着て、月光を浴びた師匠――カジカ姫が立っていた。
「お師匠。私は――このまま、ガマの姿で地上で正座の修行を続けます。正座さえできれば外見は何でもいいのです」
雅馬は神妙な顔で告げた。
「本当にそれでいいのですか?」
「はい」
「今一度尋ねます。本当にそれでいいのですか?」
「……はい。そう思っています」
「わらわと天と地に別れてもよいと?」
「は?」
カジカ姫は真っ赤になって雅馬をよ~~く見つめ直し、
「わらわは待っていたのです。正座で真に思いやりを悟ったそなたと結ばれるのを」
「お師匠! いえ、カジカ姫さま、そのお覚悟でしたら、この雅馬、命をかけて永遠にお守りします」
雅馬は、ガマがピョンと跳ぶようにカジカ姫のなよやかな身体に抱きついた。
「雅馬……、嬉しいです。月のように永遠に一緒に存在していましょうね」
ふたりはガッシと手を取りあった。
すべてを見ていた小鬼姫とギボシ姫は悲鳴をあげた。
「何よ、これ!」
「私たち、大失恋てわけ?」
月は音もなく雲間をすべりゆき、人間界を見下ろしていた。








