[298]市松模様の苔に正座すれば……
 タイトル:市松模様の苔に正座すれば……
タイトル:市松模様の苔に正座すれば……
掲載日:2023/07/03
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
山寺のまゆらちゃん(孔雀明王)と孔雀のピーちゃんは、最近、庭の整備に大わらわ。ご住職から苔の植え替えを頼まれたのだ。
彼女らを木の枝から見つめる、美しい白と青と茶の混じった孔雀の姿があった。
彼は青花滋(せいかじ)と名乗り、庭の整備の手伝いをする。それでも手が足りず、「庭師募集」とネット広告に出すと、巨体の蘇芳児という男がやって来た。
ご住職と囲碁をしていた万古老の眼がキラリと光る。

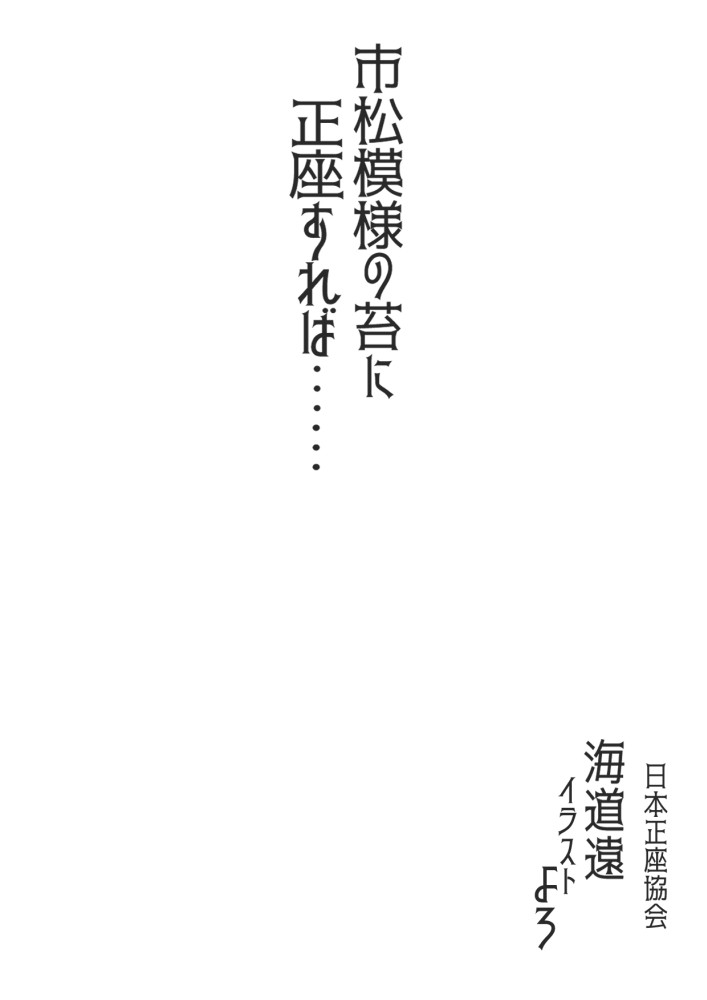
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 青花滋(せいかじ)模様の孔雀
最近、孔雀明王のまゆらちゃんと、孔雀のピーちゃんは庭作りにハマッている。山寺の住職から庭の世話をまかせられたからだ。
「あ~~あ、こんなに外の作業して……。日焼けしちゃうわ!」
不平をもらしながらも、4本の腕をせかせかと動かし、地ならしや苔植えに余念がない。
「まゆらちゃん、ほら、九条家の薫丸(くゆりまる)くんとこのひじきさんに市女笠を借りてきてあげたよ」
孔雀のピーちゃんがクチバシで市女笠を持ってきた。
「まあっ、なんて気が利くピーちゃん! ありがとう!」
まゆらちゃんはさっそく市女笠をかぶって、作業を続けた。孔雀のピーちゃんは普段、孔雀明王を背に乗せる役割なので、ふたりは心がひとつなのだ。
寺の縁側では、正座師匠の万古老とご住職が日向ぼっこをしながら、囲碁の勝負をしている。
「おや、あの鳥は……」
ふと、庭の隅の青もみじの木を見上げた万古老師匠は、枝の上に見たことのない美しい鳥が止まっているのに気がついた。
(なんと例えればよいか……新鮮な緑の葉をつけ、青い小花をあしらった白百合の花束とでも言えばいいのか。いや、それにしても大きい鳥じゃのう。麗しい……)
胸まである白いヒゲを撫でながら、
「おい、ピーちゃん! あの鳥は、おぬしの仲間じゃないかえ?」
「ええ〜〜?」
孔雀明王まゆらちゃんから苔を受け取っていたピーちゃんが、万古老師匠の声に木を見上げた。
その目玉がみるみるデカくなって、足で掴んでいた苔のカタマリを落としてしまった!
(あいつは……、青花滋(せいかじ)の羽根の……)
まゆらちゃんが、
「はい、これ。次の苔よ」
心ここにあらずのピーちゃんは、苔のカタマリを落としたことにも気がつかない。
「どうしたのよ、ピーちゃん!」
ピーちゃんの視線を追ったまゆらちゃんは、枝の上の、極楽にいそうな派手な鳥を見て、固まってしまった。
(なんて美しい……鳥というより大輪の花……?)
枝の上から、まゆらちゃんとピーちゃんを眺めていた美しい鳥もまた、大きくため息をついた。
(孔雀明王まゆら様……、相変わらずお美しい……)
「ピーちゃんよ、あの鳥は孔雀でないかい?」
囲碁の手を止めて、ご住職が言った。
「違いますよ。ボクは知りません!」
「まあ〜〜! なんて美しい孔雀かしら」
まゆらちゃんも思わず声を上げた。
「まゆらちゃん、そんな鳥、放っておいて。庭仕事を頑張ろうよ」
「そ、そうね」
(また、まゆらちゃんの惚れっぽい腹の虫が騒がないように)
まゆらちゃんの反応に気づいたピーちゃんは、すっかり警戒体制にはいっている。
「ご住職、市松模様の庭と囲碁盤とは、よく似ていますなあ」
「そう言えばそうですな。あはは……」
ご住職は、お茶をひと口飲んで改めて碁盤に目をやった。長年やりたかった苔の植え替えを、まゆらちゃんたちにやってもらっているが、ご住職の見立てでは人手が足りない。
「人手を募集するか」
昨日、ピーちゃんがネットに「庭師募集」の広告を出した。
第二章 市松模様の庭
極楽にいそうな白と瑠璃色の鳥が、庭にバサバサと羽ばたいて木の枝から降りてきた。
まゆらちゃんは、あまりの白の眩しさに羽根から光がこぼれたような気がした。
「やあ、綺麗な市松模様のお庭だなあ。緑の苔が目に沁みるよ」
突然、見知らぬ鳥に褒められ、まゆらちゃんは照れた。
「ありがとう、褒めてくれて。あなたは誰?」
「お嬢さん、ボクは青花滋(せいかじ)といいます。一度、本堂で青い孔雀に背負われてらっしゃるお姿を拝見しました」
「あら、そうだったの」
「このお寺では、正座のお稽古もされてますよね」
「ええ、そうよ」
青花滋と名乗った孔雀は、庭をぐるりと見回した。
「お見事な市松模様ですね! 正座のお稽古に使えますね」
「え?」
「みんな四角でしょう。正座にぴったりだ!」
万古老師匠が、いきなり立ち上がった。
その姿は白いヒゲが消え、藍色の長めの髪、敷居で頭を打ちそうな身長の若い青年の姿に変わっていた。万古師匠は若い時と現在と自在に姿を変えられるのだ。
「――藍ちゃん―――藍万古!」
まゆらちゃんが、思わず庭に立ち上がった。
「ね、いい考えでしょう、正座の師匠さん」
美しい鳥がにっこりして藍万古に言った。
「た、確かに! お弟子さんたちに、ひとりずつ市松模様の中に座っていただければ、美しい景色になる!」
「苔と苔の間の砂地に、朱い毛氈を敷いて正座していただいても、美しいと思いますよ」
「確かに!」
藍万古は目をいきいきさせて、苔の上や間の砂地に、お弟子さんが座る姿を想像した。
「全員が庭に座れば壮観でしょうな」
ご住職が目を細めた。
青花滋くんはさっそく、檀家(だんか)に声をかけて回り、市松模様の庭で正座のお稽古を企画した。
「ここってまるで、最初から正座道場のために作られたデザインじゃないか!」
思わぬひらめきに、藍万古とご住職から褒められる。
第三章 新しい庭師
「庭師募集」を見たと行って、蘇芳色(濃い赤)の衣の巨漢(きょかん)が訪れた。貌(かお)つきが勇ましく、身体の大きさといい腕やスネの太さといい、仁王様のような逞しさだ。
「蘇芳児(すおうじ)」と名乗った。
「蘇芳児とな?」
ご住職は、怪訝そうに男を見つめた。
「蘇芳とは、どういう意味ですの?」
まゆらちゃんが尋ねた藍万古の答えは、
「濃い赤色のことだ。血の色にも例えられる」
だった。
蘇芳児は怪力を発揮して、庭に大きな石をいくつも置き、市松模様の庭に苔を全て植え付けてしまった。青花くんを凌ぐほどの庭師の腕を買われて、採用されることになった。
ところで山寺には、林の奥に古井戸があった。井戸の底には蘇芳色の蝶の巣窟(そうくつ)があると言い伝えがあるが、誰も見た者はいない。
蘇芳児という巨漢は、
「ちょいと井戸を調べて進ぜる」
と言って、ずんずん暗い森の中の井戸まで行き、巨体に縄を巻き付け、井戸の中へ下りていった。
「お〜い、大丈夫か?」
井戸の縁から青花滋くんが叫んだ。暗闇に声が幾重にも反響する。
しばらくすると、鳩ほどの大きさの蘇芳色の翼を持ったものが、大量に井戸から羽ばたいた。
「うわ!」
「きゃ――!」
まゆらちゃんと青花滋くんは思わず叫ぶ。顔を両腕で覆ってしゃがみこんだ。
蘇芳色のものがバサバサして、大量に飛んでいく。
しばらく伏せていた、まゆらちゃんと青花滋くんが、
「な、何? 今のは?」
「巨大な蝶だ。不吉の象徴だ」
青花滋くんが言った。
井戸から戻った蘇芳児は、勇み立った表情で報告した。
「睨んだ通り、井戸の底は蘇芳色の蝶の巣窟になっている」
ご住職が、
「蘇芳児どののお名前と何か関係があるのですか?」
と尋ねると、
「俺は蘇芳色の蝶どもをおびき寄せるために、自分も蘇芳児と名乗ってあの色のマントを着ているのだ」
「ふ〜〜む、おびき寄せるために名前を同じにしたとな?」
ご住職やまゆらちゃんたちは、きょとんとした。
「俺の一族は、さっき井戸から飛び立った蘇芳色の巨大な蝶に襲われて被害をこうむった。だから、敵討ちがしたいのだ」
皆は、目を見張った。
「あの蝶たちは大勢の人間に害を与える。また戻ってくるだろう」
ご住職は敵討ちに反対したが、藍万古がご住職に頭を下げた。
「蘇芳児どのにしてみれば無理もないことです。ご住職もこのまま、あの蝶に庭を明け渡すおつもりはないでしょう?」
「そ、それはそうじゃ。でも、正座の稽古に呼んだ村人たちは?」
「俺が用意するマントを着ていただく」
蘇芳児は答えた。
第四章 苔の上に正座して
補修が終わった苔の庭で、お祝いに正座教室が開催される。
藍万古の指導で村人たちも真面目に稽古するが、用意されていた濃い赤のマントに、少々うろたえていた。
「藍万古さま、何ですか? この赤いマントは」
「所作がやりにくいでしょうが、蚊よけのため、しばらく身につけていただけませんか。宜しくお願いします」
藍万古が進み出て、
「よろしいですか。まず背筋を真っ直ぐに立ち、そうそう、背骨を両方の腰の中央に据えるように」
村人たちはマントさばきに苦労しながら、言われる通りにした。
「その場にひざまずいて」
「緑の綺麗な苔の上にひざまずくのですか? バチが当たりやしませんか?」
「大丈夫です。マントは後ろに流し、衣はお尻の下に敷いて、かかとの上に静かに座る」
村人たちはマントを邪魔そうにあしらいながら、お稽古はどうにか終わった。
ところが、お弟子さんたちが立ち去ろうとした時――、それぞれの苔からブスブスと煙が上がり、蘇芳色の炎が出て燃え上がるではないか。
「うわあ、逃げろ!」
驚く藍万古たち。
青花滋くんとピーちゃんは、桶に水を汲んで上空から水を撒き、まゆらちゃんと藍万古も一生懸命、消火活動をした。
火は鎮火し――、
焼けた苔の後から無数の蘇芳色の蝶が飛び立った。
異様な情景だった。蝶の鱗粉に触れた者は、火傷を負ったり高熱を出したりして寝込んでしまったという。
ご住職と藍万古は、病人の家を一軒ずつ見舞いお詫びに回った。
そんな場所で、とても正座の稽古は続けられない。
「仕方ない、しばらく正座教室は休みだ」
藍万古が諦めようとすると、孔雀のスタイルの青花滋くんがカンムリ毛をピンと立てて、口を開いた。
「いや、市松模様の苔の庭をもっと作り、蝶をおびき寄せるのです」
「何だって?」
一同は驚く。
「蝶たちの長は仲間を繁殖させ、人々を病にして村を乗っ取ろうと企んでいるのでは? 今、駆除しないと被害はもっと広がりますよ。藍万古どの。蘇芳児どのと3人力を合わせて蝶を全滅させましょう」
「待て、青花滋くん。その前に私は蝶の長と話してみたい」
藍万古は藍色の髪をきりりと結わえて言った。
「藍万古師匠、本気ですか!」
「……長の本心を聞いてみたい。何か事情があるのかもしれん」
第五章 蘇芳児の陰謀
藍万古は、森の中の古井戸の底へ降りていった。
底から道が続いていて、しばらく行くと巨大な青銅の扉が行く手をふさいでいた。
「これは……」
錆びてぼろぼろだが青銅の造りで、かなり古い時代のものだ。
きしむ扉をそっと開けると、真っ暗な中、か細い泣き声が聞こえてきた。ほのかに明るい灯をともした岩肌のむき出しになった窪みに、女が崩折れて泣いていた。
「蘇芳色の蝶の女長どのか」
藍万古は女を助け起こした。
「俺は藍万古と申す正座の師匠だ。山寺の庭で正座をしていたら、蝶の大群に襲われて、苔は燃え、人々は病に倒れて困っている。蘇芳色の蝶は人に害を成す存在なのか?」
女は顔を上げた。
「藍万古どのとやら。藍色とは……【真理を見極める力の意】ですね。わらわどもに着せられた容疑を晴らそうと、来てくださったのですね! 神々しい藍色の髪です。あなたさまを信じましょう」
女は背筋を伸ばし、正座に座り直した。
「申し上げます。わらわは蘇芳蝶の女長(おんなおさ)。蘇芳色の蝶が人々を全滅させようとしているというのは、全て蘇芳児の嘘です。蝶を利用しているのは蘇芳児の方。あやつの正体は……」
「正体は?」
「大陸の『殷』(いん)という古代王朝の名前をご存知でしょうか?」
「殷王朝というと、紀元前1700年ほど前に興った(おこった)中国の王朝だな」
女長はうなずいた。
「蘇芳児は、遠い昔……古代中国に君臨した殷王朝の最後の皇帝なのです。あやつの愛用する赤い色は『朱殷』(しゅあん)という血の色。占いに頼る悪政を行い、酒に溺れ、周りの国から反感を買い、謀反を起こされて呆気なく滅亡した王朝です。名は血の色を意味する朱殷……。同じ赤でも私どもの翅(はね)の色『蘇芳』(すおう)色とはまったく別ものなのです」
「そなたの申すことを信じてよい根拠は?」
「わらわどもの祖先は、朱殷の悪政をすべて目撃しておりました。現に、わらわたちが苦手な青銅の扉の中に閉じこめたのは、あやつですから。あやつは証人のわらわどもを抹殺したいのです。信じてください。殷王朝の時代からの記憶を祖先から受け継いでおります」
(確かに、殷王朝は青銅の物をよく作ったと聞いている)
藍万古は考えこんだ。
「どうか、お信じください。先日、朱殷は蝶の翅(はね)の鱗粉に粉の火薬を混ぜて、蝶たちを放ちました。何か良くないことが起こったのではないでしょうか」
女長(おんなおさ)は藍万古の腕をつかんで縋り(すがり)ついた。金や銀の腕輪がしゃらしゃらと音を立てる。
「そのせいで、苔から発火したのか!」
藍万古は合点がいった。
第六章 新鮮な緑
「藍万古師匠、大丈夫ですか?」
青花滋くんが地上から叫ぶ声が聞こえた。
「ああ、俺なら大丈夫だ~~。今、上に上がるぞ~~」
「庭の焦げた苔は、元通りに植え替えましたよ!」
「それは早いね、ご苦労さま」
青花滋くんが縄を引っぱり、藍万古は地上に戻った。井戸の外は新緑の世界で目に沁みるようだ。
地下の蘇芳色に包まれていたから、よけい緑がしたたる世界が美しく見える。
「藍ちゃん! 無事で良かった!」
胸に飛びこんできたのは、まゆらちゃんだ。孔雀の髪飾りが、深い緑で彼女のくっきりした目鼻立ちに映えている。
「あら? 甘い匂いがするわ。それに、この細かいキラキラ光るものは何なの、藍ちゃん」
「ああ、蘇芳蝶の女長の鱗粉だな、これは」
「女長ですって! 鱗粉がくっつくほど接近してたの? 蘇芳蝶の女長って、さぞ美人だったんでしょうね?」
まゆらちゃんは、四本の腕で藍万古の胸ぐらをつかんだ。
「どうして、女長が美人だってわかるんだ?」
「私のアンテナは特別なのよ! やっぱり美人だったのね!」
「まゆら、そんなことより、あの蘇芳児を捕まえなければ、また市松模様の苔を燃やされるかもしれないぞ」
会話を聞きつけて、青花滋くんがやってきた。
藍万古は、蝶の女長から聞いた、古代、殷王朝の話をした。
謀反により滅んだ殷王朝の朱殷という者が、蘇芳児の前世の姿だと。
「――というわけで、蘇芳児と名乗っている巨漢は、本当は朱殷という王で、謀反を起こされて滅亡した過去を知る蘇芳の蝶を滅ぼしたいのだ。蝶の女長がすべて覚えていた」
「何ですって? 蝶の女長の目撃談は信用できるんですかい? 何千年も昔のことでしょう?」
「まあ、俺もトシを聞かれると困るんだがな、青花滋くん」
藍万古が照れ臭そうに小鼻を掻いた。
「紀元前10世紀頃に滅んだ国だ。――ちょうど、俺が生まれた頃かな――」
最後の方は、ぼそぼそと小さな声でつぶやいた。
「つまり、ボクたちは蘇芳児という男によって、蘇芳色の蝶を滅ぼす陰謀に利用されるところだったのですね。危ないところだった。騙されるところだった……」
青花滋くんが拳を握りしめた。藍万古も、
「俺もすんでのところで騙されるところだった」
「せっかく、ボクと青花滋くんが一生懸命、植え直したのに、また燃やされてたまるかい! あの蘇芳児ってヤツ、あくどいよな! 許さないぞ!」
ピーちゃんが、翼をバサバサしながら怒った。
第七章 お詫びの会
本名、朱殷(しゅあん)の蘇芳児が、正体がバレたとも知らず、山寺にやってきた。
「蘇芳の蝶どもを全滅させてやる!」
と、息巻いている。
「あんた、本当は――っ」
顔を見るなり喰ってかかろうとしたピーちゃんを、藍万古は急いで引き止めた。
(ピーちゃん、まだ、ヤツの正体を知ったことはヒミツだ)
ひと月後――、
藍万古たちは、村人たちの体調が回復したのを確認して回り、お詫びのお茶会を開くから来て下さい、と招待する。
「お詫びの」などとご住職や万古老から気を使われたのでは、断わるわけにもいかず、大半の村人が承知した。
さて、「お詫びの会」当日。
前回、正座のお稽古に出席して、蘇芳色の蝶の大群に襲われて、挙げ句、苔から出火して、さんざんな目に遭った村人だったが、「お詫びの会」が開かれるのは、またもや市松模様の苔の庭だった。しかも、苔と苔の間の砂地には、真っ赤な毛氈が敷かれている。緑色と赤のチェッカーフラッグの模様だ。
「ま、また、この庭に座るというのですか!」
「赤と緑にして、クリスマスパーティーでもするつもりですか?」
呆れて怒り出す村人もいる。
藍万古とご住職は縁側から下り、正座して丁重に頭を下げた。
「その節は、皆様に多大なご迷惑をおかけしました」
「庭はこの通り苔を植え替え、焦げた跡は残っておりません。どうぞ、ご安心ください」
「本当か?」
「ワシらの座っていたところから、どうして発火したんだ?」
村人たちから質問が飛ぶ。
「それはまだ、お役人の取り調べ中ですが、危険は無いだろうと見なされました」
「見なされたぁ? そんないい加減な報告が通用するか!」
人々が立ち上がりかけた時、藍万古が、
「鱗粉が発火する危険のある赤い蝶たちは、青銅の箱にすべて閉じ込めました」
「鱗粉が発火する危険? 青銅の箱?」
「はい。蘇芳色の蝶は青銅の箱に入れておくと、冬眠したように大人しくなるのです。大学の生物学師と孔雀の青花滋くんが教えてくれました」
「そんな口から出任せ、誰が信じるかい!」
寺から帰ろうとする村人と押し問答になった。
その時、皆の足元に美しい鳥がひれ伏した。純白と新緑のような緑と空の青が混じった鳥、青花滋くんだ!
「村の方々、信じてください。この寺は孔雀明王さまが長く護られてきた寺。村の方々にウソを申したりいたしません」
「そういうお前はどこの孔雀だね? 見慣れんが」
「私は、孔雀明王さまをお乗せしているピーちゃんの親友で、青花滋と申す孔雀でございます」
「いつから親友になった?」
ピーちゃんが叫んだので、まゆらちゃんが、慌ててクチバシを押さえつけた。
青花滋くんが咳ばらいをして、改めてご住職、藍万古とそろって頭を下げた。
「この通りでございます。私どもに『お詫び』をさせてくださいませ」
村長が庭の傍らをチラリと見た。どうやら、それなりのお膳も用意してあるようだ。
「そこまでおっしゃるなら――」
村人たちが毛氈の上にひとりずつ座りかけた。
「ささ、蘇芳児さん。あんたの分もお膳を用意してあるよ。好きな席に座ってくれ」
ご住職が声をかけると、蘇芳児が酒瓶をぶら下げて、のしのしと歩いてきた。
「この度は蘇芳児さんにもご迷惑をおかけした。存分にやってくだされ」
第八章 宴の途中で
見上げれば、薫風かおる新樹光(しんじゅこう)。
若葉に囲まれた市松模様の庭に敷いてあるのは、新鮮な苔と緋色の毛氈だ。
村長はじめ村人は、だんだん機嫌をなおし、お膳に舌つづみを打ち酒を酌み交わした。
(先日、この庭で大きな蝶が飛び回り、直後に苔から火が上がるなんて妙なことがあったが、今日の青天井の空を見ていると、すべて幻だったに違いない)
(きっとそうだ、幻だ)
(息子は火傷したと言っていたが、治ったらしいし)
(孔雀明王は、いつものようにしなやかな4本の手で皆にお酌してくださるし、ご住職と藍万古師匠もご機嫌だし、あの見慣れない大柄な庭師も黙って酒を飲んでいる)
(叫んでうるさいのは、ピーちゃんと新入りの白みどりの孔雀だけだ)
(こんなにいい天気で料理も美味いのに、いったい何をいがみ合っているんだか)
「踊らないか、皆!」
そこまで村の男衆に酔いが回ったところで――。
――ズシン!
大きな音に、皆が何ごとかと目をやると――、
大柄な庭師が地面に拳を打ちつけて、膳をひっくり返したところだった。
(ひゃあ、いったいどうしたんだ?)
藍万古の鋭い眼が蘇芳児を捉えた。
「おのれ、俺の国を返せ、俺の玉座を返せ!」
どこからか、また蘇芳色の蝶が激しい勢いで飛んできて、庭の人々を襲った。
「うわ~~っ、また、赤い蝶だ!」
村人が逃げようとしたところへ、藍万古が静かに立ち上がり、
「皆さん、落ち着いて」
しかし、恐怖にかられた村人たちは逃げまどう。
蘇芳児が、庭の一角にある松の木を睨んだ。根元に、蘇芳色の衣をまとった女の姿があった。
背すじを真っ直ぐにし、膝をつき、衣をお尻の下に敷いて、かかとの上に座った。
「わらわの名前を返しなさい。蘇芳児」
落ち着きはらった座礼をして、蘇芳色の蝶の女長は言った。
第九章 蘇芳色の蝶の女長
「わらわこそが、蘇芳の蝶の長である。名前をお返しなさい、血塗られた名前の朱殷よ」
「う、うっ、ワシの真の名前をどうして……」
「お前の真の名は朱殷。3000年前に滅亡した殷王朝の最後の皇帝……。お前の彷徨える魂は今も邪悪な沼から抜け出せず、よくもわらわの名前を盗み、蝶たちに悪事を命じたことよ」
「蝶たちに悪事だと?」
「とぼけるでない。鱗粉に病の粉や火薬の粉を混ぜてばらまき、罪なき人々に火傷を負わせたであろう」
「ど、どうしてそれを……」
「藍万古どのが、すべてを解明してくれた。――お前はかつて愚かな所業で国を失った。そのことをよく思い出すがよい。わらわと蝶どもが証人だ。もう、蝶たちをお前に利用させはせぬ」
女長の目が怒気(どき)を帯びた。
バサバサと羽ばたきが聞こえ、蘇芳色の巨大な蝶の群れがやってきた。
朱殷の巨体を取り巻いて飛び、動けなくした。
「うわあ〜〜っ、まさか、報復に火傷を負わせる気か」
「朱殷よ、こちらにおいでなさい」
女長が、とりわけ新鮮な苔の上に呼んだ。
「鱗粉をつけて病にするつもりか、それとも発火させて焼くつもりか」
朱殷の気持ちとは逆に、巨体はひとりでに苔に近づいていくではないか。
「う……うわ……」
逆らっても蝶に誘われるように、朱殷は苔の上にひざまずいていた。衣に手を添えてお尻の下に敷き、かかとの上に座る。
「やっぱり、俺に復讐する気だな」
次の瞬間、朱殷の周囲から真っ赤な炎が燃え上がった。
「うわ~~~っ!」
朱殷の絶叫が響いた。
「熱い…… 熱い……。手も足も。焼かないで、焼かないでくれえっ」
情けない叫びをあげながら、巨体の男はその場に伏せた。
「許してくれ、許してくれ。占いの政治ばかりを行い、民から膨大な穀物を取り立て、多くの臣下を粛清(しゅくせい)した。すべては朕が愚かだったゆえだ! 反省しておる!」
伏せたまま、しばらく時が過ぎ――、
朱殷は、そっと目を開けた。
周りで燃え盛っていた炎は消え去り、女長と藍万古が目の前に立っているだけだ。
「朱殷よ、恐れてばかりいないで、この新しい若葉や青い空を見上げてみよ」
女長が言った。
「俺は……焼かれたはず。蘇芳色の蝶はどこへ行った?」
「俺とはなんです? 仮にも殷王朝の最後の皇帝陛下だったのですよ。言葉遣いから直さなければ、残忍な性根が改まらないようですね」
「ち、朕(ちん)と申せばよいのだろう」
朱殷は自分の両手を見た。火傷はない。蝶の鱗粉もない。
「朱殷よ、お前の見た炎は幻だ。お前の罪深さが見せた幻影だったのだ。見上げてみよ。日本の国の初夏の青空を。お前のどす黒い野望を洗い浄めてくれる『青』であろう」
藍万古が言った。続けて女長が、
「名前を返してもらったかぎり、乱暴はせぬ。お前の魂は常世の国にあるのだから」
「えっ」
「いい加減に支配欲など捨て、大人しく常世の国で眠るがよい」
恐れおののく表情のまま、朱殷は、初夏の薫風に吹き消された。
第十章 火焔蝶(かえんちょう)の長
藍万古は女長に向き直った。
「女長どの。古井戸の中で初めてお会いした時、あなたが美しい正座で座礼してくれた。見知らぬ者に頭を下げられる、あなたこそ勝利の女神だと確信したのです。朱殷の撃退に力を貸していただき、ありがとうございました」
「いえいえ、わらわの可愛い蝶たちのためですもの。こちらこそ、名前を取り返すことができました。ありがとう、藍万古」
女長は森へきびすを返しかけたが、振り返り、
「わらわは、二度と悪い考えの者に可愛い蝶たちを思い通りにさせないために、これを機に力強い名前に改めようと思います。『蘇芳』という名前は捨てて、『火焔蝶の長』と名乗ります」
「火焔蝶……これはまた、激しく勇ましいお名前ですな」
藍万古が見送り、火焔蝶の長は森の井戸へ飛び立った。広げられた翅(はね)はまさしく清らかな、悪を焼き滅ぼす「朱」の色だった。
村人たちが市松模様の庭で酒を酌み交わし、料理に舌鼓を打っていた。
「一同には何も見えず、覚えていません。良かったですね、藍万古どの」
青花滋が言った。
「私には全部、見えてたわよ!」
まゆらちゃんの眉がつり上がっている。
「蝶の女神さまは美しい方だったわね!」
「そうかのう、いくらお美しくても、ワシにはもう応えられる精力がありはせぬ……」
藍万古は、背を丸めて白いヒゲを垂らした万古老の姿に戻っていた。
「藍ちゃんたら! ズルいわよ!」
青花滋くんがご住職の前に正座し、
「お願いがあります。どうか、ボクをしばらくピーちゃんの代わりに、まゆらさまをお乗せする役割をお与えください」
「なんだってええ~~~!」
ピーちゃんの冠毛が逆立った。
「まあまあ、囲碁の勝ち負けで順番を決めてはどうじゃな?」
ご住職が目を細めて言った。
「囲碁なんて知らないもん! 何のゲームで決める? 青花滋!」
「そうだなあ、いっそ、市松模様ゲーム作るかい?」
ふたりとも、やる気満々である。








