[139]第17話 正座の歴史は浅い?
発行日:2010/4/13
タイトル:第17話 正座の歴史は浅い?
シリーズ名:やさしい正座入門学
シリーズ番号:17
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
販売価格:100円
著者:そうな
イラスト:あんやす
金澤暁夫
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/3177733
本文
 ――利休はアグラをかいていた――
――利休はアグラをかいていた――
いきなりの発言である。これは本書からの抜粋であり、今回の話の中心となるといえるだろう。「正座」といえば、「日本の伝統」と続くように、「茶道」と聞けば、おそらく「正座」を連想するだろう。それはあながち間違いではないのだ。今の時代では、それも作法の一つであるから。そう、今の時代だから……これこそが、この固定観念の許される解釈なのである。
では、それはどうしてだろうか。今や茶道に正座は欠かせない。現に、この著者も冒頭でこう書いていた。「正座をしないでお茶を飲むなんて考えられない」、「和服ではアグラはかけない」と、患者さんに言われたと。しかし、著者はその常識を疑問に思い、こういう。「利休はアグラをかいていた」と。その根拠は何か、その著者の考え方をここで紹介させて頂きたい。
著者は冒頭で、次のように記している。「お茶にしてもお花にしても、あるいは書にしても、それらは昔から正座をして行っていると信じられています。とりわけ茶道。正座は茶道によって始められ、広められたという説があります」。そして、こう言い切る。「まず、私は『始められた』という説に異を唱えたい」。それはなぜか。この後かみ砕いて説明していこうと思う。
 まず、千利休といえば「茶道の人」ということで有名であると思う。近年でも日本の役者が扮する千利休が某CMに出ていることから、やはり結構な知名度であるように思える。しかし残念ながら、その千利休は画面で見る限りは座していたのだが、ちょうど名前のテロップが足元にかかっていたため、正座をしているかは分からなかった。ピンと伸びた姿勢から推測すると、アグラより正座の方が確率は高いのだが。他にも、本格時代劇などでも利休等が正座をして茶を飲んでいる場面が見られたと思う。とまぁ、正座の代名詞にしてもいいくらいのお茶の人、利休であるが、著書を読んでいくと茶道と正座の意外なことが分かる。
まず、千利休といえば「茶道の人」ということで有名であると思う。近年でも日本の役者が扮する千利休が某CMに出ていることから、やはり結構な知名度であるように思える。しかし残念ながら、その千利休は画面で見る限りは座していたのだが、ちょうど名前のテロップが足元にかかっていたため、正座をしているかは分からなかった。ピンと伸びた姿勢から推測すると、アグラより正座の方が確率は高いのだが。他にも、本格時代劇などでも利休等が正座をして茶を飲んでいる場面が見られたと思う。とまぁ、正座の代名詞にしてもいいくらいのお茶の人、利休であるが、著書を読んでいくと茶道と正座の意外なことが分かる。
長谷川等伯(はせがわとうはく)という人が、当時の利休の肖像画を描いている。これが一番有名で、その名も『利休居士像(りきゅうこじぞう)』である。利休とも直接交流をもっていたといわれる画家が描いたその利休の絵は、なんとアグラをかいているのだ。それだけではない。更に、江戸時代に彫られたといわれる利休の座像(木像)もあり、それもまたアグラをかいているという。
しかし、千家三代目である千宗旦(せんのそうたん)が描いたとされる千利休画像の利休も、著者は正座をしているように見えるのだそうだ。だが、著者はそれを「この肖像画は利休の没後、ある一定の期間を経て、孫の代に描かれているので、後世の作の可能性もあります」と説明している。また、当の千宗旦自身の肖像画も残されており、その絵は明らかにアグラをかいているのだそうだ。著者は記す。「茶道といえば、正座で行うことが、今では常識です。しかし、少なくとも利休や宗旦は、そのようなことを説いてはいなかったと私は考えます」。
どういうことなのか。まるで茶を広めた千利休がアグラをかいたり、かかなかったりと決まりもなく茶道をしているようにとれる気もする。しかし、元来の茶人そのものが正座をしていなかったとしたら、茶礼に正座を必要としていなかったとしたら……それは現代の「ある種の正座の常識」を破ることになる。
著者はこう考察している。「茶人は正座をしていなかった」。なんと、これは事である。「茶事といえば正座で行う」と認識してしまう現代人の固定観念をどうしてくれよう。そもそもお茶というものは、本来漢方薬として平安時代に遣唐使によって日本にもたらされたものである。しかし、それは根付くことはなく廃れてしまうそうだ。渋かったからだろうか。なにか臭かったのだろうか。変な想像が捗ってしまう。
その後、鎌倉時代になり、栄西(えいさい)によって禅宗とともに抹茶が伝えられる。著者は、その栄西の書いた『喫茶養生記』に、「茶は末代養生の仙薬なり、人倫延命の妙薬なり」と記されていることから、栄西は茶を長寿の薬と考えていたと判断しているようである。
更に、室町時代になると、酒と共に茶を飲んだり、飲んだ茶の銘柄を当てたりする一種の遊戯ともいえる闘茶(とうちゃ)が、一部の人たちの間で流行ったという。著者は、「このころには、今に続く茶道の精神性は微塵も感じられません」と記している。どうやら、現代の礼法等のお茶の感覚とは全く違うようだ。つまり、お茶が日本にきてから、すぐに茶道というものができたわけではなく、しばらくは高級な品として貴族たちの飲み物になっていたということが、私たちにも想像できると思う。「人倫延命」ということからも、殿様などは、ことあるごとに飲んでいたのではないだろうか。
そんな中、今までの茶会や飲酒を禁止し、茶会の精神性を重視し始める人物が現れる。村田珠光(むらたじゅこう)という人物である。この珠光について、著者はこう説明している。「珠光は、室町幕府八代将軍・足利義政に茶の湯を指南し、同時に『とんちの一休さん』で知られる一休宗純(いっきゅうそうじゅん)に参禅し、茶禅一味の境地を開いたともいわれます。わび茶を創始した珠光は、今日まで茶道の開祖といわれています」。
時代をたどれば分かる通り、この人物は、千利休よりも昔の人である。つまり、今でこそ千利休はお茶の代名詞のようなものだが、それより前に茶道を始めた人や確立した人がいたということだ。確かに、昔受けた学校の歴史の授業でも「千利休は茶の湯を広めた」としか習っていなかった気がする。
そして、その茶道の開祖といわれた珠光の孫弟子に、武野紹鴎(たけのじょうおう)という人物がいるのだが、この人の肖像画もまたアグラをかいているのだそうだ。ちなみにこの人は、わびの境地を確立した人なのだとか。
お師匠様の意向をついで、孫弟子がわびの境地を確立する。このような理想的な受け継ぎ方をした彼らには、何かステキなドラマが沢山ありそうで気になるところだ。似たようなセンスの持ち主は、そうそう現れるものではないからだ。ちなみにこの武野紹鴎という人は、利休と同じ堺の生まれで利休の師に当たるという。ここで利休がつながってくる。
ここまで利休とその師匠の代の様子を見てきたが、では、その後はどうなっていったのだろうか。つまり、利休の弟子の代である。それについて、著者は次のように記している。
「千利休の愛弟子であった細川三斎(ほそかわさんさい)の伝書『細川茶湯之書』には、『客が安座してくつろいでいる時は、主人は片膝を立てていた』と、安居香山氏の著書『正座の文化』には記されています」とある。おっと、アグラの次は片膝立ちのようなものがでてきた。どんどん座り方が進化していっているのかと思いきや、客がくつろいでいるとき(アグラもしくはそれに限らず、ゆったりとした姿勢でいる時)限定のようなので、もしかしたら気の置けない仲の相手に対する時だけしていたのかもしれない。どちらにせよ今のところは明確な情報がないので、そこのところは分からないが、堅苦しく厳かに行われていたワケではないことが分かる。涼やかに爽やかに、時にはサロンのように茶の湯を楽しんでいたのだろうかと推測する。
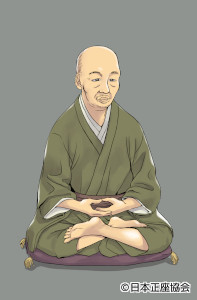
そして時代を更に下ると、川上不白(かわかみふはく)という人物が出てくるのだ。この人物の紹介をしたいと思う。利休と直接の関係があったのかは記載されてはいないが、彼は表三家中興の祖といわれる七世如心斎の命を受けて、江戸で茶道を広めた人物である。それと同時に、茶道の流儀も創始した人物だ。
つまり、千利休を基準にして考えると「利休以前には茶道の流儀はなかった」ということになる。著者はその人物の正座の有無についてこう語っている。「川上不白の木像が残されていて、座り方を見ると、アグラか半跏趺坐(はんかふざ)のいずれかで、正座はしていません」。この半跏趺坐というのは結跏趺坐(けっかふざ)の略式で、両足の甲をそれぞれ反対のももの上にのせて押さえる形の座り方である。(いわゆる仏の座法なので、現代の生活の中で行う人は少ないと思う)この資料からも、茶の伝道師が正座をしていなかったということが分かってくると思う。
そして、著者は決定的な事実を見つけている。「この川上不白という人物は、1716年の生まれで、1807年に亡くなっていますから、江戸中期から後期にかけての人物です。ということは、この木像は江戸中後期を生きた茶道の流祖が正座をしていないことを表す決定的な資料といってよいでしょう」
そして、今日の茶道と正座をワンセットとして考えているその思考にメスを入れる。「これらを総合して考えると、寺院の儀礼的な飲茶茶礼から亭主と客が心を通わせる茶の湯、更には精神性を高めた茶道へと発展する過程に、正座は全く関与していなかったといえそうです。少なくとも江戸時代後期までは正座と茶道を結びつけるものはないと考えるのが妥当です。また、茶会における座り方は明治時代になるまで自由だったと、多くの専門家が指摘しています」。こ、これは……「正座が全く関与していない」というのも衝撃の事実である……。
さて、ここまで話しを進めてきて、正座と茶道の精神性を含める関連性が、昔と今ではかなり異なることが分かってきた。そこで、疑問が出てこないだろうか。「じゃあ、礼法でも道でもないのなら、昔の茶道は一体なんだったの?」こんな感じだろうか。それについては、著者が次のように語っている。「茶の湯は命がけ」だと。なんという恐ろしい言葉だろう。それを聞いた私の脳内では、こんなことになっていた。
 まさにバトルである。発言する言葉によって嫌い嫌われることはおろか、下手をしたら一触即発の命がけの茶の湯だ! 「まぁまぁ茶でも飲みなされ。」と勧めつつ、内心「この茶を通して何を仕掛けてやろうか。いっそマゲに直接かけてやろうか。」等と考え、もらう方も「ありがとうございます。」等と爽やかに受け答えをしたものの「一体どんな変化球がくるのだろうか、ええい、もう来るならきやがれぃ!」とピリピリしているのだ。……とまぁ、この言葉だけを聞いているとこの様な素っ頓狂な考えが浮かんでしまうものだが、内容を知ってみれば、そこには人対人のかけひきのようなものが存在していた。
まさにバトルである。発言する言葉によって嫌い嫌われることはおろか、下手をしたら一触即発の命がけの茶の湯だ! 「まぁまぁ茶でも飲みなされ。」と勧めつつ、内心「この茶を通して何を仕掛けてやろうか。いっそマゲに直接かけてやろうか。」等と考え、もらう方も「ありがとうございます。」等と爽やかに受け答えをしたものの「一体どんな変化球がくるのだろうか、ええい、もう来るならきやがれぃ!」とピリピリしているのだ。……とまぁ、この言葉だけを聞いているとこの様な素っ頓狂な考えが浮かんでしまうものだが、内容を知ってみれば、そこには人対人のかけひきのようなものが存在していた。
著者はこう記している。「出陣の前に茶会を催して、狭い空間で互いに茶を飲み、相手の心を察する。本当に我が将のために命がけで働くのか、それとも寝返って、刃を向けてくるのか。その本心を読み取るのが茶席だった。これには、一対一で相対することが理想的です」。
この時代は戦国の世であり、下克上も頻繁に起こる状況にあった。戦闘方法や移動方法、情報量も異なる時代での裏切りは致命的だっただろう。中には、一人の寝返りが自軍を窮地へと追い込み、一人の密告が勝敗を左右したこともあったのではないだろうか。一人ではなく数人だったかもしれないが。
そのような人たちを相手に、茶人は狭い茶室で一対一、つまり面接をするのだ。そして、時に裏切り者やスパイを見つけ出し、時に心が揺れているものを懐柔し、時に勇ましい者には更なる褒美をチラつかせたりしたのだろう。まるで戦場のカウンセラーのようだ。著者はその時の武将の様子を、次のように記している。「織田信長をはじめとした武将たちは、大枚をはたいてまで、民間人にすぎない茶の湯の師匠を奪い合いました。有能な茶の湯の師匠は、茶席で武将の心の揺れを読み取る能力を持っています」。
 ここまで見てきたが、なるほど……お茶はのうのうと伝わってきたのだと漠然と思っていたが、時代は戦国時代、お茶も人と共に時代をかけ巡ってきたワケだ。また著者は、「織田信長や豊臣秀吉は実利一点張りの合理主義者です。彼らにわびやさびが通じるはずありません」と語っている。確かに……そう考えてみると、茶人を競って奪い合ったのは、茶を飲むためというよりも戦争に使うためと考えた方が、合点がいきそうだ。そんな織田信長の茶頭となり、天下取りを支えたのが、千利休であった。だからこそ、千利休の知名度が増したのかもしれない。あくまでも知名度の要因の一つだろうとは思うが。
ここまで見てきたが、なるほど……お茶はのうのうと伝わってきたのだと漠然と思っていたが、時代は戦国時代、お茶も人と共に時代をかけ巡ってきたワケだ。また著者は、「織田信長や豊臣秀吉は実利一点張りの合理主義者です。彼らにわびやさびが通じるはずありません」と語っている。確かに……そう考えてみると、茶人を競って奪い合ったのは、茶を飲むためというよりも戦争に使うためと考えた方が、合点がいきそうだ。そんな織田信長の茶頭となり、天下取りを支えたのが、千利休であった。だからこそ、千利休の知名度が増したのかもしれない。あくまでも知名度の要因の一つだろうとは思うが。
加えて、茶室での姿勢について著者はこういっている。「適度な緊張感と緩みを併せ持つには、アグラなどのほうが適していたのではないでしょうか。茶人に相対する武将はなおさら正座などしないでしょう」この説明、全くもってその通りだと思った。
ここまでの全てを総じて見ると、平安~江戸時代の茶道に正座が常識だったという可能性は、とても低いということが伺える。江戸時代は、なんだかんだ何百年か前の出来事であるから、そこに正座が文化として根付いていないならば、正座がほぼ必須である現代の茶道の文化はまだ浅いものとなる。深く調べてみれば、存外意外な事実が出てくるものだ。
この著者は、正座で膝を傷めた人たちを沢山診てきたからこそ、そこまでして正座を頑なに守る人たちに、他の道もある(あった)ことを提案したいのだろう。好きで行うのならまだしも、「伝統」だから「礼儀」だからと、「こうしなくちゃいけない」という義務感で行う人に、アドバイス、あるいは物申したいのだと思う。「これがお茶のマナーだから」と言っては、膝を痛める……型にはまりきって義務感の檻に囚われることは、お勧めできないということなのだろう。
私も概ね同意だが、しかし反対にこうも思える。そこまでして頑なに守り続ける「正座」という姿勢には、何か理屈等では言い表せぬ強い魅力があるのかもしれない、と。だからこそ「道」の基本には、いつも正座が潜んでいるのだろう。冒頭の患者も含め、茶道を行う人の精神も、正座を始め礼儀を重んじることにより、きっと武道と同じように研ぎ澄まされているのだろう。
次の回では、「武士と正座」について語りたい。







