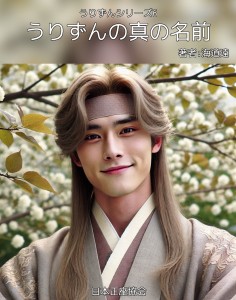[61]正座の入門
 タイトル:正座の入門
タイトル:正座の入門
発売日:2019/08/01
シリーズ名:某学校シリーズ
シリーズ番号:1
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:虹海 美野
イラスト:時雨エイプリル
内容
直は男子高校生。
元女子校のおっとりした校風から学校を決めたけれど、クラスの女子は男子に厳しい態度で居心地が悪い。
高校生になっても家族に対して素直で優しい直への当たりの強い女子、キリが特に苦手だけれど、お作法の授業で正座をした後にキリが足を痺れさせた時、直が正座の仕方を教えたことで少しだけ距離は縮まった。
学校では体育祭を控えていて、苦手な騎馬戦を前に戦々恐々とする直にキリがアドバイスをしてくれ……。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1484853


本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
某私立高校には広い和室があり、ここでお作法、お茶、お花を全生徒が学んでいる。品のある制服を着た男女が正座をし、日本文化を学ぶ様子は学校見学者からも評判がよく、また、学校行事に真剣に取り組みつつもお互いを思いやる生徒の姿勢も学校内の生徒、保護者からは高評価である。しかし、何事にも入門があるように、この理想的な図ができあがるまでには、小規模、且つ個人的ではあるが、当人にとってはそれなりの成長を伴っての努力の結果でもあった。
香賀見直は、今年某私立高校に入学した男子高校生だ。直の入学した高校は五年前まで女子校だった。良妻賢母を育成することを教育目標に掲げ、良家の子女が通うことで有名だった。大学、短大の附属高校で、進学もエスカレーター式に上がれることも大きな魅力だと言われていた。しかし、昨今の国公立大学への受験需要の高まりを受け、とうとうこの有名女子高も大きな改革に乗り出した。男女共学、国公立大学受験対策授業が打ち出された。
改革直後、この高校がどのような状態だったか直は知らないが、昨年学校見学に訪れた際には、ごくごく普通の男女共学校という印象だった。私立高校の学校見学は、結構中学生への至れり尽くせりのおもてなしをしてくれるところがあり、この高校でも夏休みの予約制一日体験では午前中の外国人の先生による英語の授業や、パソコンを使用した授業、物理の実験の授業を体験し、学食でデザート付のランチをいただき、午後は希望者への部活体験も盛り込まれていた。
女子校から男女共学になった学校だが、男子トイレから更衣室まで整備されていて、生活面での心配は皆無だった。
ただいかんせん、良家の子女が通う学校であったが故に、学食の椅子やテーブル、内装に至るまで、そこかしこに優雅さが漂い、ほかの高校とは少し雰囲気が違った。先生方も楚々としていて、すれ違う際の目礼もどこか上流階級を思わせる所作が感じ取れる。
在校生は制服をきちんと着こなし、さわやかに挨拶をしてくれる。男子は白いワイシャツに濃紺のニットのベスト、グレイのズボンで、女子は白いワイシャツにピンクのリボンに濃紺のニットのベスト、グレイにピンクの入ったチェックスカートという制服で、誰もシャツをはみ出させたり、私服を制服に合わせたりしていなかった。
学食をいただいた食堂はとても広く、説明によると高校の間はこの食堂で全員で給食だということだった。食事も大切な教育の一環で食育とともに、お作法やお茶、お花も日々学んでいきます、という説明があった。お作法、お茶、お花はもともと女子校時代からこの学校教育の特色のひとつだったらしく、それは共学になっても引き継がれている、とのことだった。
直は特にそうしたことに疑問を持たなかったが、見学に来ている男子の中には顔をひきつらせている生徒もいた。「和室で正座して授業とか、無理だよな」と言い合う小声も聞こえてきた。お作法などの和室での授業については、もともと学校案内のパンフレットにも写真入りで紹介されていたし、学校説明会でもふれていた。一緒に説明会に行った直の母は「正座は大丈夫ね」と直に訊き、直が頷くことでその件は了解ということになっている。特にこだわりはない。それに学校でお花やお茶など学ぶ機会でもなければ、この先習うことはないと思う。母は「いい機会じゃない」と、上の兄二人にも学んでほしかったわとつけ加えた。
この高校は取りあえずで受験するというよりも、学校の特色を知った上で選ぶところだと直は思い、自分にとっては「ここだ」という気がした。
直には、正座で学ぶお花やお茶、お作法をはじめ、正しく着る制服やみんなでいただく給食は、堅苦しいという印象がなく、好ましいという感想が大きかった。
2
入試の際には午前中の筆記試験の後に、昼食を挟んで面接が行われた。志望動機や中学校で頑張ったことや高校生活での目標を訊かれ、中学校で練習したように答えられてほっとしたところで、面接の先生は柔和な笑顔を作り、最後に「正座をする授業もありますが、大丈夫ですか」と尋ねた。直は大きく頷き、「はい、とても楽しみにしています」と答えた。翌日にはインターネットで合格が確認できた。
この時期にはスポーツ推薦をはじめ、私立単願の生徒は進路が決定する。そこかしこで、「高校も同じだね」とか「よろしく」という会話が聞こえてきた。そして都立高校の合格発表後には、都立を受けたが第二志望の私立になった生徒が決定し、誰と誰がどこそこの高校へ行く、という話題があちこちで繰り広げられた。そんな中、実は直だけが同じ高校にいく同級生がいなかった。元女子校、給食、特色ある教育環境、そういったものがネックになったのだろうか……。男子の同級生がひとりもいなかった点は、私立を選択する中でもスポーツに力を入れている学校を選ぶなどあることも含めて仕方がない気もするが、女子すらひとりもあの高校を選んでいなかったのは、たまたまの結果であっても、心もとない。
卒業式も、卒業を祝う会も、新たな高校で一緒に行動を供にする約束を交わす同級生の中、直だけはそうした会話とは無縁だった。
そしてあっという間に四月になった。
僕だけが一人だったらどうしようという不安を抱きつつ、直は入学式前に母親と別れ、教室に入った。
入口から飛び出して来た男子にぶつかりそうになったが、「ごめん、大丈夫?」とかなりソフトな対応で、直は瞬きしながら頷いた。「邪魔だ」とか、「ふざけんな」とか言う怒声混じりの言葉を、そういえば校内に入ってから、いや、この制服を着た学校へ向かう集団の中を歩き始めてから一度も聞いていない……。
自分の席を間違えないようにして座ると、前の席の男子と目が合った。
「よろしく」と言われ、慌てて「こちらこそ」と返す。
穏やかなやりとりでほっこりしたところへ、さっき入口でぶつかりそうになった男子が、隣の席に座った。すぐに出身中学と名前を教えてくれる。古白友と言って、部活はまだ決めていないと言う。前に座っていた男子も話の輪に加わる。江沢素と自己紹介する。
思っていたよりもずっと順調な滑り出しだと思った。
「そこ、通っていい?」
言い方は柔らかだが、ハッキリしとした声には少しのきつさと苛立ちが感じ取られた。
三人で顔を上げると、しっかりとした感じの女子がこちらを見ていた。
「あ、ごめん」
小さく直が謝ると、三人の間を通り、直の後ろの席に座った。
直の入学した高校は男女混合の出席簿で、配られた一年生のクラス別の名前を見ると香賀見直の後ろは勝田キリとあった。後ろの席のクラスメイトは勝田さん、と直は心の中でその名前を覚えた。
「あの、香賀見直です。よろしく」
笑顔であいさつしたけれど、キリは冷めた目で「どうも」と言っただけで話を続ける気はないようだった。
直たち三人は、何となく気まずそうに目配せをしたのだった。
3
学校生活が始まり、薄々わかってきたのは、この学校のもうひとつの特色だった。クラス委員を決める時や部活見学で、この学校は女子がしっかりしている傾向がある、ということだ。クラス委員を決める時にも先に女子が決まり、その後に何人かの目配せの後、どうにか男子のクラス委員が決まったし、部活動で優秀な成績を修めている部は女子部が多く、男女混合の部活も女子が主導権を握っているようだった。
もともと女子校だった伝統から、リーダーシップを女子が取っていくのがごく自然であったらしく、五年経った今も、それまで学校を先導してきた先輩から引き継いだ気質を現在の女子生徒が受け継いでいるらしい。おまけに、おっとりした校風が合っていると考えてこの高校を選んだ男子というのは受け身気質が多いようで、女子が主導権を握る体勢が出来上がっているようだった。
品のある元女子校だけあって、言葉遣いはみんなきれいだし、物腰は柔らかだが、何かを決める時や意見を言う時のきっぱりした多くの女子の態度には、男子に対する苛立ちというか、期待度の低さというか、とにかく『男子は当てにならない』という感情がかなりダイレクトに伝わってくる。
先日は風と雨の強い朝、直が学校傍まで母親の車で送ってもらい登校すると、「いいな」とか「お母さん、優しいね」と肯定的な会話をするのが男子で、「母親に送ってもらうって……」とばかにしたような、引いたようなことを言い合っているのが女子だった。キリは「電車とか普通に近くまである学校なんだし、怪我とかの事情もないなら、高校生なんだし自分で来たら?」と、『次の時間教室移動に変更だって』と必要事項を伝えるような口調で言った。
直はキリの言葉に、うまく返事ができなかった。
送ってくれると言うから、送ってもらった。
言ってしまえば、それまでではある。
けれど、年の離れた兄が二人いる直は、自分で言うのもおかしいけれど、家庭内での拠り所的な存在だった。
兄があまり家族と話したがらない年齢に入った時には、親の代わりに直が何かを訊いたり、またその返答を親に伝えていた。直が間に入ると、物事がうまく進む。もめごとが起きない。兄たちのような闘争心がほとんどなく、それゆえというべきか、何かで人よりも抜きんでた結果を出したことはなかったし、入学した高校の学力も、兄たちと比べてしまえば差は出ているが、直は直、というのが香賀見家の不文律だ。ついでに言うと、直が間に入った兄たちの「家族とあまり話したがらない年齢」に直はとっくに入っていたが、現時点に至るまで、直にはそうした時期は訪れていなかった。
高校生になっても直に家族が構いたいのは同じで、今朝送ってくれるというのも、忙しいけれど直のために、というよりは、ここぞとばかりに直と朝少し出かける、という意味合いの方が大きい。それをわかっているし、家族と過ごすのも好きな直は、「ありがとう」とその親切を受け止めた。もし、「いいよ」と断ったら、きっと悲しい顔をされるのがわかる。
それに、この時までなんとなく忘れていたというか、忘れようとしていたというか、直にも親の親切を無碍にして悲しい顔をさせた記憶はあった。中学生の頃、校外学習に行く日にほかの友達が途中で昼食を買って行くことになり、自分もそうしようと突如決め、朝母親が用意していたお弁当を持っていかなかったことがある。「友達と買うからいい」と言った時、しまった、と思ったこと。「そう。ちゃんと買える? お金あるの?」とすぐに直の心配をする母親に、「うるさいな」と言ったこと。友達はみんなそういうふうに言っていると聞いていたし、兄二人もそんな感じだった。自分もそうなるんだ、という思いもどこかにあった。これでいい、と思った。けれど、振り切っても振り払えない痛みがあって、それは自分の心の痛さではなく、自分によって傷つけた親の心の痛さだと気付いた。誰に頼まれるでもなく周囲に合わせようとした本意でない行動で、自分も親も心を痛めるのなら、それは自分に必要な成長過程ではないと思った。ちなみに帰ってからお弁当を食べるつもりでいたが、それは母の昼食となり、謝った直に母は感激する始末で、それほど大きな出来事ではなかった。
ただ、その時の葛藤や気持ちを、キリに説明してわかってもらえる自信がない。
多分、友や素はわかってくれると思う。
友は年子の弟がいると言っていたし、素はまだ小学校低学年の妹と弟がいると言っていたけれど、話していると家庭での雰囲気は直のところと似ている。
キリに言われてうまく返せない直の心情が伝わったらしく、友は直の肩を優しく叩き、素は「家族の仲がいいんだよな。いいことだよ」と代わりに言ってくれた。
キリは眉をひそめ、鬱陶しそうに三人を見ると、そのまま女子の友達のところへ行ってしまった。
4
なるべくキリをはじめとした女子とは関わらないでおこう、と直は思い始めていた。しばらくは、それでも仲良くしていく方法を模索したけれど、もともとキリたち、この学校の女子は男子と良好な関係を築きたいと思っていないらしい。時々これみよがしに、近所の有名男子高との交流のことを話している女子もいて、何とも言えない居心地の悪さも感じる。
英語や古文の採点後の小テストが休み時間中に机に配られていることがあり、通りかかったキリに見られると、その点数の微妙さからばかにされている気がする。
久しぶりに中学校の友達と駅前で会って話すと、男子と女子の仲のよさについては、学校や部活によって違いはあるものの直のクラスのように事あるごとに女子からばかにされるような話は聞いたことがない。楽しそうな様子を聞いた後に、「直は?」と訊き返されると、正直に話せずに「同じような感じ」と曖昧に答える。たまに直の行く学校を知っている友達が「正座の授業とかあるんだよね」と訊いたり、「そういう学校の女子って、やっぱお嬢様って感じ? 優しくて上品な子が多い?」と少し羨ましそうに訊くこともあった。正座に関しては「うん、あるよ」と頷くが、女子に関しては「普通」と答えるのが直にとっては精一杯だった。もともとの性格から、直は中学校までは男の子でも女の子でも比較的仲良くできていた。きつい言葉を使うこともなかったし、使われたこともない。家でも学校はどうかと、取りとめのない会話の中で訊かれる。具体的な話はできないものの、『女子が少し怖い』と言うと、兄たちからは、ごく常識的且つまともな助言が繰り出される。けれど、そこが兄たちと直の違うところで、平均的に反抗期があり、家族との会話を避ける時期を通って大人になっている兄と、それを通さずに高校生まできた直とでは、そもそもの人間関係における体勢が違った。口ごもる直を見て、何となく家族が心配そうな顔をするので、家でもあまり学校のことは言わないほうがいい気がしてくる。
そんな鬱々とした生活の中で、お作法の時間があった。お茶やお花の時間もある直の学校では、お茶のお道具やお花に使用するはさみなどを入学時に注文する。お作法の時間はお道具はいらないので、忘れ物の心配がない、気楽な時間だった。
校内にある広い畳の部屋に入り、礼の仕方や正座について先生から教えてもらう。
小テストがあったり、黒板の前に出て数式を解く授業に比べると、かなり気楽な時間だと直は思った。
優しそうな女の先生を前に、直はほっと心が安らいだ。
先生のお話を聞く初日は畳に正座をする。正座を含めた所作も一年経つ頃には見違えるほど上達しますよ、と先生は言った。そしてスカートを広げて正座していた女子には「スカートはお尻の下に敷くようにしましょう」と、初日の正座についてふれ、該当した女子はそれを直した。
お話は一年を通して学ぶお作法についてや、お作法の必要性についてなどで、それに関しても柔和な語り口調とともに、穏やかな先生の人柄が感じられ、直にとっては心地よい時間だった。
先生は授業終了後に体育が控えていることまで配慮してくださり、三分前には授業を終えてくださった。
「いい先生だったね」と素や友と話しながら立ち上がろうとすると、隣に座っていたキリが、がくんと横に体勢を崩した。とっさに直は手を貸し、「大丈夫」と訊いた。
キリは瞬時に対応に困ったらしく、言葉に詰まった。そして、顔をしかめた。
「足、痺れた?」と直が訊くと、キリは小さく頷いて耳まで赤くした。
「僕も前は痺れたことあるよ」
足を痺れさせたことを恥ずかしそうにするキリをフォローし、そう言葉を添える。
「あと、正座って背筋を真っ直ぐにして、膝はつけるか握りこぶしひとつ分離すくらいにして、足の親指が離れないように気をつけると、だいぶきれいにできるよ」
直が目を合わせて笑って言うと、キリは小さく「ありがとう」と言った。
お礼を言われる側だけれど、確かにその時直は何かが少しだけ前進したと思ったのだった。
5
体育の時間は五月半ばに行われる体育祭の練習だった。
この体育祭の練習が、直は少し苦手だった。
直の学校は元女子校ということもあってか、生徒の安全を慮ってか、騎馬戦は男子でも帽子の取り合いに留め、騎馬の崩し合いは行わない。それはいいのだが、それまでこういった闘争心がものを言う競技で直は目立たない役が多かった。言わずともそういった競技に向いているクラスメイトが選ばれていたので、わざわざ希望を伝えるまでもなかった。しかし、である。似たような穏やかな性格の男子ばかりが集まったこの学校では、騎馬戦の上に乗りたいという男子がいなかった。そして体重の軽い順に上に乗る生徒が決められ、直もその一人に入ってしまった。
騎馬は前に背の高いクラスメイトが入り、左右は友と素の二人だ。
絶対に勝てとかそういう発破をかけられることがなく気は楽だが、いかんせん対戦競技である。
この日の練習でも、直は早々に相手に帽子を取られ、陣地に引っ込む不甲斐ない結果となった。
陣地に引き返す時、向こうで同じく騎馬戦の練習をしている最中のキリと目が合った。キリはいくつもの帽子を手に、奮闘した後で、直は騎馬戦の練習の結果というより、キリに駄目な自分を見られたことの方が辛い気がしてきた。
そんな直の心境に気付いてか、「俺らは俺らで頑張ったからいいんだよ」と友が言ってくれた。「うん」と頷きながら、何となく、変わりたいと直は思い始めていた。
昼食時も直はそのことを一人考えていた。
今日の昼食は焼き魚に副菜の野菜の和え物、ごはんに揚げ、わかめ、長ねぎの味噌汁だった。この学校の教育は食事にも及び、箸の持ち方から魚のいただき方までの教本を渡されている。そして魚は皮までいただくことになっている。
隣の席で素が魚の身をほぐすのに少し苦労している。
魚は裏返さず、中骨を箸で持ち上げて取り除く。
いちいち食べ方を先生方が見ているわけではないので、一応マナーは学び、後は自主性に任せることはわかってきたが、根が正直な素は言われた通りにしなければと思っているらしかった。
直は素の箸を借り、中骨を取り除く手助けをする。
「ありがとう」と言う素と直を、ちらりとキリが見ていた。
これまで肯定されるに終始する世界で直は生きていたと思う。同じ価値観の人ばかりが周囲にいたかといえばそうではなく、直には直の立ち位置というものがあり、そのままでいることで丸く収まっていた節がある。個性の尊重といえば聞こえはいいし、その通りだとも思うけれど、敢えて直の改善すべき箇所を見直す機会を素通りしてきたとも感じる。
できればこのままでいたいと直は思う。
不都合なく、このままでいること。わかり合える優しい人に囲まれること。
けれど、どこかで自分はそろそろ変わるべきなのでは、という気もしてくるのだった。
6
この週はお茶の時間があった。お作法、お茶、お花はローテーションが組まれ、週に一度の枠内で行われる。
一人一人が湯を沸かす釜も用意し、各自がその前で正座をしてお茶を学ぶ時間である。今日はまだ道具の確認や一年を通しての予定、文化祭で茶道部が活動しているので、よかったらそちらの部活も考えてみてくださいね、というような話で終わった。
これまた直にしてみれば気楽な時間だった。
何となく、周囲を見回していた直は、ふと隣で背筋を伸ばし、きちんと正座をしているキリに気付いた。
あ、と直は声を出しそうになった。
キリは先週直が伝えた通りに正座をしていた。
聞き流されるくらいの気持ちで伝えていた正座の仕方だったが、キリは足を痺れさせたあの場で直の助言を聞き、今日それを実行していた。
本当のところ、意地の悪い女子だと思っていた。
勉強もできるみたいだし、体育も得意そうだし、直がキリを嫌いだと一度自覚すればそれは僻みになる気がした。そう思うのが嫌だった。けれど、だからと言って仲良くもなれなかった。
そのキリの意外な一面を見た。
そして、勉強や体育が明らかに直より優れているのは、キリが常に真面目でいることと、真剣でいることが大きかったと直は今更ながらに思った。直が不真面目にしているわけではないが、もともとの心構えの段階で差があったように思う。キリは男子である直が嫌いだというよりは、物事に対して甘さがあると受け取れる直の態度が気に入らなかったのかも知れない。
そう気付くと、ただ嫌いだと思っていたことが、自分の器の小ささの反映だという感じがして、今更ながらに一人恥じ入る。もっと早くにキリの言わんとしていることに気付けていたら、或いは気付こうと心がけていたならば、キリとの関係はもとより自身にとって多くの実のある時間や結果をもたらしてくれていたのではないか。
授業の後、すっと立ち上がったキリは「香賀見」と直を呼び止めた。
「この前はありがとう。今日はちゃんと座れた」
キリにそう言われ、直は少し困って「ううん、役に立ってよかった」と言った。
キリは周囲を見回し、キリや直の友達がほかの生徒と話している最中なのを確認すると、「騎馬戦」と切り出した。
「え?」
「騎馬戦、もし、勝ちたいなら、香賀見は敵の後ろに回って狙った方がいいと思う」
黙ってキリを見ている直に、キリはもう少し噛み砕いて説明しようと思い直したらしく、「だから」と言葉を継ぐ。
「香賀見は正面からやり合うの、苦手だと思う。だったら、そういう正面からやり合うのが得意そうな人が騎馬同士で戦っているところを狙って、後ろに回って帽子を取っていくんだよ。そうすれば戦っている味方も騎馬を崩されないで済むし、また他で戦えるから。うちの学校、一騎同士の対戦はなくて全部団体戦だから、こういう作戦もありなんだよ。逆に言えば、正面から戦うのが苦手な生徒にもチャンスがあるっていうのが、うちの学校の体育祭だとも思うけど」
「なるほど」と直は頷きながらキリを見た。
人生初の騎馬の上の役割で、常に追いまわされて帽子を両手で押さえて騎馬に逃げ回ってもらうのみだった直は、とてもそこまで考えが及ばなかった。
「勝田さんて、頭いいね」
「こういう騎馬戦の作戦て、普通はみんなあるんだよ。先輩から教わったり。でもうちの学校の男子の間では、そういう引き継ぎみたいなのがなくて、そもそも作戦を立てて勝利に貢献しようって考えがあるのかどうかも謎だから、わざわざ言う気にもならないでここまで来たような感じもする」
「そうなんだ。じゃあ、僕、女子から男子への重要な引き継ぎを今したってこと?」
キリは鼻白んで、「そこまで大きい話ではないけど」と言い、「だいたい、今の作戦は作戦であって、実戦でどこまで頑張れるかは本人次第だから」とつけ加えた。
一気に距離が縮んだかに思えたが、やはりキリはキリというか、ハッキリと自分を持っていて、こちらに寄せてくることはないし、慣れ合う気もさらさらないことはわかった。少しわかり合えた気はしたけれど、油断はしないでおこうと直は思ったのだった。
7
キリにとても有効な助言をもらったものの、そもそも体育祭の練習はそれほど体育の時間に費やさない。その後は短距離走のタイムをとったり、体力測定をしたりするのに体育の時間は使われ、そのまま当日を迎えることになった。
中学校から体育祭は昼食を生徒は教室で摂ることもあり、保護者は立ち見で自身の子どもやクラス対抗リレーなどの見たい競技のみを応援し、早々に引き揚げる。高校でも似たような感じらしいが、直の母は見に来ると言っている。体育祭は平日なので来られない父や兄までもが、行けないことを残念がっていた。素のところは両親で来ると言っているらしいし、友のところは母と祖父母が来るらしい。一方、聞こえてくる女子同士の会話では「来なくていいって言ってるんだ」とか、「もう高校なんだから、来なくていいよね」と言う、あまり保護者に見に来てほしくない、といった内容が多かった。
そうは言っても、体育祭当日はどう見ても男子の保護者だけ、という感じではなく、かなりの人数の保護者が観覧スペースに詰めかけていた。
直の学校では午前中の最後の競技が騎馬戦、午後の最後の競技がクラス全員リレー、及びクラス選抜リレーだ。
つまり午前中の最注目競技が騎馬戦だ。
騎馬戦は男女別で、男子全学年、女子全学年参加競技だ。
直たちの学校は、公立高校の一学年がだいたい八クラスから九クラスであるのに対し、一学年六クラスとやや人数が少ない。そのため、団体競技は三学年合同で行うことが多い。
直は騎馬戦の前にキリから教わった後ろに回る作戦を友と素、騎馬の前になる男子に伝え、そこから友と素がクラス内に伝え、それが陣地内の味方側の二年、三年にも伝わっていった。温和な性格の男子が多いので、こういった伝達はかなり円滑に行われる。更にじゃあ、僕は誰が戦っている時に後ろから回って援護するからと、だいたいの正面から戦う騎馬と、後ろに回る騎馬の役割も決められていった。
そんな中、直はやはり不安だった。
靴と靴下を生徒席で脱いで入場し、ラインの内側で騎馬の上に乗っても不安は消えない。
「ねえ、向こうでカメラ持って手を振ってるの、直のお母さん?」と素が訊く。
「え、あ、うん」
直とは対照的に嬉しそうに母は満面の笑みでこちらに手を振っている。
「手、振ってあげれば?」と友が言う。
「今、それどころじゃないよ……」
「そうだよね。ごめん」と友が謝る。
「できるだけ、狙われないように、ちゃんと走るから、あんまり心配しないで」と素が言う。
たくさん感謝の言葉はあったけれど、がちがちに緊張している直は何も言えなかった。
ふと顔を上げた時に視界に入ったのは、満面の笑みで手を振る母ではなく、腕組みしながら『まあ、期待してないけど。できれば負けないでね』という感じのクラスの女子たちの姿だった。
逆境に立ち向かうとか、いざとなると力を発揮するといった性格とは対角線上にいる直は完全に委縮していた。
そしてそのまま競技開始の笛が鳴った。
どうする、どうする、とじりじりと動かないでいる直たちの騎馬だったが、周囲は言うまでもなく動く。
周囲から味方が移動していき、どうしよう、どうしようとなる。
そのうちに後ろから強そうな敵の騎馬が直たちに目をつけ、近付いてくる。
「逃げろ」と、ささささ、と騎馬が移動する。
どうしよう、どうしようと直が混乱に混乱を来たした時、相手側の騎馬を名指しし、後ろに回れ、という指示が飛んできた。高い女子の声で、我に返る。直は咄嗟に騎馬の三人に頼み、方向転換して指示された騎馬の後ろへと走った。戦っている相手側の騎馬はクラスメイトを押して優勢の状態だった。直は後ろから手を伸ばし、帽子を奪った。
「やった」という声がクラス席から聞こえた。
それを契機に、当初話し合った作戦が実行され始めた。
本来従順であり、言われたことをこなす傾向にあるこの高校の直たち男子は、目的をしっかり持てば確たる実行力を発揮する。
あちこちで戦っている相手の後方からの帽子の奪還が始まる。
観客席から拍手が起こる。
騎馬の数が減って行く中で、とうとう正面から相手の騎馬がやって来た。
「いくよ」と騎馬の前の男子が声をかける。
「大丈夫」と友が言い、「いける」と素も士気を上げる。
人生初の正面突破、という時、ついいつもの癖で直が身を引くと、相手が大きく体勢を崩した。本来ここが好機ではあるが、直は相手が体勢を戻すのを待った。それがフェアだと思った。そして体勢を崩した相手が直の向こうに目配せしているのに気付いた時、ふっと頭上が軽くなり、気付くと後ろから帽子を取られていた。
しまった、と思った。
こんなにも悔しいと思ったことは今まであっただろうか……。
直は相手から奪った帽子ひとつを手に、帽子を取られた状態で陣地に戻った。
せっかく作戦を教えてくれたキリに申し訳ない気持ちになる。
奮闘はしたが、騎馬戦は引き分けだった。先に行われた騎馬戦では直たちの側の女子、それも直たちのクラスの女子の圧勝だったので、男子が勝てばかなり優勢になるはずだった。
とぼとぼとクラス席に向かった直だったが、そこでは女子が拍手で迎えてくれ、男子一同キツネにつままれたような顔で首を傾げた。
「お疲れ」
「よくやったよ」
「あとはリレーで女子がリードするから、君らは自分のところしっかり走ればいいから」
この時、入学して二カ月弱、初めて同じクラスで学ぶ同士として、女子に認められたことに直たちは気付いた。
そして、ああ、女子は勝つか負けるかより、男子にもっと本気で取り組んでほしかったんだ、と直は思った。それを言葉にするのは難しく、苛立ちばかりが募っていたのだろうし、そもそも本気になる、というのは言われてなるものでもなく、逆に言えば言われるまでもないことでもあったのかも知れない。故意にだらけていたわけではない。悪気もなかった。ただ、男子は周囲と調和することを心がけていた。つい、それ以外が後回しになった。それがキリから直への助言をキッカケに、そして騎馬戦が開始された時、キリのクラス席からの指示で動き始めた。
「頑張ったね」
席に着くと、キリが来てそう言った。
「あの時、大声で言ってくれてありがとう。あれで、動けた。でも、帽子取られたけど」
「そんなのはいいんだよ。頑張ったの、見ていてわかったから」
「ありがとう」
さまざまな感謝を込めて、直はそう言った。
「直―!」と言う声がし、顔を上げると母親が手を振っていて、直もそれに応えた。キリの視線が気になったけれど、ここは変える必要はないと思った。
午後の最後のリレーでは、いつも冷めた表情のキリが俊足を活かした走りでコーナーに差しかかったところで「キリー!」という大声援が響き、キリの父母と思しき二人がぴょんぴょん跳んでいたのだった。
8
体育祭の翌日は休日で、その翌日はお花の授業のある日だった。お花の授業は、先生がお花を用意してくださる。まだ初心者なので、簡単な生け方から始めるらしい。
それぞれに正座をし、先生の指示でお花を生けていく。
これが意外というか、先生から褒められるのは男子が多かった。先生は穏やかな笑みで「この学校は男の生徒さんもとても柔らかな感性をお持ちですね」と言った。
そのうちにお花は作品として飾られるらしいが、今回は生けたお花は戻し、持ち帰る。
今日もきれいな正座をしていたキリが、お花をまとめている時、ふと一瞬だけ直の手元を見た。直に配られたのはピンクのガーベラで、キリはオレンジだった。
「これ、よかったらあげるよ」
差し出した花をキリは見て、一瞬ためらう。
「でも」
「いいよ。まだあるから」
「いいの?」
「うん」
キリがちょっと嬉しそうに笑う。
それを見て直も嬉しくなる。
友と素とお花を持って歩きながら、「これ、お母さんにあげたら喜ぶかな」と友が言い、素が「あ、妹にあげよう」と言う。
「直は?」と訊かれ、「じゃあ、僕もお母さんに持って帰ろう」と花を見ながら答えた。
母をはじめとし、直の家族は昔から直が学校で作ったとか、もらったとかいうものを「へえ、直が」、「まあ、直が」と何でも珍しがったり、喜んだりする。まあ、学費から出ている中で買っているお花ではあるけど、お母さん、喜ぶかなと顔をほころばせていると、かなり引いた顔をしたキリと目が合った。
「うちのクラスの男子、やっぱやばくない?」
そんな別の女子からのささやきが聞こえると、直たち男子は顔を見合わせ、「家庭円満は大事だよ」と言い合って、そそくさとその場を立ち去った。