[277]砂漠の水琴窟(すいきんくつ)に座る
 タイトル:砂漠の水琴窟(すいきんくつ)に座る
タイトル:砂漠の水琴窟(すいきんくつ)に座る
掲載日:2024/03/05
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
奈良時代の倭国(日本)。丹後地方の籠(この)神社の奥殿の欄干には、五色の座玉(すえたま)がある。大陸の唐王朝から伝わった「正座」という座り方をした時の痺れを防ぐ効力があるという。
ある日、五色の中の碧い座玉が無くなった。どうやら盗まれたらしい。神社の守護にあたっている海都一族の少年頭領は、正座するとひどい痺れに悩んでいた。さっそく、大陸から帰ったばかりの年上の少女もえぎに、「座玉を元に戻せ」という命令が下る。

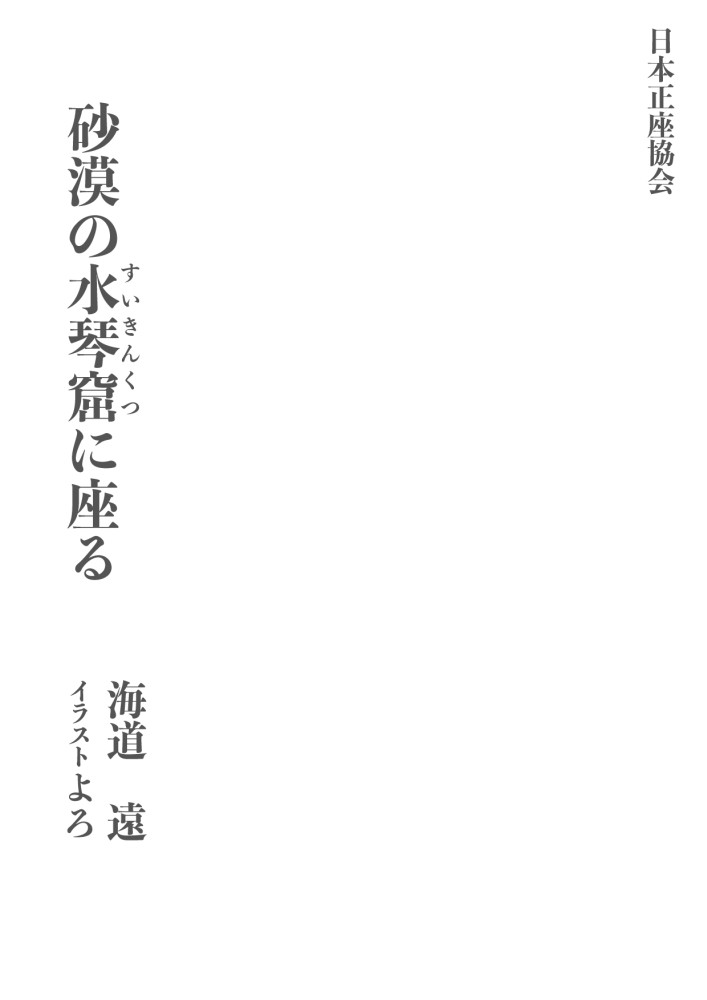
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 ぺき様
朝から、丹後地方の籠(この)神社の裏手の山中にある建物には、叫び声が満ちていた。
簀の子(すのこ)をドタバタと走る音に、17歳のもえぎは、おなごばかりで寝ていた小部屋で腕の刺青(いれずみ)を踏んづけられて目を覚ました。
「あいたたっ、こら、清らかなウミガメの刺青を踏んでいくとは、何ごとよっ」
「ごめんなさい、もえぎさん!」
仲間のおなごは謝りながら廊下を走っていく。
「な、なにごと? 昨夜、船で帰ったばかりなのに……」
丸まって寝ていた褐色のうさぎも驚いて、ぴょこんと起き上がった。
「どうした、何かあったのか……?」
格子戸を開けて、廊下を走っていく仲間に声をかけた。若い男が立ち止まり、
「お、もえぎ、帰ってたのか」
「朝から何の騒ぎだ」
男は、もえぎの耳に口元を寄せて、
「大変だ。奥殿の欄干から碧の座玉(すえたま)が無くなった!」
「無くなった……? ええっ? ――そりゃ、大変だ!」
もえぎは急いで褐色のうさぎを抱き上げ、頭領の元へ急いだ。
倭国(日本)の奈良時代――。
ここは籠神社を陰で支える警護集団、海都(かいづ)一族の本拠地である。
頭領といっても、まだ12歳の少年だが、碧王丸(へきおうまる)の元には、一族の者が続々と集まりつつあった。
「碧の座玉が無くなったというのは誠か」
「はい、ぺき様。どうやら盗まれたようでございます」
碧王丸は配下の者から「ぺき様」と呼ばれている。
「どうやら盗まれたとは、何たるのん気な、何ごとか!」
少年頭領は精一杯、威勢を張って怒鳴りつけた。
「も、申し訳ございませぬ。情報を集めたところ、座玉は盗まれて大陸行きの船に乗せられたようでございます」
一族のひとりが平伏して言った。
「むむむ……」
碧王丸の顔がよけい険しくなる。
「一刻も早く見つけ出し、取り戻すのだ! ここには、もえぎだけ残れ」
配下の男たちが散っていき、碧王丸の元には、もえぎだけが残った。
「困ったことになりましたな、ぺき様。碧い座玉がなければ、ぺき様は正座する時に、ひどく痺れてしまわれる」
「しっ!」
碧王丸の人差し指が口の前に当てられた。
「海都一族の頭領の余が、正座の痺れに困っているなどと、誰かに聞かれでもしたら、なんとする」
もえぎは急いで、頭領のご前に礼儀正しい所作で正座した。
背すじを真っ直ぐに伸ばし、床に膝を着き、衣をお尻の下に敷いて、かかとの上に座る。
もえぎも碧王丸も、神社の宮司さまの指導のおかげで正座は完璧な所作が身についている。
ふところから、褐色のうさぎが顔を出した。
「そのうさぎは?」
「この度の大陸行きで、草原にいたのを連れ帰りました。まだ子うさぎでしたので、あたい……いえ、私が育てました」
「なんと、あえかな存在じゃな」
あえかとは、か弱いとか儚げ(はかなげ)とかいう意味だ。
「しかし、そのうさぎは案外、お転婆なお前より強い存在やも? お前を守ってくれるやもしれぬぞ。そういう気がする」
「ぺき様、そんなことをお感じで」
うさぎをふんわり抱きしめた。
「たいそう愛でておる様子。名は?」
「胡族の地で出会ったので胡太太と名づけました」
「コタタ?」
やんちゃなうさぎにぴったりだ。
「では、お前に命令を下す。大陸に派遣しているライザと力を合わせて碧き座玉を探し出し、持ち帰れ!」
少年頭領のひと声で、もえぎは大陸へトンボ帰りして任務につくことになった。
第二章 砂漠の地へ
大陸では、唐王朝が繁栄していた。
西の砂漠に勢力を持つ遊牧民族の吐蕃(とばん)国(現在のチベット地方)と交易したり、時には小さな戦を繰り返したりしていた。今は、公主(こうしゅ=王女)をひとり王族へ嫁入りさせ、平和を保っている。
もえぎは大陸行きには慣れている。
東シナ海の一か月の長い船旅を経て大陸へ上陸し、馬を借りて都の長安を目指した。長安には海都一族の姐御、ライザが潜伏している。
「ライザ姐御!」
街はずれで馬を下りるなり、幼なじみのライザに走り寄って抱きしめた。
「ライザ姐御! 一年、いや二年ぶりかな? ますますお色気たっぷりで元気そうだね!」
「あはは、ご苦労さんだねえ。この前、倭国に帰ったばかりだったって聞いたよ」
ライザ姐御はすっかり唐の美女に化けて、柔らかい衣を着こなし、耳玉を揺らせて朱い唇で苦笑した。
「ぺき様の大切な碧い座玉を見つけるためなら、仕方ないさ。で、新しいこと何か分かったかい?」
「それが――、吐蕃の国へ向かう隊商が荷に積んでいたのを目撃していた者がいるんだよ」
「吐蕃だって? そりゃ、もっと西の高地っちゅうか、半分、砂漠の国を経て万年雪を頂く高い山がある国じゃないか!」
「仕方ない。私たちも一緒に行くから、吐蕃へ行こう!」
ライザたちと合流したもえぎたちは、吐蕃へ向かうことになった。もえぎにとって初めての地だ。
唐との国境近くで馬からラクダに乗り換えることにする。商人が多くのラクダを待ち受けさせている。
もえぎは、ラクダに乗り慣れていない。コタタを大きな布で包みこみ、肩からかけてしっかり離れないようにした。
日中はかなり暑いが、コタタは元々、草原のうさぎなので耐えてくれることを祈った。
何日目かに、砂嵐が襲ってきた。目も開けていられない。一行はラクダを地面に伏せさせ、身体の陰に寄り添った。しっかりラクダの荷物につかまっていないと吹き飛ばされそうだ。
いつまで続くかしれない砂嵐が、魔の叫びのように聞こえた。
どのくらい経ったのか――、
ようやく静かになり、手元の布の中を覗いてみる。良かった。コタタは元気そうだ。
「よしよし、よく辛抱したね」
砂漠を見回すと、仲間たちの姿が見えない。
「ライザ姐御~~! みんな~! どこ~?」
(砂嵐に吹き飛ばされたってことは……、ないよね?)
しかし、ライザ姐御や配下の男の姿が誰ひとり見えない。地平線には赤い日輪が沈もうとしている。
「どうしよう、こんな砂漠でひとり……、コタタ、お前とふたりきりなんて初めてだよ。しかも……」
水入れの水筒を振ってみてもチャパチャパ鳴る音は少ないし、食料も少ししかない。
辺りは紫色になってきた。コタタがもえぎの胸にぴったり身を寄せてくる。
第三章 地下湖
急に冷えこんできた。
抱いているコタタの体温がありがたい。睡魔に襲われて眠りそうになった時――、いきなり、コタタが耳を立てて起き上がった。
どこかからポタリ……ポタリ……と、水の落ちる音が聞こえてくる。
「こんなに砂漠の真ん中で水が落ちる音……?」
美しい音だ。まるで弦楽器がつま弾かれるような。
もえぎはコタタを抱いて立ち上がり、音のする方角を探そうと歩き出した。
とたんに足元の砂が崩れて、すり鉢状の穴へ吸いこまれていく。
「うぐぐっ、息ができない! 吸いこまれてく!」
苦しい! もう駄目、と思った時、ドスンとどこかへ落ちた。
(ここはどこ……? あたいは砂に飲みこまれて……)
(コタタ、コタタ、どこ?)
コタタのヒクヒクする鼻先が頬に当たった。
「コタタ、無事で良かった!……」
地面はかたく、これ以上滑り落ちる心配はなさそうだ。コタタが後ろ足立ちになって鼻をヒクヒクさせている。頭を上げると、向こう側はほの明るく岩盤の天井に水の模様がゆらゆらと映っている。
立ち上がって歩いていってみた。水面がのっぺりと白く明るい地底湖があるではないか。
「わ――! 大きな湖!」
思わず走り寄って水辺に膝をつき、手のひらにすくって口に含んだ。まろやかな味――、飲めそうだ。
飲めると分かるが早いか、夢中で水を飲む。コタタにも手から飲ませてやった。干した果物も与えてもらったコタタは元気になった。
「ありがとう。お前が水の音に気づいてくれたから、水にありつけたんだよ」
吐蕃王朝が、砂漠の中に大きな水甕(みずがめ)を埋めこんだという、おとぎ話か伝説のような話は聞いたことがあった。しかし、信じてはいなかったし、まさか自分が吐蕃の国へ来ようとは思いもしなかった。
湖の真ん中にこんもりとした黒い影がある。島があるようだ。しかも樹木が繁っているように見える。
(あそこにいけば、果実が成ってるかもしれない)
岸辺を歩いていくと、小舟が乗り捨ててあるではないか。
(舟がある……人がいるんだな)
もえぎは小舟を調べてみた。どうやら使えそうだ。小舟なら、港から舟子のふりをして扱い慣れている。
(生き延びるには、小舟で行ってみるしかなさそうだ)
第四章 再会
小舟の櫂(かい)を操り、小島へ到着した。
対岸から見た通り、多少の樹木が生えている。島の真ん中は土地が盛り上がり、高くなっている。
不思議に思いながら進んでいくと、
「何者だ」
珍しい織模様の布を巻きつけた男たちが、剣を持って数人、飛び出してきた。
「旅の者だよ。砂嵐に遭って道に迷ったんだ。食べ物になるような果物でも成っていないかと……」
「黙れ、よそ者は立入り禁止だ」
身体を縛られかけた時、奥から白髪混じりの年配の女性が走り寄ってきた。やや身分の高そうな身なりをしている。
「私が連れていく」
そのひと言で男たちは引いた。
島の真ん中へ進んでいくと、見慣れない木造の建物が建っていた。柱には色とりどりの紋様が描かれている。
先ほどの年配の女性が、更に奥の建物に案内した。
幾重にも重厚な布で守られた部屋に入っていくと、女人たちが十人ほど、壁に開けられた階段の入口から降りてきた。周りを囲まれている中心の女性は、ひと際あでやかな風情で年配の侍女が手を取った。
彼女の指図で周りの女たちは姿を消し、女あるじひとりが残る。
「こんなところで会おうとは」
美しく通る声に何度も目をぱちくりしてから、もえぎは叫んだ。
「し……真朱(しんしゅ)さま?」
「いかにも。よう覚えていたな、もえぎ……」
それは、10年近く前に大陸へ渡った碧王丸の姉、真朱だった。海都一族の一の美しい姫だ。
「わらわが倭国を離れる時、幼かった碧王丸と共に見送ってくれたもえぎ。すっかり娘らしゅうなって」
「真朱さま! どこかへ嫁がれたと聞いたまま、お父上も籠神社の宮司さまもお口を閉ざしたままでした。こんなところでお会いできるとは!」
吐蕃の民族衣装なのだろう、色彩豊かな衣に身をつつんでいる真朱は、名の通り「朱の女王」とでもいうような気高さを身につけていた。
「近う寄れ、もえぎ」
真剣な目つきで呼ばれ、言われる通りにした。
「お前を信頼して申す。わらわは吐蕃の王、馬簾(ばれん)さまの妃だ。ただし――、唐王朝の公主として輿入れしてきたことになっている」
「……!」
「夫の馬簾王もその事は知らぬ。わらわを唐王朝の公主と信じておられる」
「そのような重大なことを、あたいなぞに打ち明けてくださってよいのですか!」
「よいとも。お前のことはよう覚えておる。碧王丸の良き遊び相手になってくれていたではないか。あの頃から、お前は主に誠を尽くす、良き娘だと見込んでいたぞ」
もえぎは更に後じさりし、絨毯の上に土下座した。腰の袋から飛び出そうになるコタタを慌ててひっこめる。
「――どうしてお前がここに?」
「どうして、真朱さまがこんな地下に?」
ふたりして同時に問うたので、やや間があってお互いに笑いあった。10年近い時間が飛び越えられた。
第五章 座玉ぬすびと
「わらわから申す」
真朱が先に口を開いた。
「吐蕃の国は北方の辺境民族と戦の最中だ。もしも敵が都へ攻め入って、わらわの身が危うい事態にならぬよう、王がこの地下湖の小島にかくまってくださったのだ」
「まあ。馬簾という王様は、真朱さまのことを大切に思ってくださっているのですね」
「うむ。勿体ないことだと思っている。わらわは、本当は唐の公主でないことを申し訳なく思いながら……」
真朱の濃いまつ毛が伏せられた。
「真朱さま。その点では、あたいも祖国の籠神社の宮司さまに申し訳なく思っているのと同じかもしれません」
もえぎは少し、うなだれた。
「実は、以前、正座の痺れに効くと偽って、唐王朝の皇帝に奥殿の欄干に並んでいた座玉をひとつ、偽物とすり替えて献上したことがあるのです」
「ま、まあ、お前という娘は」
呆れると同時に、真朱の顔に複雑な表情が浮かんだ。
「碧王丸は元気にしているか?」
「はい! 背が伸びられて、立派に頭領を務めておられます。ただ――。この度、欄干の碧い座玉を盗まれて、正座する時に困っておられます」
「碧い玉を? まさか、碧王丸も正座すると痺れるというのでは?」
「……はい……。あたいが紅い座玉を皇帝陛下に献上した罰が下ったのでしょうか」
もえぎは、ぺろりと舌を出した。
「いえ、天罰ではないわ。これをそっとごらん。こちらへ来て」
真朱が呼び寄せて、寝室の垂れ布の隙間からチラリと見せたのは、探し求めている碧い座玉ではないか!
「真朱さま、これは!」
「天罰を受けるのは、わらわじゃ。座玉の噂を耳にして、籠神社の欄干から盗んでくるよう、配下に命令を下したのだから」
もえぎは驚いて口をパクパクさせた。
「夫の馬簾王も、正座の痺れに困っておられたのだが、碧い座玉を膝の上に置くとかなり良くなった」
「そ、それは、ご夫婦で仲のよろしいことで良かったですね。でも! 真朱さま。盗みはいけません。お仕えする籠神社を裏切ることになるのですよ。それに、ぺき様も困られます。どうなさいますか?」
「……それは、お前の言うとおりだが……」
真朱の顔が曇った。夫の馬簾を助けたいが、やはり神社から失敬することに罪悪感を感じているらしい。黙りこんだ。
第六章 王の帰還
吐蕃の若き王、馬簾が辺境地方から帰るとの知らせがもたらされた。
「王が! 馬簾さまがお帰りになる!」
侍女から知らせを受けた真朱は、目を輝かせて浮足立っている。
やがて、多数の馬蹄音(ばていおん)が地下にも響いてきて、うさぎのコタタが落ち着かずにぴょんぴょん跳ねている。
馬簾王が、秘密の通路から地下宮殿に姿を現した。
もえぎが多数の侍女に混じって迎え、お顔を配すると、猛々しいアゴひげを生やした精悍な王だ。
真朱は妃の間で待ち受けていて、王に玉座を譲った。ひざまずき、顔を伏せる。
「この度のご戦勝とご帰還を心よりお祝い申し上げます」
「真朱。そなたも無事で何より」
「陛下がこの地下湖の宮殿にかくまってくださったおかげです」
「先日、余のために碧い座玉を手に入れてくれた礼だ」
馬簾は、碧い座玉を真朱が唐王朝から取り寄せた品だと思いこんでいる。よもや、倭国の籠神社から盗ませた品などとは夢にも思っていない様子だ。
真朱が戸惑っているのが、もえぎにはよく分かった。
王は、久々に見る妃の美しい正座姿を見て満足気だ。
「新しい侍女も正座ができるようだな」
王はもえぎに目を止めた。
「凱旋祝いに『碧き座玉を釜で煮る儀式』を行う」
王の命令に、もえぎはギョッとなった。
「碧い座玉を釜で煮る――?」
あれよあれよという間に、支度が整えられていく。
湖のほとりに火が焚かれ、大きな釜が用意されて熱せられた。沸騰した釜の湯の中に碧い座玉が入れられる。グツグツと煮えられる玉から碧い湯気が立ち昇り、湖の面に映ってなんとも美しい碧色に染まっていく。
碧い色には映るが、湖水はたいそう熱くなるので気をつけるようにと、兵が触れ回った。
「この儀式を経ると、座玉はいっそう痺れを抑える効力を発揮してくれるのだ。これで三度目だ」
(座玉を釜で煮ると、痺れを軽くする効力が増す――? 本当かな)
もえぎには初耳だが、王はご機嫌だ。
「もえぎ、碧い色に、故郷の倭国の海を思い出して心が和むのよ」
真朱が呼び寄せて言った。
「でも、これは口が裂けても言ってはダメよ。わらわがもっとも恐れているのは、王に身元が判明してしまうことなの」
今にも心臓が破裂しそうな真朱の緊張がよく伝わった。
(真朱さまは、馬簾王を心よりお慕いされているのだ)
第七章 座玉を煮る
真朱と王は、煮え立つ釜の前でじっと正座を続けている。王の表情が、ややしかめられる。
炎の熱を避けるため、ふたりは座席を降りてきて飲み物を摂った。
岸辺に敷かれた絨毯に、もえぎは近寄った。
「お妃さま。王様にご奏上したき儀があるのですが」
真朱は目を丸くした。
「おみ足の痺れを軽くする別の方法です」
もえぎはコタタを膝に乗せてから、絨毯の上に置いた。
馬簾王は興味深げに、もえぎの成すことを眺めた。
「これなるうさぎは、四角くなり、四肢を身体の下に敷くのが得意です。くつろいで長いことそうしております。身体の下にうまく手足をしまいこむ方法を心得ているのです」
「ほほう」
王はうなずき、コタタの胴体の下に手を入れてみた。
「誠じゃ。うまく手足を曲げておる」
「多分……多分ですが、うさぎは四肢を柔軟に折りたたむことで痺れを感じない様子です。このように柔軟な手足を作れれば、痺れを永久に回避できるのではないでしょうか?」
「う~~む、このように柔軟にのう。確かに、年じゅう馬の鞍の上にいるゆえ、余の身体はガチガチだからのう」
王は笑い飛ばしたが、真朱は血相を変えてその場に土下座し、もえぎに叱りつけた。
「もえぎ、陛下に直に進言するとは何ごと! うさぎを連れてすぐに下がるがよい!」
碧い座玉を煮る行事は終わり、釜から取り出されて、熱が冷めるまで特別あつらえの台の上に乗せられた。
座玉を凝視していた馬簾王の彫(ほり)の深い瞳の色が、だんだん――、険しい色に変わっていった。
第八章 ウミガメの刺青
その夜は、妃の宮殿で王の凱旋祝いの宴が催された。従軍した将軍たち数人とその側近など30人近くは出席しているだろうか。
王は踊り娘の舞を鑑賞しながら、酒の杯を重ねている。
「真朱よ。相変わらず、そなたの正座の所作も姿も神々しい」
隣席の真朱の正座姿を褒める。
「お言葉、感謝いたします」
侍女たちの下座で、もえぎが将軍たちに酒を注いでいた。
「もえぎと申したな。そちの正座もなかなか。――うむ?」
王の視線が、手元に一瞬止まった。もえぎは急いで何重もの金属の腕輪で見えないようにした。
籠神社を警護する海部一族には、皆、腕の内側に一族の証拠であるウミガメの形の刺青が施されている。
馬簾王は急に押し黙り、盃を口元に運ぶ手を止めた。
あでやかな布をひらひらさせていた踊り娘たちは、踊りを止め、太鼓や笛や弦楽器を奏でていた楽人たちも演奏の手を止めた。
「真朱、そなたの左腕の内側を見せよ」
王が命じた。真朱が絨毯の一点を見つめたまま、凍りついた。
「見せよ、と言うに!」
妃は肩をびくっとさせて、近衛兵どもに、恐る恐る左腕を差し出した。兵は妃の袖をめくり上げた。妃の上腕に赤い痕(あと)が確認された。
「これは幼き頃の火傷の痕と申しておったな。侍女長のキスゲよ、これへ!」
年配の侍女が、進み出てひざまずいた。
「さようでございます。お妃さまはご幼少のみぎり、戦乱の際に火事に見舞われ、その時に――」
侍女長の額に薄く汗がにじんでいる。
「ふむ。妃が輿入れして以来、何度も目にしているが、火傷に間違いはないな」
王は真朱の腕を放し、両手をパンパンと打った。
「釜の係の者ども、先ほど熱していた碧い座玉をこれへ!」
ひと抱えほどもある碧い座玉が、宴の中心に運ばれてきた。
「もえぎ、これへ参るがよい」
もえぎは一歩一歩、側へ上がった。
「この――碧い座玉に刻まれているウミガメの印と、お前の腕にある刺青のウミガメがそっくりなのはどういうわけかな」
碧い座玉には、今まで見えなかったウミガメの印がくっきり見える。もえぎの左腕にも同じウミガメの刺青が――!
真朱の唇がわなわなと震えた。
第九章 雫の音
もえぎは、王の命令で牢につながれてしまった。
ウミガメの刺青から倭国人であることがバレてしまったのだ。
(真朱さまは大丈夫だろうか。牢に連れて来られた気配はない)
うさぎのコタタだけは、しっかり抱いて離さなかった。
(コタタ……。守ってやるからね)
コタタは、もえぎの懐に頭を突っこんでおとなしくしている。
もえぎは牢の壁に背中をもたれて、膝を抱えた。
ウミガメの刺青は海都一族の決まりだが、座玉にまで刻印されているとは聞いたことがない。座玉は海都一族のものではなく、あくまで籠神社のものだからだ。では、釜で煮られた座玉は偽物ではないだろうか。
(だとすれば、刻印の入った偽物を、真朱さまに渡したのは誰だ?)
(籠神社の座玉を手に入れるよう、誰に命じられたのだろう?)
――ライザ……?
ふと、快活な彼女の姿が思い浮かんだが、頭を振って打ち消した。
(ライザ姐御がそんなことをするはずはない。私たちは三人姉妹のように仲良く育ったのだから)
ポタリ……ポタリ……。また美しい音が響く。
石の牢の床を、ひとひたと足音がした。馬簾王が真朱の火傷痕のことを証言させた侍女長だ。
「あの音は?」
もえぎは尋ねてみた。
「この島の周囲にある地下湖は、神々の住む山の雪解け水が溜まってできた湖ですから、その雫が落ちる音です」
「白い雪を頂いた嶺のこと?」
「そうです。雪解け水が長い長い年月をかけて、ひと雫、ひと雫、天井から落ち、湖を作ったと伝えられています」
気が遠くなるような年月だ。
「この地下の空間は巨大な水甕です。大昔、砂漠に住んでいた一族が『砂漠に作った巨大な水琴窟だ』という伝説があります」
ふたりは牢の格子を挟んで、雫の落ちる音に聞き入った。
「あなたは、長く真朱さまにお仕えしてきたのですか」
「ええ。倭国におられた頃から」
「倭国から? では、海部一族の方ですか?」
侍女は相好を崩してうなずいた。
「そうです。もえぎさんのことは、小さい頃からよく存じていました。私はキスゲと申します」
「まあ、キスゲさん! おぼろげな記憶しかないけど、覚えているわ」
思いがけない海部一族の老女との再会だ。もえぎは、今ぞとばかり牢の格子を握って顔を出そうとした。
「あなたなら知っているのでは? 真朱さまが馬簾王のために、誰から碧い座玉を受け取ったか」
「それは、あたいの口から言うわ、キスゲ」
背後から聞き覚えのある声がした。
第十章 ライザ姐御
「ライザ姐御!」
先日の艶っぽい唐風の美人とは大違い、まるで山賊の女頭領だろうかというような、毛皮と編み物の混じった民族衣装をまとった姿で、腰に手をあて牢の入口に立っていた。
「偽の碧い座玉を真朱に渡したのは、あたいなのさ」
「ど、どうして」
もえぎは唇を震わせた。
「あたいたちは幼なじみ。倭国の丹後の海で三人仲よくふざけ合って海水を掛けあったり、泳ぎの競争をしたりしたじゃないの。なのにどうして?」
「そう。幼なじみ。でも――あたいたち奴婢(ぬひ)は毎日、重労働。真朱は一日中、着飾っていればいい一族のお姫様」
ライザは、ペッと噛んでいた葉っぱを吐き出し、階段を降りてきた。
「ある年、真朱は入念に着飾らされて船でどこかへ旅立ったと思ったら、砂漠の向こうの吐蕃という国にお嫁入りしていた」
「姐御は真朱さまが嫁いだ先を知っていたんだね?」
「たまたま数年前に、吐蕃へ潜入する命が下った時にね」
「……」
「しかも嫁いだ相手は、青年王の馬簾。都では民から慕われ、戦となれば軍神と謳われる神々の申し子。真朱が、彼のために籠神社まで裏切って、碧い座玉を手に入れようだなんて……」
ライザの声は、激しさを増す。
「そんなことは赦せない! ――だから、偽物を渡したのさ」
もえぎの顔が引きつった。
「ライザ姐御、どうしてしまったの? あんたらしくないよ!」
真っ暗闇に落ちた心地だ。信じていたライザ姐御が……。
(悪い夢だわ、これは)
冷えた床に座りこんだ。膝に乗ってきたコタタの身体からは、かすかな体温が温めてくれた。
第十一章 一番、大切なこと
一方、真朱は、島の中央の高台に築かれた台座に正座して、天井の岩盤からの雫を頭の天辺(てっぺん)の「百会(ひゃくえ)」というツボに一滴ずつ受けて、自分の身体で試していた。
――痺れに悩んでいる馬簾のために……。
頭のツボに雫を受ければ、正座しても痺れない身体が得られるという説を信じて――。
もえぎが、コタタとたびたび聞いたポタリ、ポタリという雫の音は、真朱の願いの音だったのだ。
【碧い座玉に、膝に乗せれば痺れが軽くする効力があったとしても、馬簾さまは生涯、玉を持ち歩かなければならない。それよりは、痺れないお身体になっていただきたい】
「――という真朱さまのお考えなのよ」
キスゲは、もえぎを寝室に案内してから打ち明けた。
「雫は、碧い玉を釜で熱した時の熱が天井にこもって一滴ずつ落ちてくるから、かなり熱いんですよ」
「雫が熱い? てっきり冷たいんだと思ってた。さすが真朱さまのお優しい思いつきね。雫の効果がありますように」
温かい飲み物をもらったもえぎは、少しホッとした。
真朱の必死の取り成しを聞き、王の怒りは解け、倭国の海都一族の苦悩も理解してもらった。それもこれも真朱の人柄ゆえ、王が理解を示したと言える。
「でも、ライザ姐御が真朱さまを憎んだままだわ」
キスゲは袖を口元へ持っていった。
「あれはライザさんの作戦です。馬簾王の配下の中にも、唐王朝の息のかかった者が混じっていますから、それに倭国との婚姻を快く思わない朝廷の連中が、いつ、どこにいるか判りませんから」
「え? じゃあ」
「ひと芝居打たれたんですよ」
「まあ! でも、あの言い分では、海都一族はどっちの肩を持ってるんだか、よく分からない芝居だったわ。どっちかというと、ライザ姐御のヤキモチだとしか聞こえなかったけれど……」
もえぎは唇を尖らせた。
キスゲは、改めてもえぎの元に正座した。
「よろしいですか。一番大切なことは、籠神社の座玉を痺れに効くなどという風評を真に受ける連中から盗まれないことです。それが海都一族の務めです。真朱さまのためにも、倭国に残られている碧王丸さまのためにも。そして――、何より籠神社のためにも」
「そ、その通りね」
ポトリ――、ポトリ――。
岩盤からの雫の音が響いた。
「そろそろ、真朱さまをお迎えに行かなくては」
キスゲは、慌てて部屋を出ていった。
真朱の健気な行動を、もえぎから聞いた馬簾は、真朱の部屋を訪ねた。
「もえぎから聞いたぞ。美しい音の雫を受けていたということを」
「あの娘ったら、よけいなことを。陛下のおみ足の苦痛が少しでも取り除けるならばと、方法を探っていただけです」
はにかんで、真朱は答えた。
「たとえ方法が見つからずとも、嬉しいのは、そなたの思いやりだ」
仲睦まじいふたりの様子に安心して、もえぎはそっと外へ出た。
ライザ姐御から、思いがけず文が届いた。
『本物の碧い座玉は、倭国の海部一族の屋敷の奥深くに仕舞いこんであるよ。任務は終わった。さっさと神社へお帰り』
「なんですってえ~~! あんのぉ~~、嘘つき!」
頭から湯気が出たのと、ほっとしたのと同時だった。
「コタタ、倭国に帰るよ。ぺき様が待ってる」
微笑んで、腕の中にいるうさぎをふわりと抱きしめた。








