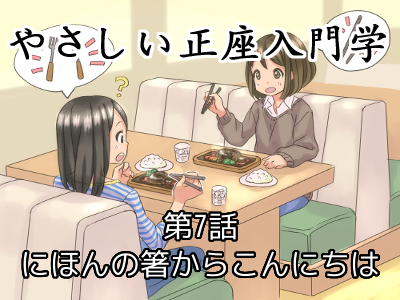[315]メリーゴーランドの九十九(つくも)神
 タイトル:メリーゴーランドの九十九(つくも)神
タイトル:メリーゴーランドの九十九(つくも)神
掲載日:2024/10/28
著者:海道 遠
内容:
いとこ同士の学生、千紗(ちさ)と摩周(ましゅう)は久しぶりに祖母の元を訪れた。具合が良くないらしい。祖母の千登世は、物置きから「あるもの」を取ってきてほしいと言う。それは祖父の周五郎が英国に留学していた頃に買い求めたメリーゴーランド型のオルゴールだった。
その夜、祖母の隣りに寝た千紗は、奇妙な夢を見る。回るメリーゴーランドの中で正座するよう、摩周が命令するのだ。

本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
序章
二十世紀の初め。ガス燈が点灯夫(てんとうふ)の手で、ひとつずつ灯される夕暮れ。
英国の古びた骨董品店である。ショウウィンドウの片隅に、メリーゴーランド型のオルゴールがちょこんと置かれている。
木馬に混じって馬車が細工されていて、中には膝を折って座る少女の小さな人形がいた。
初老の骨董品店のあるじは、奥の椅子で本に没頭していたが、大きい木製の柱時計が五時を打つと、立ち上がってオルゴールに近づいた。小さなハタキで埃をはらいながら、
「お前さんを作ったオルゴール職人は、変わった座り方をさせたものだね、小さなレディ」
東洋の青年が覗きに来た。
「ほら、あんたの王子様が今日も会いに来たよ、レディ」
第一章 祖母の家
(沈丁花(じんちょうげ)の香りだわ)
久しぶりで訪れる祖母の家の玄関で、濃く甘い香りを嗅いで、千紗は足を止めた。
(お祖母ちゃんの家は、築百年は越えてるけど植木がきれいで好きだわ)
「千紗! だよな?」
後ろから声をかけたのは、絣(かすり)着物に袴を着けた青年だ。
「摩周にいちゃん、しばらくねえ。 その格好は何? 何かのコスプレ? まるで明治時代の書生じゃないの」
「お前、背が伸びたなあ」
「私だって大学生ですもん。で、その格好は?」
「これは、大学のとある研究会で感化されて……。ま、それはおいおい話す。――お祖母ちゃんの具合が悪いらしいから、様子を見に行くようにお袋から連絡が来たんだけど」
「私もよ。お祖母ちゃん、ひとり暮らしだから。いつも元気だけど、やっぱりトシには勝てないのかな?」
「とにかく顔を見なきゃ」
摩周がチャイムを押してふたりで待った。しばらくすると、弱々しい声がかすかに聞こえてきた。
「摩周くんと千紗ちゃんなの? 玄関は開けておいたからお座敷へ来てちょうだい」
ふたりが座敷まで上がると、祖母は床(とこ)の上でカーディガンを羽織って座っていた。
「まあ、ふたりともすっかり大人になったわねえ」
「そんなことより、お祖母ちゃん、大丈夫?」
「大したことないのよ。でも、ちょうどお願いしたいこともあったから来てもらったの」
「風邪とか疲れなの?」
「身体がだるいだけよ。しばらく横になっていれば治るから」
白髪が多くなってきた祖母は、顔色が良くない気がする。
「病院へ行くなら付き添うわよ」
「ありがとう、千紗ちゃん。でも大丈夫。それよりお願いを頼まれてくれる?」
「いいわよ。何をすればいいの?」
「二階の物置きにある、奥の棚の木箱を持ってきてほしいのよ。手が届かなくなってね」
千紗と摩周は、さっそく二階の物置部屋へ行き、見当をつけて埃のかぶった木箱を持って降りた。
「この木箱のこと?」
「そう、これよ。ありがとう」
祖母が、木箱にかけられていた紐を解いて、ゆっくり蓋を開けた。中には、尖がった屋根のメリーゴーランド型のオルゴールが入っていた。そっと取り出してみて細かい作りに千紗は目を見張った。
「なんてきれいなのかしら! 色んな動物が遊園地のメリーゴーランドそっくりに作られているわ!」
ユニコーン、タツノオトシゴ、ブタ、イルカ、トンボやウサギなどが支柱で支えられている。屋根は真っ赤な布、宝石を散りばめられた豪華な品だ。お姫様が乗るような小型の馬車まである。
「周五郎さんが若い頃、ヨーロッパ留学に行かれた時のお土産なの。千登世が好きそうだからって」
周五郎とは祖父の名前、千登世とは祖母の名前だ。
「まあ、お祖父ちゃんが若い頃の?」
祖母は目を細めてオルゴールのゼンマイを巻いた。か細く美しい「なき王女のためのパヴァーヌ」のメロディが流れて、メリーゴーランドが回り始める。
「懐かしいわ」
祖母はうっとりとして、飽きないで何度もゼンマイを巻き、メリーゴーランドを見つめた。
第二章 夜の遊園地
摩周は帰ったが、千紗はその夜、祖母の隣りに布団を敷いて眠りについた。
ふと気がつくと、暗闇の中に華やかな光を放って遊園地サイズのメリーゴーランドが布団のかたわらに出現しているではないか。
(いつの間に遊園地に来たのかな)
メリーゴーランドの側にはひと気がないが、明々とライトが灯されて眩しい。
よく見ると、仔馬やイルカ、ウサギ、いろんな動物の鞍の上に、それぞれ色んな衣装を着たピエロたちがまたがっている。カラフルな衣装のピエロもいれば、モノクロの角を生やし、不気味な黒い大きな唇のピエロもいる。
「あ、あなたたちは?」
彼らはへらへら笑うばかりで何も答えない。
白い馬車には誰も乗っていないようだ。
千紗はパジャマのまま、そっと馬車に乗ってみた。真紅のビロウドの絨毯(じゅうたん)が敷かれているが――、
(座席がない? 真っ赤な床だけ? 変な馬車ねえ)
そこへ、乗り込んできたのは摩周ではないか。着物に袴姿で昼間と同じ格好だ。
「私は正座の勝負師だ。君は参加者か?」
「正座の勝負師? 何のこと? 摩周にいちゃん」
摩周は千紗を見ても反応を示さない。
「今からメリーゴーランドを回す。馬車の中で、ちゃんと正座ができるかどうかの試験をおこなう」
「何、言ってるの、摩周にいちゃん」
「気安く呼ぶな。私は正座の勝負師だ」
無表情で繰り返す。
「ここにいるピエロたちは、完璧に正座の所作ができるぞ。娘、お前は何の心得もなさそうだな。正座の所作を覚えてもらおう」
「正座の所作?」
「真っ直ぐ立ち上がれ。身体の芯を中心に持ってくるつもりで。それができたら床に膝をつく。着物をお尻の下に敷き、かかとの上に座る。できたか? ――ダメだ、やり直し!」
いつもとは違う厳しい口調で、何度もやり直しさせられた。ピエロたちが笑っている。
千紗は言われるまま所作を繰り返し、ようやく摩周が言った。
「一応、正座は所作どおりできるようになったな。次は台を回転させるぞ。回転する馬車の床で正座ができるかどうかの稽古だ」
メリーゴーランドがゆっくりと回り始めた。ピエロたちは木馬や動物たちから下りて、台上で正座の所作を始める。回転台が、だんだんスピードを増していく。
「きゃあっ! こんな速さじゃ正座するどころか、立つこともできないわ!」
馬車の床に伏せて辛抱する。どうにか膝で立ち上がり、窓わくにつかまるのがやっとだ。
摩周がギアを引いて回転を止めた。千紗は肩で息をしていた。
「さっさと立て! 一回も正座が出来なかったな。これでは正座勝負できないぞ」
「頼んでないのに勝手に正座の所作を教えて、メリーゴーランドを回転させて、摩周にいちゃん、どうしちゃったの?」
第三章 謎の少女
紫色のサテンのドレスを着た少女が、静かに馬車に乗りこんできた。十四、五歳だろうか。輝くプラチナブロンドの巻き毛がふさふさしていて、厳しい眼で千紗を見つめて唇は引き結んでいる。
摩周が心得ていたように声をかける。
「刻音(ときね)、どうだ、さっきの回転で正座して、座礼は何回できた?」
「二十回」
千紗は耳を疑った。さっきの激しい回転中にそんなに沢山、正座して座礼ができたとは。いったいこの少女は?
「刻音はお前の正座勝負の相手だ。強敵だぞ」
「正座の勝負?」
正座の回数を勝負するなんて! メリーゴーランドに乗ったまま!
(ここはどこの遊園地? 摩周にいちゃんは様子が変だし、それに、どうしてメリーゴーランドの中で正座するの?)
千紗は気がついた。
(これは現実じゃない、夢なんだわ。そうよ! 目覚めたら、こんな変なもの全部吹き飛ぶわ!)
千紗は一生懸命に目覚めようとした。祖母の声が聞こえてきた。
(千紗ちゃん、千紗ちゃん、苦しいの? しっかりして)
ようやく目を開けると、机の上にあったオルゴールのメリーゴーランドをまともに見てしまった。
「きゃあ――!」
「千紗ちゃん!」
祖母が細い身体でつつむように抱きしめてくれた。
「夢を見ていたのね」
「夢……、苦しい夢だった。メリーゴーランドのオルゴールと同じ大きなものが知らない遊園地にあったわ。ピエロがたくさん乗りこんでいて、摩周にいちゃんがメリーゴーランドを回転させ始めて……」
千紗は汗びっしょりのまま説明した。
祖母が温かいお茶を淹れてきてくれた。
「落ち着いて。これをお飲みなさい」
「そうだ、知らない女の子もメリーゴーランドに乗ってきたの」
千紗は祖母にしがみついた。
「可哀想に。よほど怖かったのね」
玄関の戸がガラリと開いて、摩周がふたりのところへやってきた。
「ごめん、ごめん。千紗に怖い夢を見させてしまって」
あっけらかんと笑っている。
第四章 夢の後
祖母が、やや厳しい声で、
「正座は心を穏やかにするための座り方です。摩周くん、必要以上に厳しくお稽古をつけてはいけません」
「お祖母ちゃん、どうして私の夢の中のことを?」
千紗は驚いた。
「私も同じ夢を見ていたのよ」
祖母は落ち着いて言う。
「きっと亡くなった周五郎さんが、たまにはメリーゴーランドを思い出してやってくれって見せてくれた夢でしょう」
祖母の頬がほんのり紅い。今も祖父を愛していて、思い出に浸っているのだろう。
「ちょっと疲れたから横になるわね」
寝床に戻る祖母に、千紗は手を貸した。
「朝から騒いでごめんなさい。ゆっくり横になってね」
祖母を寝室でひとりにして、千紗と摩周は居間に移動した。
「どうして、お祖母ちゃんは私と同じ夢を見れたのかしら」
「僕がそうしたんだ」
摩周が答えた。
「大学の妖怪研究会で夢操り(ゆめあやつり)の、ちょっとした手法を学んだんだ」
「妖怪研究会だなんて気味が悪いわ。もう二度と怖い夢を見せたりしないでよ」
「そうもいかない。お祖母ちゃんの体調が良くないのは、メリーゴーランドが関係してるんだから」
「何ですって?」
「オルゴールのメリーゴーランドを長い間、物置に放ったらかしにしてあったから、九十九神が生まれて不満を持って、お祖母ちゃんの体調を狂わせているんだ」
「九十九神?」
「百年以上経った古い物に発生する妖怪だ。カタチになってるのは、紫の服を着たプラチナブロンドの刻音という少女だ」
「ああ、あの子!」
「とにかく、お祖母ちゃんを元気にするために、九十九神をおとなしくさせなければ」
「それで、正座をピエロたちにも教えたのね」
「正座は気分を浄化してくれるからな。所作は、中学時代にばっちりお祖母ちゃんから習った。ま、お前にメリーゴーランドの中で正座させたのは、やりすぎだったけどな」
摩周が舌をペロリと出して言ったので、千紗は頭に来てしまった。
「ひどいわ! ふざけたのね!」
第五章 刻音の執念
その夜、千紗の夢に紫のドレスを着た刻音が再び現れた。
黒い小さな帽子を頭に乗せて、チュールレースが顔を半分隠している。
「許さないわ。周五郎さんが私を英国で買ってくれたのに、大切にしないで物置きに入れっぱなしにして……」
憎しみの炎を燃やした瞳で睨みつけてくる。
「私は周五郎さんが大好きだったのよ。ずっと一緒にいたかった。なのに、薄暗い物置きに長い間閉じこめてしまって。――だから、貴女の祖母を弱らせてやったのよ」
「それは、あなたの勝手な嫉妬じゃないの。人間は『もの』とは結ばれないわ。落ち着いてちょうだい。長い間、物置きに放っておいたことは謝るから」
「いえ、許さない。祖母の病気をもっと重くしてやるわ!」
「やめて、お願い」
千紗は頭をめぐらせた。この少女の憎しみと嫉妬の炎を消し去るには――。
(やっぱり正座だ! 正座の所作をして落ち着いてもらうしかない!)
そこで目が覚めると、枕元に祖母が座っていた。
「千紗ちゃん、また怖い夢を見たのね」
祖母にはお見通しのようだ。
「刻音という少女のことを、お祖母ちゃんは知っていたんじゃないの?」
祖母はうなずいた。
「ええ。ちょっと『困ったちゃん』な九十九神だってことも分かっていたわ。でも、ここまで憎まれていたとは……」
「摩周にいちゃんが、偶然、妖怪研究会とかに入って気がついてくれたのね」
「そのようだね。あの子は、亡くなったお祖父ちゃんに好みがよく似ているから、九十九神のことも気づいてくれたのじゃないかしら」
顔をしかめる祖母を見て、千紗は思いを巡らせた。
(このまま、刻音って子の思う通りに祖母の身体を弱らせるわけにはいかない。あの娘の憎しみと嫉妬を鎮めなければ……)
「お祖母ちゃん、お願い! お祖父ちゃんから習った正座の所作を教えてちょうだい」
「どうしたの、いきなり」
「お祖母ちゃんを守るためなの」
祖母は大きくため息をついた。
「教えたいのはやまやまだけど、しっかり立ち上がることもできないからねぇ」
「無理させて、身体を弱らせては本末転倒だわね」
千紗は唇を噛みしめた。
「何を悩んでるんだ、ふたりとも! 正座のことなら、俺がいるじゃないか」
先日の夜明けと同じように摩周がやってきていた。
「ああ、驚いた。あなた、本当にお祖父ちゃんによく似ているわ」
「でも、お祖父ちゃんそっくりの摩周にいちゃんから正座を習ったと知れれば、刻音っていう子の心を逆なでしてしまうわ」
「刻音は嫉妬深いが、素直な面もある。こちらが親切に根気よく正座につきあってやれば気持ちは通じるだろう。千紗、一緒に稽古して話し相手になってやってくれ」
(なんだか、この前メリーゴーランドで、厳しく正座させた摩周にいちゃんとは別人みたいに優しいわ)
千紗は、祖母を元気にするために、摩周の言う通りにすることにした。
第六章 ワルツ
次の夢は、異国の夕暮れの街角から始まった。しっとり濡れた石畳の通りに等間隔に並ぶガス燈が、飴色の光を放って美しい。千紗はそんな橋のたもとに立っていた。
ガス燈の点灯夫が、やっと最後のひとつに光を灯した。
どこからともなく刻音が歩いてきた。
「刻音、来てくれたな」
千紗の背後に、摩周も現れた。刻音は照れ臭そうにもじもじした。
「貴方が骨董品店で私を買ってくれた夕暮れとそっくりな景色だわ。霧がかかってロマンティックね」
(昔に私を買ってくれた? ってことは、この人は摩周にいちゃんじゃなくて、もしかして……?)
千紗はふたりを交互に見つめた。まるで欧州へ渡った留学生と、お人形だ。
「行くぞ、ふたりとも。正座の稽古だ」
摩周は石橋を渡り、ふたりを小さな教会へ連れて行った。
こじんまりした聖堂に入ると、マリア像のかたわらにピアノが置かれている。
摩周は慣れた様子で座り、鍵盤に両手を置くと、なめらかなメロディを奏でた。
千紗と刻音はうっとりと聞く。
曲を弾き終えると、摩周はメリーゴーランドのオルゴールを取り出してゼンマイを巻いた。先ほど摩周がピアノで弾いた曲が流れ始める。
「お前のために作ったワルツだよ、刻音」
刻音は赤い唇の口角を上げて、にっこりした。
星屑のかけらが舞い散るように、繊細な音色がオルゴールから響く。
メリーゴーランドのユニコーンや動物たちが、軽やかに回転し、またがっているピエロたちも歌ったり、帽子を投げたり、指笛を鳴らしたりしてはしゃいでいる。
千紗は夢の中と分かりながら、夢ならではの世界を楽しんだ。
(おとぎ話の世界にいるみたい……)
摩周が刻音の手を取った。
「踊ろうか」
リードしてステップを踏み始める。小柄な刻音は長身の摩周に伸び上がるようにして、一生懸命にステップについていく。
「はい、次は千紗の番」
「ええ? 摩周にいちゃんと踊るの?」
「そんなイヤそうな顔するなよ」
「小さい時から知ってる摩周にいちゃんと踊るなんて、照れ臭すぎ……。できるかな?」
「自然な流れで踊ればいい。はい、俺の手を取って」
「仕方ないなあ、踊ってあげるわよ」
(でも、なんだか……?)
心の中にくぐもっている何かが分からないまま、ぎこちなくステップについていく。
刻音の眼が、黒いチュール越しにねっとりと見つめている。
第七章 木っ端微塵(こっぱみじん)
ダンスが終わり、摩周がもう一度オルゴールのゼンマイを巻いた。
「いよいよ正座の所作の稽古を始めるよ。さあ、背すじをしゃんとして立ったら、床に膝をついて。柔らかな絨毯だから痛くないだろう?」
千紗と刻音は同じ所作をした。
「次はスカートの裾をお尻の下に敷きなさい。刻音のスカートはフリルがたくさんあるから、人様のじゃまにならないようにちゃんと敷いて。千紗は普通のスカートだから大丈夫だね」
ガタ―――ン!
激しい音と共にオルゴールが床に落ちた。メリーゴーランドの細かい細工の木馬やイルカやブタやウサギや支柱が、床に木っ端微塵になってはじけ飛んだ。
それでもまだ、メロディは鳴り続けている。
「ああっ、オルゴールがバラバラに!」
千紗が叫ぶ。気づくと刻音が瞳をらんらんとさせていた。
「何よ! どうせ、私のスカートは人のじゃまをするびらびらした低俗なものよ」
刻音のヒステリーな思いが、メリーゴーランドを床にはじき飛ばせたのだ。
「刻音、そんなことは言っていない。少し注意すればいいことだ。さあ、おとなしく所作の続きをしなさい」
オルゴールのメロディが不協和音を奏ではじめた。歯車がギシギシと鳴りだす。ユニコーンたちが立ち上がり、教会の床をあちこち走り回る。ピエロたちも悲鳴をあげている。
「な、何? どうしたのかしら?」
「いけない、千登世が苦しんでいる! 早く夢から覚めなければ!」
摩周が叫んだ。
「千登世? お祖母ちゃんをそんな呼び方するのは……」
次の瞬間、千紗と摩周は祖母の寝床のかたわらにいた。
祖母が苦しそうな呼吸をしている。
「病院へ運ぶぞ!」
摩周が叫んだ。
第八章 祖母のお稽古
散らばったオルゴールの紳士のシルクハットから、白いうさぎが顔を出して、やにわに言った。
『私は病院に行かなくて大丈夫よ。それより刻音さんに、今一度、正座のお稽古を!』
うさぎの口を借りた祖母の声ではないか。
「お祖母ちゃん、本当に大丈夫?」
千紗は、床にかがんでシルクハットのうさぎに耳を寄せた。
ピエロたちが、一斉に笑いはじめる。
『お前のお祖母ちゃんは無理をしてる』
『本当は苦しいけど、強がり言ってるのさ』
けたたましい笑い声がはじける。
『お黙りなさい、あなたたち!』
祖母の声がぴしゃりと言う。
『私はどれだけ憎まれてもかまわない。でも、周五郎さんのことを許してもらわなければ。物置きに入れっ放しにしていたことを謝ります。私が摩周くんに代わって正座をご指導するわ』
うさぎは引っこみ、祖母は寝床から起き上がろうとした。
刻音が祖母の前に座った。
「千紗ちゃん、手を貸して立たせてちょうだい」
額から汗をしたたらせながら、祖母は立ち上がった。
「真っ直ぐ立てている?」
「ええ……」
刻音も祖母に合わせて真っ直ぐに立った。
「では膝を床に着きます。スカートに手を添えてお尻の下に敷いて、かかとの上に座ります。できましたか、刻音さん」
刻音はおとなしくうなずいた。
「フリルがいっぱいのスカートもちゃんと敷けてるわ。よくできましたね」
祖母は膝の前に指をついて深々と頭を下げた。
「長い間、貴女を物置きに入れたままにして、本当にごめんなさい。二十年前に周五郎さんが急な病で亡くなってしまい――、思い出すのが辛くなって、そのままにしてしまったのです。あんな薄暗い湿っぽい部屋に――」
祖母の眼に涙があふれ、千紗がそっとハンカチをあてた。
「どう? 正座していると、オルゴールのメロディが聞こえてこない? あなたが周五郎さんとワルツを踊った時の――。懐かしくて心が甘酸っぱくならない?」
「……」
刻音の濃いまつ毛が伏せられ、耳をすませている。
第九章 刻音の回想
「私を作ったオルゴール職人は……」
刻音がゆっくりと話しはじめた。
「出来栄えが――、人形の私の座り方が納得できないと言って、裏街のゴミ箱に捨てたの。暗くて寒くて……ジメジメしていて、生ゴミの肉や魚や野菜の切れっぱしがジロジロ見つめて、恐ろしい場所だった。そんな時、骨董品店のあるじが私を見つけて、拾ってきれいに拭いて、自分の店のショウウィンドウの片隅に置いてくれたの」
「まあ、そんな怖い経験を」
千紗と祖母は神妙に聞いていた。
「それから長い間、私は売れ残っていた。ある日、通りのガス燈に明かりを灯す(ともす)点灯夫が歩き回る時刻になると、私を見に来る東洋人の学生さんがいることに気がついた。決して店に入らず、ショウウィンドウの外から眺めるだけだけど、あるじは察して、ゼンマイを巻き、メロディを聞かせてあげたりしていた」
「優しいあるじさんね」
「何か月かして、学生さんが息を切らせて走ってくると、初めてガラスの扉を開けて奥のあるじの元へ直行して――、『ショウウィンドウの片隅にあるメリーゴーランドのオルゴールをください! やっと窓拭きの賃金が貯まったのです!』と言ったの」
千紗が興奮を隠せずに、先に、
「それが祖父――、周五郎お祖父ちゃんね?」
「いやあ、そんなこと思い出されると照れるなあ」
女性たちの背後で摩周が、頭をかきながら小声でもらした。
「摩周にいちゃん! 変だと思っていたら、摩周にいちゃんの身体を借りてるのは……」
「しっ!」
摩周は人差し指を唇の前に立てた。
刻音は話を続ける。
第十章 窓辺の思い出
「周五郎さんは、下宿に戻るとメリーゴーランドを机の上に置いたわ。さっそくゼンマイを巻いてメロディを聞きながら、ぐるぐる回るユニコーンや動物たちを、瞳を輝かせて眺めた。狭い部屋ひとつ。机とベッドと小さな本棚だけ。食事はどこでいただくのだろうか? と思ったり」
「床がギシギシと音をたてる天井の低い建物だけど、小さな薪ストーブがあって、夜には明々とオレンジ色の炎が部屋を温めてくれた」
「昼間はプラタナスの葉に触れられそうな窓辺にメリーゴーランドを置いて、葉みどりに染まりながら、馬車の中の小さな私と目を合わせた」
『お前はこの国の職人が作ったんだろうに、どうして正座をしているのかな?』
「(正座? 正座って何だろう?)……くらいにしか思ってなかったけど、私を捨てた職人が、うまく作れないって異国語でブツブツもらしていたわ。メリーゴーランドやユニコーンたちはブリキでできているけど、私の身体は針金を芯にした布でできているの」
「周五郎さんは、毎夜、祖国に残してきた婚約者の千登世さんのことを話したわ。『きっとメリーゴーランドとお前を気に入ってくれると思うんだ。細かい作りやメロディや、刻音のノーブルな顔立ちも座り方も、きっと彼女の好みだ』……ってね」
「彼が千登世さんを大好きなことが、よ~く分かってきた。もちろん妬けたけど、私は千登世さんという女性がどんな方だか知りたくなっていった」
「写真を見せてもらった。色白の美人さん。日本の行儀作法がちゃんとできて、着物という民族衣装を美しく着こなしている。座った姿が、私の馬車の中の座り方と同じ、正座だということを周五郎さんから教わった。ますます千登世さんに会いたくなった」
(憧れと嫉妬がない交ぜになった感じかな)
千紗はそっと思った。
「周五郎さんの愛する女性を見届けて、自分の方が優れていると確かめて優越感に浸りたかったの。でも――、いざ、周五郎さんと一緒に日本に来てみると、千登世さんは、私のような小娘の足元にも及ばない大らかで素敵な女性だった。私は打ちのめされた――。静かに見守ることにした。やがてふたりは結婚した。豊かとはいえないようだったけど、希望にあふれた新婚夫婦だった」
「歳月は流れ、周五郎さんは建築設計の仕事も順調で穏やかな日が続いた。ふたりの子どもが生まれてすくすく育った。そんな矢先だった。周五郎さんが病魔に侵されたのは」
第十一章 紫の座布団
「周五郎さんはみるみるうちに痩せていった。ふたりの子どもたちは、まだ学生。千登世さんは慣れない通いの女中の仕事を始めて、入院した周五郎さんの元へも通い、夜には着物の仕立ての仕事をして生計にあてた」
「その間も、ずっと刻音さんは居間で私たちを見守っていてくれたわね」
祖母がしみじみ言った。
「見守ってくれた?」
「ええ。可愛い貴女がメリーゴーランドの中から見守ってくれたから、私はがんばれたのよ」
「そんな風に言われるなんて……」
刻音は戸惑っていた。
「今、気がついたわ! 最初にロンドンの裏町のゴミ箱から助け出してくれた骨董品店のあるじ、それから周五郎さん、今回も、物置きから出してくれた千登世さんたち。私は九十九神でありながら何度も助けられて、今、ここにいるんだわ。いくら感謝しても足りないわ」
刻音のつぶらな瞳から大粒の真珠がぽろぽろと落ちた。
「正座のお稽古で、あんなにヒステリー起こして、メリーゴーランドを床に落としてしまってごめんなさい。千登世さんを病気にしてやるなんて言ってしまってごめんなさい!」
摩周が、刻音の頭ごと胸に抱き寄せた。
「ごめんなさい、を言う時は?」
「あ、そうだったわ」
刻音は急いで床に膝をついた。
祖母が枕元の風呂敷包みを引き寄せた。
「刻音さん。これを使ってちょうだい」
包みから紫のサテン地の座布団というか、クッションが現れた。周りを黒と白のレースが縁どっている。
「これは……?」
「あなたが正座する時に、使ってもらおうと思って、縫っていたの」
「まあ! なんて素敵なゴスロリ座布団! 刻音さんのドレスにぴったりだわ」
千紗が思わず叫んだ。
「お祖母ちゃんたら、これを作っていて疲れたんでしょう」
「これくらい平気よ。さ、刻音さん、使ってみて」
刻音は胸がいっぱいになったのか、唇を震わせながら紫の座布団を抱きしめた。しばらく顔に押しつけてから、立ち上がって正座の所作を最初から始めた。ゆっくり座り、指をついて頭を下げた。
「ヒステリー起こしてすみませんでした」
「所作がお見事よ。こちらこそ長い間、物置きに入れたままですみませんでした。この小さな座布団はメリーゴーランドの中で座る時に使ってくださいね」
ハンカチを四つ折りにしたくらいの可愛いサイズの紫の座布団を渡す。
「なんて可愛い!」
オルゴールから親指ほどの白いうさぎが跳び出してきて、座布団をくわえて戻っていった。
摩周は、正座して謝りあうふたりを見て、
「やれやれ、千登世お祖母ちゃんの不調は、裁縫に夢中になっていたからだろう。根を詰めちゃ駄目だよ。刻音も、『かまってちゃん』を卒業しなさい」
千紗がため息まじりに、
「確かに九十九神って、『かまってちゃん』だわね。でも、持ち主が察してあげなくちゃ」
「物」にも魂があるってことを、身をもって知ったのだった。
「ね、お祖父ちゃん」
摩周に微笑んでみせた。
「千紗、お前……」
「分かるわよ。中身がお祖父ちゃんだってことくらい。私に厳しくお稽古つけたのは摩周にいちゃんで、それ以外はお祖父ちゃんなんでしょう。――いったいどうやって?」
「例の妖怪研究会で『成り切り』って妖怪の術を借りたんだよ。お祖父ちゃんの霊が降臨したわけじゃない」
「あら? つまんない。せっかくお祖父ちゃんとお祖母ちゃんを再会させてあげられると思っていたのに、がっかりだわ」
刻音が進み出て、
「千紗さん。心配ないわ。千登世さんは、周五郎さんと今もしっかり心が結ばれているから。――じゃあ、オルゴールを組み立てて、私は帰るわ」
――ふと、刻音の持つ特有の空気が消えた。
メリーゴーランドは復活したのかどうか、それきり刻音は姿を現さなくなり、祖母も元気を取り戻した。
春爛漫のある日、縁側に正座する千登世さんの耳に、かすかにオルゴールの音色が流れた。風に乗って流れる桜の花びらと共に――。



![[208]正座フェロモン・夢好(ムスク)](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)