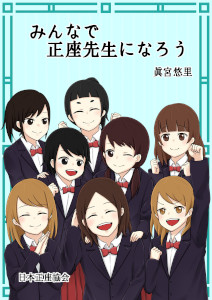[292]お江戸正座7
タイトル:お江戸正座7
掲載日:2024/06/06
シリーズ名:お江戸正座シリーズ
シリーズ番号:7
著者:虹海 美野
内容:
文五郎は茶葉を売る諏訪理田屋の五男である。
真面目に店で働いていたが最近ほかの兄弟と比較し、気落ちしていた。
気晴らしに行った茶店で、いつもと違う茶が出たことで落胆する文五郎だったが、正座をして茶を飲んでいたおゆうという娘が茶の味が違うと店主に指摘するのに遭遇する。
文五郎は間に入り、うちの店にいつもの茶があるとおゆうを誘う。
おゆうが遠縁の娘だとわかり二人は向かい合って正座をし、互いの心の内を話し……。
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
1
文五郎は、茶葉を売る諏訪理田屋の五男である。
長男は店を継ぎ、所帯を持ち、子にも恵まれた。
次男は暖簾分けをし、家を出た。
文五郎の家は、先に挙げた長男、次男の下に、三男の文三、四男の文史郎、そして文五郎、その下に六郎、末っ子の文左衛門がいる。
末っ子の文左衛門は、生粋の江戸っ子ではあるが、諏訪理田屋の兄弟の中でただひとり、いつも何か考え事をしているような様子で、ちゃきちゃきと周囲を見ながら動いてお客に笑顔で駆け寄るお商売というものに不向きなようであった。その末っ子も十九の時に戯作者になると師の元に弟子入りしてそのお宅でお世話になった後、一人暮らしを始め、少し前に戯作を発表した。戯作者の名に、店と同じ諏訪理田を名乗ったあたりは、一応店のことを本人なりに気にかけていたのか、という思いがした。
末の弟のそんな気遣いに、ほんわかと心温かくなる一方、文五郎は昔から自分は損な性分であるという気がしていた。
長兄は諏訪理田屋の跡取り、次男も暖簾分けという将来があった。
その下の兄弟は店で手代の立場で働いている。
店主の長男を除けば、文三がこの店を仕切る場が多く、それに次ぐのが文史郎であった。この長男、次男に文三、文史郎は子どもの頃から何かと文五郎に命令した。
幼い頃は遊びに行った先で何か必要になれば、年の近い文三、文史郎が文五郎に取って来いと言いつける。稽古事に兄弟で行けば、長男、次男が、自分たちだって出かける直前に『ちょっと待て』と偉そうに言いながら、厠に行って弟を待たせる。そのくせ、やたらと文五郎には迷惑をかけるな、早く支度しろと前日から口うるさい。年の近い、すぐ上の文史郎だってそう言われそうなものだが、妙に要領がよいというか、何食わぬ顔で支度も素早くしているし、兄たちに何を言われても物おじしないし、暖簾に腕押しといった具合で、恐らくは無自覚のまま、兄たちから受けるある種宿命的なものを交わしているように見えた。そのくせ、文五郎に命令はするんだから、腹立たしいのを通り越して、あっぱれな性格である。男ばかりの家の真ん中に生まれるのに、大層適した性分とも思える。
そうして、文六、文左衛門と下の弟二人が物心つきはじめ、いざ文五郎が兄の立場になった時には、長男、次男、文三、文史郎は剣道だ、稽古事だと忙しくなり、そうすると、弟の文六、文左衛門の世話は文五郎の役目だった。だから、文三、文史郎は文五郎に威張り散らしておく立場のまま、うまい具合にその下の弟の面倒を見ずに大きくなった。兄弟の真ん中に生まれたのは同じでも、ほんの幾つかの年齢差で、随分と待遇も違うものである。
文五郎は幼い弟にこれといって威張ることも、何か遣いを頼むこともなく、ただただ面倒を見るだけだった。おまけに文六は算術が得意、文左衛門は読み書きに大層長けており、手習いで二人は入った当初から褒められており、なんとなく、文五郎は自身の影が薄いのを感じ取った。そのくせ、手習いに行く時には、必ず二人を連れて行き、忘れ物だ、厠だと、細々した面倒は全て文五郎が見て来た。それを恐らく文六も文左衛門も覚えてはいない。そうして、長兄も次男も三男も四男も、昔文五郎をいいように使ったことを忘れている。時折思い出して文句を言おうものなら、一体いつの話をしているんだ、今お前が安泰のお店で何も困らずに決められたことだけをやって恵まれた暮らしができているのは、お前の兄たちがいてこそだと咎められる。
それでは納得がゆかない。
あの時不条理な思いをし、それが解決できぬままここまできたから言っているのに、ここ最近の話で打ち消すというのは、やや乱暴な話ではないか。
おまけに文五郎は二十を三、四年も過ぎているのに、未だお店の仕事で一日が終わる。
長兄も次兄もご新造さんがいて楽しそうにやっているし、末の弟に至っては、まだ十九かそこらで一人暮らしを始めたというではないか。
文五郎にいちゃん、文五郎にいちゃんと、いつも不安そうに追いかけて来る末の弟。その間に立ち、文五郎兄ちゃん、また文左衛門がついて来てないよと、冷静に言う文六。あたふたと駆け寄る文五郎。思えば文五郎だって、十くらいの子どもであった。子どもによっては、文五郎より年上でも、妹や弟の立場で兄や姉に守られ、面倒を見てもらっていた。
嗚呼、やはり不条理だ。
ようやく昼餉の刻限になり、文五郎は奥へと引っ込む。
その時、先に飯を済ませた文三が、「昼からも忙しいから早くしろよ」とごく当然といった顔で言った。
自分は先に飯を食ったくせに。
その間店に立っていた文五郎にねぎらいの一言もないのか。
文句を言えば、そんなことは十も承知だ、兄弟だからこそ、気兼ねなくものが言えるとか、言わなくとも感謝が伝わるのが兄弟だとか言い出すのは目に見えている。それがでまかせでないのも知っているが、やはり文五郎は少々苛立っていた。
昼餉をかきこみ、すぐに店に出ようと思ったが、厠へ向かう振りをして、裏の戸から外へ出た。
そうして晴れた空を久しぶりに見て、伸びをひとつすると、足取り軽く、近所の茶店へ向かった。
諏訪理田屋で茶を買っている店で、たまにはいいか、と意気揚々と外の縁台に座り、看板娘に茶と団子を所望した。
そうして運ばれてきた茶を啜る。
人に淹れてもらう茶というのは、普段お客に新茶です、おすすめですと、忙しくも細心の注意を払って淹れて出す側にとって、大層贅沢に感じられる。
味も香りも知っている茶を飲んで一息、と文五郎は考えていた。
ここで気晴らしをすれば、また頑張れる、そういう心持ちであった。
ところが。
飲んだ茶は、うちで買っているものではなかった。
湯呑の中の緑も明らかに薄い。
出がらし、というのではなさそうだ。
それは茶の香りと味でわかる。
二番煎じ以降の茶は、ぬめったような味がすると文五郎は感じる。
あの温かく、包むような感覚に、一本筋が通っているようなしっかりとした味が茶にはあるものだ。この茶もそうしたしっかりとした味を伝えてはいる。
だが、これはうちの茶ではない。
まあ、うちで買った茶を必ず出す、という約束があるわけでもない。
この茶はこの茶でよいのであろう。
だが、文五郎が期待した味とは違った。
茶の種類を掲げてのお商売ではないのだから、勝手に期待するのがお門違いというものだ。
それは承知の上だが、何やら心がしおしおと、元気をなくした菜っ葉のようにしぼんでいくのを感じた。
文五郎は気落ちし、団子を食っていた。
その時、奥の座敷から、「このお茶、いつもと違いますね」という鋭い娘の声がした。
「ああ、そうだっけ」という店主の声。
「いつものお茶の方がここの団子に合います。せっかくの団子の味も損なわれるようで、残念です」
ずいぶんとはっきりとものを言うお嬢さんだ、と思った。
「お勘定」と文五郎は告げながら、それとなく、座敷を見遣った。
大層よい着物に刺繍の施された帯、豪奢な簪を挿した、少々失礼だが、この安い茶店には不釣り合いなお嬢さんが、背筋を伸ばし、豪奢な着物をきちんと尻の下に敷き、足袋を履いた足の親指同士をつけ、膝ももちろんきちんとつけ、脇は軽く開く程度の正座をし、安い湯呑を手に、まだ言い足りない、といった様子で店主を見ている。
なんとなく、まずいな、と文五郎は思った。
ほかの客の前で茶の味にけちをつけられては、店主もいい気分はしないだろう。
「お嬢さん、ここはいろいろな方が息抜きをする大切な場です。よろしければ、お望みのお茶を私がご馳走しますよ」
そう言って、文五郎はこのお嬢さんの分のお勘定も済ませると、そのまま「さあ、さあ」と茶店の外に連れ出した。
「なんなんです」と、通りまで来たところでお嬢さんが立ち止まった。
「ああ、すみません。なんだか見ていられなくて。お茶をお出ししますと言ったのは本当です。私はこの先の茶葉を売っている諏訪理田屋の息子です。いつもあのお店で飲むお茶でも、ほかのお茶でも淹れて差し上げます」
「諏訪理田屋さん……」と、娘は暫し、その名に何か考えを巡らせた様子で、「あ」と顔を上げ、しげしげと文五郎を見る。
「ご存知でしたか? 諏訪理田屋さんの大旦那のおかみさんの弟さんの奥さんのお兄さんが、諏訪理田屋さんに昔奉公して、その後暖簾分けをしてもらったんです。その大旦那のおかみさんの弟さんの奥さんのお兄さんというのが、うちの店の先代、つまり祖父です」
「え、そうだったのですか」
大旦那、つまり文五郎の祖父のおかみさん、文五郎の祖母の弟、大叔父の妻、大叔母の兄……。かなりややこしい。遠い親戚ではあるが、文五郎と直接血のつながりはない、昔の諏訪理田屋の奉公人、恐らく番頭まで勤め上げたお人というのが、目の前のお嬢さんの祖父ということだ。
「うちは、この少し先です。すぐ傍に饅頭や団子を売っているお店と羊羹を売っているお店があって、裏通りは住居ですから、一度に大量の茶葉を買う人はおりませんが、定期的にお客さんが来るので、お店の方は順調です。今日はこの先にある踊りの師匠のところへ行った帰りです。もともとはうちの近所にお住まいだったのですが、転居されて、こちらまで習いに来ております」
「そうですか。いやはや、こんなところでお会いできるとは……」
先ほど茶が期待していたものと異なり、消沈していた心がまた浮上した。
しおしおの菜っ葉がしゃきん、と元気になったかのようである。
「ささ、ではよろしければ、うちでお茶を召し上がりませんか。そちらのお店では今どんな茶葉を仕入れていますか? ぜひうちの自慢の茶を召し上がってください」
文五郎はいそいそとお嬢さんを連れ、店に戻った。
「文五郎はどこで油を売ってる!」と怒り心頭の長兄の怒鳴り声が外まで聞こえたが、文五郎の連れて来たお嬢さんを見るなり、すっとその怒りを隠した。
「文五郎、お前、どこにいた……。これはこれは、おゆうさん。随分と久しぶりですな。みなさん、息災ですか」と尋ねた。
おゆうというのが、このお嬢さんの名らしい。
この様子だと、親戚での祝い事か何かで、長兄は以前からおゆうと面識があったらしい。
「今日は突然伺い、すみません」とおゆうが詫び、「ついさっき、偶然お会いして、こちらにお連れした」と文五郎がしらっと続ける。
おゆうが上品な笑顔で、「茶店でいつもの茶葉ではなく、つい私がきついことを申してしまいましたら、文五郎さんが間に入ってくださいました」と説明する。
茶店、というくだりで長兄の目がふっと変わったが、おゆうの手前、「そうでしたか、そうでしたか。では、うちでどうぞ、ゆっくりしてらしてくださいね」と笑顔で応じ、「家の床の間を使え」と、すれ違いざま文五郎に言い、長兄は足早に店に入って行った。
2
「突然すみません」と尚詫びるおゆうに、「ささ、どうぞ。誘ったのは私です」と座布団を勧める。
座敷に上がる際も、おゆうの所作は大層美しかった。
座布団に正座をする際には、袖や裾に気を付け、着物をきれいに尻の下に敷き、膝をつけ、足の親指同士が離れぬようにし、脇を締め、手は太もものつけ根と膝の間に指先同士が向き合うように揃えられている。
文五郎は鉄瓶で湯を沸かし、頃合いを見て、丁寧に茶を淹れる。
ひとつはいつも茶店に卸している茶。そうしてもうひとつは今年おすすめの新茶を淹れた。
「どうぞ」と盆でお出しし、菓子も添えた。
茶を点てる席では先に菓子を出すのだが、今回は茶店で菓子とともに茶をいただくように、茶と一緒に菓子を食べてもらおうと思った。
一緒に淹れた自身の茶と菓子を前に、文五郎もおゆうの向かいに正座する。
一応諏訪理田屋の息子は全員、手習いの後、お稽古にも通っている。
礼儀作法も簡単にではあるが、教えられた。
しかしここのところ、仕事仕事で何やら心に張りを失いかけていた文五郎は、自然と猫背になり、座り方も適当なものであった。さすがに足を投げ出さぬまでも、到底茶会などの席で通用するような座り方ではなかった。
ああ、そういえば、作法は長兄たちと一緒に習ったのだった……。
長兄が小声で「文五郎、背筋を伸ばせ。膝が離れすぎだ」と、師匠の見えぬところで注意してくれた。自身も習いに来ている立場であるが、あの場で一番下だった文五郎を長兄は気にかけてくれていた。
文五郎は背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、脇は軽く開く程度、膝は握りこぶし一つ分開くくらい、足の親指同士が離れぬようにし、手を太もものつけ根と膝の間に指先が向かい合うように揃えた。
足がしびれぬかとやや心配したが、大丈夫であった。
そういえば、あのお作法のお稽古で足がしびれた文五郎が立ち上がり際よろけそうになった時、それとなく支えてくれたのは次兄だった。
師匠に笑顔でたいへんよくできましたね、と褒められた時、「よかったなあ。これでお店でもちゃんとやっていける。文五郎がしっかり頑張ったって、お父ちゃん、お母ちゃんに言わないと」と、言ってくれたのは文三だった。
「緊張したな。だけど、文五郎が隣にいたし、しっかりしないとと思って、頑張れた。文五郎はもっともっと緊張しただろう」と慮ってくれたのは、文史郎であった。
「いただきます」というおゆうの声で、文五郎は我に返る。
「どうぞ。では私も」と、茶を飲む。
「ああ、美味しい」と、おゆうは言った。
「今日踊りのお稽古があって、明日はお三味線のお稽古があって。ああ、帰ってからまたおさらいをしないといけないと思ったら気が滅入りました。踊りにお三味線、私にとって好きなことであっても、それがお弟子さんの中で一番になれるかというのとは、また別なんです。それでなんだか自分が嫌に感じられて……。そんな時に飲みたかったお茶が出なかった。それでつい……。茶店のご主人にも悪いことをしました。明日、お詫びに行きます」
「そうでしたか」と、文五郎は呟くように言った。
「私はもうお商売きりで、ほかに何もございませんが、うちは兄弟が多く、なんだか最近、ほかの兄弟と比べて自分は、と妙に気分が沈みまして。そこで飲みに行った茶がいつもと違う。ますます悲しくなったところへ、おゆうさんがあのように店主に言っているのを見て、まるで私の代わりに言ってくれているようで、ついつい、口を挟みました」
初対面の、しかも自分より五、六歳は若いお嬢さんに何を言っているのだと思ったが、「お友達に話すと、弱みを見せるみたいで嫌だったけど、文五郎さんには話せました。それは文五郎さんが、人一倍、お優しい方だからですね。文五郎さんは立派にお店でやってらっしゃるのに、それを全然自慢なさらないでしょう。そのまま、正直でいられるのは、とても難しいことだと私は思うんです」とおゆうは言う。
「いやいや、私は度胸もなく、茶の味が違うとわかっても、何も言えません。おゆうさんのようなきちんと言えることこそが尊い」
互いに、相手がいかに優れているかを言い合った後、おゆうは菓子を懐紙の上で食べ、「ああ、美味しい」と、笑った。
『よろしければ私のも』と言おうとし、それを留めたところで、ふと思い出したことがあった。
おやつに兄弟一つずつもらった饅頭を、文六と、文左衛門が「文五郎にいちゃんに」と言って、くれようとしたことがあった。長男や次男、文三、文史郎が「おい、なんで俺たちじゃなくて、文五郎なんだよ」と、幼い弟二人に訊くと、「文五郎兄ちゃんはいつも自分のことより先に面倒を見てくれる」、「文五郎兄ちゃんは、急に厠に行きたいと言っても、茶をこぼしても怒らないで、厠までおぶって走ってくれたり、『熱くなかったか』って心配して拭いてくれる」と答えた。
そうだ。
そんなこともあった。
おゆうと会ってまだ間もないが、ふと心が温かくなると同時に、文五郎は、そうした幼い頃のことを思い出した。
3
もともと文五郎とおゆうが遠縁にあたること、おゆうの家はおゆうを筆頭に三姉妹であること、長年勤めていた番頭は故郷(くに)に帰ると決めたことなどから、文五郎が婿入りする二人の縁談は内輪でとんとん拍子に進んだ。
だが、諏訪理田屋の兄弟は、長男、次男が所帯を持ち、文三、文史郎の兄二人はまだ独り身である。
そのことを長兄に言うと、実は文史郎には、もう決まったお相手がいると言う。ただ、文三にまだ決まった相手がいないことから、そのことは今のところ長兄とご新造さん、文史郎、それに今回文五郎を含めた四人のみが店では知っているのだと教えられた。
「そうか、文三兄ちゃん……」と文五郎が呟くと、「なんだ、じゃあ、おゆうさんとの縁談を文三に譲るか」と長兄が訊く。
「駄目だ、駄目だ、駄目だ、それだけはあんちゃんでも許せない」
思わず大声を出した文五郎を、長兄は「冗談だ」と言って落ち着かせた。
「まあ、よかった。半分は家同士の結婚のような縁談だが、それだけ本気であれば、この先もうまくやっていけるだろう。それにお前さんは、誰よりも実直でお商売にひたむきだ。忙しい時でも落ち着いて、丁寧に客に向き合えるのはそうそうできることじゃあない。書き入れ時は特に頼りになる。手放すのが惜しいくらい、しっかりした商売人だ」
「あんちゃん……」
なんだ、見ていてくれたのか……。
気が抜けて、急に文五郎は目頭が熱くなった。
4
そうしたわけで、まだ祝言は挙げられないが、文五郎は時折おゆうの家に赴き、そのお店でのお商売を少しずつ手伝い始めた。
一度、おゆうの家に行く前に、二人であの茶店に寄ったのだが、店では『茶にうるさい茶屋の二人』とすっかり認識されたようで、店の主が直々に茶を持って来て、茶葉の銘柄、諏訪理田屋で買ったものだということまで伝えたのには苦笑し、礼を言った。
おゆうと文五郎のことは伏せてはいたが、長兄が『文五郎は、遠縁の店をたまに手伝いに行くことになった』と皆に伝えた。
まあ、嘘ではないので、隠し事をしているという後ろめたさはそれほどない。
そういえば、『文史郎が定期的にお得意さんのところへ茶を届けに行くことになった』と長兄が以前皆に言い、たまに昼餉の頃に文史郎が出かけているが、あれも、実際茶葉を持参して行くのかどうかは知らぬが、許嫁殿との逢引ではなかろうか……。
おゆうの実家のお店は、諏訪理田屋ほど大きくはないが、良心的な値で、よい茶葉が揃えられていた。諏訪理田屋と同じところから取り寄せている茶葉も多く、遠縁であり、同業であるから、仕事はおおよそ同じではある。それでも「それぞれの店のやり方があるでしょうから」と及び腰の文五郎に、「文五郎さんのお仕事は、諏訪理田屋の旦那のお墨付きです」と、おゆうの父は悠然と構える。そして、「なあに、大丈夫。そう思っておれば、いいのですよ」と、からりと笑う。その笑顔が追い風になり、文五郎は初めはそれでもぎくしゃくとし、ひとつひとつ周囲を見て動いていたが、次第に調子が出て来るようになり、自然に仕事ができるようになった。
そうしておゆうの家に行った日は、そこで昼餉をご馳走になり、午後はおゆうのお三味線の練習を聞いて過ごす。
背筋を伸ばし、着物を尻の下にきれいに敷き、足の親指同士離れぬようにつけ、膝をつけて正座するおゆうの奏でるお三味線を、文五郎も背筋を伸ばし、着物を尻の下に敷き、膝は握りこぶし一つ分開く程度、脇を締め、足の親指同士が離れぬようにし、手を太ももと膝の間に指先が向かい合うように揃え、拝聴する。
おゆうと出会い、心満たされる文五郎は、お三味線を聞きながら、いずれ別に暮らす兄や弟を想った。

![[286]お江戸正座4](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)