[320]棒手振(ぼてふ)りの正座くらべ
 タイトル:棒手振(ぼてふ)りの正座くらべ
タイトル:棒手振(ぼてふ)りの正座くらべ
掲載日:2024/11/18
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容:
明治時代の半ば。毎日、植木や生花を天秤棒に担いで売りに来る青年がいた。姿が美しいので、おかみさんたちは騒いでいた。青年は元、武家の出身で安定丸。
長屋住まいのゆり子とタワミは、安定丸の嫁さんになる憧れから、大家のりりゑ婆さんの勧めで天秤棒の板の上で美しい正座ができるようにお稽古に通うことに。
ある日、安定丸は元締めの華太郎から植木の仕入れを差し止められる。ご一新前に、父親と元締めの父親との間の諍いが原因だった。


本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 安定丸
「植木ぃ~~、植木はいらんかね~~!」
天秤棒を肩にかつぎ、前後の板の上に植木鉢を乗せた筋肉逞しい若い男が声を張り上げて、丘の上にある白い壁の小さな教会から坂を下りてくる。
明治の半ば、江戸の下町の昼下がり、天秤棒を肩に担いでいるのは、棒手振りと呼ばれる商売人である。
「天秤棒の貴公子だわっ」
「安定丸さんの澄んだ声だわっ」
「いつ聞いてもいい声ねえ」
町の小路で井戸端会議をしていた、若い女たちがざわめく。
「声に聞きほれていないで、早く行かなくちゃ!」
女たちは下駄を飛ばして駆けつける。
ザンギリ頭をきれいにそろえた植木売りの青年は、町はずれで天秤棒を下ろした。真四角の前後二枚の荷台には咲き誇ったサツキや、水仙の鉢がてんこ盛りになって並んでいる。
「こんなにたくさん。重かったでしょう、安定丸さん」
タワミが、さっそく手ぬぐいを持って青年の額の汗を拭きながら、ねぎらう。
「なあに、植木鉢の荷をバランス良く運ぶために、毎日、鍛えてるから大丈夫さ、朝一番に仕入れた白百合の配達に、教会にも回ってきた。ありがとよ、タワミねえさん」
「んまっ、タワミねえさんだなんて、水臭いじゃないの。タワミでいいのよ!」
そこへ口を挟んだのは、まだよちよち歩きの赤ん坊をおんぶした小ぎれいな着物を着た細身のゆり子だ。
「タワミさん、ご一新前は、安定丸さんはお武家さんだったのよ。そんなに気安く口を聞いていいのかしら?」
「あなたこそ、ゆり子さん。戦争で亡くなられた旦那さまに申し訳ないと思わないの? 背中の均平(きんぺい)くんは、まだ乳離れしていないっていうのに、若い殿方に色目を使っていいのかしら?」
「何ですって! 誰が色目を使ったっていうの?」
ふたりとも、つかみ合いのケンカを始めんばかりの剣幕だ。
「まあまあ、落ち着いて。おふたりとも、いつも季節の花を買ってくださる大切なお客さんだ。仲よくしてくださいな」
青年は白い歯を見せて、にっこり笑いながら、植木鉢を下ろしはじめる。
「さすが、『天秤棒の貴公子様』だわ! 普通の植木屋さんの言葉遣いより、なんて丁寧なんでしょう」
他の娘や若いおかみさんたちも、うっとりと眺める。
「あの~~、鉄砲百合がつぼみをつけ始めたよ。俺の顔なんかより、こっちを見てください」
「まあ、本当! 純白の百合が、私の名前と同じように清楚(せいそ)に!」
ゆり子が鉄砲百合の鉢を持ち上げた。
「なにが清楚よ。ゆり子さん、あんたはすでに人妻で子持ち。清楚も純潔もほど遠いわよ。安定丸さんにあやかって、均平くんを『やじろべえ』なんて呼んでも無駄よ」
タワミがズケズケと言った。
「我が子をどう呼ぼうが、私の勝手よ」
安定丸がパンパンと手を打った。
「さあさ、サツキもバラもつぼみをつけてるよ。朝顔のタネもたくさん仕入れた。ゆっくり見ていってくださいな」
第二章 イースターリリー
「この鉄砲百合ってのは、キリスト教のイースターっていうお祭りに飾られる花です。最初は欧米ではマドンナリリーっていう種類の百合を飾っていたそうですが、鉄砲百合の方が、花もちがいいとかで、琉球産の鉄砲百合が広く出回っているんです」
「へええ、さすが天秤棒の貴公子、博学でいらっしゃるわあ」
「花への愛情が深くていらっしゃるのよね。鉄砲百合の鉢はおいくら?」
「一鉢、一銭です」
「まあ、それじゃ一鉢いただこうかしら」
「私は朝顔のタネをいただくわ!」
「毎度!」
法被姿にスネに脚絆、わらじを履いた格好でも、安定丸はどこか品があるので娘たちは黄色い声で取り巻いている。
そこへやってきたのは、腰が少し曲がったごま塩の髪を結い上げた長屋の大家さん、りりゑ(りりえ)婆さんだ。年齢相応のちりめん皺が顔全体にあるが、とても元気そうだ。
「安定丸の植木屋のおにいさん、相変わらず商売繁盛だねえ」
「婆さん、毎度! お好きなツツジもサツキもありますよ」
「じゃあ、ツツジを二鉢もらおうかねえ。その紅色のを」
「毎度ありがとうございます」
安定丸が地面に膝をついて座り、植木鉢を用意する。
「お行儀もいいねえ、頑張ってお作法を習いに行っておいでかね?」
「はあ、まあ」
ゆり子とタワミは聞き逃さなかった。
「りりゑ婆さん、お作法を習いにって、安定丸さんが?」
「そうだよ。五丁目の花街に近い、お作法のゆらら師匠のところへね」
「何ですってえ~~! あの色っぽいお師匠さんのところへ?」
ふたりは、りりゑ婆さんを揺さぶった。
「うむう。植木鉢を下ろすのも丁寧な所作だねえ。商売人は扱う品を大切にする所作をしなくちゃねえ」
第三章 一日入門
安定丸がゆらら師匠のお作法教室へ通っていると聞いて、ゆり子とタワミは面白くない。
「ゆり子さん、ちょっと話があるんだけど」
タワミが猫なで声で誘ってきた。
「ゆらら師匠さんとこでお稽古している安定丸さんのこと、気になるでしょう?」
「まあね」
「私たちいつもケンカしてるけど、しばらく停戦しない? お師匠さんのところへ一日入門させてもらって、安定丸さんの様子を見に行くっていうのは?」
「一日入門? でも、私には均平がいるからねえ」
「二時間ほど、りりゑ婆さんに子守をお願いしましょうよ」
ゆり子はりりゑ婆さんに均平の子守をお願いして、お師匠の稽古日に一日入門を申し込んだ。
「ゆり子さんとタワミさんですね。ようこそ、一日入門へおいでくださいました」
ゆらら師匠はシミひとつないお顔と首筋の眩しいほどの美しさだ。玄関でついた指先は、これこそ白魚の指というのだろう。
安定丸は、お弟子さんたちに混じって座敷に待機していた。
「はい、では安定丸さん、先日の正座の所作のでき具合を拝見しますから、どうぞ」
「はい」
安定丸はすっくと背すじを真っ直ぐに美しく立ち上がった。骨盤の上に幅の広い両肩が乗った位置でカンペキだ。そして膝を着き、着物をお尻の下に敷きながら、かかとの上にゆっくり座った。両手はゆったり膝の上に乗せる。
お弟子さんたちからため息がもれた。
ゆり子とタワミはもちろん、改めて魅了された。
「安定丸さん、よくできましたね。皆さんのお手本でいてください」
お師匠もベタ褒めだ。
「天秤棒の貴公子が正座の貴公子になった瞬間だわ」
タワミがため息と共に言ってから、ゆり子と目を合わせた。
「正座を美しくできるようにならなければ!」
「安定丸さんに注目してもらわなくてはね!」
そろって頷き、決意を固めた。
ゆり子は、りりゑ婆さんに預けた均平を引き取りに伺った。
「ありがとうございました。やじろべえや、お利口にしてましたか」
「あ~ちゃん!」
よだれかけをかけた均平が玄関に走り出てきた。
「とてもお利口じゃったよ。一日入門はどうじゃった?」
「私たち、決意しました。安定丸さんに注目してもらえるように正座を上手にできるようになりましょうって! ね? タワミさん」
「ええ!」
りりゑ婆さんは、シワ深い眼をきらめかせて唸った。
「う~~む。普通にお師匠さんのお稽古を受けていたのでは、一向に目立たないじゃろう。いっそのこと彼が天秤棒に下げている板の上で正座するというのはどうじゃ?」
「婆さんたら、植木鉢を積んでる四角い板の上に正座ですって?」
「そう。そのまま安定丸さんに天秤棒でぶら下げてもらうんじゃ」
ゆり子とタワミは目をまん丸にした。
「そんなことしてもらえたら、飛び上がるほど嬉しいけど……。安定丸さんが担いでくださるかしら?」
「何のために担ぐのかって思うでしょうね」
りりゑ婆さんの眼が、いっそう光った。
「ゆらつく天秤棒から下げた板の上で正座の所作ができるか、女の勝負をすると言えばよいのじゃ」
「な、なるほど~~」
第四章 一枚の写真
文明開化を迎えて二十数年。
日清戦争を経て、まだまだ世の中は落ち着いていない。
そんな中でも健気に咲いている花を見て癒されてほしいと、安定丸は毎日、花売りを頑張っている。同時に、元の武士の家に生まれたからには品位を大切にしたいと思い、売上の中からお作法のお師匠に月謝を工面して所作を習いに行っている。
実は、お師匠のところへ正座を習いに行ってる理由はもうひとつある。少年の頃、植木市場の元締めのところで見た一枚の写真――、キリスト教会の聖堂で白百合の花を持って正座する少女の姿があまりにも可憐で美しく、忘れられないからだ。
安定丸は写真の少女がお師匠のゆららだと信じている。
ある朝、植木を市場で仕入れた安定丸は、荷台に植木鉢をたくさん積み、天秤棒を担いで出発しようとした時――、空がぐるぐる回って見えた。
「あれえ?」
たくさんの植木が崩れて植木鉢が割れる音が聞こえ、視界が真っ暗になった。
「安定丸、どうした!」
市場の衆が騒いで医者のところへ担ぎこむと、医者は、
「栄養不良じゃ。特に鉄分が足りん」
植木売りの仲間たちが心配してついてきた。
「スズメの涙ほどの稼ぎを作法教室の月謝にあてていた? それで食うもの食ってねえのか?」
「おばか野郎だな」
事情を聞きつけたゆり子とタワミが、安定丸の長屋へ青魚やほうれん草など、鉄分を含んだ食べ物を届けに行き、料理して食べさせた。
「食べるものも食べないで、植木の稼ぎを正座のお稽古に回してるとはねえ」
「あんなに重い物を運ぶのは重労働なのに」
二日ほどして顔色が良くなった安定丸は、懐から一枚の少女が写っている古ぼけた写真を大切そうに出して、
「いつか、この娘に会えた時にきれいな正座ができるように、稽古を頑張っているんだ」
と、照れながら打ち明けた。
ゆり子とタワミは写真にガバッとのしかかり、
「まあ、なんて美少女!」
「教会の中で白百合なんか持って!」
そこへ、鉄鍋と鶏レバーや納豆をどっさり持ってきた、りりゑ婆さんが一喝した。
「タワミさん、団子屋の下働きと正座のお稽古は? ゆり子さんはお仕立ての仕事と、やじろべえをお隣に預けたままではないかえ?」
ふたりとも飛び上がって、安定丸の家を飛び出した。
第五章 お前には売れん
数日後、安定丸はいつも取引している植木の仲買人たちから、いきなり「取引できない」と言われた。
「取引できない? どういうこった、そりゃ! 仲買さんには一件もツケは無いはずだ! いきなりそんなことを言われても……」
「確かにツケは無い。でも売ってやれないんだ」
「だから、なぜ?」
「なぜと言われても、こっちの事情でな」
仲買人たちは口をそろえて「取引はできない」の一点張りだ。
(なんでだ……、俺が寝こんでいる間に愛想をつかされたんだろうか)
がっくりして天秤棒の道具だけを抱えて長屋に戻る途中、りりゑ婆さんに会った。
「どうしたんだね、今日の仕入れは?」
「それが……」
若柳の揺れる川端で、りりゑ婆さんに今朝の事情を聞いてもらった。
婆さんは、しばらく川面を見つめて考えていたが、袖をつかんで引っぱっていく。
「安定丸さん、ちょっと一緒においで」
着いたところは大きな門構えの屋敷だ。表札には「大松」と書かれている。
「大松って、植木市場の元締めの家じゃないか!」
「そうだよ、どうして仲買人があんたとの取引をやめたのか、元締めに聞けば分かると、ピンと来たんだ」
背中に「大松」と染め抜いた法被(はっぴ)を着た使用人がふたりを迎えた。
元締めの大松は、江戸時代の朝顔ブームで財を成して、その勢いで二代目の元締めの華太郎が商売を継ぎ、朝顔だけでなくさまざまな種類の植木を手広く扱っている。ご一新前は、町人ながら「苗字、帯刀」を許され、大きな屋敷に左団扇(ひだりうちわ)で暮らしている。
安定丸が驚いたことに、りりゑ婆さんは使用人から態度を改めて頭を低くされて、門を通り抜けて踏み込んだ母家の入口で、使用人の頭らしき男が三つ指ついて迎えた。
「これはご隠居さま。今日はまた?」
「ちょっと大松さんに伺いたいことがあってね、いなさるかね?」
「はい、しばしお待ちくださいませ」
使用人の頭は、戻ってきてふたりを奥に案内する。
縁側を通っていくと植木市場の元締めの屋敷だけあって、広大な庭には古刹(こさつ=古い由緒ある寺)のような凝った庭が造られている。
贅沢な松はもちろん、ツツジの植木や桜、椿。大きな岩がいくつも並び、広い池には錦鯉が悠々と泳いでいる。
「ご隠居、どうなされたかな? 朝っぱらから」
元締めの華太郎(かたろう)は座敷の奥で煙草をふかせていた。
「どうもこうも、真面目に働いている安定丸さんに植木を売れないと言ってる仲買人がいるそうじゃないかね? 元締めなら何かご存知だろうと思い、伺ったんですよ」
「ふん、その青二才、前から市場では嫌われていたんだ。士族のくせにわざと貧しいマネをして棒手振りなんかしおってってな」
華太郎の元締めは鼻息荒く言い放った。
「わざとだなんて!」
安定丸は思わず言い返す。
「士族がみんな裕福だと思ったら大間違いです! うちはご一新前から身分の低い武家だし、今は平民です。一日一日食べていくのがやっとなんですよ!」
「とにかくお前さんには一切、植木を売ってはならんと市場の各店に触れを出した。諦めるこった」
りりゑ婆さんが膝を乗り出し、
「華太郎の元締め。そりゃ、あんまりじゃないかい? 安定丸さんには何ひとつやましいことは無いってのに」
「いくらご隠居の頼みでも聞けないですな。植木市場に揉め事の芽が出る前に摘み取ってしまわないと」
「はは~~ん」
婆さんがわざと苦笑いした。
「華太郎の元締めが下町の正座で知られるお師匠さんに……ってのは、本当のようだね」
「なっ、何のことだ!」
元締めはフグがふくらんだような顔を真っ赤にした。
第六章 お師匠の怒号
「じゃあ、華太郎の元締めはゆらら師匠にホの字なのかい?」
屋敷を後にして帰る道すがら、安定丸はりりゑ婆さんに話しかけた。
「そうさ。お前さんが目をかけてもらってると噂を聞き、嫉妬して仕事ができないようにしたんだろう。男のクセにね。――でも、それだけじゃない気がするんだ。お前さんは、いつでも仕事が再開できるように栄養を取って身体を鍛えることに専念すりゃいい」
「はあ……」
りりゑ婆さんは、長屋の路地で遊んでいる小僧に小銭を握らせ、耳元で頼み事をした。
(これは、他にも恨みを持っているな。見張らせてもらうよ、元締め)
しばらくすると、華太郎の元締めは羽織袴に着替えて出かけたと小僧が知らせに来た。りりゑ婆さんがそっと後をつけていくと、巨体を細い小路に滑りこませた。
(この小路は、ゆらら師匠のところへ通じる路……)
元締めは髪にツバをつけてめかし込み、照れ臭そうにこじんまりした家の玄関をガラリと開けた。お師匠宅だ。
垣根の陰に、りりゑ婆さんが隠れて様子を窺っていると、最初は静かな会話が聞こえてきたが――。
突然、
「このアマ、わしのどこが下品だと?」
「全部だよ! 全部! その派手な羽織も、油を塗りたくった髪も鼻をつまみたくなるような臭い足も! そんな臭い足でお座敷に上がらないでくださいなっ」
お師匠の意外にも意外なドスの利いた声に、婆さんも飛び上がった。
「わ、わかった、出直すわい!」
クソミソにけなされた華太郎の元締めは、靴を抱いて逃げ出した。
「二度と来ないでくださいな~~~!」
師匠はトドメに塩までまいた。
(おやおや、元締めは師匠に嫌われているのかい。それと……)
りりゑ婆さんの足は役所へ向いた。
第七章 諍い(いさかい)
話は数十年前にさかのぼる。
大政奉還以前の安定丸の父親は、名を中野泰然(たいぜん)と言い、士分の中では低い足軽で、殿の御台様(正室)のお花の世話のお役目をたまわっていた。
毎朝、花屋から運ばれてくる花を受け取り、奥座敷の床の間に活けるのがお役目だ。華道も正座の所作も有名な流派の免状を持っており、丁寧に正座し御台様のために心をこめて活けていた。その真摯な様子が後ろ姿からも感じられると家中でも評判になっていて、殿と御台様のお気に入りでもあった。
お屋敷出入りの花屋は、明治になって、泰然の息子である安定丸に「お前には売らん」と宣言している華太郎の元締めの父親にあたる人物だ。
裏口で神妙に切り花を納めてから、垣根越しに奥座敷を覗き見して、心の中では生花を活ける際に正座する泰然を軽蔑していた。
(男のくせに、花を活ける役目だと? 俺たち、花を育てて市場に納めたり出荷したりする者が、どれだけ土や肥しにまみれて力仕事をしていることか)
(だのに、その花を切ったりひん曲げたりして活けることがお上品で免状もんだと~~? なにが正座だ、所作だ!)
ひがみ、妬みが元締めの心の奥にくすぶっていた。
ある朝、泰然の下男が、元締めから生花を受け取る際に土間に落としてしまい、白百合の花が幾本か汚れて折れてしまった。
頭に血が昇った元締めは、
「御台様にお持ちした花が台無しだ! わざと手をすべらせただろうが!」
と、難癖(なんくせ)をつけた。
これには下男も黙っていられない。
「わざとだと? 武士に向かってその言い草はなんだ! そっちこそ、わざと落とすように渡したのだろう」
ふたりで怒鳴り合いのケンカを始め、泰然が奥から駆けつけて厳しく叱りつけた。
「お方様のお好きな白百合のことで、何を醜い争いをしている! ケンカ両成敗だ。うちの下男は謹慎。元締めさんもしばらく出入り禁止にさせていただく」
ふたりはしぶしぶ引き下がった。
りりゑ婆さんは役所で、この諍いの記録を発見した。
第八章 一枚の写真
大政奉還となり、世の中はひっくり返った。ちょうど安定丸が生まれた頃である。
主筋の大名家は子爵家として残ったが、足軽だった安定丸の父親、中野泰然は平民として花売りの道を選んだ。華道を通して慣れ親しんだ花に携わり、周りの人たちにも花を愛でてもらいたいという考えからだった。
それを見て育った安定丸もまた、十五歳になると自然に花売りの仕事を選んだ。
――正座して花の中心を静かに眺めていると、心静かになれた。特に純白の百合の清廉な美しさは、苦しい毎日の嫌なことを吹き飛ばしてくれた。
安定丸は長屋でひとり暮らしを始めた。
長屋の大家、りりゑ婆さんは、気っ風(きっぷ)の良さで店子(たなこ=家を借りている人)から慕われていた。
ある日、二代目植木市場の元締めの華太郎が、得意そうに一枚の写真を見せびらかしていた。
「これが、白百合の女神さまだぜ」
群がる植木売りの人垣からチラッと見えた写真には、キリスト教会に仕える修道服を着た思春期の少女が一輪の白百合を持って正座していた。
安定丸は見た瞬間、全身にじ~~んと熱い痺れを感じた。
(なんという清楚な白百合の女神だろう)
しっかり瞼(まぶた)に焼きつき、寝ても覚めても少女の面影が胸を去らない。
(誰だろう。どこかで見たような……)
華太郎の元締めは、酒が入るたびに写真を見せびらかしていた。ある宴会の後、懐からひらひらと落としたことに気づかず、仲間に担がれて行ってしまった。
地面に落ちていた写真に気づいたのは、安定丸だった。
(早く元締めに返さなくては)
……とは思ったが、白百合の正座姿を見てしまうと、写真をしっかと持ったまま動けなくなった。
(そうだ! 長屋の向こうに住んでいるお作法教室のお師匠さんに似てるんだ!)
気づくが早いか入門を申しこんだのだった。
第九章 女の反撃
さて、ゆり子とタワミは、あれから、ゆらら師匠の華道と正座教室に入門してお稽古を重ね、正座初級の免状をもらった。
ゆり子はやじろべえを背負って時々お乳をやり、おむつを換えながらお稽古を頑張った。
ふたりは顔を見合わせ、
「これで、天秤棒の貴公子にかついでもらって正々堂々と正座の勝負ができるわね」
「負けないわよ、タワミさん」
ふたりの会話を聞いた師匠が、
「何ですって? 天秤棒でかついでもらって正座するんですって? 安定丸さんの?」
ふたりは座り直して目を輝かせた。
「そうです! ちゃんと正座できて安定丸さんが選んで下さった方が、許婚者(いいなずけ)になるんです!」
「この勝負のために頑張ってきました。安定丸さんの力のほどを皆さんに知っていただく良い機会になると思うのです!」
ふたりはやる気満々だ。
「安定丸さんは承知してらっしゃるの?」
「いいえ、これからお願いするつもりです」
「呆れた……」
ゆらら師匠は、くったりと座りこんだ。
「あなた方、何もご存知ないのね。安定丸さんは、ここしばらくお稽古にいらしていないでしょう」
「そういえば。お仕事が忙しいのでしょう」
師匠は首を横に振った。
「違うの。安定丸さんは今、仕事をしたくてもできないの。市場から仕入れができないのよ。お嫁さんをもらうどころではないのよ」
「仕入れができない? どうしてそんなことに?」
「これ以上のことは、私には分からないわ」
ゆらら師匠は下を向いた。
ゆり子とタワミは、りりゑ婆さんのところへ飛んでいった。
「……というわけさ。安定丸さんは親の代での元締め親子との諍いから、仕入れができないでいるのじゃよ」
りりゑ婆さんは話し終わると肩を落とした。
ゆり子の背中でぐずりはじめた、やじろべえを抱きとってあやす。
「やじろべえや。泣きなさんな、よしよし」
ゆり子もタワミも眉がつり上がっている。
「なんてことかしら。親同士の小さな諍いを根に持つなんて、華太郎の元締めも大きな身体のクセして器が小さい人ねっ」
「ふたりとも、このことは他言無用にな……」
りりゑ婆さんが言った時には遅かった。
「ゆり子さん! 行くわよ、お師匠さんのところで知り合った華道の生徒さんたちのところへ!」
「どうするの?」
「華太郎の元締め傘下の仲買人からは、安定丸さんへの弾圧を止めないかぎりお花を買わないでくださいって、お願いして回るのよ」
「タワミさん、言い考えね! 安定丸さんのためなら、皆さん、協力してくださるわ!」
第十章 白百合の妖精
ゆり子とタワミは手分けして、華道師範たちに元締めの仕打ちを訴え、花を買わない運動に参加してほしいとお願いして回った。華道師範たちは、ゆらら師匠の教室での安定丸の真面目さをよく知っている。
「安定丸さんが、そんなピンチに? 是非、力になりますわ」
次々に賛同してくれた。
師範たちには、りりゑ婆さんからそっと、代わりのお花の手配がされていた。
たちまち華太郎の元締めが勘づいた。
「下町じゅうの華道師範が花の取引をしない? もしかすると安定丸の仕返しか?」
元締めは歯ぎしりして、安定丸の長屋に押しかけた。
りりゑ婆さんはじめ、ゆり子とタワミが待ち構えていた。
「やい、貴様! 華道の師範たちを騙して俺の商売をじゃましているだろうが」
安定丸は唖然とし、
「俺は、何も……」
言いかけるのを、ゆり子たちが口元をふさいだ。
「元締めさん、いつまでも昔のことにこだわって弱い者いじめなんかしているからですよ」
「弱い者いじめ? 安定丸は元、武士だぞ。弱い者いじめしてるのは、どっちだ」
タワミが素早く安定丸の懐から「白百合の少女」の写真を抜き取り、
「これがどうなってもいいの?」
「あっ、いつの間にその写真を!」
元締めは鬼の形相になりかけた。
「俺の大事な写真を盗みやがったな!」
「違うわ。あんたが落としたのを、安定丸さんが拾ってあげたのよ」
「くそ~~! 返せ!」
元締めは急に涙声になり、ひざまずいた。
「お願いだ、返してくれ。それは俺の心のよりどころなんだ……。白百合の聖女……」
太い腕で涙をぬぐう。
「おや? それほど想っていてくれたとはねえ」
りりゑ婆さんが両手を広げて呆れてみせた。
「長崎の教会で撮影した若い頃のアタシだよ。清楚で可愛いじゃろう?」
「……!」
「……!」
一同は絶句した。中でも安定丸は蒼白になっていた。
(この白百合の妖精が、りりゑ婆さんだって?)
第十一章 青空の下で
梅雨の中休み、久しぶりに青空が広がった。色とりどりの紫陽花(あじさい)も陽の光を浴びて輝いている。
長屋周辺の住民たちが、ぞろぞろと見物の輪を作った。
輪の中心にいるのは天秤棒を用意した安定丸だ。かたわらには、やじろべえを抱っこしたゆり子とタワミ。
見物人のかぶりつきには、りりゑ婆さんとゆらら師匠が陣取った。遥か後方の木立の陰からは、華太郎の元締めが様子を窺っている。
「そろそろ始めます」
安定丸が号令をかけ、ゆり子とタワミが立ち上がった。やじろべえは婆さんに抱っこされる。
ゆり子とタワミは、草履を脱いで正方形の板の上に乗った。
見物人のひとりが、
「安定丸さんがふたりのうち、正座がきれいにできた方をいいなずけにするって本当?」
隣にいた娘が吹き出した。
「まさか。ふたりともそれは諦めたらしいわ」
「じゃあ、どうしてこんな勝負を?」
「正座を上達するって宣言したからでしょう」
「安定丸さんは、よく承知なすったわね」
「憧れていた写真の白百合の乙女がりりゑ婆さんだったと判って、ヤケクソになって引き受けたらしいわ」
「そそっかしいのね。若い頃のりりゑ婆さんをお師匠さんと間違えるなんて」
女たちはお喋りが止まらない。
「……では、そろそろ……」
安定丸がやる気のない声を出した。
「おふたりとも頑張って!」
ゆらら師匠が声援を送る。いよいよ安定丸が天秤棒をかつぐ。
第十二章 勝負の時
安定丸は天秤棒を肩に乗せると、ぐっと腰を落とした。力みこみ、板に乗せたふたりを持ち上げようとする。
ふっくらしたタワミの方が地面に傾き、ぐらぐらした。
「ゆり子さんが軽いんだ」
りりゑ婆さんがもどかしくおぶい紐をほどき、やじろべえをゆり子の膝に乗せた。二枚の板はようやく釣り合った。
「さあ、これからね」
「ええ、負けないよ!」
ゆり子とタワミは顔を見合わせ、安定丸にも頷いてみせた。
「せ――の!」
ふたりは同時に立ち上がり、膝をつく。やじろべえを抱っこしたゆり子もぐらつくことなく膝をつくことができた。空いた方の手で着物に手を添えお尻の下に敷きながら、かかとの上に座る。負けじとタワミも同様にできた。
ふたりがそろって頭を下げると、見物人から大きな拍手が起こった。りりゑ婆さんも胸を撫で下ろし、
「ふたりとも立派な正座じゃ」
ゆらら師匠も頬を紅潮させて叫んだ。
「素晴らしい所作だったわよ」
やじろべえが、
「だあ!」
笑顔でバンザイしたので、人々はどっと笑った。
「ご声援、ありがとうございました。安定丸さん、ありがとうございました」
ゆり子とタワミは皆に深く頭を下げた。安定丸もふたりを下ろし、晴れ晴れとした顔で礼を言った。
「よう頑張ったのう」
りりゑ婆さんが、板から下りたふたりに一本ずつ白い百合を渡した。
「これは?」
ふたりは、白百合と婆さんを交互に見た。
「この白百合は写真の少女が」
りりゑ婆さんはにんまりして、
「あの丘にある教会の庭で栽培している。わたしゃ昔から白百合が好きでな」
安定丸も目を見開いて、
「やっぱり、写真の少女は婆さんだったのか」
ゆらら師匠が、
「そうよ。りりゑ婆さんは以前、長崎にいらした神父様の養女さんよ。この村に来られてからは和洋折衷(わようせっちゅう)の畳敷きの教会を建てて、正座を広められたのですよ」
ゆらら師匠は少女時代に、その教会で正座に親しんだという。
長屋のおかみさんたちから、
「りりゑ婆さんとお師匠じゃ、親子ほど年代が違うじゃないの。なんで間違えるの」
安定丸は照れ臭そうに頭をかいた。
もうひとり、悲鳴を上げたのは人垣の後ろで見物していた華太郎の元締めだ。
「白百合の乙女~~! 亡くなったおっかさんの若い頃だとばかり思ってたのに~~!」
クスクスと笑い声がもれた。婆さんが慰めて、
「元締めさんのことは、やじろべえくらいの時に子守させてもらったよ」
「なんだって?」
「普段、大勢の人手を指図している元締めさんでも、お母さんが恋しいのね。それで私に甘えようとしたのね」
ゆらら師匠が口をすべらせたので、元締めは逃げ出した。
「これで、二度と仕入れいじめなどせんじゃろう。安定丸さん、堂々と花を仕入れて商売ができるよ」
りりゑ婆さんの笑い声が梅雨の中休みの青空に響き渡った。
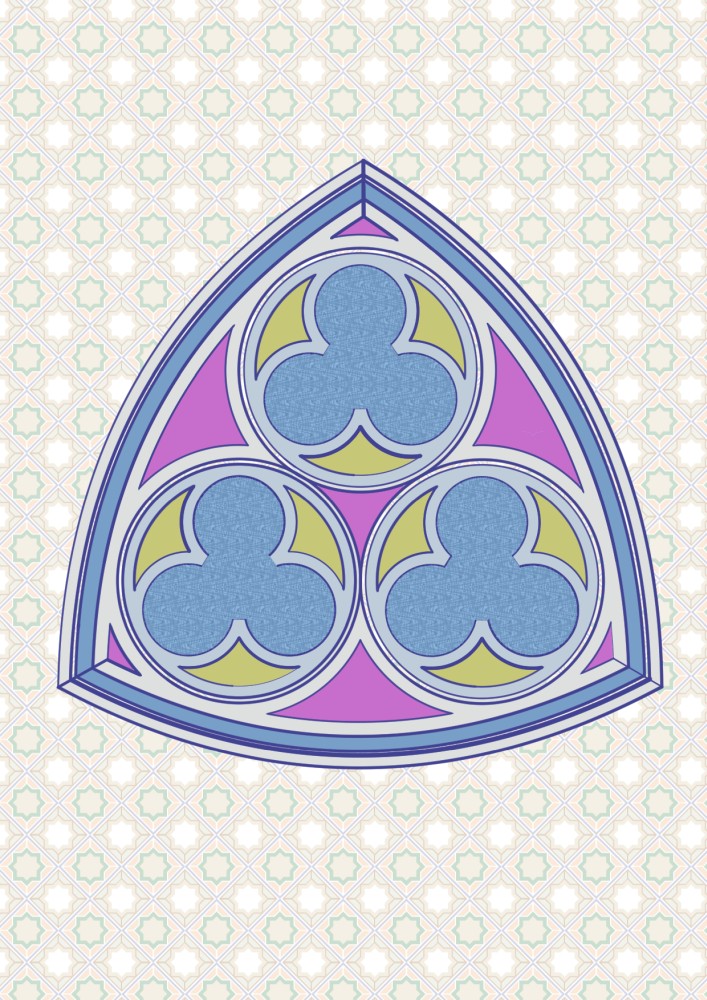



![[1]正座のある生活 1](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)



