[44]誰がお前なんか
 タイトル:誰がお前なんか
タイトル:誰がお前なんか
分類:電子書籍
発売日:2019/01/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:80
定価:200円+税
著者:東谷 駿吾
イラスト:鬼倉 みのり
内容
友達と遊んでいる時間は最高で、家に帰って怒られている時間は最低で。
高校に通う園部浩一(そのべこういち)は、父親からの「正座しろ」という言葉をずっと嫌だと思っていた。正座の真意はどこにあるのか。父の語る理由を受け入れられない浩一だが、その心の中には小さな違和感が生まれ始めていた。
大人へと成長していく青年の内心を細緻に描写した短編小説作品。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/1158966

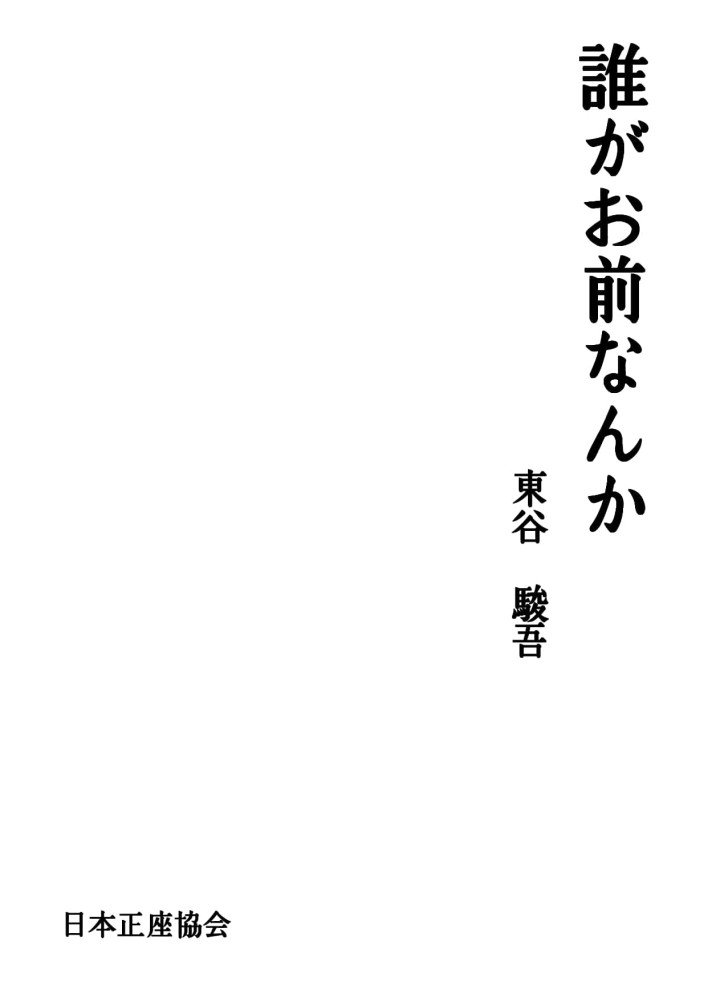
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
一 ある午前零時
涼しい夜風が頬を撫でる。街から少し離れた住宅街はひっそりと静まり返って、俺のスニーカーがアスファルトを叩く軽い音だけがリズムを刻んでいる。
ちょっと遅くなったかもしれない。ポケットからスマホを取り出して画面を見ると、日付が既に変わって金曜日になっていた。一緒に遊んでいた健伍達は、無事に家に帰り着いたのだろうか。SNSを開いてみると、祐輔が家のトイプードルを抱きかかえて「帰宅~」と呟いていた。なんだか急に彼が少し遠いところにいるような気がして、俺は足を速めた。
「ただいま」
鍵のかかっていない玄関戸を開けながら声を投げたが、返事はない。居間の電気は落ち、家の中も、沈黙の音だけが支配している。靴を脱ぎ、物音を伺う。寝息も聞こえない。まるで廃屋に肝試しに来ているようだ。俺の中に、怒声を浴びせられずに済んだという安堵と同時に、冷たくささくれ立った霜が湧きおこってくる。一つの溜息でそれらすべてを溶かしつくして、二階の自室へと続く廊下を曲がった。
「おい」
「うわっ」
低い声に、思わず変な声が上がる。
「……なんだよ、父さんかよ」
そこには、上下スウェット姿の父さんが立ちはだかっていた。
「『なんだよ』じゃない、今何時だと思っているんだ」
暗闇の中でも、彼の眼はギラギラと光って見える。
「何時でもいいだろ、別に。明日も学校だし、寝るから」
「待ちなさい」
言われずとも、彼がどけてくれなければ、俺は部屋へは戻れない。大学時代にラグビーで鍛えられたといつか自慢していた肉体は、五十を過ぎた今になっても、かなりがっしりとしているように見える。記憶の中にある彼の姿よりは、腹の肉が少し増えて猫背になり、髪の毛もだいぶ薄くなったように思えるが、それでもトレーニングらしいことは一切していない俺に比べれば、ずっと強そうだ。正面を切って殴り合いなんてしても、絶対に勝ち目はない。
「どいてよ」
「話がある」
「俺にはないから」
「俺があるんだ」
父さんの目が怒っている。油断した。瞬間にでも「今日はツイてるな」なんて思ったのが間違いだった。こうなると、彼は意地でも譲らない。『説教一時間コース』のスタートである。俺は観念して、「分かったよ」と言い、彼の後ろをついて、仏間へと向かった。
仏間は外と同じくらいひんやりと冷たく、湿っぽい空気に包まれていた。カチリと電灯を点けると、父さんは赤茶けた木のテーブルの向こう側に腰を下ろす。そして、「ん」と俺の方を目で指して座らせた。
「正座」
重く低い声で言われるがまま、俺は崩した足を整える。何度正座をしても、慣れない。もぞもぞと動いて、尻が一番安定する場所を探す。
「まだ高校生だろ、お前は」
父さんはぴんと背を張って、俺のことを見下ろしている。
「髪の色だって、校則違反なんじゃないのか」
無論、そうである。だが、違反だからこそやっているというところもある。他の誰もがやらないこと、俺だけがやっていることが、俺のアイデンティティを示しているはずだ。金髪や赤髪の奴はいるけれど、茶髪は、同級生の中では俺くらいしかいない。そんなことをこのカタブツに言っても、理解してくれるはずもない。俺は黙って、ただ時間が過ぎて彼が眠くなるのを待つだけだ。
「第一、こんな時間まで何やってたんだ」
不毛な時間。一方的に投げかけられる質問と、黙りこくった俺。刑事ドラマなら、ここでカツ丼でも出てくる頃だろう。遊びまわって腹が減っているのは間違いない。ここでおにぎりの一つでも出されたら、口の回りがよくなって何か喋るかもしれないと、そんなことを思った。
「黙っていても、分からんぞ」
父さんの声に、とげが生えてきた。ちらりと顔を見る。今までに見たことのない表情だ。怒っているような、どこか寂しそうな目。電車でよく見る疲れたサラリーマンのそれとは違う、もっとしっかりとした感情のある顔。
「浩一」
深いため息が聞こえた。
「父さん、明日も仕事だが、お前が喋るまで寝ないぞ」
「えっ」
「これまでは折れてきたが、お前の話が聞きたい。お前の口から言葉を聞くまで、俺も寝ないし、お前も寝かせない」
……困った。
先週は「夜遊びをやめるように」「髪を黒に戻すように」「母さんは大事にするように」などと色々と「課題」をもらって終わっていた。その前も、その前も。俺はその課題に一つも手を付けていない。無視したと言ってもいい。だが、それが通用しなくなった。俺にその気がないということが分かったのだろう。
父さんの表情から、「早く寝かせろ」というようなメッセージは感じ取れない。むしろ、「早く声を聞かせろ」という感情の方が、ずっと強い。父と子という関係から生じる、回避不能な圧力。俺は観念して、思っていることを言うことを決心した。だが、最低限だけ口を開いて理解してもらえるようにしたい。無い知恵を絞って、口を開いた。
「まず、足を崩したいんだけど」
父さんはかたい顔つきのまま、次の言葉を待っているらしい。
「なんで、毎回正座させるんだよ」
これまで、ずっと不満だった。
なんて言ったって足が痺れる。五分もこの姿勢でいれば、そのあと立って移動するのもつらいし、それ以上に長引けば寝るまで痛むことだってある。座らせるだけなら、別に胡坐でも、体育座りでもいい。
それに、正座だと叱られているという気分が増して、嫌味が過ぎるように思うのだ。ただでさえ面倒な説教の時間が、余計にひどく退屈で、億劫で、とても受け入れられないもののように感じる。
こころを開いて話せというのなら、もっと受け入れやすい楽な姿勢のほうが、話に集中できるような気がする。……いや、そうなったからと言って、友だちとの付き合いを変えるようなつもりは無いのだけれど。
「いいか」
父さんは、深刻そうな顔をして俺を見た。
「俺がお前を正座させるのには、理由があるんだ。きちんとした、な」
当たり前だ。理由もなく正座させているのであれば、それはまさに体罰。実の親子といえど、いや、実の親子だからこそ、そんなことは許されていいはずがない。家庭内暴力だ。
「正座には、精神を集中させて、安定させるという効果がある――と、俺は信じている」
思わず前のめりにこけそうになるのをこらえて、俺は彼の顔を見た。冗談を言っているようには見えないし、もともと、父さんは冗談を言うようなタイプでもない。
「信じてる、って」
俺はその目を見つめた。
「根拠ナシかよ」
「根拠ならある」
父さんは、ふう、と大きく息を吐いて、目をつぶった。
――昔俺が、まだ大学生だった時の話だ。全国大会の予選が迫っていた。俺は三年生で、いよいよスタメンで出場出来るか、というところまでいっていた。前の年、同じポジションで不動のエースだった先輩が卒業してな。甘い見立てだったというつもりはないが、自分も、周りの評判からも、俺が登録されるだろうと思っていた。だが、結果はベンチスタート。一つ学年が下の奴が、スタメンに起用されたんだ。監督の采配だった。確かに後輩のフィジカルは決して悪くない。だが、俺か、それとも後輩かという二者択一なら、間違いなく俺のほうが上だという自信があった。俺は監督に詰め寄った。なんで俺じゃないんですか、とね。監督は黙って俺の言い分を聞いていた。学年的な優位も少なからずある。体力も上、経験も上。それなのに、どうして。十分ほど言いたいことを言ったら、今度は監督が一言、「だからだよ」と言ったんだ。……正直、意味が分からなかった。困惑した顔をしているのが分かったんだろう。彼は、「お前に徹底的に足りないものがある」と言った。それがメンタルだった。
「お前は、体力は十分にある。当たり負けもしないだろうし、日々のトレーニングの量だって誰よりも多い。だが、精神力が圧倒的に足りない。今だってそうだ。自分にどんな落ち度があったかを自省しても答えが分からなかったら、黙って落ち着いて聞きにくればいい。お前にはそれが出来ない」
ショックだった。そのことばに、俺は何一つ言い返せなかった。「園部、いいか」と、先生は俺の目をじっと見た。
「ここで、今、正座しろ」
それを言われたときの気持ちは、きっとお前の今感じている理不尽さや、ぶつける先のないものと同じだろう。どうしてそんなことをしなくちゃいけないのか、体罰じゃないのか。――いや、あの頃は体罰なんて当たり前だったから、殴られるよりはマシだろうと思ったのも事実だが、それでも、暴力で上下関係をしっかりと線引きさせるための行動だろうと思った。逆らっても仕方がないから、俺は監督の言う通り、その場に膝をついて座り込んだ。夏場なのにひんやりと冷たい床が、妙に居心地が悪くて、もぞもぞと何度も足を動かした。
「じっと、目を閉じろ」
言われるがまま、俺は目をつむった。
「そして、深く深呼吸だ。自分の中の悪い考えや気持ちを、空気に溶かして吐き出していくように」
そこまで言われて、俺は恐ろしくなって反発した。
「先生、それじゃまるで宗教です」
「それでもいい。騙されたと思ってやってみろ」
強面の監督に言われるがまま、また目をつぶってみる。
目を閉じた真っ暗な世界の中に、ロウソクのような細くて弱い光が、一つ見えた。それが、ふわふわと浮かんだり沈んだりして、安定しない。息を吐きだすと、それがたなびいて、今にも消えそうなほどだ。慎重に、消さないように、ゆっくりと呼吸する。それに合わせて、不満を溶かしていく……。なぜ俺がメンバーに選ばれなかったのか。今までの俺の練習は間違っていたのか。もし間違っていたとしたら、なぜ監督は俺のフィジカルを褒めたりしたのか。俺になくて、後輩にある精神力というのは、一体……。
「先生」と声を出した。
「何か分かったか?」
「寝そうなので、今日は帰ります」
「そうか」
俺がそう言うと、監督は初めて俺の前で笑顔を見せた。
「冬にはスタメンになれるように、メンタルも鍛えておけ。もちろん、フィジカルは継続するように」
俺は彼の言っていることが、そのときは全然分からなかった。だが、バカにされたようで悔しくて、毎日、来る日も来る日も正座して、監督の言う「メンタル」が何なのか、探り続けた――。
父さんの顔が、またこちらをギリっとにらんだ。
「あのとき先生が言った通り、冬にはスタメンに入れてもらえた。精神を落ち着けること、自分の内側を見つめること。正座を通して、俺は自分のこころと向き合う方法を知った」
「それが」
俺には、まるで絵空事に聞こえた。父さんが話の中で持ち出した『宗教』ということばが、まさにぴったりだった。
「何だって」
ぴりぴりと痺れ出す足を後ろ手で揉んで、もう片方の手で前髪を掻いた。俺の態度に、父さんは言葉を返さない。
「自分と向き合う? そんなのは、言われなくても出来てるよ。俺は今を全力で楽しんでる。自分が考える一番いい状態で、俺は生きているよ」
「母さんをこれ以上心配させるな」
「母さんだって、それでいいって言ってくれてる」
嘘じゃない。母さんは俺が遅く帰って来ることも知っているし、それを知った上でなお、「事故に遭わないようにね」とだけ言っている。終電を逃すのは流石に心配させるだろうと思って、俺はそれよりも早くは帰ってきているのだ。むしろ充分孝行なほうじゃないか。
「母さんは強く言えないだけなんだよ。本当は、もっと早く帰ってきてほしいと思っている」
「そんなの、父さんの勝手な推測じゃないの」
父さんは目で怒りを伝えているが、俺はそれを受け取らない。正座の話だって、古臭い根性論に感じるし、母さんのことだって、その正座の話で負けそうになったからわざわざ持ち出してきたような気がしてならない。どちらにしても、俺がこれ以上彼の話に付き合うのは、時間の無駄らしく思えた。
「ねえ、もう寝ていい? 明日も学校あるし」
俺のことばに、父さんは一瞬不快そうな顔をした。それから「いいぞ」と言って、先に腰を上げた。
「よく考えろ、自分の人生だからな」
捨て台詞のようにそう言って、彼は仏間を後にした。
「ふぃー……あててて……」
残された俺は、その場に足を崩して、そのまま仰向けに寝転がった。足が痺れていて、うまく立ち上がれないのだ。いつもならもうとっくにベッドの中にいてもおかしくないくらい時間が経っていた。
板張りの天井を見上げると、目玉のような木目の一部がこちらをじっと睨みつけている。小さい頃は、あのシミがとっても怖くて、この部屋に一人で残されるのが嫌だった。大きくなるにつれて、木にはバウムクーヘンのような丸が何重にも重なった部分があって、それは年輪という名前であることを知った。年輪の存在を理解すると、この天井のシミは決して目玉などではなく、紛れもなく木の一部であって、それが植物として生きてきた証なのだと認識できた。それ以来、この部屋はただの恐ろしい部屋から、何の変哲もないただの仏間へと変わっていった。そしていつからか、父さんに怒られるだけの、冷たく色のない空間へと変化していったのだ。
足を揉みながら、「あー」と鈍く声を出す。軽く脱色した髪が目にかかっている。これだって、何がいけないのか分からない。黒髪のままでいることが、そんなに偉いことなのだろうか。理由のない校則にただしがみつくことが、優等生なのだろうか。それは、守り抜かねばならないほど、自分の「よりよく生きていきたい」という気持ちよりも上にやってくるほど、素晴らしい価値のあるルールであり、名誉なことなのだろうか。揉んでいく手を止めて、首を軽くひねる。
やがて、遠くから冷蔵庫のジーッという乾いた電子音が、この空間全部を包み込んだ。自分以外の生物がすべて活動を止めてしまったような静寂の中で、俺はゆっくりと体を起こす。まだ少し足は痛いが、歩けないほどではない。スマホの画面にタッチすると、すでに一時を回っている。明日も八時くらいには家を出ないといけない。
学校に遅刻するのは、違う。夜遅く帰って来てもいい、という点を認めさせるための第一歩であるから。「学校には遅れず行ってるんだから、いいだろ」ということができるのである。これが学校にも遅刻して、夜も帰ってこないというのでは、怒られても仕方がないだろうと思う。そして、俺はこうやって夜遊びを始めてからは一度も遅刻していないし、インフルエンザで出校停止になった時以外は、きちんとサボらずに学校に行っている。……テストの点数は、まあ、ご愛嬌というものだ。出来ないものは出来ない。
よろよろと立ち上がり、居間の横を通る。廊下から、ふと、ダイニングキッチンに何かがあるのを見た。暗がりの中に目を凝らすと、テーブルの上に、ラップのかかった皿がある。その奥に、誰かが突っ伏して寝ている。多分母さんだろう。ということは、あそこに置かれているものは、きっと俺のための何かに違いない。友達と食べて来るからいらないと言っておいても、母さんは時折ああして用意してくれることがあった。今日もそうだったに違いない。いや、すでに『昨日も』か。俺は悪いなと思いながら、母さんを横目に階段を上って行った。もう俺の睡眠を邪魔する父さんはいない。母さんも、あんな場所でではあるが、夢の中にいる。俺を阻むものは何もない。部屋の扉を開けて、着の身着のままベッドへと体を投げた。
二 友人
教室の隅でパンにかじりつく。あんな「自分と向き合う」なんていう話をされたせいか、よく寝付けなかった。
「浩一、顔色悪いぞ」
祐輔が俺の肩を後ろから叩いた。
「あのあと、まだ遊んでたの?」
「いや、帰ったよ。そんで説教」
「うえぇ」
祐輔はわざとらしく舌を出して顔を歪める。
「祐輔んところはいいよなあ、お前の親、何にも言わないんだろ」
健伍が隣の席にどかっと腰を下ろした。
「言わないなあ。言わないっていうか、言えないのかも」
祐輔の意味ありげな言い方に、俺は「なんで?」と合いの手を入れる。
「中学の時に親とケンカしたことがあってさあ。帰りが遅いとか、ゲーセンで遊ぶなとか。うるさくてさ、家出したんだよね、一か月くらい」
「一か月も?」
「そ。流石に焦ったらしくて警察に連絡行ってたんだけどさー」
はは、と軽く笑っているが、笑い事ではない。
「龍ん家泊めてもらったりしてさ、なあ?」
少し離れた席でお茶を飲んでいた龍が振り返って、「呼んだ?」と声を上げた。
「ほら、中学の時さぁ」
祐輔はもう一度同じ話を、同じようにする。龍は「あー、あったね」と笑った。
「こいつ下着も何にも持たないで来やがるからさあ、コンビニでシャツとパンツと靴下買って、ズボンは俺のやつ貸したんだよな」
龍が笑うと、「そうそう」と祐輔が返す。
「結局、二人で遊んでるときに警察に見つかっちゃって」
「あん時は焦ったよなあ」
「焦った焦った。それに、警察に迎えに来た、うちの母さんの顔な」
祐輔は言いながら、むいっとしかめっ面をして、「こんなんだったよな」と笑う。
「ちょっと太ってムチムチになっててさー。自分の息子が家出してる間に何食ってたんだよっていうね」
「そんで、真っ白の化粧してさー。警察に息子引き取りに来るのに、そのメイクかよってな」
その場に居合わせていない俺や健伍には分からないが、随分それは楽しい光景だったのだろう。二人の盛り上がりから、そんな風に思える。
「まあ、それ以来、父さんも母さんも、何にも。言ったらまた出ていくかも、って思ってるのかもね」
「それでも、本当に問題だと思ってたら言うだろ」
健伍がつまらなさそうに言う。
「いいよな、祐輔ん家。トイプードルいるし」
「可愛いぞ。今度遊びに来いよ。初めて来る奴にはだいたい冷たいんだけど、威嚇して歯茎見せてくるのも、『負け犬』感が強くて可愛い」
祐輔が、その表情を思い出したのか、ニタニタと笑っている。龍が体を完全にこちらに向けて、「あ、俺はパスね」と言った。
「祐輔のとこの犬、なんでか俺にはガッツリ噛みついてくるんだよねー」
「そうだっけ?」
「そうだよ。しつけの方法間違ってんじゃないの?」
「んなことないと思うけど。お前がなんか旨そうなニオイしてるんじゃない?」
「ちゃんとエサやれよ」
龍が呆れたように口を歪ませた。
「健伍の家はどうなの? 夜遅くまで遊びに出てて、何も言われない?」
「あー、うちは父さんいないし、母さん夜の仕事だから」
しまった、というように、祐輔が目をキョロキョロさせる。俺もただ、「あー」としか言いようがない。祐輔の家は、父さんがどこだかの銀行に勤めていて、ありていに言って金持ちだと思う。持っているものも聞いたことのあるブランドのものだったりするし、小遣いがピンチのときは貸してくれたりもする。逆に、健伍の家は決して裕福じゃないことは、みんな知っていた。この瞬間までそんなことになっているとは思っていなかったが、それでも健伍と一緒に遊ぶときは、出来れば大して金を使わずに済むプランを検討する。長く居れるファミレスで駄弁ったり、フリータイムで遊べるカラオケだったり。そういうのを暗黙のうちに俺らはやっていたのだ。
「ごめん」
祐輔が謝ったが「何が」と健伍は返した。
「別に祐輔が謝ることじゃなくない?」
「いやまあ、そうかも知れんけど」
健伍は「はあ」と溜息をついた。
「母子家庭だから云々って訳じゃないけどさ、まあ、別にって感じだよね。帰ったら誰もいないから、まっすぐ帰っても遅れて帰っても特にリアクションなし。うるさくなくていいけど、怒られてもみたい、とは思うね、正直」
「いやいや止めとけって」
俺は頭を振る。
「ろくなもんじゃないから」
「そうそう」
龍が割って入る。
「俺、普段は何にも言われないんだけどさ、親が夫婦ゲンカしてるタイミングで帰っちゃうと、とばっちり喰らうんだよねぇー。『お前がもっとしっかりしてれば』って、俺カンケーないじゃん」
ははっ、と軽く龍が笑うが、その眼はしっかりとした怒りに満ちている。
「そういう時に限って、俺の素行がどうのこうのでケンカしてるって言うんだけどさ、休みの日とか聞いてたら、だいたい金の話か、親父の浮気か、どっちかだよ。いちいち巻き込まれて、ホントウザい」
俺の場合は、そこまでじゃない。いや、正確にはそっちのほうが明白に理不尽だからいいような気もするが。
「昨日も正座させられてさ」
「え、正座?」
祐輔が目を丸くする。
「そうそう。精神が良くなるとか何とか」
「え、『昨日も』ってことは、説教の時、いっつも正座なの?」
「そうだよ」
俺が飽き飽きしたように言うと、全員から「えー」と声が上がった。これが民意だと言ってやりたい。精神がどうのと言う以前の問題として、俺は、あるいは俺の同級生たちは、正座そのものに対して、強く反対なのだ。
「それってギャクタイじゃないの?」
祐輔が困惑の表情で言うので、俺は「さあ」とだけ肩をすくめて返した。
「いやいや、ホントに。警察とか行ったほうがいいって」
「終電で帰る学生のほうが怒られるって、そんなの」
もう一口、パンにかじりつく。もそもそして、口の中の水分が全部持っていかれるようで、不味い。
「まあ、いいんじゃないの、浩一がいいって言ってるわけだし」
龍が椅子に背を預け、頭の後ろに手を組んだ。
「そんなもんかなあ」
「そんなもんでしょ」
なおも心配する祐輔を、健伍も止めに入る。
祐輔は、きっと俺の両親が――いや、正確には父親だけなのだが、彼が何か踏むべきステップを誤って、俺との間に微妙な隙間が出来ているものだと思っているに違いない。だが、実際は違う。俺と父さんとの間にあるのは、きっとそういうものじゃない。立場だけで言えば、俺よりもなお悪いだろう健伍と龍のことを思えば、これ以上祐輔が俺らを詮索し、あるいは間を取り持とうとすることはまったく意味をなさない。勉強は出来ないが、決してただのアホではないし、そういう「面倒ごとが起きそうな空気」というのには人一倍敏感な自信がある。祐輔は、少なくとも俺のところで止めておかなくては、きっと健伍と健伍の母さんが仲良くなるためにはどうしたらいいかとか、さらにひどくなるなら龍の両親の仲を取り持つために、なんて言いかねない。祐輔はお人よしだ。いい奴だが、それがたまに空気を悪くすることもある。それが、まさに今ここで起こりかけた状況だった。
「パン、食う?」
俺は袋に残ったボソボソのイギリスパンのひとかけを祐輔に差し出した。
「まずいけど」
「まずいのかよ」
精一杯おどけた俺の気持ちを知ってか知らずか、祐輔はそのパンを「あざーっす」と言って奪っていった。
放課後、俺たちはまた、だらっと街へと出掛けて行った。別に何がしたかったわけでもないが、まっすぐ帰る気には到底なれない。特に、あんなことを言われた翌日だ。余計に家には足が向かない。
「顔色悪くないか」
龍が肩を叩いたが、俺は「そうかな」と聞いて顔を上げた。調子が悪いような気はしないが、自分で思うよりも元気がないらしい。祐輔と健伍も「具合悪そうだな」などと口々に言った。
「イライラしてんのかなー」
ぼそっと口走った言葉で、俺はハッとする。多分そうなのだろう。心の声が漏れた、というやつだ。だが、イライラという言葉ではあまりに軽すぎる。思えば思うほど、極度の緊張と怒りに満ちているような気がしてきた。アスファルトの上に咲いた名も知らない雑草を思いきり蹴散らす。千切れた葉先が軽く風に舞って、暗い路地へと吸い込まれていく。
「あー」
あてる先のない怒りで、ポケットの中に突っ込んだ手が湿っていく。
「カラオケ行こうぜ」
地面に向かって言うと、「珍しいな」と祐輔が言った。
「確かに。カラオケっていったら龍のイメージだよな」
「そうか? 祐輔だって結構言ってるだろ」
「え? そんなことないって――」
友達がワイワイ盛り上がっているのに、どうしてか、俺はその輪の中に入れない。先ほど蹴散らしたばかりの草の下に、白くて小さな花が咲いていたのを、じっと見ていた。
精神を、鍛える。真面目に、自分の気持ちと向き合う。
馬鹿馬鹿しい。俺は出来ている。楽しく遊んで、満足している。遅くに帰ったくらいでぐちゃぐちゃ言われることこそ――正座なんかさせられて叱られ続けることこそ、俺にとって大問題なのだ。自分の気持ちや、自分のちょうどいいリズムを崩す、一番の原因なのだ。
それで? 俺はその結論に達しながら、どうしてこうも、イライラし続けているのだろう。何かが引っ掛かっているのかもしれない。でも、何が? 俺は間違っていない。間違っていない。間違っていないのに――。
「浩一?」
「ん?」
「お前、やっぱ調子悪そうだけど」
健伍も心配した顔をしている。龍の心配性はいつものことだからそこまで気にする必要もないかもしれないが、健伍がそう言ってくるということは、相当ひどい顔をしているに違いないと思った。だが、帰りたくもない。
「いや、行こう。カラオケ」
いつの間にか先に立って振り返っていた三人を、俺は一気に追い抜いた。行かなくちゃいけない。そうじゃなければ、またあの家に、それもこんな日の高いうちから帰る必要が出てくる。俺の進んだ後ろから、六つの足音が不規則なリズムで追いかけてきた。
カラオケには午後四時過ぎから、フリータイムで入った。六時間までは自由だが、そのあとに延長料金のかかるプランだ。
「いっつも思うけどさあ」
龍が歌っている後ろで、祐輔が俺に叫び声をあげる。
「ここのフリータイムって、別にフリーじゃないよな」
「は?」
俺も怒鳴るように、声を返す。龍は普段とは全く違った、はっきりと大きな声を出す。活舌も妙によくなって、音程もよく取れて、本物の歌手みたいだ。流行りの歌も、俺らが生まれる少し前に流行った曲も、何でも卒なくこなす。だが、トークをする後ろで歌わせるには、パンチが強すぎる。
「だーかーらー」
間奏の隙間に、祐輔がもう一度声を張り上げる。
「ここのフリータイムってぇ、全然、フリーじゃねぇよなーって!」
「あー、そうだね」
「はぁん?」
俺には彼の声が聞こえたが、今度は俺の返事が聞こえなかったらしい。
「そうだねって!」
「なー」
龍が歌っている後ろで入れるから悪いのだ。とは言え、カラオケに来たら、結局ほとんど龍がマイクを握っているのだけれど。
「はー」
全力で声を出し切ったようで、曲の後奏が終わる前に、龍はぼてんと体をソファーに放り投げて、リモコンで曲を打ち切った。
「浩一は歌わなくていいのか?」
龍がゴツゴツした機械を差し向ける。
「いや、俺は別に」
「は?」
三人の好奇の目が俺に注がれる。
「じゃあなんでカラオケ来たがったんだよ」
「そうだよ、歌いたいんじゃねえのかよ」
「そういうわけじゃなくて」
背もたれに背中をびったりと吸い付かせて、烏龍茶を口へ。冷たい液体でのどが潤う。
「まず、クーラー効いてるじゃん。で、ダラダラできるでしょ。龍は歌えるし、その気になれば適当に喋っててもいいし」
「あのさー」
しばらく黙っていた健伍が、頬杖を突いたまま、俺をじっと見た。
「やっぱお前、今日ちょっと変だよ」
「かもな」
首をぐるぐると回すと、痛みこそないものの、張っているような気はする。
「ちょっと昨日、説教長かったし」
それだけなのか、それともそれ以上の何かがあるのかは分からなかったが、ひとまずそれは事実だ。
「帰って寝たほうがいいんじゃねーの」
「いいって」
俺は面倒だということが伝わるように、極力はっきりそう言った。
「だいたい、せっかくのフリータイムなのに勿体ないだろ」
「言っても、あと一時間ちょっとだけどな」
「は?」
さっき入ったばっかりだと思っていたのに、もうそんなに時間が経っていたのか。
「ほら、やっぱちょっとおかしいって」
健伍の表情が、茶化すようなものではなく、心配そのものといった感じに変わっている。よく見ると、祐輔や龍も、そういう顔色だ。
「最後までは、いよう」
俺はもう一度烏龍茶を口に含んだ。そういえば、すっかり氷も溶けきっている。いつからだったのだろうか。そしてこの消えた数時間の間、俺は一体、何を――。
「フリータイムが上がったら、そこで今日は帰ることにするから」
「……浩一がそれでいいっていうなら、いいけど」
健伍の言葉に、龍と祐輔が互いに目を見合わせていたのを、俺は横目で見ていた。
三 繁華街の深夜
祐輔、健伍、龍と別れたのは、それから一時間ほど後だった。約束通りにカラオケを出て、三人を駅まで見送る。俺は「トイレに寄ってから帰るから先乗ってて」と嘘をついて、夜の街中へと歩き出していた。彼らと一緒にいたくなかったというわけではない。ただ、なんでか、少し一人になる時間が欲しかったのだ。同時に、家には帰らないでいられる時間が。
これくらいの時間に四人でふらつくことは時々あったが、一人でというのは初めてだった。いつもなら何ということのない雑踏。白いジャケットを着た男や、真っ赤な顔のスーツの親父。どこの誰が逃がしたのかわからない犬。化粧と香水の匂い。降り注ぐ音、音、音。俺の数十倍、数百倍もの大きさのある街という巨大な生き物が、丸ごと人間を飲み込んでしまっているように感じる。
「お兄さんひとりー?」
怪しげなキャッチの男に肩を叩かれ、それを振りほどくように払いのけた。見るからに居酒屋か、いかがわしいサービスの店の呼び込みだ。学生服を着ている俺に用事があるはずもない。こういうのは見境なくとりあえず声をかけているのかもしれないが、何にせよ、カラオケを出てしまうと居場所らしい場所もないことに驚いた。腹は減っていないからファーストフードに行くのも違う。かといって、もう一回カラオケに戻るのも違うような気がした。祐輔のように、健伍か龍の家に避難させてもらったほうがよかっただろうか。それなら、この怪物に取り込まれてしまうような悪い錯覚も起こらなかっただろう。ふらふらと、モンスターに気付かれないように、その歯の隙間を縫って出ると、そこに小さな公園があった。小川があり、木があり、ベンチがある。若い男女が座っている隣の、本来なら二人か三人くらいで使うだろう範囲に、どかっと腰を下ろした。ここなら、化け物に見つからず、わずかばかり自分の存在を保てるような気がする。ようやく呼吸を取り戻して、俺は川の流れを見た。
右から左へ、ゆっくりと流れていく水。自然のものなのか、それとも人工のものなのか。そのせせらぎの上を、一枚の枯葉が流れていく。さっき蹴散らしたのとは違って、大きく、ボートのようになった葉だ。夏の盛りがこれから来るというのに、役目を終えてしまったのか、黄色く変色して、どんどん俺の目の前から遠くへと行ってしまう。
正座をすると、精神が研ぎ澄まされる、か。
こんなところで正座なんてしたら、変な奴に思われるかもしれない。だが、俺はそれを試してみたくてたまらなくなってきた。みんなにはめちゃくちゃだと思われるかもしれない。俺もそう思う。だが、どうしてもやってみたくなったのだ。この酒の臭いとタバコの煙が混じった怪物の吐息に吹かれ、ギラギラと光る眼に威嚇され、その中を流れていく、他に寄る辺なきものを寄せ付けてくるこの小川を前にして、俺は、その中の誰よりも孤独に、この一筋に向き合うことができる唯一の存在だったのだ。
靴を脱いで、ベンチの上に胡坐をかく。バランスは問題なく取れそうだ。広い座面板の上に膝を曲げて座ると、握りこんだ手を膝の上へ。背を伸ばす。目を閉じ、大きく息を吸い込む。鼻に、よどんだ空気がどっぷりと染み込んでくる。のどというフィルターを通して、多少マシになった酸素が、肺へ。それから、全身に移動するに従って、冷たく洗練されていく。足先までたどり着くころには、すっかり新鮮な、あるいは、森の一部でさえあった原初の公園を思わせるような爽やかさを取り戻していた。
ふと、目を開ける。
いや、これは深呼吸の効果だ。確かに瞬時、きりっと冴えて、すべてを理解できたような、あるいはすべてを許容できるような穏やかな気持ちになった。だが、それは「自分を見つめなおす」のとはまるで違う。自分を自分たらしめるものを理解することとは、まるで違う。
俺は面倒になって、足を崩し、そのまま放り投げて靴を履いた。馬鹿らしい。やっぱり、大真面目にそんなものがあるような気になって損したのだ。いい笑いものだ。街全体から笑われているような気がして、後ろを振り返った。大きな木がざわめいている。ごまかしても、俺には分かる。父親のどうでもいい戯言に惑わされて、ちょっとその気になって一瞬「これは凄いかもしれないぞ」などと思った馬鹿野郎だと、みんなそう思っているのだろう。ますます、家に帰る気が失せて、俺はスマホを取り出した。
「あ」
思わず、口が開いた。三人から、グループメッセージで通知が入っている。内容は「大丈夫かー」とだけ。……考えてみれば、顔色が悪いとあれだけ言われた後だ。ありがたいような気もするが、自分勝手な嘘を吐いたせいで心配をかけていると思うと、悪い気がしてならない。大丈夫だよ、と返信しようとして、ぴかっと怪獣の目が光った。
「君ィ」
白いライトが、上から下まで俺を照らしている。懐中電灯のような、小さい光だ。怪獣の子分らしい。
「高校生だね」
光の向こう側から、薄水色の制服で防護した二人組のおっさんが、まるで毛虫でも見るような目で俺を見下ろしている。ヤベ、と口走りそうになった筋肉を抑えて、小さく「はい」と答えた。
この繁華街にあって、交番は驚くほど小さく、みすぼらしかった。周りの光や音にエネルギーを吸われてしまって、大きく育てなかったのかもしれない。
「名前は」
机の向こう側には、父さんよりも二回りも三回りも大きい、丸々とした、まるで力士のようなおっさんが、鋭い一重の目で俺を刺すように見ている。
「園部」
「下の名前は」
「浩一」
「ソノベ、コウイチ君ね……」
目を伏せていても、何かをさらさらと書きつけているのは耳に入ってくる。これが俗に言う「調書」というものなのだろうか。カッコ悪いなあ。今まで結構夜の街にはいたが、こんな風に警察に捕まったのは初めてだし、周りでもそんな話は聞かない。もちろん遅くまで出歩いていただけで逮捕なんてされるわけでもないが、だからこそなおのことカッコ悪い。逃げようと思えば逃げれたのかもしれないが、ぼんやりしていたのが、また最悪だった。
「もうちょっと、椅子にちゃんと座りなさい」
別に、崩して座っているつもりはない。もちろん正座のような姿勢ではないが、それだって、学校よりはもっとしっかりと座っている。
「それから、ポケットから手を出して」
言われるがまま、一つずつ従っていくと、やがて形だけ立派になった高校生の俺がそこに現れる。
「なんでこんな時間に外にいたんだ」
「別に」
「別にってことないだろ」
荒ぶるとも、また許すともない声色。普段の恐喝染みた父さんの声に慣れてしまっているからか、怖くは感じない。思いきり体当たりされたら骨の二つや三つ消し飛んでしまいそうだが、こちらが変に暴れたりしなけりゃ、そんな手荒な真似はまさかしないだろう。ただ、成り行きに任せるしかない。
「高校生の門限、分かっているのか?」
「ちょっと電車に乗り遅れただけです」
「ここから駅までは五分近くあるぞ」
「具合が悪くて。ゆっくり座れる場所にいたかったんです」
はあ、と深いため息が漏れた。俺がまともに答える気がないというのが分かったのだろう。顔を上げて警官の様子をうかがうと、どうやら思った通りらしい。夜だからというのもあるだろうが、すっかり疲れ切った顔に、深いしわがぎっちりと刻み込まれているように見える。奥のほうでは、同い年くらいの少女が、同じように不貞腐れて取り調べを受けている。いたずらに伸ばした時季外れの白いセーターの袖が手をほとんど覆い隠している。その内側から生えるように、スマホ。目の前にいる婦警は、しかし俺の前にいる彼とは違って冷たい表情で何やら書き付けている。二人の態度から見るに、あの少女はここの常連なのかもしれなかった。新入りの俺に、ここの作法や基本姿勢を教えてくれているのか。こんないかにも面倒な場所には、俺はもう二度とこない。
「あー、きみ」
男が急に声に疲労を乗せて声を上げる。
「お父さんかお母さんの電話番号、分かる?」
「はい」
父さんがここに来たら、面倒が面倒を呼ぶに決まっている。「父の」と明言されなかったことを幸いに、俺はスマホを触って、母さんの電話番号を読み上げた。警官は、ただ言われるがままにそれをメモし、古臭い固定電話の受話器を取る。
「あ、夜分遅くすみません。こちら――」
さっき俺に向けていたのとはまるで違う、オクターブほども違う声色で、男が名乗る。電話の向こうには母さんがいるに違いなかった。さっきまで張り詰めさせていた背中から力を抜いて、生ぬるいパイプ椅子の背もたれにまた体重を任せる。天井を仰ぐ。白いでこぼこの塗装。見れば、まだ遠い雪の季節が思い出される。
「はい、コウイチくんが」
事態が伝えられるにつれて、受話器の向こうから母さんの声が聞こえてくるような気がした。ここにきて、少しだけ悪いような気がしてくる。ちらっと、さっきの少女を見た。まだスマホをいじっている。彼女にも、迎えに来てくれる親がいるに違いない。もう「悪い」なんて感情も失ってしまったのだろうか。光が映り込んで雪のように白く光るの内側には、どんな表情も見て取れない。交番の中の鳩時計が、午後十一時を告げた。
母さんが俺を迎えに来たのは、それから三十分もしない頃だった。おそらく少しも化粧をしていないのだろう。いつの間にか少し増えたシミとシワを、こんなに明るいところではっきりと見たのは初めてだった。
「すみません」
彼女の顔には、少しの笑みもない。頭をぐっと深く下げると、警官が「まあまあ」と口を開いた。
「別に何か犯罪をしたというわけではないのですが、お宅からかなり離れた夜の街をウロウロしている、という意味での補導ですから」
「すみません」
「校則違反でもありますし、ご家庭でもしっかりと指導の方をですね」
「はい、本当に、申し訳ありません」
母さんは少しも顔を上げずに、そう続けて繰り返した。そこまで悪いことをしたという気は、さらさらない。もちろん、善良で優秀な行動だとは思っていないが、しかし親にここまで謝らせるほどの悪事だろうか。俺は警察官の顔をちらりと見た。彼は何かを俺に言おうと口を開きかけたが、小さくため息をついて首を振った。そして、きっとさっき言おうとしたものとは全く違うことばを発した。
「とりあえず、今日はお母さんと一緒に帰りなさい。あまり、遅い時間まで出歩かないように。ご両親にも心配をかけるから」
俺は返事をするのが癪で、首を小さく縦に振った。
帰り道、母さんは俺に何も言わなかった。俺よりいつの間にか一回り小さくなった背中の後ろをくっ付いていく。スピードも、俺が一人で歩いたほうが早いはずなのに、その人を追い抜かすのが悪い気がした。電車から降りて、いくつかの街灯を通り過ぎて、二人は沈黙を保ったまま冷たく沈む玄関の扉を開けた。
「浩一」
薄々、そんな気はしていた。昨日と似た、父さんの声。
「来なさい」
別に行かない理由もない。俺は俺の思った通りのことをしただけで、それをとがめられる言われもなければ、自分を見つめなおして何かを考えることも必要なかった。むしろ、あの怪物の前での数秒、数分を、苦情として伝えたいくらいだった。
母さんは、父さんの後ろをついていく俺に対して、やっぱり何も言わなかった。
冷え切った仏間で、俺はだらりと足を崩している。昨日と違うのは、俺が彼の目を、ただじっと見ているということ。きっと今日は、これまでとは違うことが起こると思った。警察という一つの障壁があるおかげで、俺と父さんの間には、これまでに感じたことのないほどの大きな距離、深い谷のようなものがある気がしている。父さんは、それを悠々と超えられるのは自分だけだろうと思っているのかもしれないが、そうではない。俺だって、俺なりの考えがあって、こういう結果になったのだ。それを、きっちりと伝えなくてはいけないと思った。一方的な、半ば恫喝にも似た叱責ではなく、対等な一つの生物として、言いたいことを言うべきだと思ったのだ。
「正座」
父の強い言葉に、俺は「しない」とはっきり一言断りを入れた。今まで、ここでノーを言ったことはなかっただけに、父さんが瞬時、困惑の色を浮かべた。
「別に、俺は俺が正しいと思ったことをしただけだから」
じとっとした、重苦しい空気が流れる。まるで大悪党として裁かれる前のような、不穏な沈黙がある。耐え切れず、「うん」と、無意味に言葉を付け足した。
「そのお前の正しいと思うことが、母さんを警察に呼ぶことか」
「そうじゃないけど」
「じゃあなんだ」
地を這うような、低く重苦しい声。
「こんな夜遅くに警察から電話がかかってくるってだけで、母さんがどんな気持ちになったか、考えられないのか」
「だからそうじゃないって」
「じゃあどういう意味なんだ。言ってみろ」
まるで試すような強い言葉。だがそれに反するように、俺のこころに渦巻く気持ちは、しっかりとしているような気がした。
警察がどうの、というのは、あくまで結果論の後付けだ。俺は最初から警察に捕まって補導されたいなんて言う気持ちを、これっぽっちも持っていなかった。どちらかと言えば、捕まった瞬間に「マズい」とさえ思ったくらいだ。あの交番にいた時だって、この男のことはいざ知らず、少なくとも母に対しては、申し訳ないような気持ちが渦巻いていた。彼女のこころを考えていないなんて言うことは、まるで大嘘の妄想であって、真実ではない。
そもそも、今日に関しては遅くまでみんなとで歩いていたかったというわけではない。どっちかというと、一人になりたかったのだ。この監獄にも帰ってきたくなかったのはいつも通りだが、友人たちとも少し距離を取りたかった。一人になるためには、その十分な時間をとるためには、少なくとも今晩やろうとしたことは間違っていなかったはずなのだ。
あの川べりで俺が、わずかばかりこの男のことを信じて正座してみたことを、今は猛烈に後悔している。その時間があれば、俺はきっと警察に見つかることもなかっただろうし、こうやってまた二晩目の似たような夜を過ごす必要もなかったのだから。
俺は悪くない。絶対間違っていないかと言われれば自信はないが、少なくとも、悪であると決めつけられ、罵られるほどのことはしていない。それだけは確実に言える。
それに比べて、この男はなんだ。彼がしていることと言ったら、一方的な断罪だけ。よっぽど。俺よりも、よっぽど。
「うるせぇな」
これらの長く長い感情を言い表せる言葉を、けれど、俺は知らなかった。
「なんだと」
「うるせぇんだって」
俺は掴みかかりそうなほどに前のめりになった父さんの肩を、ぐっと押した。
「誰がお前なんか」
立ち上がって、仏間の引き戸を開け、体を外へ。そして、後ろ手にぴしゃりと閉めた。お前なんか――なんだろう。正座のこと。説教のこと。俺の気持ちを少しもわかってくれないこと。色々と言わなくちゃいけない言葉はあったような気がするが、やっぱり、俺は何と言っていいか分からなかった。廊下を進んでいく。居間から視線を感じてちらっと見ると、母さんが心配そうにこちらを見ていた。
「おやすみ」
俺は、それだけ言って、自分の部屋へと足を進めていった。
四 沈黙
それから一週間、父さんと口を利くことは無かった。その代わり、俺は夜遅くまで出歩くこともめっきり減っていた。何となくだが、そんな気になれなかったのだ。龍や健伍からは、「付き合いわりーな」と笑われたが、それは俺が補導されたことを気に病んでいると思ってのことかもしれない。祐輔は俺以上に補導の事実を心配しているらしく、遊びに誘うこと自体を控えているらしい。別にそれによって仲が悪くなったという感じはしないが、無駄に距離を取られているような気がするのはいいものではない。
まあまあ混み合う電車に乗り込んで帰るのにも慣れた。まだ明るい街並みを背に家に入る。
――、――。
「……?」
沈黙が、家の中に広がっている。母さんの、「ただいま」という声がない。期待しているわけではないが、いつもあるはずのものがない違和感が大きくて、急に、胸の拍動が激しくなっていくのを感じた。
「母さん?」
ひたひたと、自分の足音が冷たく廊下に響く。階段を通り過ぎ、居間を通り過ぎ、仏間を開ける。いない。戻って、居間をちらりと見る。人の気配がない。この時間に買い物に行っているのだろうか。いつもなら、もうとっくに晩御飯の準備も終わっているころだろうに。
ふと、テーブルの上に、紙が一枚置いてあるのが見えた。近づいて行って、それをのぞき込む。殴り書きのメモで、近所の病院の名前と、「お父さん、事故」とだけ書いてあった。
「なんだよ」
鼓動が、どんどん速くなっていく。百メートルを全力疾走したときだって、こんなにバクバクと音を立てることは無いくらいに。俺は震える手でスマホを取り出すと、病院の電話番号を調べ始めた。
あっという間だった。
それは、きっとトラックに直面した時に父さんが言うべき言葉だったのだろう。俺はぼんやり宙を眺めたまま、白い煙が漂っているのを見ているしかなかった。座布団が意味をなさないほど、俺の体は壁に預けられている。五十歳。健康だけが自慢みたいな男だったのに、何がどうなるのか、分からないものだ。二日前までは、母さんの焼いたトーストを食べていた。同じような日焼けした肌は、まだ生きていた時のそれと大差ない。見るのも嫌だった。見たら、触ったら、それがもう息をしていないと気付いてしまうから。それに、俺が最期に彼に言った言葉を思い出してしまうから。
母さんは、俺よりは少しばかり元気のようだった。落ち込んでいる時間もないのだろう。それでも、時折ふと、じっとり暗い顔をして、お父さん、と、それに声をかけている。返事をするわけなんてないのに、まるでただ寝ている人にそうするように語り掛けるのだ。いつか、休日の朝に彼を起こす母の姿を見たが、あれと、寸分たがわない、優しくて、いたわるような声。
俺は、母さんが居間で親戚の相手をしているのを横目に、父さんが寝ている仏間へと向かった。そこには、想像した通りの姿で、彼がじっとしていた。いつもはあれほど俺に正座しろと言い続けていた男が、今は天井を向いている。
「あー」
胡坐をかいたまま、膝に肘をつけ、頬杖をついた。
「せいせいした」
誰に言うわけじゃない。父さんにだけ聞こえるような小さな声で、ぼそっと言った。もちろん、生きていれば、だが。
「でも、大変よねぇ」
親戚の誰かの声が、ここまで突き抜けてくる。
大変なのは父さんだ。死んじゃったんだから。轢かれそうになった小学生の身代わりになっただなんて、本当についていないし、父さんらしいと思う。顔はきれいだが、身体は何か所か骨が折れていて、それを形だけ整えているらしい。意味があることなのかは分からないが、それがきっと母さんにとっては一番良いんだろうとも思う。
「浩一君だってまだ高校生で」
大丈夫。俺はもう高校生なのだ。ふらふらと遊んでばかりもいられないかもしれないが、卒業したらすぐに働くことができる。今からアルバイトだって、出来なくはない。健伍と変わらない、父のいない家庭になるだけなのだ。
「いくら義理とは言え、お父さんが亡くなったんじゃあ」
……?
義理? 今、間違いなくおばさんの中の誰かがそう言った。義理の、ってどういうことだ。確かに、俺は父さんよりは母さんに似ていると思っていた。でも、そんなのってよくあることで、息子は母親に似るからって、そんなのは普通で――。父さんの、いや、もしかしたら父さんでもなんでもなかったかもしれない男の顔をじっと見て、心臓の音を感じる。ずっと止まっていた呼吸が再開する。喧騒が遠くなる。居間の雑談が、すぐ隣で行われているように聞こえてくる。
「あんたもついてないわよねえ、旦那が立て続けに死んじゃうなんて」
「やだケイコちゃん、そんなこと言うもんじゃない……」
「でも、ホントそうよ。ついてないっていうか、変なもんが憑いてるっていうべきか」
母さんの声は聞こえてこない。
「浩一君はどうするのよ、知ってるんでしょ、お父さんのこと」
「……やだ、知らないの? 嘘でしょ、高校生にもなって――」
「二十歳になるまでは、ってあの人が――」
母さんの声が、誰よりも弱く、か細い。俺は胡坐のまま、がっちりと固まってしまって、死んだまま動かない父さんと寸分たがわない置物になった。
ああ、そうなんだ。そういうことだったんだ。
ようやく、理解できた気がした。父さんが俺に異常と思えるほどに冷たく、厳しかった理由が。つまり、実の息子じゃないから、多少厳しくしたところで胸が痛まないってことだったんだ。そうならそうと、早く言えばよかったのに。体中の筋肉が硬直して、さらに力がこもって小刻みに震える。腹立たしい。ムカつくという感情より、もっと内臓のさらに内側からあふれてくる怒りだ。
「おい」
俺は小さく、口を開いた。父さんは、返事をしない。
「そういうことかよ」
彼は沈黙を決め込んだまま、この暑い中で涼しそうな顔をしていた。
通夜が始まる二時間前。平日なのに学校にも行かず、それなのに制服に体を包まれているのはむず痒い。
「母さん」
仏間でずっと彼の顔を見ていた母に声をかけた。母さんは無言で、俺の顔を見た。
「この人、俺の父さんじゃないんだってね」
「……聞こえてたよね」
「当たり前じゃん」
あの声量で聞こえていないほうがどうかしている。どれほど気持ちにわだかまりがあったとしても、父さんは父さんなのだ。こんなときにイヤホンで音楽を聴いたりすることは無いだろう……もちろん、俺がそう思っていただけなのだが。
「……こーちゃん」
母さんが、正座のまま、俺のほうにぐいと向き直って、はっきりと声を出した。
「お父さんは、こーちゃんのこと、本当に大事に思っていて」
「いいよ、母さん」
俺はわざとその声を遮る。
「父さんが俺のこと邪魔だって思ってるんじゃないかってのは、うすうす感じてたし」
はっとして、それから彼女はうつむいたまま立ち上がると、仏間を出て行ってしまった。
「母さん?」
突然の行動に、俺は驚いて同じく立ち上がる。そして他人の亡骸を背に、母さんの後を追いかけていく。
母さんがいたのは、夫婦の寝室だった。振り返った母さんは、古ぼけたノートを俺に突き出している。
「これ」
「……なんだよ」
「読みなさい」
「もうこれからお通夜始まるんでしょ? 後からでも――」
「いいから、今読みなさい」
押し付けるようにそれを手渡して、母さんは出て行ってしまった。
表紙には、父さんの字で、「日記」とだけ書いてある。ずいぶん昔からつけているものなのか、手垢で黒ずんで、角にはコーヒーをこぼしたようなシミもついている。
浩一が、俺のことをようやく「おとうさん」と呼んでくれた。記念に日記をつけ始めようと思う。この日記は、彼と俺とをつなぐ一冊になると思う。本当の父親以上に、父親として、与えられるだけの愛情を注いでやりたい。
浩一が初めて友達を家に連れてきた。結局おもちゃの取り合いで殴る蹴るのケンカになってしまったみたいだが、男の子らしくていいとも思う。ただ、悪いことは悪いと言わなくてはいけない。俺が「こら」と言うと、口を尖らせて言い訳をする姿は、母さん譲りなのだろう。
浩一は進路で悩んでいるらしい。野球が好きでプロになりたいと言っていたが、選手を本気で目指すというのは至難の業だ。かといって、そういう夢をあきらめさせるのも違うような気がする。こういうとき、どんなアドバイスをするべきだろうか。本人のやりたいことを後押ししてやりたいが……。
浩一が受験に失敗した。もともと勉強は苦手だと言っていたから、仕方がないのかもしれない。相当落ち込んでいるようだが、うまく励ましてやれなかった。声を荒げるのも違うとは思うが、けれど、こんなとき、本当の父親ならなんと声をかけてやるのだろうか。俺は、どうしたら良かったのだろう?
母さんから、最近浩一の帰りが遅いと聞いた。試しに早く仕事を切り上げて浩一の帰りを待ってみると、十二時くらいに帰ってくる。これが毎日だというのだから、いけない。強く言いすぎてもいけないだろうが、せめて、まっすぐ育って欲しい。大人になって、恥ずかしくないように。
誰が、お前なんか、か……。確かに、俺は本当の父親じゃないし、浩一にとって都合のいい人間でもないし、尊敬に値する人間でもないだろう。明日から、どうやって浩一に接していこうか。
今日で、浩一と口を利かなくなり始めて四日が経った。これまでは少ないなりに朝の挨拶くらいはしていたのだが、それもない。ただ、浩一はまっすぐ家に帰ってくるようになったと母さんが言っていた。俺は嫌われてしまったみたいだが、浩一が変な方向に行って帰ってこなくなってしまうのだけは避けられたようだ。寂しい気もするが、俺は、これでいいような気もする。父親らしいことを、ようやくしてやれたような、そんな気がする。
もう、浩一と口を利かなくなって一週間にもなる。明日は金曜だし、少し早めに帰って、話してみたい。やっぱり、他人とは言え、俺にとっては大事な息子だ。このまま会話がないままなのは、俺が耐えられない。
俺はそれ以上が空白になっているノートを閉じて、立ち上がった。母さんなら、きっと仏間の父さんの前にいるはずだ。ふらふらと、何かに引っ張られるように歩く。襖戸を開けると、そこに、俺のよく知っている、けれど全く違う形になったばかりの夫婦がいた。
「ただいま」
俺の声に、母さんは何も言わなかった。俺もそれ以上何も言わず、ただ黙って、母さんの横に座った。自然と、正座になった。父さんの顔を見る。他人になったり、父親になったり、忙しい人だ。
「読んだよ」
「そう」
俺のことばに、母さんはそれだけ言った。
最初から、俺は父さんのことを、本当に父親だと思っていたよ。疑ったこともなかったよ。変に凝り性だったりするところも、父さん譲りだと思ってたよ。
俺がプロ野球目指すって言ったとき、父さん困ったように笑いながら、「いいんじゃないか」って言ってたよね。そんで、俺が学校から帰ったら、この辺りの野球少年団のパンフレットごっそり差し出してきて、「選べ」って、それだけ言ってたの、覚えてる? 俺、もっと軽い気持ちだったのに、父さんのほうがマジになっちゃってさ。バットとグローブも、スポーツショップで結構いいの買ってくれたじゃん。あれ、あんまり使わないままだったんだよね。父さんもグローブ一緒に買って、「キャッチボールしよう」って言ってくれたのに、面倒がってほとんどやらなかったよな。
高校落ちた時も、ほとんど叱らないで、ただ、なんとなくぎゅって強く抱きしめてくれたじゃん。「お前は俺に似て馬鹿だからな」って言われて、「うるさい」って答えちゃったけど、あれ、結構救われてたんだよ。つらくて、本当にどうしようもなくなっちゃいそうだったのに、父さんがそう言ってくれて、俺、もうちょっと頑張ろうって思ったんだ。
それで。この人のこと超えようって思って。俺、馬鹿なりに色々考えたんだけど、間違ってたっぽいって、今気付いたわ。今。本当に、今の今。
あー、俺、やっぱり結構ひどいこと言ってたよね。父さんに向かって「お前」なんて言っちゃダメだったよね。まして、義理の父だったなら、なおさら。知らなかったって言えば許してもらえる問題じゃないよね。
父さん。
俺の声が、もうこの人に届くことは無い。ようやく、まっすぐな気持ちで、きれいな姿勢で、この人の前に座ることができたのに。遅過ぎたんだ。馬鹿だからで、そんな軽い言い訳でごまかせるほど、簡単な話じゃない。
誰が、こんな俺のことなんて、と思っていた。あの言葉は、まぎれもなく、俺が俺自身に投げた言葉だったんだ。
「母さん」
ぽたりと、膝の上で固く握った手に、熱いしずくが落ちていく。声がしわがれて、響きを失っている。
「なに」
「ごめん」
母さんに謝っても仕方のないことだと思う。それは分かっている。でも、今この目の前で眠りこけている父さんの代わりになれるのは、この人しかいないのだ。それを分かっているのか、彼女はただ、「うん」とだけ返した。
そうか。父さんが俺に伝えたかったのは、こういうことだったんだ。俺は、父さんのことを――いや、それ以上に自分自身の過去のことも振り返ることはなかった。これまでの経験を思い返すことは、これからの自分の行動をどうすべきか考えるための基礎になる。何をしたら失敗するのか、どう考えたら成功するのか。それをゆっくり考える時間が必要だったんだ。正座でただ黙している時間、その静寂の中に過去の自分を映し出すことができる。俺には、これが必要だったんだ。これまでを振り返ること。これからを見つめること。その中で、『自分』というものを見つめること。
それに、もしかしたらだけれど、父さんは寂しかったのかもしれない。俺が忘れていった過去を思い出して欲しくて、たまらなかったのかもしれない。それなのに、俺は、今、ようやく。
足が、ゆっくりと痺れていく。尊敬していたはずの父親の忘れ形見を放したくなくて、俺は奥歯を噛みしめた。二つの鼻をすする音が、仏間に響いている。天井の木目が、父さんの代わりに俺を見下ろしていた。








