[238]降魔面(ごうまめん)に正座させるぜ!

タイトル:降魔面(ごうまめん)に正座させるぜ!
発行日:2022/11/01
分類:電子書籍
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:56
販売価格:200円
著者:海道 遠
イラスト:よろ
内容
平安時代。貴族の子息、十四歳の薫丸(くゆりまる)は、宮中への殿上童(でんじょうわらわ)に任命され、女房からは正座のお稽古をさせられ、きゅうくつな貴族暮らしに飽き飽きしていた。
そこへ毎年訪れる傀儡子(くぐつし)(人形使いなど)の一団がやってきて、屋敷を飛び出して行ってしまう。傀儡子集団には、新入りのオダマキという年下の女の子がいた。
夕方になり、黒っぽい面を着けた僧の一行が通りがかる。疫病退散の力を持つ、羅山寺の良玄(りょうげん)の一行だった。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/4284127

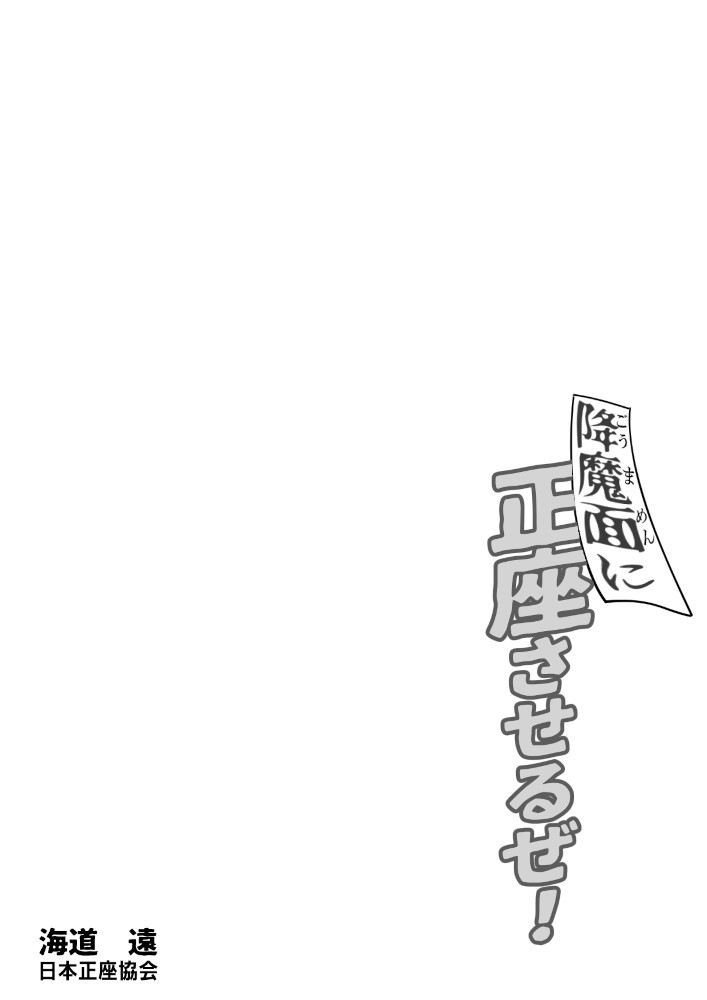
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 薫丸
「薫丸さま~~~」
「若君さま~~」
「どちらへ行かれました?」
「今宵は、帝のおわす宮中へ参内のために髪を下げみづらにお結いしたというのに~~」
乳母や女房たちが探し回る声を背中で聞きながら、薫丸は、お付きの舎人童の縹色(水色)の水干をはぎ取って狩衣から身軽に着替え、庭の松に登って塀に飛び移った。
下げみづらの髪のすそが、ぴょこんと跳ねる。
「窮屈な屋敷にずっといるのさえこりごりなのに、殿上童になって帝のおわす宮中に参内するなんて、やなこった!」
「若君さま、水干に下げみづらなど、ちぐはぐのご装束で~~」
草履を先に地面に投げてから、ぴょんと外側へ飛び降りた。十四歳とは言っても身が軽いのだ。
辻の向こうから笛や太鼓の音色が聞こえてくる。
(あれは、きっと傀儡子(人形使い)の楽の音色だ!)
草履を履くのももどかしく白い埃の舞う路地を、くくり袴にスネを丸出しにして鎮守の社向けて走り出した。
鳥居をくぐると、思ったとおり傀儡子の一団が色んな芸をしている。男衆は笛や太鼓、二本の剣をお手玉のようにしたり、お姐さんたちは艶やかな着物で水芸を繰り広げたりして民を集めている。
季節ごとに京へやってくるお馴染みの集団だ。
薫丸は大人を押しのけるように群衆の一番前に出た。
朱い頭巾を被った女の子が胸の前に抱えた箱の上で人形を操っている。
笛に合わせて躍らせるのが、とてもうまい。見物人から農作物や古着が親方の前に置かれていく。
「お~い、今日はこれくらいにしておこう。皆、ご苦労」
親方が、綱渡りや猿使いの芸を見せていた男たちにも声をかけた。
人形操りの女の子も、人形を箱に収めて背負った。薫丸は女の子に歩み寄った。
「お前、初めて見る顔だな」
「は、はい。あたいは親方から芸の許しをもらったばかりで……」
「とても上手だった。麿は薫丸ってんだ。お前は?」
「オダマキです……」
鮮やかな縹色の衣をまとった少年を、女の子は不思議そうに見つめた。
「麿……、いや、おいらでいいや。この格好が珍しいかい?」
「うん。間近で初めて見るから。きれいな着物だねえ。空の色みたい」
傀儡子の男たちは色あせた垢まみれの着物しか着ていないので、女の子が感嘆するのも無理はない。
「ちょいと派手なんだよ。仲間から着物を借りてくれないか」
「え、でも」
「いいんだ。しばらく屋敷には帰らないから」
女の子は、コックリとして親方の方へ走って行った。
入れ替わりに硬貨の穴にヒモを通して数えながら、黒いあごひげを生やした親方がやってきた。
「おや、六条家の若君じゃありませんか。いつも、ご贔屓をありがとうございます。庶民の着物がご入用で?」
「ああ。この色じゃ、どうしても目立っちまうからな。――贔屓って、ただ見しかしてないぜ」
「若君さま。そんな粗暴なものの言い方をなすっていては、下々の色に染まっちまいますよ」
「いいんだ。これの方が気楽で。今夜、どこかに泊まるだろ。ついていくぜ」
「やれやれ、言い出したら聞かない若君なんだから。オダマキ、若君さまの世話を頼むぜ」
「え、あたいが?」
オダマキは大きな眼を開いておどおどしていたが、薫丸が先に立って歩き始めた。
町はずれの森の中に、朽ちかけた無人のお堂が建っている。傀儡子たちは、今夜はそのお堂に泊まるらしい。
オダマキが仲間から地味な着物を借りてきたが、なかなか薫丸に渡そうとしない。
「若君さま、やはりそのままのお姿でいらしたら?」
「なんだ、貸してくれないのかい」
「着物をお貸ししたら、髪のカタチまで結い直さなきゃならないでしょう。とっても美しいからもったいなくて……」
肩にかかる真っ直ぐな漆黒の髪が絹糸のようだ。
「下げみづらっていうカタチなんだ。そんなに褒めてくれるのなら、このままにしとくよ」
「それがいいわ! 垂らした黒髪に水色の着物がとても似合ってるもの!」
「その代わりに、ひとつ願い事がある」
「え?」
「麿……、おいらのこと、薫丸って呼んでくれないか。若君さまって堅苦しいよ。オダマキ」
「分かったわ、薫丸」
オダマキはにっこり笑った。
紫色の夕闇が濃くなってきた。傀儡子たちがお堂に荷物を運び入れようとしていたところへ、僧の一行が通りがかった。
数人連れの僧の中に、黒っぽい面を被り、自信のない歩き方で早く通り過ぎようとしている者がいる。
「あの僧たちは?」
薫丸が、親方に尋ねた。
「ああ、羅山寺の良玄さまですよ。宮中に参内されるのでしょう。いかつい黒いお面をかぶっておいでですから」
「なんで、あんな怪物のようなお面を被っているんだ?」
「噂では、美男でいらっしゃるそうで、素顔で参内すると宮中の女官たちが騒ぎ立てるので、お顔を隠していらっしゃるそうですよ」
親方は笑いをがまんしながら説明した。
「そんなに美男の坊さんなのか!」
「美しいだけでなく、疫病退散のお力も強いので、御札をたくさん町の家々に配られているそうです。その御札を家の入口に貼っておけば、疫病が入ってこないそうです」
「へええ。そんなに効き目があるのか。一度、どんな御札か見てみたいな」
「良玄さまの御札なら、俺も一枚、持ってるぜ」
肩幅のがっしりした青年が傀儡子仲間の中から歩み出てきて、懐から御札を出した。
「なんだ、こりゃ。ガガンボが手踊りしているような、ひょろひょろした姿だな。これが疫病に効き目があるのかい」
御札には、やせ細った小鬼のような姿が描かれていた。
「良玄さまが疫病の神に襲われた時に、苦しんで鏡に映した姿だそうだ」
御札を見せた青年、半夏が言った。
「本当かな? イカサマのにおいがするぞ」
薫丸は、帰り道の良玄一行を待ち伏せすることにした。
第 二 章 待ち伏せ
薫丸は、傀儡子の中から半夏と、後三人の男を選んで準備をした。
「宮中に出入りできる、位の高いお坊様なんでしょ。待ち伏せなんかして大丈夫なの?」
人形の手入れをしていたオダマキが心配そうにしている。
「おいらは、九条家の嫡男なんだぜ。坊さんがなんだっていうんだ。あの御札はイカサマに違いない。それを暴こうっていうんだから、善いことをするんだぜ」
「……」
自信満々な薫丸に、オダマキはそれ以上、何も言えなかった。
京の町はずれの森は深い闇に包まれ、フクロウの鳴く声がホウ、ホウと響くだけだ。
「ずいぶん夜が更けたな。いつ帰ってくるかな、あの坊さんたち」
「さあ、宮中でお膳でも召し上がってらっしゃるんなら、帰りは夜中になりそうですな」
半夏が答えた。
「ヒマだな……。そうだ!」
薫丸は急に目を輝かせた。
「傀儡子のおじさんたち、『正座』ってもんを教えてやるよ」
「正座? なんだね、それは」
「唐渡りの目新しい座り方だよ。うちの女房たちに教えられたんだ」
「ほう、唐渡りの座り方……」
「『正座』して静かにしていると、日頃のイライラが鎮まるんだ」
「ほほう?」
「平な地面に真っ直ぐに背すじを伸ばして立つだろ。それからその場に膝をつき、衣類はお尻の下に敷いて、かかとの上に座る。やってみな」
「ええ? 足を折り曲げて窮屈そうじゃないか。あぐらの方がいい」
男たちがちっとも薫丸の真似をしない中で、ひとり、正座をしていた者がいる。オダマキだ。
「これで、ちゃんと正座ってもんをできてるかな」
「オダマキ! もう遅いぞ。子どもは寝る時間だぞ」
「ねえ、正座できてる?」
「あ、ああ。一応。できてる」
「やった!」
オダマキは無邪気に喜んだ。
「これ、人形たちにやらせるわ。新しい出し物になるわ」
「お前、ちゃっかりしてるな。子どものくせに」
「子ども子どもって、十二よ。もう子どもじゃないわよ」
「子どもだよ」
「若君さまだってまだ十四でしょう」
くだらない言い合いをしているうちに、半夏の緊迫した声が響いた。
「しっ! 彼方から坊さんの行列が近づいてきた」
先頭の僧が提灯を持ち、真っ暗な田んぼの畦道を数人の集団が歩いてくる。
薫丸は真正面から堂々と大股で大地を踏みしめ、近づいていった。
「羅山寺の良玄どのの、ご一行とお見受けする」
「な、何者?」
良玄を囲む僧たちは、暗闇の中から突然現れた水色の水干姿の少年に驚いた。
「何用じゃ」
「ちょいと良玄どのの『降魔面』とやらをはぎ取ってみたくて」
言うが早いか面を被った男に近づき、面を取り去った。
「あっ、何をする!」
間髪を入れず、待ち伏せしていた仲間が提灯を近づけた。
「や、やめなさい!」
面を剥がれた僧は、必死に袖で顔を隠そうとしたが、傀儡子の仲間たちが両腕を押さえこんだ。
「あっ」
薫丸が声をあげた。
面を剥がれた僧の顔面には、あばたがたくさんあったのだ。
「見るでない!」
僧は泣きそうな声で叫び、僧衣の袖で顔を覆った。
「美男だという噂だったが……」
薫丸は呆然と突っ立った。
「これは幼い頃、疫病に罹った時にできたものだ。疫病が憎くて、ひたすら疫病退散のための修行をしている。そなたはいったいどこの公家の子だ。無礼にもホドがあるぞ!」
「それは悪かった。ちょっとしたイタズラ心だったんだ」
「むむう……」
「おいらじゃなくて、麿は九条家の息子だ。薫丸という」
周りの僧たちも怒りの色を隠さずに睨みつけた。
「良玄さま、とんでもない野蛮な童、いかがいたしましょう」
「九条家の子息ということだから、しょっ引いて突き出してやりましょう」
「あっ、それはご勘弁を……!」
慌てた薫丸である。
第 三 章 良玄の稽古
待ち伏せしていた仲間は、とっとと姿を消してしまっている。
「それだけはご勘弁ください。父君から大目玉を食らってしまう!」
薫丸は畦道の上に慌てて座りこみ、ガマガエルのように土下座した。
僧たちは、どうしてやろうと取り巻いている。
田んぼから這い上がってきた小さな影が、薫丸の側へ寄った。
「薫丸!」
「オダマキ?」
「お坊様たちに、さっきの正座の所作を教えてあげるのよ。正座をすれば心が穏やかになるんでしょう?」
「正座をか? でも、坊さんたちは頭から湯気を立ててるぜ。とても言い出せる雰囲気じゃないよ」
「待ち伏せなんかして、お面を剥ぎ取ったりするからよ。誰でも怒るわよ」
顔面に「降魔面」を戻した良玄が、僧たちに命令した。
「とりあえず、我が寺に連れていけ。九条家と揉めたくはないゆえ、内密にな」
薫丸は良玄の寺へ連行された。
僧坊(僧が寝泊りする部屋)に放りこまれて、朝になるのを待った。夜が明けてしばらくすると、若い僧が、食事を運んできた。お椀にかゆ一杯と菜っ葉の煮物だけの質素な朝餉である。
「これじゃあ、すぐにお腹が鳴ってしまうよ~~」
厚かましいことをわめきながら、薫丸は箸を置き、膳を下げに来た僧を捕まえた。
「良玄さまに会わせてくれないか。昨夜のお詫びをちゃんと申し上げたいんだ」
「良玄さまは朝の勤行中です」
「そう冷たくせずに……」
薫丸がねばりにねばったせいで、良玄からお許しが出た。
(やった!)
薫丸は内心、しめた! と思い、良玄の部屋へ向かった。
修行僧の後に続いて、寺の広大な庭を横に見ながら、奥の院への長い廊下を歩いていった。
良玄は奥の一室で、静かに書物を読んでいた。
薫丸が背後に座ると、振り返ったが、相変わらず降魔面をかぶっている。明るいところで見ても背すじがぞっとする迫力だ。
素直にお詫びしようと思っていた薫丸は、躊躇してしまった。
「これが怖いか、九条家の息子よ」
「怖いよ。脱いでる方がいいって!」
「私の醜い素顔を見たであろう。あのような顔で過ごしたくはない」
確かにあばたが顔全体にあって、何歳くらいだか分からない顔になっている。
「今後は絶対にあのような疫病をはびこらせてはなるまい。その執念から、疫病退散の意味で降魔面をかぶっているのだ。私とて、再びあれと別の疫病にかかるやもしれぬ」
「そりゃそうかもしれないけど……」
薫丸は、良玄がかなり頑なになっているのを感じた。頑なになると心が曇る。
オダマキが昨夜、耳うちしてくれたことを思い出した。
「良玄さま。悪い事は言わないから、『正座』の稽古をしませんか?」
「突然、何を言い出すのだ」
「唐渡りの正座の所作をして正座し、心を穏やかにすると、そのお面を取ろうという気になってきますよ」
「なに……」
「貴方だって、お面を外して、すっきり清々しい空気を吸いたいでしょうに」
障子窓の向こうには、美しい緑あふれる庭が見え、爽やかな風が吹き渡っている。
良玄はしばらく窓の外に目を投げ、眩しそうに眺めた。
「薫丸どの。その『正座の所作』というものを、知っておるのか? 確か、唐渡りとかの……」
「知ってるともさ! うちの女房たちに幼い頃からイヤっていうほど仕込まれたんですから」
「ほう」
「そのおかげで能天気でいられますよ。物事を明るく考えられるような気がします」
「心穏やかになれて明るくなるだと? こんな顔でもか」
「顔と心持ちは関係ありませんって」
「そんなことが言えるのは、お前がきれいな顔をしているからだ」
「ほら、拗ねてる! 正座を習慣にすれば、拗ねることもなくなりますよ。本当はそんな怖いお面なしになりたいんでしょ?」
「そ、そこまで言うなら……」
良玄は咳ばらいして、立ち上がった。
「そうこなくちゃ!」
薫丸は、オダマキに届くように片目をつむって見せた。
「まず背すじを真っ直ぐに立って。床に膝を着いてください。法衣はお尻の下に敷き、かかとの上にゆっくり座る。両手は膝の上に静かに置く。できましたか?」
「ああ。できたつもりだ。読経の時にはあぐらに似た座り方をしているが、こちらの方が楽かもしれん」
「読経の時も無心に拝んでらっしゃるでしょうけど、どうしてもリキ入るでしょう? こちらの座り方は力を抜いて、心を鎮めて……」
稽古が終わった後、良玄は縁に出て、何回かひとりで正座の所作をやってみた。風に吹かれながら心を穏やかに務めた。
第 四 章 節分会へ
いつものように傀儡子たちが、町の辻で芸を披露していると、良玄が共の僧たちを連れてやってきた。
居合わせた薫丸はたまげた。
良玄がにこにこして素顔でやってきたのだ。あばたはまだあるが、すっきりした表情をしている。
「どうしたんです、良玄さま。今日は降魔面を被っていないのですかい?」
「ああ、薫丸さんから教えてもらった正座を毎日していると、お面を外して外を歩いてみようかという気になったのです」
「そりゃあ、良かった!」
「それに、あれから薫丸さんの使いだと言って、私のあばたに効くという軟膏薬を届けてくれる少女が参りましてな」
「軟膏薬? おいらは知らないけどな」
「そうですか? 薫丸さんのお名前を信じて、毎日、顔に塗っていると、だんだん平になってきたような気がします」
薫丸は、グンと側に寄って良玄の顔を見つめた。
「そう言われれば、きれいになったような?」
「あ、あの少女ですよ。良玄さまに軟膏薬を持ってきたのは」
良玄の連れている僧が、傀儡子たちの中で人形を操っているオダマキを指さした。
「オダマキ! お前だったのか。良玄さんに軟膏薬を届けたのは」
オダマキは、照れながら頷いた。
近寄ってきて、良玄にぺこりと頭を下げる。
「薬が効いたようで何よりです。お坊様。旅をして回っていますから薬売りのおじさんから、良いという評判の薬は、たくさん買っておくのです」
「礼を申すぞ。娘御」
良玄はとてもご機嫌で、オダマキの頭を撫でた。
「薫丸。羅山寺では毎年、節分(大晦日)に追儺式という行事を行う。鬼を退散させるための行事だ。見物に来るがよい。そこな娘御、オダマキ。お前もいかがかな?」
「節分の行事ですか? 行きたいです!」
薫丸はひとつ返事で引き受け、オダマキを見やった。
「あたいも行っていいんですか?」
「ああ、もちろんだとも」
それから数か月経った。
いよいよ大晦日だ。羅山寺では節分会の追儺式鬼法楽が催される日を迎えた。
薫丸は、この日をわくわくして待ち、申し合わせておいた傀儡子の一行も京へ上ってきた。
「おお、親方、オダマキも半夏も、元気だったかい」
「若君さまもお元気そうですな。風邪にもかかられず」
黒いあごひげの親方が逞しく馬車で一行を率いてきた。
「昨年から良玄さまの御札を持ち歩いているから、効き目があるようですよ」
「あんなにイカサマだって騒いでいたのに、手のひらを返したような若君さまだなあ」
半夏とオダマキが顔を見合わせて笑っている。
「オダマキ、背が伸びたんじゃないか?」
「そうですか、あれから少ししか経っていないのに、嬉しいな」
「伸び盛りの年頃だからな」
「薫丸さまは、あまり変わりませんねえ」
「う、うるさい。おいらはどうせチビだよ」
「今日も童子の着る水干が似合ってますよ」
オダマキはからかって笑った。
羅山寺の門前には、見物の民衆が押し寄せていた。
やがて山門が開かれ、民衆はどっと寺の中へ入っていく。
薫丸と傀儡子一行も民衆に続いて、大師堂前に設けられた舞台の側へ進んだ。
大師堂では、護摩行の修法が執り行われている。良玄も一心に読経しているはずである。
お日様が真上に登る頃、大きな太鼓とほら貝が鳴らされた。
舞台の隅から、赤い面、青い面、黒い面を着けた鬼どもが現れた。民が鬼に扮しているのだ。
それぞれ松明や宝剣、大斧を持って、民衆に振り回してみせる。
民衆がどよめいている中、薫丸はヘン、と鼻を鳴らした。
「あんな鬼ども、降魔面に比べたら、ちっとも怖くないじゃないか!」
「赤い鬼は人間の貪欲、青い鬼は怒りや憎しみ、黒い鬼はグチを表してるそうよ」
オダマキが言った。
鬼どもは、大師堂の中へ入って踊りながら修法のさまたげをしようとする。
読経の声は逞しく続けられ、やがて外の舞台に、なんと、あの降魔面を被った追儺師が弓矢を携えて登場した。堂々とした背格好の青年だ。
「よっ、待ってました!」
民衆から声が飛ぶのに釣られて、薫丸も、
「待ってました!」
と叫ぶ。
「薫丸ったら、あたいたちの芸を見物してるんじゃないんだから」
オダマキがたしなめた。
「だって、皆、叫んでるじゃないか」
「あなたは九条家の若君さまなのよ。はしたないじゃないの」
「乳母や女房みたいなこと言うなよな。外に出てる時は、ただの『薫丸』だよ」
追儺師は勇壮な弓を構えて、東西南北と天の真上へ降魔矢を放ち、鬼どもは退散していった。
弓矢には霊妙な力があると信じられている。
第 五 章 追儺師やらせて!
面を取ると青年僧が表れた。
良玄ではないか。白い歯を見せて、少し笑ってみせた。
あばたが見えない、すっかり滑らかなお顔になっている。
「良玄さまだ!」
薫丸がつい叫んだ。
民衆からも、
「良玄さま!」
「魔滅大師、良玄さま!」
喜びに満ちた声が上がり、皆、顔を輝かせている。
追儺師の勇壮な弓術を目の当たりにした薫丸は、すっかり魅せられてしまった。
「おいらも追儺師になる!」
などと言い出した。
翌日、つまり新年の元旦に、さっそく良玄を訪ねた。
「新年おめでとうございます。良玄さま」
「新年おめでとう、薫丸さん。鬼法楽はいかがであった?」
良玄は朗らかに迎えた。
「降魔矢のお手並み、素晴らしかったですよ! 是非、おいらを来年の大晦日の追儺師に任じてください!」
いきなりの願いに、良玄は返事に詰まった。
「薫丸さん、弓矢はできるのですか?」
「全然できないけど……」
「私は稽古させてあげる時間がとれませんぞ」
「半夏という弓の出来る者が傀儡子の中にいますから、教えてもらうつもりです! 半夏は元、京の検非違使(今の警察官)だったんで、弓矢の腕は確かですから」
「ほほう?」
「傀儡子たちにも正座を教えますから、鬼法楽の日に興行させていただきたいので、舞台で正座して挨拶してもらいます」
眼を輝かせて薫丸は言う。
「薫丸さん、そなたの胸中の計画は、すべてできているようですな」
「うん!」
「弓矢がちゃんとできるようになってから、もう一度いらっしゃい」
「う……」
(やんわりと断られたかな?)
薫丸はしょんぼりしてしまった。
しかし、負けず嫌いの薫丸は翌朝になると、がぜん、元気を取り戻して半夏に弓矢の稽古を頼みこむため、傀儡子たちが寝泊りしているお堂へ出かけた。
「ねえ、半夏。おいらに弓矢を教えてくださいっ」
順番どおりに正座の所作をして、床にぺったりおでこをつけて頼みこんだ。
半夏は二日酔いの様子だ。まだ半分、夢の中だ。
「もうちょっと寝かせてくれよ……。ああ、寒いっ。冷えるなあ、このお堂……」
「ちょっと待ってください!」
屋敷までひとっ走りして、雑色(下働き)に火鉢と炭を運ばせてきた。炭火を入れると、すき間風だらけの中でも少し温かくなってきた。
「おお、温かくなったな。ありがとうよ、若君さま」
「隙間風は雑色に材木を持って来させて打ちつけますからねっ」
まめネズミのように走り回り、薫丸自ら、慣れない大工道具で板を張りつけ始めた。
がんがんトンカチの音が響いていると思ったら、
「いてぇ―――!」
情けない悲鳴が半夏に聞こえてきた。
「あ~~あ、大工仕事なんてやったことないくせに」
半夏は外へ呼びかけた。
「若君さま、後は雑色さんにおまかせして中へお入りなさい」
薫丸は入ってきて、藁の上に座っている半夏の前に正座した。
「弓矢を習いたいというのは、本気ですかい?」
「もちろんだよ! この前の追儺師みたいに、東西南北と真上に颯爽と矢を放ってみたいんだ」
「あの追儺師、カッコ良かったですもんね。でも、私のなまった腕でお教えできるかなあ」
「検非違使やってたって言ったじゃないか!」
「朝廷行事の賭弓(弓の腕を競う行事)では、賞品が支給されたこともありましたが、なにせ、ずいぶん昔のことなんで……」
「お願い、このとおり!」
薫丸は、もう一度、土下座した。
「ふ~~ん、若君さまにそこまでされると……。前からご贔屓にしてもらってることだし」
「ことだし?」
「いいでしょう。お稽古つけましょう。その代わり、途中で放り出したりしないで頑張ってくださいよ」
「やった―――! これで、良玄さまにもう一度頼みに行ける!」
様子をうかがっていたオダマキが、ため息をついた。
(弓矢が上達すればですけどね)
第 六 章 半夏、倒れる
寒風の中、薫丸は屋敷の警護の者から弓矢を借りてきて、稽古が始まった。
半夏の声がいつもと全然違って厳しい。目つきも違う。
「まず立ち方です。上体を正しく保ち、息を吸いながら腰を伸ばしつつ一方の足を爪先を立て、次に他の足も爪立て、丹田(ヘソ下三寸の位置)に力を込め、深呼吸して足を踏み出し、つま先を軸として他方の足をそろえ、うなじを伸ばし、息を吐く。できましたか?」
「順番が覚えられないよう」
「何度となくやっているうちに身についてきますよ」
「むむ」
「次に、矢を構える所作。弓と一緒に目線の高さに持ち上げる。目の高さです。ただし、目は矢を見ては行けません。立った時に十三尺あまり向こうの高さに目線を定めること」
「う~ん、難しいなあ」
難しいながら、正座と通じる心を落ち着ける所作だと感じる。
「ははは、正座の所作のつもりで頑張りなされ」
薫丸はワラ人形の的をめがけて毎日、弓を引いた。
傀儡子たちが京を去って西の国へ巡業に出立しても、半夏から言われた指導を頭に入れて稽古を続けた。
春が終わり、梅雨も過ぎ去り、真夏の陽射しが京の町に満ちる頃、傀儡子たちが帰ってきた。
「親方、半夏、オダマキもお帰り!」
子犬のようにじゃれついて薫丸は迎えた。
「若君さま、お元気そうですな。相変わらず水干姿で」
「動きやすいから、これが好きなんだ!」
「弓矢の稽古はサボらずやっておられましたか?」
「うんともさ! 稽古場へ来てよ、半夏! いや、半夏先生!」
半夏の太い腕をつかんで、いつも稽古している草原へ引っぱって行く。
「あのワラ人形を見ていてください」
ゆっくり弓をかまえた。
足は大きくゆったりと広げ――。腹の中心のやや下辺りに力を入れて――。矢をつがえて大きく弓を張り――。
「今だ!」
放たれた矢は、真っ直ぐ的めがけて突進し、ワラ人形の胸に中った。
「どう? 半夏?」
「お見事です! 半年間よく頑張りましたね!」
暑さのために顔面に汗をかいた半夏が、笑顔で褒めた。
「これで、良玄さまにもう一度お願いに行けます……ね……」
半夏の大柄な身体が、ぐらりと傾き地面に倒れていく。
「きゃああああ!」
稽古を見物していたオダマキが悲鳴をあげた。
親方が駆けつけてきて、半夏の様子を見た。
「ひどい熱じゃ。それにこのポツポツ……。二十年ほど前に流行った疫病と同じだ!」
薫丸と傀儡子の仲間たちは真っ青になった。
親方がさっそく指図した。
「半夏を小屋に隔離しろ! 皆、近づくでないぞ。清らかな水でよく手を洗うのじゃ」
「親方、半夏さんの看病はあたいがやるよ」
オダマキが、鼻と口元に布を巻きつけて言った。
「オダマキ。お前にできるか?」
「前の疫病時代を知ってる姐さんたちと交代でやるから大丈夫」
オダマキは、呆然と立っている薫丸に目をやり、
「薫丸は、すぐにお屋敷に帰って、皆さんに口元に布を当てて、よく手を洗うように言うこと!」
「お前、よく知ってるな」
「薬売りのおじさんから教わったのよ」
オダマキは少女ながら逞しい。
「では、ワシは薬売りの郷まで行ってくるよ。くれぐれも半夏のこと、頼んだよ。皆も気をつけてな」
親方は、先ほど解いた荷をまたもや旅支度した。
「頼みますぜ、親方!」
薫丸と傀儡子たちは、心細く見送った。
数日中に、京の町中でも疫病の感染者が出始めた。
降魔面をつけた良玄が、傀儡子たちの滞在する小屋の側を通りがかった。
「なに? 半夏さんが疫病にかかった?」
薫丸が告げると、良玄はすぐに、半夏が隔離されている小屋を見舞った。
半夏は、高熱のため意識が朦朧としていた。
「半夏さんというのはそなたか。いつぞや宮中の賭弓の行事で腕を競い合った検非違使どのではないか」
「おお……」
半夏は良玄の見舞いに感激して涙を浮かべた。
「しっかりされよ。私も一度はかかった病だが、ちゃんと治ったぞ」
「そりゃ、良玄さまは魔滅大師ですから……。変だな、御札を肌身離さず持っていたのに」
震える手で御札を差し出してみせる。
「御札なら、たくさん所持しておるぞ。もっと身体のあちこちに貼りつけて進ぜよう」
半夏の全身にペタペタ貼り付けた。
ふたりの会話を小屋の外で立ち聞きしていた薫丸は、良玄が外へ出てくるなり叫んだ。
「ふたりは昔から知り合いだったのか!」
「賭弓ではお互いに好敵手だったさ」
良玄がニヤリとした。
「どうして半夏は検非違使から傀儡子の仲間に?」
「薫丸さん。人には色々と事情というものがある。尋ねてはならぬこともな」
「……つまんないの」
「薫丸さんは元気そうだな。しかし疫病には心せよ。今年の大晦日には疫病はどうなっていることか。お前が追儺師になれるほど弓術が上達していても、鬼法楽を行うのは無理かもしれぬ」
良玄の表情は深刻だ。
「そうなったら仕方ない。おいらひとりでも降魔矢を放ちますよ!」
「薫丸……」
良玄は、やる気満々の表情に元気をもらった。
「その時は、私が隣に正座して読経して進ぜよう」
第 七 章 降魔面を射る
夏の終わり、半夏は親方が薬売りの郷から持ち帰った薬の効果もあってか、疫病を克服した。
しかし、京や周囲の町や村には疫病が蔓延し、帝は寺の法楽や神社の神事や祭りなど、人が集まる行事はすべて禁止した。
そして、大晦日。
追儺式鬼法楽は、やはり行われないことになった。
薫丸は、かねてからの良玄との約束どおり、羅山寺の大師堂前で弓矢の支度をした。
装束は半夏がそろえてくれた。大師堂の脇に控えている。
水干の上から肩に装着する射籠手を着け、弓懸という革の手袋を着ける。足元は物射沓という履物で、準備万端だ。
かたわらの毛氈の上では、良玄が正座して一心不乱に数珠を繰りながら読経を行っている。ずっと背後には、傀儡子仲間が並んで正座し、合掌した。
昼間だというのに暗い雲が湧きおこって、生温かい風が吹きつけてきた。
地獄から響くような笑い声が聞こえ、雲の中から赤黒い大きな降魔面が現れた。
「姿を現したな~~、疫病の象徴の親方!」
薫丸は弓に矢をつがえた。風でみづら髪の先が弓に巻きつくのを、うっとおしそうに振りはらう。
「若君、少しお待ちを」
半夏が駆け寄って矢の先に炎を点けた。
「御札を仕込んだ神聖な火矢です! 降魔面を燃やしてくれるはず」
「おお、ありがとうよ」
矢をつがえ直した薫丸は、東西南北に放ってから赤黒い降魔面に的を合わせた。
面は笑いながら迫ってくる。
充分、引きつけてから――、
「失せろ、疫病神!」
放たれた火矢は一直線に空を昇り、面の眉間に命中!
少しの時間、空気は沈黙し――、やがて昏い雲の中で神聖な炎が燃え上がった。
「ぐわあああああ」
疫病神の断末魔が響き渡った。
辺りは元どおり明るくなり、おどろおどろしい気配は消えた。
「やったな、薫丸さん!」
「若君さま、よくぞ!」
良玄と半夏が叫び、遠くから見守っていたオダマキも薫丸に駆け寄った。
「すごいわ、薫丸!」
「役病神の象徴を撃退したな」
薫丸はほっとして、皆に揉みくちゃにされるがままになった。
「良玄さまと皆のおかげだよ」
沓を脱ぎ、その場に恭しく正座して頭を深く下げた。
まもなく、疫病の広がりは治まっていった。


![[275]お江戸正座2](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)





