[253]正座師匠あぐらくん
 タイトル:正座師匠あぐらくん
タイトル:正座師匠あぐらくん
掲載日:2023/04/05
著者:海道 遠
イラスト:鬼倉 みのり
内容:
江戸時代。下級武士の娘、リツは上級の武家屋敷にご奉公に上がっているが、年越しの休みをもらって実家に帰ってきた。両親と弟が迎える。ラブラブの許婚(いいなずけ)の阿蔵之介(あぐらくん)にも会えると思ってワクワクしていたのだが、あぐらくんは町奉行所に置かれていると聞いて、飛んでいく。
もうひとつの悩みは、幕府から反物令が発令されて、毎年、お正月に母親が新調してくれる着物で正座しようとするとキュウクツになってしまったことだ。

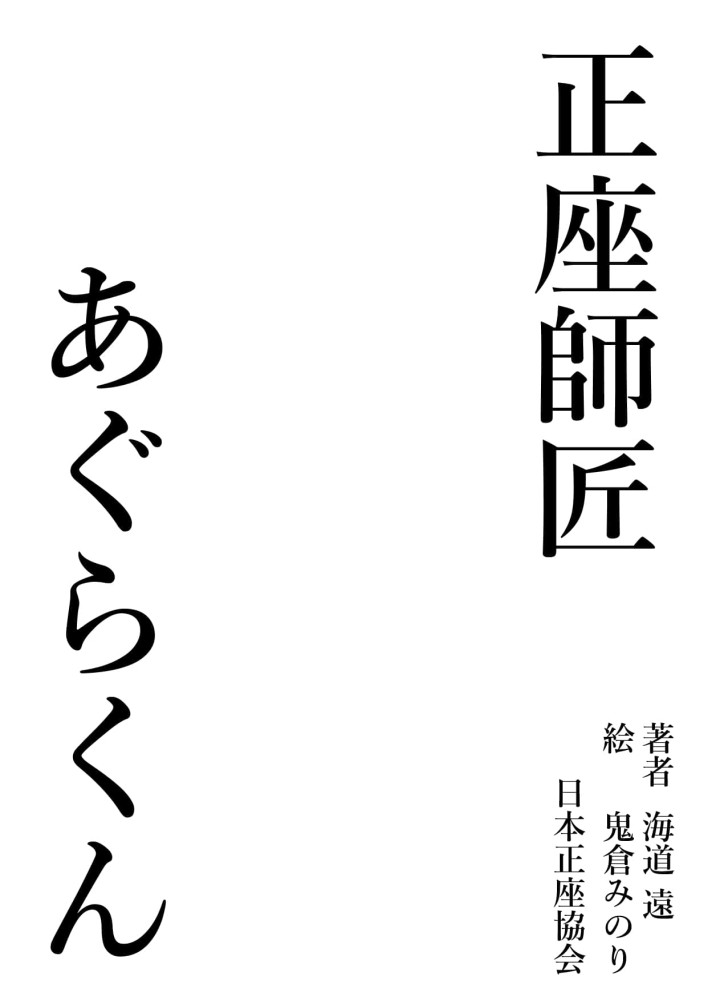
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第一章 お宿下がり
その年も年末になり、歳を越すために下級武士の娘、リツは奉公先の武家屋敷からお宿下がりしてきた。
実家に帰るのは、お盆以来だ。
(師走の慌ただしさも無事に乗り越えたし、やっと一息つけるわ。父上や母上、やんちゃ坊主の章太郎は元気にしてるかしら。それと、あぐらくんはどうしているかしら)
胸をはずませて帰ってきた。
母親がお正月になると、いつも新調した着物を枕元に置いておいてくれるのも楽しみのひとつだ。
(今年はどんな柄の着物を縫ってくれたのかな?)
小さな風呂敷包みをひとつ持って、城下町の角を曲がると我が家が見える。下級武士の家なので長屋だが、リツには大切な我が家だ。
玄関の障子戸をガラリと開けると、かまどで手ぬぐいを姉さんかぶりにした母親がこちらを向いた。
「リツ。お帰り」
「ただいま、母上。みんな元気?」
「ええ。父上も章太郎も元気ですよ。ただ……」
母親の表情が曇っている。
「ただ、どうしたの?」
「阿蔵之介さんが……」
「あぐらくんがどうかしたの?」
あぐらくん、本名――阿蔵之介は、先のお盆に許婚(いいなずけ)を認められたばかりのラブラブの彼氏だ。その、あぐらくんに何かあったらしい。
「阿蔵之介くんたら、他の侍といさかいを起こして、町奉行所に置かれているのよ」
「あぐらくんが、町奉行所に!」
リツの手から風呂敷包みが落ちた。
町奉行所というと、今の警察のことである。大切な許婚が警察にしょっぴかれるなんて!
「父上も武士のはしくれでしょう、娘の許婚がこんなことになって、面目立たなくてお屋敷にも上がれないのよ」
「あぐらくんはやんちゃだけど、悪党じゃないわ。いったい何があったの?」
「姉ちゃん」
かたわらから、まだ前髪の取れない弟の章太郎が袖を引っぱった。
「あぐらのにいちゃん、どうやらヤバい相手と小競り合いになったようなんだ」
「ヤバい相手って?」
章太郎はリツの耳元でごにょごにょと告げた。
「ええっ? 将軍様?」
「しっ、姉ちゃん、声がでかい!」
あぐらくん――阿蔵之介は、お顔は一級品だが行儀が良いとは言えない。下級武士の息子で、たまに飲んで騒ぐことはあっても町奉行所にしょっぴかれたことはない。
しかし今回は、お忍びで夜の町に出ていた三代将軍家光公とその家臣の荒木緑エ門(あらきりょくえもん)に、江戸の花街(かがい)で派手に遊んで、お代まで踏み倒そうとしたところを目撃され、若輩者の夜遊び禁止令を発布された。
めちゃんこ頭に来たあぐらくん。
知り合いに花街での代金を借金しまくったことを棚に上げ、仕返しに、男色遊びが激しいと噂される家光公にあてつけがましく、
『男色遊びは許されて、若者の夜遊びは許されんのか』
という抗議文を、江戸の町のあちこちに張り紙したという。
「将軍様に仕返しの張り紙ですって! !」
リツは卒倒しそうになった。
(あぐらくんてば、なんて怖い者知らずでおバカなの! 張り紙している現場で首が飛んでも不思議でないじゃないの!)
リツは、草履がはじき飛ぶ勢いで町奉行所へ飛んで行った。
第二章 あぐらくん
武将がお側つきの若い家臣を男色の相手にするのは珍しいことではなかったが、将軍家光公までがその傾向にあることは、有名な噂だった。
お小姓に取り上げた人物ともそういう関係だとかで、他にも緑ェ門のような下級武士も恋人のひとりであるという噂だ。
家光を育てた有力な乳母、春日局にとっても頭痛のタネになっているとの噂が広がっていた。
町奉行所に駆けつけたリツは、門前で土下座した。
「お願いです、阿蔵之介さんに会わせてください!」
ようやく出てきた役人から、
「釈放してほしければ、保釈金十両を持ってこい」
言われたきり門前ばらいを食らった。
リツは途方に暮れる。
それにもうひとつ、リツは新年用の母親手縫いの着物を楽しみに帰ってきたのだが、幕府から着物の反物寸法をきっちり決めた「反物制」が発令されたので、窮屈な着物に出来上がっていた。
「お上からのお達しだから、その通りにしなければ仕方ないんだよ。リツ」
「こんな窮屈な寸法じゃ、足を伸び伸びさせられないわ」
むくれて不満を垂れるのだった。
「あんたのようなじゃじゃ馬には、今回の寸法の方が正座の習慣になって、とても良いと思うんだけどね」
母親が苦笑いして言った。
『正座を奨励』している幕府の意向は分かる。
武士の場合、命を守るための相手の服従の証拠なのだから。
リツの父親もまた下級武士ながら、江戸城に上がる殿から正座を言い渡されて頭を抱えていた。
「殿様の前でも何年か前まで気軽にあぐらで良かったのに、将軍さまの前では正座が奨励されては、わしらまで、そうせざるを得ないからな~~。困った、困った」
武士の正座は、相手がすぐに立ち上がって切りかかれないようにするためだ。正座をしていれば足がしびれて、すぐに立ち上がることができない。家光公が身の安全のために考えた制度である。
第三章 キヌちゃん
リツは、友達の呉服屋のキヌちゃんに相談に乗ってもらう。
キヌちゃん家のお店(たな)では、反物片付け係としてあぐらくんが『ばいと』していたのだ。
店先でお客の相手をしながら、反物をくるくる巻く美しい手つきはかなり板についていて、お客の若いおなごたちが「きゃあきゃあ」かまびすしい。
「キヌちゃん、どうしよう。あぐらくんがお役人に捕まっちゃった!」
「なんですって、町奉行所に?」
「あぐらくん、お仕事は真面目にやってくれてるのに」
キヌちゃんの母親も驚きを隠せない。
「最近、お店が終わってから、若い仲間と夜遊びしていたそうだからね」
とりあえず、あぐらくんのためにお店が保釈金の半分を用意して、リツやあぐらくんの親元が方々に借金して回り、釈放してもらうことができた。
それと、将軍家光の恋人である緑ェ門が、家光公に、
「これ以上、騒ぎを大きくしては、我々が糾弾(きゅうだん=問い詰める)されることになるやもしれませぬ」と、進言したおかげもあるとか。
リツは拝むようにお役人様にお礼を言い、あぐらくんの身柄を引き受けて帰る。
「心配かけたな、リツ」
あぐらくんは悪びれずにひと言だけ言った。
第四章 鉢合わせ
キヌちゃんも母親も、反物制には頭を悩ませていた。もし、違反して寸法の違う反物を売ると、処罰の対象になるという。
「処罰! 牢に入れられて体罰か何か受けるかもしれないのね? そんなことになったら、お店も続けられないわよね」
リツはボーゼンとなる。
「私は正座が苦手だから、反物の寸法が短くなると着物の幅まで狭くなって正座しづらくなるのが悩みのタネだわ」
キヌちゃんたちが困っているのは、着物の寸法が変わる混乱だけだ。正座して店に座ることは慣れている。
あぐらくんでさえも、
「何い? 正座? まかせとけ!」
と、軽口をたたくくらいには正座ができるが、正式な所作は知らない。
そこへキヌちゃんが、言い出した。
「茶道のお稽古へ行くっていうの、どうかしら? 知り合いのお師匠の蓮庵(れんあん)さんとこなら顔が利くわよ。ちょうど初釜の時期でしょう?」
茶道は室町時代に起こった文化だ。
狭い茶室に、数人も座らなければならないから、お師匠は皆、正座の達人に違いないと思いついたのだ。
リツとあぐらくんも正式な所作を習うためについて行く。
キヌちゃんの茶道のお師匠の蓮庵は、白いあごひげを生やした好々爺(こうこうや)で、とてもおおらかな人物だ。気軽にリツとあぐらくんの入門を引き受けてくれた。
入門の願いをしに行った日に、正座の稽古をつけてくれた。
「はい、ふたりとも、背すじを真っ直ぐにして立ちなさい。その場に膝をついて――。着物はお尻の下に敷き、かかとの上に静かに座る。そうそう。そして手は膝の上に置く。そうそう」
にこにこして、あごひげを撫でながら稽古風景を眺めていた。
茶道稽古の初日に行ってみると、茶室には、獅子頭(ししがしら)という椿の一種が一輪、床柱の器に挿してあり、床の間にも水墨画が飾ってある。きっと師匠が初釜用に選んだ絵なのだろう。
お抹茶色の頭巾を被ったままの年配の女性と、江戸紫色の頭巾の若い侍が先客として座っていた。
(どこの方だろう? 茶室で頭巾を取らないなんて)
リツとあぐらくんは目で合図するが、頭巾の女性と若い侍は、師匠の点てたお茶を黙々といただくだけで何も話さない。
目元から察するに、ふたりとも品のある顔立ちと思われる。
そのうち、あぐらくんがお点前をいただく番が来て、前ににじり寄り、
「お先に頂戴いたします」
挨拶した時に、ふと若い侍からの視線を感じた。
役人に捕まった時に、家光公は、あぐらくんの顔を見ているのだ。
「そなたは!」
(あ、家光公!)
双方、気づいてニガ虫を咬みつぶしたような顔になった。
(まずい)
(まじぃ)
頭巾の女性が、家光公の様子がおかしいのに気づいた。
(上様、いかがなされました? お顔の色が)
(いや、なんでもない。そろそろ失礼しよう)
そそくさとお茶室から退席して帰ってしまった。
残された師匠とリツとあぐらくんに、とんでもなく間(ま)の悪い風が吹き抜けた。
第五章 窮屈な着物
城に帰った家光は、荒木緑ェ門を呼んだ。
金ぴかの龍の掛け軸が飾られた部屋で、脇息にもたれながら、扇で口元を隠して話しかけた。
「まずいことになった。茶道の師匠のところへ先日の阿蔵とか申す浪人が来た。あの者が口を開いて師匠に我らのことを話すと、春日にも知れることになるぞ」
乳母の春日の局には、家光は頭が上がらない。
将軍の座を実弟に決められそうになった時、春日局が駿府城まで直接出向き、家康公の側室を通して「家光公を三代将軍に」と進言したのだから。
家光が最近、男色の道に走っていることを春日局は、当然、よく思っていない。阿蔵とかいう若い浪人が、ふたり一緒に街に繰り出したところを目撃していることまで局の耳に入ってきた。これは家光にとって将軍の威光に関わることである。
一方、リツは、お師匠さまから正座の所作と茶道の所作を丁寧に教わる。
母親が縫ってくれた新しい着物を着ていったのだが、正座してみると着丈も見幅も寸法が狭くなった分、キュウクツでキュウクツで、少しも足が崩せない。
(せ、せっかくのおニューの晴れ着が……、あ、足をくずせない…っ。今までの着物は裾がゆるゆるだったのにっ)
反物制が発布されるまでは、丈も幅がゆったり取った寸法だった。
(だから、出雲の阿国(いづものおくに=安土桃山時代の踊り手)さんとか、手足を伸び伸びして自由に踊れたんじゃないかしら?)
お稽古がひと通り終わるまでなんとか頑張った。
しかし、立ち上がる時が問題だ。足がしびれてコケそうになり、あぐらくんに助けてもらったのだった。
「おっと。大丈夫かい? 足がまっすぐになってないぞ」
「あ、ありがとう。足が崩せないから痺れてしまって……」
(この先、ずっとこの寸法の着物で通さなきゃならないの? お先、真っ暗だわ)
第六章 頭巾の女性
次回は、キヌちゃんとその母親とリツの三人でお稽古に出席した。
キヌちゃんは正座も茶道もお師匠から褒められていた。
先日の頭巾の女性はひとりだけで参加していた。こちらをちらりと見て会釈したので、キヌちゃんの母親も慌てて頭を下げた。
「先日もご一緒でしたね」
お言葉までちょうだいしたので、キヌちゃんの母親は飛び上がって恐縮した。
「は、はいっ、お局さま」
「呉服屋の女将さん、ここでは身分の差はありませんから、そう緊張なさらず」
お師匠の蓮庵がにこやかに言った。頭巾の女性も穏やかに、
「そうですよ。私とて元はというと、人様から後ろ指さされる立場でした。ここでは皆、平等ということで」
春日局、本名はお福という。
織田信長に謀反を起こした明智光秀の重臣、斉藤利三氏の娘である。謀反人の家臣ということで父親は処刑された。
斉藤氏は守護代の家柄で、お福は母方の親戚に当たる三条家で養育された。これによって、公家の素養である書道、歌道、香道等の教養を身につけることができた。
~~てなことを、お師匠がつらつらと述べるものだから、リツたちはよけい硬くなってしまった。
当の春日局は、いたって愛想よく、
「この度、反物制発令にあたり、女性は正座を余儀なくされることになりましたゆえ、私も稽古に参っている次第です」
謙虚なことを言われる。
第七章 説得
そろそろ厳しい寒さの中にも春の気配が感じられる頃となった。
江戸城では、春日局が、改まって家光公に話がございますと言ってふたりきりの時間を持った。
「上様。このお福、二十数年間、上様のためだけを思い、自分の子ども四人は嫁ぎ先に置いたまま、乳母として上様のおそばへ上がり、お仕えしてまいりました」
「何を今さら……。そなたの忠心はよくわかっておる」
「お身体の弱かった上様を、なんとかお丈夫にと色々なお食事を工夫したり、武芸で鍛えていただく算段をしたり」
「よく分かっておると言うに」
家光は聞き飽きた話をため息で応え、脇息にもたれている。
「実母様が弟君を将軍にというご意向を察して、お祖父さまの家康公に、上様を次期将軍にと強くお願いしました」
「それも、よく分かっておると申すに」
「いえ、分かっておられませぬ!」
春日局の声が広い座敷に響き渡った。
「分かっておられれば、男子を近づけることなど、なさらなかったはずでございます」
「うっ」
「大名のお子を小姓に取り立てることは致し方ないことではございますが、身分の低い者までおそばに置かれるとは……」
(緑ェ門のことだな)
家光公は思った。
(男に安らぎを見いだすのは、春日の強すぎる態度を感じているせいかもしれぬ)
「上様!」
春日がもう一度叫んだ。
「上様は、立派なお世継ぎをもうけなければならぬお立場でございます。どうかどうか、男子はお近づけになられませぬよう、このお福、心の底より真剣にお願い申し上げます」
涙を含んだ声になっている。深く頭を下げ、畳に額を押しつけた。
「……」
家光公は、困って黙りこんだ。
しばらくして、春日局は顔を上げた。目が輝いている。
「……そうですわ! 上様、心を落ち着かせるために、『正座』のお稽古をされてはいかがでしょう?」
「正座の稽古じゃと?」
「はい。ご家臣の方々に『正座』を奨励されておいででございましょう。上様がお手本をお示しになれば、ご家臣も進んで『正座』をされることになるでしょう」
「うううむ、なるほど」
「ご家臣への『正座』の勧めは、足がしびれて上様のご面前ですぐに立てなくするため。家臣の忠義を確かめるため。もしも謀反を目論む者があれば、由々しきことでございます。春日は、その方法には感服しております」
「ふむふむ」
家光公は、まんまと春日局の「飴とムチ作戦」にはまり、正座の稽古をすることにした。
このことにより――、
春日局の意向で、茶道の師匠、蓮庵の推挙により、なんとあぐらくんが、家光公の正座の師匠として選ばれた!
第八章 あぐら先生
茶道の師匠が、あぐらくんを推したのは、
「いやあ、長く呉服屋で『ばいと』していただけあって、阿蔵くんの正座は、お客様と反物に対する誠実さが沁みこんでおる」
という褒め方が決め手となったのだった。
「あぐらくんが、将軍様の正座の先生になるんですって?」
リツと両親たちの驚きのあまり口がきけないほどだ。
あぐらくん自身は、以前に将軍の悪口を書いた張り紙したりしたのも忘れて、
「こりゃ、いい小遣いになるぞ!」
大喜びである。
いい小遣いどころか、将軍様から少々ではあるが、禄(ろく=お給料)をいただくことになった。これで浪人は卒業である。
リツも慌てて、奉公先にお宿下がりを願い出た。
「こうなったら、奉公なんかしていられないわ。あぐらくんがちゃんと正座を教えられるか、見届けに行かなきゃ!」
着物が窮屈とか言っている場合ではない。あぐらくんに失敗が無いよう、監視しに行かなくては!
茶道師匠のお茶室で、あぐらくんは改めて家光公とふたりだけになった。外の庭には腕の立つ警護の家臣が数名ついている。
「正座のご指導役をうけたまわり、居座山(いざやま)阿蔵之介、恐悦至極(きょうえつしごく)にございます」
改めて挨拶すると、家光公は素っ気なく言う。
「前から夜遊びの街で顔見知りではないか。今さらよそ行きの顔をしても意味はないぞ」
「この阿蔵之介、心して、正座のご教授をさせていただきます。では、さっそく……」
茶室の空気がほんの少し緊張した。
「お背すじを真っ直ぐになさり、お立ちくださいませ」
「うむ」
「そして畳の上にお膝をついてくださいませ」
「うむ。ついたぞ」
「お召し物をお尻の下にお敷きになりながら――かかとの上に静かにお座りくださりませ」
「うむ」
座ってから、袴をパン! とはたいた。袴の五本の折りすじがきれいになった。
「両の手はお膝の上に置かれて、視線は自然に畳の上に……」
「ふむ」
第一回めのお稽古は無事に終わった。
「付け加えさせていただくと、身体の重心は下腹の方に意識なされてお座りくださり、頭の重心は後頭部に意識されてくださり……」
「ふむふむ。これで良かろう。――今さら、そちから改まった言葉で言われるのは、違和感があるのう。その口調、毎日、聞き飽きておる。もう少しくだけた感じにならぬか?」
「上様」
あぐらくんは、主君の前に素早く正座した。
「この阿蔵之介、春日局さまよりくれぐれもと、ご命を受けております。将軍様と先日まで浪人だった者が言葉を交わすことさえ恐れ多く思っております。くだけた感じなどとは、もっての外でございます!」
瞳を輝かせて言う。
「やれやれ。いつまで保つかな? まあ、そちの正座の教え方はほど良しである。とは評価してやろう」
茶室の壁越しに、植木の陰でふたりの会話を聞いていたリツは、ほう~~っと胸を撫で下ろした。
とたんに、
「何ヤツ?」
家光公の警護の者に気づかれたが、短くなった着物の裾をからげて、猫のようにすばしこく逃げた。
第九章 決心
何日目かの稽古が終わった後、家光は、
「しばし、ひとりにしてくれぬか」
と言った。あぐら之介は、静かに頭を下げて茶室を下がった。
ひとりになった家光の耳に、鹿威し(ししおどし)のカコーン! という音が鮮烈に響いた。
(だいたい、余が男を側に置くようになったのは、春日の過保護から逃げたい心境のせいもあるが、京の公家から迎えた御台(みだい=正室)の孝子と心が通わせられないせいもある……)
(お互いに政略結婚だということは、よく分かっているのだが形ばかりの夫婦でも、少しくらいは情が通わないものか……。孝子は顔を合わせてもにこりともせず、京からついてきた侍女に囲まれたままである)
(その点、緑ェ門は、大名の血筋でもないし、気軽に戯れることができる相手なのだが。純情で憎めないヤツでもあるからな)
(しかし、正座の稽古を重ねてきて、そろそろアヤツともおしまいにせねばなるまいと感じてきた。いつまでも、緑ェ門を縛りつけておくわけにもいかないからな。アヤツにはアヤツの人生がある)
たとえ将軍といえども、罪なき家臣の未来を邪魔する権利はない。
阿蔵之介の指導の下、正座を稽古しているうちに自我を抑える稽古もできたようだ。
(緑ェ門には正直に別れを告げよう)
膝の上でパチリと扇をたたむ。家光の心は決まった。
茶室の上を吹き渡る風が木々をざわつかせた。
第十章 寸法違反
それからひと月ほど経ったある日、キヌちゃんが、リツの家に駆けこんできた。
「リツちゃん、大変なの!」
「どうしたの、キヌちゃん!」
リツはキヌちゃんの声がただ事でないことに気づき、すぐに玄関に出てきた。
「町の中を、派手な遊び女数人が歩き回ってるの」
「そ、それがどうかしたの?」
「みんな、反物制が発布される前の長い丈、広い幅で縫った着物をわざとずるずる引きずるようにして歩いて、『素敵な着物でしょう、これは、山城屋さんで買った反物で仕立てたんだよ。やはり着物はゆったりしていないと優雅さが出ないですもんね~~』
って、おしゃべりしながら歩いているのよ!」
山城屋とは、キヌちゃんとこのお店の名前である。
「うちのおとっつぁんは反物制が発布されてから、ちゃんと寸法の制度を守っているわ。同時に華美な柄や贅沢な品も庶民には売らないことになってるから、あんな派手な反物は売らないわ。
遊び女の言ってることはでたらめよ!」
あぐら之介も駆けつけてきた。
「キヌさん、俺は旦那さんを信じるぜ」
「じゃあ、遊び女たちは何のためにそんなことを言って回っているのかしら。このままでは、キヌちゃんのおとっつぁんはお縄になってしまうわ!」
リツは泣きそうな顔だ。
「うむ。遊び女を捕まえよう!」
路地の砂ボコリを蹴立てて走っていく。リツもキヌちゃんもそれに続いた。
町の大通りをふらふら歩いていた遊び女三人を、ひとからげにして、あぐらくんは引っぱってきた。
「姐さんたち、その着物を仕立てた反物はどこで手に入れた?」
「だから言ってるだろ。山城屋さんだって。ねえ?」
ひとりの遊び女が、仲間にあいづちを求める。
「そうともさ。やっぱり山城屋さんは大したもんだねえ。ご公儀が頭の固いことを言って反物の幅を短くしちまったのに、長くて映える品を売ってくださるとはねえ」
キヌは目に涙を浮かべて、
「嘘だわっ! うちの反物はみんな、お上の制度を守った寸法よ。おとっつぁんは違反したりしないわ」
その時、路地に少女が走りこんできた。山城屋の女中である。
「おカヨ、どうしたの」
「お嬢様、大変です! 旦那さまと番頭さんが町奉行所に連れて行かれましたっ」
「なんですって?」
キヌちゃんは血相変えて、お店へ女中と駆けて行った。
第十一章 緑ェ門
あぐらくんは、捕まえた遊び女たちをうっちゃっておいて、反対の方向へ走り出す。
「どうしたの、あぐらくん!」
リツも後に続いた。
あぐらくんは朱色の格子に囲まれた花街に駆けこんだ。一軒の茶屋の暖簾を跳ね上げる。
「やい、緑ェ門はいるか!」
「お客様、今はまだお天道様が高い時間です。営業しておりませんよ」
番頭が引き止める。
「いや、あいつはどこかに隠れているはず」
あぐらくんは構わず、二階への階段を勢いよく昇った。
ひとつの部屋の襖を開けると、緑ェ門が、遊び女としどけなく戯れながら酒を飲んでいた。
「おや、あんちゃんはあぐらの……」
真っ赤になった顔で緑ェ門は振り向いた。
「緑ェ門。お前、山城屋をハメようと企んだな!」
胸ぐらをつかんで引き上げた。
「な、なんのことだ、苦しいじゃないか」
「最近、上様はお前を遠ざけている。その腹いせに、山城屋に反物寸法違反の罪を着せたな!」
「な、何のことだか? 山城屋っていうのに、罪を着せて俺が何を特するってんだよ?」
「何でもいいから、ガムシャラに家光公の世を乱そうと企んだんだろう。器の小さいお前の考えそうなことだ」
緑ェ門は、あぐらくんの力強い腕から薄っぺらい布団の上に叩きつけられた。
「ふん、そうだよ。すべて俺が遊び女にやらせたことだよ!」
「白状したな!」
「悔しかったんだよ。上様は俺に別れを告げて、春日局の言いなりだ。それに……」
「それに?」
「お前と茶室に籠もっていた。お前は顔立ちがきれいで上様好みだものな」
「は?」
あぐらくんは口をポカンと開けた。
「お前、まさか、俺にジェラシーしたのか」
「……」
「バッカ言うな! 俺はお前と違って、男に断じて、ぜ~~んぜんん興味はない! ちゃんとリツっていう可愛い許婚がいるんだ」
襖の外で一部始終を聞いていたリツは、胸がドキドキするのを感じた。
「お稲荷さま、八幡さま、天満宮さま、あらゆる神様に誓って言う。俺は男に興味などない! 家光公とは、真剣に『正座の稽古』していたんだ」
「……」
緑ェ門は全身の力が抜けたようだった。
第十二章 改心
キヌちゃんとこのお店は、町奉行所にて、営業停止処分を下された。お店から寸法違反の反物も押収された。
しかし、直後に荒木緑ェ門という若い武士が、奉行所に出向き、『自分が仕組んだことで、遊び女を使ってお店に反物を置かせたこと、それで仕立てた着物を着させて、わざと町を歩かせたこと』を自白した。
緑ェ門には半年の牢屋入りの命令が下された。
半年で済んだのは、春日局が口を聞いたのかもしれない。が、それは不明なままだ。
山城屋の旦那と番頭は釈放され、平和が戻った。
リツはキヌちゃんと手を取りあって喜んだ。
「良かったね。おとっつぁんもお店も無事で」
「あぐらくんのおかげよ。リツちゃん、いい人を旦那様に決めてもらったわねえ」
「この前まで花街で遊んでいたのにね」
「いざとなったら頼りになる人じゃないの。だから、将軍さまの正座の先生にも推挙されたんだわ」
「キヌちゃんたら」
リツは照れて、真っ赤になった。
半年後――。
リツとあぐらくんの祝言の日取りが決まった。両家の両親は喜びに浮足立っている。
「うちのリツが、浪人どころか、将軍さまの正座師匠を努めるお方と夫婦になるとはねえ」
リツの母親は嬉し涙の毎日だ。
「でも、寂しくなるねえ」
「嫁入りの衣装は全部、おっかさんに縫ってもらいますから、寂しいなんて言ってるヒマはなくてよ」
横から章太郎も、
「そうだよ、母上。それに俺がいるじゃないか」
「ありがとう、リツ。章太郎」
母親はたもとで涙を拭いた。
ある日、祝言のことをリツの家に打合せに来ていた、あぐらくんが帰る時間になった。
見送るために長屋の路地をリツが出てくると、人影が去ろうとした。
「あっ、待って!」
人影はくたびれた着流し姿の緑ェ門である。小さな風呂敷包みだけを持っている。
「お、緑ェ門。釈放になったんだな」
あぐらくんもやってきた。
緑ェ門はマゲが歪んで情けない様子だが、何か言いたそうだ。
「家光公のお計らいで半年で自由の身になれて良かったな」
緑ェ門はいきなり、その場に土下座した。
「お願いだ! 正座を教えてくれ! 俺は……正座が出来ないのだ」
「えっ、お前に?」
緑ェ門はこっくりした。
「正座が出来ないから、あんたに嫉妬しちまったんだよ。それに迷惑かけちまった呉服屋さんに、ちゃんと正座して謝りたいんだ」
「おやおや、すごく改心したと見える」
リツとあぐらくんは顔を見合わせた。
「あぐらくん、教えてあげて。キヌちゃんとおとっつぁんも納得してくれると思うわ」
リツが真っ直ぐな視線を向けた。
「リツ、優しいな」
「あぐらくんだって優しいわ。もう心の中では、緑ェ門さんに正座を教えるって決めたんでしょう?」
「えへん、えへん!」
章太郎がわざとらしく咳ばらいした。
「いい加減にしてくれよ。人前でいちゃいちゃと。見ちゃいらんねえよ!」
「この子ったら」
リツは真っ赤になり、あぐらくんは頭を掻いた。
あぐらくんの特訓を受けた緑ェ門は、茶道師匠の蓮庵も納得する正座ができるようになった。
顔つきもいきいきとして、
「あぐら之介さん。お世話になりました。俺、国元へ帰ってやりなおします」
きちんと挨拶して、わらじのヒモを結び直し、江戸を後にした。
リツとあぐらくんの祝言は、秋も深まりつつある紅葉の美しい日に無事に挙げられた。
白無垢に身を包んだリツと紋付袴羽織のあぐらくんは、山城屋さんのお座敷を貸していただき、神妙に正座をして三々九度を交わした。
足がしびれたリツは、祝言の間はなんとかガマンしたが、披露宴の途中で限界が来た。キヌちゃんに肩を貸してもらいながら、控えの間で足を伸ばした。
「ひぇ~~。この反物の幅はやっぱ、きついわあ」
一方、家光公は男色を卒業し、春日局が探してきた何人かの側室を迎える。
城下では、反物の寸法幅が庶民に馴染みはじめ、正座が広まり始めるのだった。


![[208]正座フェロモン・夢好(ムスク)](https://www.seiza.net/main/wp-content/themes/hueman/assets/front/img/thumb-medium-empty.png)





