[91]猫の香箱座りをいたしましょ
 タイトル:猫の香箱座りをいたしましょ
タイトル:猫の香箱座りをいたしましょ
分類:電子書籍
発売日:2020/05/01
販売形式:ダウンロード販売
ファイル形式:pdf
ページ数:48
定価:200円+税
著者:海道 遠
イラスト:keiko.
内容
雅(みやび)と風美(ふうび)の兄弟は、母方の祖父を香道の家元に持つ高校生だ。しかし、父親の軍治が風来坊で行方をくらましていて、雅は父方の実家、蕎麦処の「まなか」に、母親の香織と風美は母方の香道家元に身を寄せていた。
香道とは。心身共に清らかにし、暮らしの中でも愉しむことが出来る。それも根底には正しい正座が出来てこその基本がある。
ある日、軍治が蕎麦処の実家に帰ってきた。早速、雅に風呂敷包みを家元のところにいる母の香織に持っていくように命じる。一族は大の猫好きで両家には猫がいたが、雅だけは猫嫌いなのだ。さて風呂敷包みの中は何だろう? と思いながら、祖父の家にやってきた雅だが……。
販売サイト
https://seiza.booth.pm/items/2025835

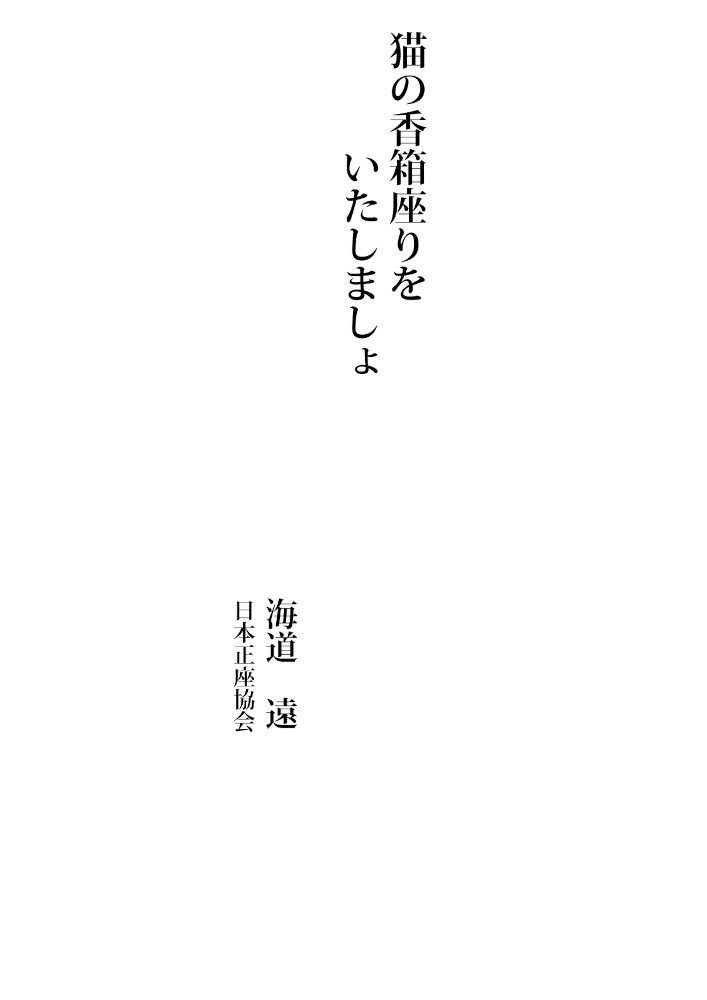
本文
当作品を発行所から承諾を得ずに、無断で複写、複製することは禁止しています。
第 一 章 蕎麦屋の息子
「へ~~い、らっしゃい」
ガラッと戸が開く音がして、蕎麦処「まなか」の女将が威勢の良い返事で迎える。
「ただいま~~」
「なんだ雅、お前かい。お客さんだと思ったじゃないか」
白髪まじりのひっつめ髪で暖簾を分けて覗いた女将が言った。厨房からは、出汁のいい匂いが漂っている。だが最近、鼻水が止まらず鼻づまりの雅には分からない。
雅はサッカーのユニフォームのまま二階へ上がろうとする。大きなガタイで砂だらけだ。雅という名にはほど遠いアウトドア派である。
「こら、雅、足くらい裏で洗ってから上がりなさい。どうしてそんな恰好のままなんだい」
「……分かったよぉ」
階段を昇りかけていた雅は戻ってきた。その階段の上がり口から、ひょいと覗いた顔がある。大きな体格の男、顔面、無精ひげだらけだ。
雅は固まった。
「と、父ちゃん?」
それは、三年ぶりに会う父親の軍治だった。作業服姿で油まみれだ。
「どーしたんだよっ! 今までどこをうろついてたんだよっ」
「そこいら辺をちょいとな」
本人は全然、悪びれないで雅を眺めてニコニコしている。
「そんなんだから母ちゃんに逃げられるんだよ」
「えっ、逃げられちゃいねえぞ。母ちゃんはずっと父ちゃんにぞっこんだ」
「よく言うよ。母ちゃん、父ちゃんが行方不明になってから、しばらくここで一生懸命働いて待ってたけど、一年前、風美を連れて、あっちへ帰っちまったよ」
風美とは、雅と一歳違いの弟だ。雅とは対照的な細身のインドア派である。
「香道家元の祖父さんとこへだろ。母ちゃんからの連絡で知ってるよ。お前はなんで置いていかれた?」
「苦手なもんが、いっぱいだからさ」
「ああ、猫か。そんな図体して猫が怖いなんて、お前意気地なしだな」
「母ちゃんと息子ふたりを置き去りにしてへらへら帰ってくる方が、よほど変わってるよ」
ふたりは気まずく黙った。
「まあまあ、三年ぶりに会ったんだ。親子ゲンカはおよし」
女将が仲へ入った。
シャワーを浴びてきた雅が、奥の茶の間で豪快に麦茶をがぶ飲みしてひと息つくと、父の軍治が、
「お前に頼みがあるんだがな。これを、母さんとこへ届けてくれないか。三時間以内だ」
「何だよ、この風呂敷包み。いやにずっしりしてるな」
唐草模様の風呂敷で包まれた箱らしきものを持ちあげて、包みを開けようとした。
「おっと待った。開けちゃいかん。どんなことがあってもだ。母ちゃんにちゃんと渡すんだぞ」
「玉手箱かよ」
そこへ、ポニーテールのセーラー服姿の女の子が飛び込んできた。
「きゃっ、おじさん! おじさんよね。雅の父さんよね?」
「そだけど?」
「私よ、リカ! 雅くんたちと幼なじみの、リカ」
「おお、リカちゃんか! すっかり女らしくなって! おじさん、ひと目惚れしちまわあ」
「いや~~ね。あ、雅」
リカはポニーテールを跳ねさせて、
「ごめんね、今日は洗濯できなくて。母さんがインフルエンザで寝込んじゃったんで、私が家のことしなくちゃいけないから持ち帰りってことで我慢してね」
「そりゃいいけど、お袋さん、放っといて大丈夫か」
「うん。落ち着いてる」
風呂敷包みを持って出かけようとする雅に、リカは気がついた。
「どこか行くの?」
「ああ、使いで祖父ちゃんとこへ」
「お祖父ちゃんて香道の家元の先生とこね。どうして?」
「母ちゃんに渡してくれって、父ちゃんが」
裏口から飛び出して、往来を走っていく雅の後ろ姿が小さくなっていく。
「香道の家元のお祖父ちゃん……」
リカは繰り返した。香道の奥伝て、何十年も修行しなきゃ取れない位らしい。ましてや歴代の家元……。そんなお祖父さんを持ちながら、サッカー三昧の孫息子の雅のことを改めて思った。
「雅はいずれ、香道家元を継ぐのかなあ」
第 二 章 香道奥伝の腕
香道は日本古来の香を楽しむ世界で、所作の中にも精神的な落ち着きを求める道である。「良い香りを楽しむ」が基本だ。香木そのものを小さく刻んだものを燃やして香りを楽しみ、心の余裕を得ることことを目的とする。
師範格の「皆伝」は十五年。「奥伝」ともなると二十五年から三十年以上の修練期間を必要とされる。
香宗派に生まれた雅と風美の祖父は、四十五歳の時に香宗派を継いだ。
少し雨が降った。
苔の艶やかな庭を背にどっしりと正座して、※香を聞いていた家元の香宗蒼栄は、庭の羊歯の群れへ目をやった。
※香は、「嗅ぐ」と言わず「聞く」と表現する。
【香道の在り方】
香りは心身共に清らかにし、暮らしの中でも愉しむことが出来る。
それも根底には正しい正座が出来てこその基本がある。さすがに香炉を持った時の家元の正座は真っ直ぐな背筋、かかとの上に静かに座る様子、行儀作法は一流のものだ。
加えて、香宗派には家元だけしか知らない秘密があるらしい。秘密とは何なのか、雅の弟、風美が祖父に尋ねたところ、猫に関係があるとかないとか、はぐらかすように笑って答えたらしい。
家元の総髪の肩までの髪は白いものが目立つ。引き結ばれた口元、白い顎ヒゲ、厳しい角度の眉、香炉を睨む眼光、頑固そのものである。香炉を持ち上げ、顔面近くまで持っていき右手で香炉を覆って香りを聞く。真剣すぎる表情に庭の植木まで沈黙している。
そんな家元が、庭からひょいと上がり込んだ黄金色の長い毛足の猫を見て相好を崩した。
「おお、おお、さっきから鳴いていたのは、麒麟丸じゃったか。どこへ行っておった? 雨に濡れたか。こんなに背中が湿っておるな」
黄金猫を抱き上げた家元は、孫を慈しむひとりの老人だ。
「お~~い、香織。麒麟丸が雨に濡れた。タオルを持ってきてやってくれんか」
「お父さん。麒麟丸ったら一晩中帰らなかったんですよ。お風呂に入れなければ」
大島紬を纏った香織が、タオルを持ってきて顔を曇らせた。
「そんなに怖い顔をしなくても良かろうになあ、麒麟丸。お風呂に入れておもらい」
家元の目尻は猫を抱いたまま下がりっぱなしだ。麒麟丸をタオルで受け取りながら、香織が、
「お父さんてば、猫たちは目に入れても痛くないのね。その分、少しはお弟子さんたちに優しくご指導されれば?」
「うむむ? わしは弟子たちにも十分優しく指導しとるつもりじゃがな」
「古弟子さんたちでも、家元のご機嫌がよくない時は、いつ香炉が飛んでくるか、ビクビクしてるっておっしゃってましたよ」
「人聞きの良くない……。わしは香炉や道具を人様に投げつけたことなど、一回もないぞ」
「え、あるじゃないですか」
香織の言葉に家元はしばし考えてから、
「ゴホン、あの男がお前をください、なんぞと己をわきまえずお願いをしに来た時かな」
「そうですとも!」
香織は胸のむしゃくしゃを晴らすように、麒麟丸をタオルの中でひっくり返しながらプーッと、むくれた。
「お父さん、あの時はあの人の言葉をまったく聞こうともせず、香炉を投げつけて、座敷に香木がばらばらに散らばってしまってどうしようもなかったわ」
「でも、あの男には当たらなかったぞ」
麒麟丸は香織の腕から逃れて、床の間で香箱を組んだ。普段、香道の道具をしまう香箱そっくりに手足を引っ込める座り方を「香箱を組む」という。
「麒麟丸や、わしがお風呂へ入れてやろう」
家元が立ち上がった。
「お父さん、また逃げるんですね! この話になったら必ず」
赤い花柄エプロンの裾で、香織は目頭をぬぐった。
「お風呂どころじゃないですよ、お父さん。もうじきお弟子さんたちがお稽古に見えられる頃ですよ」
実際、弟子たちが笑顔でおしゃべりしながら、玄関に到着し始めた。
第 三 章 風呂敷包み
その時、裏口で声がした。
「お~い、母さん。誰かいないの?」
男の子の声だ。香織には息子の雅だと分かっていた。
「いないのなら勝手に上がるよ。猫ども、近寄るでない。雅さまのお通りだ」
でかい図体で、塵ひとつない座敷に上がり込んできた。
「お袋、どうしたの、泣いてるのか」
香織の眼が赤いことに気づいた雅は声をかけた。
「いえ、なんでもないのよ。それよりその風呂敷包みは?」
香織は心を鎮めて、風呂敷包みを解いてみた。唐草模様の風呂敷から出てきたのは香箱だった。螺鈿で花や鳥などの意匠を施した、素晴らしい品だ。
「何か、ゴソゴソするんだよ。何が入ってるんだろう。父ちゃんがお祖父ちゃんに持っていけって」
「ゴソゴソする? 香木とお道具だけだと思うけど」
香織が蓋を開けてみると、箱いっぱい詰め詰めの茶色と白の毛のかたまり―――蕎麦処の猫、茶トラが飛び出してきた。
「うわっ! 俺、今までこんなの抱えて走ってきたのか?」
猫にはめっぽう弱い雅が半泣きの声で飛びすさった。
「あなたも相変わらずねえ。こんなに可愛いのに。ねえ、茶トラ」
香織が猫を膝の上に乗せて、首輪に何かを発見した。
「あら? おみくじみたいに紙が巻きつけてある」
そのねじり文のようなものを首輪から外して開けてみた。
「そば屋に帰っている」とだけある。曲がりくねった下手な文字だ。
「この子供みたいな字……あの人ね!」
香織の美しい眉が吊り上がった。
「三年もどこに行ってたんだか」
「さあ、父さんの放浪癖は今に始まったことじゃないだろ。母さんだって放浪先で拾われてきたんだから」
「拾われてきただなんて猫みたいに」
香織は雅の膝の上に茶トラをぽんと置いた。
「うわ~~~~!」
雅が、茶トラを放り出して立ち上がった。茶トラは一転宙返りして見事、着地する。
「気持ちわりい、くねくねの身体……」
「どうしてそんなに嫌がるの。お祖父ちゃんも『まなか』のお祖母ちゃんも風美だってお母さんだって、皆、大の猫好きだってのに」
「どうしてったって、好きや嫌いに理由はないって! あ、わかったぞ。これは母ちゃんの陰謀だろう」
「陰謀って」
隣の部屋で香のお稽古の準備を始めていたお弟子さんたちは、一斉に振り返った。
「母ちゃんは俺を猫に慣れさせるのを口実にお祖父ちゃんとこへ呼び寄せて、香道の跡継ぎにしようと思ってるんだろう」
「あら、バレちゃった? お父さんは猫のこと以外、跡継ぎのことは何も知らないけどね」
香織が舌をペロリと出した。
「あいにくだな。俺は二年前から花粉症になっちまってハナが利かないんだよ」
「……!」
それを聞いた香織と隣の部屋の弟子一同が凍りついた。
香道の家元跡継ぎ息子のハナが利かない! なんてことだろう! そうでなくても香道の奥伝免状をいただくのだけでも何年、何十年もかかるというのに。
「雅が花粉症……」
香織が呆然と洩らす。
「風美が香りオンチだと分かったのに、雅までが花粉症だなんて」
「風美が香りオンチだって?」
今度は雅が驚く番だった。
香織の話はこうだった。
ある日、香織が風美に香道の基本的なお香、「伽羅」を聞かせて(嗅がせて)みた。すると、マラッカ産の「真那加」と間違えてしまったのだ。
区別がつかずにケロリとしている息子に念を押してテストしてみると、六種ある香の全てが聞き分けできない。
「これはダメだ……」
祖父も香織もがっかりしてしまった。
ゆくゆくは家元を継がせようと思っていた風美は、カンペキな香りオンチだったのだ。
もっと庶民的な例を出そう。
風美が高校から帰ってきて、
「今日は母さんの得意なビーフシチューだね。嬉しいな」
それを聞いた香織は思わず皿を落としてしまった。その日はブリ大根だったのだ。
「風美、この香りが何だか分かる?」
目を閉じさせてフリージアの花を鼻先に持って行った。すると風美は、
「チューインガム。いや、香水かな?」
香織はのけぞってしまった。
第 四 章 香りの効能
「こんにちは~~~」
リカは家元の屋敷のだだ広い玄関で叫んだ。が、全然誰も出てくる気配がない。奥では人がざわめく気配と声がしている。待ちきれずに、リカはそっと玄関から奥へ上がっていった。
「風美の香りオンチのせいで、俺を跡継ぎにしようなんて計画したんだな!」
雅が欄間で頭を打ちそうになりながら、仁王立ちになっている。
「そうよ、だって、風美のハナが駄目ならあなたってことになるじゃない」
「蕎麦屋に置いてけぼりにして、母ちゃんも父ちゃんも俺の人生をなんだと思ってるんだ?」
雅の表情はかなり険しかった。
お弟子さんたちが、母と息子の言い合いがどうなることかと、ビクビクしながら覗きに来ている。香織はさすがにまずいと思い、雅を奥の小部屋に呼んだ。
「雅……そこに座りなさい」
小さな床の間の前に正座した母親は厳しく言った。
「母ちゃん! 俺は絶対、やだからな」
「いいから座りなさい」
しぶしぶ座った雅の膝へ、二匹の猫……さっきの茶トラと三毛が乗りに来た。
「うわ~~~、俺はお前たちが苦手なんだよぉ」
香織はくすりと笑った。
「飾り障子のところに香箱組んでいるクロベエをごらんなさい」
葉っぱの影が揺れてる飾り障子の際に、前足も後ろ足も身体の下に引っ込めて四角くなっている黒猫がいる。
「お行儀いいでしょう。クロベエ。あれが猫の正座よ。ああいう風に座ってこそ人間も物事を落ち着いて考えられるのよ。お香もそう。香道の基本は、正座の姿勢からです」
「……」
「だから、ちゃんと正座しなさい」
「わ、分かったよ。でも、この猫たちを俺の膝からどかせてほしいんだけど! 部屋にあふれてる猫どもも、どこかへやってほしいんだけど!」
「仕方ないわねえ」
香織が立ち上がったところへ、小部屋の入り口に立つリカを見つけた。
「あら、あなた、雅のサッカー部の」
「はい、前崎リカです。勝手にお邪魔してます」
「どうぞ、ごゆっくり」
香織は、部屋のあちこちに寝そべっている猫を全部、他の部屋へ移動させ、雅とリカに桜餅とお茶を持ってきた。
「ちょうどいいわ。ふたりに香道の話を聞いてほしいの」
ふたりは唾を飲み込んだ。
「猫の香箱座りみたいに、人間もちゃんと正座すると、香木を薫らせて静かに目を閉じているのと同じ、瞑想に入れるわ。世の中のたくさんある嫌なこと、劣等感や他人との争いや傷つけ合い、すべて愚かな考えは『感謝』に変えることができるわ」
「だから何だよ、母ちゃん」
「雅に、そんな素晴らしい香道の道を継いでもらえればいいなって」
「風美の代わりだろ」
「元々物静かなあの子の方が香道は向いていると思ったわ。でも、ハナが利かないのを機会に考えてみたの。雅、お前は少し粗暴な子どもだった。今もサッカーに夢中になって勉強の方はどうなってるか知らないけれど。でも、あなたの方がもしかして、香道に向いてるんじゃないかと思ったの」
リカが桜餅を頬張りながら、うんうんと頷いた。
「なんだよ、リカ、お前まで」
第 五 章 家元と風来坊の対決
その時、家元が部屋へ入ってきたので、リカは喉に桜餅を詰めそうになり、大急ぎでお茶で流し込んだ。
「こんにちは。サッカー部の前埼リカといいます」
家元は、リカににっこり笑って応えてから、
「母さんの言う通りじゃ、雅。わしもお前に家元を継いでほしいと思っている」
「俺の将来を勝手に決めないでくれよ、お祖父ちゃん!」
雅は立ち上がりかけた。
「花粉症だって言ってるだろう。ほら、今だって鼻水と涙が出てきた」
「花粉症がなんだ、この香宗家元の血筋が花粉症なんぞに負けるわけがない」
その時、外側からドシーンと襖が倒された。
立っていたのは父親の軍治だ。部屋の中の四人は驚いて立ち上がる。
「やい、祖父さん、雅を家元にするってえのか!」
軍治の眼が血走っている。香織とリカは思わず抱き合った。
軍治と家元が対峙した。
「俺の息子は蕎麦処の跡取りだ! 勝手に香道なんかに取られてたまるか!」
「なんじゃとお、この風来坊が!」
ふたりとも、頭から湯気が立ちそうなほど怒り狂っている。
「お嬢さんを嫁にください」と言いに来て、家元が香箱を投げつけた時からの犬猿の仲のふたりだ。
視線がぶつかりあい、火花が散った。
「あのう、私、急用を思い出しましたので」
「私も頭痛が……」
お弟子の女性たちは、居心地の悪さに背を丸めて慌てて帰り始める。
家元が重い声で軍治に、
「あんたは、娘と孫たちを置いてどこかへ行ってしまった。そんな者に孫の将来に口出しする資格はない」
「むむむ……。確かに香織と息子たちを置いていった。しかし、蕎麦屋『まなか』をやってるお袋に預かってもらっていると思えば、俺は安心して留守にしていられたんだ」
「留守ばかりして、夫や父親の務めを果たさず、何をしていたんじゃ!」
家元の白い眉毛の下の瞳が本気で怒っている。
「それは言えん」
軍治は珍しく眼を伏せた。
「言えんだとお、この風来坊が。出まかせばかり言いおって。この道楽者!」
家元が、香炉を投げつけようとしたが、香織が泣きながら引き留めた。
「お父さん、また香木をバラバラにする気なの、やめて! 香木は私たちの命よ、そうでしょう」
「むむむ」
「香炉を投げようが、母ちゃんを泣かそうが、俺は香道の家元なんか継がないぞ! サッカー選手になるんだからな!」
雅も怒号を放つ。
「雅まで。落ち着きなさい!」
家元、軍治、香織、雅が激高し、リカは部屋の隅でクロベエを抱いて震えていた。
そんな修羅場へ、細身の少年が小部屋へやってきた。
「皆、落ち着いて正座して下さい!」
第 六 章 風美
「さあ、縁側で香箱を組んでいる麒麟丸を見習って」
細いながら、風美の声はよく通って強い。
争っていた五人は、決まり悪げにひとりずつその場へ膝をつき、正座を始めた。
「雅兄ちゃん、背中を真っ直ぐ! 母さんもいつまでも泣いていないで」
グレーのジャケット制服のままの白皙の少年、風美は、てきぱきと大人たちを正座させた。リカも、猫を下ろして正座しようとする。
「背筋を真っ直ぐにして膝を折り、かかとの上に座る。あ、リカちゃんはスカートを膝の内側に折り入れて。そう、それでいい。両手は膝の上に静かに置く」
少々、時間が流れた。
小部屋に聞こえてくるのは、遠い往来から聞こえてくる車の音、庭水の流れるちょろちょろした音、砂地にある水琴窟に、林の風が渡る涼やかな響き。
そこらここらで戯れている猫たちの泣き声など。
なんという静けさ―――。
皆の心がようやく静かになったのを確認して、風美は自分も正座した。なんとも美しい正座だ。足はぴしりと曲げ、背筋は杉のように立ち、手のひらは柔らかく膝の上に置かれている。
麒麟丸が香箱座りから顔をあげて、みゃあと鳴く。
(人間たち、騒々しいなあ、何を言ってるんだろう)
という感じだ。
「皆さん、落ち着かれたようですね」
風美が澄んだ泉のような眼で見渡した。
「お祖父さん。僕を家元にという話は僕にとってはまったく寝耳に水でした」
「でした?」
家元が怪訝な顔を向けると、風美は答えた。
「はい。父さんからどうやらそうらしいと聞くまでは」
皆、一斉に軍治の方を見た。
軍治は窮屈そうに膝を曲げて正座しながら話した。
「そうとも。二年ほど前、香織から、家元がそう考えていると連絡を受けて、俺は風美に連絡を取ったんだ。そしたら、風美は香りオンチだっていうじゃないか」
「そんな息子を無理やり家元にするなんて無茶な話があるかと俺は思った。でも、話を聞いてみると、風美は家元を継ぎたいっていうじゃないか」
「ええっ」
一同、風美の顔を見た。
「はい。お祖父さんの香道の世界、僕はとても興味があって」
にっこり笑った。
「それで、風美がその気なら、絶対、香りオンチを治してやらなきゃ駄目だと思い、この二年間、日本中あちこちの病院をめぐっていたのさ。なあ、風美」
「はい」
風美が切れ長の瞳を煌めかせて頷く。
「それで、日曜日ごとに旅に出るって留守してたのね。風美」
「そうなんだ。黙っていて悪かったよ。母さん。でも正直に言って、もしうまくいかなかったら、母さんはもっとがっかりするだろうと思って黙っていたんだ」
「じゃ、今、打ち明けてくれたってことは?」
「う~~ん」
風美は照れ臭そうに頭をかいた。
「この騒ぎのせいで打ち明けるのが、ちょっと早まったけどね、耳鼻科の名医から、少し時間はかかるけど地道に治療すれば完治するって言われた」
「まあ!」
香織の顔が母親らしく輝いた。
「風美の鼻が治る。じゃあ、これで香宗流家元も継げるわけね」
「母さん、治療して完治したらの話だよ」
「いいえ、あなたが決心したことだもの。きっと治って香道の道を行ってくれるわ」
「母さんがそれまで、お祖父ちゃんの補佐をしながら、待っていてくれなきゃ」
「わかったわ」
嬉し涙にむせながら、香織は頷いた。そして軍治の方へ向き、頭を下げた。
「軍治さん。私の知らない間に、風美のために病院めぐりをしてくれていたのですね。なんとお礼を言っていいか」
「お礼なんてよせやい、夫婦で親子じゃねえか」
軍治は真っ赤になってもぞもぞしてから、
「お義父さん」
珍しい呼びかけで家元に向いた。
「さっきは香炉を投げさせるほどの失礼な口をきいて悪かったと思っています」
「ああ、わしもつい、カッとなって……」
「風美の跡継ぎのことも決まったも同然です。雅は、どうか好きなサッカーをさせてやっていただけませんでしょうか?」
軍治の神妙な言葉に老人は頷いた。
「分かった。サッカーでも何でも好きなことをすればいい。香道のことは、香織と風美に任せてな」
「お父さん、ありがとう」
「お祖父ちゃん、僕が出来ない代わりに風美のことを頼む。それと父ちゃん、風美の鼻のこと、ありがとうな。病院を探してくれて」
香織と雅は頭を下げた。正座して頭を下げたお礼とお願いを込めた挨拶は、普段、サッカーグラウンドで埃まみれでトレーニングしている少年とは思えないほど礼儀正しかった。
「お父さん、病院治療と並行して、この家の秘伝の方法があること、お話したら?」
香織が言った言葉に一同は家元を注目した。
「秘伝? ああ、猫に効く秘伝の香のことか」
「なんですか、それは。初めて聞きましたよ」
風美も雅も軍治も膝を乗り出した。
「そんなに聞きたいか? 麒麟丸や、こちらへおいで」
黄金の毛並み、青い瞳の麒麟丸が飼い主の膝へやってきた。
「この麒麟丸は、マタタビが効かないほど鼻が良くなかったんじゃが、わしの秘伝の香を嗅がせているうちに、治ったのじゃ。じゃから、もしかすると風美にも効果があるかもしれん」
「………」
一同、信じられなくて口を開いたままだった。
クロベエが、庭からぴょんと縁側へ飛び乗ってやってきた。
「わあ、こっち来るな、猫!」
整った正座はどこへやら、クロベエを見るなり飛び上がった雅の慌てように、皆から笑い声がこぼれた。
家元が改まって、
「どうでしょう皆様、いつまた頭に血が昇るか分からない愚かな私のために、蕎麦処『まなか』のお祖母様も呼んで香の会を開きませんか。風美の門出と思うて」
「賛成」
雅がぶっきらぼうに言い、リカが張り切って言った。
「『まなか』のお祖母ちゃんに電話するわね」
終 章
「お香が初心者の方もおられます。今回は香を競うのではなく、味わって聞いて(嗅いで)いただくだけで結構です」
猫まみれになりながら、家元は集まった一同に告げた。袂に飛びつく猫、膝に座る猫、周りに香箱座りをしてくつろぐ猫、さまざまである。
「これこれ、お前たち、静かになさい。ちょっと皆さん、うちの麒麟丸に秘伝の香を聞かせます。マタタビを感じるようになる香と、正反対に鎮静する香と二種類作ってみたのです」
家元が、香箱の中から香木を取り出して香炉に何種類か入れる。そして、他の猫たちと一緒に飛び回っている麒麟丸を抱き上げ、香を近づけた。
麒麟丸はみるみる間にうっとりして家元の膝の中で静かになった。マタタビを感じて転びまわるのとはまったく違う。
「へ~~え、臭い、いや香りの効果ってのはすごいんだな」
軍治が大きく感嘆した。
家元が麒麟丸をそっと絨毯の上に下ろし、皆に向き直った。
螺鈿の上品な香炉を一番に渡された『まなか』の女将は、恭しく受け取り、そうっと手のひらで囲って香を聞いてみた。
「頭の奥がすうっと晴れていくような香りですね」
女将は、微笑んだ。
「この香りが、麒麟丸の鼻を治したのです。風美にも効果があるかもしれませんからのう」
「今、毎日試しているところだよ、お祖父ちゃん。なあ。麒麟丸。お前には負けられないからな」
風美は祖父の膝から麒麟丸を抱きとって鼻面を突き合わせた。
「それにしても孫の風美の鼻が治るという吉報は、年寄りには何よりのことです。軍治さんにお礼申し上げたい」
軍治は慌てた。
「俺の方こそ、香織と息子ふたりの面倒を押し付けちまって申し訳ないと思ってますです」
「なんだか気持ち悪いな」
苦笑しながら雅が洩らした。
リカが笑いながら、
「こら、雅、せっかくの席によけいなことを言わないの」
家元が、柔和に言う。
「いかがでしょう、皆様。香のことを証明してくれた猫たちに、人間の正座をしてお礼をするというのは」
「そうですね」
一同も賛成して、背筋を真っ直ぐしてかかとの上に静かに座り、そろえた両手を畳の上に置き、猫たちに頭を下げた。








